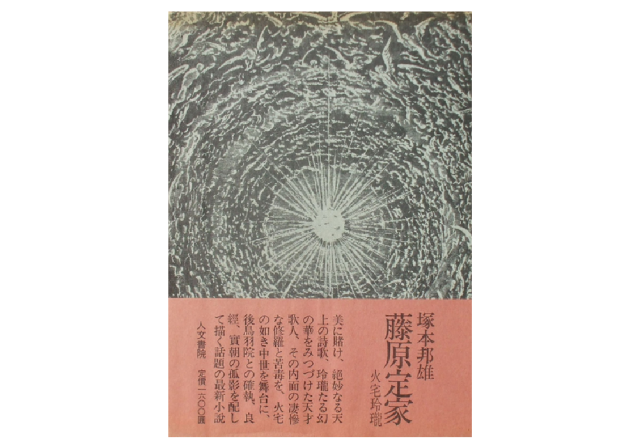『藤原定家 火宅玲瓏』塚本邦雄/不吉な花(岩倉文也)
文字数 2,258文字
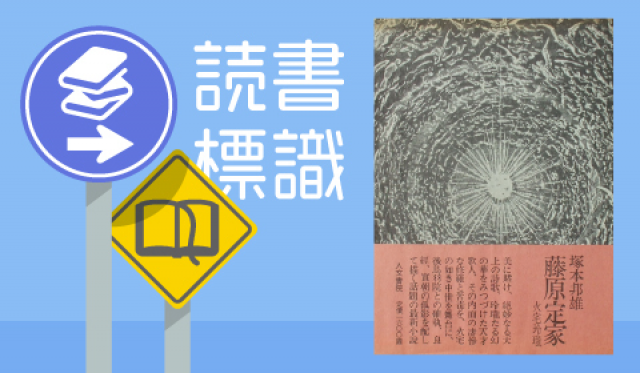
書評『読書標識』、月曜日更新担当は詩人の岩倉文也さんです。
塚本邦雄『藤原定家 火宅玲瓏』(人文書院)について語ってくれました。
詩人。1998年福島生まれ。2017年、毎日歌壇賞の最優秀作品に選出。2018年「ユリイカの新人」受賞。また、同年『詩と思想』読者投稿欄最優秀作品にも選出される。代表作に『傾いた夜空の下で』(青土社)、『あの夏ぼくは天使を見た』(KADOKAWA)等。
Twitter:@fumiya_iwakura
ここ最近人に会うたび就活をしているか問われるのであるが、無論そんなことはしていない。ならばどうするのかと言えば、ぼくにも分からない。分からないので、「就活? してないです」とだけ答えて黙り込むと、相手はなんとなく得心したような顔になり、「いやあ、いいですね、詩人らしくて」と、半ば嘲るように言うのが常である。実に正しい反応だと思いつつ、飲みかけのオレンジジュースに口をつけると水っぽくてとても飲めたものではない。
「詩人らしさ」に殉じることのできる人間など本の中にしか存在しないのであり、ぼくに就職の意志がないのは単に向き不向きの問題である。ぼくは言葉に向き、それ以外に向かなかった。自分に向かないことは、死んでもしたくない。思えばぼくは、ずっとそのように生きてきた。いまさら生き方を変えることはできない。
ならばどうするのか? と再び己に問うてみる。どうするもなにも、このまま行くところまで行くしかあるまい。デッドエンドに至るまで、見るべきものを見、書くべきものを書く。それで駄目なら、そのときにまた考えればいい。
ぼくは楽天家である。だが今回紹介する作品にはおよそ楽天的な要素など微塵もなく、徹頭徹尾、芸術家として生きかつ死ぬことへの苦い認識のみが横溢している。
『藤原定家 火宅玲瓏』。本書は歌人・塚本邦雄の手になる長編小説である。タイトル通り、主人公は中世を代表する歌人・藤原定家。歌人が歌人の小説を書いているのには訳がある。帯に付された「著者の言葉」から引こう。
定家の魂の煉獄の苦患は歌人である私によつて初めて類推可能であり、「花も紅葉もなかりけり」なる凄まじい呪詛に応ずるには、現代なる末世に生きる者の呪禁の辞以外にはあるまい。この一篇は私と定家が発止と切結んだ狂言綺語の火花である。
言わば本書は、〝現代の定家〟塚本邦雄による、藤原定家への千年の時を隔てた挑戦状であり、また熱烈な恋文なのである。
よって本書において、あらゆるアンビバレンスは反復される運命にある。定家と後鳥羽院の関係を中心に据え、定家と良経、定家と『新古今集』、定家と和歌。愛と憎しみの同時共存は再演され、物語に複雑な影を投げかけてゆく。
しかし考えてみれば、反復、というのは、王朝和歌の重要なテーマのひとつであった。季節は反復する。その時代時代に生きる人間の心のみがわずかに異なりながら、全てはゆるやかな円環の内に閉ざされる。
そんな王朝和歌の世界が、最後に輝きを見せたのが本書の舞台となる鎌倉初期という時代であった。既に世の趨勢は武者たちに傾き、王朝の威光は、わずかに後鳥羽院の院政の元で命脈を保っていたに過ぎない。都の貴族たちは自らの衰亡を予感しつつ、幻に幻を重ねるようにして絢爛たる和歌の創作に興じていた。
藤原定家はそうした貴族の代表格である。彼は十九歳のときに日記『明月記』に「紅旗征戎吾が事に非ず」と記し、芸術家として生きることを自らに宣言している。
ただし本書が扱っているのは定家四十五歳の春から、七十八歳の晩年に至るまでの期間である。すでに青春は去り、二度と帰ることはない。定家は病み衰えた身体を引きずりながら、『新古今集』の浄書に没頭してゆく。
極端に会話文の少ない本書は、ともすれば塚本邦雄による歌論、ないしは『新古今集』論といったものに近づきながらも、ぎりぎりの所でそれを回避している。恐らく本書を小説たらしめているのは、定家の歌に対する狂的なまでの執念であろう。
天変地異が相次ぎ、後鳥羽院の主催で壮麗な和歌管弦の催しが繰り返される末期の京を背景に、定家の歌はますます冴えてゆく。そしてそれは狂気と紙一重のものであった。
誰をも真に愛さず、遂には己の歌業さえ否定せずにはおれなかった不世出の天才・定家。彼の歌への思いを、地獄のような孤独を、現代に生き生きと甦らせた本書は、芸術を夢見る全ての人間の前に、玲瓏と咲き誇る不吉な花であることをやめない。
※本文の引用に当たって、漢字の旧字体は適宜新字体に改めた。