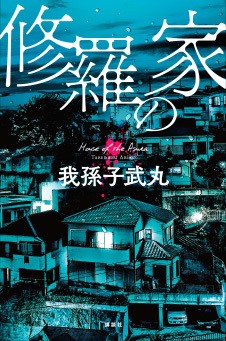〈4月25日〉 我孫子武丸
文字数 1,502文字
久しぶりに、鼻をつく夫の加齢臭で目を覚ました。昨夜はこのところ夫の寝ていたソファベッドで、夫の枕に顔を埋めたまま寝たのだということを思い出す。二週間、夫はずっと書斎に籠もって仕事も食事もしていたのだ。君にうつすわけにはいかないから、と。
何もかも夢であればいいと思っていたが、恐る恐るソファベッドの下を見下ろすとやはり夫はそこにいた。スマホがその手の近くに落ちているところを見ると、どこかへ電話しようとして、間に合わなかったらしい。
昨日の朝、ドア越しに聴いた彼の声はいたって元気だった。一時高かった熱も下がったようで、咳は相変わらず辛そうだったけれど、毎年のように罹 る喉風邪とさほど変わらないので、多分アレではないと本人も言っていた。夜遊びもしていないし、出勤していたときもマスクは欠かさなかった(使い回しではあったが)。でもタチの悪い風邪なのは間違いないし、うつさないに越したことはない。万が一アレだったとしても軽症で済むよ、まだギリ四十代で病気もないし。
彼の言葉を信じた。テレビでも医師が同じ事を言っていた。そしてもちろん、悪くなったとしたら、それから病院に行く暇くらいはあるのだと思っていた。LINEに返事があったのは夕方までだ。それ以降返信がなくなり、電話にも出ないので心配になって仕事を無理矢理早退し、戻ってきて見つけたのは氷のように冷たくなった夫の亡骸 () だった。
夫の手元にあるスマホを使うことは躊躇 () われたので、階段を駆け下り、廊下に置いてあるFAX複合機の受話器を取って考えた。110? 119?
119だ。救急車なら119。間違いない。──でもそもそも、救急車を呼ぶべきなんだろうか?
さっき触った、夫の身体の冷たさを思い出す。
死んでいた。とうに死んでいたのだ。救急車を呼ぶなんて馬鹿げてる。もし来てくれたとして、現場で事情を知れば、そのまま帰ってしまうに違いない。警察? 保健所? いずれにしろその後どうなるのかは想像もつかなかった。はっきりしているのは、多分もう二度と夫とは触れあうこともできず、顔も見られないまま火葬されるだろうということだ。そんなのは嫌だ。絶対に。
受話器を置き、ふらふらと再び階段を上がり、夫の書斎へと入った。しばらく見下ろしていたが、やがて意を決して夫に触れた。さっきも触ったのだ、構うまい。
誰のせい? 誰のせいでこんなことに? テレビに出ていた医者? 基準を決めた人? 電話しても検査をしてくれなかった保健所の職員? それとも──
ゆっくりと身を倒し、彼の身体に寄り添って頭をかき抱いた。冷たい唇にキスをした。深呼吸する。彼の身体の中で増殖し、彼を食い尽くしたウイルスをすべて取り込んでやる。そう、そして枕にはたっぷりとそれが付着しているとも聞いた。
書斎で寝始めて三日目の朝、夫がしていたのと同じ咳が出た。これでいい。これで、「責任者」のところへ行ける。そして──
我孫子武丸(あびこ・たけまる)
1962年、兵庫県生まれ。京都大学文学部哲学科中退。同大学推理小説研究会に所属。新本格推理の担い手の一人として、1989年に『8の殺人』でデビュー。『殺戮にいたる病』等の重厚な作品から、『人形はこたつで推理する』などの軽妙な作品まで、多彩な作風で知られる。大ヒットゲーム「かまいたちの夜」シリーズの脚本を手がける。近著に『怪盗不思議紳士』『凜の弦音』『監禁探偵』『修羅の家』などがある。
【近著】
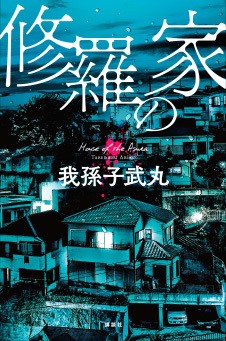
何もかも夢であればいいと思っていたが、恐る恐るソファベッドの下を見下ろすとやはり夫はそこにいた。スマホがその手の近くに落ちているところを見ると、どこかへ電話しようとして、間に合わなかったらしい。
昨日の朝、ドア越しに聴いた彼の声はいたって元気だった。一時高かった熱も下がったようで、咳は相変わらず辛そうだったけれど、毎年のように
彼の言葉を信じた。テレビでも医師が同じ事を言っていた。そしてもちろん、悪くなったとしたら、それから病院に行く暇くらいはあるのだと思っていた。LINEに返事があったのは夕方までだ。それ以降返信がなくなり、電話にも出ないので心配になって仕事を無理矢理早退し、戻ってきて見つけたのは氷のように冷たくなった夫の
夫の手元にあるスマホを使うことは
119だ。救急車なら119。間違いない。──でもそもそも、救急車を呼ぶべきなんだろうか?
さっき触った、夫の身体の冷たさを思い出す。
死んでいた。とうに死んでいたのだ。救急車を呼ぶなんて馬鹿げてる。もし来てくれたとして、現場で事情を知れば、そのまま帰ってしまうに違いない。警察? 保健所? いずれにしろその後どうなるのかは想像もつかなかった。はっきりしているのは、多分もう二度と夫とは触れあうこともできず、顔も見られないまま火葬されるだろうということだ。そんなのは嫌だ。絶対に。
受話器を置き、ふらふらと再び階段を上がり、夫の書斎へと入った。しばらく見下ろしていたが、やがて意を決して夫に触れた。さっきも触ったのだ、構うまい。
誰のせい? 誰のせいでこんなことに? テレビに出ていた医者? 基準を決めた人? 電話しても検査をしてくれなかった保健所の職員? それとも──
ゆっくりと身を倒し、彼の身体に寄り添って頭をかき抱いた。冷たい唇にキスをした。深呼吸する。彼の身体の中で増殖し、彼を食い尽くしたウイルスをすべて取り込んでやる。そう、そして枕にはたっぷりとそれが付着しているとも聞いた。
書斎で寝始めて三日目の朝、夫がしていたのと同じ咳が出た。これでいい。これで、「責任者」のところへ行ける。そして──
我孫子武丸(あびこ・たけまる)
1962年、兵庫県生まれ。京都大学文学部哲学科中退。同大学推理小説研究会に所属。新本格推理の担い手の一人として、1989年に『8の殺人』でデビュー。『殺戮にいたる病』等の重厚な作品から、『人形はこたつで推理する』などの軽妙な作品まで、多彩な作風で知られる。大ヒットゲーム「かまいたちの夜」シリーズの脚本を手がける。近著に『怪盗不思議紳士』『凜の弦音』『監禁探偵』『修羅の家』などがある。
【近著】