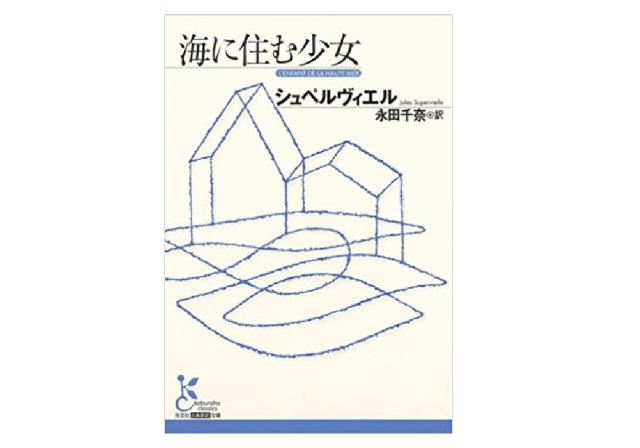『海に住む少女』シュペルヴィエル/魂にまで悲しみは(岩倉文也)
文字数 1,853文字
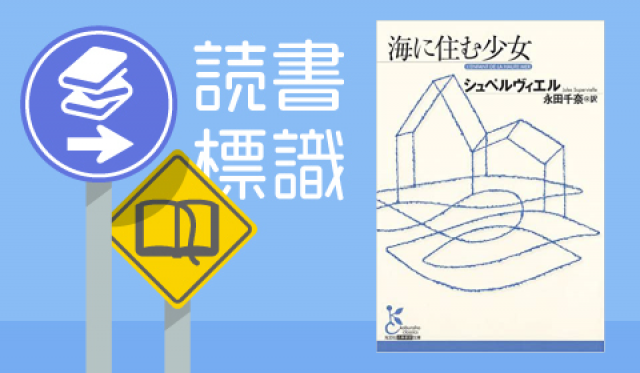
シュペルヴィエル『海に住む少女』について語ってくれました。
詩人。1998年福島生まれ。2017年、毎日歌壇賞の最優秀作品に選出。2018年「ユリイカの新人」受賞。また、同年『詩と思想』読者投稿欄最優秀作品にも選出される。代表作に『傾いた夜空の下で』(青土社)、『あの夏ぼくは天使を見た』(KADOKAWA)等。
Twitter:@fumiya_iwakura
この世界で起こるたいていの出来事は、ほんのわずかな間しか持続することがない。誰かに対して強い感情を抱いたとしても、それは束の間のうちに消えてしまう。さびしさ、退屈、よろこび、幸せ、なにかを美しいと思う気持ち。みんな一瞬のことだ。気がついたときには、感情の欠片すら心には残っていない。そうした感情があったという記憶はあっても、当の感情自体はもう二度と甦ることがない。
記憶喪失ならぬ感情喪失。これは誰しもが日常的にやり過ごしている、いやむしろそれに助けられている喪失であって、問題にすることもないのかもしれない。
しかしこの世界には、そんな感情の喪失に耐えることのできない人間も存在する。
詩人──そう呼ばれている者の多くがそれである。
短編集『海に住む少女』の著者・シュペルヴィエルもまた詩人だった。ぼくは小説本を手に取り、著者略歴の欄に「詩人、作家。」などと書かれていると、それだけで少し興奮してしまう。詩人でありつつ作家でもあるって、なんて贅沢なんだろう。喪失に対抗する手段は、多ければ多いほどいい。という訳でもないことは知っているけれど、ついつい、感じ入ってしまう。
喪失。本書の表題作「海に住む少女」に描かれているのは、喪失そのものというより、喪失がもたらす過剰さに対する視線である。
人はなにかを失うと、それを補おうとする。たとえば友人が死んだら、その死を、そのままに受け入れるということを人は決してしない。喪失を喪失のままに受容するなんて、およそ不可能だ。ぼくであれば、その友人が生前見たもの好きだったものを、自分の中に取り入れようとするだろう。そうして死んでしまった友人を、自分の中でもう一度作り上げようとむなしい努力をするだろう。
恐らくこの世界に、大切な者の死を納得できる人間などひとりも存在しない。誰もが死者を前にして、一度はこう願うはずだ。「ああ、せめてどこかで生きてさえいてくれたなら」。
だがもし、その願いが本当に叶ってしまったら? 誰も知らない場所で、たったひとり、ただ生きつづけるだけの、そんな孤独な存在が生まれてしまったとしたら?
少女はこの世に、自分以外にも女の子がいるなんて知りませんでした。いえ、そもそも自分が少女であることすら、知っていたのでしょうか。
とんでもない美少女、というわけではありませんでした。…(中略)…ぱっちりというわけではありませんが、輝く灰色の瞳が印象的なこの少女、灰色の瞳に動かされているようなこの少女の存在に気づいたとき、あなたは時間の底から大きな驚きが湧き上がり、身体をつらぬき、魂にまで届くのを感じることでしょう。
大西洋のまっただなかに浮かぶ、幻の街に住むひとりの少女。この少女に仮託されているのは、不毛な、しかし抑えることのできない強い想いが生み出した、悲しい永遠である。
本書の最後に収録された「牛乳のお椀」も、「海に住む少女」と同じ味わいを持った作品だ。3ページ程の掌編ではあるが、「海に住む少女」が童話的であるのに対し、こちらはより現実に即した形での、喪失に対する不合理だが物寂しい人間の行動が描かれている。
なにかが失われたとしても、それは、この世界から完全に消えてしまうことを意味しない。失われたものは爪痕を、必ずどこかに、誰かに、はっきりと残してしまう。
シュペルヴィエルは、その爪痕を想像力を以て、最も美しく残酷な形で描き出す。ぼくはシュペルヴィエルの作品が、こう言っているように思えてならない。「なにも失われることはないんだ。誰も本当に死んでしまうことはないんだ。とても、とても悲しいことにね」。