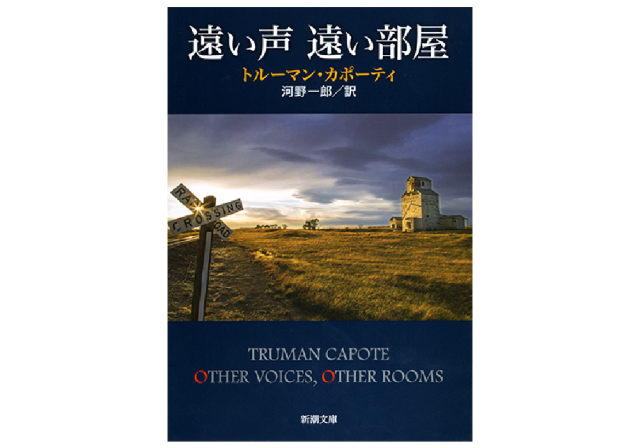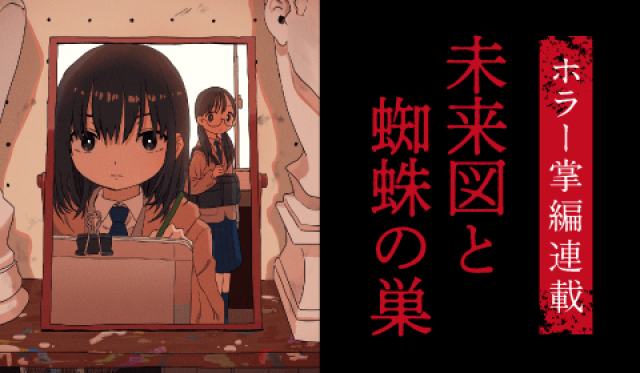『遠い声 遠い部屋』カポーティ/きっとよくなりますからね(岩倉文也)
文字数 2,517文字

次に読む本を教えてくれる書評連載『読書標識』。
月曜更新担当は作家の岩倉文也さんです。
今回はトルーマン・カポーティの『遠い声 遠い部屋』をご紹介していただきました!
詩人。1998年福島生まれ。2017年、毎日歌壇賞の最優秀作品に選出。2018年「ユリイカの新人」受賞。また、同年『詩と思想』読者投稿欄最優秀作品にも選出される。代表作に『傾いた夜空の下で』(青土社)、『あの夏ぼくは天使を見た』(KADOKAWA)等。最新単行本は『終わりつづけるぼくらのための』(星海社FICTIONS)。
Twitter:@fumiya_iwakura
少年期を代表する感情は「退屈」ではないかと思う。ぼくは子供の頃、実に多くのことに退屈を感じていた。学校の授業中はもちろんのこと、家に帰った後も、そして休日も、不断の退屈に苦しめられていた。
そんなことはないはずなのに、少年の頃の記憶を探ると、ひとり遊びに興じる自分の姿ばかりが思い浮かんでくる。ぬいぐるみで、ゲームで、昆虫で、自転車で、ぼくはずっと遊んでいた。ちっとも楽しくはなかった。
子供にとっての退屈は、大人にとってのそれとは本質を異にする。大人の退屈とは娯楽の不在ないし不十分を意味するが、子供にとっての退屈とは、そのまま、この世界自体に対する直接的な退屈を意味している。思うにこの世界とは、かなり複雑な手続きを経て読み解かなければ、恐ろしく無味乾燥でつまらぬものだ。
例えば一本の木があったとしよう。大人ならその樹齢を考え、過去に思いを馳せることができる。同時にその木が朽ち、倒れてしまう未来を想像し、憂愁に沈むことができる。また現在の木の姿、梢の震え、葉のそよぎに情緒を感じることも可能だろう。しかし子供にとって、木は木である。それ以上でも以下でもない、極めて退屈な物体である。木登りが出来なければ、蹴っぽってその場を立ち去る他はない。
要するにぼくは、子供の感性をあまり信じてはいないのである。感性というのは、ある種の歪められた認識のことだ。詩人は詩人の、歌人は歌人の、小説家は小説家の感性をもって世界を歪め、その歪みを作品に表す。だが子供には、いまだまともな感性など備わってはいないのである。早熟な一部の例外を除いて。
カポーティ最初の長編作品である『遠い声 遠い部屋』は、彼が二十歳から二十二歳の間に書き上げられた。その絢爛にして繊細、精妙にして大胆な修辞の数々は、カポーティ作品の中でも屈指のものではないかと思われる。ぼくはいま彼の遺作となった『叶えられた祈り』も読み進めているが、こちらの作品では詩的な修辞は鳴りを潜め、もっとそっけなく乾いた文体となっていることに驚かされた(もちろんこれは作者の意図する所でもあるのだが)。
本書の内容に入る前に、まずはこの『叶えられた祈り』から本書の読解の手がかりとなりそうな一節を引いておきたいと思う。
〝あなた〟とはカポーティの分身である主人公のこと。つまりここでは、著者が自身の作品の特質を登場人物に語らせている場面なのである。ここで指摘されていることは、そのまま『遠い声 遠い部屋』にもぴったりと当てはまる。
本書は、十三歳の少年ジョエルが母親の死をきっかけに、母と離婚した父親を探してアメリカ南部の田舎町を訪れる場面からはじまる。そして父の住む屋敷に案内されたジョエルは何故かなかなか父親には会わせてもらえず、黒人の召使いの少女ミズーリや、父の再婚相手のいとこである謎の多いランドルフ、近所に住むおてんば娘のアイダベルなどと交流を深めてゆく。そうした中で慄きながら成長してゆく少年の心理が、豊饒な言語感覚を通して自在に語られている。
そして先に引用した『叶えられた祈り』にある言葉通り、本書に登場する人物はみな「叶えられる筈のない目的」を持ち、それを引きずりながら生活を送っている。ミズーリは南アメリカを離れ雪のある所に行きたいと願い、ランドルフはかつて別れた最愛の人をいまでも探し続けている。またアイダベルは祭りの夜に町から逃げ出そうとジョエルに持ちかけ、さらに祭りのショウで出会った小人の娘ミス・ウィスティーリアは成長せずに自分を愛してくれる男を求めている……。
傷つきやすい心を持った少年は、しかし、そうした場に留まることはできない。そうした人物たちの仲間になることはできない。なぜなら父との再開を果たした少年には、もはや目的などないからである。いや、そもそも少年が成長するのに、目的はいらない。少年はただただ叶えられぬ目的に押しつぶされ、埋没してゆく人々からは遠く離れて、この町を去らねばならない。物語には出口が必要である。少年の日々にもまた。
けれどぼくは少年の成長と出立を思うとき、古い世界に取り残される人々のことも思わずにはいられない。いみじくもランドルフは言っている。
「われわれがいちばん欲しいと思っているのは、ただしっかりと抱きとめてもらい……そして言ってもらうことなんだ……みんな(みんなというのはおかしなものさ、赤ちゃんのミルクだったり、パパの目だったり、寒い朝の音を立てて燃える薪だったり、梟だったり、学校の帰り道のいじめっ子だったり、ママの長い髪の毛だったり、こわがることだったり、寝室の壁のゆがんだ顔だったり、するんだからね)……みんなそのうち、きっとよくなりますからね、って。」
叶えられぬ祈りを持った彼らも、ただ一言、そんな言葉を掛けてもらえたら、それで救われたのかもしれない。だが少年は去るのみである。たった一度だけ、置き去りにする世界に輝かしい一瞥を投げかけて。後には風も、甘美な記憶も残らない。