『本が紡いだ五つの奇跡』アルパカブックレビュー
文字数 2,638文字
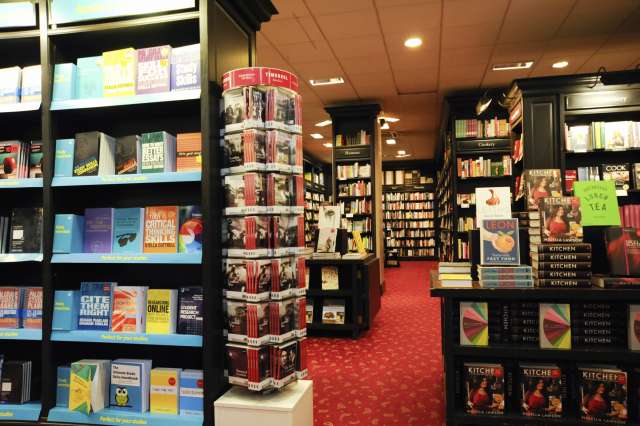
1冊の小説が、みんなを動かし、みんなを救う──。
癒やしと感動の『本が紡いだ五つの奇跡』(森沢明夫・著)。
編集者、作家、装丁家、書店員、そして読者。
苦悩を抱えた人々が、本と出会って生まれる5つの感動の物語。
「大好きな本です!」というアルパカさんことブックジャーナリストの内田剛さんが、「元書店員」目線で熱くレビューしてくださいました!
「わたしは空が好きだ。とても。」
冒頭の一節からも伝わるように、森沢明夫作品には「空」がよく似合う。読みながら空を見上げたくなる。どんな遠い場所でもひとつの空につながっていると感じられる。つまりひとりでいても孤独でないと思える。
タイトルにある「五つの」とは、「編集者」「小説家」「ブックデザイナー」「書店員」「読者」のこと。すなわち一冊の本がこの世に生み出され、誰かの手に届くまでに関わる五つの立場の人々のことだ。それがそのまま五章の語り手となってストーリーが構成されている。
そして「奇跡」とは、本と人が生み出した奇跡のこと。しかし決して奇をてらっているわけではない。地味でありながらどこまでも素直なのである。本に対するピュアな想いが清々しくて、心を大きく動かされ、身体の奥底から自然とこみあげてくる感情を抑えきれなくなる。これを本物の「感動」と呼ぶのであろう。
序盤は作り手側からの視点が軸となる。章でいえば第一章「編集者」と第二章「小説家」の部分だ。編集者は26歳の津山奈緒。冴えない日々を過ごし、社内では営業への異動も噂されるまさに崖っぷちの立場であった。小説家は涼元マサミ。かつて『空色の闇』というベストセラーを出したものの、その後は泣かず飛ばず。もう筆を折る覚悟を決めていたタイミングで津山から「先生の代表作を書いてほしい」という熱烈な執筆依頼を受けるのだ。
小説家では生活できない、家族とは暮らせない。厳しすぎる現実に苦悩する涼元を若い津山がいかにして口説き落とすか、それが重要な読みどころのひとつなのだが、最初のパートは津山視線で構成されて、次は逆に津山側から語られる。真逆の立ち位置だった二人の想いが、次第に交わっていくさまが素晴らしく、セピア色の情景が色づいていく瞬間を見てとれるのだ。クライマックスは雪が舞う電話のシーン。何度読み返しても涙があふれる。
この部分だけを切り取れば上質なビジネス小説、ひとりの人間の成長譚として読むことができるのだが、本書はそうしたジャンルの「枠」を軽々と超えていく。特別な想いをもって世に出された小説が、「ブックデザイナー」や「書店員」の熱い想いを加えて、どうやって読者へ伝わっていくのか。さらにはどんな奇跡を呼ぶのかは、ぜひ本書でじっくり味わってもらいたい。
小説が完成するのは著者が原稿を書き上げた瞬間ではない。読者の手元に届いて読んでもらったときにはじめて出来上がる。もちろんどんな本にもそれぞれに物語がある。しかし忘れてはならないのは、書店店頭POPや身近な誰かの口コミ、映像化作品の原作というような「きっかけ」を通じて、読まれるべき本が読むべき者に伝わるということ。川の流れにも例えられる著者から読者へとつながる道行きには、尊いストーリーがあるのだ。
この文章を書いている僕は元書店員で約30年のキャリアがあるのだが、この本を読んで驚いたのは、出版業界の描写が実にリアルであること。とりわけ僕が体で覚えている本を売る現場の空気が、隅々まで誠実に再現されていてまったく嘘がない。売る喜びや綺麗ごとばかりではなく、仕事の裏には厳しさと苦しさも溢れていることが手に取るように分かるのだ。
ベストセラーとなる幸せな本はほんの一握り。内容的に素晴らしい本が売れることの方がむしろ奇跡に近い。書棚に埋もれ、さらには店頭にも並べられない良書がいかに多いことか。書店は利益率が極めて厳しく、売りたい本より売らされている本の比率も高まっている。悪質な万引きやクレーマーも増加し、書店員の日々のストレスも限界超えをしている。
そんな疲弊しきった店頭に光を灯し、悩める書店員たちの気持ちを奮い立たせてくれるのは、誰にでも薦めたくなる物語だ。書店員の仕事の核となるのは、著者(創り手)と読者(読み手)の距離を縮めることだと思うが、『本が紡いだ五つの奇跡』はまさにそうした想いを凝縮させた貴重な一冊である。
本に対する一途な愛と直向きな情熱が、出合ったことのない絶景を見せてくれる。素晴らしいラストを全身で体感してもらいたい。本に関わるさまざまな立場の人生の「転機」に巡りあった真剣勝負の一冊。それは書き手や売り手の想いを超えて、悩める人々の心を救うのだ。原点回帰のメッセージや、人生の真理が真正面から伝わるだけではない。世代を超えて未来へと繋いでいくべき価値のある物語なのである。
活字離れ、読書離れが叫ばれて久しいが、決して悲観するべき状況ではない。潜在的にはたくさんの本好きがいて、ただ「きっかけ」を探しているだけなのである。森沢作品が読書の入口となれば、これ以上の幸福はない。これからの豊かな読書人生が待っているはずだ。
内田 剛(うちだ・たけし)
ブックジャーナリスト。本屋大賞実行員会理事。約30年の書店勤務を経て、2020年よりフリーとなり文芸書を中心に各方面で読書普及活動を行なっている。これまでに書いたPOPは5000枚以上。全国学校図書館POPコンテストのアドバイザーとして学校や図書館でのワークショップも開催。著書に『POP王の本!』あり。仕事に行きづまった編集者の津山は、本当に作りたい本を作るため、かつて自分が救われた小説の著者、涼元マサミに新作を依頼する。
そうして生まれた作品が、娘と縁が切れそうだった涼元から、余命宣告された装丁家、心に傷を抱えた書店員、そして自分の時間が止まっていた読者まで、みんなの人生を動かす。
1969年千葉県生まれ、早稲田大学卒業。2007年『海を抱いたビー玉』で作家デビュー。14年『虹の岬の喫茶店』が映画化されて話題になる。小説に『夏美のホタル』(16年映画化)『癒し屋キリコの約束』(15年テレビドラマ化)『きらきら眼鏡』(18年映画化)『エミリの小さな包丁』『ぷくぷく』『恋する失恋バスツアー』『雨上がりの川』『青い孤島』など、エッセイに『あおぞらビール』『森沢カフェ』など著書多数。




