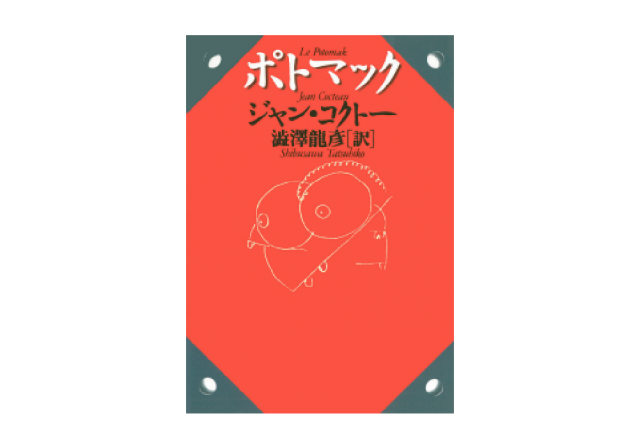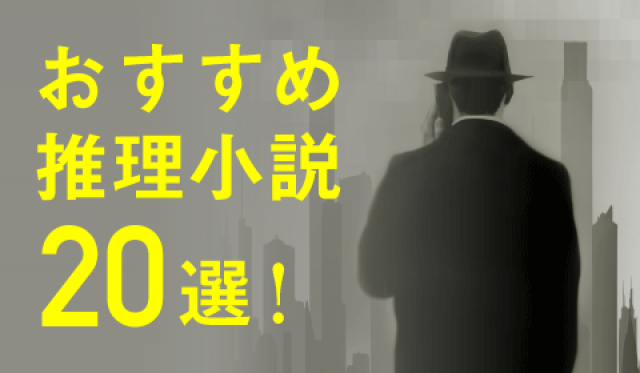『ポトマック』ジャン・コクトー/一条の軌跡(岩倉文也)
文字数 1,804文字

本を読むことは旅することに似ています。
この「読書標識」は旅するアナタを迷わせないためにある書評です。
今回は詩人の岩倉文也さんが、ジャン・コクトー『ポトマック』について語ってくれました。
ぼくは人の死に接するたび自分のあまりの無関心に驚くことがある。知り合いが死んだり、あるいはかつてテレビ越しに親しんだ芸能人が死んだりした際に感じるのは、ただ一瞬の浮遊感。その人がいた世界から、いない世界へと切り替わるときの、ほとんど物理的ともいえる衝撃のみだ。それは、走行中の車が急停止するのに似ている。ぼくはぐんと前につんのめり、嫌な汗が額を流れる。そして、呆けたような笑いが口からは洩れてくる。
いや、死ぬということは、何ものとも繋累を持たない。君が死ぬということとさえも、繋がりがない。死は死にすぎない。
『ポトマック』の中でそうコクトーは繰り返す。「死ぬということは何ものにも似ていない」と。「死と関係があるのは死だけなのだ」と。ぼくはこうしたコクトーの言葉に、彼の死に対する誠実さを見る。
本書が書かれたのはコクトーが二十五歳のとき。言わば青春の書だ。しかし、いや、それ故に、と言うべきだろうか、本書は死へと向けられた作者の鋭敏な眼差しに満ちている。
ぼくは思うのだが、人は年を重ねるごとに死から遠ざかってゆき、ある一定の年齢を超えると、また死へと近づいてゆく。
青春とはつまり、死の圏内で戯れることだ。そして死は、病的で、繊細で、荒唐無稽な、さまざまなイメージをぼくらに齎す。箴言、書簡、自由詩、デッサン、対話、エッセイ、寓話、怪異譚……複数の形式で書かれた文章を「ポエジー」の糸で縫い合わせたような本書は、そうしたイメージの見本市とも言えるのである。
僕は五里霧中で書いていた。あとで気がついたことだが、そのとき僕は脱皮していたのであり、体の組織が変わるあの危険な状態のなかで書いていたのであった。このようにして、人間は死ぬ前に何べんとなく死ぬのである。
冒頭における作者のこの言葉は、本書を通底しているある危うい雰囲気──すこし手を触れただけでもばらばらになってしまいそうな──の理由を説明している。それは、ひとりの詩人が別の何かへと、今までの感性を、その在り方をふり払って変身(メタモルフォーズ)してゆくまさにその瞬間の、身を裂くような危うさなのである。
この本は結局、人がなぜ物を書くのかという根源的な部分に接しているがために、現在においても奇妙な輝きを放っている。
人はなぜ物を書くのか? それは、自己を前へと投げ出すためだ。自己を未知の場所へと連れ去るためだ。少なくとも、消耗のためにのみ物を書く人間のことを、詩人とは呼ばない。
この本は「小説」とは言いながら半ば小説の体を成していないのであるが、そんなことは問題ではないのだ。グロテスクな怪物ウージェーヌや、地下水族館に暮らす幻獣ポトマックをめぐる挿話の数々、それに退廃詩人ピガモンとの交流など、不気味でいてどこか祝祭的なイメージの連続を、ぼくらはただ万華鏡をくるくると回すように楽しめばいい。
神様は自分の姿にかたどって人間を創ったのだから、人間は自分自身に近づけば近づくほど、神様に近づいたことになる。他の人たちが悪魔に誘惑されるように、神様に誘惑された僕は、一所懸命自分自身に向って急ぐのだ。
しかしこうした言葉にぶつかっては、ぼくはハッとする。分裂した形式に、混沌としたイメージ。一見無造作に構成されたように見える本書も、「自分自身」へ至りたいという欲望において、ただひとつの方向を示している。
コクトーは無邪気な少年のように、「神様」のいる方へと脇目もふらず駆けてゆく。そして後に残された一条の軌跡こそが、この『ポトマック』というユニークな書物なのである。
詩人。1998年福島生まれ。2017年、毎日歌壇賞の最優秀作品に選出。2018年「ユリイカの新人」受賞。また、同年『詩と思想』読者投稿欄最優秀作品にも選出される。代表作に『傾いた夜空の下で』(青土社)、『あの夏ぼくは天使を見た』(KADOKAWA)等。
Twitter:@fumiya_iwakura