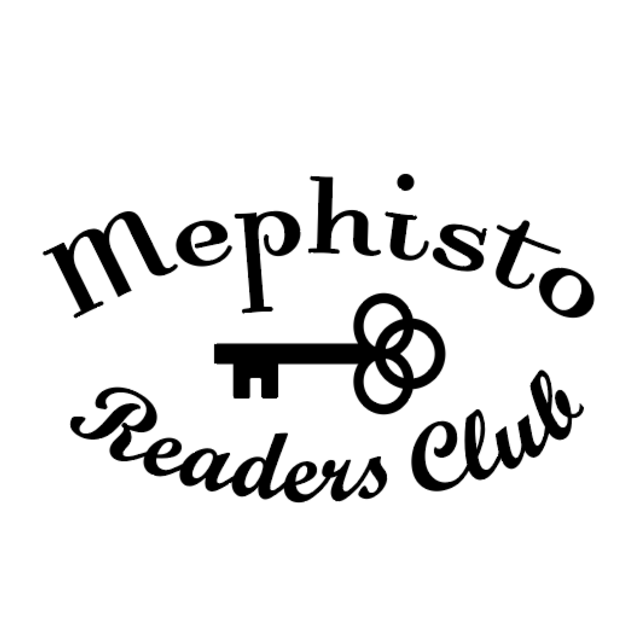森深紅 「マッドサイエンティストへの恋文」
文字数 2,264文字

幼い頃に一度だけ、ラブレターを出したことがある。
人に話せば笑いを禁じえない、痛烈な勘違いに終わった恋だったが、その後の人生を左右したくらいに彼の存在は大きかった。その人は、私が愛して止まない「マッドサイエンティスト」なのだ。
(注:マッドとサイエンティストの間に敢えて「・」を入れないことで、その道に詳しい読者には、ご了解願いたい)
私の恋したマッドサイエンティストN氏は、白衣こそ纏っていなかったが、狂気を象徴するモジャモジャヘアを持ち、黙々と珍妙な発明品を作り上げることにのみ心血を注いでいた人だった。
人間との相互理解を必要としない彼は、人とはかけ離れた姿のロボットを製作し、自らの助手にしていた。「できるならば、私も貴方の改造を受けて、僕になりたい!」
正直な気持ちを手紙に認めて送ったのだが、残念ながら返事が届くことはなかった。
想いが叶わなかったその後も、私は科学への興味を失くすことなく電子工作に勤しみ、それが高じて機械関連会社に入社する。
薄っぺらな技術革新を遂げる製品と戦いながら数年が過ぎ、諸事情あって作家デビューをさせていただいたわけだが、今も変わらず、私の中には科学の狂気と過度への憧れが強いようだ。
亡くした子供の再生を夢に見た作家が、陰惨な夜にフランケンシュタイン博士を生んだように、生命の操作は、愛と悲劇と疎遠に彩られている。神技だとか奇跡だとか言われているそれを、科学的手段を用いて実現させようという科学者の無謀さや愚かさに、どうしようもなく惹ひき付けられるのだ。
昔から私の妄想に登場するマッドサイエンティストは、己が手で地球殲滅をも企む輩とは異なっている。昏い欲望を他者に向けるより、己の小宇宙を支配しようと邁進する姿が好きで、その方法と被造物は、狂気を感じさせるに足る、美しく、頽廃的なものであって欲しい。
だが残念ながら現実世界で、そこまでパンチの効いた科学者には出会えていない。勤め人時代、基礎研究者が多く出入りしそうな開発棟を徘徊して、近い像を求めてみたのだが、見つからなかった。社会性を大きく欠いた人々はいたが、それは自分も含め、ただのダメなサラリーマンで、マッドではない。
純粋な科学とその技術的応用の線引きは、昔から曖昧なものだったのに、どうしてフィクションを凌駕するような、マッドサイエンティストは誕生しないのだろう。私は、それを考えるたびに神の反逆者という重要なポジションを与えられながら、未だに復活の兆しを見せない悪魔との親和性を感じている。彼らもまた、人知を超えた力を持ちながら、人間に核ボタンの一つも押させられないままでいるのだ。
両者が邪悪の分かりやすい形である限り、その企みが、これまた分かりやすい正義の味方に阻止されているだけなのか。人類をどうこうするという目的が、そもそも俗っぽく、悪魔やマッドサイエンティストの食指が動かないのか。
答えはその存在と同じく、謎に包まれたままだ。
いない、と全否定してしまうのは乱暴だし、もしかしたら悪魔は存在して、口説いた科学者が狙い通りの悪事に走ってくれないだけなのかもしれない。マッドサイエンティストにしても、悪魔の召還を可能にする何某かは発明したのに、なかなか期待するような悪魔が現れてくれないだけかもしれない。
いそうで、いない。だからこそ、虚構の世界に、未知の科学に、その存在に期待してしまう。
本という扉を開き、社会的な固定観念の世界から飛び出すことのできる、私も「マッド」な読者である限り、狂気の科学者と、タッグを組む悪魔の到来に期待して、マッドサイエンスの入り口である、フランケンシュタインの門の下に立ち続けているのである。
そして、その待ちぼうけは一通のラブレターから始まった。
恋文の宛名は「ノッポさんへ」だ。
若い読者はご存知ないかもしれないがノッポさんは、NHKの教育番組に登場するキャラクターで、ゴン太くんというマスコットを連れている工作のお兄さんである。
当時、セロテープと糊こそが、あらゆる物体をくっつけると信じて疑わなかった私は、ノッポさんが一瞬で画用紙を張り合わせてしまう技に感動し、工作物と同様、助手のゴン太くんを製作したのだと本気で思っていた。それもこれも、ノッポさんが一切の言葉を発することなく、虚無の笑顔と手品のような鮮やかさで、物を作り出していたからで、幼い私には異人である大人の男であった点も大きいだろう。
現実には彼はマッドどころか科学者でもなく、ゴン太くんはロボットでも、孤独なノッポさんの助手でもなかった。
工作バサミという丸い狂気を手に、虚構と現実を両面テープで張り合わせていた怪しいマッドサイエンティストは、実在しなかったのだ。
ただ……思い返せば、ノッポさんの脇に控えていたゴン太くんは、熊とも犬とも言えない不思議な外見をしていた。重量のありそうな体を支えるにしては小さすぎる足。人を惑わせる怪しい赤鼻。鳴き声と共に軽やかなステップを刻む、あの奇妙なケモノに、幼い私はTV画面を通して囁かれていたのかもしれない。「お前はまず、科学の道を行け。そして将来は作家となり、マッドサイエンティストを生み出すのだ」と。
いや、間違いない。ここで皆さんにお目にかかれたのも、ファウスト博士を誘惑した巧妙な悪魔の仕業なのだから。
森深紅