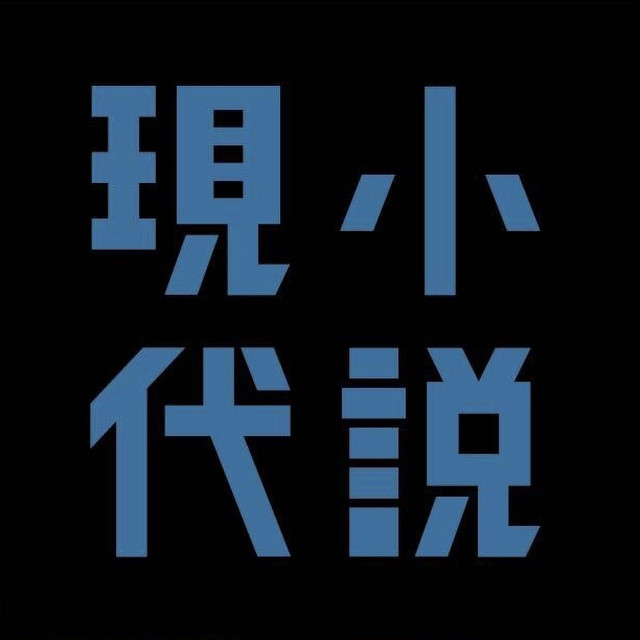第15話
文字数 3,228文字

それは雨降りの平日、7月の中旬にしては肌寒い夜だった。こんな日は、観客と踊り子の数がたいして変わらないこともある。しばらくすると、宿の浴衣を着た温泉客たちがぱらぱらと舞い込んだ。ステージから「どこの旅館ですか?」などと話しかける。なんとか2回目の公演まで場を繫ぎたい。客数が増えない場合は、1回で終わってしまうこともあるのだ。
今回のあわらミュージックは、出演する3人の踊り子の中で、いちばんぺーぺーの私がトリだった。通常、最も人気のある踊り子が最後の演者となる。前回の大和ミュージックで「いつかトリを務めてみせます!」と社長に宣言したのだが、もちろんその「トリ」とはワケが違った。新人に経験させてあげるための「トリ」である。
一見さんの多い温泉地の劇場なら、贔屓の踊り子がいないため、文句も出にくい。しかしストリップを観たことがなくても、紅白歌合戦のように、最後に出てくるのはよっぽどのベテランか、実力のある踊り子なのだろうと期待するはずだ。私がそれに応えられるとは、到底思えなかった。
2番目のお姐さんのオープンショーが終わる。「最後までお楽しみくださ~い」と客席に呼び掛ける声が聞こえた。緞帳を少し持ち上げて待ち、「お疲れ様です」を交わしたら、入れ違いに暗転したステージへ出る。静まった場内に、天井を叩く雨の音が響いていた。
これから踊る演目は、素肌に黒いジャケットを羽織り、吊りベルトの黒い短パンと、腿まである黒いロングブーツを合わせた衣装だ。踊り子としては極めて地味な衣装だし、新人らしい初々しさもない。ユニセックスなスタイルは、好悪もわかれるだろう。自分で作ったくせに、いまいちやりきれていない演目だった。
恋をする女の、ドロリとした感情がテーマなので、出だしの音楽も照明も暗い。そのせいで、私からは客席がほとんど見えなかった。それでも、樹音姐さんをイメージして背筋を伸ばし、まっすぐ前を見て踊り出す。どんな時でも、絶対に手は抜かないと、それだけは心に決めてデビューしたのだ。
それにしても何だ、この違和感は。振りを間違えているような、そもそもここに立っていることが間違いであるような、遅刻して間違えた教室に飛び込んでしまった時のような、不穏な空気を感じる。明らかに何かが違う。曲調が変わって照明が明るくなると、がらんとした客席が目に入った。どこだ。観客はどこにいる。
1階と2階で100席以上ある座席を、隅々まで必死に目で舐める。あの奥の暗がりか、それとも2階席か。さっきはそこに1人いたはずなのに。さらに曲が盛り上がり、花道を進もうとした瞬間、テケツに居たはずのオーナーが走ってきて、踊る私を遮った。「今日の公演は、もうここで止めよう」。まだ音は鳴っていたが、確かに彼はそう言った。私は間抜けにも、誰もいない客席に向かって踊っていたのである。
楽屋に戻り、姐さん方に事情を話す。情けなさで、消えたかった。1回目のステージで、もう一度私を観たいと思わせることができなかった結果が、これである。ところが、いちばんベテランのお姐さんが、私も経験があるよ、と何でもない風に言った。すぐにおかしいと気付いたそうだ。誰もいない客席は、1人でもいる客席とは、全く空気が違う。経験したばかりの私は、そのゾッとする感覚がよくわかった。舞台における観客の存在は、想像より遥かに大きかったのだ。
自分が観客だった頃は、舞台に立つ人がいるから、客席に自分の居場所ができると思っていた。だけど、ステージに立てば、観てくれる人がいるから、舞台に立つことができると思える。最後まで踊れず、硬くなっていた心は、いつしかまたやる気に満ちていた。
踊り子としてステージに立った回数より、書店員として主催し、登壇したトークイベントのほうが、まだ圧倒的に多い。前の会社ではイベント担当として働いていたこともあり、一時期は、日に2度も開催することがあったほどだ。コロナウイルスの影響で、今までのように書店イベントの開催ができない今を、残念に思うと同時に、どこかホッとしてもいる。
対談形式のトークイベントは、開催が決まった瞬間が「嬉しい」のピークだ。あとはもう、集客のための宣伝と、チケットやポスターなどの準備に追われ、当日はひたすらドタバタと過ぎ、楽しむ余裕もない。満員御礼ならそれも酬われるが、必ずしもそうとは限らないのが、水ものと言われるイベントだ。
サイン会の事前予約が100名だったのに、当日は半分しか来ないこともあった。作家のトークイベントの観客が数名しか集まらず、しかもそのうちの1人が、登壇する作家の奥さんというイベントもあった。彼女は一番前の真ん中の席に座って、熱心に頷きながらトークを聴いていた。しかし、そんなことは自宅の居間でもできるだろう。
私は一体、会社にお金をもらいながら、何をしているのか。これはなんの茶番だ。そう思うのに、貴重な経験をしている、となぜか得したような気にもなっていた。今思えば、それらの経験が、日々集客数を問われる、踊り子という特殊な仕事に役立っている。さすがに観客0の経験はなく、動揺してしまったのだが。
7月下旬は、あわらミュージックからそのまま上野へ荷物を送り、シアター上野で踊った。24日が誕生日なので、いつもよりは、正の字が増えるかもしれない。ストリップ業界は、踊り子の誕生日やデビュー日を大事にする。特に、デビューした日を毎年祝う「周年」は、ファンや踊り子仲間から花輪や花束が届き、踊り子自身も、衣装にお金をかけた周年作を発表したり、オリジナルTシャツを販売したりするお祭りだ。そこまでではなくとも、誕生日もちょっとした祭りなので、ぜひとも7結は上野に乗りたかった。
あわら最終日の翌日、朝5時の始発に乗って上野に乗り込むと、さっそくお花がいくつか届いていた。公演期間中は、ホールケーキをいくつももらったり、ピザやお寿司の差し入れがあったりで、ただでさえ狭い楽屋は、食べ物で足の踏み場がなくなった。だが、通常なら明けているはずの梅雨が長引き、都内の感染者数は、もう昨日より増えたんだか減ったんだかわからないほど大きな数に膨らみ、全体的な客数は落ち込むいっぽうだった。
それはまた雨降りの平日、7月末の蒸し暑い夜だった。最終日を明日に控え、特にイベントもないこんな日は、がくんとお客の数が減る。上野での出番はトップで、最終回の時間になると、お姐さん方の常連さんが、ぱらぱらと舞い込んだが、私の正の字は増えなかった。それでも、今まででいちばん上手に踊れた。お客の心が動いたような手応えもあった。しかし写真コーナーになると、誰も私の写真を欲しがらなかった。
「よかったらいかがですかー」と半裸の変態みたいなコスプレをした私はみじめで、舞台の高揚もしゅるしゅると消えていく。「それじゃあ本の宣伝でも……」と言いかけた時、トリを飾るお姐さんがお札を片手にステージ脇から飛び出てきて、私の写真を撮りたいと言った。本来はありえないことである。もしかしたらルール違反なのかもしれない。でも、私はそれと全くおなじことを、この先、誰かに姐さんと呼ばれる立場になったときに、してあげたいと思った。絶対にするだろうと思った。追いかけるように、トリの前のお姐さんも出てきて、ツーショットの写真を撮る。
自分のお客さんにまではっぱをかけてくれたおかげで、写真はたくさん売れた。写真の売上は、全て劇場のものになる。しかし、写真が売れない踊り子に仕事は来ないのだ。お姐さんたちが撮ってくれても、根本的な解決にはならない。だが、そうしたいと思ってくれたことが、どれほどの励みになることか。情けなさでも恥ずかしさでもなく、泣けた。ただ嬉しくてたまらなかった。
誕生日週である7結の上野は、目に見えるものも見えないものも、抱えきれないほどいただく日々であった。