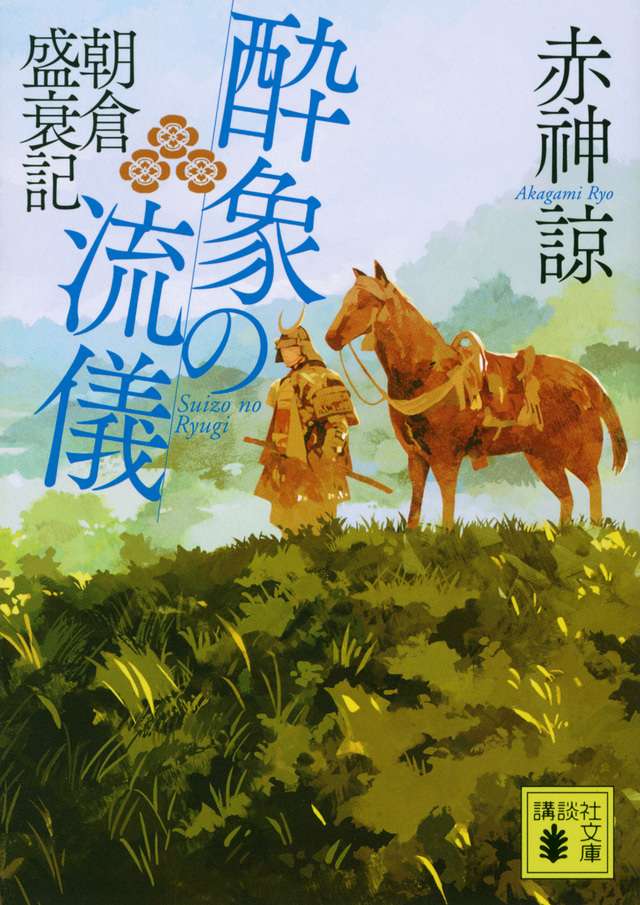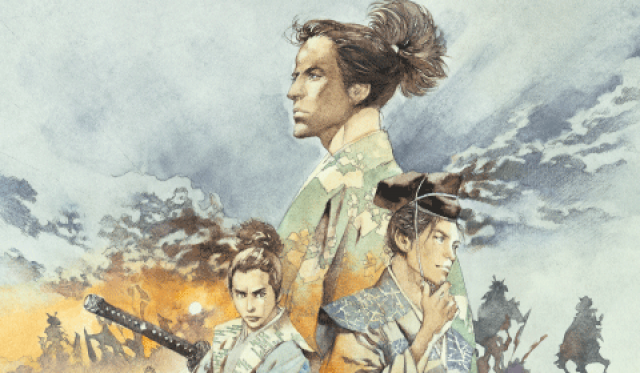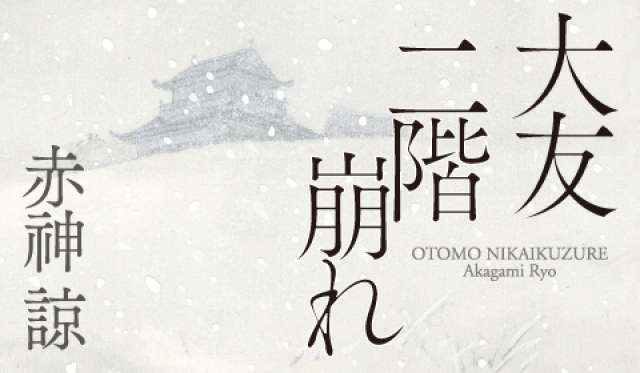◆No.8 幻の一乗谷城籠城戦 ~戦国朝倉家の7大 if(イフ)その5
文字数 1,862文字
天正元年(1573年)8月、義景は近江に出陣して織田軍と対峙しますが、寝返る家臣が出ると、形勢不利と見て撤退を始め、滅亡に直結する壊滅的な大敗を喫します。
刀根坂の戦いと呼ばれています。
『酔象の流儀 朝倉盛衰記』の物語は、この合戦の直後から始まります。
義景は、一乗谷での籠城戦を避けて大野へ逃れますが、従兄の景鏡に裏切られ、朝倉家は滅亡します。
Q: もしも義景が出陣せず、最初から一乗谷城で最終決戦を挑んでいたら、どうなっていたでしょうか。
A: 史実では、朝倉家のほうが浅井家よりも先に滅亡するのですが、おそらく浅井家が先に滅亡したでしょう。あるいは、越前に逃れて共に籠城したかも知れません。
朝倉家はどうなったか。
一乗谷城は約100年の栄華を誇った朝倉家が、念入りに作った要害です。
信長はそれほど簡単に落とせたでしょうか。
この時点では、朝倉家は長年の宿敵だった本願寺と同盟を結んでいますから、織田軍も手こずった加賀一向一揆と連携して、籠城戦を戦い抜いた可能性もあります。
家臣の裏切りが相次いではいましたが、刀根坂の戦いが起こらず、そこで戦死していたはずの山崎吉家ら諸将が健在だったとすれば、それなりの籠城戦はできたはず。
盟友の浅井家を見捨てることになりますが、一乗谷に受け入れて共に戦うという選択肢はなかったでしょうか。越前は安定して富んだ国でしたし、浅井勢も加わったなら鬼に金棒。
信玄が病没したとはいえ、武田も、本願寺も、もちろん毛利もまだ健在です。
場合によっては、上杉謙信の助力が得られたかもしれません。
史実では、後に本願寺が謙信の協力を得て、手取川の戦いで織田に勝利しました。
もちろん綱渡りではありますが、織田軍が石山本願寺や三木城攻めなどに苦労したことを考えても、朝倉家はそう易々と滅びなかったのでは……と思ってしまうのです。
もし朝倉家が存続していれば、長篠の合戦でも、信長は北に敵を抱えていることになり、武田に圧勝できなかったかも知れません。
『酔象の流儀 朝倉盛衰記』では、吉家は一乗谷での決戦を企図しますが、意外な人物の〇〇により、義景が自ら出陣し、運命の刀根坂撤退戦を迎えることになります。
吉川英治は諸葛孔明が陣没した後の『三国志』を描きませんでしたが、刀根坂後の朝倉滅亡譚は、小説とするには、登場人物が複雑に入り乱れて分かりにくく、かつ陰惨なので、少なくとも朝倉側からは描きたいとは思いませんでした。
国の滅亡に際しては、人の美しさと醜さが同時に現れるものですね。
■主な登場人物
山崎吉家 内衆の重臣。宗滴五将の筆頭「仁」の将
前波吉継 義景の側近。内衆の名門、前波家の庶子
堀江景忠 加越国境を守る国衆。宗滴五将の「義」
魚住景固 内衆の重臣。宗滴五将の「智」
朝倉景鏡 義景の従兄で大野郡司。宗滴五将の「礼」
朝倉義景 第五代・越前朝倉家当主
印牧能信 景鏡の懐刀。宗滴五将の「信」
お宰 義景の三人目の室
小少将 義景の四人目の室。美濃斎藤家にゆかり
蕗 小少将の侍女
いと 吉家の室
山崎吉延 吉家の弟
朝倉伊冊(景紀) 同名衆有力者で敦賀郡司。景鏡の政敵。
朝倉宗滴 朝倉家最高の将。