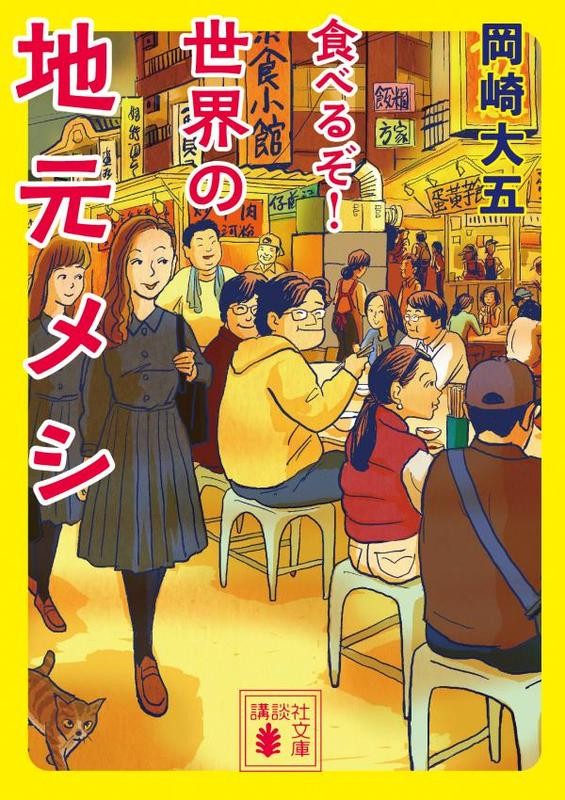◆社会主義国キューバの地元メシ
文字数 5,756文字

魅惑の国、キューバ。
資本主義が世界を席巻する中で、社会主義を押し通す。中国よりも、ロシアよりも、ベトナムよりも、より社会主義体制なのだと。
いったいどんな国なのだろう。
植民地時代の建物が建ち並び、五〇年代のアメ車がいまだに走っているという。
地元メシ探しをライフワークとする僕としては、食べ物も楽しみである。キューバの人たちはいったいどんな地元メシを食べているのか。
そこで二〇一〇年、僕と妻は、中米旅行の途中、メキシコのカンクンからキューバの首都ハバナに飛ぶことにした。距離は五百十キロ、飛行機で一時間半である。
二月上旬は繁忙期らしく欧州系の人々で満席だった。妻の頭上から水滴がポタポタ落ちる。まるで水滴責めの拷問だ。客室乗務員を呼ぶと、修理などまったく眼中にないとばかりに、にこやかにティッシュを多めに渡された。
そういうことではないだろう?
でもまあこういうことは、世界ではよくある。満席だし。不都合な事実に対しては、自分の都合のいいように解釈するのだ。文句を言っても始まらない。仕方がないので妻は、僕の持っていたタオルを頭の上に、インド人のターバンのように巻く。
そして機内食である。梅雨時の生乾きの洗濯物のような臭いのするケーキとぬるいコーヒーが出てくる。
この機がキューバの航空会社運航ということを考えると、ケーキもまたキューバ製造なのだろう。だからといって、まずいからと拒否しない。腐っていたら、それこそ拙いが、そこまでではなかったので全部いただく。
やがて飛行機が降下し始める。するとクーラーの噴出口から水煙が立ち込めてきた。
機内はまるで霧の中である。三つ前の座席ですらよく見えなくなってくる。
次から次へと社会主義国キューバの洗礼を受けているかのようだった。
不安に脅えるざわめきと緊張に包まれながら、飛行機は無事滑走路に降り立った。どこからともなく拍手が起こる。アフリカで飛行機に乗った時と同じ反応である。
空港内には万国旗が飾られていた。しかしいくら探してもアメリカ国旗はなかった。
こういう事実がやたらにうれしい。さすがに反米である。
入国を済ませると両替が待っている。米ドルからの両替だと十パーセントも手数料を取られる(反米は徹底している)ので、ユーロを事前に用意しておいた。
CUC(兌換ペソ)に両替。地元の人が利用する商店や食堂などはMN(人民ペソ)を使っているので、CUCから若干額をMNにも両替する。
ああ、社会主義って、めんどくさいね。
ホテルはこれも社会主義らしく、ざっくりと高級ホテルとカサ(民宿)しかない。インターネットで調べられるが、予約はできない。住所を示してタクシーで向かった。
町には、ピンクや水色できれいに塗装し直された五〇年代アメ車が走る。カッコいい。しかし観光客用なのだろう。いかんせん数が少ない。大半がおんぼろの車で、白い煙を吐き出しながら走っている。新車は欧州車か韓国車。市中では、今時アジアでも見かけないようなぼろバスに、褐色の肌をした労働者が鈴なりになって乗っている。
内務省のビルが見えてきた。鉄製のチェ・ゲバラの肖像アートが壁面に飾られている。実にクールだ。町で目を引くのはカストロではなく、ゲバラばかりだ。
目指して向かった評判のいいカサの建物玄関には、政府公認を示すブルーの錨マークが付いていた。間違いない。インターフォンを押すと、しばらくしてワンピース姿の老婦人が出てきた。色白である。
物腰の優雅なご婦人は、渋い顔をして首を横に振った。
わからないスペイン語だが、雰囲気で解釈するとこうである。
「中華レストランで働く中国人たちがずっと泊まっているんですの。彼らはキューバで中華料理のコック資格を取って世界に働きに行くようですわ。ですからうちは、このところいつも満室なのです」
どうやらキューバと中国は、かなり親密らしい。
おかげで僕と妻は、別のカサを探すことになった。
スーツケースを押しながら、旧市街をとぼとぼ歩く。徐々に暗くなってくる。
町は安全そうだが、着いたばかりだ。よくわからない。不安が募る。
町には年代物の古い建物が建ち並ぶ。おおむね五、六階建てである。写真ではきれいだったが、よく見ると壁がはがれ、腐った木製の柱がむき出しになっている。
下水が詰まっているのか悪臭が漂い、汚れた水たまりもそこここにある。
憧れていたハバナのイメージが、不安とともに音を立てて崩れ始める。
カサはどこにある? それにハラも減ったし。雑貨屋を覗いた。
店内にはカウンターがあり、商品はまるで温泉街の射的場のように、カウンターの奥に陳列されていた。自分で商品に触れられないばかりか、射的場の景品よりも数が少ない!
「これだけしかないのか?」
僕は英語と身振り手振りで訊ねた。
「そ、そうですが……」
白いTシャツにジーンズ姿の若い店員が、ややのけ反りながら言う。
「あ、でも、明日の朝には商品が届きますから」
一転、吞気な顔になって、彼は僕に微笑みかけた。
「……そうなんだ」
これこそが社会主義、配給制の計画経済なのである。レストランも少ないというし、にわかに飢餓に対する恐怖が胃のあたりからせり上がってきた。
慌ててビールを二本にポテチを二袋、水を一本、『白ラム酒』をMNで買っておく。
小一時間も歩いて汗だくになり、ようやく錨マークのある建物を見つけた。
アパートの中の一戸がカサを営んでいた。リフォームされた中はきれいだ。四十代のご夫婦に高校生くらいの女の子とお手伝いさんがいた。
ご主人は筋肉ムキムキで、聞けばボクシングの選手だったという。スポーツで活躍し、政府からこのような生活を与えられたのだろう。夫人のファッションは、先ほどの老婦人とは違い、どことなく成金趣味である。
一人一泊二食付きで二十二CUC(約二千六百円)は、この国では安くはなかった。「じゃあ、お肉を買ってこなくっちゃ!」と夫人が喜び勇んで出かけた。
この夜の献立は、レタスとトマトのサラダ、真っ白いごはんに煮豆とビーフステーキだった。ステーキは、ほどよい硬さで普通にうまい。煮豆に手を付ける。豆は黒インゲン豆。あずきより一回り大きい。少々煮崩れている。ごはんに混ぜて口に運んだ。
豆の丸みのある甘さが口中に広がった。ゆっくりと嚙む。やわらかい豆が米粒にまとわりついて、豆と米、二種類の甘みが重なり合ってくる。鼻からはほんのりとビネガーとコリアンダーの香りが抜けていった。
やさしいうまさにうっとりとした。
砂糖など使っていないようである。素朴な味が、かえって素材の味を繊細に伝えてくれる。パエリアやリゾットに愛用されるバレンシア米だから余計に合うようである。
料理の名前は『アロス・コン・フリホーレス・ネグロス』。キューバの代表的な家庭料理だ。豆と肉を一緒に煮込んだら、ブラジルの『フェジョアーダ』である。
空腹がおさまり、白ラム酒の『ハバナクラブ』を軽く飲む。キッチンではお手伝いさんが立って食事をしていた。サラダと煮豆ごはんだけの予定だったが、僕たちが来たことでビーフが加わった。そんなことを、肉を頰張りながらうれしそうに語った。
一般家庭では、米と豆、野菜が中心の食事なのだろう。
なるほど、だから町中で、アメリカのように超肥満体型の人を見かけないのだ。

ほろ酔い気分で妻と二人夜の町に繰り出した。
町の中心に近づくにつれ、ラテン音楽がどこからともなく聞こえだし、僕たちの歩みも軽くなる。生演奏をやっているバーでカクテルを飲む。
かのヘミングウェイが愛した『モヒート』は、ミントの葉が新鮮だからか、白ラム酒がいいせいか、爽やかで、暑気払いにもってこいだった。小腹がすいてきた。妻がメニュー表を見て、『カスタード』を発見! いわゆるプリンのことである。
注文すると、バーテンダーがカウンター下のキッチンでごそごそやっている。覗くとコーラの空き缶を半分に切った容器からプリンを出している。型もないのか?
皿にコーラ缶のかたちをしたプリンが載せられ出てきた。やや不格好である。
しかし妻は、一口スプーンですくって食べると快哉を叫んだ。
「おいしいーっ!」
なんと……な。
やや粗めの舌触り、濃厚で豊潤な味わい。どこか懐かしい。そう、その昔、母親が、子供の喜ぶ顔が見たい、その一心で作ってくれた味と似ている。
似ているが、それよりもちろんうまかった。なぜか?
二人で首を捻った。
「そもそも牛乳と卵がおいしいんじゃない」と妻。
なるほど。しかしそれだけではないはずだ。じっと食べかけのプリンを見つめる。
黒光りするキャラメルソースが妙にキラキラして見える。
「サトウキビ!」
僕と妻はプリンを指差し、声を合わせた。これが何よりプリンを引き立てていた。
それから僕たちは、世界遺産の町トリニダーに行った。トリニダーは時間が止まったような町だった。石造りの建物や路地に車はほとんど通らない。馬車が行き来し、子供たちは自転車に乗っている。日陰に集まった人たちがおしゃべりに興じる。
夕方になると街角でおじさんバンドがラテン音楽を奏でる。地元の人や観光客が集まってきて、多くが立ったまま耳を傾ける。この町の静けさが何よりの音響効果だ。混じりけのない音に混ざるのは、風の音と遠くから聞こえる子供たちの笑い声である。
演奏を聴きながら、心からくつろげた。
泊まったカサには中庭があり、食事は庭を見ながら、真っ白いテーブルクロスのかかったテーブル席でいただく。メニューはサラダと海老ごはん。
塩コショウで軽く炒めた小海老を容器に敷き詰めて、その上から米を押しずしのように載せ、皿にひっくり返せば出来上がり。白い米の山の頂を覆っているのはピンク色の海老だ。実に鮮やかできれいだ。
シンプルな料理だったが、これがなかなか。海老の甘さと米の甘さが、塩とコショウでいい塩梅に混ざり合わさる。日本に帰ったら、ぜひとも作ってみよう。
そしてトリニダーからの帰り道、ドライブインで、最高のコーヒーに出くわした。
香りが抜群、味わい深く、しかもスプーンの代わりにサトウキビのスティックが付いてきたのだ。これでコーヒーをかき回し、しゃぶる。浸してまたしゃぶる。
言ってみれば、しゃぶるコーヒー? 最後はもちろん飲んだけど。
コーヒーもサトウキビも、キューバの名産である。うまくて当たり前だった。
ハバナでの最終日はバレンタインデーである。多くの若者が晴れ着のように白い服を着ている。白い日傘に帽子から靴まで全身白というカップルもいた。
この夜僕たちは、町のレストランに『パエリア』を食べに行くことにしていた。海に囲まれたこの国で、シーフードパエリアは外せない。
午後六時過ぎ、昼間目をつけておいたレストランに赴いた。すると一軒家の店のまわりを一周するように、百メートル以上はあるだろう長蛇の列ができている。
妻を列に並ばせて、近所にある数軒のレストランをチェックする(数軒しかない!)も、どこも同じような混み具合だ。家族連れも多いが、それ以上に白い服で身を固めたカップルが多かった。
しかも、ここでもそこでも抱き合って、チュッチュ、チュッチュとやっている。
あてられるなあ……。
それくらいこの国は、夜でも安全なのだろう。
治安の良さは北中南米では群を抜き、日本以上かもしれない。
キューバの反米社会主義は、この国から自由と経済を奪った代わりに、健康と安全をもたらし、素朴と音楽を残した。
妻のところに戻って順番を待った。待つこと二時間。ようやく僕たちの番が来た。
まずはビールを頼む。渇いた喉に一気に潤いが広がった。
次に食事のメニュー表が来た。あった、これだ、シーフードパエリアだ。
ところがである。
白いシャツに蝶ネクタイ姿のマネージャーは、気の毒そうに首を横に振った。
「申し訳ございません。品切れでございます。残るはチキンだけでして」
なんだと? 前夜もチキンなのである。
しかしここで怒るわけにもいかない。この日の配給分が終了しただけなのだ。
「これがキューバの社会主義なのさ」
僕は妻に負け惜しみを言った。
そしてやんわりとチキンを断り、店を出ると、外国人専用のファミレスで、値段の高いナポリタンを食べた。
すると、これがまずかった。第一、外国人専用では、地元メシとは言い難い。
地元メシ探しは、タイミングを逸すると、痛い目に遭う好例である。
しかし、旅人らしい強がりを言わせてもらうなら、旅には忘れられない夜がある。この夜はそんな夜だったとも言えるのである。
その後、僕たちは、五つ星ホテルの最上階にあるディスコで、夜更けまでラテンのリズムに合わせて踊りまくった。
注文したのはもちろんモヒートである。
************************************
岡崎大五(おかざき・だいご)
1962年愛知県生まれ。文化学院中退後、世界各国を巡る。30歳で帰国し、海外専門のフリー添乗員として活躍。その後、自身の経験を活かして小説や新書を発表、『添乗員騒動記』(旅行人/角川文庫)がベストセラーとなる。著書に『日本の食欲、世界で第何位?』(新潮新書)、『裏原宿署特命捜査室さくらポリス』(祥伝社文庫)、『サバーイ・サバーイ 小説 在チェンマイ日本国総領事館』(講談社)など多数。現在、訪問国数は85ヵ国に達する。
岡崎大五『食べるぞ! 世界の地元メシ』好評発売中!