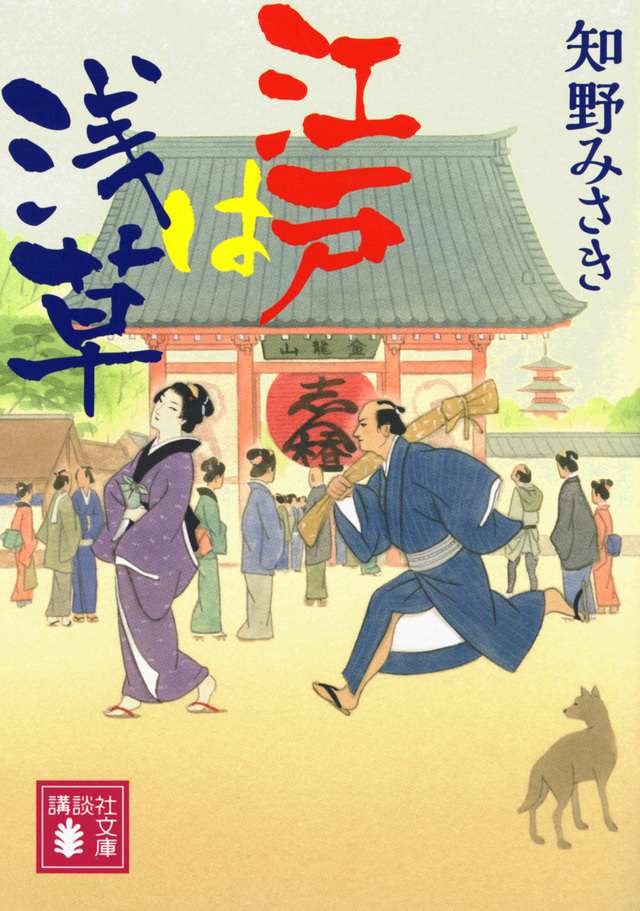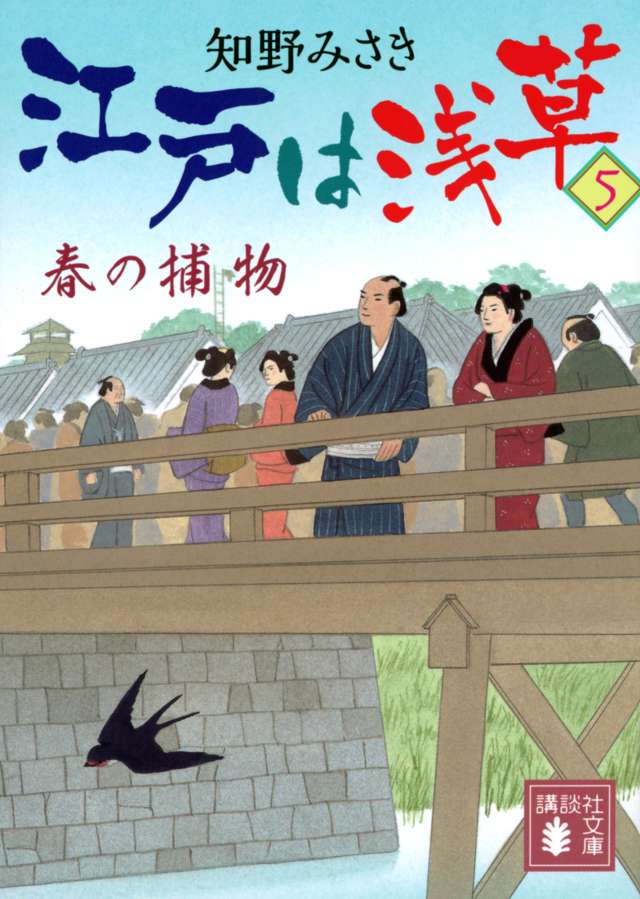第1話
文字数 38,112文字
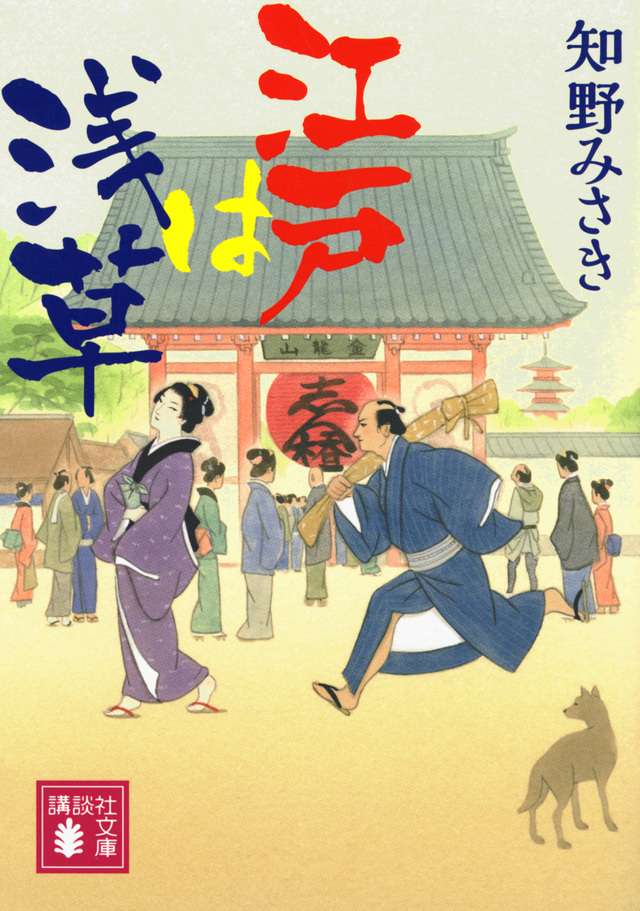
知野みさきさんの大人気シリーズ「江戸は浅草」の第一話をどんと全編試し読み!
↓↓↓からどうかお読みください!
第一話 六軒長屋
密やかに流れ込んできた冷気に、真一郎は目を覚ました。
身じろぎせずにいると、戸口が開け閉めされる擦れた音が耳に届く。
すわ盗人か? と、眉をひそめたのも一瞬で、すぐに内心苦笑を漏らした。
自分が通りすがりの見知らぬ寺の本堂に、勝手に入り込んでいたのを思い出したからだ。
天井に揺らぐ影からして、持ち込まれた火は小さいようだ。
隈なく探されない限り、端で横になっている己は見つからぬと高をくくり、そっと灯りの方を見やって今度はぎょっとする。
鬼だった。
闇に溶け込んだ墨色の着物から、白い手と足首だけを覗かせた鬼女である。
小振りの龕灯に照らされた角が揺らぎ、赤い唇がぬらりと光る。
鳥肌立ったまま身動き一つできずにいたが、これまで狐狸妖怪の類は目にしたことがない真一郎だ。
気取られぬよう恐る恐る盗み見ることしばし、女が面をかぶっていることに気付いた。
いわゆる般若の面とは違うが、よくできていて、あつらえたかのごとく女の顔にぴたりと収まっている。
丑の刻参り──じゃねぇよなぁ……
本物の鬼でなかったのはありがたい反面、何やらがっかりしないでもない。
静かに身体を起こすと、真一郎は更に女を窺った。
丑の刻参りといえば白装束だが、女の着物は正反対の黒である。五徳を頭に載せている訳でもなく、胸に鏡を吊るしてもおらず、藁人形も五寸釘も手にしていない。
何よりここは寺であって神社ではなかった。
龕灯を一旦、板張りの床に置くと、女はおもむろに着物の裾をからげた。
むっちりとした、白く艶めかしい二本の足が露わになって、図らずもどきりとする。
胸元から襷を取り出して袖をたくし上げると、女は須弥壇の裏に回った。
しばしがさごそしたのちに戻って来た女は、風呂敷包みを抱えていた。
やっぱり盗人……?
隠し金でも取りに来たのかと、首をかしげながら真一郎は女の所作を見守った。
女は座り込んで風呂敷包みを開き始めたが、背をこちらに向けているため、真一郎には中身が見えない。
片膝を立てた女の尻が見えそうになり、真一郎がやや身を乗り出した矢先、おもむろに女が両手を挙げた。
右手には槌、左手には鑿を持っている。
はっとして息を吞んだ転瞬、女が振り返った。
面越しに目が合った女が低くつぶやく。
「見たな……」
「あ、いや、その」
「見ぃ──たぁ──なぁ──」
「いや、まだ何も……」
飛んできた鑿が左耳から半寸と離れぬところをかすめて、後ろの壁に突き刺さる。
微動だにせず、真一郎は女を見つめた。
見つめ返した女の瞳が、ほんの微かだが和らいだ。
「……腰を抜かした、ってんじゃないようだね」
「小便ちびったってんでもないぜ。目はいい方なんだ。当たらねぇのは判ってた」
はったりではなかった。
鑿が女の手を離れた瞬間に、己に当たらぬことは見切っていた。
「ふぅん……」
鉈を片手に、ゆらりと立ち上がって近付いて来た女が、真一郎を見下ろして問うた。
「何故逃げぬ?」
「あんたが本物の鬼ならもう手遅れだろうし、そうでないなら、もうちっと見極めてからでも遅くはねぇと……」
噓の通じる相手ではないと判じ、正直に真一郎は応えた。
「何故ここにいる?」
「上方に行く道中なんだ。長屋はもう引き払っちまった」
これも噓ではない。
「上方? ならば何故ここにいる?」
女が繰り返したのは「ここ」が江戸の北東、向島だからだ。
江戸から上方に行くには品川宿からたどる東海道か、板橋宿からの中山道が主で、向島など通らない。
「俺はもとは常陸の出でね……一度上方へ行ったら、いつこっちへ戻るか判らねぇ──もしかしたらもう二度と戻ることはねぇかもしれねぇし、それでなくとも江戸の外に出るのは久方ぶりだ。だから今一度、筑波山を拝んで行こうと思ったんだ」
「……ふぅん」
真一郎から目を離さずに女はかがみ込み、空いた手で壁に突き刺さった鑿を引き抜いた。
鬼の面を目の当たりにし、鑿をちらつかされても、不思議と恐怖は感じなかった。
投げられた時もそうだったが、女からは真の殺気が感ぜられない。
それよりも、女の胸元から香とは違うほのかな甘い香りを嗅ぎ取って、逸りそうになる己にどぎまぎとする。
ふん、と女が鼻を鳴らした。
「とぼけた男だね」
呆れたというよりも、からかうように言って女は鉈と鑿を後ろに放った。
ゆっくり外されていく面の下から笑みを湛えた唇が覗く。
灯りを背にした女の顔は陰っているが、切れ長の美女なのは見て取れた。
「お前のせいで気がそがれちまった。相応の償いをしてもらおうか」
「つ、償い?」
「ほんの気晴らしさ」
「気晴らし?」
阿呆のように繰り返す間に、女が自ら襟元をはだいて、両腕を真一郎の首に回す。
思ったよりずっと豊満な身体に抱きしめられて、真一郎は生唾を飲み込んだ。
気晴らしでもなんでも、これほどの女を抱く機会はそうあるものではない。
この際、何者だっていいさ。
たとえこいつが狐狸妖怪の類だとしても──
急ぎ女の背中に手を回し、真一郎は夢中になって帯を解き始めた。
翌朝、真一郎が目覚めた時には、女の姿はどこにもなかった。
雨戸は閉まったままだが、隙間から差し込んでくる陽の光からして、六ツはとうに過ぎているようだ。
気怠い身体を引きずり起こして脱ぎ散らかした着物を着ると、真一郎はまず須弥壇の裏へ回ってみた。
須弥壇はほんの一尺ほどの高さで、その上に置かれている厨子も高さ四尺、幅三尺、奥行き一尺ほどとそう大きくない。そもそも本堂しかないこの寺はそれは質素なもので、六十畳ほどの床は全て板張りだ。荒れ寺というほどではないにしても、障子にはいくつか破れがあるし、陽が昇っても雨戸も開けぬような寺らしい。ただし掃除だけは行き届いていて、須弥壇の裏にも埃はなかった。
半ば予想はしていたが、風呂敷包みも見当たらない。女が持ち帰ったのだろうと勝手に合点して、真一郎は表に出るべく障子戸に続いて雨戸を開いた。
──と。
「こりゃ!」
声のした方を見やると、半町ほど離れたところに二人の男が立っている。一人はでっぷりとした坊主、もう一人は細身の町人だ。
「何しとるんじゃ、この不届き者が!」
濡れ縁を下りると、ぷりぷりしながら坊主が近付いて来る。
「どうもすいやせん」と、真一郎は深々と六尺近い身体を曲げて頭を下げた。
「すっからかんで宿に泊まる金がなく……こちらで夜明かしさしてもらいました。まだ野宿には寒くて……」
如月も半ば近く、じきに春分だが朝夕はまだかなり冷え込む。
「すっからかんだと? 博打か、女か?」
「ええと、強いて言えば女ですかね……? 浅草で子連れ女が困ってて──」
昨晩の女には話さなかったが、これも本当のことである。
追ってやって来た町人と坊主へ、真一郎はしどろもどろにいきさつを話した。
坊主は寺の住職で名は孫福。町人は隠居で名を久兵衛というそうだ。二人とも還暦近いと思われる年配で、幅は違えどほぼ五尺という背丈も揃っている。
「順繰りにまとめると、こういうことかい?」
一通り話し終えると久兵衛が言った。
「お前さんは元矢師で名は真一郎。矢師をやめて早五年。あれこれ違う仕事に手出ししてみたものの、此度はその日暮らしの江戸に見切りをつけて、生まれ故郷の常陸に寄ってから上方に行こうと思い立った」
「ええ」
「しかし、行きがけに寄った浅草寺で、困った様子の母子連れを見かけた。訊けば、女は具合を悪くして歩くのもおぼつかない。子供に頼まれて、お前さんは母親を抱えて近くの木陰に連れて行ったが、のちにこの母子に財布を掏られたことに気付いた」
「気付いてすぐに引き返したんですよ。そしたら向こうも俺に気付いて逃げ出しやがった。つまり、具合が悪いってのは芝居だったんでさ。ま、でも、路銀は道々稼ぐつもりだったんで、財布にゃ一分ほどしか入ってなかったんですがね」
江戸から上方まで行くのに、一人およそ二両かかると言われている。しかし、裏長屋暮らしの町人が二両貯めるのはなかなか難しい。
「……だが一文無しになったお前さんは、このまま江戸を出るべきか一旦留まるべきか悩んだ挙句に日暮れを迎えた。宿には泊まれぬゆえ、遠目に見つけたこの大福寺に忍び込み、ここで一夜を明かすことにした」
「この寺は大福寺ってんですか?」
真一郎が問うと、久兵衛はにやりとして応えた。
「うむ。住職が大の大福好きでな」
「こりゃ! つまらぬ噓を言うな、久兵衛!」
傍らの孫福は丸い頰を更に膨らませたが、久兵衛は構わずに話を続けた。
「お前さんが言うように、まだ野宿するには早い時節だ」
「そうなんでさ」
「雨風をよけるためだとしたら、ご本尊の観音さまも勝手に本堂に忍び込んだことを許してくれよう。だが……」
「だが?」
「日暮れから今朝まで、何ごともなかったのかい?」
「と言いますと?」
「この寺には、時折鬼が出るという噂があるんだ。だから孫福もほれ、あちらの山谷浅草町の端に住んでいる」
「だからとはなんじゃ」と、孫福が口を挟んだ。「儂はけして鬼が怖いのではないぞ。前職も町に住んでおったし、儂は町で子供らに手習いを教えておるんじゃ」
「──鬼なら見ましたよ」
真一郎が言うと、二人は揃って目を見張った。
「そ、それでおぬしはどうしたんじゃ?」と、孫福。
「どうしたもこうしたも……」
盆の窪に手をやって、躊躇いつつ真一郎は応えた。
「まあ成り行きで一戦を交えて──」
闇にしなった女の身体を思い出して真一郎がついにやけると、孫福が顔を真っ赤にした。
「な、な、なんと! あの鬼と一戦を交えたとは──それはつまり──」
その狼狽ぶりから、どうやら孫福は鬼の正体を知っているらしいと真一郎は踏んだ。
「向こうから仕掛けてきたんでさ」
「鬼から仕掛けてきたとな?」
目を剝いて孫福が問い返す。
「ええ。なんで、受けて立たねば男の沽券にかかわるってもんで……」
「こここ、この不埒者が!」
上ずった声を出した孫福の横で、久兵衛は面白そうにのんびり問うた。
「それで一戦交えたのちに、鬼はどうしたんだね?」
「それがその後、俺はうとうとしちまって……先ほど目覚めたばかりなんですが、鬼は既に影形もなく、もぬけの殻でさ」
「文字通り精根尽き果てたということだな。しかし、鬼をほったらかしにして寝てしまうとは、お前さんはとぼけた男だな」
女と同じ評を下して、久兵衛がにやりとした。
「はあ……」
女の肌身が離れていったのは判ったのだが、追うどころか呼び止めるのもままならぬほどの眠気に襲われたのだ。
「横になってたら、しばらくして何やら遠くで小気味よい──太鼓の拍子みてぇなのが聞こえてきて、それがまた眠気を誘い、ついそのまま朝まで眠りこけて……」
頰を搔き搔き真一郎が言うと、「信じられん」と孫福は憮然とし、「あはははは」と久兵衛は笑い出した。
「まったくとぼけた男だよ。だが、お前さんみたいなのは嫌いじゃない。今日はこれからどうするんだね? このまま江戸を発つのかい?」
「それにはまず先立つものがねぇと……日銭を稼ぐにも、千住宿よりも浅草の方がよさそうなんで、一旦浅草に戻ろうと思います」
「それなら儂について来るがいい」
「え?」
「え?」
真一郎だけでなく孫福も問い返して、まじまじと久兵衛を見る。
「これも何かの縁だろう。駄賃仕事でよければ世話してやろうじゃないか」
「ありがてぇ。恩に着ます」
頭を下げた真一郎へ久兵衛はにっこり頷いたが、孫福は渋面を作って見せた。
「久兵衛、こんな男はさっさと江戸の外へ追いやってしまえ」
「仮にも坊主ならそう冷たいことを言うな、孫福」
「しかしこやつは鬼と……鬼が……仕掛けて……」
ぶつぶつと言う孫福を横目に、久兵衛は真一郎を手招いた。
「さ、おいで」
まるで子供を呼ぶように目を細めた久兵衛にいざなわれるままに、真一郎は昨日通った道を戻り始めた。
どうやら六ツどころか五ツの鐘も聞き逃したらしく、もう半刻で四ツになるという。
そう聞いた途端に真一郎の腹が派手に鳴り、久兵衛が苦笑を漏らした。
まずは腹ごしらえを、と、山谷浅草町の茶屋の縁台に腰を下ろした。
真一郎に握り飯を、自身には茶だけを注文してから、久兵衛が切り出す。
「さぁて、どうしようかね? 手っ取り早く稼ぐなら力仕事になるが……」
「構いやせん。なんでもしますよ。自分で言うのもなんですが、こう見えて俺は器用者なんでさ。大概のことは並以上にこなせやす」
「多芸は無芸だ。矢師として大成しなかったのはそのせいじゃないか?」
「それもありやすが、この太平の世に弓矢なんて、もう入り用じゃないんでさ」
寛政三年。江戸に幕府が開かれて百八十八年になる。応仁の乱に始まったといわれる戦乱の世はとっくに終わり、戦で武具が使われぬようになって久しい。刀はまだ武士の証として日常的に見かけるものの、鎧や兜は飾り物となりつつあり、槍や弓はその道をたしなむ者の道場くらいでしか目にしなくなっている。
「郷里では猟師たちの矢の他に、神事のための矢もたまに作っていました。まあ、俺はそん時はただの見習いでしたがね。十三の時におふくろが死んで、親父と一緒に江戸に出て来たんです。十年ほど親子で矢作りを続けましたが、五年前に今度は親父が逝っちまって──」
父親の名は真吉で、死因は流行り風邪。罹患してから十日ほどのあっけない死であった。
「それで、これ幸いと矢師をやめたのか?」
「幸いってんじゃあねぇですが、矢師じゃ身を立てられねぇと、江戸に来た時から判ってやした。諦め切れねぇようだったが、親父も判ってたと思いやす」
剣術に比べ、弓術をたしなむ者はそう多くなく、そういった者たちは既に懇意にしている弓師や矢師がいた。試しの矢を気に入って注文してくれる者もいたのだが、暮らしを賄えるほどではなかった。江戸に移っても以前からの神事用の矢の注文は届いたものの、これとてそうあることではなく、時にはいかがわしい矢場の矢を意に反して引き受けたりもした。
「俺は親父の仕事が──矢師の仕事が好きでしたよ」
だからこそ真一郎は真吉が死すまで、絵に描いたような貧乏暮らしに甘んじて、父親と一緒に矢を作り続けた。
「もちろん、いくら作ったところで売れなきゃ金にならねぇんで、暮らしのために片手間にできる仕事はなんでもやりました。親父が死んでから矢作りはすっぱりやめて、内職から人足、振り売り、売り子、客寄せと、これまた一通りはやってみましたが、まあ何をやっても大して変わらねぇといいやすか……だったらまだ身体の利くうちに、上方に行ってみようかと。身寄りのねぇ独り身なんで、身軽なもんですや」
「そうかい……」
昨晩夕餉にありつけなかった真一郎は腹ぺこだ。
運ばれて来た握り飯を頰張る真一郎を、久兵衛は茶を飲みながらのんびり待っている。
そこへ、ぬっと、一人の男が現れた。
「見つけた──」
眉間に皺を寄せて二人を見下ろした男は、真一郎よりやや年上──三十代半ばの、身なりのよい町人である。
「別宅にいないから和尚のところかと思いきや、和尚も不在で……また二人で悪さしてたんですか?」
「お前の知ったことではないよ、重太郎」
「そんなことはありませんよ。昨日はどちらに? この十両もの借用書をどう申し開きなさるおつもりですか!」
重太郎という男が突き付けたのは、確かに十両の借用書で、久兵衛の名前と爪印が押されている。
「お前の知ったことではない」と、久兵衛は繰り返した。「儂の金をどう使おうと、儂の勝手だ」
「そりゃそうですが……しかしあのようなやくざ者に取り立てに来られては、店の体面にかかわります。お願いですから、危ないことは控えてください。両備屋の隠居として恥ずかしくない振る舞いを──」
「こんなところできゃんきゃん騒ぐな。十両ぽっちで騒ぎ立てるなぞ、お前の方こそ両替屋の主としてみっともないわ」
察するに久兵衛さんは両備屋という両替商の隠居で、重太郎はその跡取りか──
二人のやり取りから推察しながら真一郎は握り飯を食べ続けた。
「私はただ、やくざ者とかかわるような真似はなさらぬようにと。何かあってからでは遅いのですよ。先日だって、よからぬ場所で喧嘩に巻き込まれて、腰を痛めたばかりではありませんか」
「それならもう案ずるな」
息子を見上げると、真一郎へ顎をしゃくって久兵衛が言った。
「ほれこの通り、用心棒を一人雇ったでな」
「えっ?」
えっ? と、真一郎も内心思ったが、顔に出すほど未熟ではない。
何か事情があるのだろうと、握り飯の残りを急ぎ飲み下し、のっそりと立ち上がる。
「真一郎と申します」
久兵衛ほどではないが、重太郎も背丈五尺ちょっとと小柄な方だ。
目を見開いて己を見上げた重太郎へ、真一郎は丁寧に長身を折ってお辞儀した。
「あなた何を……父さん、何を勝手に──いいや、私は騙されませんよ」
重太郎は一瞬うろたえたものの、そこは店主らしくすぐに落ち着きを取り戻して、真一郎と久兵衛を交互に見た。
「ご浪人ならともなく、背丈しかないようなこんな男に、用心棒なぞ務まるものですか」
「信じられないのも無理はありやせん」と、真一郎はにっこりして見せた。「ご覧の通り丸腰の町人ですが、荒事には自信がありやす。しかし、ならず者じゃあありやせん。神田で職人をしとりましたがそっちの方はさっぱりでして、食い詰めて困ってたところを、ご隠居に腕っぷしを見込まれ、雇われたんですよ」
「そういうことだ」
澄ました顔で久兵衛が頷くと、重太郎はむっつりと渋面を作ってから言った。
「……騙されませんよ」
「お前はほんに疑り深い。まあ、とにかくお前が案ずることはない。儂とて我が身が可愛いからな。あのような無茶はもうせぬし、よしんば巻き込まれたとしても、真一郎が守ってくれよう」
「私は……騙されませんからね」
絞り出すように繰り返すと、真一郎をねめつけてから重太郎は踵を返した。
足早に茶屋を去って行く重太郎の後を、少し離れたところからこちらを窺っていた伴と思しき若者が追う。
「……やれやれ」
二人の姿がうんと小さくなってから久兵衛はつぶやいた。
それから改めて真一郎を見やり、にやりとする。
「お前さんはなかなか機転が利くな」
「はあ」
「肝も据わっておる。それとも本当に腕に覚えがあるのか?」
「まさか。喧嘩の方はからっきしですや。まあご子息が仰る通り上背だけはあるんで、はったりは利きやすが……それだけです」
「儂にはそれで充分だ。上方には急いでおらんのだろう? それならお前さん、しばらく儂の用心棒になりなさい」
「えっ?」と、今度は声に出た。
「噓をついたと、後で倅になじられるのは面白くない。一月でも二月でもお前さんを雇えば、あやつを騙したことにはならんからな。うんそうだ。それがいい。働いた分の給金はちゃんと払う。お前さんにも悪い話じゃないだろう?」
「そりゃ、稼げるなら俺に否やありやせんがね……しかし、やくざ者が相手じゃ、はったりは利きやせんぜ?」
「ああ、やくざ者の喧嘩に巻き込まれたというのは噓だ」
「え?」
「あの日は儂も、久方ぶりに一戦交えてなぁ……」
要するに色事で腰を痛めたそうである。
「だから荒事の心配はいらんのだ」
呆れたものか、感心したものか……
なんにせよ、しばらくこの老人のもとで働くのも悪くない、と真一郎は思った。
「まあ……噓も方便と言いやすからね」
「そうなんだ。が、此度は噓から出た実といこう。ちょうど長屋も一軒空いておる」
「長屋?」
「六軒町にある長屋でその名も六軒長屋──もとい久兵衛長屋──つまり儂が大家であり家主でもあるのだ。うんうん、そうだ。ちょうどよい」
一人で勝手に合点しながら折敷に金を置くと、久兵衛は立ち上がって歩き出した。
真一郎も慌てて後を追う。
早足の久兵衛から半歩下がったところを、真一郎は悠々とついて行く。
「──前の店子が昨年亡くなってな」
「亡くなった?」
「うむ。それで次の借り手が見つからぬのだ」
「それってつまり──こいつが出るってことですか?」
指先を下に両手を胸元に持ち上げ、いわゆる「幽霊」を真似てみた。
振り向いた久兵衛がくすりと笑う。
「だったらなんだ? 鬼は平気で幽霊は駄目なのか?」
「あの鬼はほら、ご隠居だってご存じなんじゃあ……? まあいいか。幽霊なんて、滅多に拝めるもんじゃねぇしな」
「そうとも。もしも出たら呼んでくれ。儂も一目、幽霊というものを見てみたい」
「ってぇと、ほんとは出ないんで?」
「判らん。儂は今まで狐狸妖怪はもちろん、死霊も生霊も見たことがないのだ」
「俺もでさ」
「なんだ、お前さんもか。……つまらんな」
「はぁ……そのお人はどうして亡くなったんで?」
「やくざ者の喧嘩に巻き込まれたのさ」
「へ?」
死んだ男の名は亥助。浅草界隈を仕切る顔役のもとで、表向きは香具師、裏では盆──賭場──で壺を振っていた。
すなわち亥助はやくざ者であり、久兵衛はやくざ者とかかわりがある──あった──ということになる。
そういうことなら、息子の心労も判らねぇでもねぇ──
真一郎はほんのちょっぴり重太郎へ同情を覚えた。
あくまでほんのちょっぴり、である。
久兵衛への興味の方が十倍も二十倍も強かった。
「年の瀬の盆が大荒れに荒れて、二十人からの男どもが殴り合ったそうだ。亥助はうちに帰って来た時はしゃんとしてたんだが──どこか打ちどころが悪かったらしい。夜中にすごいいびきをかいて、翌朝に息を引き取った」
「……さようで」
お悔やみを口にすべきか迷った真一郎を、久兵衛が振り返った。
「さ、着いたぞ」
木戸は見慣れた裏長屋のものだが、反対側の表店が広いせいか、長屋は左右に三軒ずつとこぢんまりしている。
「なるほど、だから六軒長屋……」
真一郎がつぶやいた矢先、左側の真ん中の家から湯桶を持った女が出て来た。
気怠げに戸を閉めてから、こちらを見やった女と目が合った。
昨夜の鬼女──もとい、美女である。
「あんた──」
思わず声を高くした真一郎を一瞥して、女は久兵衛に問うた。
「久兵衛さん、この人は?」
「大福寺で拾った新しい店子さ」
「大福寺で……相変わらず久兵衛さんは物好きで」
「物好きはお前さんだろう」と、久兵衛は苦笑した。
久兵衛へ肩をすくめて見せてから、女はじろりと真一郎へ向き直った。
「上方へ行くんじゃなかったのかい?」
「あ、いやそれが」
「──噓つきは嫌いだよ」
ぷいっと顔をそらして女が木戸を出て行くと、今度は右側の真ん中の家から少年が一人、興味津々で顔を出した。
「……なんだかしんねぇけど、嫌われちまったね、兄さん」
十五、六歳と思った少年は実は既に二十二歳で、名を大介といった。
「大介ねぇ……」
つい上から下まで眺めてしまったのは、大介が五尺二寸とそう高くない背丈だからだ。童顔の美男で、身体つきは細く、女も羨むだろう白い肌をしている。
「どうせ、名にそぐわねぇちびだって思ってんだろう? だが兄さんだって、そのなりのまま生まれてきたんじゃねぇだろう? 坂田の金時ならともかく、赤ん坊なんて生まれたては似たり寄ったりさ。赤ん坊がどう育つのか、名付けの時分にゃ知りようがねぇや」
「そらそうだ。すまねぇ、つい……お前さん、役者かなんかかい?」
「大介は笛師だ」と、久兵衛が言った。「と言っても、女たちと戯れるばかりで、ろくに仕事はしとらんがな」
「久兵衛さんこそ、遊んでばかりいないで、そろそろ家に戻られては? 今朝がたお梅さんがお怒りのご様子で訪ねてらっしゃいましたぜ?」
「これ、大介。何故それをさっさと言わん」
財布から一分を取り出すと、久兵衛は真一郎に握らせた。
「支度金だ。家は空なんでな。大介、ちょと面倒を見てやってくれ。釣りは不要だが、儂の用心棒として恥ずかしくない身なりをさせろ」
「用心棒?」
応える前に行ってしまった久兵衛に代わり、真一郎が事情をかいつまんで説明した。
「そりゃあ、すげぇ成り行きだね、真さん」
「そうなんだ。でもまあ、悪かねぇ成り行きさ」
真一郎がのんびり微笑むと、大介もくすりとした。
「久兵衛さんが気に入るだけあらぁな……じゃあ、ちょいと身の回りのもんを揃えに出かけようか。久兵衛さんの頼みじゃ断れねぇし、夕刻までは付き合ってやらぁ」
大介の案内で、着物やら夜具やら茶碗やら、暮らしに必要な物を次々買い込んだ。二組の着物と履物は大介の見立てで古着でもそれなりにいいものを揃えたが、他の物はその場しのぎの中古の安物だ。
残金から酒と肴を少し買って長屋に戻ると、大介が右側の一番奥の家に声をかけた。
「守蔵さん、新しく来た真さんと飲むけど、どうだい?」
「いらん」
戸口の向こうからにべのない声がしたが、大介は気を悪くした様子もなく、真一郎に顎をしゃくった。
「あの通り、ちょいと偏屈な親爺なんでさ」
長屋のことは、買い物の最中に少しずつ大介から聞いていた。
家主兼大家の久兵衛は、銀座町の両替商・両備屋の隠居で今年還暦を迎えたそうだ。左の奥、守蔵の向かいが久兵衛の家である。息子の重太郎が「別宅」と言っていたから、長屋がそうなのかと思いきや、六軒町から少し北の浅草今戸町に、梅という女と暮らす家が別にあるという。
守蔵は錠前師兼鍵師で四十七歳。錠前や鍵だけでなく、からくり箱なども手がける職人らしい。型ができると知り合いの鍛冶屋へ赴くが、家にいることの方が多い居職で、一旦仕事に取りかかると、寝食を忘れてこもりきりになるそうである。
長屋は戸数が少ない分、井戸や雪隠を含めた庭が他の裏長屋に比べると広めで、長身の真一郎にはありがたい。間取りも奥の四軒は間口も奥行も二間なのだが、真一郎に与えられた家と向かいの二軒は見慣れた九尺二間であった。
その向かいに住むのは鈴という女で二十歳──大介に言わせると「年増になったばかり」の胡弓弾き。
「目があんましよくねぇんで、七ツ過ぎには戻ってくらぁ」
「ふぅん……それで、その隣りの女は……?」
それぞれの茶碗に酒を注いだのちに、真一郎は切り出した。
本当は真っ先にそのことを聞きたかったのだが、「そいつは後で」と、道中では大介がもったいぶって教えてくれなかったのだ。
「へへっ」といたずらな笑みを浮かべてから、大介は声を潜めた。「あの久兵衛さんが見込んだ真さんを見込んで話すんだ。ここは一つ、口外無用に頼むぜ」
「おう。これでも口は堅いんだ」
「ま、下手に漏らしたら、俺よりもお多香さんが黙っちゃいねぇだろうけどな」
「あの女──人はお多香さんっていうのか」
「ああ。真さんは二十八だったね。だから真さんと同い年──おっと、こいつは聞かなかったことにしといてくんな」
うっかり、ではなさそうだったが、女に歳を訊ねるほど野暮ではない。それよりもあの多香という女が己と同い年だというのはやや驚きだ。
「二十二、三か、せいぜい中年増くらいじゃねぇかと思ったんだが……女の歳は読めねぇな。でもまあ、あの色気だ。そんなに驚くことじゃあねぇやな」
数えで二十歳になると年増、二十五歳で中年増、三十路で大年増といわれているから、二十八歳の多香は中年増よりも大年増よりということになる。
「驚いたのはこっちだよ、真さん。いや、そうでもねぇか。お多香さんは格別面食いでもねぇからなぁ……」
「どうせ俺は、背丈だけの男だよ」
己が色男からほど遠いのは百も承知だ。
でこが広めで、顎がやや角張っているが、顔はまあ人並みではないかと自負している。しかし色白でもなく、目元涼しくもなく、どことなくもっさりとした印象なのは否めない。それでもまだ火消しのごとく隆々としていればよかったのだが、食べるだけで精一杯の暮らしの中、居職と出職をいったりきたりの真一郎はどっちつかずの凡下な──背丈を鑑みれば若干細めの──身体つきでしかなかった。
「あはは、でもまあ男は面じゃあねぇや」
「……俺もそう思うが、お前さんに言われるとなんだか癪だ」
「あはははは。でもよぅ、天は二物を与えず……俺も真さんくれぇ背丈がありゃあ、今頃千両役者だったかもなぁ」
笑い飛ばした大介だったが、大介にとっては背丈はまさに玉に瑕なのだろう。
「まあ、それはさておき、お多香さんだ」と、真一郎は話を戻した。
「そうだ、お多香さんだ」と、大介も頷いた。「お多香さんは面打師だ。でもよ、女が作った面じゃあ売れねぇってんで、『貴弥』って男名を使って仕事をしてる。とはいえ、面は注文があった時に打つだけで、日頃は矢場で働いてら」
「矢場?」
「楊弓場の矢取り女だ。『当たぁ~りぃ~』ってやつさ」
女の声音を真似て大介が言った。
楊弓場というのは真一郎の父親が嫌っていた「いかがわしい矢場」で、金を取って二尺八寸ほどの小さな弓を打たせる場所だ。男客ばかりの遊戯場だから矢取りには主に女を置いている。的に当たった矢を取るためにかがんだ女が足を見せたり、集めて来た矢を渡すのに科を作ったりするので、女目当ての客も多い。ゆえに、表向きは楊弓場でも、裏で女に客を取らせる淫売宿を兼ねていることもある。
陽が昇ってから起き出して、湯屋へ行き、昼過ぎから楊弓場で働いて、注文があれば夜中に大福寺で面を打つ……というのが多香の暮らしらしい。
「大福寺の住職と久兵衛さんは旧知でね。どうせ無人なのだから、あそこで面打ちをさせてやれと。でもって、あの坊主はとんだ生臭だからよ。お多香さんを一目見て、一も二もなく承知したって久兵衛さんが言ってたぜ」
そう言って大介は忍び笑いを漏らした。
町から離れているし雨戸も閉めているのだが、時たま漏れ聞こえる音に誘われて現れる者がいるそうで、そういった者たちを鬼の面で驚かせて追い払っているのだという。
「俺は見たことがねぇけど、それは恐ろしい面らしいね?」
「ああ。だが、もっと恐ろしいのはあの鑿を投げた腕さ。お多香さんは武芸の心得があんのかい?」
「さぁ? 聞いたことはねぇけど、あの人なら何を心得てても驚かねぇな……」
そうこう話すうちに七ツの鐘が鳴った。
「じゃあ、俺はここいらで」
空になった己の茶碗を片手に大介が立ち上がる。
「ん? 酒はまだ残ってるが……ああ、女のところか」
「そういうことさ」
にやりとして戸口の外に出た大介が、木戸の方を見やった。
「あ、お鈴──」
どうやら向かいの住人が帰って来たようだと、真一郎も腰を上げる。
表へ出ると、胡弓を抱いた華奢な女がびくりと足を止めて身を固くした。
「怖がるこたねぇぜ、お鈴。この人は真さん──真一郎さんてぇんだ。久兵衛さんが連れて来た新しい店子さ」
大介より幾分低い五尺ほどの背丈で、手足は日に焼けている。
真一郎が名乗ると、かぶっていた菅笠を取って、「鈴です」と小さくもしっかり応えて頭を下げた。
化粧気がなくて細身な分、色気もないが、小ざっぱりとした愛らしい顔立ちをしている。
やや伏せた目はそのままに鈴が問うた。
「新しい方というと、私のお向かいに?」
「そうだ。四十九日もとうに過ぎたしな。亥助さんももう成仏したろうよ」
「ええ、そうですね」
「ってぇことは、やっぱり出る──出た──のか?」
「なんでぇ真さん、そんなでけぇなりしてても幽霊が怖いのか?」
「いや、出るなら一目見てみたい」
「……真さん、見損なったぜ。面白半分に言うことじゃあねぇや」
口を曲げた大介を見て、真一郎は慌てて謝った。
「すまん」
同じ長屋の住人が亡くなって、まだほんの二月ほどだ。己の発言は亥助を軽んじた不謹慎なものであった。
「ふん。お鈴、こんなやつは放っておけ」
「大介、俺が悪かった」
真一郎たちのやり取りに曖昧な会釈を返して、鈴は引き戸に手を伸ばした。
その手が引手から少し外れているのを見て、真一郎が思わず差し伸べた手を、大介が横からぴしゃりとはたく。
「てっ!」
「余計な手出しをすんじゃねぇ。お鈴はてめぇのことはてめぇでちゃんとできるんだ。なぁ、お鈴?」
鈴を見やって大介が言う。
「ええ」と、鈴は頷いた。
「目は利かなくても口は利けるんだ。助けがいるときゃ、そう言うさ。なぁ、お鈴?」
「はい。あの……お構いなく」
「ああ、すまねぇ。どうもその、慣れてなくて……」
「気を付けてくんな。余計な手出しは無用だからな」
繰り返し釘を刺されて、真一郎は内心苦笑した。
大介の言う「手出し」が男女に関する含みを持っていることに気付いたからだ。
同じ長屋のよしみか、兄貴分──はたまた一人の男としてか。
なんにせよ、愛いやつめ──
そう真一郎は思ったが、口にするほど莫迦ではなかった。
翌日から、真一郎は久兵衛の仕事をするようになった。
といっても、用心棒らしくしているのは両備屋やその客先を訪ねる時だけで、普段は買い物の荷物持ちや遣い走りに加え、時には洗濯やら飯炊きやらまで担う雑用係である。
長い茶会のために二刻も玄関先で待たされる日もあれば、朝一番に菓子を買いにやらされてそれきりの日もあった。給金──というよりも手間賃──は仕事に応じてくれるので、日によって実入りはまちまちだ。
梅のいる家へは一切伴をしないため、久兵衛が梅のところで数日過ごす合間などはまったく実入りがないのだが、長身の新参者は町の者の覚えもよい。十日もすると桜もちらほら咲き始め、花見の手伝いをするうちにちょこちょこ雑用を引き受けるようになり、それが駄賃や食べ物になった。
「真さんはなんでもできるねぇ……」と、評判も上々である。
自ら器用者と久兵衛に豪語した通り、炊事・洗濯・裁縫などの家事はもちろん、ちょっとした大工仕事から囲碁将棋の相手、子守まで、なんでもござれの真一郎だ。忙しいおかみやら、身体の利かない年寄りからは特に重宝されている。
それでも一日みっちり仕事がある日は少なく、空いた時間は散歩に出たり昼寝をしたりと気ままなものだ。
少し懐が温かい時は、多香の勤めている田原町の楊弓場へ出かけた。
亥助のことで怒った大介とは翌日すぐに仲直りしたものの、多香はへそを曲げたままである。挨拶はおざなりだし、酒や飯に誘っても、菓子を土産にしても、通り一遍の断りか礼を言うだけであった。
多香のことをもっと知りたい。あわよくば「気晴らし」でいいからもう一度──と、真一郎は期待を抱いているが、道はなかなか険しそうだ。
矢師の一人息子として生まれついた真一郎だ。初めて手にしたおもちゃは父親手作りの弓矢だったし、物心ついた時から矢場へ通い、時には猟師に混じって鳥や獣を狩ることもあったから弓術には自信がある。楊弓場へ通っているのは、無論、多香の気を引こうとしてのことだが、今のところさしたる手応えは得られていない。
──今日も真一郎は暇つぶしを兼ねて、楊弓場・安田屋に顔を出した。
しかし残念ながら多香は既に他の客の相手をしていて、真一郎についたのはみきという名の矢取り女だった。左目に泣きぼくろのあるおっとりとした愛らしい顔立ちで、二十歳そこそこの、真一郎からしたら若い女である。
五本射って五本とも的中させると、みきがいそいそと矢を取りに行く。
「相変わらず、お上手ねぇ……」
にっこり笑って、みきは両手で取って来た矢を差し出した。
どの女も男の目を誘うために襟元をわざと緩めてあるのだが、みきはもっともあからさまで、矢を受け取る際にどうしても胸元を見てしまう。
おっと、いけねぇ──
さりげなく目をそらすと、今度は少し離れたところにいた多香と目が合った。
ふっと、多香は笑みをこぼしたが、微笑というより嘲笑である。
男に媚びを売るのが仕事だから、多香も他の矢取り女同様に安田屋ではそれなりの色香を振りまいている。だがそれは総じて芝居でしかなく、たとえ客が色男でも他の女のように本気で科を作ることはなかった。
「昔取った杵柄さ。餓鬼の頃は、毎日のように矢場に通ってたからよ」
多香に相手にされぬ憂さを晴らすべく、みきを見つめて殊更愛想よく真一郎は応えた。
在所で通った矢場は道場と呼ぶほどではないが、至極まっとうな矢場だった。女は一切置いておらず、的があるだけで弓矢は自前、矢取りも客が各々行った。
「在所の矢場は猟師が多くてな……むさ苦しいところだった。おみきのような別嬪でもいりゃあ、もっと稽古に励んだんだがなぁ……」
言いながらそっとみきの腰に触れると、みきは満更でもない顔をして、逃げるどころか真一郎の胸へ軽く手を触れた。
「真さんはお世辞もお上手ね。でも私がお上手って言ったのはお世辞じゃないわ。店のみんなも驚いてるのよ。だって、ほら、うちはこういう店だから……」
真一郎が手にした矢を、つんと指で弾いてみきは微笑んだ。
楊弓場は所詮、遊戯場だ。貸し出される弓も矢もちゃちいもので、傷みや歪みがそこここにあるために、弓術に慣れた者でも正鵠を射るのは難しい。だが、これまでありとあらゆる弓矢に触れてきた真一郎は、手にしただけでその弓矢の癖を見抜くことができた。
「なんせ名前からして安田屋だもんなぁ──」と、真一郎は苦笑を返した。
安田は「あだ」とも読めるから、安田屋は「徒矢」にかけた店名である。
徒矢というのは的に当たらぬ無駄矢のことで、転じて「徒労」や「無駄骨」「肩すかし」を意味する言葉として使われている。金を取って的に当たらぬ弓矢を使わせながら、女たちにも期待はするなと言っているようなものであった。
「ほんとにふざけた名前よね」
「ああ。でも俺ぁ嫌いじゃないぜ」
「あら、お優しいこと」
ふふふと笑いを交わしたところへ、店主の房次郎が顔を見せたので、みきは慌てて真一郎から少し離れた。
「さ、真さん、次の矢を……」
楊弓場は客に矢を打たせてこその商売だ。
客のほとんどは女たちが目当てだから、中には金を渋って一本一本、やたら時間をかけて射る客もいないことはない。だが、江戸者は総じて見栄っ張りだ。生まれ育ちは常陸でも、もう十五年も江戸で暮らす真一郎も例外ではなく、貧乏でもしみったれではなかった。
みきに勧められるまま、次の五本も間を置かずに放ち、またしても全て的中させた。
「当たぁ~りぃ~」
当たるごとにみきが華やいだ声を上げ、真一郎を知らぬ客は目を丸くし、既に見知っている客は苦笑や羨望をそれぞれの顔に浮かべる。
店主の房次郎は苦笑を浮かべた者の一人で、真一郎と目が合うと、如才なく丁寧に頭を下げた。三十路過ぎの房次郎はがっしりとしていて、穏やかな顔つきでも眼光は鋭い男であった。まだ言葉を交わしたことはないものの、悪くない男だというのは女たちの様子で判る。
またそうでなければ、多香が居着く筈もなかった。
あいつがお多香の「いい人」ってんじゃあなさそうなんだがなぁ──
気まぐれに男を誘い、誘われるという多香だが、決まった男はいないらしい。が、それも大介と久兵衛から聞いただけで多香に直に確かめてはいない。
取って来た矢を渡しながら、みきが再び身を寄せた。
ちらりと房次郎が裏へ去って行くのを見やってから、声を潜めてみきは言った。
「ねぇ、真さん。真さんを見込んで話があるの」
「話?」
「内緒の相談よ。今晩、店が引けた後に会えないかしら? お願いよ」
「そりゃあ俺は構わねぇが……なんで俺に?」
みきの好意は本物らしいが、あくまで良客に対するものでしかない。みきが真一郎についたのは今日が初めてで、これまでは挨拶以外の言葉を交わしたことがなかった。
「──だって、お多香さんが、真さんは頼りになるって……」
「お多香が?」
なんだ。
そういうことだったのか。
冷たい素振りをしながらも、多香は己を気に留め、認めていてくれたらしい。
「なんでぇ、そういうことなら、おみきのために」──引いてはお多香のために──「一肌脱ぐのもやぶさかじゃねぇ」
やや照れながら真一郎が言うと、みきも嬉しげに頷いた。
──七ツ半に平右衛門町の「浜田」って店で、一杯飲みながら話しましょう──
夕刻まで遊ぶ金はないから一旦長屋に戻ったものの、みきに頼まれた通り、真一郎は七ツ過ぎに長屋を出て南へ足を向けた。
浜田という店を真一郎は知らなかったが、大介が描いてくれた絵図によると、平右衛門町でも神田川沿いで、浅草御門の北西に位置している。
あと半刻で日暮れだが、御門界隈は居酒屋、飯屋、旅籠が多く、夜遅くまで賑やかだ。
店の暖簾をくぐってから、大介がにやにやしていた理由が判った。
浜田は居酒屋でも一膳飯屋でもなく、茶屋だった。しかも、茶屋は茶屋でも男女の密会に使われる、いわゆる「出会い茶屋」である。
みきはあらかじめ真一郎の容貌を伝えていたらしい。
真一郎が迷う間もなく、気付いた番頭が部屋へ案内した。
「──ちゃんと来てくれたのね。さ、まずは一杯」
部屋で待っていたみきの頰には既にほんのり赤みが差している。一人で飲み始めていたようで、真一郎の猪口を満たす前に徳利が空になった。
「もう一本。ううん、面倒だから二本一緒に持って来て」
「おい、おみき──」
「いいのよ、真さん。ここは私が持つから……」
あまり持ち合わせのない真一郎にはありがたい話だが、なんだか投げやりなみきの様子が気になった。
「それで、おみき、話ってのは一体なんなんだ?」
「話ってのは、お多香さんのことよ」
「お多香の?」
内緒の話だとみきは言った。
まさか、おみきはお多香の秘密を知ったんじゃあ──?
そう危惧したのも束の間だ。
運ばれて来た酒を手酌しながら、みきはふふっと忍び笑いを漏らした。
「やっぱり真さん、お多香さんに惚の字なのねぇ」
「惚の字ってほどじゃあねぇが──」
「あら、だって、お多香さんを追って神田から浅草に越したんでしょう?」
「なんだそりゃ? 浅草に越したのはただの成り行きだ」
「でも、お店じゃそういう噂だわ。店でお多香さんに一目惚れした真さんは、お多香さんの素性を調べ上げて、六軒長屋に住むことを突き止めたのち、久兵衛さんに頼み込んで店子にしてもらったと──『幽霊なんざ怖くねぇ。お多香のためなら、人死にが出た家でも構わねぇ』って……」
「なんだそりゃ」と、真一郎は繰り返した。
噂の出どころはお多香だろうか?
惚れた弱みが己にあるのは確かだが、こうも大げさな噓をつかれると莫迦にされた気がして癪である。
「誰が流した噂か知らねぇが、浅草に越したのは久兵衛さんに雇われたからさ」
流石に多香との一夜は口にしなかったが、大福寺で久兵衛に出会ったいきさつを酒の肴の代わりに真一郎は語った。
話を聞く間もみきは次々と猪口を空け、更に二本の酒を注文した。
安田屋にいる時と変わらず愛想はよいが、見ようによっては自棄酒とも思える飲み方だ。
「でも……」
猪口を一息に空けて、少しとろんとしてきた目を上目遣いに、みきは科を作った。
「お多香さんとはそういう仲なんでしょう……?」
「それはまあ……だがそう深い仲じゃあねぇ」
曖昧に真一郎は誤魔化した。
恋仲ではないが、何もないことには──あの夜をなかったことには──したくなかった。
「なぁんだ」
注いだ酒を更に一息で飲み干して、みきは言った。
「まあでも、そうよね。だって本当に惚れてたら、こんなに容易く私の──他の女の誘いに乗ったりしないもの」
「いや、しかし浜田がこんな店とは、俺は──それに、お前が相談ごとがあると……」
「じゃあ浜田がこういうところだと知っていたら、来なかった?」
それは……どうだろう?
多香に悪い気がしないでもないが、袖にしているのは向こうの方だ。それなら多香と同じくこっちも「気まぐれ」に女を抱いたところで、多香に文句は言えぬだろう。何より「相談」がでまかせなら、「頼りになる」と多香が言ったというのもおそらく噓で、己はやはり多香にとっては十把一絡げの男に違いない……
そんな真一郎の胸中をみきは瞬時に見抜いたようで、けたけたと笑い出した。
「そんなもんなのよ、男と女なんて」
やや蓮っ葉に、判ったようなことを言いながら、みきは猪口を持ったまま真一郎にしなだれかかる。
「おみき──」
「ねぇ、真さん。いいでしょう……?」
「いいも悪いも……」
「いいじゃない。少しくらい羽目を外したところで、私も真さんも独り身だもの。咎められるいわれはないわ」
「それもそうだが……」
何やら引っかかる。
日頃もてない自覚があるから、何か裏があるのではと、つい勘繰ってしまうのだ。
それに──たとえ裏がなくとも、お多香と同じ店の女に手を出すのはまずくはないか?
「だが、何よぅ──」
真一郎の逡巡をよそに、甘えた声でみきが抱きついてきた。
袖から露わになった白い腕を見た途端、情欲が疑念を隅に追いやった。
「おみき──」
「真さん……」
腰に手を回し、抱き抱えるようにみきを横たえると、みきの手から猪口が転がった。
みきの名を囁きながら覆い被さり、襟元へ手を伸ばしたところで真一郎は眉根を寄せた。
くたりとして横を向いたみきからは、紛れもない寝息が聞こえてくる。
「おい、おみき、そりゃねぇぜ」
呼びながら顎に触れようとして手が止まる。
みきの目尻に浮かんだ涙が、一筋流れて畳に染み込んでいった。
「なんでぇ……」
のろのろと身体を起こすと、真一郎は枕屛風の向こうにあった夜具を広げてみきを寝かせた。上からしっかり布団をかけたのは、みきのためというよりも、己の情欲を押しとどめるためである。
「そりゃねぇぜ、まったくよぅ……」
もう一度つぶやいて、徳利に残った酒をあおると、真一郎はごろりと横になり、手枕をして目を閉じた。
──一刻ののち、みきが殺されるとは知る由もなく。
「ほんじゃてめぇは、おみきとは駒形堂の手前で別れたってのかい?」
「へぇ……」
又平という岡っ引きに問い詰められて、真一郎は頷いた。
翌朝、朝餉を終えて、五ツの鐘を聞いたところである。
神妙に膝を詰めている真一郎を、上がりかまちにどっかと座った又平が睨み付ける。
「別れたと見せかけて、後を追ってったんじゃねぇのかい?」
「だったら初めからついて行きまさ」
「そうか? 浜田で仲違いでもしたんじゃねぇのか? そんで、おみきに袖にされたのを恨みに思い、後を追って、ずぶりと一突き──」
「勘弁してくだせぇ。俺じゃあねぇです」
「真一郎は、殺しなんかするような男じゃありませんよ」
隣りに座っている久兵衛が言うと、又平はわざとらしく大きな溜息をついた。
「そうは言ってもですね、久兵衛さん、浜田の者がおみきがこいつと仲良く帰って行ったのを見てるんで」
「仲良くなんて……おみきがまだちょいと酔ってただけで……」
小声で真一郎が言い返した矢先、「そうですよ」と、表から多香の声がした。
三人揃って戸口を見やると、寝間着代わりの襦袢の胸元を合わせながら多香が現れた。
「又平さん、この人は下手人じゃありませんよ」
「そりゃまだ判らねぇぜ、お多香さん」
「判りますよ」と、多香は言い切った。「昨夜、この人があんまり遅いもんだから、私、探しに行ったんです。御門の傍で飲むと聞いていたから、提灯持って迎えに行こうと……そしたら駒形堂の前で、おみきと連れ立ってるところを見かけたんです」
「……それで?」
又平は眉根を寄せて、疑わしげに多香をうながす。
見られていたのか──と、真一郎が狼狽したのも一瞬だ。
「幸いすぐに二人が別れたので、おみきが見えなくなるのを待ってから、この人を問い詰めました」
すらすらと真っ赤な噓をつきながら、多香は草履を脱いで部屋へ上がると、真一郎の真横にぴったり座って口を尖らせた。
「……それで?」
「よりにもよって、おみきに手を出すなんて──悔しくって、家に連れ帰って一晩中とっちめてやりました」
「一晩中?」
ごくりと喉を鳴らして又平が問い返した。
多香は尖らせていた口を緩めて真一郎を見上げると、思わせぶりに微笑んだ。
「ええ、一晩中。お隣りの久兵衛さんやお鈴には悪いことをしちまいましたがねぇ……」
腕を絡めてきた多香にどぎまぎしたが、横目に久兵衛が目配せしたのをとらえた。
「又平さん。お多香の言い分は合っていますよ。真一郎とおみきが浜田を出たのが五ツとして、お多香も五ツの鐘を聞いてから、迎えに出て行きましたからね。やがて戻って来てからは……その、お多香の言う通り……」
言葉を濁した久兵衛を見て、又平は真一郎に向かって苦々しげに向き直った。
「そういうことか」
「そういうことなんですよ」
多香の厚意を無駄にせぬよう、真一郎はわざと困った笑みを浮かべて頷いた。
「すいやせん。そういう訳で、ちょいとした痴情のもつれはあったんですが、俺はおみきを殺しちゃいません」
「──ってぇことは、大介か?」
「へっ?」と、真一郎が驚いたところへ、「俺でもねぇや」壁の向こうから声がする。
どうやら隣りで聞き耳を立てていたらしい。
ひょいと戸口から顔を覗かせた大介に、睨みを利かせて又平が言う。
「おみきの長屋で聞いたんだ。てめぇもおみきといい仲だったみてぇじゃねぇか」
「そりゃもう六月は前のことでさ。おみきさんだけが女じゃねぇし、おみきさんも俺とはただの遊びだった」
「噓をつけ。おみきはつい先日も、同じ長屋の女にお前に会いに行くと言ってたんだ」
「だとしたら、そいつぁ、おみきさんの噓でさぁ」
「どうかな? てめぇはこの新入りにおみきの心が移ったのが悔しくて、可愛さ余って憎さ百倍。二人の後をつけた挙句に、おみきが一人になったのを見計らってずぶりと──」
又平の推し当てを、大介は肩をすくめて一蹴した。
「おみきさんにはこれっぽっちも未練はねぇし、殺しをするほど女に不自由してもねぇ。俺ぁ、昨夜は五ツまで中にいましたぜ。尾張屋の座敷持で冬青って女に訊いてみてください」
中、というのは吉原のことである。
大介の台詞を聞いて、又平は舌打ちを一つ漏らして立ち上がった。真一郎たちを一回りねめつけると、無言で踵を返して戸口を出て行く。
又平の足音が充分遠ざかったのを確かめてから、多香がすっと身体を離した。
「お多香、その、助けてくれて──」
真一郎が礼を言う前に、どすの利いた声で多香が言った。
「どういうことか、初めから残らず白状しな」
「いや、だから」
「俺も聞きてぇな」
「儂も聞きたいねぇ」
にやにやする大介と久兵衛にうながされて、仕方なく真一郎は口を開いた。
「だから又平さんに言った通り、相談ごとがあるとおみきに誘われて──まあ相談ごとってのはでまかせで、ただの気晴らしというか、ふいに人恋しくなったような……」
じろりと多香に睨まれて、真一郎は慌てて付け足した。
「だがお多香、俺はおみきに手出ししちゃいねぇ」
「そうなのかい?」と、大介。
「そうとも」
大きく頷いて見せてから、真一郎は続けた。
「俺は浜田があんな店とは知らなかったが、ただ引き返すのは野暮じゃあねぇか。だからしばらく世間話をしつつ飲んでたら、いつの間にか寝ちまって……又平さんにだってそう言ったろう? ただ酔い潰れたのを、又平さんが勝手に勘繰っただけさ」
「いつの間にか寝ちまった、ねぇ……」と、多香は疑わしげだ。
「信じられねぇのも無理はねぇ……実は酔いに任せておみきが誘ってきたんだが、俺は頑として突っぱねた。俺ぁ、お多香一筋だからよ。他の女に惑わされたりするもんか」
「ふぅん……」
「そ、それに何より、お多香の勤め先の女に手出しするほど戯けてねぇや」
にべのない返答につい余計なことを言ってしまったが、これにも多香は「ふぅん」と一瞥したのみである。
久兵衛が苦笑しながら先をうながした。
「それで世間話をしながら酒を飲み、二人して寝こけてたら茶屋の者に起こされた、と」
やがて五ツの鐘が鳴り、茶屋の者が起こしに来たのである。
「おみきは七ツ半から一刻半分の部屋代しか払ってなかったそうで……まだ酔ってたが歩けねぇほどじゃなく、泊まりはもったいねぇから一緒に帰る、と」
──眠っちゃうなんて……ごめんなさいね──
乱れのない着物を見やって、みきは殊勝に謝った。
──なんなら続きは私の家で──
──いや、今日のとこはまっすぐ帰るさ──
真一郎が応えると、困惑と安堵の混じった顔をして、みきは再び頭を下げた。
──真さん、ほんとにごめんなさいね──
「一人で平気だと、おみきが言ったんだ。ここからなら長屋はそう遠くないから、と。歩みは鈍かったが、千鳥足じゃあなかった。おみきは遠慮したんだが、俺は夜目が利く方だから、浜田で借りた提灯はおみきに持たせて、駒形堂の少し手前で別れたんだ」
しかし又平の話によると、みきが長屋に戻ることはなかった。
駒形堂から二町ほどにある長屋の木戸を通り過ぎ、西へ少し進んだ三島明神社の裏手で出刃を刺されて死したのである。暗がりに置き去りにされたみきの亡骸は、家路を急いで来た者によって町木戸が閉まる四ツ前に見つかった。
「大介、お前が中にいたってのは本当なんだろうな?」と、真一郎は念を押した。「おみきとは、もうまったく会ってなかったのか?」
「ああ、最後に会ったのは昨年の文月だったか葉月だったか……岡っ引きの旦那に噓をつくほど大それちゃいねぇよ、真さんと違ってさ」
「なんだと?」
「案外肝っ玉が据わってんだな。お多香さんや久兵衛さんの芝居にしれっと乗ってよ。それに、おみきさんに誘われても思いとどまったなんて、真さん、思いの外、一途だねぇ……」
からかい口調の大介に、憮然としながら真一郎は言った。
「思いとどまってつくづくよかったよ。危うくてめぇと兄弟になるところだった」
「つれないこと言うねぇ……俺ぁ、ちっとも構わねぇぜ。真さんと兄弟になってもさ」
ぬけぬけと言って大介はちらりと多香を見やったが、氷のごとく冷ややかな目に射すくめられて、慌ててそっぽを向いた。
「どうもつまらねぇことを──」
もごもごと詫びた大介へ多香は小さく鼻を鳴らした。
「まったくだよ……男どもはこれだから」
「これ、お多香。男ども、と一括りにするのはよしとくれ」
見かねた久兵衛が割って入る。
この機を逃すまいと真一郎は話を戻した。
「それにしても、誰がおみきを殺ったのか……」
「そうなんだよなぁ」と、大介も首をひねる。
すると、「ちょうどいい」と、久兵衛がぽんっと小さく膝を打った。
「儂は昨日ちょうどお梅と、飛鳥山へ今年最後の花見に行こうと話しとったんだ」
「はあ……」
「王子の旅籠でゆるりとしてくるゆえ、三日は戻らん。真一郎、お前はその間に、大介と一緒におみきの下手人を探しておいで」
「──え?」
「そうだそうだ。それがいい。下手人が見つかれば、お多香もお前たちをちっとは見直してくれるだろうよ。なぁ、お多香?」
「はあ」と、素っ気なくも多香が応える。
「よしよし。ならば真一郎、ちと支度を手伝え。支度が調い次第、儂はお梅のところへゆくからの──」
費えとして久兵衛から渡された金は一両。
「二人で割って三日で二分か。けちくせぇ仕事だな」
「そうか?」
大介は不満げだが、真一郎はそうでもない。
二分は一両の二分の一で、一両は六千五百文である。振り売りの実入りが日に約千二、三百文だから、少ないといえば少ないが、振り売りのように一日中担ぎ物をしなくともよいし、次の日の仕入れ金も無用だ。
「大体、岡っ引きの旦那たちが既にあちこち走り回ってんだ。俺らの出る幕なんざねぇさ」
「そうでもないぜ、大介。あの人らは俺やお前を疑って、余計な足を使ってる。それに俺らには又平さんにはない強みがあらぁな」
「又平さんにない強み……?」
「お前だ、大介。ちょいとおみきの長屋へ行って、女たちから話を聞いて来いよ」
大介に会いに行く、と、みきが同じ長屋の女に言っていたというのが気にかかる。
「それをお前が噓だってんなら、おみきには誰か密かに会ってた男がいると思うのさ。そいつはきっと、他の女に自慢したくなるような色男なんだろう。なんらかの訳があってそいつの名を明かせない代わりに、おみきはお前の名を口にしたんじゃねぇか? おみきに男がいたならそいつが下手人かもしれねぇし、そうでなくても、そいつは俺たちの知らない何かを知ってる筈さ」
「なるほど……真さん、存外鋭いこと言うねぇ」
「存外たぁなんだ」
「だって、いつもなんだかのんびりしてるからよ……じゃあ俺は、おみきの長屋に行ってくら。真さんはどうする?」
「俺は浜田に行ってみる。あすこの番頭はおみきを見知っていたようだから、おみきが連れ込んだ他の男を覚えてねぇか探ってくるさ。その後は安田屋に行って──」
「安田屋なら、私が探ってくるよ」
戸口から湯桶を持った多香が顔を覗かせた。
「どうせ仕事で出向くんだ。私はおみきが気に入らなかったし、あっちも私を嫌ってたけど、こんな死に様は気の毒だからね。それに大介ならともかく、あんたが訊ね回ったところで、女たちはろくにしゃべっちゃくれないだろうよ」
どうせ俺は背丈だけの──と拗ねたくなったが、大人げないと思い直した。
己よりも多香が適役なのは明らかだし、これで随分手間も省ける。何より、多香が力を貸してくれるのがただ嬉しい。
「じゃあ、安田屋の方はお多香に頼まぁ」
微笑んだ真一郎には応えずに、多香はふいっと戸口から離れて行ってしまった。
「お多香さん、やっぱり真さんに気があんのかな?」
「そう見えるか?」
「きっとわざとつれねぇふりしてんのさ」
「それは早計だ。わざとじゃねぇ時もごまんとあるからな……」
お前には判らんだろうが……
胸中を察したのか微苦笑を漏らした大介をうながして、真一郎は長屋を出た。
みきの時とは逆に、駒形堂まで大介と共に行くことにする。
大介の話から、みきが既に二十六歳だったことが判った。
「二十歳そこそこだと思ったんだが──」
驚きを隠せぬ真一郎へ、大介がくすりとする。
「若作りに苦心してたからなぁ、おみきさんは。お多香さんを嫌ってたのも、歳が近かったせいさ。お多香さんの方が年上で、見た目もおみきさんより上に見えるけどよ。お多香さんは男に執着しねぇ性質だし、面のおかげで金にも苦労してねぇし、おみきさんには妬ましかったらしいや」
睦言でそれらしきことをよく匂わせていたという。
「──だから俺を誘ったのか」
多香に執心──というほどでもないが──している己を口説くことができれば、少しは多香の鼻を明かすことができると考えたのだろう。
「俺を誘ったのだってきっと同じ理由さ」
そうでもねぇだろう──と思ったが、これも大介の気遣いかと、口にはしなかった。
駒形堂を過ぎたところで大介と別れ、浜田に向かう。
浜田の番頭は真一郎を見てはっとしたが、事情を話すとわざわざ他の者を呼んで玄関先を離れ、真一郎が知りたかったことを裏であっさり話してくれた。
みきにはやはり男がいた。
「色白の優男で、名前は大さん──」
「大さん?」
あの野郎──と、大介を疑ったのも一瞬だ。
「大次郎とか大三郎とか、大方そんな名前でしょう。お客さんほどじゃありませんが、背が高くてすらりとしたぼんぼんです。お忍びなのかいつも駕籠で乗り付けて来て、頭巾で顔をあまり見せないようにしていますんで」
「年の頃は?」
「それもお客さんと同じくらい。二十五、六ってとこでしょうかね」
幾分若く見られたようだが、女と違って大して嬉しくはない。
「──昨夜も来てましたよ」
「えっ?」
「おみきが来る少し前に駕籠で……だからおみきが来た時、てっきり大さんと待ち合わせたのかと思ったら、後からのっぽの──つまりお客さんが来るから、と」
「おみきはその、大なんとかって野郎が来てることを知ってたのか?」
「おそらく。大さんが来ているか問われたので、『お待ちですよ』と私が言ったら、『あら大変。今日は違う人と待ち合わせなのよ』……と。しかしさほど困った様子ではありませんでした」
「初めから俺を当て馬にするつもりだったんだな」
「そのようですね」
年下の真一郎にも慇懃な番頭は三十代半ばだ。このような店に勤めているからには、男女の機微にも聡いと思われる。
「……真相を知ってお客さんが逆上したんじゃないかと思ったんですが、違ったようですね。しかし大さんは、昨夜は五ツ前に駕籠でお帰りになりましたが──」
「女はどうした?」
「女は朝までこちらに。部屋代は大さんが払われました」
「大さんは、帰りの駕籠は店に呼ばせたのか? 見知った駕籠舁きなら、教えてくれ」
「見知った者たちですが、あれたちも大さんの家は知りませんよ。いつも越後屋の前で降ろすように言われるそうです」
越後屋は言わずと知れた、室町にある呉服屋だ。
「この店では客の素性をいちいち調べてるのか?」
番頭の周到な応えに感心しながら、真一郎は問うた。
「誰も彼もじゃありませんが、うちのような店は何がもとで足をすくわれるか判りませんからね。用心に越したことはありません。お客さんのことも少し存じておりますよ」
「俺の?」
「両備屋のご隠居の用心棒だとか。又平さんにお話しした時は、それと知らずにご無礼いたしました」
含みを込めた言い方から、久兵衛は己が思っていたよりもずっと顔が広いようだと真一郎は踏んだ。番頭がすぐに話に応じてくれたのも、久兵衛の雇い人と知ってのことだろう。
「ただの遣い走りさ」
真一郎が言うと、番頭はようやく微笑を浮かべた。
「番頭の粂七と申します」
「真一郎だ」
「これに懲りずに、どうか今後も浜田をご贔屓に」
如才なく頭を下げた粂七に苦笑を返して、真一郎は浜田を後にした。
一旦長屋に戻ろうか、それともこのまま越後屋まで足を運んでみようかと、思案しながら浅草橋の袂に出ると、「真さん」と大介が呼び止めた。
「男の手がかりが得られたからよ。真さんがまだ浜田にいねぇかと思ってそっちに向かってたとこさ。頭一つ出てると、こういう時に便利だね」
「まあな。それで手がかりってのは──?」
「おみきに男がいたのは間違ぇねぇ。おみきは俺と寄りを戻したようなことを言ってたらしいが、長屋の女たちは薄々疑ってたらしいや。それで名前やなんかは判らねぇけど、おそらく塗物を扱ってる男じゃねぇかと……」
「塗物?」
大介が相手ではなかったと知れると、女たちはしたり顔で頷き、それぞれの疑惑を吐露し始めた。その中で等しく口にしたのが塗物だった。
この三月ほど、みきは時折、分不相応な塗物を持ち帰っていたという。
「椀ならまだ判るが、盆やら重箱やらは一人暮らしには贅沢だ、きっと男絡みに違いないとみんな思ってたらしいぜ」
「そうと聞いたら、大介、これから室町へ行こうや」
「へ?」
「越後屋の近くの塗物屋を探すんだ」
橋を渡って浅草御門を通り抜けながら、真一郎は粂七から聞いたことを大介に告げた。
「じゃあ、相手はおそらく塗物屋のぼんぼんで、大の字を名前に持つ男……」
「そういうことさ」
頷いて見せると、真一郎を見上げて大介がにやりとする。
「ちょいと面白くなってきたね、真さん」
「ああ、なんだか面白くなってきた。おみきには悪ぃが……」
不謹慎だと判っているが、手がかりを得るほどに何やら胸が浮き立ってくる。
それに下手人を突き止めることができれば、ちったぁ供養になるかもしれねぇし──
真一郎と大介、大小の二人は連れ立って早足で室町を目指した。
越後屋で辺りを見回して、真っ先に目に入った向かいの塗物屋に行ってみる。
いくらなんでも向かいの店ではないだろうと思ったが、同業なら「大さん」を見知っていてもおかしくない。
店先で客を見送ったばかりの手代と思しき男を呼び止めて訊いてみた。
「すいやせん。ちと、大さんのお耳に入れたいことがあるんですが、いらしたら呼んできてもらえませんかね?」
「大さん?」
「こちらの若旦那の大さんで」
ああ、それなら──と、手代は一石橋の方を指さした。
「大五郎さんの店ならうちじゃなくて、北鞘町の『山埜』って店ですよ」
「そうでしたか。越後屋の近くだと聞いたんでてっきりこちらだと……助かりやした」
丁寧に礼を言ってから、大介をうながして北鞘町へ急ぐ。
「大五郎で大さんらしい」
「早くそいつの面を拝んでみたいね。おみき殺しがばれた時の吠え面をさ」
相手がぼんぼんの色男で、同じ「大」の字を持つせいか、大介の台詞には何やら対抗心が滲んで聞こえる。
「そいつが殺したと決めつけるのはまだ早いが──」
真一郎が苦笑しかけた矢先、行く手から怒号が聞こえた。
「しらばっくれんじゃねぇ!」
聞き覚えのある声だと思ったら、山埜の店先から昨日出会ったばかりの又平が出て来た。
もう一人、やはり岡っ引きと思われる別の男に襟首をつかまれ、細身で色白の男が暖簾の向こうから引きずり出される。
あいつが大五郎か……
「わ、私じゃありません。私は殺しなんかしちゃいないです……」
「噓をつくな! おめぇはおみきにしつこくされて、こらえきれずに夜道でずぶりと──」
「そ、そんな……いくらしつこくされたからって、殺しなんて大それたことは……」
「そうですよ。いくらなんでも倅が殺しなんて──」
山埜の店主──大五郎の父親──と思しき男がすがるように後に続く。
「まあ、まずは番屋でじっくり話を聞こうじゃねぇか」
涙目の大五郎を、岡っ引きがしょっ引いて行く。後に続いた又平は真一郎たちに気付いたが、小さく鼻を鳴らしただけで、何も言わずに通り過ぎて行った。
「……早速お前の願いが叶ったな、大介?」
「そうだけどよ……又平さんに先を越されるたぁ、なんだかしらけちまった」
真一郎も同じ思いだ。
「──とはいえ、俺らは岡っ引きでもなんでもねぇ。やつを問い詰めたところで、うまくいったかどうかは判らねぇし、かえって手間が省けたじゃねぇか」
「けどよぅ……真さんは太っ腹だなぁ」
微かな皮肉のこもった大介の台詞に、真一郎は小さく肩をすくめた。
改めて野次馬を見回すと、同情的な者は思ったより少なく、大半は面白半分といった態で、冷笑を浮かべている者さえいた。つい三間ほど離れたところに佇んでいる二人の女もうっすら笑みを浮かべていたが、一人は真一郎と目が合うと、慌ててうつむき踵を返した。
二人は連れではなかったらしく、残った女は店先でおろおろしている奉公人たちを見つめている。
女に聞こえるように、真一郎はやや声を高くしてつぶやいた。
「あの若旦那、とうとう刃傷沙汰になっちまったか……」
大年増の身なりのよい女は、真一郎を見上げて一瞬眉をひそめたが、真一郎が微苦笑を漏らすと、我が意を得たりとばかりに近付いて来た。
「私もずっと、いつかこんなことになるんじゃないかと思ってましたよ」
鉄漿と丁寧な物言いからすると、近隣の店のおかみらしい。
「相当なたらしだったようですからね」
「ええ、泣かされた女は数知れず……この界隈で年頃の娘を持つ者は用心していて、だから近頃は浅草だの深川だの、少し離れたところで遊んでたんですよ。店の手伝いもせずに、親御さんからお金をせびっては遊び呆けてる、顔だけのどうしようもないぼんぼんでした」
言いながら、女はちらりと大介に目をやった。
むっとした大介に目配せをして、女に会釈を返す。
やがて散り始めた野次馬に混じって、真一郎たちも室町を後にした。
「それでそのまま戻って来たのかい?」
呆れた声で言った多香の茶碗へ、真一郎は酒を注ぎ足した。
多香の隣りでは、守蔵がちびちびと一杯目を口に運んでいる。
大五郎が捕まったので、帰りしなに手つかずの費えから酒を買ったのだ。捕まえたのは岡っ引きだが、下手人を見つけたのだから仕事はこれまでだと、残金を大介と山分けし、守蔵を酒に誘ったところへ、多香が安田屋から帰って来たのである。
「だって、岡っ引きがしょっ引いてくのに、手出し口出しはできねぇよ」
「そうだそうだ」と、大介も頷く。「一足違いで惜しかったけどよ。岡っ引きの旦那らが目星をつけたやつにたどり着いたんだから、俺たちも捨てたもんじゃねぇ」
「そうだ、大介」
「そうとも、真さん」
笑みを交わした真一郎たちを見やって、多香が大仰な溜息をつく。
「まったく浅はかなんだから、男ってのは……」
「なんでぇ、お多香」
真一郎が口を曲げると、守蔵がぼそりと言った。
「番屋にはついてかなかったのか?」
「ついてったところで、又平さんに追い払われるだけさ」と、大介。
「じゃあ、そいつが下手人かどうか、しかと確かめてはないんだな?」
「でもよ、守蔵さん」
「そいつはやってねぇって言ったんだろう? お前たちと同じじゃねぇか」
「けどよ、守蔵さん」
「──詰めが甘ぇんだよ」
呆れたようでも怒ったようでもなく、ただつぶやいて守蔵は立ち上がった。
「ごちそうさん」
一杯だけなら──と言った通り、きっかり一杯しか飲んでいない。
持参した茶碗を片手に出て行く守蔵の背を見送ってから、多香が言った。
「守蔵さんの言う通りさ。あんたたち、祝い酒にはちと早いよ」
そう言いながらも多香は瞬く間に茶碗を空にして、大介へ顎をしゃくって酌をうながす。
「……どういうことでぇ?」
むくれた大介に、己の茶碗もついでに差し出しつつ、真一郎は問うた。
「安田屋の女たちから聞いたのさ。十日ほどばかり前の、私が店を休んだ日に、女が一人遊びに来たんだと」
「女が──安田屋に?」
弓術をたしなむ女もいないことはないだろうが、楊弓場の客にはまずないことだ。
「そりゃもしや、男色ならぬ女知音……」
物知り顔で顎へ手をやった大介へ、「莫迦」と真一郎と多香の声が重なった。
知音とは親友や情人を意味する言葉だ。つまり、「女知音」というのは「男色」──男を好む男──とは逆の、女を好む女のことである。
「莫迦たぁなんでぇ。しかも二人揃ってよぅ」
「おみき殺しの話をしてんだぞ? おみきが女知音だったとは到底思えねぇから、その女はおみきを探りに来たんだろう。つまりそいつはおそらく大五郎の女さ」
「その通り。その女は下手な弓を打つ間に、ついた矢取り女におみきのことをいろいろ訊ねたそうだよ。矢取り女の方はどうせ男絡みだろうとぴんときて、当たり障りのない応えで誤魔化したって言ったけど、おみきの顔かたちは見られているし、あの人の後をつけるのは易しかったろうから、長屋を突き止められててもおかしくない」
「しかし、浜田の番頭は、女は朝まで店にいたと……」
「女だからって夜道を行けないこたないよ。浜田は吉原のように鉄漿どぶも見張りもないからね。抜け出そうと思えばいつでも抜け出せるさ」
折々に夜道を大福寺まで行く多香だ。なるほどと思わぬでもないが、多香のような豪胆な女はそういるものではない。
それよりも──
「──大五郎の女が一人とは限らねぇしな。現にあいつはおみきに気を持たせつつ、他の女を浜田に連れ込んだんだ」
「そうだね」
すんなり得られた同意に気をよくしながら、真一郎は大介に言った。
「おい、明日は朝一番に又平さんのとこへ行くから案内してくれ。大五郎が下手人ならそれでよし、そうでないなら、もう一度おみきの長屋へ行こう」
「朝一番って……」
ぼやきながら手酌する大介をよそに、真一郎は多香が安田屋で訊き込んだことを詳しく聞くことにした。
みきを探りに来た女は二十歳かそこら。これは安田屋の女たちの見立てだから、間違ってはいないだろう。ほどよく愛らしいところがみきと似ているばかりか、みきと同じく左目の目尻に泣きぼくろがあったという。
それを聞いて、真一郎の頭にぼんやり一つの顔が浮かんだ。
二日後の夕刻。
六ツが鳴る少し前、駒形堂から三町ほど西にある三島明神社に、一人の女が現れた。
しっかり化粧を施した顔に、両子持縞の入った紅海老茶色の着物が愛らしい。
手水場で髷や化粧を確かめてから、六ツが鳴ると鳥居まで戻る。
女が所在なく辺りを窺うこと四半刻。
あと十日ばかりで卯月とあって陽気はいいが、日が暮れていくのは止められない。
じりじりしてきた大介を手でなだめること今しばし、足下がぼんやりしてきたのを見計らって、真一郎は社の後ろから囁くように女を呼んだ。
「お紋……」
「大五郎さん、いつからそこに隠れていたの? 意地が悪いわ……番屋に連れて行かれたと聞いて、私、気が気じゃなくて……疑いが晴れてよかった──」
声を疑われなかったのは幸いだった。待ちくたびれていたからか、増していく闇が心細かったのか、「意地悪」と言いつつも紋は何やら嬉しげだ。
が、紋の足音が社に近付いて来た時、おもむろに真一郎の隣りにいた多香が歩み出た。
「ひっ!」
紋が悲鳴を上げたのも無理はない。
袖で顔は隠しているが、多香が着ているのはみきが殺された時に着ていた藤色の着物で、胸から腰にかけてべっとりと血が染み込んでいる。幽霊らしく足下は見えないように、裾と足は墨で染めてある。
「よくも……お紋……よくも……」
地の底から絞り出されたような声音は、とても作り声には聞こえず、社の裏で真一郎と大介は顔を見合わせた。
「私は……ああ、おみきさん……私はその──あっ」
そっと表を盗み見ると、紋は腰を抜かしたらしく、尻餅をついていた。
その目はみきの幽霊に扮した多香に釘付けで、真一郎たちにはまったく気付いていない。
「……この恨み……どうしてくれよう……? 無念……まさかお前に殺されるとは……」
おどろおどろしい声で多香が続けると、頭を振りながら紋が応えた。
「だって──だって、おみきさんが悪いのよ……私のことを笑うから……」
目立たぬように置いていた龕灯から、真一郎が香木を焚き付けるのを、横から大介が団扇でそっと扇ぐ。
長屋暮らしには少し贅沢な沈香は、殺されたみきが愛用していたのと同じ物だ。
一段暗くなった境内に、沈香のほのかな蜜の甘みを含んだ香りが漂い、ふとするとまるで己が煙に紛れて消えてしまいそうな気がする。
逢魔が時とはよく言ったものだ──と、真一郎は両手を握りしめた。
扇がれた香がまた一筋流れていくのを見送ると、多香が微かに鼻を鳴らした。
「……笑うしかないじゃないか……私もあんたも……あの人にいいように遊ばれて……捨てられて……」
わななく声で紋は必死に言い繕った。
「だから──だから私、仇を取ったのよ──」
「仇……?」
「そうよ! おみきさんと私、二人の仇よ。私を──私たちをもてあそんだ大五郎さんが、罪に問われないのはおかしいわ──」
「それであんたは大五郎さんを……お上に密告したんだね……」
「そうよ……あんな男、獄門になっちゃえばいいのよ。そしたらもう、どんな女も抱けないもの……」
多香を──みきの幽霊を──見上げて、紋は乞うた。
「ねぇ、だから許して、おみきさん……」
「許す……? 何をこざかしいことを……あんたは懲りずに大五郎さんの誘いに乗って、ここまでのこのこ来たんじゃないか……」
「そ、それは──それは違うわ……」
ふっ、と嘲笑を一つこぼして、多香が声を低めた。
「……許さないよ」
「え?」
「あんたも、大五郎も許さない──」
袖を下ろした多香の顔を見て、紋が細く、高い悲鳴を漏らした。
「こうして鬼となったからには、地獄の果てまで追い詰めてやる──」
「いやっ! 堪忍してっ!」
泣きながら紋が突っ伏したところへ、男の声がした。
「おみき……もうよかろう。成仏するのだ──」
十手を手に草藪から飛び出して来たのは、岡っ引きの又平だった。
「儂の留守にそんな面白いことが……これ真一郎、何故儂の帰りを待たなんだ?」
「そんな無茶な。三日分しか費えをくれなかったのは久兵衛さんですよ。とすりゃ、こちとらも三日でけりをつけたいってもんで」
「むぅ……」
八ツを過ぎて、王子から戻って来た久兵衛に、一通り顚末を話したところである。
多香の隣りの久兵衛宅にて、真一郎に久兵衛、大介、多香の四人が集まっていた。
鈴はいつも通り、守蔵は鍛冶屋へと出かけている。面打ちの仕事が入った多香は、今日は安田屋を休んだらしい。
──二日前の朝一番に、ぶつぶつ言う大介に案内させて、真一郎は又平の家を訪ねた。
大五郎は、岡っ引き二人が脅してもすかしても殺しを認めず、とはいえすぐさま放免する訳にもいかず、室町の番屋に留め置かれたままとなっていた。
又平が大五郎にたどり着いたのは、一通の落とし文──密告──があったからだ。
この文は紋が仕込んだ物で、塗物屋・山埜の大五郎が一旦室町に帰ったのちに、別の駕籠でみきの長屋がある浅草の三間町へ向かったというようなことが書かれていた。
又平が大五郎を調べてみると、みきと思しき女がよく店を訪ねていたことが判った。そこで室町を縄張りにする岡っ引きに持ちかけ、一緒に大五郎を問い詰めたところ、浜田の名を出した途端に落ち着きを失ったので、疑惑を深めてしょっ引いた。
「それにしても、お紋という女は……恐ろしいな」
「そうなんでさ」
久兵衛が言うのへ、真一郎は頷いた。
紋も大五郎がもてあそんだ女の一人ではあるが、あの日大五郎が浜田で落ち合った女ではなかった。その女は番頭の粂七が言った通り、朝まで部屋で眠りこけていたようだ。
大五郎は紋と切れていなかったが、飽きはきていたようである。二月ほど前からつれなくされるようになった紋は、その分大五郎への執着を深めていった。みきも幾度か山埜に足を運んだようだが、紋の比ではない。「よく店を訪ねていた」のは実は紋の方だったのだが、又平が誤解したのも無理はなかった。
並べて見れば違いは明らかなのだが、みきと紋は顔立ちや背格好がよく似ていた。加えて二人とも左目の目尻に泣きぼくろがあったからだ。
左目の目尻に泣きぼくろ──
多香からそう聞いて真一郎が思い出したのは、山埜の前で薄笑いを浮かべていた女だった。
言葉を交わした人妻ではなく、真一郎と目が合うと慌てて去って行った女の方である。
多香から話を聞いたのちに、山埜と三島明神社、そして三間町近辺を調べて回った。その結果、あの時笑っていた女が紋──安田屋でみきを探っていた女──だと判った時、真一郎は紋の罪を確信した。
紋は二十一歳で、みきの長屋から三町ほど南東の諏訪町で暮らしていた。朝のうちは煮売り屋の仕込みの手伝い、日中は縫い物の内職をして暮らしを立てていたため、みきを始めとする大五郎の「浮気相手」を探る融通が利いたらしい。
みきが真一郎に誘いをかけた頃、紋は山埜へ大五郎に会いに行っていた。用事があるとけんもほろろに袖にされて一度は引き下がったものの、女の勘といおうか、ほどなくして出かけて行った大五郎の後をつけて浜田にやって来た。
やがてみきが浜田に現れ、紋は大五郎の相手がみきだと思い込んだ。
湧き上がった怒りと憎しみは、まず、みきに向けられた。通りすがりの金物屋で出刃を買い、それから既に突き止めていた長屋の近くでみきを待ち伏せた。
出刃は脅すためで、殺すためではなかった──と、紋は言った。
「大五郎さんのことで話がある」と言うと、出刃を出すまでもなく、みきは素直について来たそうだ。だが「別れて欲しい」と懇願した紋を、みきは鼻で笑い飛ばしたという。
──あんたも私も、とっくに振られてるんだよ。今頃あの人は浜田で、あんたでも私でもない女とお楽しみ中だよ……──
──そんな噓、誰が信じるもんですか──
──噓なもんか……ああ、それにしても笑っちまうね。泣きぼくろが好きだと言ってたけど、何もこうも似た女を選ばなくてもいいのにね。もしかしたら、今抱いてる女も、私らと同じく、ここにほくろがあるかもね──
笑いながらみきが左目を指したのにかっとして、思わず出刃を取り出したと紋は言った。
みきを一突きにしたのち、紋は振り返りもせずに一目散に己の長屋まで逃げ帰った。
どうやら出刃を引き抜いたのはみきだったようで、紋は返り血を浴びなかった。ゆえに道中でも長屋でも怪しまれることはなかったが、己のしでかしたことに、恐れおののきながら一夜を過ごした。
恐ろしい──と、久兵衛が言ったのはその後のことだ。
翌日、岡っ引きが探しているのがみきの「男」だと知って、昨夜の後悔はどこへやら、紋は大五郎を陥れることにしたのである。
「可愛さ余って憎さ百倍……又平さんの勘もあながち外れちゃいなかったってことか。まったく執念深い女は怖ぇや」
しみじみと大介がつぶやいた。
「ほんに恐ろしい……だが、何やら哀れな……」
大五郎にたぶらかされた紋に同情を見せた久兵衛を、一瞥して多香が言った。
「何が哀れなもんですか。逆上して人殺しをするなんて……莫迦莫迦しい」
「だがほら、お紋は既に親兄弟を亡くしていて、身寄りがいなかったそうじゃあないか。大五郎にいいようにもてあそばれたのも、きっと寂しさを紛らわすため……」
「だからなんだってんです、久兵衛さん? おみきだって、私だって身寄りがいない独り身だけど、あんな男にすがるほど間抜けじゃないし、ましてや人殺しをするほど愚かじゃありません」
「そりゃまあ、そうだが……」
言いかけて久兵衛は口をつぐんだ。
「だが、なんです?」
お紋はまだ、年増になったばかりの世間知らずで──
言いかけたのは大方そんなことではないかと真一郎は推察したが、口にしたりはしなかった。還暦の久兵衛からしたら紋はまだ小娘だろうが、世間知らずというほど若くはない。久兵衛の同情は判らぬでもないが、より同情すべきは殺されたみきの方である。
「いやぁ、それにしても首尾よく運んだもんさ」
気を損ねた多香へ少しおどけて言うと、大介も合わせて大きく頷いた。
「ああ。あのお多香さんの芝居はすごかった。まるで本当におみきさんが乗り移ったかのごとく……こう、黄泉の向こうから聞こえてくるような声で」
「まさに」
「噂の鬼の面も拝めたけどよぅ……面だと判ってても、ちびりそうになっちまった。あれに脅されて腰を抜かさなかったとは、すげぇな、真さん」
「それほどでも……」
「吞気なだけさ」
一蹴してから多香が付け足した。
「でもまあ、ぼんくらじゃあないからよしとしようか。あんた、あの又平さんを、よく説き伏せたもんだね」
紋が下手人だと当たりをつけたはいいが、証拠がなかった。そこで紋自ら白状させるべく思いついたのが、あの芝居である。
大五郎の名で三島明神社に呼び出せば、紋は必ず来ると又平に言い切った。
──お紋がうまく引っかかれば又平さんの手柄になりやす。万一しくじった時は、素知らぬふりして立ち去ってくれりゃあいい。そしたら又平さんに味噌はつかねぇ──
又平にはそんな風に持ちかけて、立会人として草藪に潜んでもらったのだ。
紋への言伝は、頼み込んで守蔵に行ってもらった。一目とはいえ、己と大介は紋の目に触れているし、多香では余計な疑いを抱かせてしまうと思ったからだ。
──誰がおみきを殺したのか知らないが、お紋、私にはもうお前しかいない。番屋ではお前のことばかり考えていた。六ツに三島明神で落ち合おう。まずはおみきの冥福を二人で祈ろうじゃないか──
「……そういうお多香こそ、よくあの着物を借りてきたな」
そればかりか、あれだけ血が染みた着物を多香は眉一つ動かさずに身にまとった。
「清めたのちは死に装束を着せるから、どうせ捨てられる物だったんだ。それなら供養がてらに借りたところで、誰が困る訳でもないさ……」
「でもよぅ」と、大介が口を挟んだ。「怖くなかったのかい? あんなに血が──それこそおみきさんの恨みがこもったような着物を着てさ」
「何が怖いもんか。怖かったのも痛かったのも、おみきの方さ」
寂しかったのも、哀れなのも──
そんな言外の言葉を聞いた気がして、真一郎は多香を見つめた。
「なんだい?」
「いや……あの着物、大福寺で焚き上げてもらうんだろう? それなら、こいつも一緒に持ってけよ」
差し出したのは、懐紙に包んだ沈香の残りだ。卯月も近いとあって、みきの亡骸は既に荼毘に付されていたが、着物は今日これから多香が大福寺に持って行くことになっている。
芝居の小道具として、みきが愛用していた香木を買って来るよう多香に言われた時は、その値の高さに驚いたものだ。しかし、そう裕福でもない暮らしの中で、値の張る香木を買い、身繕いに余念のなかったみきを思うと、安物で代用したくなかった。
「ほんの少しでいいって言ったのに、見栄張って一かけも買って来るんだから」
「見栄なんかじゃねぇ。ほんの少しでいいって言うから、一かけしか買わなかったんだ。まあ……いいじゃあねぇか。ちょいと高いが線香代わりだ。お前だってそう思ったから──」
窺うように言うと、多香はふんと笑ったが、そこに嫌みや嘲りはなかった。
「ただの遣い走りのくせして、太っ腹だねぇ。お紋を探るのに、三間町や諏訪町辺りで随分まいないをばらまいたってじゃないか。加えて守蔵さんの駄賃に、足下を隠すための墨と刷毛、この沈香……」
「そうなんだよなぁ」と、ぼやいたのは大介だ。「結句、手元に残ったのは二百文とちょっと……」
大介がちらりと久兵衛を見やったので、真一郎もそれに倣ったが、久兵衛はぷいっと顔を背けた。
「儂の帰りを待たんからだ。三日分の費えを三日で使い切ったのだから文句はあるまい」
「そりゃねぇですぜ、久兵衛さん」
大介は更にぼやいたが、この一月ほど「用心棒」をしてきた真一郎は、久兵衛が時折見せるこういった子供じみた振る舞いにはもう慣れっこだ。
「まあ、いいじゃねぇか、大介。おみきの仇は取れたし、三日間そこそこ旨いもんを飲み食いできたんだしよ」
下手人の紋が捕まったのもそうだが、騒ぎで女癖の悪さが世間に知れ渡った大五郎は、これからそう好き勝手にできぬだろう。
「真さんは、ほんと太っ腹だなぁ」
多香と違って嫌みを含んだ──だがどちらかというと呆れた声で大介が言った。
その日の夕刻。
六ツの鐘が鳴るのを聞いて、横になっていた真一郎は目を覚ました。
顚末を聞いた久兵衛はまたしても梅のところへ、多香は大福寺へ、大介は誰だか知らぬが女のところへと、それぞれ出かけて行った。さしたる用事のない真一郎は、夕刻まで一眠りすることにしたのだった。
向かいの鈴と二軒隣りの守蔵は既に戻って来ている筈だが、長屋はひっそりとしたものだ。
空腹を覚えて財布をつかみ、近くの蕎麦屋にでも行こうと引き戸を開けると、驚き顔の女が立っていた。
「あ、あの……私は喜乃と申します」
「真一郎です」
驚いたのは真一郎も同じだ。起き抜けとはいえ、女の足音にまったく気付かなかったからである。喜乃と名乗った女はおそらく三十路過ぎ。地味な顔つきと身なりだが、腰つきには年相応の色気があった。
ふっと、喜乃が笑みをこぼした。
が、口角を上げた口元とは裏腹に、潤んだ瞳を喜乃は急いで指で拭った。
「驚かせてごめんなさいね。なんだか──あの人が出て来るような気がして……」
「もしや、亥助さんの……?」
真一郎が問うと、喜乃は小さく頷いた。
「といっても、とうとう祝言は挙げてもらえなかったけど……」
──俺のように賭場に出入りしているような男とは、一緒にならねぇ方がいい──
ことあるごとにそう言っていたのだと、喜乃は言った。
それが男に都合のいい噓ではなかったことは、長屋の住人から聞いた話や、涙を押しとどめながらも笑おうとする喜乃の様子から判った。
「今日は、久兵衛さんにお礼を言いに来たのだけれど、どうやらお留守のようですね」
「ええ。今戸町の別宅に行っておりやす。おそらく今日はそちらへ泊まりかと」
「お梅さんのところね。それじゃお邪魔するのは悪いから、言伝を頼んでいいかしら?」
「もちろんです」
「此の度、無事に煮売り屋を始めることになったと伝えてください。小さな裏店だけど、東仲町に。私、やっぱり浅草を離れたくなくて……支度に一月ほどかかってしまったけれど、親分と久兵衛さんのおかげだと」
「親分」「一月ほど」と聞いて、真一郎の脳裏に一つ閃いた。
「あの十両の証文か……」
「ご存じでしたか? 身の振り方に困っていた私に、親分と久兵衛さんがお金を出し合ってくだすったんです。その……あの人の香典代わりに、と」
「そうでしたか……」
相槌を打つ真一郎の後ろを窺いながら、喜乃が問うた。
「あの……もしや、何か見たり──出たりしませんか?」
「出るってぇと、亥助さんの? いやそれが残念ながら──」
言いかけて、慌てて口をつぐんだ。
面白半分に──ましてや喜乃に向かって──言うことではなかった。
じわりと喜乃は再び目を潤ませたが、怒りからではないようだ。
「そう……本当に残念だわ。なかなか借り手がつかないと久兵衛さんが言ってたから、もしかしたら、この時分に来ればあの人に会えるんじゃないかって……」
西の空はまだ橙色だが、二軒分の灯りしかない六軒長屋は宵闇に包まれつつある。
涙を拭うために喜乃が取り出した手ぬぐいの白さが、真一郎の胸を締め付けた。
「すいやせん」
なんと言ったものか判らぬ真一郎がただ謝ると、喜乃は困った顔で苦笑を漏らした。
「あなたが謝ることじゃあないでしょうに」
「まあ、その……」
「よかったら、そのうち店にいらしてね」
「ええ、そのうち寄せてもらいやす。でもって、もしも──」
「もしも?」
「もしも亥助さんを見かけたら、そんときゃ、飛んで知らせに行きやすんで……」
言ってから、つまらぬ冗談に聞こえたかと、おそるおそる喜乃を見やったが、喜乃は気にした様子もなく、手ぬぐいを胸に抱いて微笑んだ。
「必ずよ。必ず知らせてちょうだいね」
雑用をこなしつつ、六日が過ぎた。
夕餉を食べて一旦横になった真一郎だが、五ツ半を過ぎた頃、向かいの長屋の戸が密やかに開け閉めされるのを聞いて起き出した。
真向かいの鈴の家の戸ではなく、その隣りの多香の戸口である。
多香が木戸を出て行くのを見計らって、用意していた包みを懐に、真一郎も家を出る。
七日前に注文を受けた多香が、どうやら今宵面を打ちに行くらしいと、日中、久兵衛から聞いていた。
町木戸が閉まる前で、表にはまだちらほらと人通りがあった。
真一郎は提灯を持っておらず、長潮の月明かりは頼りにならぬが、夜目が利く上、多香の行き先は判っている。ゆえに多香の持つ小さな龕灯を追いながら、半町から一町ほど離れて、真一郎はのんびりと大福寺への道のりを歩いた。
山谷浅草町の町木戸を抜けてしばらくすると、四ツの鐘が鳴った。
大福寺に着くと、足音を立てずにそぅっと忍び寄り、濡れ縁に上がった。
雨戸の外から様子を窺うことしばし、小気味よく──迷いのない槌音が聞こえてきた。
多香が面打ちだと聞いて思い当たったのだが、以前、眠りの中で聞いた太鼓のような音は、多香の槌音だったのである。
濡れ縁に横になり、真一郎はひととき槌音に聞き入った。
槌音は四半刻ほど続いたが、一旦途切れたところを見計らって、声をかけてみる。
「お多香。俺だ。真一郎だ」
本堂は束の間しんとしたが、やがて足音が近付いて来た。
引き戸に続き雨戸が静かに開いて、鬼の面が真一郎を見下ろした。
三度目でもついぎょっとしてしまうほど、よく出来た面である。
ずいっと一歩前に出た多香が、冷ややかな声で問うた。
「何故ここにいる?」
「今夜辺り、お前が面打ちをするんじゃないかと、久兵衛さんが教えてくれたんだ」
「だが何故あんたがここにいるのさ?」
「そりゃ、その、久兵衛さんが言うにゃ、面打ちは根気がいる仕事だと……」
「そんなの錠前師でも笛師でも矢師でも一緒だろ」
「そらそうだが、あまり根を詰め過ぎるのはよくねぇ。大福でも食いながら一休みはどうかと思ってよ。『八千代屋』の大福を持って来た」
つれなくされている真一郎を気の毒に思ったのだろう。菓子なら、聖天町にある八千代屋の大福が多香の好物だと、数日前に鈴が教えてくれたのである。
「八千代屋の大福か……気が利くじゃないか」
膝を折った多香が鬼の面を外した。
襷で露わになった白い二の腕に加え、やや汗ばんだ額、うなじ、そして胸元……
出会った時と同じく、ほんのりとした甘い匂いが真一郎の鼻をくすぐった。
開いた戸口から漂ってくる白檀の香りとは、また違った匂いである。
「……茶はねぇけどよ、こいつで一休みしながら、その、『気晴らし』でもどうかと──」
さりげなくつばを飲み込み、微笑んだ真一郎へ、多香もにっこりと笑みをこぼした。
どきりとしたのも一瞬だ。
白い腕がひょいと伸び、真一郎の手から包みを取った。
「そりゃどうも、ごちそうさん」
立ち上がって腰を伸ばしながら多香が言った。
「ありがたく、後で一人でゆっくりいただくよ」
「おい、お多香──」
「仕事の邪魔だ。とっとと帰んな」
「そりゃねぇぜ、お多香。もう町木戸も閉まってら。俺は提灯も持ってねぇし……」
「じゃあ、そこらで朝まで野宿だね。この陽気なら風邪を引くこともないだろう」
「お多香──」
腰を上げかけた真一郎の眼前で、ぴしゃりと無情にも雨戸が閉まる。
「そりゃねぇぜ……」
がくりとうなだれてから、真一郎は再び濡れ縁の上に身体を横たえた。
あと五日もすれば卯月である。多香が言うように風邪を引くことはなさそうだ。
仰向けになると、月が細い分、満天の星がよく見える。
──悪かねぇ。
多香と出会い、六軒長屋に住むようになって一月半が経った。
六軒町での暮らしぶりは以前と大して変わらぬが、久兵衛の案で、駄賃の中から少しずつ久兵衛に預けてきたおかげで、掏られた金と同じくらいは既に貯まっている筈だ。
だが……
──今しばらく江戸にいるのも悪くねぇやな……
夜空にちりばめられた星を見上げていると、本堂で再び槌音が響き始めた。
粗彫りは終えたようで、先ほどよりやや小さく、柔らかな槌音だ。
そうとも。
てんで悪かねぇ……
くすりとして目を閉じた真一郎は、快い音に身を任せて春の夜をまどろみ始めた。
気になった方は↓↓↓