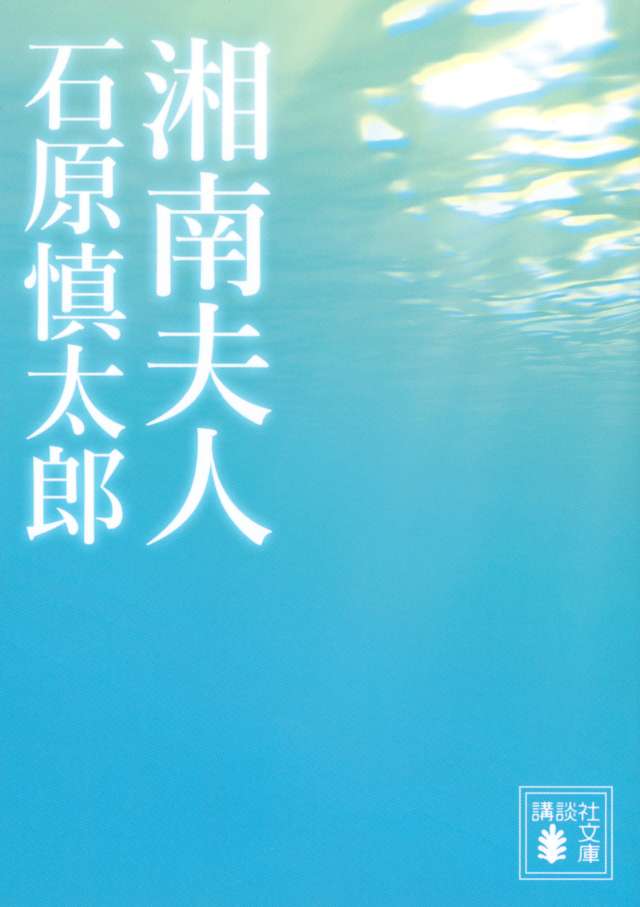-追悼 石原慎太郎-「極」なる海をめざした文学者/富岡幸一郎
文字数 7,011文字

石原慎太郎氏が2022年2月1日、逝去されました。
謹んでお悔やみを申し上げます。
文芸評論家の富岡幸一郎氏による追悼文を転載します。(「群像」2022年4月号より)
石原慎太郎小論
富岡幸一郎
二月一日に石原慎太郎氏が八十九歳で亡くなった。訃報に接したのは午後だったが、その日の夕方にかけて二つの新聞社文化部からコメントを求められ、翌日別の新聞社から追悼文の依頼があった。この文章を草しているのも本誌から二月五日の午後に依頼があった(その直前、石原氏の追悼文を書いていた西村賢太氏の急逝を知って驚いた)からだが、まとまった石原慎太郎論を書いたことがない自分としては正直少し意外であった。政治家・石原慎太郎の世上に〝物議〟を醸しながらの華やかな活動の陰にかくれて、作家・石原慎太郎は今日、世間からも文壇からも忘れ去られているのか。
周知のように一九六八年、三十五歳で史上最高の三百万票余を得て参議院議員に当選後の石原氏は、東京都知事時代もふくめて、何よりその政治家としての言動が衆目の一致するところとなった。政治家になった後も創作活動を続けていったのは(『生還』『わが人生の時の時』『秘祭』といった代表作を書く)、政治と文学を、理論(雑誌「近代文学」に集った第一次戦後派のような)ではなく、実践において敢行しようとの企図があったからだろう。「政治は表現である」というテーゼが若き石原氏のなかに滾っていたのは確かである。
参議院議員になった直後、『季刊藝術』(一九六八年十月)での江藤淳との対談「人間・表現・政治」で石原氏はこう語っている。
《……小説の場合には小説家が描こうと思う情念なり芸術的な理念というものをもたなければ、小説を書くというひとつの機能が生れてこないし、表現が機能として働いてこない。ところが、理念がなくても政治という機能は動いているんだよ。それが現代の日本の政治の悲劇で、政治が表現になってないんだ。表現すべき理念がないのに政治の機能だけがあるんだよ》
では、その後の石原氏の半世紀にも及ぶ政治活動は、政治に語り得るべき「理念」を持ち込み、その表現者たり得たのか。タカ派「青嵐会」(一九七三年)の旗揚げ(幹事長)にせよ、環境庁長官・運輸大臣・東京都知事等々その政治パフォーマンスは際立ったが、時代や状況のなかで「表現すべき理念」を実現したかと問えば、否であると思う。石原氏は政治家として一個の表現者たらんとしたが、それはあくまでもこの国の「戦後」体制への批判者、反逆者としてであり、何か新しい思想や価値をそこで表現することはなかった。いや、できなかったのではないか。学生作家として『太陽の季節』でデビューし芥川賞を受賞したのが、昭和三十一(一九五六)年であったことは改めて確認されていい。同じ年の経済白書は、敗戦からの経済復興をさして「もはや戦後ではない」とのキャッチフレーズを打ち出し、前年(昭和三十年)には自由党と民主党との保守合同、右派と左派に分かれていた社会党が統一され、いわゆる「五十五年体制」がスタートした。つまり、政治と経済とが「戦後の終焉」という偽装を開始した、まさにその時である。政治家・石原慎太郎はこの偽装にたいして、一貫して強い憤懣と抑えがたい羞恥を表わしたが、現実には今日ここに至るまで、日本人は自ら進んで自存自立の矜持を持つことなく、この「戦後」に従属してきた。国家や経済だけでなく、個人の自我も、敗戦・占領以来の「戦後」のなかに埋没させ続けている(この二年間のコロナ禍はそのことを顕在化している)。時代を真に転換させる政治の「理念」などあり得ようはずもない。政治家としての石原氏は、この長い長い「戦後」体制の持続装置と化した「政治の機能」に苛立ちながら、晩年は橋下徹氏のような者を持ち上げる「暴走老人」(本人の言葉)になるしかなかったのは致し方ない。
しかし、それでも石原慎太郎氏を常に時代の表現者たらしめたのは、いうまでもなく彼が一個の作家であったからだ。実際に今回、十巻に及ぶ『石原愼太郎の文学』(二〇〇七年一月一日~十月刊、文藝春秋)を改めて繙きながら、その光彩陸離たる文学表現には圧倒されるほかはなかった。
初期作品でいえば、『太陽の季節』というタイトルだけが人々の記憶に残っているが、暴力や蛮行を描いた『完全な遊戯』や『処刑の部屋』の情感を抑制した怜悧な文体の緊密さは見事であり、麻薬中毒のピアニストの奏するジャズのライブを再現してみせた『ファンキー・ジャンプ』などは今日読んでも前衛的、実験的であり、散文のなかに詩の輝きが鮮烈に放たれている。三島由紀夫が、『太陽の季節』をその題材(学生拳闘選手)と「本質的にまるで反対の文章、学生文学通の文章」と評した同じ作家のものとは思われない言葉への求心力がある。後年の傑作『わが人生の時の時』の掌編の文章の凝縮力はすでにここにある。たとえば、『ファンキー・ジャンプ』について江藤淳はかつてこう評論している。
《ここで作者は、小説を詩に反転させ、さらに詩の言葉をジャズのビートそのものに反転させて、そのかなたに彼の「完璧」とそれをとらえようとしてもがく麻薬中毒者の天才的ピアニストの行為のイメージを描き出す、ということをやってのけた。特筆すべきはこの作品にある強烈な現存感─読者が悪魔的な演奏をじかにその耳で聴いているような感覚にとらわれるということである》(新潮文庫『完全な遊戯』解説 一九六〇年九月)
この言葉の技巧による「反転」の行為。ここに石原作品の魅力と衝撃力の出発点があり、原点がある。ちなみに、『完全な遊戯』については、『石原愼太郎の文学』の九巻の解説で、中森明夫氏が『戦後短編小説再発見』(講談社文芸文庫)のアンソロジー第一巻(「青春の光と影」)に収録され、太宰治から大江健三郎、三島由紀夫と錚々たる作家たちの秀作の並ぶなかで、その衝撃力は他を圧して突出していると指摘する。
《これは石原文学の最高峰であることに間違いない。いや、百年後、二百年後、仮に石原慎太郎という名前やその存在が忘れ去られる時代が到来したとしても─断言したい─必ずこの作品だけは生き残るだろう。『完全な遊戯』は日本語で書かれた短篇小説の最高傑作である》
私自身も二十年前に『戦後短編小説再発見』の編者の一人としてこの作品を改めて読み、作中の若者たちの反倫理や虚無的な荒廃ぶりよりも、明治以降の近代小説の文学的文章を扼殺する、その日本語の力に瞠目した。今回再読してもその印象は変わらない。古びていない。昨年の日本文藝家協会編の『文学2021』の解説者として十六の短編について─「現代文学の最前線」と称して言及したが、ここに『完全な遊戯』一編をまぎれこませたらどうだろう、と思う。遜色がないどころか、その破格の文体の堅牢さは現代の「最前線」の顔色をなからしめるだろう。
もちろん文学的な修辞や叙情的な比喩が、石原作品にないわけではない。長編『星と舵』では、太平洋の無限の量感の水の連なりのなかへヨットで雄々しく漕ぎ出しながら、海そのものが原初の母胎となっていき、また船も女体の官能を体現する。また中編『行為と死』は、第二次中東戦争(エジプトのナセル大統領のスエズ運河国有化に端を発した英仏両国の介入によるイスラエルのシナイ半島侵攻)を背景にして、この戦争に巻き込まれていく日本人の商社員の主人公が、現地のファリダという女性と戦火のなかで究極的な愛の交わりを至福の時として体現する物語であるが、アラブ人たちの戦いに、愛のために生命を賭す異教徒の陶酔を描く筆致は流れる星々のように美しい。爆破するための船を女に見立てて暗闇の海を泳ぐ男は、冒険小説の主役のようでもある。しかし、この作品では死を抱いた愛の恍惚と充足は、全てが終わり日本へと帰国して何の危険もない安穏で平凡な日常のうちに戻ると、たちまちに自堕落な、醜悪な精神の屍となって現われる。作家の言葉はここで「反転」して、女との性愛に溺れてゆく主人公の姿態を奇妙な生物のように描き出す。戦争小説、冒険小説の文体の抒情性は、一転して荒涼とした抽象のなかへと拡散する。
《痙攣の海の中で、彼女は海精のように叫んでいる。いや、叫んでいるのは彼でもある。
「死ぬ!」
彼女は叫ぶ。
〝死ね。死ぬがいい。この果てに在るものは死よりも遠い極なのだ。そして俺たちは、死すらも通り抜けて今この極の極に到り、それを開こうとしている。
そこへ到りつくより前に、お前は死ぬと言うのか─〟
彼は彼女を嚙んでくわえ、引き戻す。嚙んでくわえながら彼女を、彼自身をこの極の極に向って曳いていく。
凝固した彼女の眼、彼女はもう何をも見ていない。何も感じようとはしない。彼女は彼女を脱け、全く彼の内にいる。二人は今完全に等しい一個だった》
その「極」はしかし日常のなかで繰り返され、惰性によって反復されるがゆえに偽物でしかない。血と肉が飛び散る戦乱のスエズの時空、死の君臨のなかにだけ、確たる存在として現われる真の「極」に対して。
《いや、あの夜、刻まれていく時計の針に追われて必死に遠ざかる彼の背後で闇をとどろかして上った爆発の閃光、あれこそがまがいなく、彼とファリダが作り上げた二人が到りつくすことの出来た、極に違いなかった。
あの瞬間、黒い水の中で一人狂気のように声を上げて叫び彼女の名を呼ぶ彼をあおり上げ渦にまいて過ぎた爆発の余波に身をまかせながら、彼が水の中で一人感じたものは、ファリダであり、彼自身であり、その瞬間獲ち得ることの出来た二人きりの世界の輝かしさだった。泡立つ水の中で、彼はその時叫んで名を呼びながら彼女を抱きしめていたのだ。
それが二人にとってのすべてだった。二人にとっての極に違いなかった》
主人公は闇も閃光もない東京の、無機質な時空のぬかるみのなかで女を抱きながら、決して到達することのない「極」を求めあがき苦しむ。偽物の恍惚と戦慄の内側にあって、《俺は結局、その中で溺れている土左衛門でしかない》と思う。
『行為と死』は一九六四年、作家三十二歳のときの作品だが、ここには石原文学の核心部が露呈している。人間の精神と肉体の相克によって互いに縁を接しながら合一する、その絶対の瞬間。死を前にして、天啓のような時のきわみを身心が感受する一刹那。『太陽の季節』では、月夜のヨットと海の神秘的な海月の明滅のなかで主人公の竜哉と英子がこの至福の愛の一瞬を体感するが、それは日常の時間の波にさらわれればたちまちに消え失せてしまう。至上の「時の時」としての、その「極」は、しかし自分の力を超えたものからしか決してやって来ない。『行為と死』では、アラブ人の「国家」であり「民族の運命」が、一人の女への愛の回路から主人公へと手渡される。そこで異邦人として彼ははじめて武器を取る。
《「僕に、武器はないのか。僕自身を守るための」
ファリダは静かに微笑し返し、首を振って見せた。
「あなたが自分でとらない限り、私が、あなたにどうしてそれを渡せて。お願いよ、あなたは帰るべきだわ。私にはあなたを守る余裕はきっとありはしないわ」》
架空の物語を作家はここで設定する。だから東京へと帰ってきた主人公は死地における「極」の幻影以外の他には何も持ってはいない。放心と下降の感覚だけが彼を捕える。《生きながら俺は死んでいるのだ》という自分の言葉が自身に突き刺さる。だが、おそろしいことには、物語は書き手である作家自身を追いかける。
昭和四十一年十一月、作家は「週刊読売」の特派員として南ベトナムに赴き、前線部隊へ取材カメラマンと潜入、夜間にベトコンを迎撃する修羅場を体験することになったのだ。これは短編『待伏せ』という作品に昇華する。密林から来る敵の兇暴な原始的な武器、基地の歩兵の訓練所で見たナイフ、棍棒、弓矢、後ろから襲いかかり音もなく相手を殺す小さな二個の木片と一本のピアノ線で出来た兇器。その恐怖を感じつつ闇のなかにひたすら蹲り待ち伏せする。
《沈黙も静寂とは違っていた。音がしないというのではなく、音の代りに、石のように重い沈黙が我々を塞いでいた。沈黙が闇であり、闇こそが沈黙だった。
それは俺が今まで来たことも覗いたこともない、誰に聞かされることもなかった、全く未知の世界に感じられた》
『行為と死』の主人公は戦争のために武器を取るが、『待伏せ』の「俺」は、米軍が武器を支給してくれようとした時、それを拒む。《彼らの申し出は筋が通っていた筈だ。しかし、この土地で行われていることに関して、俺は第三者でしかない。渦中にいない人間の筈だ》。しかし実際に闇の下に閉じ込められながら、それが決定的に間違っていたことを痛感する。
《敵か味方か、どちらかが殺す側か、殺される側。(略)俺は正しくこの渦中にいながら、この手に武器がない。このことの中で、俺に一体何が出来る。ただ、待つことのほかに》
《〝全体、なんのためにこんなところへ出かけて来たのだ〟
埒もなく、くり返しそればかりを考えた。俺は多分、生れて初めて、本心、自分に愛想をつかしていた》
ベトコンと米軍のどちらにも属さない中立的な日本人としての「俺」は、この殺すか殺されるかの場所で非存在と化す。敵でも味方でもない、武器を持たず何もできずにいることの恐怖。闇中から伝わって来る足音、「射て!」の声で闇が裂け銃声が炸裂し、ほぼ一瞬で敵は全滅する。年寄もまじるベトコン兵の屍体が並べられ、負傷した若い助かる見込みのない捕虜がその横で頭を射ち貫かれる。その光景を「俺」はただ茫然と眺めながら、《〝これでよかったんだ。俺がこうやってここに立っているためには、こいつらがこうならなければならなかったんだ。それだけは間違いない道理だ〟》と思う。
『待伏せ』は昭和四十二年の『季刊藝術』春号に発表される。黄昏から闇の濃さを重く増していく戦場は、鋼のような簡潔な文体で描かれ、死の沈黙のなかに投ぜられた主人公の全感覚がそこに鮮明に浮かびあがる。会話は短く、足元に横たわる屍体の前から歩き出した「俺」に米兵の曹長が「どうだね」と尋ね、《俺は考えた挙句、「一度で沢山だ」と言った》が最後の一行である。いっさいの文学的な修辞は剝ぎ落され、小説の言葉は作者自身の肉体感覚とぴったりと重なり合い、物語のあらゆる擬装は無効となる。作中人物は作者その人と一致し、戦後という擬制の平和のなかにある個我は、無数の銃弾に貫かれてここで粉砕される。鮮烈な奇蹟のようなこの掌編を書きあげたことで、作家・石原慎太郎は一度死んだといってもよい。翌年(昭和四十三年)に政治家への転身を決めたことはおそらく偶然ではない。それは直接のベトナム体験ではなく、死と向き合う「極」をむしろ小説家の言葉として体現し得たからであろう。
《僕は政治を、僕自身の表現の一つの方法として選んだわけでね。じゃ何を表現するのか。自分の存在論を表現する》(「人間・表現・政治」)
江藤淳との対談のこの表明は、すでに述べたように石原氏において現実「政治」的には達成できなかったと思う。平成二(一九九〇)年に刊行される石原文学の頂点といってもよい『わが人生の時の時』は、作家としての石原慎太郎が、もう一度帰還した日常の時のなかに、俗世における溺死のなかにあって摑み取った「極」の実相を描いたものとして、この国の近代文学史に残るだろう。この年、作家は五十八歳であった。
石原慎太郎(いしはら・しんたろう)
1932年兵庫県神戸市生まれ。一橋大学卒業。’55年、大学在学中に執筆した「太陽の季節」により第1回文學界新人賞を受賞しデビュー。翌年同作で芥川賞受賞。『亀裂』『完全な遊戯』『死の博物誌 小さき闘い』『青春とはなんだ』『刃鋼(はがね)』『日本零年』『化石の森』『光より速きわれら』『生還』『わが人生の時の時』『弟』『天才』『火の島』『私の海の地図』『凶獣』『あるヤクザの生涯 安藤昇伝』『宿命(リベンジ)』など著書多数。作家活動の一方、’68年に参議院議員に当選し政界へ。後に衆議院に移り環境庁長官、運輸大臣などを歴任。’95年に議員を辞職し、’99年から2012年まで東京都知事在任。’14年に政界引退。‛15年、旭日大綬章受章。2022年2月逝去。
文芸評論家。1957年生まれ。
湘南を舞台に巨大企業グループを擁する一族の栄枯の美を描いた石原文学の真骨頂。急逝した三代目の残された夫人は複雑な関係の中で。
湘南の地に広大な邸宅を構え、巨大企業グループを擁する北原家。手掛ける事業は鉄道から機械、観光開発にまで及ぶ。その三代目社長・勝彦が急逝し、残された妻の紀子は亡夫の異母兄弟・志郎と結ばれることでその血脈を繋いでいた。だが、縁戚で音楽評論家の野口による音楽事業の提案や、その甥・明からのレジャーの誘いなどによって、複雑に入り組んだ一族同士の関係に微妙な変化が起こりつつあった。その美貌で男たちの心を捉え、また並外れたピアノの才にも恵まれた紀子。彼女の人生にこれから待ち受けているものとは……。