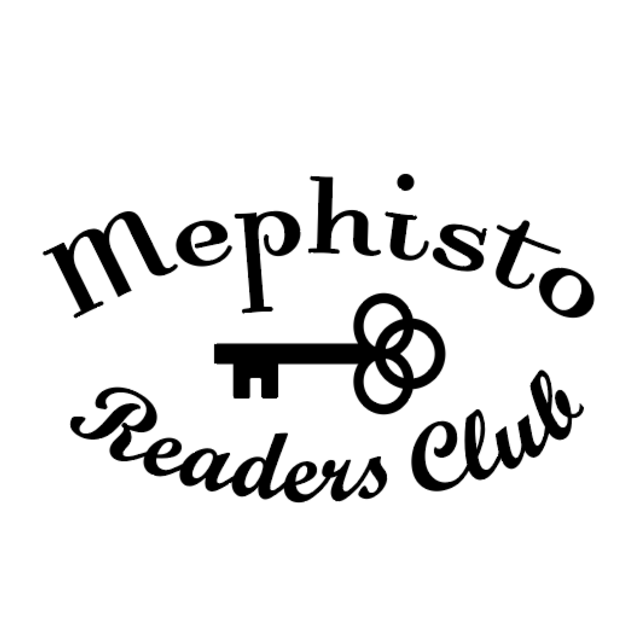刊行記念特別ショートストーリー「夜間降下」
文字数 4,539文字
クリスマス時期の梅田で好きな場所は、阪急百貨店。正確には店内じゃなくてショーウィンドウのディスプレイ。もっと正確には、二十六日になるとクリスマスからお正月仕様にがらっと変わる、あの恐ろしいほどの潔さ。前日までの舶来感を残らず脱ぎ捨て和風にモードチェンジする。二十五日を過ぎればお祭りはおしまい、さあ全部片づけて幕を下ろして。夢から覚めたような切り替え。粋だなあと思う。ここもひとつの舞台だった。
その、クリスマス直前の日曜日、わたしは実家に顔を出した帰り、久しぶりに梅田を歩いて消耗した。といっても「安全ピン」の記事が載っている若手芸人特集の雑誌を探して阪急三番街とグランフロントの紀伊國屋書店を回っただけなのに、人混みのせいだと思う。二店目で無事ゲットした雑誌には亨と弓彦くんが大きく取り上げられていて嬉しかったけれど、グランフロント二階のキルフェボンの行列を見ると、一時間待ちをものともしない人たちのバイタリティにあてられてさらにぐったり度が増した。こんな日はカフェに入るのもひと苦労に違いないからさっさと帰るに限る。ワム!もマライア・キャリーも山下達郎も、繁華街を歩いているだけでメドレーで聴くことができた。わたしが山下達郎の「クリスマス・イブ」を聴くたびに思うのは、どうして来ないと思いながら、告白しようと待ち続けているのかということだった。今なら言えるのに、とこっちが思うタイミングで待ち人は来ず、もし来たら今度はやっぱり言えないような気がする。でも、「安全ピン」は竹内まりやの歌を出囃子にお借りしているので、わたしの中では芋づる式に山下達郎への好感度も高い。この歌が道行く人を楽しませ、山下達郎にお金が入る、そしてまたいい歌を作る、すてきなWin-Winだと思う。この世のすべてのエンタメがそんな感じで循環してくれますように。わたしの元にサンタが来てくれるのならそれをリクエストしたいけれど、あのおじいさんの手には余るかもしれない。
御堂筋線に乗り込むと、平日のラッシュ時の、憂うつを缶詰にしてみました状態とは違う、フルーツポンチみたいな色とりどりの活気にあふれていた。
「敗者復活戦てもう終わった?」
ふと、車両のどこかからそんな声が聞こえた。若い男の子だと思う。
「知らん。まだやってんちゃうん」
「投票せな」
きょうは、大きな漫才コンテストの決勝戦だった。ゴールデンタイムに三時間以上かけて生放送される大会はいつの間にかこの時期の恒例番組として定着し、特に大阪では当たり前みたいに二十%以上の視聴率を取っている。全力でバカをやる人たちを真剣に審査し、点数をつけるという何だかシュールな催しがこんなに人気なのは、漫才そのものより、今夜誰かの人生が劇的に変わる、その瞬間を見届けたいからじゃないかと思う。五千組をゆうに超える参加者の中から、決勝に残れるのは十組。さらにその中のたった一組がチャンピオンになる。今夜は、誰の「始まりの日」になるんだろう。
なんばの駅を抜けたところで栄作にいさんを見かけた。この鈍いわたしが、一度会っただけの人に雑踏で気づくというのは奇跡的なことだから迷わず「こんにちは」と声をかけた。なんばウォークに向かって歩いていたにいさんは、振り返って困惑した表情を浮かべる。
「あの、覚えてらっしゃいますか、以前心斎橋でお会いした……」
「ああ、亨の」
「その節はごちそうになりまして、ありがとうございました」
深々と頭を下げると、にいさんは居心地悪そうに「いやいや」と頭を下げ返す。
「ずっとお礼したいと思ってたんです、どこかでお茶かお食事でもいかがですか」
「いやもう、そんなんしてもらうようなことちゃうから。亨にも申し訳ないわ」
あんまりぐいぐい押しても迷惑かもしれないので、「じゃあ、ソフトクリーム食べませんか」と方向性を変えた。
「ソフトクリーム?」
「近くにお店があるんです。そんな高いものじゃないですし」
ソフトクリームは老若男女に人気なので、にいさんも「ほな、お言葉に甘えて……」と遠慮がちに乗ってくれた。なんばCITYの一階にある生クリーム専門店にも女の子たちが列を作っていたけれど、イートインのお店じゃないからそんなに時間はかからない。もこもこした見た目の、雲を固めたようなかわいいソフトクリームをふたつ買い、通路の端っこで立って食べた。
「五百円もすんねやな、百円くらいかと思とったわ」
申し訳なさそうなにいさんが、口をつけるなり「うまぁ……」と真顔になったので笑ってしまう。
「久しぶりに食べるとおいしいですよね」
「やっぱ五百円のはちゃうわ」
しばらくそのまま無言で食べるのに集中し、下のコーンにたどり着くと、栄作にいさんが「きょう決勝やな」とぼそっとつぶやいた。
「はい」
「亨はどこまで行ったんやったかな」
「三回戦で落ちました」
「そうか、三回戦難しいからな。二回戦通るだけでえらいで」
三回戦からは、すでにテレビで活躍しているような「世間に認められた」人たちでもばっさり落とされる。それは裏を返せば、今現在テレビに出られないような人たちにもチャンスがあるということ。認められた人たちも、認められていない人たちも、針の穴からこぼれてくるようなかすかな光を目指して、もがく。
「決勝は、テレビでご覧になるんですか?」
わたしの問いに、栄作にいさんはゆっくり首を横に振る。
「いや、よう見んのよ。まぶしすぎて胸焼けするいうかね……悔しさとかは、もうないんやけども」
クリスマス用の装飾に彩られたなんばCITYはどこからもどこまでもぴかぴかと華やかだった。天井から吊り下げられたベル、お店の前のツリーやオーナメント。すべてが煌々としているからわからないだけで、もし自分が闇の中にいたら目をそむけるかもしれない。
「でっかいクリスマスケーキみたいなもんで。クリームたっぷりで、上にサンタとか家とかぎっしり乗っかっとって。うまそやなあ、て一瞬思っても、実際それをおいしく食べられる気がせえへん。ひと口でお腹いっぱいやのよ。ソフトクリームのほうがええわ」
栄作にいさんのイントネーションや喋り方は亨にちょっと似ている。亨がこの人と過ごした時間の長さ、大事さを思った。そのままお店の前で別れる時、わたしは今年初めて「よいお年を」と口にした。
亨もマコちゃんも仕事だったので、夜は郁子さんとふたりでこたつに入ってテレビを見た。晩ごはんは特売品の鮭を使ったみそ味の石狩鍋。
「郁子さん、ワンタン入れてもいいですか?」
「ええよ。雨ちゃんワンタン好っきゃな」
「はるさめに飽きてからはこれなんです」
つるっとした口当たりや喉越しが気持ちよく、お腹にも溜まる。冷やしてもいけるし、具も包めるし、汁物に入れてよし、ゆがいてポン酢をかけるだけでもよし。非の打ちどころがない。
「餃子の皮でもええん?」
「粉の種類が違うみたいです」
「ふうん。そういうたら、ワンタンって漢字で『雲を呑む』って書くやん。ちょっと雨ちゃんぽいな」
「そうですか?」
「うん。何か、ようわからん栄養で生きてそうなとこ」
春雨女子に続いて雲呑女子、どっちにしても流行らないのは確か。
「あ、始まりましたよ」
「言うて前置き長いからな」
漫才は一本四分という決まりだから、いろんな要素を膨らませないと長時間の番組は成立しない。ケーキのクリームやデコレーションと同じ。この舞台に立つことを許されたひと握りの芸人にとっては長いのか短いのか。
始まる。マイクの前だけが誰にも邪魔されない、約束された自分たちだけの時間。ツイッターのトレンドは目まぐるしく入れ替わり、わたしが「キングオブ知らんがな」に認定している「こいつらで笑ったことない」というお約束のつぶやきも湧いた。
他人の人生に乗っかって、という弓彦くんの言葉を思い出す。この盛大なコンテンツが、勝手なドラマに仕立て上げられるのはもうどうしようもない。観客は夢や希望や恨みつらみやリベンジを、さらに盛りつけていく。だからこそ、この四分だけは、そんなもの全部吹っ飛ぶくらい、ただ笑わせて。一方的な共感を、なすりつけられる涙を、言葉ひとつで振り払ってねじ伏せて踏みつけて、飛んでみせて。
パチンコ台を思わせる極彩色のセット、そこに至るまでの廊下、せりあがりのほんの数秒、出囃子と拍手と歓声。一本きりのろうそくみたいなセンターマイク。
そこで燃える炎を見たくて見たくてここまで来た、漫才師という、おかしな人たち。
深夜、がらっと引き戸が開く音がした。亨のような気がして、パジャマの上にぶ厚いカーディガンを羽織って下に降りると、台所に立つ後ろ姿が見えた。
「おかえりなさい」
「おう」
やかんに水を入れ、火にかけるところだった。点火すると、流しの下から日清カップヌードルを取り出す。
「決勝、見てた?」
「劇場で。通しでは見てへんけど」
換気扇の紐を引いて、煙草にも火をつけた。
「優勝するって、どんな気持ちかな」
「三回戦落ちに訊くんか」
「うん」
亨は、見えない火を吹き消すようにふっと強く煙を吐いた。どこを見ているのかわからない目に、手が届かない光を追う痛みがよぎってはいないかと、わたしは慎重に見つめる。それが伝わってしまうのか、亨は黙ってまぶたを閉じた。
「……鉛筆削りに突っ込んでいく鉛筆の気持ち」
「どういうこと?」
「ドゥルルルッて削られてくねん。もう、次の朝からテレビでばんばん取り上げられて、スケジュールがちがちに組まれて、『優勝ネタを披露していただきます!』ってハンバーガーより気安くオーダーされんねん。生い立ちも結成秘話も感動のエピソードも何もかもこすり倒されて消費されて、年が明ける頃には『見飽きた』って言われる。かつお節みたいな削りカスがぱんぱんに溜まって、それがいつ終わって、終わった時鉛筆が何センチ残ってんのか、誰にもわからん」
身を削っても、鉛筆削りのねじれた刃の奥にあるものを知りたいと願う芸人が、きっとまたあの板の上を目指す。
お湯が沸くと、亨は容器の内側の線ぴったりまで注ぎ、冷蔵庫の扉にくっつけられたマグネット式のキッチンタイマーを三分ジャストに合わせた。わたしは残りのお湯を鍋に空け、水を足してもう一度火にかける。
「何や」
「ワンタン、トッピングしてあげる」
「いや別にいらんし」
「騙されたと思って食べてみて、特に変わらないから」
「足す意味」
鍋からはすぐにもわもわ湯気が立ち、亨の吐き出す煙とともに換気扇の回転に吸い込まれて呆気なく消える。
見たいよ、とわたしは言った。
「『安全ピン』が残らず削りカスになるところだって。何にもなくなっても、わたしが覚えてるから」
「こわ」
亨の顔は、驚いたようでも、笑っているようでも、びびっているようでもあった。わたしが初めて見たその表情は、雲を呑んだようだったかもしれない。
〈了〉
その、クリスマス直前の日曜日、わたしは実家に顔を出した帰り、久しぶりに梅田を歩いて消耗した。といっても「安全ピン」の記事が載っている若手芸人特集の雑誌を探して阪急三番街とグランフロントの紀伊國屋書店を回っただけなのに、人混みのせいだと思う。二店目で無事ゲットした雑誌には亨と弓彦くんが大きく取り上げられていて嬉しかったけれど、グランフロント二階のキルフェボンの行列を見ると、一時間待ちをものともしない人たちのバイタリティにあてられてさらにぐったり度が増した。こんな日はカフェに入るのもひと苦労に違いないからさっさと帰るに限る。ワム!もマライア・キャリーも山下達郎も、繁華街を歩いているだけでメドレーで聴くことができた。わたしが山下達郎の「クリスマス・イブ」を聴くたびに思うのは、どうして来ないと思いながら、告白しようと待ち続けているのかということだった。今なら言えるのに、とこっちが思うタイミングで待ち人は来ず、もし来たら今度はやっぱり言えないような気がする。でも、「安全ピン」は竹内まりやの歌を出囃子にお借りしているので、わたしの中では芋づる式に山下達郎への好感度も高い。この歌が道行く人を楽しませ、山下達郎にお金が入る、そしてまたいい歌を作る、すてきなWin-Winだと思う。この世のすべてのエンタメがそんな感じで循環してくれますように。わたしの元にサンタが来てくれるのならそれをリクエストしたいけれど、あのおじいさんの手には余るかもしれない。
御堂筋線に乗り込むと、平日のラッシュ時の、憂うつを缶詰にしてみました状態とは違う、フルーツポンチみたいな色とりどりの活気にあふれていた。
「敗者復活戦てもう終わった?」
ふと、車両のどこかからそんな声が聞こえた。若い男の子だと思う。
「知らん。まだやってんちゃうん」
「投票せな」
きょうは、大きな漫才コンテストの決勝戦だった。ゴールデンタイムに三時間以上かけて生放送される大会はいつの間にかこの時期の恒例番組として定着し、特に大阪では当たり前みたいに二十%以上の視聴率を取っている。全力でバカをやる人たちを真剣に審査し、点数をつけるという何だかシュールな催しがこんなに人気なのは、漫才そのものより、今夜誰かの人生が劇的に変わる、その瞬間を見届けたいからじゃないかと思う。五千組をゆうに超える参加者の中から、決勝に残れるのは十組。さらにその中のたった一組がチャンピオンになる。今夜は、誰の「始まりの日」になるんだろう。
なんばの駅を抜けたところで栄作にいさんを見かけた。この鈍いわたしが、一度会っただけの人に雑踏で気づくというのは奇跡的なことだから迷わず「こんにちは」と声をかけた。なんばウォークに向かって歩いていたにいさんは、振り返って困惑した表情を浮かべる。
「あの、覚えてらっしゃいますか、以前心斎橋でお会いした……」
「ああ、亨の」
「その節はごちそうになりまして、ありがとうございました」
深々と頭を下げると、にいさんは居心地悪そうに「いやいや」と頭を下げ返す。
「ずっとお礼したいと思ってたんです、どこかでお茶かお食事でもいかがですか」
「いやもう、そんなんしてもらうようなことちゃうから。亨にも申し訳ないわ」
あんまりぐいぐい押しても迷惑かもしれないので、「じゃあ、ソフトクリーム食べませんか」と方向性を変えた。
「ソフトクリーム?」
「近くにお店があるんです。そんな高いものじゃないですし」
ソフトクリームは老若男女に人気なので、にいさんも「ほな、お言葉に甘えて……」と遠慮がちに乗ってくれた。なんばCITYの一階にある生クリーム専門店にも女の子たちが列を作っていたけれど、イートインのお店じゃないからそんなに時間はかからない。もこもこした見た目の、雲を固めたようなかわいいソフトクリームをふたつ買い、通路の端っこで立って食べた。
「五百円もすんねやな、百円くらいかと思とったわ」
申し訳なさそうなにいさんが、口をつけるなり「うまぁ……」と真顔になったので笑ってしまう。
「久しぶりに食べるとおいしいですよね」
「やっぱ五百円のはちゃうわ」
しばらくそのまま無言で食べるのに集中し、下のコーンにたどり着くと、栄作にいさんが「きょう決勝やな」とぼそっとつぶやいた。
「はい」
「亨はどこまで行ったんやったかな」
「三回戦で落ちました」
「そうか、三回戦難しいからな。二回戦通るだけでえらいで」
三回戦からは、すでにテレビで活躍しているような「世間に認められた」人たちでもばっさり落とされる。それは裏を返せば、今現在テレビに出られないような人たちにもチャンスがあるということ。認められた人たちも、認められていない人たちも、針の穴からこぼれてくるようなかすかな光を目指して、もがく。
「決勝は、テレビでご覧になるんですか?」
わたしの問いに、栄作にいさんはゆっくり首を横に振る。
「いや、よう見んのよ。まぶしすぎて胸焼けするいうかね……悔しさとかは、もうないんやけども」
クリスマス用の装飾に彩られたなんばCITYはどこからもどこまでもぴかぴかと華やかだった。天井から吊り下げられたベル、お店の前のツリーやオーナメント。すべてが煌々としているからわからないだけで、もし自分が闇の中にいたら目をそむけるかもしれない。
「でっかいクリスマスケーキみたいなもんで。クリームたっぷりで、上にサンタとか家とかぎっしり乗っかっとって。うまそやなあ、て一瞬思っても、実際それをおいしく食べられる気がせえへん。ひと口でお腹いっぱいやのよ。ソフトクリームのほうがええわ」
栄作にいさんのイントネーションや喋り方は亨にちょっと似ている。亨がこの人と過ごした時間の長さ、大事さを思った。そのままお店の前で別れる時、わたしは今年初めて「よいお年を」と口にした。
亨もマコちゃんも仕事だったので、夜は郁子さんとふたりでこたつに入ってテレビを見た。晩ごはんは特売品の鮭を使ったみそ味の石狩鍋。
「郁子さん、ワンタン入れてもいいですか?」
「ええよ。雨ちゃんワンタン好っきゃな」
「はるさめに飽きてからはこれなんです」
つるっとした口当たりや喉越しが気持ちよく、お腹にも溜まる。冷やしてもいけるし、具も包めるし、汁物に入れてよし、ゆがいてポン酢をかけるだけでもよし。非の打ちどころがない。
「餃子の皮でもええん?」
「粉の種類が違うみたいです」
「ふうん。そういうたら、ワンタンって漢字で『雲を呑む』って書くやん。ちょっと雨ちゃんぽいな」
「そうですか?」
「うん。何か、ようわからん栄養で生きてそうなとこ」
春雨女子に続いて雲呑女子、どっちにしても流行らないのは確か。
「あ、始まりましたよ」
「言うて前置き長いからな」
漫才は一本四分という決まりだから、いろんな要素を膨らませないと長時間の番組は成立しない。ケーキのクリームやデコレーションと同じ。この舞台に立つことを許されたひと握りの芸人にとっては長いのか短いのか。
始まる。マイクの前だけが誰にも邪魔されない、約束された自分たちだけの時間。ツイッターのトレンドは目まぐるしく入れ替わり、わたしが「キングオブ知らんがな」に認定している「こいつらで笑ったことない」というお約束のつぶやきも湧いた。
他人の人生に乗っかって、という弓彦くんの言葉を思い出す。この盛大なコンテンツが、勝手なドラマに仕立て上げられるのはもうどうしようもない。観客は夢や希望や恨みつらみやリベンジを、さらに盛りつけていく。だからこそ、この四分だけは、そんなもの全部吹っ飛ぶくらい、ただ笑わせて。一方的な共感を、なすりつけられる涙を、言葉ひとつで振り払ってねじ伏せて踏みつけて、飛んでみせて。
パチンコ台を思わせる極彩色のセット、そこに至るまでの廊下、せりあがりのほんの数秒、出囃子と拍手と歓声。一本きりのろうそくみたいなセンターマイク。
そこで燃える炎を見たくて見たくてここまで来た、漫才師という、おかしな人たち。
深夜、がらっと引き戸が開く音がした。亨のような気がして、パジャマの上にぶ厚いカーディガンを羽織って下に降りると、台所に立つ後ろ姿が見えた。
「おかえりなさい」
「おう」
やかんに水を入れ、火にかけるところだった。点火すると、流しの下から日清カップヌードルを取り出す。
「決勝、見てた?」
「劇場で。通しでは見てへんけど」
換気扇の紐を引いて、煙草にも火をつけた。
「優勝するって、どんな気持ちかな」
「三回戦落ちに訊くんか」
「うん」
亨は、見えない火を吹き消すようにふっと強く煙を吐いた。どこを見ているのかわからない目に、手が届かない光を追う痛みがよぎってはいないかと、わたしは慎重に見つめる。それが伝わってしまうのか、亨は黙ってまぶたを閉じた。
「……鉛筆削りに突っ込んでいく鉛筆の気持ち」
「どういうこと?」
「ドゥルルルッて削られてくねん。もう、次の朝からテレビでばんばん取り上げられて、スケジュールがちがちに組まれて、『優勝ネタを披露していただきます!』ってハンバーガーより気安くオーダーされんねん。生い立ちも結成秘話も感動のエピソードも何もかもこすり倒されて消費されて、年が明ける頃には『見飽きた』って言われる。かつお節みたいな削りカスがぱんぱんに溜まって、それがいつ終わって、終わった時鉛筆が何センチ残ってんのか、誰にもわからん」
身を削っても、鉛筆削りのねじれた刃の奥にあるものを知りたいと願う芸人が、きっとまたあの板の上を目指す。
お湯が沸くと、亨は容器の内側の線ぴったりまで注ぎ、冷蔵庫の扉にくっつけられたマグネット式のキッチンタイマーを三分ジャストに合わせた。わたしは残りのお湯を鍋に空け、水を足してもう一度火にかける。
「何や」
「ワンタン、トッピングしてあげる」
「いや別にいらんし」
「騙されたと思って食べてみて、特に変わらないから」
「足す意味」
鍋からはすぐにもわもわ湯気が立ち、亨の吐き出す煙とともに換気扇の回転に吸い込まれて呆気なく消える。
見たいよ、とわたしは言った。
「『安全ピン』が残らず削りカスになるところだって。何にもなくなっても、わたしが覚えてるから」
「こわ」
亨の顔は、驚いたようでも、笑っているようでも、びびっているようでもあった。わたしが初めて見たその表情は、雲を呑んだようだったかもしれない。
〈了〉