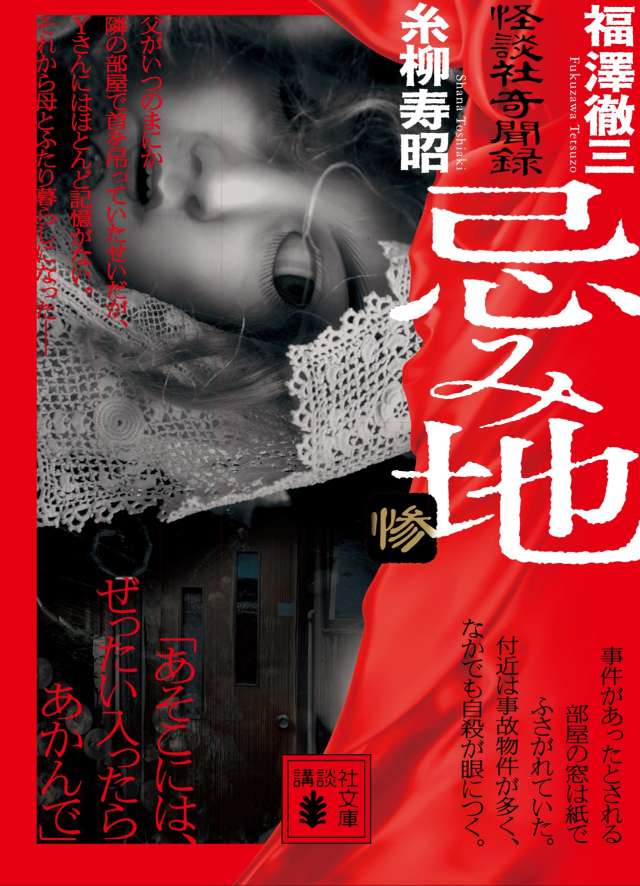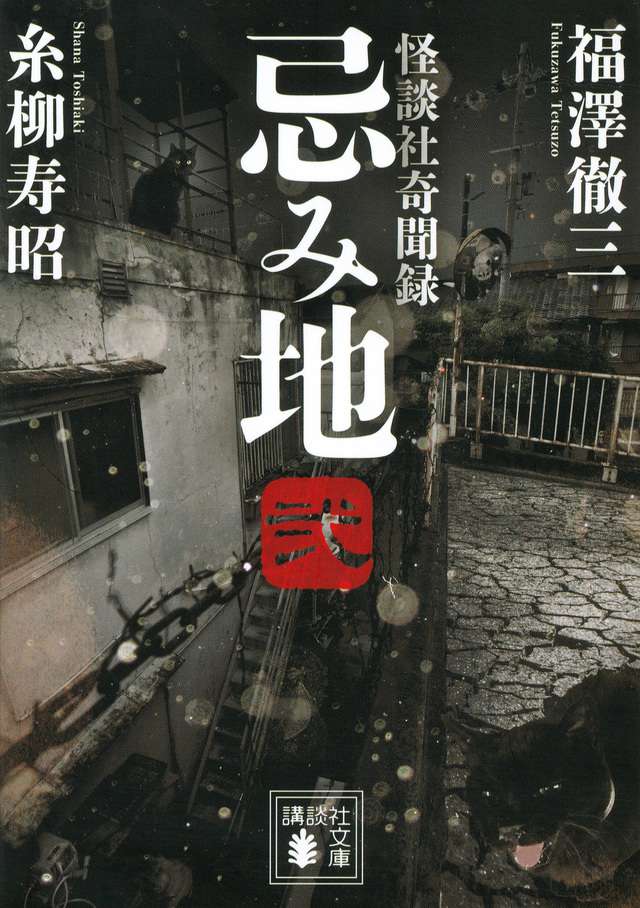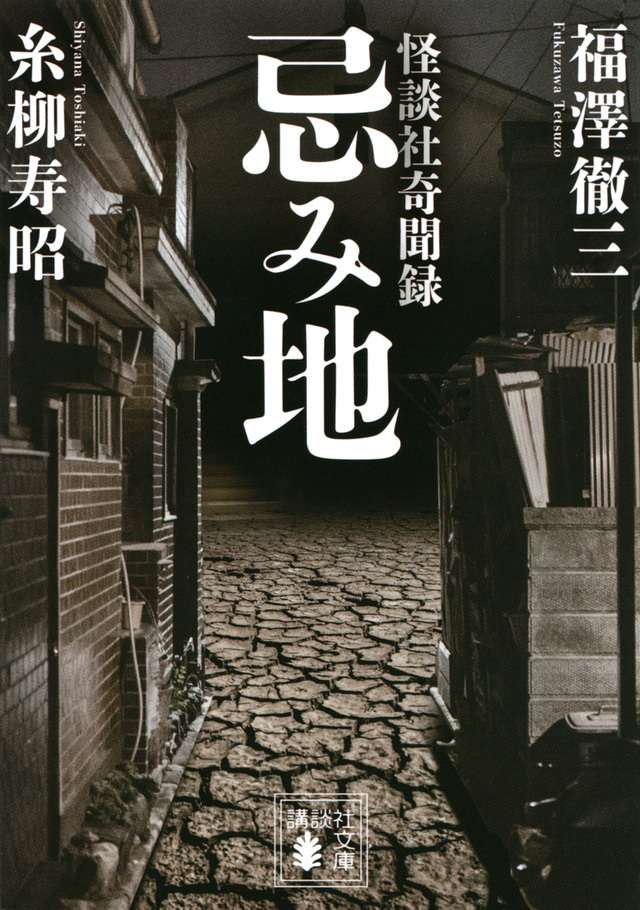➂桟橋の少年/福澤 徹三,糸柳 寿昭
文字数 1,894文字

寝苦しい夜のおともにぴったり!
怪談社の糸柳寿昭と上間月貴が全国各地で怪異を取材、作家の福澤徹三がそれを書き起こす。心霊スポットや事故物件など、さまざまな「場所」にまつわる怪異はときに不可解な連鎖を遂げ、予想外の恐怖と戦慄にたどり着く──。
ページをめくるにつれて読者の日常をも侵食する最恐の怪談「実話」集、3巻目『忌み地 惨 怪談社奇聞録』刊行を記念して3本試し読み! 第3弾(最終回)「桟橋の少年」をお楽しみください!
もっと読みたい!と思った方は、『忌み地 惨 怪談社奇聞録』をぜひ!
糸柳は以前、埼玉県の居酒屋で、二十代なかばの男性からこんな話を聞いた。
数年前の夏、彼は友人たち六人でドライブにいった。その帰りにある公園に寄ると、女性のひとりがベンチを指さして、
「あそこに幽霊がいる」
と騒ぎだした。
彼女は日ごろから霊感があると自称していたが、ベンチには誰もいない。気のせいだろうといったら、彼女はそばにいた男性の腕をつかんで、
「なんで見えないの。ほら、あそこよッ」
と叫んだ。とたんに腕をつかまれた男性は悲鳴をあげて走りだした。てっきり冗談だろうと思ったが、男性は車に乗っても真っ青な顔で震えている。
「あたしが腕をつかんだから、見えたのかも」
霊感があるという女性はそういった。
ほかのみんなもしだいに怖くなり、カラオケボックスで朝まですごしたという。
さして珍しい話ではないがネットで調べたら、ずいぶん前のテレビ番組でその公園の木に顔が浮かんでいると放送されたことがあるらしい。
Oさんのアパートを訪れた翌日、糸柳は件の公園にいき、そこにいたひとびとに取材を試みた。けれどもベンチやその付近で怪異があったという話はない。ただ公園内の池で、すこし前に男性の遺体が発見されたと聞いた。
公園の案内図を見ると、池の名称はボートに乗れるような印象だったが、実際にいってみると船のたぐいはなかった。池のほとりで二十代前半くらいの女性ふたりに声をかけたら、ひとりがこんな話をしてくれた。
彼女の同級生が近くに住んでいて、同級生の姉が犬の散歩でこの公園にくる。夏のある夜、犬を連れて公園を歩いていると、犬が興奮して池のほうへいこうとする。
「どうしたの。そっちじゃないでしょ」
彼女が止めても犬はいうことを聞かない。リードをひっぱられるまま池にむかったら、池にせりだした桟橋に着いた。そこに少年がぼんやり腰かけている。
時刻はもう十時だから不審に思って、
「ぼく、そこでなにしてるの」
少年はぎくりとした様子だったが、わけを訊いたら母親に叱られてられて家を飛びだしたと途切れ途切れに答えた。あぶないからこっちにおいで、といったとき、三十代に見える男女が走ってきた。
ふたりは少年の両親で、心配して捜しにきたという。
「ママはもう怒ってないから。早くこっちにおいで」
母親がそういうと少年はゆっくり腰をあげ、桟橋に置いていた松葉杖を手にとった。そのときになって、少年の片足に白いギプスが巻かれているのに気づいた。
「おまえ、どうやってそこに入ったんだ」
と父親がいった。桟橋の入口に眼をやると、放射状の棘がついた扉でふさがれており、扉には南京錠がかかっている。
「ふつうに入れた」
少年はそういってから扉を見て、あれ? と首をかしげた。扉は開かなかったが、通りかかった中年の男性と四人がかりで、少年を桟橋から運びだしたという。
糸柳はその桟橋にいって入口の扉を見た。
「めっちゃがんばれば乗り越えられそうやけど、松葉杖やからなあ」
少年がどうやって桟橋に入ったのか見当がつかなかった。

福澤徹三(ふくざわ・てつぞう)
小説家。『黒い百物語』『忌談』『怖の日常』など怪談実話から『真夜中の金魚』『死に金』などアウトロー小説、『灰色の犬』『群青の魚』などの警察小説まで幅広く執筆。2008年『すじぼり』で第10回大藪春彦賞を受賞。『東京難民』は映画化、『白日の鴉』はドラマ化、『侠飯』『Iターン』はドラマ化・コミカライズされた。他の著書に『作家ごはん』『羊の国の「イリヤ」』などがある。
糸柳寿昭(しやな・としあき)
実話怪談師。全国各地で蒐集した実話怪談を書籍の刊行やトークイベントで発表する団体「怪談社」を主宰。単著として『怪談聖 あやしかいわ』があり、怪談社の著作に『恐國百物語』『怪談社RECORD 黄之章』『怪談師の証 呪印』など多数。狩野英孝が司会を務めるCS番組「怪談のシーハナ聞かせてよ。」に、本作に登場する怪談社・上間月貴とレギュラー出演中。本書は福澤徹三と共著の『忌み地』『忌み地
弐』続編となる。