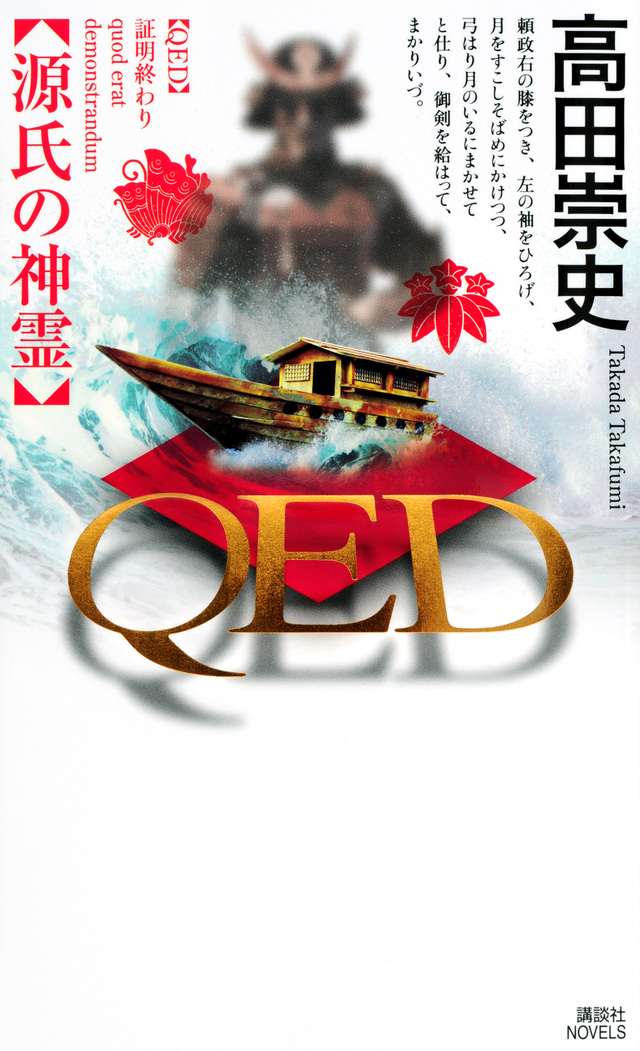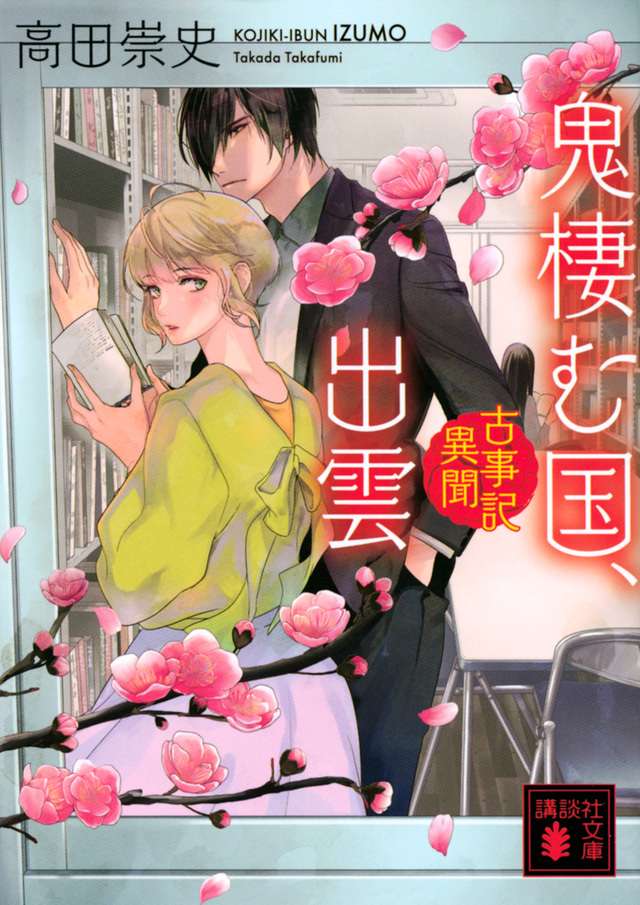④『妖怪』も『鬼』と一緒で、実在していた?
文字数 1,994文字
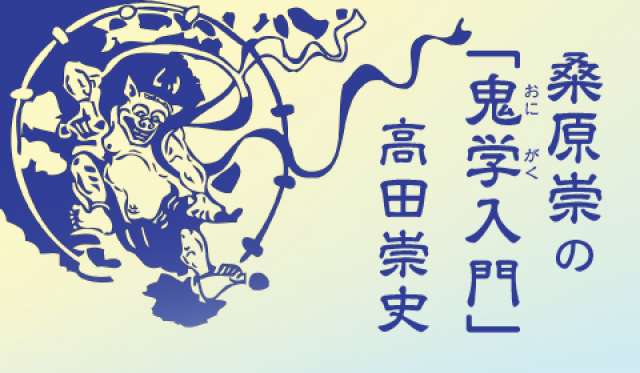
「それはそうだけど……」
まだ納得できなそうな大地に、崇は尋ねた。
「今言った『妖怪』はどうかな」
「妖怪って」大地は眉をひそめる。「鬼より、もっと信じられないよ」
「実在が?」
「小学校1~2年の頃ならともかく、今は無理」
笑いながら顔を上げる大地に崇は言う。
「確かに、一般的には『妖怪』は『人知では解明不能な現象』や『科学では説明のつかない異様な生物体』だというし、轆轤首や文車妖妃や雪女や口裂け女などは、かなり信憑性が薄くなるね。でも、さっき言ったように『妖怪』も『鬼』と一緒で、実在していたモノたちがたくさんいる。たとえば、河童や一つ目小僧だ」
「河童や一つ目小僧が、この世に存在していたって?」
「もちろん、そうだ」崇は大きく頷く。「俺たちと同じようにね。1つ違うのは、彼らの多くは産鉄民だったということなんだ。主にタタラ製鉄によって、当時は金より価値があると言われた鉄を製造していた人々だ。その頃は『鉄を制する者は、世界を制す』とまで言われていたから、彼らは日本史のあらゆる場面に登場してくる」
「……タタラって?」
「鉄を生成するための炉に、アコーディオンのような仕組みの大きな鞴を足で踏んで空気を送り込むんだけれど、その鞴が『タタラ』と呼ばれていた」
「ああ……何かのアニメ映画で観たことがある」
「この方法だと、かなり純度の高い鉄を造ることができたが、しかしこれは、かなりの重労働だった。三日三晩、不眠不休で作業が続けられるという、実にハードな仕事だった。そのために、従事者たちの多くは職業病に罹ってしまった。たとえば、炉の火を絶えず片目で見続けていなくてはならなかった村下という技師は大抵、目をやられてしまう。また、何時間かおきに交代とはいえ、鞴を踏み続けていた番子という労働者たちは、誰もが足を悪くした」
「当然だ……」
納得する大地に、崇は言う。
「そんなことから、彼らの象徴として『片目』『片足』『山に棲む』妖怪たちが作られた。今の河童や一つ目小僧の他にも、山童、一目連、イッポンダタラ、山精、などなど『片目』『片足』の妖怪が生まれた。山に関しては、土蜘蛛、ダイダラボッチ――これはそのまま『タタラ法師』になる――などだ。関連する『神』には、天目一箇神という、片目で暴れん坊の神様もいるけれど、やはり圧倒的に『妖怪』が多い」
でも、と大地は尋ねた。
「どうしてタタラの人たちが、そんな『妖怪』と呼ばれるようになったの? 当時は金より重要な物を造っていたんでしょう」
「まず、彼らは村や山の外からやって来た職業集団だった。つまり『異界の者』だったから、それだけでも村人たちから嫌がられた。その上、タタラ製鉄には膨大な量の炭――樹木を必要としたり、製鉄所から流れ出る水で麓の田畑を汚したりもした。だから地元の人々から益々嫌われ、いつも争い事や揉め事が起こっていたんだ」
「異界の……」
しかし、と崇は続ける。
「実は、もっと大きな理由があった」
「それは?」
「朝廷が、彼らの鉄を奪うための名目にしたんだ。あそこで鉄を造っているのは『人』ではなく単なる『妖怪』だ。だから、その鉄を奪っても全く咎められることはないという」
「奪うって!」
「所有者の意志に反して、無理矢理取り上げる」
「違うよ。言葉の意味じゃなく」
「当時の朝廷は」と崇は言う。「欲しい物があれば問答無用で持って行った。所有者が何と言おうともね。『日本書紀』などには、それに反抗した人間が殺されたなどという話が、いくつも載っている。しかし、命を落としたのは人間ではなく『鬼』や『妖怪』たちだから一向に構わない」
「そんな!」
「当時の朝廷の貴族たちはそれを、もっと大掛かりに、しかも当たり前のように行っていたんだ」
「そう……」大地は困ったような顔で溜息をついた。「ぼくは、タタルさんが『実在していた鬼』って言ったから、それはきっと大きな人ということだと思ってた。『鬼のように』大きくて強い人なんだって。でも、そんな意味があったなんて……」
すると崇は、大地の顔を見て微笑んだ。
「きみは、面白い」
「えっ」
「無意識的に物事の本質を衝いている。おそらく、自分では気づいていないだろうけど」
(⑤ 4月28日公開へつづく)