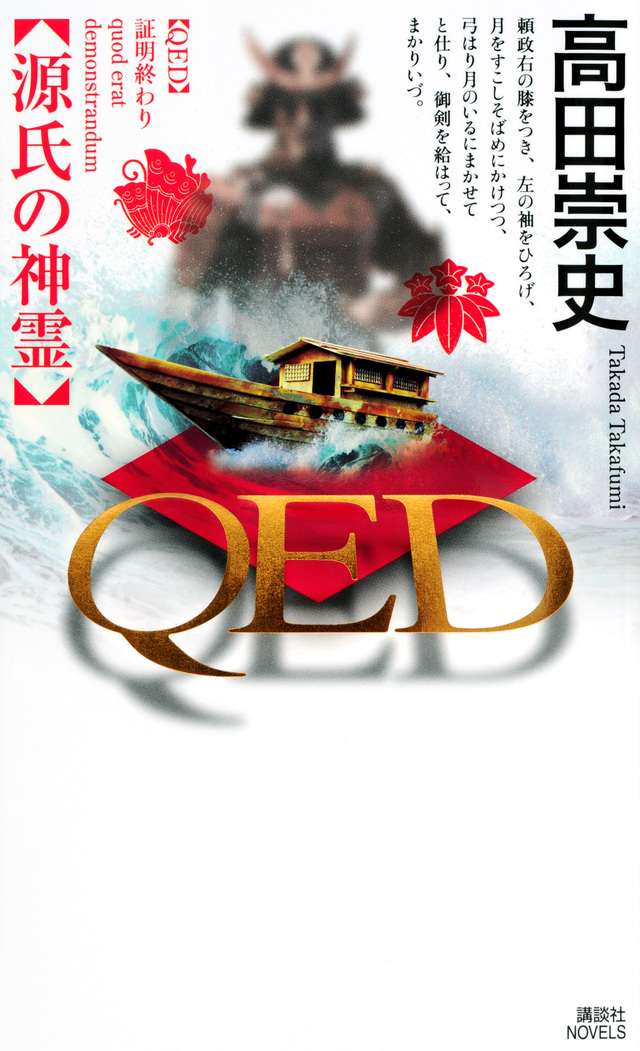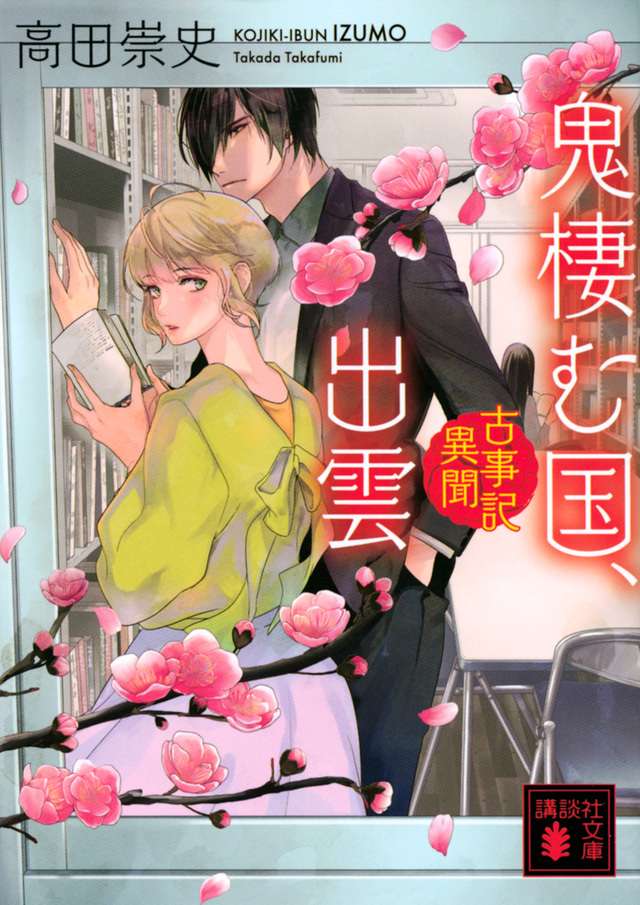②『鬼』と『人』とは、どう違う?
文字数 2,049文字
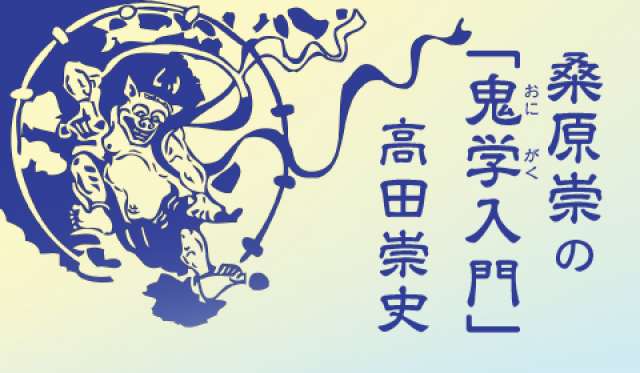
「えっ」大地は顔を上げて崇を見た。「立派な人?」
「そうだよ」崇は頷く。「そんな立派な人に向かって、俺たちは豆を投げつけ、この家から出て行けと追い払う。しかも季節は真冬。身も凍えるような寒空の下、相手はパンツ一丁の裸なのにね」
「え……」
口籠もる大地に、崇は言う。
「鬼が、子供が投げつける豆粒ごときで逃げ出してしまうほど弱々しい生き物なら、いつでも追い払える。それならば、もう少し暖かくなるまで家に置いてあげても良いだろう。それが人情というものじゃないか」
「そんなこと言われても」大地は頰を膨らませる。「そもそも、どうして『鬼』が立派な人なの? 本当にいたわけじゃないのに、どうやって分かるのさ」
「『和名類聚抄【わみょうるいじゅしょう】』という平安時代の漢和辞書などを見ると、鬼は『隠【おん】』、あるいは『隠忍【おんにん】』からきているという。また中国ではこの文字は『人の遺体が風化した物』であり、『死者の霊魂』や『精霊』のように、姿が見えないモノともいう。そして、やはりわが国の『広辞苑』にも『鬼』は『隠』で姿が見えないとか、地上の悪神・邪神。伝説上の山男。死者の霊魂・亡霊。もののけ。想像上の怪物……などと載っている」
「やっぱり空想の中の生き物じゃないか」
「でもね、沢史生さんなど、何人もが指摘しているように『隠忍』や『隠』が訛って『おに』になったという説は、無理がありすぎるし、とても納得しがたい。『日本書紀』や『出雲国風土記』といった、昔の公式文書の中にも、実際に鬼を見たという記述がたくさん残っているしね」
「じゃあ、何だっていうの?」
いや、と崇はコーヒーを1口飲んだ。
「その前に、俺から質問しても良いかな」
「うん」
「『鬼』と『人』とは、どう違う?」
「だから……」大地は、もぞもぞと体を動かした。「実際に生きている『人』と、空想の中の『鬼』」
「もしも『鬼』が、本当に生きていたとしたら?」
「あはは。そんなわけないじゃない」
「仮定の話だよ。もし本当に『鬼』がいたとしたら、『人』と『鬼』はどう違うと思う」
「それは……」大地は笑った。「見た目が全然違う。鬼は角が生えているし、牙だってあるし。あと体型も違う。鬼はすっごく大きくて逞しいけど、人間は人間」
「他には?」
「鬼は、いつも褌一丁で金棒を持ってる」
「見た目以外では、どうだい」
「鬼は、人間の宝物や女の人を盗んだりさらったりして、山の奥に隠れ棲んでる」
「その他は?」
「んー……」
またしても唇を尖らせる大地に、崇は言った。
「実は『鬼』と『人』には、もっと根本的・根源的に大きな違いがあるんだ」
「……それは何?」
「平安時代の貴族たちには、ざっと30種類以上の官位――序列があった。聞いたことがあるだろう、お稲荷さんも持っている正一位から始まって、従八位とその下までね。その中で――例外もあるが基本的に――昇殿を許されるのは『殿上人』と呼ばれた従五位下の貴族たちまでだったんだ。それ以下は『地下』と呼ばれた」
大地は、崇がノートに書いた文字を覗き込んだ。
「じげ?」
「この呼び方には、一般の庶民も含まれている。そして――」崇は大地を見る。「この頃は、殿上人たちだけが『人』と呼ばれていた」
「じゃあ、その『地下』の人たちは?」
「もちろん『人』じゃないから『人でなし』だ」
「人でなしって!」
大地は叫んでしまい、小さな両手であわてて自分の口を押さえた。それを放して、小声で崇に尋ねる。
「どういうこと?」
そのままだよ、と崇はあっさり答えた。
「『人』じゃない人。つまり、河童や天狗や土蜘蛛や……鬼」
「人が鬼?」
「『人』じゃない、その他の人間だ」
「そんな……」
「平安時代の日本の人口は、一説では約500万人といわれてる。その中で、貴族は約1500人。そして『人』と呼ばれた殿上人は、たった50人くらいだったのではないかという。ということは、その頃の『人』の割合はというと、500万分の50だから?」
ええと……、と大地は計算する。
「100万分の10で……0・001パーセント!」
「そうだ。10万人に1人だけが『人』だった」
「残りは……鬼や河童なんか?」
「そういうことだよ」崇は頷いた。「おそらく我々の祖先の殆どが『人』ではなかったから、俺たちは皆、『鬼』や『河童』や『土蜘蛛』の子孫なんだよ」
(➂4月24日公開へつづく)
高田崇史(たかだ・たかふみ)
1958年東京都生まれ。明治薬科大学卒業。
『QED 百人一首の呪』で第9回メフィスト賞を受賞しデビュー。
怨霊史観ともいえる独自の視点で歴史の謎を解き明かす。
「古事記異聞」シリーズも講談社文庫より刊行中。