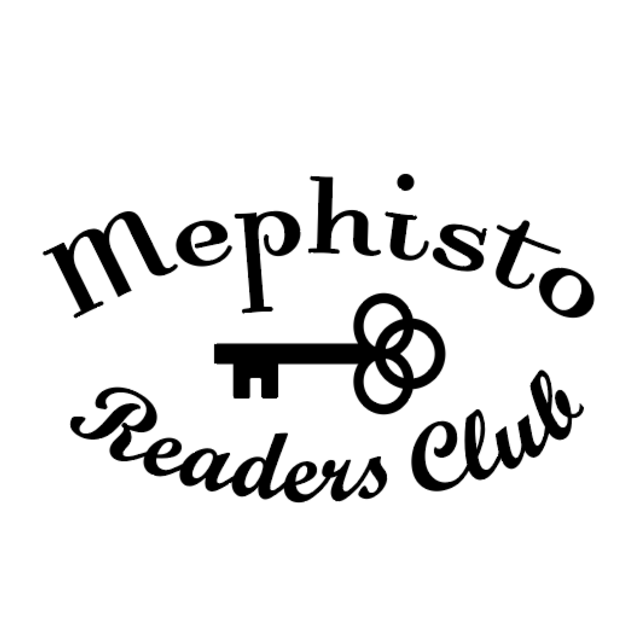サインを描く旅/『線は、僕を描く』5万部突破記念エッセイ
文字数 5,276文字
第1回受賞者の森博嗣さんをはじめ、辻村深月さん、西尾維新さんら素晴らしい才能を輩出してきたメフィスト賞。その第59回受賞作『線は、僕を描く』は、水墨画をテーマに「命」について「生きること」について描いた物語です。
熱い支持を受けるこの物語の作者・砥上裕將(とがみ ひろまさ)さんは、水墨画家。この記事は、小説家になってからのことをはじめて書いたエッセイで、雑誌「本」に掲載されました。
水墨画家の目を通して見る「本」の世界は、どんなものだったでしょう。

日本中どこに行っても、絵を描いている。
正確には、日本中どこの書店に行っても絵を描いている。
慣れない道を歩いて訪問させていただく書店を探し当て、失礼のないように緊張しながらも挨拶をし、お店のバックヤードに通されると、用意していただいた本を確認する。上着を脱いで、ゆっくりと腰を落ち着けて、ぺんてるの筆ペンの蓋を開け、ウェットティッシュを用意し、机の端に置いた後、自分のスマホを文鎮代わりに、開いた本の端に置いて、書店員さんと雑談しながら、始まりの合図もなくサインを描き始める。自分の名前を書き、そして、絵を描き込む。
書店の方々は笑顔で快く迎え入れてくださるのだけれど、僕が絵を描き始めると言葉がすっと止まる。誰かが筆を持つと、なぜだか空気は厳粛なものに変わっていく。僕はそういう強張った雰囲気があまり好きではなくて、手の動きのリズムとはまるで違う言葉のリズムで、地方の名産品やその土地の話を続ける。絵は次々に、筆ペンの先から描出され、それは竹になり、椿になり、ときには春蘭になり、白い牡丹の花になったりする。そして最後に、「独楽」と彫られた落款を名前の下に押し、小さな和紙を挟んで本は静かに閉じられる。一冊のサイン本はそうして完成する。
この数ヵ月、日本中の書店を訪問させていただいて、自著にゆっくりとサインを描く旅をしてきた。
なぜそんなことをしているのか? と、訊ねられると答えが多すぎて、簡単には説明できない。だが、その理由の真ん中にあるのは、僕が抱いている気持ちや思いのためだ。
ありふれた言葉で、サラッと説明してしまえば、それは「感謝」ということになるのだけれど、そういう言葉で簡単に説明したくない気持ちが、絵筆を、もとい、ぺんてる製の筆ペンを握っているときには、胸に迫ってくる。
* * * * * * * * * *
「砥上さん、日本中の書店さんに、感謝の言葉を伝えに行きましょう」
と、担当編集者に提案された時、日本中を旅できたら楽しそうだなあ、温かな応援の言葉をくださった書店の方々にお礼を申し上げて、本の話を一緒に出来たら嬉しいなあと、ものすごくシンプルで漠然とした動機で賛同した。だが、その旅が始まってしばらく経つと、自分が神経を研ぎ澄ましてサインを描き続けている動機や、移動し体力を消耗し続けながら行動している動機が、もっともっと複雑で根深いものなのだと、気が付いた。
不思議なもので、とんでもなくエネルギーが必要で、根底に何が隠れているのか自分でもよく分かっていない行為を、なんでもないことのように、気軽に決断してしまうことがある。自然さというのは、案外そんなものなのかも知れない。
* * * * * * * * * *
『線は、僕を描く』は、こういう自然さと、複雑さと深さを併せ持った手応えから生み出された。僕自身が水墨画の専門的な知識を有していることから、簡単に書き進められるという予感を何処かに感じながらも、一方で、僕自身の青春時代から着想しなければならず「自らについて」何かしらの形で語らざるを得ない、という難しさを持っていた。
第一作目の投稿作を面白半分に書き上げ、三作目の投稿作に挑むまでおよそ一年、僕の投稿作を読んだ編集者にハガキをもらったときから、すごく長い時間が経過したように感じていた。
最初にハガキで連絡をもらったとき小説を書いたことは覚えていたけれど、何という賞に応募したのか、どこの出版社に応募したのかさえ、僕は覚えていなかった。まるっきり覚えていなかったわけではないけれど、思い出せと言われるとしばらく時間がかかるくらいには覚えていなかった。それくらい小説家になるというのは、僕の人生にとっては非現実的なことで、僕は自分が物語を作り誰かに読んでもらえるような文章を書く能力があるなんてことを、全く信じていなかった。
下手の横好きという言葉があるけれど、僕にとって小説を書くというのはまさにそれで、プロデビューを目指して投稿してみませんか、と勧められた時も、目指していたのはプロデビューではなくて、長い小説を書きあげる達成感と文章を書くことそのものの楽しさと、その上、書いたものを読んでもらえるのは嬉しいなと思う充足感みたいなものだった。
文章を書くことが好きなのは分かっていたけれど、小説を書くことが好きかどうかは投稿作を書いている段階では正直よく分からなかった。分からないからとりあえずやってみようということで、興味半分でやり始めて一作二作と重ねたことに、気付くと僕は追い詰められていた。
「言葉で水墨画を表現するというのは、いったいどうすればいいのだろう?」
三作目に挑む時、僕の中には、その方法論も答えもなかった。
* * * * * * * * * *
秋の始まりに書き始め、その年の終わりごろに最初の原稿を書き終えるまで、小説を書くのは本業の絵にも障るし、これで駄目なら文章はきっぱりとやめようというような決意と、可能性の低いことに全力で挑み続けているという強い不安感と、自分自身が水墨画や水墨画を通して十数年間に出会ったたくさんの人や出来事から学び取って来たことを物語という形でもう一度捉え直し、文章という形に移しかえることで創造していくという不思議なほどの面白さの入り混じった複雑な気持ちを抱えていた。
それは、一面では、つらく孤独な日々で、一面では、とても美しいものや楽しいものに触れ続けることのできる得難い時間でもあった。書き終えてから半年ほど経った後、メフィスト賞の受賞が決まり、受賞報告を受けて僕の人生では稀な幸福感に包まれた午後をだいたい三十分くらい過ごし(十五分だっただろうか)、それから『線は、僕を描く』が刊行されるまで、また一年かかった。
その一年の間に、日本全国の書店員の皆様から、発売前見本を読んでの感想をいただき、自分が書いたものが、本当に多くの人達に読まれているのだ、という実感を初めて持った。水墨画に対する世間の反応というのを僕は分かっていたので、物語としての水墨画の話が、たくさんの人に温かく受け入れられていく状態に、ただただ驚き、それから深い感謝の念を抱いた。
完成した本がついに店頭に並び始めると、今度は予想もしなかったほど多くの読者の方々からの声をいただいた。それは、サプライズで差し出された花束に、さらに別の花束が重ねられて、ひょいと手渡されたような感覚で、僕はそのことをうまく理解できなかった。自分でもどう反応していいのか分からない不可思議な感覚がしばらく続き、そのあとようやく、感動がじわじわと胸のうちに溢れていった。
誰にも理解されないだろうことを前提に絵筆を振るい、作品を発表し、長い時間を過ごしてきたので、温かで優しい反応というのを僕はずっと思い描くことができなかった。だが、時間をかけて少しずつ、自分の小説が歓迎されていると理解できたとき、それは驚くほど大きな力になった。
その力は、僕をがらりと変えた。それほど得意とはいえない社会に触れる機会を自ら求め、感謝の言葉を伝えたいという意思に変わった。そうすべきだ、と絵を描く時のようにクリアに思うようになった。僕は全国の書店を訪問する、と気軽に答えたことを、どのタイミングでも一度も後悔していなかった。すごく大変だ、と思ったことは何度もあったけれど。
* * * * * * * * * *
僕が描くサインはとても遅い。
一分もかからず数十秒でサインする人もいると聞いたけれど、僕のサイン本は自分の名前を入れて、絵を入れて、落款まで押しているので、完成するまでに三分から五分かかる。予定よりもながく居座ってサイン本を作らせていただくというのは心苦しくもあるのだけれど、その一冊を開いた時に、何処かで誰かが喜んでくれるかも知れないと思うと、たった一冊でもどうしても手を抜くことができず、絵を入れてしまう。
筆ペンで描いているとはいえ、絵を描く消耗度は実際の筆とほとんど変わらない。むしろ技法の制約は大きく、その上、自宅で画仙紙に描くときとは別で、本という商品に絵を描くので失敗が許されない。名前だけ素早く書いて落款を押してしまえばすごく楽なのだけれど、この本に関しては、それはできない。僕は自分が感じている気持ちをしっかりと伝えたいと思っている。
それが自分にとっての感謝を示す態度で、絵師としての矜持でもあり、同時に物書きとして動き始めた自分の想いでもある。大切なことは、自らの手で作り上げたもので伝えたいという僕のかたくなな意思の表れだ。
線は迷わず、歪まず、まるで濁ってはいない。
言葉は思いの形を伝えるけれども、思いそのものを伝えたりはしない。けれども絵は、思いの形を伝えはしないけれど、思いそのものを伝えることができる。
だからその二つがあれば、なんとか自分の意のあるところが伝わるのではないかと思って、旅を続けている。
* * * * * * * * * * *
本書の主人公、青山霜介も、自分の心や思いがうまく伝えられず、その方法を、水墨画を描くということに委ねた。物に命が宿り、想いが形になるという思想を気付かずに受け入れていくのが、絵師の在り方だと思うのだけれど、青山霜介に劣らず僕もまた、同じ原理で自分の想いを形作っている。
訪問した書店の方々から、本の感想と共に様々なエピソードをうかがう。一目惚れでした、とか、大好きです、といった本に関する率直な感想を聞く度に本当に、どうしようもなく頭を深く垂れてお礼を申し上げたくなる。小さな散らかった部屋で原稿を書き続けていた日々が報われたなと、かつての自分にそっと伝えたくなる。
丁寧に飾り付けられた棚や手書きのポップで想いは、はっきりと伝わってくる。ああ、これは頑張らねば、いい絵を一冊でもここで描かなければ、と僕は自著の置かれた棚の前でいつも思う。
そういう気持ちが筆に乗った時、絵師の筆というのは、軽々と自分の限界や疲労を超えていく。僕は日々描くことが、生業だったから、話すように筆を振るうことができるし、実際、話しながらも筆を振るうことができる(いつも大抵、喋りながら絵筆を走らせるので、サイン本を作っている様子を見た人には驚かれている)。そんなサイン本を、もう何百冊も日本中で作って来た。
どの本もとても和やかで、優しい雰囲気の中で作られたものだ。
* * * * * * * * * * *
書店の方々のお話から感じるのは、一冊の本に対する並々ならぬ情熱と愛情で、小説という文化を支えているのは、この無償の愛なのだと思わずにはいられない。僕は作品を書くときに、自分の作ったものを愛するけれど、書店の方々はその気持ちも抱きとめるように、もっと大きな愛情で作品を包んでくれている。幾つもの愛が重なって最後は読者の心に届いていた。その行程を眺めていられること、その大きな愛に直接会いに行けることが、いまの僕が絵筆を振るい、物書きとして旅をする力になっている。
そして、僕もその愛に溢れた世界を愛し始め、一歩踏み出すごとに、親しみを感じている。季節の変わり目に、新しい季節にごく自然に気付き、それを好ましく思うようなささやかな気持ちだけれど、それは、疑いようもなく本物の感覚だ。
僕はたぶん、本当に幸福な物書きで、この本に関する日本中のたくさんの方々の温かな想いと声の在処を知っている。
誰とどんなふうに仕事をしているのかを、自分の足を使って、心と経験によって学ばせてもらっている。僕は一冊の本が生み出した線の中を歩いている。
(掲載「本」2020年1月号)
―――――――――――――――――――――
とがみ・ひろまさ/1984年、福岡県生まれ。水墨画家・作家。温厚でおだやか。お年寄りの趣味と思われがちな水墨画の魅力を、小説を通して広い世代に伝えたいという志をもって、本作品を書き上げた。ウイスキーにジャズ、そして猫を心から愛する。
『線は、僕を描く』あらすじ/両親を交通事故で失い、喪失感の中にあった大学生の青山霜介は、アルバイト先の展覧会場で水墨画の巨匠・篠田湖山と出会う。なぜか湖山に気に入られ、その場で内弟子にされてしまう霜介。それに反発した湖山の孫・千瑛は、翌年の「湖山賞」をかけて霜介と勝負すると宣言する─。