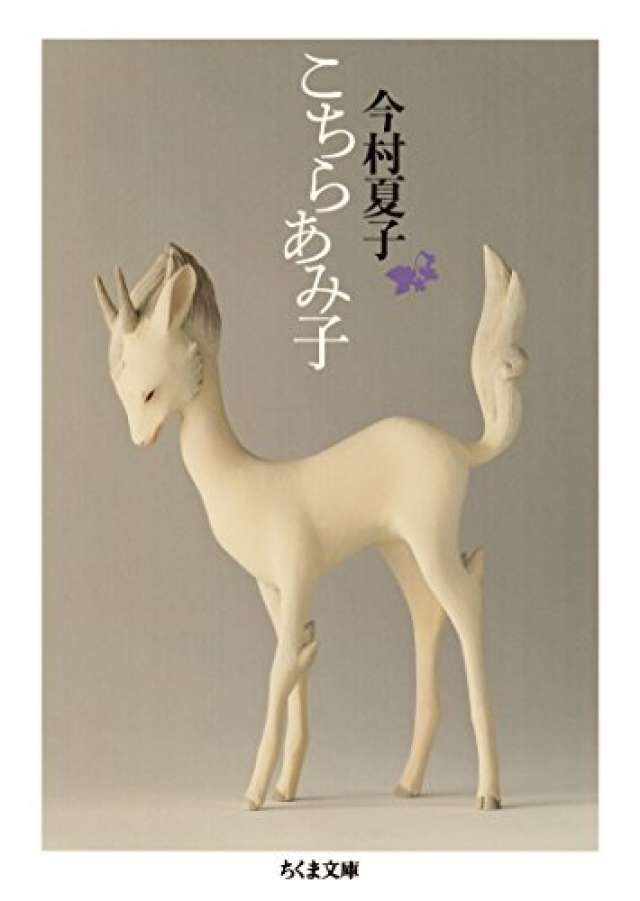丸いクッキーのぞっとする話/『こちらあみ子』
文字数 3,239文字

Youtubeチャンネル登録者数66万人超え!
「1人前食堂」を運営する、料理・食材愛好家のMaiによる初書評連載。
動画に映り込む本棚、そこに並ぶ数々の本。
Maiによって選び抜かれた1冊1冊に秘めた想いが明かされる。
第1回は今村夏子『こちらあみ子』に潜む悲劇について。
「クッキーの表面を覆っているチョコレートだけをきれいになめとってしまうと、あみ子の腹は空気を吸うのも苦しいほどに満腹になってしまった」
今村夏子の諸作には、度々リアリティ溢れる食べ物描写が登場するが、処女作である“こちらあみこ”のチョコレートクッキーもその一つである。
主人公あみ子は、チョコレートクッキーの他にもさくらんぼのゼリーは実の部分だけほじくり、さつまいもの蒸しパンは黄色いところだけむしり取って、あとは食べないで兄にあげてしまう。
そんな無邪気で子供らしいあみ子をみると、好きなものしか食べず親に叱られた子供時代を思い出す。(ピザの具の詰まったところだけかじったり...)暫し童心にかえりあみ子にシンパシーを感じたのだったが...ノスタルジーに浸っていたのも束の間、このあと、チョコレートクッキーが思いもよらぬ事態を招くこととなる。

あみ子は、そのチョコだけ舐めた丸いクッキーを大好きなのり君に食べさせてしまうのだ。
しかも悪意ではなく純粋な善意の気持ちで。
ビスコのクリームを舐めたやつを犬にあげるくらいならまだ想像できるが、あみ子の行動は普通の範疇を超えて、常人には野蛮にさえ映る。良かれと思ってしたことが反対に周囲の人たちを傷つけてしまうのだった。
私自身思い返せば、誰かと関わって傷つけたり、傷ついたりする度に私の中のあみ子を着実に削り落としていったような気もする。
だが幸か不幸か傷つかないあみ子は一生あみ子なのだ。
そんな小さな異端児に周りの人々は容赦なく、集団となって嘲笑し、罵倒し、暴力まで振い排除しようとする。一方、あみ子のピュアな眼差しは社会の矛盾をえぐりだし、この世の善悪をひっくり返してしまうほど馬鹿力である。チャップリンの名言で「人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見れば喜劇だ」という言葉があるが、目も当てられない現実もあみ子あるいは今村夏子のレンズを通すと忽ち愉快で滑稽な光景に見えてしまうのだ。まだ子供と大人の間で揺れていた私は、あみ子の存在をひそかに歓迎し、望みを託すような気持ちで読み進めたのだった。
しかし、歳を重ねるたび、あれから今村夏子が生み出す数々の名作に触れるたびに、ふと初期に読んだ“こちらあみ子”の存在が思い出された。当時の私の小さな視野で“こちらあみ子”の世界をどれくらい見渡せていたのだろうか。この小説にはまだ子供で未熟な私には見つけられなかった悲劇が潜んでいるような気がした。

願わくばこの小説を10代の瑞々しい記憶のまま保管しておきたかったし、作品の解釈は人それぞれ正解も不正解もない。
しかし、それでも書き手の真意を知りたいと思うのが読者の常である。
よってこの連載をいいことに再度読み返してみた。
その頃の私は、あみ子というアトラクションに乗って小説の中をスルスル滑ってゆくだけでスリル満点だった。しかし、乗り物酔いこそしないが、もっぱらアトラクションではしゃげなくなった現在20代後半の私は、もっと視野を広げて『こちらあみ子』というテーマパークを楽しもうと試みた。その中で、最も私の胸を突いたのがあみ子と母の関係性についてだ。
『こちらあみ子』の原題は『あたらしい娘』であったと言われている。“あたらしい娘”とはほかでもないあみ子の継母である“あたらしい母”からみたあみ子のことを指している。
継母であるところの母は、こちら側のあみ子を最も拒絶するあちら側の人間として描かれる。
ある日、生まれてくる弟とトランシーバーで遊ぶと意気込むあみ子だったかが、母のお腹の赤ちゃんは死んでしまう。母を励ますべく、昔飼っていた金魚とカブトムシのお墓の隣に“弟の墓”を立てて母にプレゼントとする。それを見た母は泣き崩れてしまうのたが、当のあみ子は「いきなり泣き出した」と呆然としてしまうのだ。
“弟の墓”の一件により心が壊れてしまった母はあみ子に見つからないように隠れて生活するようになる。子どもの無神経な悪戯だと思って見過ごしてあげてもよかったのではないか...と、当時の私はこちら側の目線で母親の大人気なさに納得いかず、一方的にあみ子を疎外する母を残酷な人物だと思った。

しかしその疎外の矢印は、ほんとうに母→あみ子の一方向だけに向けられていたものなのだろうか...。
小説の後半こんな場面がある。母と初対面の日、「好きな食べ物はなんですか」と聞く母の横顔にぐろぐろと実ったほくろを見つけたあみ子。あみ子はもうそこから目が離せなくなるのだ。
ほんとうの家族ならそんな風に見たらいけないはずなのに、あみ子はどうしても母のほくろにこだわってしまう。
そういえばあみ子のこだわりはほくろ以外にも及んでいた。
冒頭で書いたチョコレートクッキーやさくらんぼのゼリー、さつまいもの蒸しパンのようにあみ子は一貫して食べたいものしか食べない。あみ子を避けるのり君には懲りずに求愛するほど興味があるが、唯一あみ子に優しい隣の席の坊主頭の少年は顔すら覚えられない。この無意識の選別も見たいものしか見ないあみ子の揺るがない視線の現れである。
そうした食べたいものや見たいもの以外を徹底して避けるあみ子の振る舞いに私は些かぞっとするのだが、もしそのような排除の意識が家庭にまで及んでいたとするとどうだろう。いつまで経っても母は母親ではなく、ほくろに見えてしまうあみ子。他人であっても家族になれるという母の世俗的な”希望”は、あみ子には通用しない。さくらんぼのゼリーや坊主頭の少年を取り除いたように、知らず知らずのうちに母もあみ子に弾きだされてしまった存在なのかもしれない。
今の私なら少しわかる。母をはじめあみ子を取り囲む人々の心の嘆きが行間からこぼれ落ちているのが。
こちら側のあみ子の視点で描かれた喜劇的な文章の端々にあちら側の人々の悲劇が内包されている。
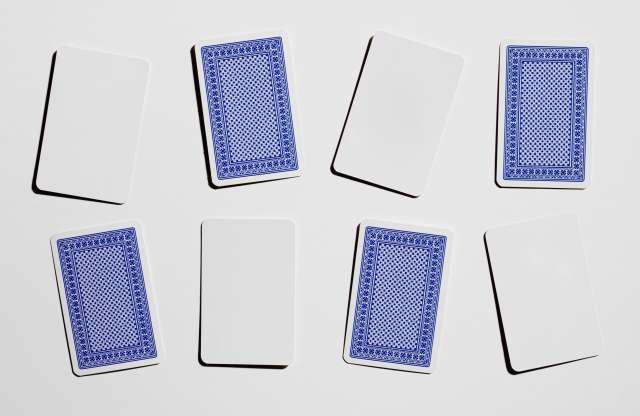
『こちらあみ子』以降、今村夏子の諸作では、子どもが多く登場する。『あひる』の、主人公の家で飼っているあひるを見にくる子どもたち、『むらさきのスカートの女』の、公園で座っている女の肩をたたく子どもたち、『父と私の桜尾通り商店街』の商店街の子ども達。どれも子どもの無垢で残酷な性分が描き出されているが、あみ子もその例外ではなく、ピュアでおっかない子供のひとりである。
純真さをただ理想として賛美するのではなく、そこには透明な暴力が潜んでいることを教えてくれる。
最後まで周りと心を通じ合わせることができないあみ子は、応答するか分からないトランシーバーに呼びかけ続ける。
『こちらあみ子』は限りなくファンタジーなあみ子を主人公とした寓話であるが、あみ子と母の関係性が一重にそうであるように、強者弱者、正常異常、善悪が対立する物語ではない。それは、どこにでもいる、分かり合えないが分かり合いたい他者の集合体である私達についての話。
ここ数年私は、YouTubeで動画を配信していて、今ではそれが生活の一部である。寝ても覚めても、会ったことも見たこともない誰かに向けてメッセージを考えている。ほんの一瞬、誰かとわかり合うために今日も「こちらあみ子。応答せよ」と動画を投稿しようと思う。
料理・食材愛好家。Youtubeで料理動画投稿チャンネル「1人前食堂」の運営をしている。
著書に『私の心と体が喜ぶ甘やかしごはん』『心も体もすっきり整う! 1人前食堂のからだリセットごはん』など。
Twitter:@ichininmae_1
Instagram:@mai__matsumoto
Youtube:1人前食堂