翻訳(という) 家の窓から見える風景/木原善彦
文字数 3,539文字
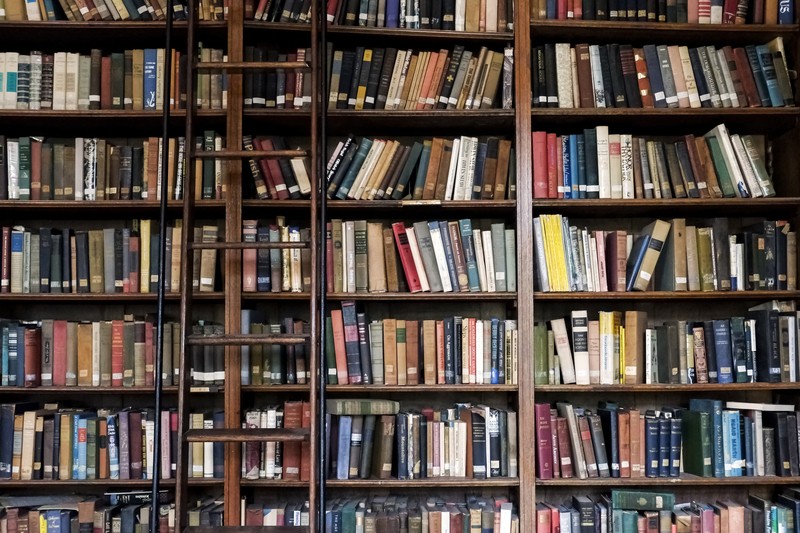
いきなり私事で恐縮だが、去る4月末、ウィリアム・ギャディス『JR』の翻訳で日本翻訳大賞という賞をいただいた。同賞は、特定の出版社の後援なしに、翻訳物好きな一般読者が「これぞ」という候補作を推薦するところから出発して、金原瑞人さん、岸本佐知子さん、柴田元幸さん、西崎憲さん、松永美穂さんという錚々たる面々が選考をするというもので、その受賞はおそらく翻訳者にとって最高の栄誉であり、個人的には「翻訳家を名乗ってもいいよ」というお墨付きをいただいた心持ちだ。
授賞式当日、受賞者と選考委員が顔を合わせてインフォーマルに話す時間があった際、「『JR』みたいな作品を翻訳していてどう楽しいのか?」みたいなことを尋ねられた私は、数年前から飼っているアカハライモリがたまたま今春、初めて産卵し、ちょうど孵化したばかりだったこともあって、偉い先生方を前に、「赤ちゃんイモリの餌やりに似た喜びがある」という妙な比喩で返事をした。
私が言いたかったのは、「まるで不動のモノリスみたいに見える重厚・長大・難解な文学作品も、翻訳する私にとっては繊細で小さな生き物のご機嫌をうかがっているようで、微妙な加減でぴたっとはまった気がするときもあれば、なかなか食いついてくれずに苦労することもしばしば」ということだった。
授賞式の3日後、あるラジオ番組で「日本翻訳大賞特集」が組まれた。その締めくくりで、司会者に「海外文学を読む意味とは?」と尋ねられた柴田元幸さんは、「僕は“意味”とか“意義”とかが苦手だ」という前置きの後、「だってラーメンを食べるのに誰も意義を求めたりしない。ただうまいから食べるんだ」とお答えになった。うまい答えだ。その通りだと思う。
それからひと月ほど経って、ウェブマガジン「考える人」に日本翻訳大賞を振り返る西崎憲さんのエッセイが掲載された。そこには「翻訳というものは、駅や港や空港や川なのだ。それは外からやってくるものを迎える場所であり、外界への扉だ」と書かれている。うまいたとえだ。その通りだと思う。
お二人の発言を勝手に足し算するなら、「窓の外に見える風景はいつだってうまい」ということだ。というわけで、ここでは、ついに半数ほどが上陸したわが家のイモリたちの近況ではなく、私が今年に入ってからどんなうまい小説を食べて、窓の外にどんな風景が見えたかを少しだけご紹介したい(以下の作品はすべて未訳)。
今読んでいる小説はリベリア出身、アメリカ在住の女性作家ワイエトゥ・モアが書いた『彼女は王になる(She Would Be King)』(2018年)で、次のように始まる。
ベッサはもしも先に進みたければ、ゆっくりと道を這っている蛇をどかさなければならなかった。その金色の目は太陽のようで、じっと見ていられなかった。緑がかった茶色の体は這い出てきた藪と同じ色だったので、まるで周囲の森が彼女の出立を嫉妬して、その行く手を遮るために足の先を伸ばしてきたみたいに感じられた。
舞台は1830年頃の西アフリカなので、蛇の目の印象も私が知っているものとは異なり、森自体も何か生命を持った魔術的な存在であるかのようだ。
西アフリカの森で5度の乾季を生き延びた女、ジャマイカ出身の姿を消せる男、アメリカでの奴隷生活から逃げてきた、弾丸を撥ね飛ばす能力を持つ男、風になった奴隷女らを中心にして語られるリベリア建国の物語は、ガブリエル・ガルシア=マルケス『百年の孤独』やサルマン・ラシュディ『真夜中の子供たち』を彷彿とさせるばかりでなく、昨今のハリウッド映画のスーパーヒーロー集結ものをも想起させる。私はこんなエキゾチックでドラマチックな味付けには目がない。
『真水(Freshwater)』(2018年)を書いたアクウェイケ・エメジはジェンダー的にはトランスで、「間の空間に基盤を置くイボ=タミール系作家」を自称しているので、作品はさらにエスニックな味がするのかと思いきや、作者自身の自傷癖、双極性障害、解離性同一性障害などをイボ族の神話体系を下敷きにして描く(主人公の内側にいる精霊のような存在たちが語り手)というもので、エスニックさと現代風の超域的な味付けとが絶妙に合体した、驚きの作品だった。
先の作家はいずれも「どこの国の人?」と思わせる名前だが、名前のインパクトがさらに強烈な作家がいる。私が翻訳大賞をいただいた2日後(4月29日)、アメリカでは、今年のペン/フォークナー賞がイラン系の若い女性アザリーン・ヴァンデアフリートオルーミの『コール・ミー・ゼブラ(Call Me Zebra)』(2018年)に与えられることが発表された。
やけに目立つその長い名前と、メルヴィル『白鯨』本編冒頭の台詞「わが名はイシュメール」をもじったようなタイトルに私は惹かれた。この作品は、文学至上主義一族の末裔としてイランからトルコ、スペインなどを経てアメリカに渡った若い女性が、騎士道小説で頭がおかしくなったドン・キホーテのように、文学というよろいをまとって、自分のルーツをたどる物語だ。
しかしこの小説は、異国の雰囲気よりも、混迷する現代と向き合う文学至上主義者(よろい代わりにブランショやボルヘスをまとった文学の騎士)の目から見える世界が時に滑稽なほどずれていたり、時に逆説的に、ずれているがゆえに正鵠を得ていたりする点が興味深い。空回りを続ける主人公の気合いは、冒頭部からも明らかだ。
無学者、初学者、自称選民など、あらゆるネズミどもに告ぐ─私、ゼブラは、1982年8月の焼け付くような日に、ビビ・アッバス・アッバス・ホッセイニとして生まれた。百年間、血で血を洗う争いの続いた首都テヘランを何度も捨て、けだるく湿気たマザーンダラーン州のノーシャーに逃げ延び、独学で生きてきた一族の末裔だ。
この語り口は、21世紀に生きる若い女性が語り手とは信じられないほど時代がかっていて大仰だ。だが、『ドン・キホーテ』内の出来事をドン・キホーテ自身が語るような口調はまさに、文学的な批評精神の王道を歩むものだと言っていい。これなどは、店名(作者名)が風変わりでも、そこで提供されている料理は知性とユーモアにあふれた上質な定番という例だろう。
オーシャン・ヴオングというベトナム系詩人(ゲイと公表している)の小説デビュー作『私たちは地上でつかの間輝く(On Earth We’re Briefly Gorgeous)』(2019年)は、母に宛てた手紙という形で、無数の小さなエピソードをこの上なく詩的な文章で次々に綴っていく。その美しさは、最近、英語圏で増えてきたオートフィクション(作家自身の日常を虚構混じりに綴ったエッセイ風の小説)の中でも出色だ。
人間の目は最も孤独な創造物だとあなたはかつて教えてくれた。外の世界がどれだけ瞳から入ってきても、中はいつも空っぽ。眼窩の中にぽつんとある目は、わずか3センチの所に自分とそっくりな、空虚で飢えた仲間がいることさえ知らない。あなたは玄関を開けて、人生初の雪を私に見せながらささやいた。「ごらん」と。
こういうタイプの小説は、筋を追うところにほとんどエネルギーを使わずに、ただひたすら目の前にある言葉、文をじっくり味わうだけで楽しめるのがいい。
こうしてざっと見ただけでも、かつてアメリカ文学史の教科書で大雑把にくくられていた「黒人作家」「女性作家」などという区分は、もはやほとんど意味を成さなくなっていることが分かる。アフリカ系でも、奴隷の子孫もいれば、新たにアフリカから移住してきた作家もいる。新たな移民の出身国も多様だ。作家たちの性的指向・性自認についても、20世紀までとは隔世の感がある。私は多くの面でどちらかと言うと保守的な読者で、マイナーな作家を選んで読んでいるわけではないので、私が手に取る作家がこれほどまでに多様化しているのは、実際の文学界がそれだけ多様化しているからだと考えて間違いない。
日々、せっせと英語圏の小説を訳している私の家の窓はいつも同じ方向を向いているけれども、そこから見える風景は気づかぬうちに驚くほど変わっている。その風景はいつだってうまい。
【木原善彦(きはら・よしひこ)】
アメリカ文学者。67年生まれ。著書に『UFOとポストモダン』『実験する小説たち 物語るとは別の仕方で』、訳書に『両方になる』『JR』など。



