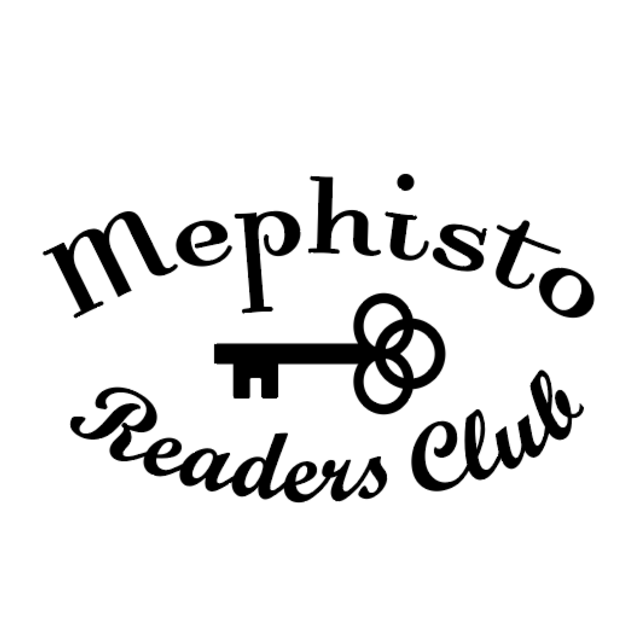砥上裕將×吉田大助 『7.5グラムの奇跡』深掘り対談③
文字数 3,283文字
砥上裕將(水墨画家・作家)×吉田大助(ライター)
『7.5グラムの奇跡』深掘り対談(全3回)
第3回 「働くということ」の神聖さとチームの喜び

お仕事小説としても素晴らしい本作。
「たった一つのことを選ぶ」仕事の本質について、
スペシャリストでるあることについて、
砥上裕將さんと吉田大助さんが語り合います。
誇りを持って仕事をしている人たちの神聖さ、
「生きよう」の4文字を選んだ理由
吉田 この対談の冒頭で、「働く人の気持ちを次はきちんと書くべきだと思った」とおっしゃっていました。書きながら、実際どんなことを感じていましたか?
砥上 こつこつと寡黙に自分の仕事をしている人たちが、世の中を支えている。そのことに対する敬意を、改めて強く感じました。誇りを持って仕事をしている人たちというのは、神聖だとも思いました。
職業というものは、一種の神聖さとか清らかさみたいなものを生み出すんだなと。そういう感覚に触れた気がします。
吉田 「神聖さ」に紐付けて言うと、僕自身は、天職ということを考えました。
第1話で、まだ学生だった野宮が北見眼科医院を訪ねて、就職の面接を受けるシーンがあります。そこで院長から「なぜ視能訓練士になろうと思ったのか」、建て前ではなく「本当のことを教えて」と言われて、「たった一つのことを選べれば、なにかになれるかもしれない」、と答えます。視能訓練士が野宮にとって天職であるかどうか分からない、誰にも分かりようがないんですよね。
ただ、さまざまな偶然も作用して選び取った視能訓練士という職業を、天職に「する」。僕自身も人生を振り返った時に、まさにそういう回路を経由して、自分の職業を天職と感じるようになったのかもしれないなと思ったんです。その回路というのは、偶然や不安に満ちた人生に対して、めげずに立ち向かう態度にも繫がるんじゃないかな、と。
砥上 僕自身は、好きな絵だけを描いて生きてきましたが、厳しいことや辛いこともありました。世の中は厳しいものであるという感覚は、やっぱりあるんですけれども、予想外に嬉しいことも折々にあって、そういう経験が自分を成長させてくれたなとか、続ける力にもなったなって思うことがあります。
だからこの小説では、厳しさや辛さよりも仕事の喜びの方をできるだけ拾いたかったし、野宮君にもそれを感じて欲しかったんです。
吉田 本作は野宮の物語であると同時に、北見眼科医院というチームの物語でもありますよね。例えば、野宮は不器用で、新米ゆえに検査結果の見落としも多い。でも、先輩視能訓練士には気付けないことを気付けた、思わぬヒントを手に入れていた、という場面が幾度か登場します。広瀬先輩の「人がたくさんいるってことは、それだけ可能性があるってことだから」というセリフは、チームの力を強く喚起させるものでした。
砥上 視能訓練士が2人いて、片方の視能訓練士は全く気づかないことを、もう片方は気づくことって現実によくあるらしいです。診察時に、実際に検査をした人の手ごたえとか感覚が頼りにされるところが多いので、優秀な視能訓練士さんは先生たちも一目置く存在なんです。
そういう視能訓練士のかっこよさも書きたいなという思いはありました。
吉田 チームで仕事をする喜びや役割意識は、水墨画家を主人公にした前作にはなかったもの。この点もまた、本作だからこそ書きたいと思われたのでしょうか?
砥上 訊ねられて思い出しましたが、書きながら、チームで仕事するのって、ちょっとうらやましいなと思いました。自分はこれまで個人プレーばっかりしてきたから(笑)。
お話を伺ったそれぞれの先生は、視能訓練士さんや看護師さん、受付の事務の方など、病院に勤めるみんなのことを信頼していました。全員揃ってはじめて診察が回っていくものだ、という認識を持っていらっしゃる。そういう感覚に、社会というものを教えてもらったような気がします。
吉田 小説家にとって書くことは孤独な作業ですが、本を世に出す、本を読者の元に届けるところまでのプロセスには、たくさんの人が関わっていますよね。編集者であったり営業さんであったり、書店員さんであったりと、そこにも一つのチームが出現している。
第1作を出さなければ経験できなかった、そのチームの感触が、本作のチーム感にフィードバックされていったところがあるのではないか、と想像したりもしたんですが。
砥上 あるかもしれません。1冊の本を作るのにこんなにたくさんの人が関わっているんだということは、小説家になって初めて知りました。
みんながそんなに頑張ってくれるなら自分も頑張ります、と言っちゃって自分の言葉にびっくりした経験もあります。
書店に自分の本があるのを見た時は、不思議な感じがしましたね。僕が置いたわけではないので(笑)、並べてくださった人がいるわけじゃないですか。
吉田 ある種の奇跡ですよね。決して、当たり前のことじゃない。そういう奇跡の経験が、本作における「見えるという奇跡」の表現にも繫がっているのかもしれない(笑)。
砥上 奇跡という意味では、この作品がちゃんと書き上げられて世に出たこと、これは奇跡じゃないかなと思います。
第1話を書いた後に気づいたんです。これ、めちゃくちゃ難しいことをやろうとしてるんじゃないか、と。誰も死なないし、淡々と検査して帰っていくし、情報をリアルにすればするほど、劇的な展開にはならない。書き上げることができたのは、取材させていただいた医療関係者の方々や編集部のおかげです。
吉田 最後にお伺いしたいことがあります。この対談記事の前に本サイトにアップされた書評でも記したことんですが、前作ではクライマックス直前、重要人物が物語から去るエピソードにおいて、本作では最終第5話のクライマックス、「光への瞬目」という鍵概念が導き出される瞬間において、まったく同じ言葉が現れるんですね。
それは、「生きよう」という言葉です。例えば、宮崎駿監督の『もののけ姫』のキャッチコピーは「生きろ。」なんですね。黒澤明監督は『生きる』という映画を作っている。
砥上さんが選んだのは「生きろ」でもなく、「生きる」でもなく、「生きよう」。この4文字に、どんな思いを込めているのでしょうか。
砥上 無意識に書いていた箇所なので意外な質問ですが、三つの言葉は比べてみると、時代の違いみたいなものを感じます。
戦後の日本で激しく強く生きなければならなかった時代は「生きる」で、生活は向上していろんなことが満ち足りているのに、世界に対してネガティブな印象を持っていて、生きる意志を失いつつある時代は「生きろ」。そこからみんな、さらにしんどくなっちゃって、もしかしたら、へたりこんじゃったのかもしれない。
その状態からもう一度立ち上がって歩き出すような、そうしたニュアンスを「生きよう」という言葉に感じます。ゼロから何度でもやり直すのって、好きですよ、僕。そういう感覚を自分が持っているから、出てきた言葉なのかもしれません。
吉田 早くも次回作を楽しみにしています。それまでは2作品を折に触れて読み返して、「生きよう」を受け取っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
●砥上裕將(とがみ・ひろまさ)
1984年生まれ。水墨画家、作家。『線は、僕を描く』で第59回メフィスト賞を受賞しデビュー。同作は、王様のブランチBOOK大賞2019受賞、2020年本屋大賞第3位に選出された。
●吉田大助(よしだ・だいすけ)
1977年生まれ。ライター。「ダ・ヴィンチ」「STORY BOX」「小説 野性時代」「小説現代」「週刊文春WOMAN」などで書評や作家インタビューを行う。Twitter(@readabookreview)で書評情報を発信中。