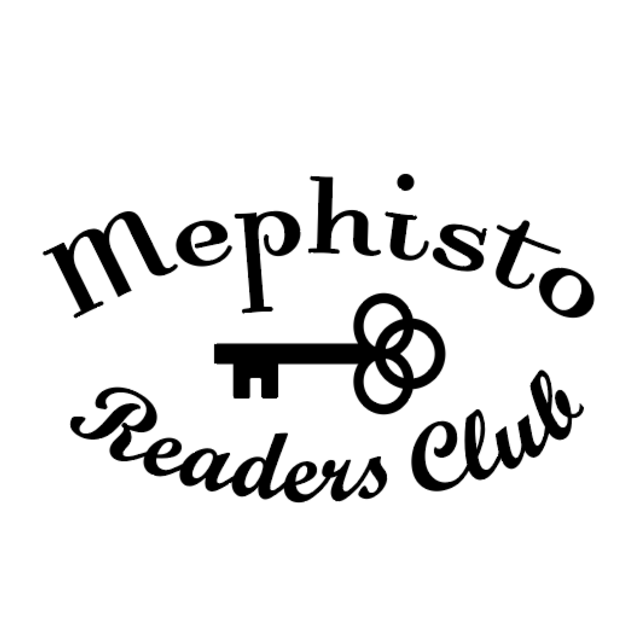砥上裕將×吉田大助 『7.5グラムの奇跡』深掘り対談①
文字数 3,252文字
砥上裕將(水墨画家・作家)×吉田大助(ライター)
『7.5グラムの奇跡』深掘り対談(全3回)

『線は、僕を描く』で第59回メフィスト賞を受賞しデビューした砥上裕將さん。デビュー作から砥上作品に注目し、2作目『7.5グラムの奇跡』も熱烈歓迎の吉田大助さん。お二人の温かく熱い対談を全3回でお届けします。
第1回 水墨画から眼科の世界へ
絵の話はやめておこうと思いました。
次は、働く人の気持ちをきちんと書くべきだと思ったんです
吉田 小説家にとって第2作、言い方を変えれば「デビュー後第1作」はとても重要だと思います。デビュー作の中にあったどの要素を2作目に引き継ぐか、あるいは引き継がないか。そのジャッジが小説家としてのその後のキャリア形成に大きく寄与していった、というケースをこれまで多々目にしてきました。
砥上裕將さんは第59回メフィスト賞受賞のデビュー作『線は、僕を描く』において、水墨画の世界に足を踏み入れた、大学1年生の青年を主人公にした物語を紡がれました。同作は、2020年本屋大賞3位に選ばれるなど大ヒットを果たします。デビュー作が大ヒットって、当該作品の存在感が増すことになるとも思うんですよね。
では、砥上さんの第2作『7.5グラムの奇跡』はどんな物語だったか。街の小さな眼科医院の視能訓練士、「目の専門の検査技師」の仕事に就いた野宮恭一の、社会人生活1年目を追いかける物語でした。デビュー作と比べると様々な点において、作風がガラッと変わっているんです。第2作の執筆にあたり、どんな意図を持って一歩踏み出したのでしょうか?
砥上 絵の話はやめておこうと思いました。
吉田 そこなんです(笑)。前作が大ヒットしたら、その路線を継いじゃいそうなところですよね。しかも砥上さんはプロの水墨画家でもありますから、使っていないネタは売るほどあったはずで。
砥上 前作では書けなかったことを書こう、という気持ちが強かったです。前作の主人公の青山君には天才的なところがあったので、次は普通の人を主人公にした普通の世界の話にしたいと思いました。働く人の気持ちをきちんと書くべきだと思ったんです。
吉田 大学1年生の青山ではどうしたって表現できない「働くこと」のリアルを、社会人1年目の野宮を主人公にすることで描いてみたかった、と。
砥上 自分と世の中との関わりは、働くことを通じて感じとることが多いんじゃないかと思います。そしてそれをもっとも強く感じとれるのは、社会に出たばかりの頃かなと。
仕事にはネガティブな面があるのも事実だけど、今はネガティブな面ばかり強調されている気がしていて、だからポジティブな面を書きたいと思いました。ポジティブだけど実感から遠くない言葉を使おうと意識しました。
誰にでも当てはまることではないけれど、小説を通して「こういう考え方もあるんじゃない?」とポジティブな価値観を提示できたらいいなと思って。
吉田 前作と本作の主人公像に、かすかな繫がりも感じたんです。前作の主人公の青山は、水墨画の世界にスカウトしてきた師匠から「いい目」を持っている、と評されています。描くことに関してはシロウトだけれども、天才的な観察眼を武器にして、水墨画の先達と肩を並べるようになっていく。
対する本作の主人公の野宮は視能訓練士であり、見ること、見えるということに対して、非常に強い愛着と好奇心を持つ人物です。前作にあった「目」というキーワードが、本作において全体化されたというふうにも感じられました。
砥上 絵師としての自分が、反映されているのだと思います。絵を描く人間にとって見ること、見えるということは、ものすごくありがたいことなんです。それもあって2作目で医療としての目を書こうと決めた時は、納得がいくというか、すとんと腑に落ちる感覚がありました。
医療従事者の普段の姿を書いてみたい。
普段の診察の裏側にある感情を言葉にしたい
砥上 この小説を書こうと思ったきっかけの一つは、妹が視能訓練士だったことです。あとは監修をお願いした友人の東淳一郎先生からお話を聞く機会があって、眼科医療に関して興味が湧きました。妹が話していたことで意味がわからなかったことも先生が解説してくれたり、それを聞いて「うちの妹、ちゃんと仕事してるんだ!」と思ったりしました。
吉田 それはデビュー前のことですか?
砥上 はい、5年以上前だと思います。
いつか視能訓練士の話を書きたいとは思っていました。でも水墨画の世界と違って、ものすごく勉強しなければ書けない。相当な熱量がないと走り出せないなと思っていました。
編集部には執筆を求められたけど踏み出せずにいた時に、コロナ禍がやって来ました。世界中で健康について考えたり、医療従事者の方々に思いを寄せるようになった。
でもコロナ禍じゃなくても、いつだって頑張っているってことを妹や東先生を通して知っていました。その医療従事者の普段の姿を書いてみたいという思いも重なって、執筆の覚悟を決めました。
吉田 さきほどの「仕事に対するネガティブではなく、ポジティブな言葉を」という話にも繫がりますが、今の世の中を見渡した時に明らかに言葉が足りていない部分、あるいは存在するんだけれどもなかなか言葉にはされていないことを、表現したいという気持ちが強いんですね。
砥上 そうかもしれないです。眼科って検査が淡々と進見ますよね。「ここに座ってください」「片目をつぶってください」って。間に何の検査か説明がないから、「今、何調べたの?」ってなったりする。でも、もちろん視能訓練士や看護師の方々は、検査のやり方や出てきたデータに対していろんな気持ちを持っています。
それは医師も同じで、患者さんに結果だけを淡々と伝えているように見えても、常にいろんなことを考えて判断している。そういった表に出てこない部分を言葉にしたいと思いました。
吉田 かなり取材されたと思うんですが、取材を受けた側も嬉しかったんじゃないでしょうか?
本作を読みながら、医療従事者たちの言葉になっていない感情や感覚を言葉にしたい、あるいは眼科医療にまつわる正確な情報を伝えたい、という書き手の意志を強く感じました。
砥上 取材した方々には、温かく迎えていただきました。どうやら面白がられてもいたようです。
東先生の他には、視能訓練士さんや眼科の医療に従事する方々、分野の違うお医者さんにも少しお話を伺う機会がありました。質問に対して「あっ、一般の人はそこから分からないんだ」ということがいっぱいあったみたいです(笑)。
取材中はいろいろな気づきがありました……例えば「診療中の細かいことはあんまり覚えてないんだよね」とおっしゃる人が結構多かったんです。
一生懸命やってないから語れないってことではないんです。逆なんです。現場でものすごく集中して一生懸命にやっているからこそ、集中していた時のことは思い出せなくなってしまう。その感覚は、僕自身が水墨画を描いている時と繫がるところがあると思いました。
吉田 それでは次回は、第1話から第5話まで各短編について詳しくお伺いしていきたいと思います。
●砥上裕將(とがみ・ひろまさ)
1984年生まれ。水墨画家、作家。『線は、僕を描く』で第59回メフィスト賞を受賞しデビュー。同作は、王様のブランチBOOK大賞2019受賞、2020年本屋大賞第3位に選出された。
●吉田大助(よしだ・だいすけ)
1977年生まれ。ライター。「ダ・ヴィンチ」「STORY BOX」「小説 野性時代」「小説現代」「週刊文春WOMAN」などで書評や作家インタビューを行う。Twitter(@readabookreview)で書評情報を発信中。