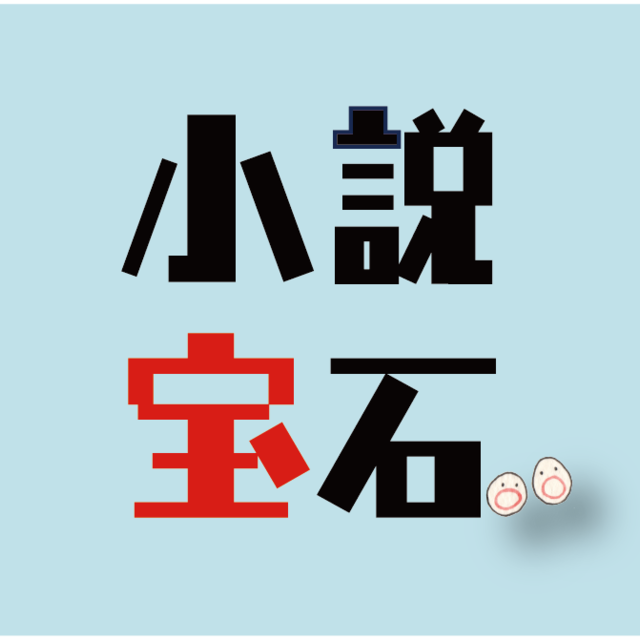『にぎやかな落日』刊行記念 朝倉かすみ インタビュー
文字数 4,147文字
山本周五郎賞受賞作
『平場の月』から二年四カ月、
待望の朝倉作品が刊行された。
今作は、80代のひとりの
老女の内面に寄り添う、
人生最晩年の物語。
誰もがいつかこんなふうに感じる
老境の心情が、
静かに切々と迫ってくる。
インタビュー・文 杉江松恋

最初の「たんす、おべんと、クリスマス」は、もともと単発の短篇として書いたものだったんです。でも、肝腎の「たんす、おべんと、クリスマス」が何なのか、というところまでたどりつけなかった。それで「続きを書きたいなあ」とずっと思ってたんですね。
冒頭に、一人暮らしをしているおもちさんが、備忘録みたいなノートをたくさんつけているというエピソードが出てきます。その中に「たんす・おべんと・クリスマス」という、自分でもなんでそんなタイトルなのかわからないものが一冊あると。おもちさんのことを書いたのは、何かきっかけがあったんですか。
うちの母です。私が母にだんだん苛立(いらだ)つようになっちゃって、母もそれに怒りだすこともあって、そういうのがすごく嫌でした。そんなころに、二人で歩いてるときに後ろから母の写真を撮ったんですよ。あの人が楽しそうに歩いてる姿を後で携帯で見ていたら、こういうお婆(ばあ)さんの話を「ごめんなさい」っていう気持ちとともに書きたい、と浮かんできました。もしかしたら私、知ってるんじゃないかと思って。その人の気持ちを。
小説にすることで、ご自分の中でも形になっていないことが表現できるかもしれないということですね。だから、ノートのタイトルの意味が書けなかったことを、もどかしく思ったんでしょうか。連作には、朝倉さんを思わせるおもちさんの長女が出てきますね。おもちさんからすると、口やかましく言われるのでちょっと煙たい存在です。
そうです。「あの人はどういう感じで生きているのか?」ということが書きたかった。母はすごく感情の起伏が激しいんです。歳を取って俄然(がぜん)そうなっていったんですよ。急に怒ったり、急に泣いたり。その感じがすごく不思議でおもしろくて。ちゃんとした大人のところもあるのに子供みたいな言動をするときがある。また、そうなる気持ちの動きは、ちょっとした目の動きとかでわかるんです。その心の中を書きたいなと思いました。
おもちさんというキャラクターがすごくおもしろいのは、考えることに彼女なりの筋が通っていることです。たとえば、糖尿病だから禁じられている買い食いをして叱られた場合は、「確かにその通りだけど、なぜ私を信じてくれないのか」と怒る。そういう風に彼女なりの理屈があるところがいいですね。背後にお母さまがいるわけですが、そのモデルが透けすぎないよう、おもちさんが独立したフィクションのキャラクターとしての独自性を獲得するように書くことに、朝倉さんはとても気を遣われたのではないかと思います。
たしかに最初はうちの母親のことを書いてる感じだったんですよ。ただ、二、三篇書いたところで、「これはおもちさんだ」ってなりましたね。もともと「たんす、おべんと、クリスマス」という私が作った言葉から始まった連作ですけど、そのタイトルも終わりに近づくにつれて、おもちさんの発したものになっていきました。「テレビ、プリン、オートバイ」でおもちさんと旦那さんが話す内容だって、母と父の会話を聞き書きしたわけではないですからね。おもちさんの若いころの思い出とかも、どんどん足していきました。母の写真を見ながらおもちさんの思い出を書く、という感じです。
「コスモス、虎の子、仲よしさん」の資産整理に行ったら通帳を隠された話とか。でも隠したことを、母は義妹にはなぜか言うんですよ。「かすみが乗り込んできちゃった。あの子に見つかるとうるさいから、預かっといて」って(笑)。それでわかりました。
あの人はすごくつけます。真面目なんですよ。糖尿病ということはすぐ忘れるのに、今日何にお金を使ったか、ということは全部書いちゃう。お医者さんに見せるほうにはちょっとしか書かないんだけど、出納帳にはパンとかアイスとか全部書いてるの(笑)。たぶん、「こんなにきちんとしてるのに、なんで怒られるんだ」って言いたいんでしょうね。
ですね。そして私の中にも芽みたいなものを感じます。探し物とかしながらお菓子とか食べてると「あーおいしい」ってそっちに集中しちゃうってところがあって(笑)。これって八十五歳ぐらいの行動だろうって。気をつけないと。
私がよく聞いていたのと違う言葉で会話しているのを聞いたり、自分で書いたりすると、本当のことを言ってない、根ざしてない感じがするんですよ。女性の発言が勝手に女言葉に翻訳されるとか、今問題になっているああいう感じに近いです。だから、本当にむき出しで喋(しやべ)らせたいときは北海道の言葉がいいですね。特におもちさんは年寄りだし、北海道にずっと住んでいるんだから「~だわ」とか言うわけがない。
母がよく転ぶんですよ。「こんなに身体(からだ)が衰えてるのに、なんで若いときのまんまスタスタ歩いて転ぶんだろう。そしてなんで『転んでない』って言い張るんだろう」ってそれが不思議で。だから、雪がある場所が必要だったんですね。
あれはちょっと寄宿舎ものの少女小説を意識しています。昔のコバルト文庫とかにいっぱいあったような。何年か前に読んだとき寄宿舎の描写が「親の入った施設に似てる」と思ったんですよ。おもちさんは可愛(かわい)いものとかが好きなんですけど、そういう少女趣味ってずっと変わらないから「寄宿舎に入れるよ」って説得したらうまくいくという(笑)。
おもちさんは老いの不具合を他人に説明しづらいことが鬱屈の原因になっています。それは結局解消されないけど、自分なりの「快く過ごすための論理展開」みたいなものを作り出して、自分を納得させていきますね。あのあたりがすごくおもしろかったです。人の思考回路が目の前で少しずつ形作られているのを見ているような感覚がありました。また、終わり方も印象的でした。いい幕の引き方ですね。
書き始める前から、「最後に死なせないよ」とは思ってました。自分なりに楽しんでいるおもちさんが「今がずっと続けばいいな」と生きていく話なので、終わらないように終わりたかった。「おもちさんのここからここまでを書きました」って感じですね。もし死んじゃうところまで書くんだったら、書き方はまったく違います。もっと社会との関わりも書いていかないといけない。戦争も子供のときにあっただろうし。だからもっと大掛かりに、朝ドラみたいな小説になりますね。
その表現おもしろいです。小さな額縁がたくさんあって、おもちさんの人生を少しずつ見せていくというイメージですね。すべての章題が「口紅、コート、ユニクロの細いズボン」みたいに三つの単語で構成されているのは、三題噺みたいな意図なんですか。
そこは自分ではわからないんですけど、短篇は早く終わるのが好きなんですよ(笑)。読むほうだって最初っから「短いぞ」って感じがするじゃないですか。読むのも書くのも短篇が好きですね。フラを入れるのも短篇のほうがうまく行く気がします。
フィギュアの荒川静香(あらかわしずか)がフリー演技のときに、得点と関係ないけど「ないとダメだから」ってイナバウアーをやったでしょう。それがフラだと思うんですよ。あれがあるかないかで短篇は全然違う。ストーリーの展開とは関係ないところで作品世界を決定づけるものを短篇のほうが入れやすいから、それで好きなんだと思います。
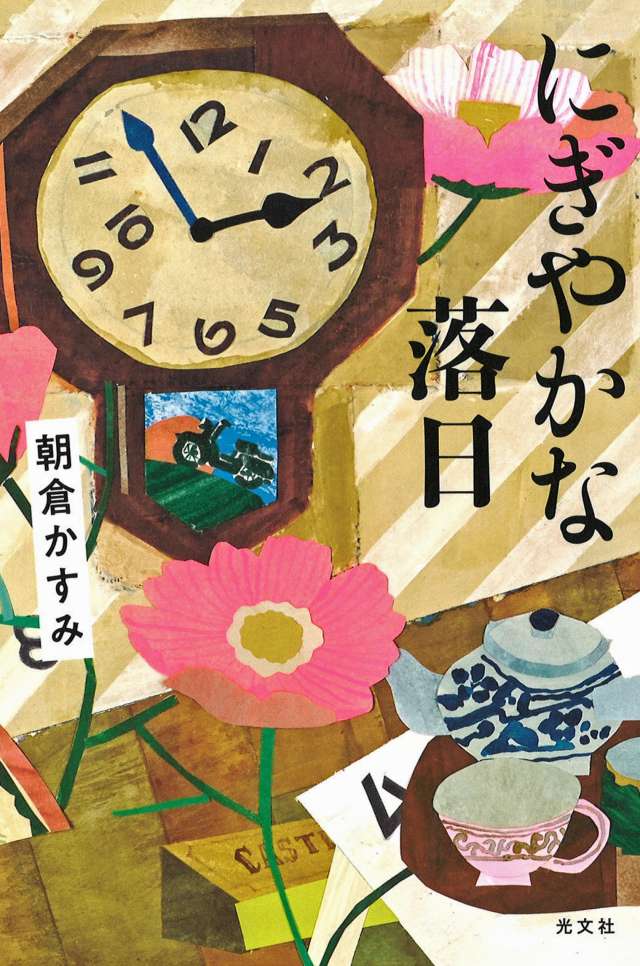
【あらすじ】
北海道で独り暮らすおもちさん、83歳。夫は施設に入り、娘は東京から日に二度電話をくれる。実は持病が悪化して、家族がおもちさんの生活のすべてを決めていくことに。可笑しくて愛らしい、揺らぐ老女の胸の裡(うち)。『平場の月』の著者の、新たな代表作。
【朝倉かすみ(あさくら・かすみ)】
1960年北海道生まれ。「コマドリさんのこと」で北海道新聞文学賞、「肝、焼ける」で小説現代新人賞を受賞しデビュー。2009年『田村はまだか』で吉川英治文学新人賞受賞。2019年『平場の月』で山本周五郎賞受賞、直木賞候補にも。