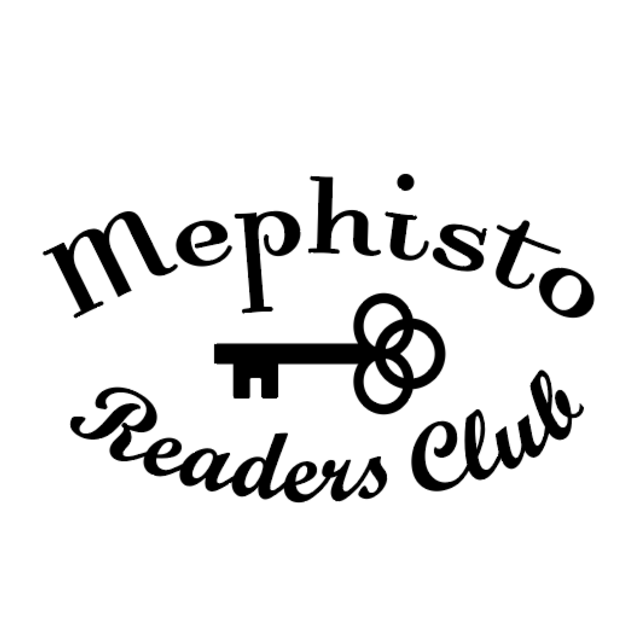祝!第9回静岡書店大賞受賞記念!
文字数 7,682文字

本当にありがとうございます!!
動画配信による授賞式はこちらから⇒https://www.youtube.com/watch?v=8AKJIn3wRsQ
一穂さんの感涙必至のメッセージが聞けます!
受賞を記念して、一穂さんが特別に書き下ろしたショートストーリー「人魚」を無料公開!
こころが震えるラストが待ち受ける傑作掌編です。『スモールワールズ』とともに、ぜひお読みください!
――あのさ、今まで黙ってたけど、人魚、なんだよね。
僕の恋人は、人魚らしい。少なくとも本人はそう主張する。その時僕たちは、清水マリーナサーカスの観覧車の中にいた。海沿いも海沿いの、オーシャンフロントで回るかわいらしい観覧車からは清水港と太平洋と富士山が一望でき、夜になるとマリーナがライトアップされ、色とりどりのスパンコールをちりばめたような景色に変わる。
――「スペシャル・ペアゴンドラ」ってあるらしいよ、乗る?
何がスペシャルかというと、カップル仕様にデコってくれているらしい。彼女はにやにやと楽しげだったが、僕は恥ずかしく「普通のでいいよ」と断った。なぜなら観覧車が一周する十三分の間にプロポーズするつもりで、夜の観覧車というシチュエーションだけでだいぶやりすぎている自覚はあり、全部盛りラーメンにさらにバターを追加するような愚行は避けたかった。
ごく普通の水色のゴンドラに乗り込み、ゆっくり円周の軌道を進み始めたタイミングで僕は早々に切り出した。
――結婚しませんか。
膝が触れ合いそうな距離で真向かいにいた彼女はまず「え〜?」と首を傾げた。
――何で今?
――え?
――ここまでセッティングしたんなら、てっぺんで言えばいいのに。
――いや、あまりにもかな、って。
しかし後半まで寝かせておく緊張に耐えられそうもなく、序盤で勝負に出た次第だ。
――いちばん大事なとこで引き算しちゃってどうすんの。ピラミッドの頂上の三角だけない状態だよ? 意味ないじゃん。ていうかもしわたしが断ったら一周するまで地獄の時間じゃん。狭い密室で、逃げ場ないのに。
――ごめん……。
どう考えてもおっしゃるとおりだった。自分の考えのなさに落ち込んでいると、「ドンマイ」と雑に慰められた。
――頭抱えてたら、せっかくの景色が楽しめないよ。
――うん。
顔を上げると、地上の明かりがゆっくり遠ざかっていく。海に投げかけられた光が水面を青白く輝かせ、富士山は夜より暗い影絵になり、昼間とはまったく違う雰囲気でにゅうっと裾野を伸ばしている。その富士山をバックに停泊している、大きな鉄骨の塔みたいなやぐらを備えた船は地球深部探査船「ちきゅう」だ。僕たちは昼間船内公開イベントに参加し、あの船が海底から七千メートルも深い地層まで掘削し、地球の起源や巨大地震の予測などを研究していることを学んだ。新幹線でこのあたりを通り過ぎる時、たまに「変わった船があるな」と気にはなっていて、でも彼女が誘ってくれなければ一生訪れなかっただろう。彼女といると、僕のちいさな世界は思ってもみなかった方向に広がっていく。だから僕は彼女が好きで、できれば末長く一緒にいたかった。
窓に額を押しつけて下界を眺める彼女はそうじゃないのかもしれない。ゴンドラがゼロ角度の地点を過ぎ、下っていっても(なぜか上りより速く感じられる)求婚への返事はなく、係員が「おかえりなさーい」と扉を開けるのとほぼ同時に、彼女はあの台詞を口にした。
――人魚、なんだよね。
彼女と初めて会ったのは、会社の同僚に誘われて沼津へ行った時だった。深海魚食べようぜ、と社内外に声をかけて結局二十人近くになっただろうか。誰かの友人の友人、だったと思うが、はっきり覚えていない。漁港近くの食堂で頼んだ大盛りの深海魚丼にはカサゴの姿揚げがどんと載っていて、こちらに顔を向けたビジュアルのインパクトにやや引き気味の僕をよそに彼女は目を輝かせ、目玉までほじくって平らげていた。この子のことをもっと知りたいな、と直感的に思った。
LINEのIDを交換し、僕は彼女とデートを重ねた。下田の水族館でイルカショーを見て、三島の湧水に裸足を浸し、浜名湖のボートレースで一万円負けた。彼女が指定するデート場所はいつも静岡、しかも現地集合現地解散だった。僕は彼女がどこに住んでいるのかさえ知らないままだったが、詮索して嫌われたくなかったし、新幹線、在来線、踊り子号とさまざまな手段で行き来するのは楽しかった。
僕は生まれも育ちも奈良で、就職を機に上京した。僕にとって静岡というのは「長い通過地点」だった。名古屋から新横浜までノンストップののぞみで走り抜けていくだけの場所。浜名湖を見て、富士山とそのふもとに広がる工場群を見て、茶畑を見て、いくつものトンネルを抜けるうちに気づけばもう小田原付近にきている。彼女があちこち連れて行ってくれなかったら、一生足を踏み入れることさえなかったかもしれない。
奈良出身だと言うと、彼女は「海なし県!」と目を丸くした。
――海がないってどんな感じ? いやじゃない?
――考えたことなかった。
海あり県だろうがよっぽどの沿岸部でない限りそんなに海を意識しないだろうし、県境を封鎖されているわけじゃないから、奈良県民だって海に行こうと思えば行ける。
そういえば彼女とのデートは、いつも水に関係するところばかりだった。人魚だという告白を聞いた時、まずそのことが頭をよぎりはした、しかしいくら何でも「へえ、どうりで」とはならない。
――え、人魚って?
――人の魚と書いて人魚。
――ああ、うん……。
――ご質問があったらどうぞ。
ストレートのデニムを穿いている彼女はどこからどう見ても人間だった。酔ってもいないし、冗談を言っている顔つきでもない。
――足、とか……。
――割と適応してるから、水陸両用。全身水に浸かったら魚になるよ。
――えっと……卵生? 胎生?
――え、いきなり下ネタ?
――ごめん。
彼女が眉をひそめる。僕はまた間違えたらしい。しかし、大輪の光となって回る観覧車の真下でこんな会話をするカップルがいるだろうか。僕が知りたいのは、なぜ唐突に、こんなばかげたホラを吹くのかということだった。
――要するに、その……種が違うから結婚はできないって言いたいの?
そんな独創的な断り方も彼女らしいという気はするが、普通に振ってくれるほうがいい。
――ううん。あなたが気にしないんなら別に。
――え、じゃあOKってこと?
――あんま早まらないほうがいいよ。
いったいどっちなのか。思わせぶりなまねをする人ではなかったので、僕はすこし混乱した。真剣にプロポーズしたのに何だよ、と抗議してもいいのだろうが、夜風になびく彼女の髪に頭上の照明がきらめき、魚っぽいといえなくもない丸っこい目もきらきらしていて、かわいいから怒れなかった。
――熱意は伝わったよ。
彼女は言った。
――今度、うちの母に会いに来てくれる?
もちろん、と僕は即答した。
――お母さんって、どこに住んでるの。
――熱海。
十月の終わり、昼下がりの熱海駅は改札から人でごった返していた。でも僕は人混みが好きだった。いつでも先に着いて待ってくれている彼女が背伸びして僕を探し、大きく手を振る姿が見られるから。帰る時には名残惜しそうにひらひらと白い指が泳ぐ。だから僕は現地で待ち合わせ、別れるデートスタイルが結構気に入っていた。そういえば五本の指を全開にした彼女の手は、やや水かきが目立つような気がするーー僕の思い込みだろうか。
「すごい人だね、熱海ってもっと鄙びた温泉街かと思ってた」
会社の慰安旅行で行って、たたみいわしみたいに糊の効いた浴衣を着て、畳敷きの宴会場で脚付き膳の夕飯を食べて(青い固形燃料で温める仕様の小鍋はマスト)、カラオケや卓球に興じ、飲み足りなければスナックやパブへ……そんな、ちょっと古い観光地のイメージがあった。
「今はまた人気出てるんだよ。東京から程よく遠いしね」
旅情は味わいたいけど不便なのは困る、確かにそんなわがままを叶えてくれる立地だった。
「バスも出てるけど、初めて来たんなら歩こうか」
と彼女が言うので、駅前のアーケード商店街に入った。そこからはいきなり坂だった。しかもかなり急で、無人の時間帯に自転車で駆け降りたらさぞかしスリリングだろう。山を下ればすぐに海、という忙しい土地のようだ。店先で蒸気を上げる温泉まんじゅうやぴかぴかの干物を見ながら、僕は「ほんとに手ぶらでよかったのかな」と言った。ご挨拶に行くんだから何か手土産を、と好物を訊いても、彼女は「いらない、持ってこないで」と拒否した。
「うん。あのね、この前言いそびれてたんだけどね、お母さん、もうとっくに死んでるから」
「え」
「ちゃんと説明してなくてごめんね」
珍しくしおれたような表情になり、惚れた弱みしかない僕は即座に「いいよそんなの!」とフォローする。
「えっと、じゃあ、お墓参りってことかな、でも、それならそれでお供え的な何かを持ってきたのに」
「ううん、お墓ってわけでもないから。行けばわかるよ」
また謎めいた発言だったが、行けばわかるんならまあいいや、と自分を納得させた。初めて歩く熱海の街は「敢えてのレトロ」じゃない、自然な味わいが残っていた。おしゃれや映えで語られる「エモ」とは違う、ここに根ざした生活の歴史を感じ、僕は早くも熱海を好きになり始めていた。下り坂の途中から見えた海は山に向かって傾きかけた陽射しをたっぷりと受け、まばゆく跳ね返す。新幹線で一時間もかからないのに、東京より明らかに空気が澄んでいた。ここでは光が濁らずに遠くまで伸びていける。
「熱海銀座」という屋根のない商店街を抜けて海辺まで下り切ると、今度は海岸沿いを進んだ。遊歩道には屋台が並び、あちこちでパイプが組まれて何やら大がかりな設置作業が進んでいる。
「きょう、何かあるの?」
「夜、花火大会があるんだよ。熱海はしょっちゅうやってる」
「へえ」
暖かい日だったのでうっすら汗をかきながら、僕は「お母さんのことだけど」と話しかけた。
「やっぱり、お母さんも人魚なの?」
「いいことを訊いてくれました」
「はあ」
「お母さんももちろん人魚、お父さんは、不倫して出てっちゃったの。……てことは、わかるよね?」
「わかる、とは?」
「童話の人魚姫、知ってるでしょ?」
王子さまに恋した人魚姫は魔法の力で人間になったものの、恋は叶わず、王子を殺して生きるか泡になって消えるかの二択を迫られた結果後者を選び……てことは?
「あの、じゃあ、お母さんは」
「まあそういうこと」
彼女はあっさり答えた。
「で、わたしもそうだから。仮に結婚しても、あなたが心変わりしたら、殺すか死ぬかしかないの。それが人魚の掟だからね」
「理不尽すぎない?」
「人生ってそういうものだよ。元彼もその前の彼も、そんな重いのは背負えないって逃げた。しょうがないよね」
この女やべえと思われただけのような気がするが、何も言わなかった。彼女の話を否定すれば、彼女が傷ついてしまうと思った。
「お母さんは、あそこにいるの」
彼女は山のふもとに見えるロープウェイを指差した。
「秘宝館、わかる?」
「行ったことはないけど」
昔ながらの温泉地にあるB級エロ施設、という認識だった。よく見るとロープウェイの乗り場に独特なフォントで「秘宝館」と大きな看板が出ている。お子さんにはどう説明しているんだろう。
「建物の屋根のところに人魚の像があるんだけど、それはうちのお母さんをモデルに、お父さんが作ったの。まあ、だから、お墓ではないけど、一応ね」
こういう時どんな顔すればいいかわからないの……という某アニメの台詞が頭をよぎる。今だよ今。でも乗りかかった船というか、彼女の主張を最後まで確かめたいと思った。それで、僕も逃げたくなったら正直にごめんなさいと言うしかない。秘宝館とロープウェイ往復がセットになった券を買い、赤いゴンドラで山の中腹までショートカットする。町が遠ざかり、海がどんどん広がっていく。先月の間抜けなプロポーズを懐かしく思い出した。僕は彼女が好きだった。でも、死ぬまで好きかなんてわからないし、死ぬほど好きか、死んでもいいほど好きかと訊かれたら自信はない。人魚の掟は過酷すぎる。
あっという間に山頂駅につき、「あいじょう岬」という誰がつけたかわからない展望台から太平洋を見下ろしていると「早くしないと閉まるよ、五時までなんだから」と急かされた。
秘宝館の入り口には「ああ……」というフォルムの亀の像と、青い髪の人魚の人形があった。岩場を模したセットで竪琴を持っていて、なかなか出来がいい。ただ、顔立ちがどう考えても西洋系だった。
「……お母さんにあんまり似てないんだね」
「違う違う、これじゃないよ。屋根って言ったじゃん」
「複数いるとは思わなくて。屋根の人魚っていうのはどこから見るの?」
「山側だから、外から」
「え、ひょっとして中入らなくてもいいやつ?」
「まあまあ、せっかくだから。今、秘宝館は日本にここしかないんだよ」
別にありがたみは感じないし、それならもっとゆっくり海を眺めたかったのに。僕の不満をいなすように彼女はぽんぽんと肩を叩く。
内部は結構にぎわっていた。男だらけだろうと思いきや女性客もちらほらいて、夫婦やカップルらしい男女も楽しそうに春画を見ている。とりあえず、悪目立ちせずにすみそうなのでほっとした。
展示自体は予想どおりというか、アダルトグッズやら、なまめかしい人形やら、いい年の大人が本気でかぶりついて見るようなものじゃなかった。
「お、これ、見ろよ」
壁の覗き穴に目を近づけるとちょっとしたアダルト映像が見られるという仕掛けの小部屋で、大学生くらいの男が歓声を上げる。
「お前の元カノに激似じゃね」
「まじ? 見せて……こんなに乳ねーわ」
「うわ、ひど」
「だって別れたし」
別れたから、当人がここにいないから、何を言ってもいいわけじゃないだろう。下衆な会話を聞きたくなかったので足早に通り過ぎようとしたら、彼女に引き止められた。
「どこ行くの」
「いや、ここはいいかなって」
「だめ」
彼女は両手で僕の腕にしがみつき、真顔で訴えた。
「ちゃんと見て」
その剣幕に押され、僕は渋々覗き穴を順に見ていった。黒背景の空間でナース服をはだけてくれるとかその程度で、何とも思わない。背後に立つ彼女の、監視するような視線を感じながら壁に沿って覗き穴に片目を寄せる。
ある穴の前で、僕はかがみ込んだまま動けなくなった。
身体をくねらせて裸を見せつける女の人が、彼女にそっくりだったから。首から下に関しては比較できないが、顔は、髪型やメイクの時代差を考えても瓜ふたつと言っていいレベルだった。他人の空似ーーいや、違う。他人じゃない。
短く粗いムービーを何度か繰り返し見ると、僕はそっと穴から離れ「見たよ」と言った。彼女は「そう、じゃあ行こっか」と頷く。いつもの軽快な口調だった。そこからは何ということもなく、ハンドルを回して風を起こし、マリリン・モンロー(っぽい人形)のスカートをめくったり、ラブドールの精巧さに驚いたりして、それなりに楽しんだ。
外に出て振り返ると、屋根の上に人魚が横たわっていた。入り口にいたものより古ぼけてはいたが、それが却ってなまめかしかった。胸は丸出しだし、下半身は魚というより網タイツを穿いているみたいに脚のラインがちゃんとある。顔はやっぱり洋風だった。
「……やっぱり、似てないよ」
彼女は何も言わなかった。あいじょう岬に戻ると、僕はもう一度言った。
「結婚しませんか」
海をバックに、こんな名前のところで、またもやベタベタのシチュエーションだった。でも僕は前みたいにあれこれ迷わなかった。それが、彼女の告白に対する答えにもなると思ったから。
あの映像の女性が、彼女のお母さんに違いない。どういう事情かわからないが裸を見せる仕事をしていて、夫に捨てられ、この世を去った。彼女に求婚した元彼たちは、彼女のそんな生い立ちを知ると離れていった。重くて背負えない、と。もちろん、彼らにだって彼らの事情や言い分がある。人生って何て理不尽なんだろう。でも、その理不尽さが僕たちを出会わせてくれた。
彼女は僕にありのままを打ち明けられず、結果「人魚」という一見突拍子もないワードが飛び出した。すべては僕の推測で、ちゃんと話を聞かせてもらわなければならない。でも、それより今は彼女に伝えたかった。
「人魚でも魚人でもいい。心変わりするかもしれないのはお互いさまだろ? そういう不安にも、不安が現実になった時の修羅場にも、一緒に向き合っていきたい」
もう、太陽は見えなくなっていた。山の稜線からきょうの名残を惜しむように鮮やかなオレンジ色の夕焼けが覗いていた。
ありがとう、と彼女が笑う。
彼女は、ロープウェイの山麓駅すぐのホテルを予約していた。もし破局したらひとりで泊まるつもりだったらしい。大浴場で温泉に浸かりながら、頑張ってよかったと心底思った。部屋のバルコニーからは海と熱海の夜景が見えた。丸い月が水平線上に昇り、暗い海に輝く道を伸ばす。その夜の花火は、今まで見てきた中でいちばんきれいだった。もちろん僕が浮かれているせいもあるけれど、やっぱり空気がきれいなのだと思う。立て続けに打ち上がる火花が山々に反響してどぱぁんと派手な音を立て、色とりどりの光の余韻は闇の中で長いことさざめいて僕たちを楽しませてくれた。
「人魚も海の中で見とれてるかも」
と僕が言うと、彼女は「さっきあそこに顔出してたよ」と月の道を指差した。水飛沫が上がったように見えたけど、気のせいだろう。花火が終わる頃にはすっかり身体が冷えてしまい、売店で買ったウイスキーをお湯割りで飲んでいると今度は早々に酔っ払った。ふらふらベッドに倒れ込み、目を閉じてすぐ眠りに落ちる。
ふと目を開けると、枕元の照明だけがほのかに点っていた。彼女は隣のベッドに腰掛けている。
「……ごめん、寝てた」
「ううん、もう一時前だしそのまま寝てなよ。わたし、お風呂入ってくるね」
「まだ開いてるんだ」
「一時半までだって」
僕も行こうかな、とちょっと迷ったが、まだまだ睡魔が強く、断念した。大浴場の露天風呂からも満月は見えるだろうか。この時間なら誰もいなくて独占できるかもしれない。
月明かりの下、広い湯船でこっそり人魚の姿に戻り、尾びれでぱしゃんと湯を跳ねさせて遊ぶ彼女を想像しながら、再び目を閉じた。
〈了〉