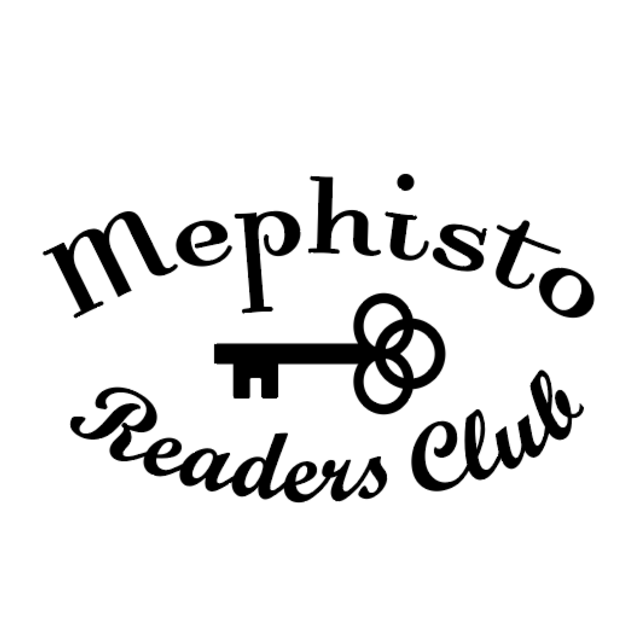『ゾンビがいた季節』(2024年4月頃発売予定) 須藤古都離
文字数 13,656文字
メフィスト賞を満場一致で受賞した
須藤古都離さんの第3作、『ゾンビがいた季節』
冒頭部分を『無限の月』の発売に合わせて先行公開!
「さっさと中に入れ! 死にたいのか!」
トムはさっき出会ったばかりの女の背中を思いっきり突き飛ばした。彼女は叫び声をあげながら、真っ暗闇の中に転げ落ちた。多少の怪我をしただろうが、知ったことではない。トムも彼女に続いて地下の階段を急いで降りて、すぐに扉を閉めようとした。懐中電灯を探す暇なんてなかったので、地下シェルターの中は真っ暗で何も見えなかった。だが、下まで降りれば手探りで電気のスイッチを探せる。
なによりもまず、この扉を閉めなくてはならない。
奴らが入ってくる前に。
鉛の扉は重く、閉めると息が詰まった。すぐに掛け金をかけるとやっと一息ついた。
扉の向こう側を奴らが叩く音が聞こえて、心臓が恐怖で縮む思いだった。耳を澄ませば、複数の足音と呻き声が聞こえる。
とにかく、ここにいれば安全だ。
核攻撃にも耐えられるように作られた地下シェルターなのだから。
そう思おうとしたが、奴らが動く音が聞こえる限り、安心はできない。
「大丈夫か?」下で泣き続けている女に声をかけながら、ゆっくりと階段を降りた。彼女は会話をできる状態ではなかった。
階段の下まで降りると、トムは女を無視して壁伝いに歩き、スイッチをつけた。パッと部屋が明るくなると、少しだけ安心した。明かりが点くまでは、もしかしたら暗がりに奴らが潜んでいるんじゃないかと不安だった。
シェルターに入るのは一年ぶりだったが、覚えている通りだった。コンクリートが打ちっぱなしの四十平米。殺風景だが非常食も水分も十分に備蓄してある。もともと家族三人で避難する想定で作った部屋なのだ、二人なら半年は生きていけるだろう。
「ほら、もう大丈夫だ。何が何だか分からんが、とにかくここには奴らはいない。助けが来るまで待ってればいいだけだ」
トムは床にしゃがみ込んでいる女に近づくと、手を差し伸べて立たせた。
「さっきは無理やり突き飛ばして済まなかった。君があのまま突っ立ってたら、二人とも死んでただろうからな。悪く思わないでくれ」
女は涙と鼻水が垂れたままの顔で頷いた。
「怪我はないか?」
女は同じように頷く。
女の泣き声は苦手だ、イライラする。トムは彼女を泣き止ませようと優しく接した。
「大丈夫だ。ここは核シェルターだから外からは開けられない。それに見て分かる通り、ここにいるのは二人だけだ」
「でも、オショネシーさん……」
「トムで良いよ」
「トム、私、こんなに怖い思いをしたのは初めてです。なんで皆、私たちを襲って来たんですか?」
「さっぱり分からん」
「この町はあんな人たちばっかりなんですか?」
「馬鹿なことを言うなよ。普通の田舎者だよ。馬鹿で下品な連中ばかりだが、人を襲ったりはしない。さっきのは、普段から仲良くしてる奴らだ。それに……、俺の妻と娘も一緒だった」
「じゃあ狂犬病か何かですか?」
「いや、狂犬病なんかじゃない。顔色も動きもおかしかったから、何かの病気かもしれないが、普通の病気じゃない。見ただろ? あいつら……、人を食ってやがった」
トムはそう言いながら、つい先ほど目の当たりにした光景を思い出した。
新作の打ち合わせがしたいとダンから連絡があったが、ブロンズドーム・エージェンシーが寄こしたのは仕事のことなど何もしらない全くの素人だった。話にならないとダンに文句を言おうと思ったが、頭を悩ませる暇すらなかった。
突然外から聞こえた叫び声に驚いて、窓の外を見ると阿鼻叫喚の地獄絵図だった。
そこにいるのはいつもの顔なじみだった。だが、まるで腐った死体のように身体はボロボロで、顔色は真っ青だった。
ガソリンスタンドを経営しているレジーがダイナーの主人のバズに組みついたと思ったら、彼の腕を引きちぎって貪り食った。その後ろではシャロンが倒れており、その上にアリスが馬乗りになって彼女の臓物を引きずり出していた。
町の住人が殺しあっていた。恐怖で凍り付いたトムだったが、その後ろからブロンズドームの女が窓を覗き込むと叫び声をあげた。
その声が奴らの注意を引き付けたのか、化け物染みた顔が一斉にこちらに向けられた。
逃げなきゃヤバいと思って彼女の手を引いて、裏口に回った。裏庭から出て、車で逃げようと思ったのだが、裏口はさらに酷い状況だった。地面に寝ころんでいるエリーの腹にメグが口を当てていた。エリーが小さい頃には、お腹に口を当ててブーっと息を吐き出す遊びをよくしていたものだ。だが、さっきのはそうではなかった。裏の扉を開けたトムに気が付いたメグが顔をあげると、彼女の口からは血が滴っていた。
そしてメグは新しい獲物を見るような視線をトムに浴びせ、獣のような呻き声を漏らした。
そうして逃げ道を失ったトムは、女と一緒に家の地下シェルターに逃げ込んだのだ。
「皆、化け物みたいになっちまった」
女は再び泣き始めた。
無理もない。疲れるまで泣かせておこう。
「大丈夫、いつか助けが来る」
トムは自分に言い聞かせるように呟いた。だが、娘を貪り食う妻の姿が目に焼き付いて離れなかった。
助けなんて、本当に来るのだろうか……。
*******
「私は先月ベトナムから帰って来たばかりです」
アメリカ中西部の田舎町であるモーセットの上空を低空飛行しながら、パイロットが話しかけた。
「まさに地獄かという光景でした」
プロペラのローター音が鳴り響き、周囲の木々が揺れているのが見える。真昼の太陽の下、それ以外に動くものは何も見えない。
「それはご苦労だったな。私も丁度先週帰って来たところだ」ホフマンが町の目抜き通りに転がる何十人もの死体を目視しながら答えた。
「死体の山だって見慣れましたし、無抵抗の女子供を撃つ兵士を見ても何とも思いません。それが戦争ですから。ですが、ホフマン大佐、この町の状況は……理解を超えています」パイロットの声は明らかに動揺していた。だが、操縦桿を握る腕がブレることはない。
「だろうな。私だってこんなものを見るのは初めてだ」
モーセットは人口百人にも満たない、町と呼ぶことすら躊躇われるような僻地だ。何もない荒れ地を真っすぐ抜ける幹線道路から奥まった地で、ガスが足りなくなった旅人が時折立ち寄るだけの場所だ。もともとゴーストタウンと呼ぶのに相応しい様相だが、今ではその表現では生ぬるい。まさに地獄と言える。
「私は隣のフォグノーの出身です」パイロットが躊躇いがちに言った。
「モーセットに住んでいる友人も何人かいたので、何度も来たことがあります。この町は覚えている通りで、何一つ変わっていないのに……。これは、疫病か何かでしょうか?」
「私は医者でも科学者でもないが、これは疫病なんかじゃないだろうな。疫病ってのは高熱が出たり、体中の穴という穴から血が出たりする。だが、決して四肢がバラバラになるなんてことはない」ホフマンは双眼鏡を使って道路に転がっている死体を観察しながら言った。
「でも、人が殺しあった後でもないですよね……」
「少なくとも銃や刃物での戦闘ではない。あんな風に体が四散しているってことは爆弾か、それに近い衝撃を受けているはずだ。だが、建物にも道路にも損害が見当たらない。まるで……」体の内側から爆発したか、もしくはウィンチで引き裂かれたみたいだ。ホフマンはそう言おうとして口を噤んだ。余りにも常軌を逸したコメントを部下に聞かれたくなかった。
「局地的な災害とも考えられません。一体何が起きたんでしょうか? ホフマン大佐、何か聞いてますか?」
パイロットに伝えるかどうか、ホフマンは躊躇した。だが自分が話さなくても、すぐに目撃することになるかもしれないのだ。隠すのは得策ではない。
「この町の住人は、正気を失っている。尋常ではない暴力と狂気のモンスターと化したのだ。身体は死人のように腐り、理性ではなく欲望のままに動く。原因は分からないが、町中が怪物の巣窟になった。町を封鎖しているから外には被害はないが、原因を探らないことには今後どうなるか分からん」
「それってまるで……」
「ああ。今、モーセットはゾンビの町だと思っていい」
町は静まり返っていた。見えるのは死体ばかりで、ゾンビはおろか、生きているものなど見当たらない。
「生存者がいた場合、救助しますか?」
「いや、我々の任務はあくまで偵察だ。救援活動をしに来たわけじゃない」
ホフマンの返答を聞くと、パイロットは黙り込んだ。
ふと、ホフマンの目が通りに面した壁の落書きに引き寄せられた。
〈汝、隣人のチンコを愛せ〉
もともとは〈汝、隣人を愛せ〉、という聖書からの引用だったのだろう。その上から強引に〈のチンコ〉と書き足されている。それは死体でいっぱいの町の中でも何故か目立った。
理解できる範囲の異常。都会なら何でもない落書きの一つにすぎないが、小さな町でこんな落書きが許されるわけがない。この落書きは不思議な印象をホフマンに残したが、今は落書きのことを考えている暇などない。
「クソ! ああ、なんてことだ……」パイロットが声を漏らした。
「どうした?」
「今、そこに見えたのはバズ・ホワイトでした」
「知り合いか?あれが誰だか分かったのか?」
「はい。高校の同級生でした。ハッキリ見えたわけでもないのに、なんでそう思ったのか自分でも不思議です。でも、見間違いではないと思います。あいつと、目が合った気がしました……」
「そうか、それは残念だった」ホフマンは道に転がっている上半身のみの死体を見ながら言った。下半身が見当たらないだけでなく、顔にも大きな穴が開いていた。鉄パイプが貫いたような、酷い状態だった。上空から身元確認ができるとは思えなかったが、疑ってもしょうがない。
「仲が良かったわけではありませんでした。喧嘩っ早い奴だったので、ろくな死に方をしないだろうとは思ってましたが、こんなことになるなんて……」パイロットは口を噤んだ。
ヘリはゆっくりと進んでいたが、すぐに町の反対側にたどり着いてしまった。
「フォグノーまで引き返しますか?」
「ああ、そうしてくれ。一旦戻ろう」
ヘリがぐるっと大回りして町の中心にある教会に達するかという時、地面を走る三つの影が見えた。それは三人の女の子だった。
「ホフマン大佐!」
「ああ、見えた。生存者がいたとはな。高度を下げろ!」
「ですが……」
「良いから下げろ! あの子たちは必死に隠れていたに違いない。今助けなければ、」
パイロットは命令に従ってヘリの高度を下げた。だが、女の子たちの異常な行動に気が付くと、慌ててヘリを急上昇させた。命令に違反するつもりなどなかったが、それでも恐怖に勝てなかった。
「クソッタレ!」ホフマンは思わず罵った。
「すみません、でもあれじゃ、まるで……」
「いや、良い判断だ。あれは助けを求めてなどいなかった」
ヘリの下に現れた女の子たちは、道路に落ちていた死体を拾い口元に持っていくと、まるでピザでも食べるように貪りついた。
「畜生! この町はもう終わりだ。生存者はいない。この町で生きていられるはずがない」
「あの女の子たち、大人の身体を持ち上げて食べましたよね……」
「ああ、俺も見た。間違いない。まるでぬいぐるみを持ち上げるみたいに楽々と摑みやがった。あれは化け物だ」
ホフマンは戦地で怯えたことなどなかった。ノルマンディーを生き残ったのだ、怖いものなど何もなかった。だが、腐肉に齧りつく女の子たちを見た時には、全身が凍り付く思いがした。
「あの不気味な死体の謎も分かったな。子供でもあの馬鹿力だ。大人のゾンビだったら、人間を引き裂くことも可能だろう」
今まで対峙したことのない恐怖がそこにあった。どんなに戦況が厳しくても、敵が残酷であっても、相手はいつだって同じ人間だった。ベトナムのゲリラ兵も恐ろしかったが、それでもあいつらは人間だった。
だが、今回は違う。人間の姿をした、何か別の獰猛で貪欲な獣だ。
ホフマンは身体の震えを止められなかった。
正体の分からないものとどう戦えばいい?
この町に広まった謎の現象の原因を突き止めるために、一体でも生け捕りにしなければいけない。スタインバーグ博士はそう言ったが、そんな悠長なことは言っていられない。
もし、あいつらがこの町から出てしまったら?
人々がどんどん化け物に変わってしまったら?
そんなことがあれば、手が付けられなくなるに違いない。
だが、今ならまだ間に合う。この町を焼き尽くせば、それで決着が着くのだ。
原因が知りたければ、焼け野原の灰を調べてくれと言う他ない。
私には、この国を守る使命がある。
たとえ町を一つ消してしまうことになったとしても、国を守るためには仕方ないのだ。
「ホフマンだ。レディング、聞こえるか?」手汗が酷く、トランシーバーを落とさないように強く握った。
「プランCだ。準備でき次第連絡しろ」ホフマンは冷静に聞こえるように、力強く言った。恐怖や困惑を悟られてはいけない。
「そうだ。モーセットを爆撃しろ。ネズミ一匹たりとも逃すな」
レディングが型通りの反論をするのを聞いて、ホフマンは怒鳴り声をあげた。
「プロトコルだと? 俺に向かって知った口を利くんじゃない! そんなことに構ってられるか! 今は大統領の判断なんて待てる状態じゃないんだ! とにかく俺の命令を聞け! それが気に入らなければ、後で軍法会議にでも引き出せばいいだろう。分かったら、クソッタレプロトコルはてめえのケツの穴に突っ込んで、さっさと行動しろ!」
レディングがしぶしぶ命令を受け入れたのを確認すると、ホフマンはため息をついた。
信仰はとうに捨てたはずだった。だが、神に祈らずにはいられなかった。
ホフマンにとって爆撃は日常だった。どこにいるか分からない敵は、徹底的に叩くしかない。だが、それは常に国外のことだった。破壊されるのは自分たちの町ではない、死んでいくのは同胞ではない。
モーセット爆撃を隣町のフォグノーで見届けたホフマンの胸中は穏やかではなかった。モーセットの混乱はこれで収まったはずだ。道路の封鎖も迅速に行い、報道の統制もとれている。モーセットの周囲は一面の荒野なので、ゾンビが隠れる場所なんてない。
だが、心が晴れることはなかった。
これで終わりだとはどうしても思えなかった。
そもそも何故モーセットの住人たちがゾンビと化したのか、それが分からない限り、安心などできない。
もし、アメリカの別の町でも同じことが起きていたら。
そう考えただけで息が詰まる。そうなったら最後、アメリカは地獄になってしまう。
モーセットから立ち上る煙を眺めながら、ホフマンは事態の収束を願った。原因なんて分からなくてもいい。どれだけ責任を追及されようと、自分に汚名が着せられたとしても構わない。
これが最後であってくれ。こんな地獄はもう見たくない。
ホフマンはとにかくそう祈り続けた。
「ホフマン大佐!」後ろから叫び声が聞こえ、振り返るとレディングが青い顔をして立っていた。
「どうした?」
「ブロンズドーム・エージェンシーの者が至急、大佐と話したいとのことです」
「もう情報が漏れたのか? 畜生! 誰だ、口を割った奴は!」
「いえ、そうではないようです」
「じゃあなんだって言うんだ?」
「とんでもないことになりました……」
レディングは冷静な男だ。モーセットの惨状を見ても、落ち着いていられた稀有な人材だ。その彼が取り乱す様子を見て、ホフマンは最悪の事態が現実になったのだと悟った。
これは終わりではない、始まりに過ぎないのだ。
1 一九六八年冬~一九六九年夏
メグがガソリンスタンドのガラス戸を開けてドアベルが鳴ると、いつものようにテーブルを囲んでビールを飲んでいる男たちが振り向いた。
「みんなお揃いね。今日も抵抗集会なの?」
「まあね。俺たちは真のレジスタンスだから」ウィルが皮肉な笑みを浮かべた。
モーセットの町は新しい高速道路建設のために立ち退き要請を受けている。だが、それに従う者はいない。町を愛しているからではない。立ち退きの条件を少しでも良くするためだ。
「メグ! 良いところに来てくれた!」レジーが椅子から立ち上がり、嬉しそうに近寄って来る。何事かと思ったが、ラジオから聞こえてきたオルガンとベースのサウンドを聞いて納得した。一緒に踊れ、ということなのだ。
「インナ・ガッダ・ダ・ヴィダ、ハニー、俺が愛してるのが分からないのかい?」レジーが調子っぱずれに歌い出す。メグは仕方なく彼の手を取って踊り始めた。
一九六八年、アイアン・バタフライのセカンドアルバムは何よりもショッキングだった。もちろん、トムが出版社から受け取ったはずの印税を持ってどこかに消えてしまったことを除けばの話だが。
トムは優秀な作家であり、最悪の浪費家でもあった。家にいる時は良い人だったが、お金が入る度に、ふらりといなくなってしまう困った人でもあった。
大学で出会ったばかりの時は謙虚で優しい青年だった。他の粗暴な男たちとは違って、感受性豊かな作家志望だった。それまで体育会系の男とばかり付き合っていたメグだったが、詩情溢れる手紙をこっそり渡してくれるトムにいつの間にか心惹かれていた。
トムは夢想家で、卒業後にどんな仕事に就いてもすぐに解雇された。いつも文学について考えているばかりで、簡単な仕事さえろくにできない男だった。メグは彼を支えるために仕事を掛け持ちしなければならなかった。メグが化粧品の販売に出歩いている間、彼は白昼夢をみるように狭い家でボーっとして、彼女がダイナーでウェイトレスをする頃、彼はタイプライターを叩き始める。
だが娘のエリーを妊娠すると、そんな生活も難しくなってきた。トムも作家の夢を諦めようかと思い始めた。そんな時に彼の書いた短編小説『夜の闇こそ我が歌声』が「テイルズ・フロム・ザ・ダークネス」誌に掲載され、少しばかりだが収入の足しになったのだ。
エリーが一歳になる頃には、近くのコミュニティ・カレッジで英語教師をしながら作品を書いていた。だが、彼が情熱を傾ける純文学的作品は全く評価されず、雑誌に掲載されるのは、たまに息抜きで書く娯楽小説のみだった。生活は苦しいままだった。
そんな時にトムはブロンズドーム・エージェンシーのダン・ウェイクマンに出会った。彼のアドバイスで書いたハードボイルド小説、『悪人の道楽』がトリプルデイ出版に売れ、今までとは桁違いの収入になった。カジノを舞台にしたノワール小説だった『悪人の道楽』は、映画化もされ、シリーズは新刊を出す度にミリオンセラーとなった。
彼は教職を辞め、故郷のモーセットに家を買うことを決めた。故郷に錦を飾る彼の姿は誇らしげで、メグは彼を支えてきて良かったと心から思った。
だが取材のためカジノに出向き、派手な街に入り浸るようになると、彼は変わっていった。ギャンブルにのめり込み、印税が入っても借金の返済で消えてしまう。
さらに彼の尊大な態度は町の住人から煙たがられた。トムは幼少期に周りから軽く見られていた。彼はそのことを根に持っていたようで、ことあるごとに自分を大きく見せようとした。
レジーが新車を買うと、それよりも高級な車を買った。カラーテレビを町で最初に買ったのもトムだった。一番顰蹙を買ったのはエアコンを買った時だった。クーパー神父が教会にエアコンを置こうと住人たちに持ちかけ、皆で資金を出し合ったのだが、トムはそれよりも先に自分の家に取り付けたのだ。
派手なサンダーバードを乗り回し、周りを見下すような言動を繰り返していたトムだったが、『悪人』シリーズの四作目にモーセットをモデルにした田舎町を出したことが、メグには信じられなかった。あろうことかトムは住人それぞれをモチーフとしたキャラを登場させ、馬鹿にしたのだ。
もちろん、町の住人以外にはそれは分からなかったはずだが、余りにも露骨な書き方だった。レジーに似せたキャラは守銭奴、ウィルは好色に描かれていた。最悪だったのはクーパー神父で、小学校で大便を漏らしたエピソードを暴露されていた。メグは恥知らずの夫に代わって町の皆に謝って回った。トムの態度に皆は腹を立てていたが、不思議なことにそれでも彼はモーセットの町に認められていた。トムが有名人だったからではない、モーセットの町が変人に優しかったのだ。
トムに連れられてモーセットに初めて来た時には、奇妙な町だと思った。隣町からも距離があるからなのか、誰も彼もが一癖ある住民ばかりだった。最初こそ戸惑いを覚えたものの、メグはいつの間にかモーセットの町が好きになっていた。大きな町と違って洗練されていないし、不便なところはあるが、居心地が良かった。
「オー、一緒に来てくれないか?」レジーの歌は続く。彼らはいつでもこんな調子だ。「俺の手を取って、一緒に歩いてくれないか?」
ガソリンスタンドのオーナーのレジー、ダイナーを早々と店じまいにしたバズ、それにいつもは販売の仕事で外に出ているウィルもいた。
曲が終わってレジーの踊りから解放されると、メグはバズの隣に座った。
「ほら、踊ってくれたお礼だよ」レジーは冷蔵庫からビールを取り出してメグの前に置くと、ウィンクをした。
「ありがとう。私で良ければ、いつでも踊りの相手になるわよ」
「メグ、次は俺と踊ってくれよ」ウィルがビール瓶を前に差し出したのに合わせて、メグが瓶を軽くぶつけて乾杯の合図をした。
「良いわよ、このビールが終わったらね。ウィルは久しぶりじゃない? 景気はどう?」
「ああ、さっき帰って来たばかりだよ。景気はまあ、いつもと変わらないかな」
「ところで、トムがどこにいるか、誰か知らない?」メグが訊ねると、三人とも渋い表情をした。
「いや、どこにいるかは知らんな。でも今朝うちで満タンにしてったから、今頃はリノにでもいるかも」レジーが言うと、皆がメグを憐れむように見た。
「そうよね、やっぱり。聞くまでもないよね」メグがため息をつく。
「あいつは本当に酷い奴だよ。まぁ、突然金持ちになったから、人が変わっちまったんだな。君みたいな良い女を放っておくなんて、本当に許せない野郎さ」
「ありがとう、レジー。ギャンブルの癖がなければ良い人なんだけどね」メグの言葉を聞くと三人が一斉に笑った。
「いやいや、あいつはギャンブルがなくても問題が山積みさ。あいつがいくら金持ちだからといって、君がいつまでもトムに愛想をつかさないのはモーセットで最大の謎だよ」
「そう言わないでよ、ウィル。あの人はあれで良いところがあるのよ」
「どうかな。トムがした良いことなんて、君をモーセットに連れて来てくれたことくらいのもんだよ」バズが鼻で笑って言った。
彼らは口を開けばトムを悪く言うが、それでも普段からトムと付き合ってくれていた。トムも自分が嫌われていることなどお構いなしで、彼らの輪に入っていく。それがメグには不思議でならなかった。トムも町にいる時は彼らと一緒にこのガソリンスタンドでラジオを聞きながらビールを飲むのだ。夕方からビールを飲むための、名ばかりの抵抗集会である。
「なぁ、トムのことなんだけどさぁ。君が金を管理するわけにはいかないのかい? あいつは金が入ったらすぐにカジノで使い切っちまうからさ」レジーが毛の少なくなってきた頭をかいた。
「それができれば一番なんだけどね。エージェントのダンにも相談したけど、やっぱりトムが認めないからダメなのよ」
「そうか。なんとかならないもんかね。このままじゃ君とエリーが不憫だよ」
「本当にそうだ」バズがレジーに相槌を打つ。
「あいつは一度痛い目に遭わないとダメだな」
「どうかしら。家に帰って来る度に『もうギャンブルには手を出さない』なんて言うくらいだから。もう大人なんだし、簡単に性格は変えられないわよ」
ラジオの音楽が止まり、ニュース番組に変わると男たちは議論に熱を出し始めた。次期大統領に選ばれたニクソンがどうやって戦争を止めるつもりなのか、ロバート・ケネディの暗殺に関する陰謀論、ソ連に負けている宇宙進出と月の裏側を回ってくるというアポロ八号について。
メグは少しばかりの居心地の悪さを感じた。ビールを飲み終わると三人に声をかけてスタンドを後にした。
***
「力になれなくてすまんな」ダンは眉を顰めると、ポケットからハンカチを取り出して額の汗を拭いた。ブロンズドーム・エージェンシーの事務所は冷えていたので、メグはトレンチコートを脱げなかった。事務所の他の職員も同様で、建物の中なのに厚着をしている。それでもダンはワイシャツ一枚にネクタイをしているだけだ。そのワイシャツもお腹周りの肉でパンパンに膨れ上がっており、ボタンが今にもはじけ飛びそうだった。彼のシャツを見ると、メグはいつも決壊寸前のダムのような印象を受ける。
彼はエージェントとして優秀なだけでなく、人としても素晴らしい。トムはダンに会わなければ作家として成功していなかっただろう。優しく、ユーモアに溢れ、気さくな人だ。そんな彼の唯一の欠点は、甘いものに目がないことだった。事務所は彼のためにドーナツとコーヒーを切らすことがない。最初に出会った頃はすらりとした好青年だったが、会うたびに彼は体重を増やしていた。今では二重あごが首を隠してしまったし、かつては魅力的だった顔はシナモンロールのように油っぽく、まん丸になってしまった。
トムの『悪人』シリーズの成功を皮切りに、彼は人気作家を何人も抱えるようになった。小さかった事務所も大所帯になった。ブロンズドームの事務所が寒いのは冬だけではない。夏は夏でダンが冷房をガンガンに効かせるので冷蔵庫の中にいるような気分になる。職場が凍えるように寒くても、彼を慕う他の若いエージェントは離れようとしない。
「前にも言った通り、トムの了解を得ない限り、印税を君に渡すわけにはいかないんだよ。で、トムはあの通りの性格だから、了解するわけがない。それになぁ……」ダンはテーブルの上のドーナツに手を伸ばして一口頰張った。そのあとでメグにもドーナツを食べるように身振りで勧めたが、彼女は軽く断った。
「印税を渡したって言っても、大した額じゃない。もう何年も新作を書いてないからね。ちょこっと増刷しただけだよ。トムに困っているのは君だけじゃない。僕らも早く新作を書いて欲しいんだ。何度も言ってるんだが、全然書いてないみたいだからね」
ダンは早くも二個目のドーナツを摑んだ。
「映画化されたのだって、最初の一冊だけだ。もっと新作を書いて話題になれば、続編も作られるんだろうけどな。で、映画化が続けばシリーズもまた売れるようになる。そうやって売って、作って、また売って、そういうサイクルを繰り返さないと飽きられちゃうからね。文学を書いているんじゃない、娯楽小説だからね。読者を飽きさせたら終わりだよ」
「なんとか無理やり書かせられないかな?」
「無理やりって?」
「ホテルに監禁するとか、銃を突き付けて」
「冗談だろ?」
「私は本気よ。あなたがなんとかやってくれるなら、私は協力するから」
「勘弁してくれよ! そんなことできるわけないだろ?」
「でも彼が書いてくれないと、もう生活にも困っちゃうような状態なの。私が働けば良いだけなんだけどさ、彼は見栄っ張りだから。ちゃんと働かないくせに、私が働くのも嫌なんだって。『お前が働いたら、家が貧乏だと笑われちまう』なんて言うの。実際、貧乏なのに、分かってないのが問題なのよ」
「メグ、君が困っているのは分かる。でもトムの性格だと、無理強いしても書いてくれないだろうな。頑固な奴だから、書けと言えば言うほど書かなくなる」
「じゃあ、どうすれば良いの?」
「さあな。何かインスピレーションでも湧けば書く気になるのかな」
「彼のためにミューズになるような女の子でも用意しろってこと?」ダンの無責任な発言にメグは苛立った。未だに他人ごとなのだ。
「そうは言ってないだろ」
「彼のエージェントはあなたでしょ? 真剣に考えてよ」
「そうだな……、君には黙っておこうと思ってたんだけど、実はトムはもう『悪人』シリーズを書くつもりがないらしい。と言っても、新しいアイデアもない。俺がなにかを提案しても書く努力をしない。それで俺は聞いたんだ。『一体、お前はどうしたら書くつもりになるんだ?』って。そしたら、どう答えたと思う?」
ダンに聞かれて、さっぱり分からないというようにメグは肩を竦めた。
「『世界が終わる日が来たら書くかもな』って言ったんだ。悪いことは言わないけど、彼が書く気になるまでは、俺たちにできることはないよ」
「じゃあ、世界を終わらせれば良いのよ」
「は?」ダンはメグの言葉に眉を顰めた。
「世界が終わるって思わせれば良いのよ。核戦争が起きると思わせて、地下シェルターに彼を閉じ込めるの。そうしたら書くんじゃない?」
「本気じゃないよな?」
「私は本気よ。キューバ危機の時に、家の地下室を核シェルターに変えたの。あそこなら何か月でも籠ってられるし。監禁ってことじゃなくて、彼が勝手に勘違いしたってことに出来るんじゃない? 世界が終わる日が来れば書くんでしょ? それなら、世界の終わりを彼のために作ってあげればいいじゃない?」
ダンは黙ってドーナツを食べながらしばらく考え込んだ。
「確かに、それなら彼も書くかもしれないな。インスピレーションとしては、これ以上ないぐらいだろう。でも、やっぱり本気で騙すのは難しいかな。俺たちが『核戦争が始まる!』って騒いでも信じないだろう。オーソン・ウェルズじゃあるまいし。地下に籠るにしても、ラジオやテレビの報道を見て、町の他の人の反応を窺ってからだろう。一人の作家を騙すために、そんな大げさなことはできないよ」
「でもね、町の人は協力してくれるはずよ。みんなトムのことが嫌いだし、彼を騙すことができるなら、喜んで協力してくれると思う。彼が働けば、町の皆からの借金も返せるし」
「そうなのか、それは心強いな。うーん、でも核戦争を現実だと思わせるのはちょっと難しいな」
「じゃあ、どうやって世界の終わりだと思わせる? どうすれば彼が自分から地下室に逃げ込むかしら?」
「地下室、地下室。地下室に逃げ込む……」
ダンは椅子から立ち上がって部屋の中をぐるぐる歩き回った。彼が動くたびにキャビネットのガラス戸がカタカタ音を立てた。
「待て、良いアイデアを思い付いたぞ。君は『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』を観たかい?」
「ゾンビの映画? 噂には聞いたけど、怖いのは苦手だから」
「あの映画ではゾンビが町に溢れて、地下室に逃げ込む人がいるんだ。何が起こっているか分からない状態で、でも地下に逃げるしかない。あの状況を作り出せば良いんだ。町の人たちが手伝ってくれるなら、これは核戦争よりも騙すのが楽だろう。君が地下に誘導すればいいだろう」
「私は地下に誘導はできるけど、作品を書かせるのはちょっとね。彼が何か書いても、私にはそれが良いか悪いか分からないもの」
「俺が一緒に地下にいられれば良いんだが、他の仕事もあるから無理だしな。待てよ。今、事務所に若手の編集者がいるから、そいつに任せよう」
トムを騙す作戦を練るのは、いたずらをするようで楽しかった。
メグはいつの間にかダンと一緒になってドーナツを食べながら、いろいろと話し合った。
本気だとは言ったものの、メグはもちろん冗談のつもりだった。愚痴を聞いて欲しかっただけなのだ。トムが新作を書いてくれないと家の借金は大変なことになってしまう。だが、トムだって本当はそれを分かっているはずだ。彼が本気になるまで待つしかないか、と思いながらメグは帰路についた。
だが、トムに新作を書いてほしいと心から思っていたのはメグだけではなかった。ダンはこのメグとの秘密の計画を実行に移すべく別の人物に話した。面白いと思ったものを形にしなければ気が済まない性分こそ、ダンがエージェントとして優れている所以だった。
メグが部屋を出た後、ダンはすぐにエドガー・ブラッドに電話をかけた。エドガーはトムの『悪人の道楽』を映画化した映画監督だ。ゾンビ映画を作る気はないか、と言われたエドガーはすっかりその気になり、その日のうちに脚本を書き上げた。
【須藤古都離(スドウ・コトリ)プロフィール】
1987年、神奈川県生まれ。青山学院大学卒業。2022年、「ゴリラ裁判の日」で第64回メフィスト賞を受賞。
須藤古都離さんの第3作、『ゾンビがいた季節』
冒頭部分を『無限の月』の発売に合わせて先行公開!
「さっさと中に入れ! 死にたいのか!」
トムはさっき出会ったばかりの女の背中を思いっきり突き飛ばした。彼女は叫び声をあげながら、真っ暗闇の中に転げ落ちた。多少の怪我をしただろうが、知ったことではない。トムも彼女に続いて地下の階段を急いで降りて、すぐに扉を閉めようとした。懐中電灯を探す暇なんてなかったので、地下シェルターの中は真っ暗で何も見えなかった。だが、下まで降りれば手探りで電気のスイッチを探せる。
なによりもまず、この扉を閉めなくてはならない。
奴らが入ってくる前に。
鉛の扉は重く、閉めると息が詰まった。すぐに掛け金をかけるとやっと一息ついた。
扉の向こう側を奴らが叩く音が聞こえて、心臓が恐怖で縮む思いだった。耳を澄ませば、複数の足音と呻き声が聞こえる。
とにかく、ここにいれば安全だ。
核攻撃にも耐えられるように作られた地下シェルターなのだから。
そう思おうとしたが、奴らが動く音が聞こえる限り、安心はできない。
「大丈夫か?」下で泣き続けている女に声をかけながら、ゆっくりと階段を降りた。彼女は会話をできる状態ではなかった。
階段の下まで降りると、トムは女を無視して壁伝いに歩き、スイッチをつけた。パッと部屋が明るくなると、少しだけ安心した。明かりが点くまでは、もしかしたら暗がりに奴らが潜んでいるんじゃないかと不安だった。
シェルターに入るのは一年ぶりだったが、覚えている通りだった。コンクリートが打ちっぱなしの四十平米。殺風景だが非常食も水分も十分に備蓄してある。もともと家族三人で避難する想定で作った部屋なのだ、二人なら半年は生きていけるだろう。
「ほら、もう大丈夫だ。何が何だか分からんが、とにかくここには奴らはいない。助けが来るまで待ってればいいだけだ」
トムは床にしゃがみ込んでいる女に近づくと、手を差し伸べて立たせた。
「さっきは無理やり突き飛ばして済まなかった。君があのまま突っ立ってたら、二人とも死んでただろうからな。悪く思わないでくれ」
女は涙と鼻水が垂れたままの顔で頷いた。
「怪我はないか?」
女は同じように頷く。
女の泣き声は苦手だ、イライラする。トムは彼女を泣き止ませようと優しく接した。
「大丈夫だ。ここは核シェルターだから外からは開けられない。それに見て分かる通り、ここにいるのは二人だけだ」
「でも、オショネシーさん……」
「トムで良いよ」
「トム、私、こんなに怖い思いをしたのは初めてです。なんで皆、私たちを襲って来たんですか?」
「さっぱり分からん」
「この町はあんな人たちばっかりなんですか?」
「馬鹿なことを言うなよ。普通の田舎者だよ。馬鹿で下品な連中ばかりだが、人を襲ったりはしない。さっきのは、普段から仲良くしてる奴らだ。それに……、俺の妻と娘も一緒だった」
「じゃあ狂犬病か何かですか?」
「いや、狂犬病なんかじゃない。顔色も動きもおかしかったから、何かの病気かもしれないが、普通の病気じゃない。見ただろ? あいつら……、人を食ってやがった」
トムはそう言いながら、つい先ほど目の当たりにした光景を思い出した。
新作の打ち合わせがしたいとダンから連絡があったが、ブロンズドーム・エージェンシーが寄こしたのは仕事のことなど何もしらない全くの素人だった。話にならないとダンに文句を言おうと思ったが、頭を悩ませる暇すらなかった。
突然外から聞こえた叫び声に驚いて、窓の外を見ると阿鼻叫喚の地獄絵図だった。
そこにいるのはいつもの顔なじみだった。だが、まるで腐った死体のように身体はボロボロで、顔色は真っ青だった。
ガソリンスタンドを経営しているレジーがダイナーの主人のバズに組みついたと思ったら、彼の腕を引きちぎって貪り食った。その後ろではシャロンが倒れており、その上にアリスが馬乗りになって彼女の臓物を引きずり出していた。
町の住人が殺しあっていた。恐怖で凍り付いたトムだったが、その後ろからブロンズドームの女が窓を覗き込むと叫び声をあげた。
その声が奴らの注意を引き付けたのか、化け物染みた顔が一斉にこちらに向けられた。
逃げなきゃヤバいと思って彼女の手を引いて、裏口に回った。裏庭から出て、車で逃げようと思ったのだが、裏口はさらに酷い状況だった。地面に寝ころんでいるエリーの腹にメグが口を当てていた。エリーが小さい頃には、お腹に口を当ててブーっと息を吐き出す遊びをよくしていたものだ。だが、さっきのはそうではなかった。裏の扉を開けたトムに気が付いたメグが顔をあげると、彼女の口からは血が滴っていた。
そしてメグは新しい獲物を見るような視線をトムに浴びせ、獣のような呻き声を漏らした。
そうして逃げ道を失ったトムは、女と一緒に家の地下シェルターに逃げ込んだのだ。
「皆、化け物みたいになっちまった」
女は再び泣き始めた。
無理もない。疲れるまで泣かせておこう。
「大丈夫、いつか助けが来る」
トムは自分に言い聞かせるように呟いた。だが、娘を貪り食う妻の姿が目に焼き付いて離れなかった。
助けなんて、本当に来るのだろうか……。
*******
「私は先月ベトナムから帰って来たばかりです」
アメリカ中西部の田舎町であるモーセットの上空を低空飛行しながら、パイロットが話しかけた。
「まさに地獄かという光景でした」
プロペラのローター音が鳴り響き、周囲の木々が揺れているのが見える。真昼の太陽の下、それ以外に動くものは何も見えない。
「それはご苦労だったな。私も丁度先週帰って来たところだ」ホフマンが町の目抜き通りに転がる何十人もの死体を目視しながら答えた。
「死体の山だって見慣れましたし、無抵抗の女子供を撃つ兵士を見ても何とも思いません。それが戦争ですから。ですが、ホフマン大佐、この町の状況は……理解を超えています」パイロットの声は明らかに動揺していた。だが、操縦桿を握る腕がブレることはない。
「だろうな。私だってこんなものを見るのは初めてだ」
モーセットは人口百人にも満たない、町と呼ぶことすら躊躇われるような僻地だ。何もない荒れ地を真っすぐ抜ける幹線道路から奥まった地で、ガスが足りなくなった旅人が時折立ち寄るだけの場所だ。もともとゴーストタウンと呼ぶのに相応しい様相だが、今ではその表現では生ぬるい。まさに地獄と言える。
「私は隣のフォグノーの出身です」パイロットが躊躇いがちに言った。
「モーセットに住んでいる友人も何人かいたので、何度も来たことがあります。この町は覚えている通りで、何一つ変わっていないのに……。これは、疫病か何かでしょうか?」
「私は医者でも科学者でもないが、これは疫病なんかじゃないだろうな。疫病ってのは高熱が出たり、体中の穴という穴から血が出たりする。だが、決して四肢がバラバラになるなんてことはない」ホフマンは双眼鏡を使って道路に転がっている死体を観察しながら言った。
「でも、人が殺しあった後でもないですよね……」
「少なくとも銃や刃物での戦闘ではない。あんな風に体が四散しているってことは爆弾か、それに近い衝撃を受けているはずだ。だが、建物にも道路にも損害が見当たらない。まるで……」体の内側から爆発したか、もしくはウィンチで引き裂かれたみたいだ。ホフマンはそう言おうとして口を噤んだ。余りにも常軌を逸したコメントを部下に聞かれたくなかった。
「局地的な災害とも考えられません。一体何が起きたんでしょうか? ホフマン大佐、何か聞いてますか?」
パイロットに伝えるかどうか、ホフマンは躊躇した。だが自分が話さなくても、すぐに目撃することになるかもしれないのだ。隠すのは得策ではない。
「この町の住人は、正気を失っている。尋常ではない暴力と狂気のモンスターと化したのだ。身体は死人のように腐り、理性ではなく欲望のままに動く。原因は分からないが、町中が怪物の巣窟になった。町を封鎖しているから外には被害はないが、原因を探らないことには今後どうなるか分からん」
「それってまるで……」
「ああ。今、モーセットはゾンビの町だと思っていい」
町は静まり返っていた。見えるのは死体ばかりで、ゾンビはおろか、生きているものなど見当たらない。
「生存者がいた場合、救助しますか?」
「いや、我々の任務はあくまで偵察だ。救援活動をしに来たわけじゃない」
ホフマンの返答を聞くと、パイロットは黙り込んだ。
ふと、ホフマンの目が通りに面した壁の落書きに引き寄せられた。
〈汝、隣人のチンコを愛せ〉
もともとは〈汝、隣人を愛せ〉、という聖書からの引用だったのだろう。その上から強引に〈のチンコ〉と書き足されている。それは死体でいっぱいの町の中でも何故か目立った。
理解できる範囲の異常。都会なら何でもない落書きの一つにすぎないが、小さな町でこんな落書きが許されるわけがない。この落書きは不思議な印象をホフマンに残したが、今は落書きのことを考えている暇などない。
「クソ! ああ、なんてことだ……」パイロットが声を漏らした。
「どうした?」
「今、そこに見えたのはバズ・ホワイトでした」
「知り合いか?あれが誰だか分かったのか?」
「はい。高校の同級生でした。ハッキリ見えたわけでもないのに、なんでそう思ったのか自分でも不思議です。でも、見間違いではないと思います。あいつと、目が合った気がしました……」
「そうか、それは残念だった」ホフマンは道に転がっている上半身のみの死体を見ながら言った。下半身が見当たらないだけでなく、顔にも大きな穴が開いていた。鉄パイプが貫いたような、酷い状態だった。上空から身元確認ができるとは思えなかったが、疑ってもしょうがない。
「仲が良かったわけではありませんでした。喧嘩っ早い奴だったので、ろくな死に方をしないだろうとは思ってましたが、こんなことになるなんて……」パイロットは口を噤んだ。
ヘリはゆっくりと進んでいたが、すぐに町の反対側にたどり着いてしまった。
「フォグノーまで引き返しますか?」
「ああ、そうしてくれ。一旦戻ろう」
ヘリがぐるっと大回りして町の中心にある教会に達するかという時、地面を走る三つの影が見えた。それは三人の女の子だった。
「ホフマン大佐!」
「ああ、見えた。生存者がいたとはな。高度を下げろ!」
「ですが……」
「良いから下げろ! あの子たちは必死に隠れていたに違いない。今助けなければ、」
パイロットは命令に従ってヘリの高度を下げた。だが、女の子たちの異常な行動に気が付くと、慌ててヘリを急上昇させた。命令に違反するつもりなどなかったが、それでも恐怖に勝てなかった。
「クソッタレ!」ホフマンは思わず罵った。
「すみません、でもあれじゃ、まるで……」
「いや、良い判断だ。あれは助けを求めてなどいなかった」
ヘリの下に現れた女の子たちは、道路に落ちていた死体を拾い口元に持っていくと、まるでピザでも食べるように貪りついた。
「畜生! この町はもう終わりだ。生存者はいない。この町で生きていられるはずがない」
「あの女の子たち、大人の身体を持ち上げて食べましたよね……」
「ああ、俺も見た。間違いない。まるでぬいぐるみを持ち上げるみたいに楽々と摑みやがった。あれは化け物だ」
ホフマンは戦地で怯えたことなどなかった。ノルマンディーを生き残ったのだ、怖いものなど何もなかった。だが、腐肉に齧りつく女の子たちを見た時には、全身が凍り付く思いがした。
「あの不気味な死体の謎も分かったな。子供でもあの馬鹿力だ。大人のゾンビだったら、人間を引き裂くことも可能だろう」
今まで対峙したことのない恐怖がそこにあった。どんなに戦況が厳しくても、敵が残酷であっても、相手はいつだって同じ人間だった。ベトナムのゲリラ兵も恐ろしかったが、それでもあいつらは人間だった。
だが、今回は違う。人間の姿をした、何か別の獰猛で貪欲な獣だ。
ホフマンは身体の震えを止められなかった。
正体の分からないものとどう戦えばいい?
この町に広まった謎の現象の原因を突き止めるために、一体でも生け捕りにしなければいけない。スタインバーグ博士はそう言ったが、そんな悠長なことは言っていられない。
もし、あいつらがこの町から出てしまったら?
人々がどんどん化け物に変わってしまったら?
そんなことがあれば、手が付けられなくなるに違いない。
だが、今ならまだ間に合う。この町を焼き尽くせば、それで決着が着くのだ。
原因が知りたければ、焼け野原の灰を調べてくれと言う他ない。
私には、この国を守る使命がある。
たとえ町を一つ消してしまうことになったとしても、国を守るためには仕方ないのだ。
「ホフマンだ。レディング、聞こえるか?」手汗が酷く、トランシーバーを落とさないように強く握った。
「プランCだ。準備でき次第連絡しろ」ホフマンは冷静に聞こえるように、力強く言った。恐怖や困惑を悟られてはいけない。
「そうだ。モーセットを爆撃しろ。ネズミ一匹たりとも逃すな」
レディングが型通りの反論をするのを聞いて、ホフマンは怒鳴り声をあげた。
「プロトコルだと? 俺に向かって知った口を利くんじゃない! そんなことに構ってられるか! 今は大統領の判断なんて待てる状態じゃないんだ! とにかく俺の命令を聞け! それが気に入らなければ、後で軍法会議にでも引き出せばいいだろう。分かったら、クソッタレプロトコルはてめえのケツの穴に突っ込んで、さっさと行動しろ!」
レディングがしぶしぶ命令を受け入れたのを確認すると、ホフマンはため息をついた。
信仰はとうに捨てたはずだった。だが、神に祈らずにはいられなかった。
ホフマンにとって爆撃は日常だった。どこにいるか分からない敵は、徹底的に叩くしかない。だが、それは常に国外のことだった。破壊されるのは自分たちの町ではない、死んでいくのは同胞ではない。
モーセット爆撃を隣町のフォグノーで見届けたホフマンの胸中は穏やかではなかった。モーセットの混乱はこれで収まったはずだ。道路の封鎖も迅速に行い、報道の統制もとれている。モーセットの周囲は一面の荒野なので、ゾンビが隠れる場所なんてない。
だが、心が晴れることはなかった。
これで終わりだとはどうしても思えなかった。
そもそも何故モーセットの住人たちがゾンビと化したのか、それが分からない限り、安心などできない。
もし、アメリカの別の町でも同じことが起きていたら。
そう考えただけで息が詰まる。そうなったら最後、アメリカは地獄になってしまう。
モーセットから立ち上る煙を眺めながら、ホフマンは事態の収束を願った。原因なんて分からなくてもいい。どれだけ責任を追及されようと、自分に汚名が着せられたとしても構わない。
これが最後であってくれ。こんな地獄はもう見たくない。
ホフマンはとにかくそう祈り続けた。
「ホフマン大佐!」後ろから叫び声が聞こえ、振り返るとレディングが青い顔をして立っていた。
「どうした?」
「ブロンズドーム・エージェンシーの者が至急、大佐と話したいとのことです」
「もう情報が漏れたのか? 畜生! 誰だ、口を割った奴は!」
「いえ、そうではないようです」
「じゃあなんだって言うんだ?」
「とんでもないことになりました……」
レディングは冷静な男だ。モーセットの惨状を見ても、落ち着いていられた稀有な人材だ。その彼が取り乱す様子を見て、ホフマンは最悪の事態が現実になったのだと悟った。
これは終わりではない、始まりに過ぎないのだ。
1 一九六八年冬~一九六九年夏
メグがガソリンスタンドのガラス戸を開けてドアベルが鳴ると、いつものようにテーブルを囲んでビールを飲んでいる男たちが振り向いた。
「みんなお揃いね。今日も抵抗集会なの?」
「まあね。俺たちは真のレジスタンスだから」ウィルが皮肉な笑みを浮かべた。
モーセットの町は新しい高速道路建設のために立ち退き要請を受けている。だが、それに従う者はいない。町を愛しているからではない。立ち退きの条件を少しでも良くするためだ。
「メグ! 良いところに来てくれた!」レジーが椅子から立ち上がり、嬉しそうに近寄って来る。何事かと思ったが、ラジオから聞こえてきたオルガンとベースのサウンドを聞いて納得した。一緒に踊れ、ということなのだ。
「インナ・ガッダ・ダ・ヴィダ、ハニー、俺が愛してるのが分からないのかい?」レジーが調子っぱずれに歌い出す。メグは仕方なく彼の手を取って踊り始めた。
一九六八年、アイアン・バタフライのセカンドアルバムは何よりもショッキングだった。もちろん、トムが出版社から受け取ったはずの印税を持ってどこかに消えてしまったことを除けばの話だが。
トムは優秀な作家であり、最悪の浪費家でもあった。家にいる時は良い人だったが、お金が入る度に、ふらりといなくなってしまう困った人でもあった。
大学で出会ったばかりの時は謙虚で優しい青年だった。他の粗暴な男たちとは違って、感受性豊かな作家志望だった。それまで体育会系の男とばかり付き合っていたメグだったが、詩情溢れる手紙をこっそり渡してくれるトムにいつの間にか心惹かれていた。
トムは夢想家で、卒業後にどんな仕事に就いてもすぐに解雇された。いつも文学について考えているばかりで、簡単な仕事さえろくにできない男だった。メグは彼を支えるために仕事を掛け持ちしなければならなかった。メグが化粧品の販売に出歩いている間、彼は白昼夢をみるように狭い家でボーっとして、彼女がダイナーでウェイトレスをする頃、彼はタイプライターを叩き始める。
だが娘のエリーを妊娠すると、そんな生活も難しくなってきた。トムも作家の夢を諦めようかと思い始めた。そんな時に彼の書いた短編小説『夜の闇こそ我が歌声』が「テイルズ・フロム・ザ・ダークネス」誌に掲載され、少しばかりだが収入の足しになったのだ。
エリーが一歳になる頃には、近くのコミュニティ・カレッジで英語教師をしながら作品を書いていた。だが、彼が情熱を傾ける純文学的作品は全く評価されず、雑誌に掲載されるのは、たまに息抜きで書く娯楽小説のみだった。生活は苦しいままだった。
そんな時にトムはブロンズドーム・エージェンシーのダン・ウェイクマンに出会った。彼のアドバイスで書いたハードボイルド小説、『悪人の道楽』がトリプルデイ出版に売れ、今までとは桁違いの収入になった。カジノを舞台にしたノワール小説だった『悪人の道楽』は、映画化もされ、シリーズは新刊を出す度にミリオンセラーとなった。
彼は教職を辞め、故郷のモーセットに家を買うことを決めた。故郷に錦を飾る彼の姿は誇らしげで、メグは彼を支えてきて良かったと心から思った。
だが取材のためカジノに出向き、派手な街に入り浸るようになると、彼は変わっていった。ギャンブルにのめり込み、印税が入っても借金の返済で消えてしまう。
さらに彼の尊大な態度は町の住人から煙たがられた。トムは幼少期に周りから軽く見られていた。彼はそのことを根に持っていたようで、ことあるごとに自分を大きく見せようとした。
レジーが新車を買うと、それよりも高級な車を買った。カラーテレビを町で最初に買ったのもトムだった。一番顰蹙を買ったのはエアコンを買った時だった。クーパー神父が教会にエアコンを置こうと住人たちに持ちかけ、皆で資金を出し合ったのだが、トムはそれよりも先に自分の家に取り付けたのだ。
派手なサンダーバードを乗り回し、周りを見下すような言動を繰り返していたトムだったが、『悪人』シリーズの四作目にモーセットをモデルにした田舎町を出したことが、メグには信じられなかった。あろうことかトムは住人それぞれをモチーフとしたキャラを登場させ、馬鹿にしたのだ。
もちろん、町の住人以外にはそれは分からなかったはずだが、余りにも露骨な書き方だった。レジーに似せたキャラは守銭奴、ウィルは好色に描かれていた。最悪だったのはクーパー神父で、小学校で大便を漏らしたエピソードを暴露されていた。メグは恥知らずの夫に代わって町の皆に謝って回った。トムの態度に皆は腹を立てていたが、不思議なことにそれでも彼はモーセットの町に認められていた。トムが有名人だったからではない、モーセットの町が変人に優しかったのだ。
トムに連れられてモーセットに初めて来た時には、奇妙な町だと思った。隣町からも距離があるからなのか、誰も彼もが一癖ある住民ばかりだった。最初こそ戸惑いを覚えたものの、メグはいつの間にかモーセットの町が好きになっていた。大きな町と違って洗練されていないし、不便なところはあるが、居心地が良かった。
「オー、一緒に来てくれないか?」レジーの歌は続く。彼らはいつでもこんな調子だ。「俺の手を取って、一緒に歩いてくれないか?」
ガソリンスタンドのオーナーのレジー、ダイナーを早々と店じまいにしたバズ、それにいつもは販売の仕事で外に出ているウィルもいた。
曲が終わってレジーの踊りから解放されると、メグはバズの隣に座った。
「ほら、踊ってくれたお礼だよ」レジーは冷蔵庫からビールを取り出してメグの前に置くと、ウィンクをした。
「ありがとう。私で良ければ、いつでも踊りの相手になるわよ」
「メグ、次は俺と踊ってくれよ」ウィルがビール瓶を前に差し出したのに合わせて、メグが瓶を軽くぶつけて乾杯の合図をした。
「良いわよ、このビールが終わったらね。ウィルは久しぶりじゃない? 景気はどう?」
「ああ、さっき帰って来たばかりだよ。景気はまあ、いつもと変わらないかな」
「ところで、トムがどこにいるか、誰か知らない?」メグが訊ねると、三人とも渋い表情をした。
「いや、どこにいるかは知らんな。でも今朝うちで満タンにしてったから、今頃はリノにでもいるかも」レジーが言うと、皆がメグを憐れむように見た。
「そうよね、やっぱり。聞くまでもないよね」メグがため息をつく。
「あいつは本当に酷い奴だよ。まぁ、突然金持ちになったから、人が変わっちまったんだな。君みたいな良い女を放っておくなんて、本当に許せない野郎さ」
「ありがとう、レジー。ギャンブルの癖がなければ良い人なんだけどね」メグの言葉を聞くと三人が一斉に笑った。
「いやいや、あいつはギャンブルがなくても問題が山積みさ。あいつがいくら金持ちだからといって、君がいつまでもトムに愛想をつかさないのはモーセットで最大の謎だよ」
「そう言わないでよ、ウィル。あの人はあれで良いところがあるのよ」
「どうかな。トムがした良いことなんて、君をモーセットに連れて来てくれたことくらいのもんだよ」バズが鼻で笑って言った。
彼らは口を開けばトムを悪く言うが、それでも普段からトムと付き合ってくれていた。トムも自分が嫌われていることなどお構いなしで、彼らの輪に入っていく。それがメグには不思議でならなかった。トムも町にいる時は彼らと一緒にこのガソリンスタンドでラジオを聞きながらビールを飲むのだ。夕方からビールを飲むための、名ばかりの抵抗集会である。
「なぁ、トムのことなんだけどさぁ。君が金を管理するわけにはいかないのかい? あいつは金が入ったらすぐにカジノで使い切っちまうからさ」レジーが毛の少なくなってきた頭をかいた。
「それができれば一番なんだけどね。エージェントのダンにも相談したけど、やっぱりトムが認めないからダメなのよ」
「そうか。なんとかならないもんかね。このままじゃ君とエリーが不憫だよ」
「本当にそうだ」バズがレジーに相槌を打つ。
「あいつは一度痛い目に遭わないとダメだな」
「どうかしら。家に帰って来る度に『もうギャンブルには手を出さない』なんて言うくらいだから。もう大人なんだし、簡単に性格は変えられないわよ」
ラジオの音楽が止まり、ニュース番組に変わると男たちは議論に熱を出し始めた。次期大統領に選ばれたニクソンがどうやって戦争を止めるつもりなのか、ロバート・ケネディの暗殺に関する陰謀論、ソ連に負けている宇宙進出と月の裏側を回ってくるというアポロ八号について。
メグは少しばかりの居心地の悪さを感じた。ビールを飲み終わると三人に声をかけてスタンドを後にした。
***
「力になれなくてすまんな」ダンは眉を顰めると、ポケットからハンカチを取り出して額の汗を拭いた。ブロンズドーム・エージェンシーの事務所は冷えていたので、メグはトレンチコートを脱げなかった。事務所の他の職員も同様で、建物の中なのに厚着をしている。それでもダンはワイシャツ一枚にネクタイをしているだけだ。そのワイシャツもお腹周りの肉でパンパンに膨れ上がっており、ボタンが今にもはじけ飛びそうだった。彼のシャツを見ると、メグはいつも決壊寸前のダムのような印象を受ける。
彼はエージェントとして優秀なだけでなく、人としても素晴らしい。トムはダンに会わなければ作家として成功していなかっただろう。優しく、ユーモアに溢れ、気さくな人だ。そんな彼の唯一の欠点は、甘いものに目がないことだった。事務所は彼のためにドーナツとコーヒーを切らすことがない。最初に出会った頃はすらりとした好青年だったが、会うたびに彼は体重を増やしていた。今では二重あごが首を隠してしまったし、かつては魅力的だった顔はシナモンロールのように油っぽく、まん丸になってしまった。
トムの『悪人』シリーズの成功を皮切りに、彼は人気作家を何人も抱えるようになった。小さかった事務所も大所帯になった。ブロンズドームの事務所が寒いのは冬だけではない。夏は夏でダンが冷房をガンガンに効かせるので冷蔵庫の中にいるような気分になる。職場が凍えるように寒くても、彼を慕う他の若いエージェントは離れようとしない。
「前にも言った通り、トムの了解を得ない限り、印税を君に渡すわけにはいかないんだよ。で、トムはあの通りの性格だから、了解するわけがない。それになぁ……」ダンはテーブルの上のドーナツに手を伸ばして一口頰張った。そのあとでメグにもドーナツを食べるように身振りで勧めたが、彼女は軽く断った。
「印税を渡したって言っても、大した額じゃない。もう何年も新作を書いてないからね。ちょこっと増刷しただけだよ。トムに困っているのは君だけじゃない。僕らも早く新作を書いて欲しいんだ。何度も言ってるんだが、全然書いてないみたいだからね」
ダンは早くも二個目のドーナツを摑んだ。
「映画化されたのだって、最初の一冊だけだ。もっと新作を書いて話題になれば、続編も作られるんだろうけどな。で、映画化が続けばシリーズもまた売れるようになる。そうやって売って、作って、また売って、そういうサイクルを繰り返さないと飽きられちゃうからね。文学を書いているんじゃない、娯楽小説だからね。読者を飽きさせたら終わりだよ」
「なんとか無理やり書かせられないかな?」
「無理やりって?」
「ホテルに監禁するとか、銃を突き付けて」
「冗談だろ?」
「私は本気よ。あなたがなんとかやってくれるなら、私は協力するから」
「勘弁してくれよ! そんなことできるわけないだろ?」
「でも彼が書いてくれないと、もう生活にも困っちゃうような状態なの。私が働けば良いだけなんだけどさ、彼は見栄っ張りだから。ちゃんと働かないくせに、私が働くのも嫌なんだって。『お前が働いたら、家が貧乏だと笑われちまう』なんて言うの。実際、貧乏なのに、分かってないのが問題なのよ」
「メグ、君が困っているのは分かる。でもトムの性格だと、無理強いしても書いてくれないだろうな。頑固な奴だから、書けと言えば言うほど書かなくなる」
「じゃあ、どうすれば良いの?」
「さあな。何かインスピレーションでも湧けば書く気になるのかな」
「彼のためにミューズになるような女の子でも用意しろってこと?」ダンの無責任な発言にメグは苛立った。未だに他人ごとなのだ。
「そうは言ってないだろ」
「彼のエージェントはあなたでしょ? 真剣に考えてよ」
「そうだな……、君には黙っておこうと思ってたんだけど、実はトムはもう『悪人』シリーズを書くつもりがないらしい。と言っても、新しいアイデアもない。俺がなにかを提案しても書く努力をしない。それで俺は聞いたんだ。『一体、お前はどうしたら書くつもりになるんだ?』って。そしたら、どう答えたと思う?」
ダンに聞かれて、さっぱり分からないというようにメグは肩を竦めた。
「『世界が終わる日が来たら書くかもな』って言ったんだ。悪いことは言わないけど、彼が書く気になるまでは、俺たちにできることはないよ」
「じゃあ、世界を終わらせれば良いのよ」
「は?」ダンはメグの言葉に眉を顰めた。
「世界が終わるって思わせれば良いのよ。核戦争が起きると思わせて、地下シェルターに彼を閉じ込めるの。そうしたら書くんじゃない?」
「本気じゃないよな?」
「私は本気よ。キューバ危機の時に、家の地下室を核シェルターに変えたの。あそこなら何か月でも籠ってられるし。監禁ってことじゃなくて、彼が勝手に勘違いしたってことに出来るんじゃない? 世界が終わる日が来れば書くんでしょ? それなら、世界の終わりを彼のために作ってあげればいいじゃない?」
ダンは黙ってドーナツを食べながらしばらく考え込んだ。
「確かに、それなら彼も書くかもしれないな。インスピレーションとしては、これ以上ないぐらいだろう。でも、やっぱり本気で騙すのは難しいかな。俺たちが『核戦争が始まる!』って騒いでも信じないだろう。オーソン・ウェルズじゃあるまいし。地下に籠るにしても、ラジオやテレビの報道を見て、町の他の人の反応を窺ってからだろう。一人の作家を騙すために、そんな大げさなことはできないよ」
「でもね、町の人は協力してくれるはずよ。みんなトムのことが嫌いだし、彼を騙すことができるなら、喜んで協力してくれると思う。彼が働けば、町の皆からの借金も返せるし」
「そうなのか、それは心強いな。うーん、でも核戦争を現実だと思わせるのはちょっと難しいな」
「じゃあ、どうやって世界の終わりだと思わせる? どうすれば彼が自分から地下室に逃げ込むかしら?」
「地下室、地下室。地下室に逃げ込む……」
ダンは椅子から立ち上がって部屋の中をぐるぐる歩き回った。彼が動くたびにキャビネットのガラス戸がカタカタ音を立てた。
「待て、良いアイデアを思い付いたぞ。君は『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』を観たかい?」
「ゾンビの映画? 噂には聞いたけど、怖いのは苦手だから」
「あの映画ではゾンビが町に溢れて、地下室に逃げ込む人がいるんだ。何が起こっているか分からない状態で、でも地下に逃げるしかない。あの状況を作り出せば良いんだ。町の人たちが手伝ってくれるなら、これは核戦争よりも騙すのが楽だろう。君が地下に誘導すればいいだろう」
「私は地下に誘導はできるけど、作品を書かせるのはちょっとね。彼が何か書いても、私にはそれが良いか悪いか分からないもの」
「俺が一緒に地下にいられれば良いんだが、他の仕事もあるから無理だしな。待てよ。今、事務所に若手の編集者がいるから、そいつに任せよう」
トムを騙す作戦を練るのは、いたずらをするようで楽しかった。
メグはいつの間にかダンと一緒になってドーナツを食べながら、いろいろと話し合った。
本気だとは言ったものの、メグはもちろん冗談のつもりだった。愚痴を聞いて欲しかっただけなのだ。トムが新作を書いてくれないと家の借金は大変なことになってしまう。だが、トムだって本当はそれを分かっているはずだ。彼が本気になるまで待つしかないか、と思いながらメグは帰路についた。
だが、トムに新作を書いてほしいと心から思っていたのはメグだけではなかった。ダンはこのメグとの秘密の計画を実行に移すべく別の人物に話した。面白いと思ったものを形にしなければ気が済まない性分こそ、ダンがエージェントとして優れている所以だった。
メグが部屋を出た後、ダンはすぐにエドガー・ブラッドに電話をかけた。エドガーはトムの『悪人の道楽』を映画化した映画監督だ。ゾンビ映画を作る気はないか、と言われたエドガーはすっかりその気になり、その日のうちに脚本を書き上げた。
【須藤古都離(スドウ・コトリ)プロフィール】
1987年、神奈川県生まれ。青山学院大学卒業。2022年、「ゴリラ裁判の日」で第64回メフィスト賞を受賞。