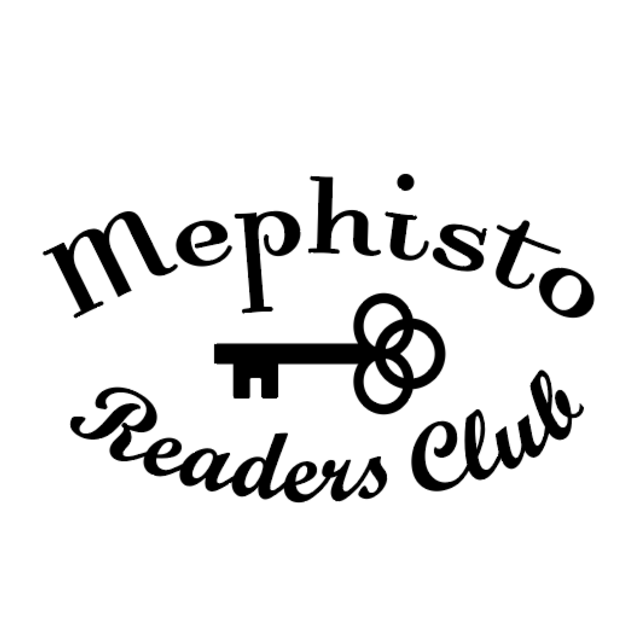『レーエンデ国物語』(2023年6月14日発売) 多崎 礼
文字数 18,397文字
多崎 礼さんの長編ファンタジー『レーエンデ国物語』の冒頭部分を先行公開!
魅せられた。銀呪の地、レーエンデに。ファンタジーはこうでなくっちゃ!〈柏葉幸子〉
これから寝床に入る者は幸福だ。朝よ来るなと怯える夜も、この物語があればいい!〈紅玉いづき〉
この波瀾に満ちた別世界をヒロインとともに歩めるのは読者 の特権です。〈田中芳樹〉
読後、放心し、空を見上げ、トリスタン、と呟く。〈恒川光太郎〉
懐かしい幻想の薫りに浸る、幸せな読書でした。――行こう。恐ろしくも美しい、レーエンデの国へ。〈柳野かなた〉

レーエンデ国物語
序章
革命の話をしよう。
歴史のうねりの中に生まれ、信念のために戦った者達の
夢を描き、未来を信じて死んでいった者達の
革命の話をしよう。
神の声を聞く者ライヒ・イジョルニは戦乱の世を平定し、西ディコンセ大陸に比類なき大国、聖イジョルニ帝国を打ち建てた。広大なる帝国領を十二州に分割し、治世を各地方の領主に任せた。
その帝国領内にありながら、法皇領と帝国十二州、いずれにも属さぬ地域があった。
それがレーエンデだ。大アーレス山脈と小アーレス山脈の狭 () 間 () にあるこの場所は、古来『呪 () われた土地』と呼ばれてきた。この世ならざるものが棲 () み、この世ならざることが起きる場所として恐れられてきた。
レーエンデが抱 () えた宿 () 痾 () と宿命。
そこに生きた者達の受難と苦闘。
法王庁が隠 () 蔽 () し続けてきた真実をここに記そう。
革命の話をしよう。
物語の始まりは聖イジョルニ暦五二二年二月十日。
麗しき月の夜だった。四年に一度の天満月だった。やがて来る動乱を知らず、世界は深い眠りについていた。迫り来る戦禍を知らず、大アーレス山脈は白く悠然と横たわっていた。
山脈の北、シュライヴァ州の州都フェデルは雪に埋もれていた。街並みは紺青に沈み、大気には静寂が満ちていた。窓の明かりはすでに消え、道行く者の姿もない。刃のような月光が冴 () え冴 () えと降る深更。
フェデル城の西の離れで一人の女児が産 () 声 () を上げた。
シュライヴァ州の首長の実弟ヘクトル・シュライヴァと彼の妻レオノーラ・レイムの第一子。後に『レーエンデの聖母』と呼ばれることになる運命の女性。
彼女の名はユリア──
ユリア・シュライヴァという。
第一章 呪われた土地
栗 () 毛 () のフェルゼ馬に乗り、ユリアは山間の隘 () 路 () を登っていた。
城の窓辺から朝な夕なに眺 () めてきた大アーレス山脈。季節ごとに色を変える美しき山河。だがこうして足を踏み入れてみると底意地の悪さばかりが目についた。曲がりくねった細道、雪解け水にぬかるんだ坂道、もし馬が蹄 () を滑 () らせればもろともに谷へ落っこちる。一瞬たりとも気が抜けない。緊張で手綱を握る手が汗ばむ。先行する父に着いていくだけで精一杯、雄大な風景を楽しむ余裕などどこにもなかった。
前を行く黒馬がブルルルッと鼻を鳴らした。あの黒毛は父ヘクトルの愛馬だ。彼とともにシュライヴァ騎士団の先頭に立ち、幾多の死線を駆け抜けてきたフェルゼ馬だ。勇敢な軍用馬だが気位が高い。背に積まれた大荷物が気に入らないらしく、先程から不愉快そうに首を振っている。
思い返せば今朝方まで、この旅にはもう一人同行者がいた。忠実なる使用人のフープが荷を積んだ驢 () 馬 () の手綱を引き、ヘクトルとユリアの後を歩いていた。しかしいよいよ最大の難所ファスト渓谷にさしかかろうという時になって、フープは突然足を止めた。
「旦 () 那 () 様、お許し下さい。ここから先はどうかご勘弁下さい」
彼は帽子を取り、その場にひざまずいた。頭を垂れ、身を震わせ、涙ながらに懇 () 願 () した。
「レーエンデは神に見放された土地です。踏み入れば銀の悪魔の呪いを受けます。全身を銀の鱗 () に覆 () われて苦しみながら息絶える。それを思うと恐ろしくて、もはや堪えられそうにありません。お見苦しい姿をお見せする前に、どうか私を……私を解雇して下さい」
ヘクトルは馬を降り、急いでフープに駆け寄った。平伏する使用人の肩に手を置いて、その身体 () を助け起こした。
「フープよ、無理をさせてすまなかった。ここまで運んで貰 () えれば充分だ。お前はフェデルに戻ってくれ。だが間違うな。解雇はしないぞ。お前ほどの忠義者、手放すつもりは微 () 塵 () もない」
そう言うとヘクトルは驢馬の荷物を自分の軍用馬へと移し替え始めた。それを手伝いながらフープは声を殺して泣いていた。
一人寂 () しくフェデルへと戻っていく彼の背中を思い出し、ユリアはきゅっと下 () 唇 () を嚙 () む。
父上一人だけならば、このような大荷物は必要なかった。フープにあんな悲しげな顔をさせることも、勇敢な軍用馬に大荷物を背負わせることもなかった。私が我 () が儘 () を言ったせいで皆が迷惑をしている。無責任な私の行動が父上の足を引っ張っている。
来るべきではなかった。
やはり来るべきではなかったのだ。
後悔が胸を苛 () む。目の奥がじわりと熱くなる。
「ユリア」
父の声が聞こえた。
「ここで少し休憩しよう」
ユリアは顔を上げ、周囲を見回した。いつの間にか隘路は終わり、見通しの良 () い岩場に出ていた。
手綱を引き、栗毛のフェルゼ馬を止める。地面に降りるとガクガクと膝 () が震えた。振り落とされないように内 () 股 () に力を入れていたせいだ。力尽きて倒れ込むような無 () 様 () な姿を父に見せるわけにはいかない。彼女は急いで近くの岩に腰を下ろした。
「よく頑張ったな」
ヘクトルが水筒を差し出す。ユリアは礼を言って、それを受け取った。水筒に唇 () を当て、一口だけ水を飲む。渇いた喉 () に冷たい水が染 () み込 () んでいく。
「なあ、ユリア」
隣の岩に腰掛けて、ヘクトルは膝の上で手を組んだ。
「フープが言ったことは気にするな。銀 () 呪 () 病 () は恐ろしい病 () だが、これから尋 () ねるイスマル・ドゥ・マルティンは古代樹の森で生まれ育った強者だ。銀 () 呪 () から身を守る術も心得ている。彼に任せておけば大丈夫だ」
銀呪病はレーエンデ特有の風土病だ。全身が銀の鱗に覆われていくという謎 () の死病だ。それに関する噂 () 話 () はユリアもいくつも耳にしてきた。フープだけではない。彼女の身近にいた者達──ばあやも庭師も料理人も銀呪病を恐れていた。レーエンデを「呪われた土地」と呼び、その名を口にするのも穢 () らわしいというように眉 () をひそめた。
だがユリアにとってレーエンデは憧 () れの土地だ。怖いと思ったことは一度もない。夢にまで見たレーエンデへの旅だ。嬉 () しくないはずがない。しかし心は沈んだまま、後悔の淵 () をさまよっている。シュライヴァ家のため、シュライヴァ州の安 () 寧 () のため、人生を捧 () げることは誉れである。そう教えられてきた。シュライヴァ家の娘としての責任を果たす。その覚悟は出来ていた。
なのに思ってしまったのだ。逃げ出したいと。どこか遠くに行きたいと。
罪悪感に打ちのめされ、ユリアは黙って目を伏せる。
そんな娘の姿を見て、ヘクトルはさらに誤解を強めたようだった。
「心配するな。そう長居はしない。今回の旅の目的は交易路の建設に相応 () しい場所を見つけることだ。大アーレス山脈を調査し、秋までには答えを出す。冬が来る前にはフェデルに戻る」
咄 () 嗟 () にユリアは言いかけた。「違うのです」と。「この気 () 鬱 () は銀呪病を恐れてのことではないのです」と。喉まで出かけたその言葉を、ため息に変えて吐 () き出 () す。首から提げた守り石を握りしめ、自分自身に言い聞かせる。駄目よ、言っては駄目。言えば、すべてを話さなければならなくなる。
「今からでも遅くはない。引き返してもいいんだぞ?」
ヘクトルの優しい声。でも今はその優しさが胸に痛い。
俯 () いたまま、ユリアは首を左右に振る。
「引き返しません。私はレーエンデに参ります」
「なぜだ? なぜそうまでしてレーエンデに行きたがる?」
たぶんレーエンデでなくてもよかった。行く先はどこでもよかった。私はフェデル城から逃げ出したかっただけ。自分の役目から逃げ出したかっただけ。でもそんなこと、父上には言えない。本当の理由は話せない。だからユリアは今までと同じ言い訳を繰り返す。
「父上からレーエンデの話を聞かされた瞬間、私は彼の土地に恋をしました。あの時から、いつか必ず会いに行こうと心に決めておりました」
それは九年前、彼女がまだ六歳の時のことだった。
東ディコンセ大陸の大部分を占める未開の荒野、通称『東方砂漠』。今から百年ほど前、東方砂漠に暮らす遊牧民グァイ族が『帝国の穀物庫』と呼ばれるレイム州を襲撃した。助けを求めるレイム州に応 () えたのがシュライヴァ州だった。
この時に始まったレイムとシュライヴァの同盟関係は今もなお続いている。シュライヴァ騎士団の騎士団長を務めるヘクトルは、夏が盛りを迎える頃、精鋭部隊とともにレイムへと赴く。国境を巡回し、東方砂漠に目を光らせ、秋の収穫が終わると役目を終えて帰郷する。
聖イジョルニ暦五二七年十一月。国境警備に出ていたシュライヴァ騎士団が州都フェデルに戻ってきた。城の中庭では騎士達とその家族が五ヵ月ぶりの再会を喜んでいた。ユリアもまた中庭に出て父の姿を捜した。が、ヘクトル・シュライヴァはどこにも見当たらない。
「父上はどうしたのですか? どこにいらっしゃるのですか?」
彼女の問いに、副団長のクラヴィウスは言いにくそうに答えた。
「ご安心下さいユリア様。ヘクトル様はご無事です。ご帰還が遅れておりますのは、東部砂漠で負傷した傭 () 兵 () に付き添い、彼を故郷の地まで送り届けに行かれたからです」
なんで? とユリアは思った。そんなこと父上がしなくたっていいじゃない、他 () の人に任せればいいじゃない。しかしすぐに考えを改めた。お戻りが遅れたぐらいで癇 () 癪 () を起こすなんて馬 () 鹿 () な子供のすることよ。私は英雄の娘だもの。少しぐらい待たされたって泣いたりしないわ。ちゃんと笑って、おかえりなさいと言うわ。
ユリアは大人しく父の帰りを待った。やがて北からの風が雪雲を運び、フェデルの街並みは白に埋もれた。ベーレの森は綿帽子を被 () り、大アーレス山脈は純白のドレスを纏 () った。冬の息吹がシュライヴァを覆 () い尽 () くしても、ヘクトルは戻ってこなかった。
不安に押 () し潰 () されそうになりながら、ユリアは毎朝毎晩、窓辺に跪 () いて祈った。
「父上、早く戻ってきて下さい。母上、どうか父上をお守り下さい」
彼女の母レオノーラはユリアを出産した三日後に天に召された。父の居室には今も彼女の肖像画が飾られている。月光のような白金髪、雪花石 () 膏 () のような白い肌、薔 () 薇 () 色 () の唇に浮かぶ微 () 笑 () みは儚 () げで、空色の瞳 () は寂しげだった。それを見るたびユリアは思う。レイム州出身の母にとって、シュライヴァは心地よい場所ではなかっただろう。重く湿った空気も、フェデル城の閉鎖的な雰囲気も、母の心身を苛んだだろう。
ユリアには繰り返し聞かされてきた言葉があった。
「母の温 () もりを知らずに育つとは不 () 憫 () な子だ」
「お母様がいなくて寂しいでしょう?」
優しげな声、同情に満ちた表情、その裏側にはいつだって揶 () 揄 () と侮 () 蔑 () が存在していた。
「あの娘はちっとも笑わないな」
「天満月生まれの娘は災禍を招くと言うし」
「あれでは嫁の貰 () い手 () を探すのも一苦労だろうて」
「本当にシュライヴァの血を引いているのかしら?」
心ない雑言や陰 () 口 () に耐えてこられたのは、父ヘクトルがいたからだ。もしこのまま父上が戻らなかったら、私は本当に一人ぼっちになってしまう。
「父上、帰ってきて下さい。お願いです。私を一人にしないで下さい」
ユリアは必死に祈り続けた。だが願いはかなわぬまま十三月は終わりを迎え、新しい年がやってきた。新年を祝って浮かれ騒ぐ者達を余 () 所 () にユリアは鬱 () 々 () とした日々を過ごした。何の音 () 沙 () 汰 () もないまま一月が過ぎ、二月が過ぎた。日差しが暖かくなり、屋根に積もった雪も溶け始めても、父は戻らなかった。
それは三月に入って間もない、まだ寒さの残る早朝のことだった。
「ユリア、朝だよ。お目覚めの時間だよ」
耳慣れた声に瞼 () を開くと、目の前にヘクトルの顔があった。褐色の髪はもつれ、顎 () は無 () 精 () 髭 () に覆われていたけれど、鳶 () 色 () の瞳は変わらず明るく輝いていた。
「おはよう、俺のお姫さま」
無骨な指が彼女の髪を撫 () でた。懐 () かしい父の匂 () いがした。
夢ではない。これは夢じゃない。そう思った瞬間、涙が溢 () れた。泣かないと決めていたのに、笑顔でおかえりなさいと言おうと思っていたのに、喉が詰まって声が出なかった。
「遅くなってすまなかった」
泣きじゃくる愛 () 娘 () をヘクトルは優しく抱きしめた。
「長らく肩を並べて戦ってきた戦友のイスマルが重傷を負ったんだ。幸い一命は取り留めたが、右足を切断しなければならなくなった。『潮時だ』とイスマルは言ったよ。『引退してレーエンデに戻るよ』とね。だがフェデル渓谷路は難所が多い。しかもイスマルは右足を失ったばかりで馬に乗ることもままならなかった。一人で行かせるわけにはいかないと思ったよ。だから、ついていくことにした」
ヘクトルはユリアの髪にキスをして、いっそう強く彼女を抱きしめた。
「イスマルを古代樹の森へ送り届けたら、すぐに戻るつもりだった。だが到着直後に大雪が降ってな。例年より一ヵ月も早く渓谷路が雪に埋もれてしまったんだ。そのせいで戻るに戻れず、連絡することもかなわず、お前には辛 () い思いをさせてしまった。けれどユリア、これだけは信じてくれ。お前を軽んじたわけではない。お前を悲しませるつもりはなかったんだ」
言われるまでもなかった。父の愛を疑ったことなど一度もなかった。しかしどんなに大人びていてもユリアはまだ六歳。不安に押し潰されそうだった日々を、鬱 () 積 () した怒りと悲しみを、吐き出さずにはいられなかった。
「れ、レーエンデというのは……そ、そんなに遠いところに、あるのですか」
鼻をすすり、しゃっくりを挟みながら、ユリアは尋ねた。
「お、お帰りが、こんなに遅くなるほど、遠く遠くにあるのですか!」
答える代わりにヘクトルは彼女を抱き上げた。左腕でユリアを支え、もう一方の手で鎧 () 戸 () を押し開ける。差し込む朝日の眩 () しさにユリアは思わず目を閉じた。冷えた空気に晒 () されて、剝 () き出 () しの頰 () がピリピリ痺 () れる。鼻の奥に冷気が染 () みて、小さなくしゃみが飛び出した。
「ごらん」
父の声に彼女は薄く目を開いた。眼下に広がるフェデルの街並み、その先には深緑色にくすんだベーレの森がある。さらに遠く、青く凍 () った空の下、大アーレスの銀領が横たわっている。
「レーエンデはあの山の向こう側にある。大アーレス山脈と小アーレス山脈の間にある森林地帯と、レーニエ湖周辺の高原一帯をレーエンデ地方と呼ぶんだ」
「で、では父上は、大アーレスを越えたのですか?」
「そうだ」
「危なくは、なかったですか?」
「道は険 () しかったが、苦労したかいはあったぞ」
ようやく泣 () き止 () んだ娘を見て、ヘクトルは微笑んだ。
「帝国建国以前からレーエンデにはウル族とティコ族という少数民族が暮らしていてな。その独自の文化に敬意を払い、始祖ライヒ・イジョルニは彼らに自治権を与えた。ゆえにレーエンデ地方は帝国内にありながら外地の影響をほとんど受けていない。あの土地では世間の常識は通用しない。血筋も身分も家 () 柄 () も何の意味も持たないんだ」
熱っぽく語る父を見上げ、ユリアは眉 () 根 () を寄せた。それのどこがいいのか、さっぱり理解出来なかった。するとヘクトルは逡 () 巡 () し、言い方を改めた。
「レーエンデは不思議の国だ。見るもの聞くものすべてが奇妙で面白い。たとえば古代樹の森に住むウル族は巨木の洞 () で暮らしている。木の実の粉でパンを焼き、光る虫を集めてランプを作る」
途端、ユリアは目を輝かせた。
巨木の家! 光る虫のランプ! まるでお伽 () 噺 () の国みたい!
「木の洞に住むなんて、妖 () 精 () みたいです」
「そうだな。ウル族は肌が白く、瞳の色も髪の色も薄くて、本物の妖精みたいだったぞ」
クスクスと笑い、ヘクトルは再び大アーレス山脈へと目を向ける。
「いつかは俺もあの場所で、彼らのように暮らしたい」
それを聞いてユリアは再び不安になった。父上はシュライヴァよりもレーエンデが好きなのだ。いつか私を置いてレーエンデに行ってしまうのだ。そう思うとまた涙が出そうになった。
そんな娘の気持ちを知ってか知らずにか、ヘクトルはユリアの髪をくしゃくしゃとかき回した。
「お前にあの風景を見せてやりたい。お前もきっと気に入る」
口を開くと泣いてしまいそうだったので、ユリアは黙って頷 () いた。
ユリアはフェデル城が好きではなかった。彼女を取り巻く人々はよそよそしくて冷たかった。いつかこの城を出てレーエンデに行く。父と一緒にお伽 () の国で暮らす。それはとても魅力的に思えた。
「では約束して下さい。今度レーエンデに行く時は、私も一緒に連れて行くと」
「承知した」
ヘクトルは大らかに首肯した。
「シュライヴァの名にかけて誓おう。今度レーエンデに行く時には必ずお前を連れて行こう」
あれから九年、ユリアは十五歳になった。もはや分別のつかない子供ではない。シュライヴァ家の娘が長期旅行に出かけるなど、決して許されないことだとわかっている。しかしヘクトルがレーエンデに赴くと聞いて、いても立ってもいられなくなった。ユリアは父の元を尋ね、「私も連れて行って下さい」と懇願した。「シュライヴァの英雄が約束を破るのですか」と迫った。そんな娘の熱意に押され、ヘクトルはついに首肯した。夏の間だけという条件で彼女に同行を許してくれた。
守り石を握りしめ、ユリアは思う。
あの時、私はレーエンデに恋をした。今も彼の地に憧れている。同行を望んだ理由はそれだけではないけれど、レーエンデに恋 () い焦 () がれるこの気持ちに偽りはない。
「父上が言ったのです。『レーエンデは不思議の国だ』と。『きっとお前も気に入る』と」
「ああ──そうだな」
ヘクトルは目を細めた。穏 () やかな目をしていると思った。同情しているのだと思った。娘のことを哀 () れに思えばこそ、父上は私を連れ出してくれたのだ。この小旅行は父の愛、父上が私に下さる最後の贈り物なのだ。
「さて、そろそろ行こうか」
ヘクトルが腰を上げる。ユリアも慌てて立ち上がった。
「父上、ここから先は私も歩きます。荷物を半分、栗毛の背中に移して下さい」
「その必要はない。まだまだ険しい上り坂が続く。お前は馬に乗っていけ」
「でも荷物が多いのは私のせいです。なのに私だけが楽をするなんて出来ません」
それ以上、父に物言う暇も与えずユリアは黒毛に歩み寄る。縄を解き、馬の背に積まれた衣装箱を下ろそうとする。
「俺がやろう」
ヘクトルが彼女の手を制した。衣装箱を肩の上へと担ぎ上げ、申し訳なさそうに眉根を寄せる。
「すまないな。お前まで歩かせる羽目になって」
「ご心配なく」ユリアはドレスの裾 () を持ち上げてみせた。「こういうこともあろうかと、革の長靴を履いてきました」
「さすが俺の娘だ」
ヘクトルは朗 () らかに笑い、ユリアの頭をぽんぽんと叩 () いた。
「この先は危険な箇所が多い。油断するな」
父娘 () は再び歩き出した。父の助言に従い、慎重に足を進める。今にも崩落しそうな砂 () 礫 () の斜面を横切り、馬の手綱を引いて険しい岩場を乗り越えた。切り立った崖 () に作られた心 () 許 () ない張り出しの上を一列になって進んだ。深い谷に渡された吊 () り橋 () は一足ごとにギシギシ軋 () む。ぐらつく踏み板の下をびょうびょうと風が吹き抜けていく。谷底に目を向けると足がすくんでしまうので、ユリアは自分の靴先だけを見て進んだ。
緊張の連続に心身ともにくたびれ果てていた。足の裏には水 () 膨 () れが出来て、踏み出すたびに刺すような痛みが走った。ユリアは奥歯を喰 () いしばり、必死に足を動かし続けた。
「見えたぞ!」
声を弾ませ、ヘクトルが前方を指さした。
「あれがレーエンデ、古代樹の森だ」
坂道を登り切り、崖の縁に立つ。
眼下に緑の海が広がっている。靄 () がかかった樹海が地平の彼方 () まで続いている。フェデル城から望む陰 () 鬱 () なベーレの森とは異なり、古代樹の森は多彩な色合いに満ちていた。滴 () るような深緑色、若さ溢れる萌 () 黄 () 色、光り輝く黄緑色、翡 () 翠 () のような緑青色。中でもひときわ目を引くのが乳白色の巨木群だ。緑の梢 () を突き抜けて屹 () 立 () する古代樹の群生。あれが古代樹林、あそこにウル族の集落がある。
「この峠は外地とレーエンデの境だ。レーエンデに来る者、レーエンデを去る者、誰もが等しく立ち止まり、置いてきたものを振り返る。ゆえにここを『見返り峠』と呼ぶのだそうだ」
大きく息を吐 () き、ヘクトルは感慨深げに呟 () く。
「ああ、ようやく戻ってこられた」
ユリアは無言で頷いた。初めて見る風景なのに、初めて見たという気がしない。どこかで見たような気もするけれど、どこで見たのか思い出せない。霞 () のごとく消えゆく記憶を引き寄せようとするほどに頭の芯 () が熱くなる。胸の奥にひたひたと何かが押し寄せてくる。
「おや?」
ヘクトルが首を傾 () げた。不可解そうに古代樹の森を指さす。
「見えるか、ユリア」
「……はい」
樹冠の上にキラキラと光るものが浮いている。虹 () 色 () の皮膜、透き通った球体、どこから見てもシャボン玉だ。大小様々なシャボン玉が続々と樹海の中から湧 () いてくる。
「なぜこんなところにシャボン玉が?」
「シャボン玉ではない。あれは泡 () 虫だ。とても珍しいもので、レーエンデでも滅 () 多 () に見かけることはないとイスマルは言っていた。が、奇遇だな。前回もこの見返り峠で泡虫を見た」
「泡虫──ということは、あれは生き物なのですか?」
「わからない」ヘクトルはにやりと笑う。「泡虫の正体を知る者はいない。世間の常識は通用しない。レーエンデはそういう場所だ」
名を呼ばれたことに気づいたのか、泡虫の群れが動き出した。ゆるゆると見返り岬に向かって流れてくる。ひとつやふたつならば可 () 愛 () いが、百とも二百ともつかない大群だ。身の危険を感じ、ユリアは父に身を寄せた。ヘクトルは左手でユリアの肩を抱き、剣の柄に右手を添えた。
見返り峠に押し寄せる泡虫達。それは二人の目前で左右に分かれた。そのまま二人の横を通り過ぎ、後方へと流れ去っていく──かと思いきや、弧を描いて戻ってきた。ユリアとヘクトルを中心に泡虫の群れが大きく緩 () やかな渦を巻く。透き通った球体がくるくると舞い、ふわふわと躍る。虹色に輝き、音もなく消えていく。淡く儚い刹 () 那 () の円舞。そこには歌も音楽もない。歓声も言葉もない。なのにユリアは感じていた。溢れんばかりの歓喜を。舞い上がるほどの感動を。
おかえり、おかえり、待っていたよ。貴方 () が来るのを待っていたよ。
声なき声を響かせて泡虫達が消えていく。
最後に残った一泡が、まるでキスをするように、ユリアの眼前でぱちんと弾 () けた。
柔らかなものが唇に触れた。鼻の奥に海が薫った。懐かしい。恐ろしい。恐ろしいのに愛おしい。愛おしいのに悲しくて、なのに嬉しくてたまらない。心が震える。琴線がかき鳴らされる。涙がぽろぽろとこぼれてくる。
「どうしたユリア? なぜ泣いている?」
ヘクトルが尋ねる。心配そうに娘の顔を覗 () き込 () む。だがユリアは答えられない。なぜ泣いているのか、彼女自身にもわからない。
しかし確信していた。狂おしいほどに確信していた。
私はレーエンデにやってきたのではない。
レーエンデに還 () ってきたのだ。
見返り峠を下り、二人は古代樹の森に入った。
森の中はひんやりとして肌寒い。しかし思っていたほど暗くはなかった。木漏れ日に照らし出された羊歯 () の葉は瑞 () 々 () しく、苔 () 生した大岩や倒木は淡い緑に輝いている。競い合うように伸びた木々、絡み合った枝には青々と葉が生い茂っている。湿った土の匂い、清 () 々 () しい新緑の香り、初夏の日差しに若葉が煌 () めき、風や空気さえも鮮やかな緑に染まって見える。
ヘクトルは慎重に森の奥へと進んだ。時折足を止め、何かを探すように木々を見上げた。
頭上でさわさわと枝葉が揺れる。銀色の小鳥が梢を行き交い、葉 () 陰 () から楽しげな囀 () りが聞こえてくる。それに紛 () れ、遠くのほうから冴 () えた鈴音が響いてきた。かすかに聞こえる鈴の音をたどり、ヘクトルは足を速めた。ユリアは足の痛みを堪え、必死に父を追いかけた。
「見ろ、ユリア!」
嬉 () 々 () としてヘクトルが叫んだ。
「あれが古代樹林。ウル族の集落、古代樹林のマルティンだ!」
森が切れ、広い空間に出た。斜めに差し込む光の中、幾本もの巨木が聳 () えている。どっしりとした根は大地を隆起させ、大岩をいくつも抱き込んでいる。窓や扉が埋め込まれた太い幹を螺 () 旋 () 状の階段が取り巻いている。枝は通路になっているらしく、梯子 () や吊り橋が複雑に絡み合い、隣の巨木と繫 () がっている。枝の間には幾重にも細い綱が張り巡らされ、無数の細長い金属片が吊 () されている。それらが風に揺れるたび、チリン、リリンと涼やかな音色が響いてくる。
呆 () 然 () としてユリアは古代樹林を見上げた。乳白色の幹が樹冠を突き抜け、はるか蒼 () 天 () へと伸びている。予想以上の高さだった。想像を絶する太さだった。圧倒されて声も出なかった。
「おおい、イスマルはいるか?」
口の横に右手を当て、ヘクトルが声を張る。
「俺だ、ヘクトルだ。約束通りやってきたぞ!」
それに応じるように一番手前の巨木の扉が開かれた。
「おう、よく来たな!」
陽気な声とともに壮年の男が出てくる。灰色の髪を首の後ろで三つ編みにした大男だ。ごつい肩、厳 () つい顎、日焼けした肌にはいくつもの傷 () 痕 () が浮いている。右 () 脇 () に挟んだ松 () 葉 () 杖 () を器用に操り、岩階段を下りてくる。下 () 穿 () きの裾から突き出た鉄の義足を見てユリアは気づいた。この人がイスマル、シュライヴァ騎士団の危機を救い、その代償として右足を失った父上の戦友なんだわ。でもちょっと待って。ウル族は本物の妖精のようだと父上は言っていた。けれど彼は少しも妖精らしくない。どちらかというと山賊団の頭領だわ。
「久しいなイスマル。しばらく見ないうちにずいぶんと貫 () 禄 () がついたな」
「そういうお前さんは変わらんなぁ。今年でいくつになるよ?」
「三十五だ」
「そうか、お前さんもついに第三の人生を始める歳 () になったか!」
ヘクトルとイスマルは互いの肩を抱き合い、再会を喜んだ。
「紹介しよう。俺の自慢の娘ユリアだ」
「ようこそ、お嬢さん」
山賊顔の元傭兵は白い歯を見せて笑った。
「俺はイスマル。イスマル・ドゥ・マルティンだ」
名乗りを上げ、肩の高さに左手を掲げる。初対面の相手には左手の掌 () を見せる。それがウル族の正式な挨 () 拶 () なのだと、事前にヘクトルから聞かされていた。
ユリアはおずおずと左手を挙げた。
「初めまして、ユリア・シュライヴァです。その節は父がお世話になりました」
「いやいや、世話になったのは俺のほうさ」
戯 () けた様子で手を振って、イスマルは背後を振り返った。
「じゃあ、俺の家族も紹介しようか」
扉の前に数人の女性が立っている。ウル族の民族衣装なのだろう。独特な模様が刺 () 繡 () された長 () 衣 () に幅広のベルトを巻き、裾を絞った下穿きをつけている。
「一番大きいのが長女のプリムラ。プリムラにくっついてるのが双子の孫娘、右がペル、後ろにいるのがアリー。その隣にいるのが次女のリリスだ」
「いらっしゃい。お待ちしておりました」
二十代半 () ばの女性、プリムラが左手を掲げた。白雪の肌に春空の瞳、金糸のような髪を背に垂らしたその姿は聖典の挿絵に描かれた慈愛の天使そのものだ。双子の少女は三、四歳。綿菓子のような金の巻き毛と、むっちりとした薔薇色の頰を持っている。顔立ちは瓜 () 二 () つだが性格は異なるらしい。ペルは興味津々な目でユリア達を見つめているが、アリーはプリムラの後ろに半ば隠れてしまっている。最後の一人、リリスはユリアと同年代の少女だった。白い肌や青い目はプリムラ達と同じだが、豊かに波打つ髪の毛はヤバネカラスのように真っ黒だった。
シュライヴァにおいて黒髪は叡 () 智 () の証 () し、賢者の印と呼ばれている。美しい黒髪に憧れて髪を染める娘も多い。ユリアの金髪は亡き母から譲り受けたものだったから、染めたことは一度もない。だが染めたいと思ったことなら実のところ何度もある。しかもリリスの黒髪は天鵞絨 () のように艶 () めいて、惚 () れ惚 () れするほど美しい。あの黒髪を持って生まれていたら悪口を言われることも陰口を叩かれることもなかったかもしれない。ユリアは羨 () 望 () の眼 () 差 () しで彼女の髪を凝視した。見つめすぎたようだった。リリスはあからさまに唇を歪 () め、不機嫌そうにそっぽを向いた。
「長旅で疲れただろ。話の続きは中で聞こう。リリス、ペル、アリー、客人達の馬を頼む」
イスマルが先に立って階段を上っていく。入れ違いに階段を下ってきた黒髪の少女に、ユリアは手綱を差し出した。
「お願いします」
リリスはひったくるようにそれを奪い取った。
「あんた、さっきからなんなの? あんまりジロジロ見ないでくれる?」
棘 () のある声で言われ、ユリアは思わず首を縮めた。すみません──と小声で詫 () びて、急いで父の後を追った。
古代樹の中は木の洞とは思えないほど広かった。床には毛 () 織 () 物 () が敷かれ、木製の椅 () 子 () とテーブルが置かれている。丸窓からは光が差し込み、奥には暖 () 炉 () までしつらえてある。乳白色の壁面はつるりとして、樹木というより大理石のようだった。
「狭くて驚いたかい?」
暖炉前の揺 () り椅 () 子 () に腰掛け、イスマルが問いかける。
ユリアは慌てて首を横に振った。
「い、いいえ。幹の中なのに、壁が石みたいだなと思って……」
「古代樹ってのは化石だからな。樹よりも石に近いんだ。階段の上り下りにはちと苦労するが、慣れてしまえばけっこう暮らしやすいところだよ」
イスマルはユリアに座るよう#促 () した。彼女が長 () 椅 () 子 () の端 () に腰を下ろすと、イスマルは改めてヘクトルへと向き直る。
「じゃ、さっそく聞かせて貰おうか。シュライヴァの首長は、なぜお前さんに交易路を造るよう命じたんだ? シュライヴァとレーエンデを結ぼうとする彼の真意はどこにある?」
「主目的は通行税を得るためだ」
膝の上に肘 () をつき、ヘクトルは身を乗り出した。
「レーエンデで作られる農耕具は質がいい。レイム州やフェルゼ州でも需要は高い。レーエンデとシュライヴァを繫ぐ道が出来て、多くの商人がそれを利用するようになれば市場は活性化する。交易が盛 () んになればシュライヴァの財政も潤 () う」
「けどシュライヴァにはシュライヴァ騎士団がいるじゃねぇか。無敵の騎士団を貸し出して、さんざん荒稼ぎしてきたじゃねぇか。なのに今になって『通行税を稼ぐために交易路を造りたい』とか言われても、信 () 憑 () 性に欠けるんだよ」
「兄上は吝 () い屋だ。相応の見返りが見込めないものに大金を投じることはない」
「相応の見返りってなんだ? しみったれた通行税じゃねぇよな? まさかとは思うが、道を造って騎士団を送り込んでレーエンデを支配するとか、ンな馬鹿なこと考えてねぇだろうな?」
「その可能性は否定出来ない」
「おいおい、お前さんはどっちの味方なんだ?」
「俺は外地の者達にレーエンデの魅力を知って欲しいんだ。レーエンデに対する偏見を払 () 拭 () し、ゆくゆくは医者や学者を招 () 聘 () し、銀呪病を根絶したいんだ。そのためには道がいる。外地とレーエンデを繫ぐ安全な交易路がいる。兄上と俺とでは考え方も目的も違うが、交易路が必要だとする点は意見が一致している」
「けど、その交易路のせいでレーエンデが戦場になるんじゃ元も子もねぇ」
「交易路には関所を作る。攻めにくく守りやすい難攻不落の砦 () を造る」
ヘクトルは肩の高さに右手を掲げた。
「シュライヴァ家の名誉に懸けて誓う。シュライヴァ騎士団はレーエンデとは戦わない。レーエンデを戦場するようなことは一切しない」
「お前さん、騎士団長の肩書きは返上したんじゃなかったのか?」
「そのつもりだったんだがな。兄上が許可してくれなかったんだ。俺が騎士団長を辞めたらシュライヴァ騎士団の値打ちが下がるってな。よって俺は休職中だ。今はあの堅物クラヴィウスが団長代理を務めている。『自分には代理など務まりません』と固辞するから、『引き受けないと例のことを奥方にバラすぞ』と脅してやった」
「相変わらず、えげつねぇことをしやがる」
「俺もそう思う」
ひっそりと笑って、ヘクトルは両手を組んだ。
「前にも言ったが、俺はレーエンデが好きだ。いずれはこの地でのんびり暮らしたいと思っている。その夢をかなえるためならば兄上の野望も利用する」
「まったく、お前さんの考えにはいつも驚かされるよ」
呆 () れたというように、イスマルはぐるりと目玉を回した。
「わかったわかった、信じよう。銀呪病の根絶なんつう話は壮大すぎてピンとこねぇが、交易路が出来ればここの暮らしもちったぁ楽になるだろうし──」
そこで何やら言いよどみ、不満げな顔で頰 () 杖 () をつく。
「けどなぁ、言っちゃあなんだがウル族の連中は頭が固い。外地との交流することを快 () く思わない者も多い。頷かせるのは至難の業だぞ?」
「それについては心配していない」
ヘクトルは自信たっぷりに右目を閉じた。
「俺がよく知るイスマル・ドゥ・マルティンは不可能を可能にする男だからな」
「よせやい」
「やってくれるか?」
「対価として塩一袋を所望する」
「土産に持ってきた」
「ありがたい!」イスマルは手を叩いた。「外地の飯に舌が慣れちまうと、レーエンデの飯は味気なくてなぁ」
「聞こえたわよ?」
明るい声が割って入った。上の階の厨 () 房 () からプリムラがお茶を運んで来る。
「私が作るご飯が気に入らないなら、お父さん、自分で作ればいいじゃない」
「違う違う、誤解だプリムラ!」イスマルは慌てて両手を振る。「お前の作る飯が気に入らねぇだなんて一言も言ってねぇ!」
「あらそう?」
「ああそうだとも。塩がふんだんに手に入るようになったら、料理にもっと幅が出るだろ? 小麦が手に入りやすくなったら、毎日真っ白なパンが喰えるようになってチビどもも喜ぶだろ? 俺が言いたかったのはそういうことだよ」
「はいはい、じゃあ、そういうことにしておきます」
プリムラはくすくす笑い、ユリアに湯飲みを差し出した。
「さぁどうぞ。疲れが取れるわよ」
礼を言い、ユリアはそれを受け取った。湯飲みには白茶色の液体が入っている。表面に黄色い油膜が張っている。立ち上る湯気から、甘いような渋 () いような馴 () 染 () みのない匂いが漂ってくる。口に含むのが恐ろしい。しかしせっかくのおもてなしだ。飲まないわけにもいかない。覚悟を決め、ユリアはそれを口に運んだ。心地よい茶の渋みが口の中に広がる。滑 () らかなバターの香りが鼻に抜ける。少し苦くてとても甘い。夢中で半分ほど飲んだ。優しい温もりに緊張が緩み、気持ちが和らぐ。
「美味 () しい?」
「はい」
「クリ茶って言うのよ」
プリムラは嬉しそうに花の顔 () をほころばせた。
「ユリアさん、ヘクトルさん、よければ一緒に夕食を食べていきません?」
「お誘いはありがたいが、先に案内人に会っておきたい」
目礼して湯飲みを受け取り、ヘクトルは視線をイスマルへと戻した。
「今夜中に段取りを説明して、明日から調査を開始したい」
「大丈夫、もう話はつけてある」
イスマルはクリ茶を一口飲んだ。
「トリスタンって若者だ。腕も立つし土地にも詳しい。けどちょいと変わりモンでなぁ。昼過ぎには顔を出せと言っといたんだが、あの野郎、まだ来やがらねぇ」
「その男、今どこにいる?」
「まだエルウィンにいるんじゃねぇかな。ああ、エルウィンってのはここから十分ほど南に行ったとこにある一本立ちの古代樹だ。トリスタンはそこで一人で暮らしてる」
クリ茶を飲み干し、イスマルは膝を打って立ち上がった。
「案内しよう。どのみち連れてくつもりだったんだ。エルウィンなら邪魔も入らねぇし、拠点にするにはうってつけだ」
「待ってくれ」ヘクトルは眉 () 間 () に縦 () 皺 () を寄せた。「一人暮らしの男の家にユリアを同居させろというのか?」
「トリスタンは変わりモンだが、お嬢さんに手を出すような真 () 似 () は絶対にしねぇ。そいつは俺が保証する。だがマルティンの若造達はやんちゃだからな。連中が狩りから戻ってきたら、それこそ大騒ぎになるぜ。しばらくは調査どころじゃなくなっちまうぜ」
「そうか、わかった」
一息にクリ茶を呷 () り、ヘクトルも立ち上がった。
「案内は必要ない。南に十分の距離なら俺だけでもたどり着ける」
それに──と言って、片目を閉じる。
「鉄足の歩く速度に合わせていたら到着前に陽が暮れる」
「ぬかせ」イスマルはヘクトルを小突いた。「じゃあ明日の朝、様子見がてらウチの#若 () ぇモンにヤギの乳を届けさせる。トリスタンによろしく伝えてくれ」
「了解だ」
ヘクトルが扉へと動き出すのを見て、ユリアは急いでクリ茶を飲み干した。礼を言って立ち上がり、父を追って外に出た。
階段の下ではペルとアリーが石 () 蹴 () りをして遊んでいた。すぐ傍には黒髪の少女が立っている。ヘクトルが声をかけると、リリスは頷き、納屋から馬を引いてきた。
「ありがとうございます」
ユリアが礼を言っても、リリスは鼻を鳴らしただけで、目も合わせようともしなかった。
二人は古代樹林マルティンを離れ、森の小道を南へ向かった。
太陽は西の山頂に近づきつつある。遠くからヤバネカラスの鳴き声が聞こえてくる。朱を帯びた光を浴び、広葉は赤銅色に輝いている。紫色に染まった森、美しく謎めいた夕 () 闇 () 、気を許したら誘われてしまいそうだった。ふらふらと道を外れ、森の奥へと迷い込んでしまいそうだった。
「ごめんなさい、父上」
闇 () から目を逸 () らし、ユリアは隣を歩くヘクトルを見上げた。
「あんなに深いお考えがあったとは思っていませんでした」
「ということは、ユリアも俺のこと、考えなしの戦馬鹿だと思っていたんだな?」
そこまでは言わないが、狡 () 猾 () な兄に踊らされるお人 () 好 () しな弟ぐらいには思っていた。
「すみません」
「謝ることはない。そう思われても仕方がない。だが安心しろ。俺には俺の考えがある。兄上のことは尊敬しているが、だからといって妄信追従しているわけではない」
ヘクトルは愉快そうに笑ったが、ユリアはとても笑う気にはなれなかった。
「ですが、もしヴィクトル様からレーエンデを攻め落とすよう命じられたら、父上は──」
突然ヘクトルは立ち止まった。ユリアを背にかばい、前方の木立を見上げる。冷え冷えとした眼光、引き締まった唇、空気がピリリと張り詰めるのがわかった。肌が粟 () 立 () つような寒気を感じ、ユリアは両手で自分の肘を抱きしめる。
父上は何を見ているの? あの木の上に何かいるの?
生い茂った枝葉は影に沈んでいる。目をこらしても何も見えない。ざわざわと梢がざわめく。それはどこか潮 () 騒 () に似て、ユリアの心をかき乱す。
「怪しい者ではない。ここにはイスマルの紹介で来た」
ヘクトルは一歩前に出た。左胸に手を当て、正式な騎士の礼をする。
「俺はヘクトル・シュライヴァ。後ろにいるのは娘のユリアだ」
枝の上の木の葉が揺れた。かと思うと、一人の男が飛び降りてくる。
斜めに差し込む赤銅色の夕日、大地に落ちる斑 () の陰影、そこに降り立った青年は長弓と矢筒を背負っていた。肌は浅黒く、束 () ねた髪は黒く、切れ長の目は琥 () 珀 () 色だった。ウル族の衣装を身につけているが、天使のようなプリムラとは似ても似つかない。悪相だが人好きのするイスマルとも違う。
ユリアは青年を見つめた。疑惑と困惑が頭の中を駆け巡る。この人、どうして木の上にいたの? あの高さから飛び降りて、どうして平気な顔をしているの? なぜ父上は怖い目で彼を見ているの? この人はいったい何者なの?
「すみません。夕食の準備をしていたら出遅れてしまいました」
涼やかな声音で青年は言った。
「僕はトリスタン・ドゥ・エルウィン。イスマルから団長の案内人を務めるよう言われています」
どうぞよろしく──と言って左手を掲げる。彼の掌は白く、その微笑みは三日月のようだった。切れ長の目は鋭く、なのにどこか寂しくて、ぞくりとするほど妖 () 艶 () だった。夜を思わせる浅黒い肌、闇を思わせる昏 () い瞳。恐ろしいのに心惹 () かれる。美しく謎めいていて目が離せない。
ユリアは思った。
ああ、この人はまるでレーエンデそのものだ。
続きは6月14日発売の『レーエンデ国物語』(多崎礼)で!
【多崎 礼(たさき・れい)プロフィール】
2006年、『煌夜祭』で第2回C・NOVELS大賞を受賞しデビュー。著書に「〈本の姫〉は謳う」、「血と霧」シリーズなど。
魅せられた。銀呪の地、レーエンデに。ファンタジーはこうでなくっちゃ!〈柏葉幸子〉
これから寝床に入る者は幸福だ。朝よ来るなと怯える夜も、この物語があればいい!〈紅玉いづき〉
この波瀾に満ちた別世界をヒロインとともに歩めるのは
読後、放心し、空を見上げ、トリスタン、と呟く。〈恒川光太郎〉
懐かしい幻想の薫りに浸る、幸せな読書でした。――行こう。恐ろしくも美しい、レーエンデの国へ。〈柳野かなた〉

レーエンデ国物語
序章
革命の話をしよう。
歴史のうねりの中に生まれ、信念のために戦った者達の
夢を描き、未来を信じて死んでいった者達の
革命の話をしよう。
神の声を聞く者ライヒ・イジョルニは戦乱の世を平定し、西ディコンセ大陸に比類なき大国、聖イジョルニ帝国を打ち建てた。広大なる帝国領を十二州に分割し、治世を各地方の領主に任せた。
その帝国領内にありながら、法皇領と帝国十二州、いずれにも属さぬ地域があった。
それがレーエンデだ。大アーレス山脈と小アーレス山脈の
レーエンデが
そこに生きた者達の受難と苦闘。
法王庁が
革命の話をしよう。
物語の始まりは聖イジョルニ暦五二二年二月十日。
麗しき月の夜だった。四年に一度の天満月だった。やがて来る動乱を知らず、世界は深い眠りについていた。迫り来る戦禍を知らず、大アーレス山脈は白く悠然と横たわっていた。
山脈の北、シュライヴァ州の州都フェデルは雪に埋もれていた。街並みは紺青に沈み、大気には静寂が満ちていた。窓の明かりはすでに消え、道行く者の姿もない。刃のような月光が
フェデル城の西の離れで一人の女児が
シュライヴァ州の首長の実弟ヘクトル・シュライヴァと彼の妻レオノーラ・レイムの第一子。後に『レーエンデの聖母』と呼ばれることになる運命の女性。
彼女の名はユリア──
ユリア・シュライヴァという。
第一章 呪われた土地
城の窓辺から朝な夕なに
前を行く黒馬がブルルルッと鼻を鳴らした。あの黒毛は父ヘクトルの愛馬だ。彼とともにシュライヴァ騎士団の先頭に立ち、幾多の死線を駆け抜けてきたフェルゼ馬だ。勇敢な軍用馬だが気位が高い。背に積まれた大荷物が気に入らないらしく、先程から不愉快そうに首を振っている。
思い返せば今朝方まで、この旅にはもう一人同行者がいた。忠実なる使用人のフープが荷を積んだ
「
彼は帽子を取り、その場にひざまずいた。頭を垂れ、身を震わせ、涙ながらに
「レーエンデは神に見放された土地です。踏み入れば銀の悪魔の呪いを受けます。全身を銀の
ヘクトルは馬を降り、急いでフープに駆け寄った。平伏する使用人の肩に手を置いて、その
「フープよ、無理をさせてすまなかった。ここまで運んで
そう言うとヘクトルは驢馬の荷物を自分の軍用馬へと移し替え始めた。それを手伝いながらフープは声を殺して泣いていた。
一人
父上一人だけならば、このような大荷物は必要なかった。フープにあんな悲しげな顔をさせることも、勇敢な軍用馬に大荷物を背負わせることもなかった。私が
来るべきではなかった。
やはり来るべきではなかったのだ。
後悔が胸を
「ユリア」
父の声が聞こえた。
「ここで少し休憩しよう」
ユリアは顔を上げ、周囲を見回した。いつの間にか隘路は終わり、見通しの
手綱を引き、栗毛のフェルゼ馬を止める。地面に降りるとガクガクと
「よく頑張ったな」
ヘクトルが水筒を差し出す。ユリアは礼を言って、それを受け取った。水筒に
「なあ、ユリア」
隣の岩に腰掛けて、ヘクトルは膝の上で手を組んだ。
「フープが言ったことは気にするな。
銀呪病はレーエンデ特有の風土病だ。全身が銀の鱗に覆われていくという
だがユリアにとってレーエンデは
なのに思ってしまったのだ。逃げ出したいと。どこか遠くに行きたいと。
罪悪感に打ちのめされ、ユリアは黙って目を伏せる。
そんな娘の姿を見て、ヘクトルはさらに誤解を強めたようだった。
「心配するな。そう長居はしない。今回の旅の目的は交易路の建設に
「今からでも遅くはない。引き返してもいいんだぞ?」
ヘクトルの優しい声。でも今はその優しさが胸に痛い。
「引き返しません。私はレーエンデに参ります」
「なぜだ? なぜそうまでしてレーエンデに行きたがる?」
たぶんレーエンデでなくてもよかった。行く先はどこでもよかった。私はフェデル城から逃げ出したかっただけ。自分の役目から逃げ出したかっただけ。でもそんなこと、父上には言えない。本当の理由は話せない。だからユリアは今までと同じ言い訳を繰り返す。
「父上からレーエンデの話を聞かされた瞬間、私は彼の土地に恋をしました。あの時から、いつか必ず会いに行こうと心に決めておりました」
それは九年前、彼女がまだ六歳の時のことだった。
東ディコンセ大陸の大部分を占める未開の荒野、通称『東方砂漠』。今から百年ほど前、東方砂漠に暮らす遊牧民グァイ族が『帝国の穀物庫』と呼ばれるレイム州を襲撃した。助けを求めるレイム州に
この時に始まったレイムとシュライヴァの同盟関係は今もなお続いている。シュライヴァ騎士団の騎士団長を務めるヘクトルは、夏が盛りを迎える頃、精鋭部隊とともにレイムへと赴く。国境を巡回し、東方砂漠に目を光らせ、秋の収穫が終わると役目を終えて帰郷する。
聖イジョルニ暦五二七年十一月。国境警備に出ていたシュライヴァ騎士団が州都フェデルに戻ってきた。城の中庭では騎士達とその家族が五ヵ月ぶりの再会を喜んでいた。ユリアもまた中庭に出て父の姿を捜した。が、ヘクトル・シュライヴァはどこにも見当たらない。
「父上はどうしたのですか? どこにいらっしゃるのですか?」
彼女の問いに、副団長のクラヴィウスは言いにくそうに答えた。
「ご安心下さいユリア様。ヘクトル様はご無事です。ご帰還が遅れておりますのは、東部砂漠で負傷した
なんで? とユリアは思った。そんなこと父上がしなくたっていいじゃない、
ユリアは大人しく父の帰りを待った。やがて北からの風が雪雲を運び、フェデルの街並みは白に埋もれた。ベーレの森は綿帽子を
不安に
「父上、早く戻ってきて下さい。母上、どうか父上をお守り下さい」
彼女の母レオノーラはユリアを出産した三日後に天に召された。父の居室には今も彼女の肖像画が飾られている。月光のような白金髪、雪花
ユリアには繰り返し聞かされてきた言葉があった。
「母の
「お母様がいなくて寂しいでしょう?」
優しげな声、同情に満ちた表情、その裏側にはいつだって
「あの娘はちっとも笑わないな」
「天満月生まれの娘は災禍を招くと言うし」
「あれでは嫁の
「本当にシュライヴァの血を引いているのかしら?」
心ない雑言や
「父上、帰ってきて下さい。お願いです。私を一人にしないで下さい」
ユリアは必死に祈り続けた。だが願いはかなわぬまま十三月は終わりを迎え、新しい年がやってきた。新年を祝って浮かれ騒ぐ者達を
それは三月に入って間もない、まだ寒さの残る早朝のことだった。
「ユリア、朝だよ。お目覚めの時間だよ」
耳慣れた声に
「おはよう、俺のお姫さま」
無骨な指が彼女の髪を
夢ではない。これは夢じゃない。そう思った瞬間、涙が
「遅くなってすまなかった」
泣きじゃくる
「長らく肩を並べて戦ってきた戦友のイスマルが重傷を負ったんだ。幸い一命は取り留めたが、右足を切断しなければならなくなった。『潮時だ』とイスマルは言ったよ。『引退してレーエンデに戻るよ』とね。だがフェデル渓谷路は難所が多い。しかもイスマルは右足を失ったばかりで馬に乗ることもままならなかった。一人で行かせるわけにはいかないと思ったよ。だから、ついていくことにした」
ヘクトルはユリアの髪にキスをして、いっそう強く彼女を抱きしめた。
「イスマルを古代樹の森へ送り届けたら、すぐに戻るつもりだった。だが到着直後に大雪が降ってな。例年より一ヵ月も早く渓谷路が雪に埋もれてしまったんだ。そのせいで戻るに戻れず、連絡することもかなわず、お前には
言われるまでもなかった。父の愛を疑ったことなど一度もなかった。しかしどんなに大人びていてもユリアはまだ六歳。不安に押し潰されそうだった日々を、
「れ、レーエンデというのは……そ、そんなに遠いところに、あるのですか」
鼻をすすり、しゃっくりを挟みながら、ユリアは尋ねた。
「お、お帰りが、こんなに遅くなるほど、遠く遠くにあるのですか!」
答える代わりにヘクトルは彼女を抱き上げた。左腕でユリアを支え、もう一方の手で
「ごらん」
父の声に彼女は薄く目を開いた。眼下に広がるフェデルの街並み、その先には深緑色にくすんだベーレの森がある。さらに遠く、青く
「レーエンデはあの山の向こう側にある。大アーレス山脈と小アーレス山脈の間にある森林地帯と、レーニエ湖周辺の高原一帯をレーエンデ地方と呼ぶんだ」
「で、では父上は、大アーレスを越えたのですか?」
「そうだ」
「危なくは、なかったですか?」
「道は
ようやく
「帝国建国以前からレーエンデにはウル族とティコ族という少数民族が暮らしていてな。その独自の文化に敬意を払い、始祖ライヒ・イジョルニは彼らに自治権を与えた。ゆえにレーエンデ地方は帝国内にありながら外地の影響をほとんど受けていない。あの土地では世間の常識は通用しない。血筋も身分も
熱っぽく語る父を見上げ、ユリアは
「レーエンデは不思議の国だ。見るもの聞くものすべてが奇妙で面白い。たとえば古代樹の森に住むウル族は巨木の
途端、ユリアは目を輝かせた。
巨木の家! 光る虫のランプ! まるでお
「木の洞に住むなんて、
「そうだな。ウル族は肌が白く、瞳の色も髪の色も薄くて、本物の妖精みたいだったぞ」
クスクスと笑い、ヘクトルは再び大アーレス山脈へと目を向ける。
「いつかは俺もあの場所で、彼らのように暮らしたい」
それを聞いてユリアは再び不安になった。父上はシュライヴァよりもレーエンデが好きなのだ。いつか私を置いてレーエンデに行ってしまうのだ。そう思うとまた涙が出そうになった。
そんな娘の気持ちを知ってか知らずにか、ヘクトルはユリアの髪をくしゃくしゃとかき回した。
「お前にあの風景を見せてやりたい。お前もきっと気に入る」
口を開くと泣いてしまいそうだったので、ユリアは黙って
ユリアはフェデル城が好きではなかった。彼女を取り巻く人々はよそよそしくて冷たかった。いつかこの城を出てレーエンデに行く。父と一緒にお
「では約束して下さい。今度レーエンデに行く時は、私も一緒に連れて行くと」
「承知した」
ヘクトルは大らかに首肯した。
「シュライヴァの名にかけて誓おう。今度レーエンデに行く時には必ずお前を連れて行こう」
あれから九年、ユリアは十五歳になった。もはや分別のつかない子供ではない。シュライヴァ家の娘が長期旅行に出かけるなど、決して許されないことだとわかっている。しかしヘクトルがレーエンデに赴くと聞いて、いても立ってもいられなくなった。ユリアは父の元を尋ね、「私も連れて行って下さい」と懇願した。「シュライヴァの英雄が約束を破るのですか」と迫った。そんな娘の熱意に押され、ヘクトルはついに首肯した。夏の間だけという条件で彼女に同行を許してくれた。
守り石を握りしめ、ユリアは思う。
あの時、私はレーエンデに恋をした。今も彼の地に憧れている。同行を望んだ理由はそれだけではないけれど、レーエンデに
「父上が言ったのです。『レーエンデは不思議の国だ』と。『きっとお前も気に入る』と」
「ああ──そうだな」
ヘクトルは目を細めた。
「さて、そろそろ行こうか」
ヘクトルが腰を上げる。ユリアも慌てて立ち上がった。
「父上、ここから先は私も歩きます。荷物を半分、栗毛の背中に移して下さい」
「その必要はない。まだまだ険しい上り坂が続く。お前は馬に乗っていけ」
「でも荷物が多いのは私のせいです。なのに私だけが楽をするなんて出来ません」
それ以上、父に物言う暇も与えずユリアは黒毛に歩み寄る。縄を解き、馬の背に積まれた衣装箱を下ろそうとする。
「俺がやろう」
ヘクトルが彼女の手を制した。衣装箱を肩の上へと担ぎ上げ、申し訳なさそうに眉根を寄せる。
「すまないな。お前まで歩かせる羽目になって」
「ご心配なく」ユリアはドレスの
「さすが俺の娘だ」
ヘクトルは
「この先は危険な箇所が多い。油断するな」
緊張の連続に心身ともにくたびれ果てていた。足の裏には
「見えたぞ!」
声を弾ませ、ヘクトルが前方を指さした。
「あれがレーエンデ、古代樹の森だ」
坂道を登り切り、崖の縁に立つ。
眼下に緑の海が広がっている。
「この峠は外地とレーエンデの境だ。レーエンデに来る者、レーエンデを去る者、誰もが等しく立ち止まり、置いてきたものを振り返る。ゆえにここを『見返り峠』と呼ぶのだそうだ」
大きく息を
「ああ、ようやく戻ってこられた」
ユリアは無言で頷いた。初めて見る風景なのに、初めて見たという気がしない。どこかで見たような気もするけれど、どこで見たのか思い出せない。
「おや?」
ヘクトルが首を
「見えるか、ユリア」
「……はい」
樹冠の上にキラキラと光るものが浮いている。
「なぜこんなところにシャボン玉が?」
「シャボン玉ではない。あれは
「泡虫──ということは、あれは生き物なのですか?」
「わからない」ヘクトルはにやりと笑う。「泡虫の正体を知る者はいない。世間の常識は通用しない。レーエンデはそういう場所だ」
名を呼ばれたことに気づいたのか、泡虫の群れが動き出した。ゆるゆると見返り岬に向かって流れてくる。ひとつやふたつならば
見返り峠に押し寄せる泡虫達。それは二人の目前で左右に分かれた。そのまま二人の横を通り過ぎ、後方へと流れ去っていく──かと思いきや、弧を描いて戻ってきた。ユリアとヘクトルを中心に泡虫の群れが大きく
おかえり、おかえり、待っていたよ。
声なき声を響かせて泡虫達が消えていく。
最後に残った一泡が、まるでキスをするように、ユリアの眼前でぱちんと
柔らかなものが唇に触れた。鼻の奥に海が薫った。懐かしい。恐ろしい。恐ろしいのに愛おしい。愛おしいのに悲しくて、なのに嬉しくてたまらない。心が震える。琴線がかき鳴らされる。涙がぽろぽろとこぼれてくる。
「どうしたユリア? なぜ泣いている?」
ヘクトルが尋ねる。心配そうに娘の顔を
しかし確信していた。狂おしいほどに確信していた。
私はレーエンデにやってきたのではない。
レーエンデに
見返り峠を下り、二人は古代樹の森に入った。
森の中はひんやりとして肌寒い。しかし思っていたほど暗くはなかった。木漏れ日に照らし出された
ヘクトルは慎重に森の奥へと進んだ。時折足を止め、何かを探すように木々を見上げた。
頭上でさわさわと枝葉が揺れる。銀色の小鳥が梢を行き交い、
「見ろ、ユリア!」
「あれが古代樹林。ウル族の集落、古代樹林のマルティンだ!」
森が切れ、広い空間に出た。斜めに差し込む光の中、幾本もの巨木が
「おおい、イスマルはいるか?」
口の横に右手を当て、ヘクトルが声を張る。
「俺だ、ヘクトルだ。約束通りやってきたぞ!」
それに応じるように一番手前の巨木の扉が開かれた。
「おう、よく来たな!」
陽気な声とともに壮年の男が出てくる。灰色の髪を首の後ろで三つ編みにした大男だ。ごつい肩、
「久しいなイスマル。しばらく見ないうちにずいぶんと
「そういうお前さんは変わらんなぁ。今年でいくつになるよ?」
「三十五だ」
「そうか、お前さんもついに第三の人生を始める
ヘクトルとイスマルは互いの肩を抱き合い、再会を喜んだ。
「紹介しよう。俺の自慢の娘ユリアだ」
「ようこそ、お嬢さん」
山賊顔の元傭兵は白い歯を見せて笑った。
「俺はイスマル。イスマル・ドゥ・マルティンだ」
名乗りを上げ、肩の高さに左手を掲げる。初対面の相手には左手の
ユリアはおずおずと左手を挙げた。
「初めまして、ユリア・シュライヴァです。その節は父がお世話になりました」
「いやいや、世話になったのは俺のほうさ」
「じゃあ、俺の家族も紹介しようか」
扉の前に数人の女性が立っている。ウル族の民族衣装なのだろう。独特な模様が
「一番大きいのが長女のプリムラ。プリムラにくっついてるのが双子の孫娘、右がペル、後ろにいるのがアリー。その隣にいるのが次女のリリスだ」
「いらっしゃい。お待ちしておりました」
二十代
シュライヴァにおいて黒髪は
「長旅で疲れただろ。話の続きは中で聞こう。リリス、ペル、アリー、客人達の馬を頼む」
イスマルが先に立って階段を上っていく。入れ違いに階段を下ってきた黒髪の少女に、ユリアは手綱を差し出した。
「お願いします」
リリスはひったくるようにそれを奪い取った。
「あんた、さっきからなんなの? あんまりジロジロ見ないでくれる?」
古代樹の中は木の洞とは思えないほど広かった。床には
「狭くて驚いたかい?」
暖炉前の
ユリアは慌てて首を横に振った。
「い、いいえ。幹の中なのに、壁が石みたいだなと思って……」
「古代樹ってのは化石だからな。樹よりも石に近いんだ。階段の上り下りにはちと苦労するが、慣れてしまえばけっこう暮らしやすいところだよ」
イスマルはユリアに座るよう#
「じゃ、さっそく聞かせて貰おうか。シュライヴァの首長は、なぜお前さんに交易路を造るよう命じたんだ? シュライヴァとレーエンデを結ぼうとする彼の真意はどこにある?」
「主目的は通行税を得るためだ」
膝の上に
「レーエンデで作られる農耕具は質がいい。レイム州やフェルゼ州でも需要は高い。レーエンデとシュライヴァを繫ぐ道が出来て、多くの商人がそれを利用するようになれば市場は活性化する。交易が
「けどシュライヴァにはシュライヴァ騎士団がいるじゃねぇか。無敵の騎士団を貸し出して、さんざん荒稼ぎしてきたじゃねぇか。なのに今になって『通行税を稼ぐために交易路を造りたい』とか言われても、
「兄上は
「相応の見返りってなんだ? しみったれた通行税じゃねぇよな? まさかとは思うが、道を造って騎士団を送り込んでレーエンデを支配するとか、ンな馬鹿なこと考えてねぇだろうな?」
「その可能性は否定出来ない」
「おいおい、お前さんはどっちの味方なんだ?」
「俺は外地の者達にレーエンデの魅力を知って欲しいんだ。レーエンデに対する偏見を
「けど、その交易路のせいでレーエンデが戦場になるんじゃ元も子もねぇ」
「交易路には関所を作る。攻めにくく守りやすい難攻不落の
ヘクトルは肩の高さに右手を掲げた。
「シュライヴァ家の名誉に懸けて誓う。シュライヴァ騎士団はレーエンデとは戦わない。レーエンデを戦場するようなことは一切しない」
「お前さん、騎士団長の肩書きは返上したんじゃなかったのか?」
「そのつもりだったんだがな。兄上が許可してくれなかったんだ。俺が騎士団長を辞めたらシュライヴァ騎士団の値打ちが下がるってな。よって俺は休職中だ。今はあの堅物クラヴィウスが団長代理を務めている。『自分には代理など務まりません』と固辞するから、『引き受けないと例のことを奥方にバラすぞ』と脅してやった」
「相変わらず、えげつねぇことをしやがる」
「俺もそう思う」
ひっそりと笑って、ヘクトルは両手を組んだ。
「前にも言ったが、俺はレーエンデが好きだ。いずれはこの地でのんびり暮らしたいと思っている。その夢をかなえるためならば兄上の野望も利用する」
「まったく、お前さんの考えにはいつも驚かされるよ」
「わかったわかった、信じよう。銀呪病の根絶なんつう話は壮大すぎてピンとこねぇが、交易路が出来ればここの暮らしもちったぁ楽になるだろうし──」
そこで何やら言いよどみ、不満げな顔で
「けどなぁ、言っちゃあなんだがウル族の連中は頭が固い。外地との交流することを
「それについては心配していない」
ヘクトルは自信たっぷりに右目を閉じた。
「俺がよく知るイスマル・ドゥ・マルティンは不可能を可能にする男だからな」
「よせやい」
「やってくれるか?」
「対価として塩一袋を所望する」
「土産に持ってきた」
「ありがたい!」イスマルは手を叩いた。「外地の飯に舌が慣れちまうと、レーエンデの飯は味気なくてなぁ」
「聞こえたわよ?」
明るい声が割って入った。上の階の
「私が作るご飯が気に入らないなら、お父さん、自分で作ればいいじゃない」
「違う違う、誤解だプリムラ!」イスマルは慌てて両手を振る。「お前の作る飯が気に入らねぇだなんて一言も言ってねぇ!」
「あらそう?」
「ああそうだとも。塩がふんだんに手に入るようになったら、料理にもっと幅が出るだろ? 小麦が手に入りやすくなったら、毎日真っ白なパンが喰えるようになってチビどもも喜ぶだろ? 俺が言いたかったのはそういうことだよ」
「はいはい、じゃあ、そういうことにしておきます」
プリムラはくすくす笑い、ユリアに湯飲みを差し出した。
「さぁどうぞ。疲れが取れるわよ」
礼を言い、ユリアはそれを受け取った。湯飲みには白茶色の液体が入っている。表面に黄色い油膜が張っている。立ち上る湯気から、甘いような
「
「はい」
「クリ茶って言うのよ」
プリムラは嬉しそうに花の
「ユリアさん、ヘクトルさん、よければ一緒に夕食を食べていきません?」
「お誘いはありがたいが、先に案内人に会っておきたい」
目礼して湯飲みを受け取り、ヘクトルは視線をイスマルへと戻した。
「今夜中に段取りを説明して、明日から調査を開始したい」
「大丈夫、もう話はつけてある」
イスマルはクリ茶を一口飲んだ。
「トリスタンって若者だ。腕も立つし土地にも詳しい。けどちょいと変わりモンでなぁ。昼過ぎには顔を出せと言っといたんだが、あの野郎、まだ来やがらねぇ」
「その男、今どこにいる?」
「まだエルウィンにいるんじゃねぇかな。ああ、エルウィンってのはここから十分ほど南に行ったとこにある一本立ちの古代樹だ。トリスタンはそこで一人で暮らしてる」
クリ茶を飲み干し、イスマルは膝を打って立ち上がった。
「案内しよう。どのみち連れてくつもりだったんだ。エルウィンなら邪魔も入らねぇし、拠点にするにはうってつけだ」
「待ってくれ」ヘクトルは
「トリスタンは変わりモンだが、お嬢さんに手を出すような
「そうか、わかった」
一息にクリ茶を
「案内は必要ない。南に十分の距離なら俺だけでもたどり着ける」
それに──と言って、片目を閉じる。
「鉄足の歩く速度に合わせていたら到着前に陽が暮れる」
「ぬかせ」イスマルはヘクトルを小突いた。「じゃあ明日の朝、様子見がてらウチの#
「了解だ」
ヘクトルが扉へと動き出すのを見て、ユリアは急いでクリ茶を飲み干した。礼を言って立ち上がり、父を追って外に出た。
階段の下ではペルとアリーが
「ありがとうございます」
ユリアが礼を言っても、リリスは鼻を鳴らしただけで、目も合わせようともしなかった。
二人は古代樹林マルティンを離れ、森の小道を南へ向かった。
太陽は西の山頂に近づきつつある。遠くからヤバネカラスの鳴き声が聞こえてくる。朱を帯びた光を浴び、広葉は赤銅色に輝いている。紫色に染まった森、美しく謎めいた
「ごめんなさい、父上」
「あんなに深いお考えがあったとは思っていませんでした」
「ということは、ユリアも俺のこと、考えなしの戦馬鹿だと思っていたんだな?」
そこまでは言わないが、
「すみません」
「謝ることはない。そう思われても仕方がない。だが安心しろ。俺には俺の考えがある。兄上のことは尊敬しているが、だからといって妄信追従しているわけではない」
ヘクトルは愉快そうに笑ったが、ユリアはとても笑う気にはなれなかった。
「ですが、もしヴィクトル様からレーエンデを攻め落とすよう命じられたら、父上は──」
突然ヘクトルは立ち止まった。ユリアを背にかばい、前方の木立を見上げる。冷え冷えとした眼光、引き締まった唇、空気がピリリと張り詰めるのがわかった。肌が
父上は何を見ているの? あの木の上に何かいるの?
生い茂った枝葉は影に沈んでいる。目をこらしても何も見えない。ざわざわと梢がざわめく。それはどこか
「怪しい者ではない。ここにはイスマルの紹介で来た」
ヘクトルは一歩前に出た。左胸に手を当て、正式な騎士の礼をする。
「俺はヘクトル・シュライヴァ。後ろにいるのは娘のユリアだ」
枝の上の木の葉が揺れた。かと思うと、一人の男が飛び降りてくる。
斜めに差し込む赤銅色の夕日、大地に落ちる
ユリアは青年を見つめた。疑惑と困惑が頭の中を駆け巡る。この人、どうして木の上にいたの? あの高さから飛び降りて、どうして平気な顔をしているの? なぜ父上は怖い目で彼を見ているの? この人はいったい何者なの?
「すみません。夕食の準備をしていたら出遅れてしまいました」
涼やかな声音で青年は言った。
「僕はトリスタン・ドゥ・エルウィン。イスマルから団長の案内人を務めるよう言われています」
どうぞよろしく──と言って左手を掲げる。彼の掌は白く、その微笑みは三日月のようだった。切れ長の目は鋭く、なのにどこか寂しくて、ぞくりとするほど
ユリアは思った。
ああ、この人はまるでレーエンデそのものだ。
続きは6月14日発売の『レーエンデ国物語』(多崎礼)で!
【多崎 礼(たさき・れい)プロフィール】
2006年、『煌夜祭』で第2回C・NOVELS大賞を受賞しデビュー。著書に「〈本の姫〉は謳う」、「血と霧」シリーズなど。