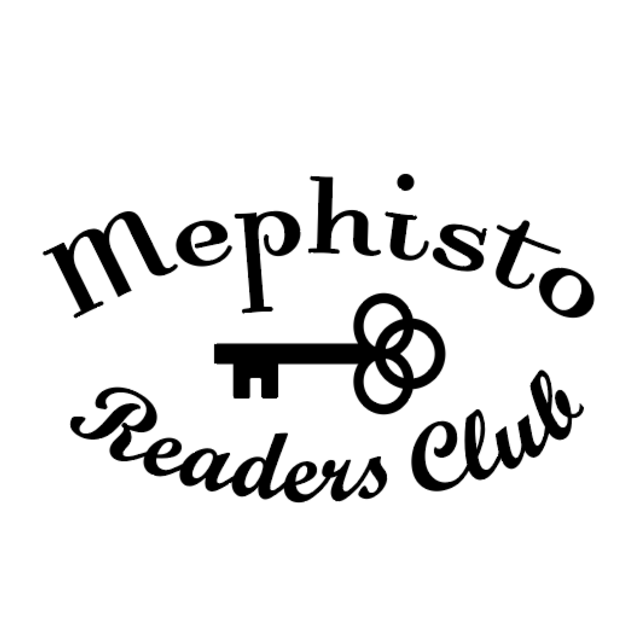『ゴリラ裁判の日』 須藤古都離
文字数 15,111文字
一
窮屈だが心地よい場所で私は寝ていた。
狭く、動きづらい。それでも私は喜びで満たされていた。
私が時間をかけて成長するごとに、部屋はより狭く感じられるようになった。
やがて住み慣れた部屋から旅立つ日が来た。
まるで世界が縮んで、私を押しつぶそうとしているようだった。
洪水のような力強い流れに運ばれ、私は母の胎内から産み落とされた。
私は羊水を
息苦しさはすぐに薄れた。手足を思いっきり動かす。
今まで私を閉じ込めていた柔らかな壁がない。
私はついに自由になったのだ。
私は目を開け、こちらをじっと見つめている母の姿を見た。
母は私を寝かしつけようとして、腕の中の私を優しく揺り動かした。
力強い腕に抱かれて、私は母の鼻歌を聞きながら目を閉じた。
私が生まれたのはアフリカのカメルーン、神秘的な霧が立ち込めるジャングルの中だった。
英語では教育熱心で厳しい母親のことを、
研究所のスタッフたちも、いつも私たちを歓迎してくれた。私は母に抱かれながら、母が研究者たちと話をするのを見ていた。まだ言葉を知らない私には何も分からなかったが、その
その時は思いもしなかったが、彼らは母だけでなく、その娘である私にも大きな期待を寄せていた。特別な母親から生まれた、特別な娘。私は世界でも類を見ない、唯一無二の存在だった。もちろん、私はそんなことは知らずに毎日を過ごしていた。
やがて私が少しばかり成長すると、母が私に言葉を教えてくれた。最初に覚えた言葉はローズ。私の名前だ。母が一番好きな花の名前を、私につけてくれたのだ。
私が簡単な単語を一つ覚えるたびに、母は大げさなほどに喜び、大きな体でギュッと抱きしめてくれた。私は母を喜ばせたい一心で、遊ぶ時間も惜しんで勉強した。
母と一緒に研究所に行き、研究所のスタッフからも言葉を学んだ。覚えた言葉が徐々に増えていくと、それらが結びついて単純な文章になった。言葉と言葉が結びつくことで
月日が
あれは何? これは何? なんでこうなるの?
まだ名前を知らないもの、目につく
〈あなたたち、何をしているの?〉
ある日、私はチェルシーという名の美しい女性研究者にそう問いかけた。
「私たちはみんな、研究をしているのよ」とブロンドの髪をポニーテールにまとめた彼女が答えた。私はその答えだけでは満足しなかった。
〈何を研究しているの?〉
「私たちはゴリラの研究をしているの」
〈ゴリラって何?〉
尽きることのない私の好奇心の強さに彼女は
「ゴリラっていうのは、あなたたちのことよ。森に住む、素敵な友達」
彼女は私が知っている単語を並べて、ゴリラを説明しようとした。
森に住む、素敵な友達。
その時、私は初めて自分がゴリラなのだと認識した。
*******
「今回のケースは難しい話じゃない。そうだろ? 常識で考えれば簡単な話さ」
重い緊張感で満たされた部屋の中で、七番の男性が口火を切った。裁判なんて早く終わらせて、さっさと家に帰りたいのだろう。他の十一人は話の続きを待った。
テーブルを囲んだ十二人の陪審員たちは、それぞれの表情をうかがうように視線を
「三歳の男の子の命が掛かっていたんだ。動物園の判断に間違いなんてないさ。余計な話し合いなんてしなくても、動物園の勝ちで
「四歳よ」三番の女性が七番の男性を訂正した。
「なんだって?」
「男の子は四歳だったの」
「どっちだって同じだろ?」
早く終わらせたいのは七番だけではない。だが、自分たちに課せられた使命を軽々しく考える七番に反感を覚えたのは一人二人ではなかった。
「私も動物園の判断が正しいと思うが、話し合いの過程を省くのには賛成しかねるな。
四番の男性が七番の軽率な態度を
「もちろん、それでも構わないさ」七番は降参だというように両手をあげた。「動物園側に落ち度があると思う人がいれば、俺は意見を聞いてみたいね」
「そうだな。じゃあ基本的な事実を簡単に振り返ってから、動物園の行動に非があったかどうかを確認していこうか。みんな、どう思う?」
四番の男性がテーブルを囲んだ十一人の表情をうかがうと、皆が賛同の意を示した。
「よし、じゃあできる限り簡潔にまとめよう。事件が起きたのは十月二十八日の午後四時。アンジェリーナ・ウィリアムズは二人の息子、ニッキーとアンドリューを連れてクリフトン動物園のゴリラパークに来ていた。母親が目を離した
「私は、実弾を使ったことに疑問を感じます」三番の女性が
「あの場合は麻酔銃じゃあダメだ」二番の男性が女性の言葉を否定するように首を横に振った。「証人の獣医が言っていた通り、麻酔が効果を発するまでの間に、男の子が危険だったと思う。みんなも映像を見た通り、男の子が柵を越えて落ちてから、あのゴリラは倒れていた男の子を捕まえて
「それは実弾でも一緒だったんじゃないでしょうか? 実弾でも撃たれた瞬間に男の子を振り回すことはできたかもしれません」
「だけど、そうならなかった」七番はテーブルの上を見つめたまま発言した。マホガニーの一枚板からなる美しいテーブルで、表面は鏡のように
「専門家はあの時のゴリラの行動に危険性はないと主張していた。ゴリラの子供と遊ぶ時と同じような行動だったとね。我々の目には危険に見えたが、本当はなんでもないことだったんじゃないだろうか?」十一番の初老の男性が次の疑問点をあげた。
「そんなことを後から言うのは簡単さ。でも、ゴリラの子供と同じように人間の子供を扱っていいと思うのか? それに動物園の人間だって、動物の専門家だろ? 彼らが危ないと判断したんだ、専門家でも意見が食い違うような場面だったってことだろうな」二番の男性が反論した。
「ゴリラは絶滅
「ゴリラが希少動物だなんて、動物園が知らないはずないだろう。殺しちゃいけない動物だとしても、避けられなかった。もし動物園に落ち度があるとしたら、安全対策が万全じゃなかったことだろうが、それは今回の争点じゃない」
誰かが散発的に思いついたことを口にし、他の誰かがそれを即座に否定するだけで、議論が盛り上がることはなかった。
「もっと単純な話じゃないでしょうか?」今まで黙っていた一番が、七番に視線を向けながらゆっくりと話し始めた。
「単純な命の選択の話です。人間と動物、どちらの命を選択するか、それだけの問題ではないでしょうか。そのままにしていたら男の子の命が危なかったんです。動物園はゴリラの命と引き換えに男の子の命を救いました。私はその選択は間違っていないと思います」
一番の話を聞いて、二番が大きく頷いた。
「その通りだと思う。人間の命は動物の命に優先される。それは常識みたいなもんじゃないかな」二番は一度口をつぐんだが、思い出したように先を続けた。
「もちろん、人間の命も動物の命も同等だ、って考える人もいるだろうけどな。俺はそんな言葉信じないね。一匹のネズミを助けるために、自分の命を差し出すような
「人の命と動物の命か……。そう考えたらやっぱりゴリラより人間の命の方が大事ですよね」
簡単に答えを出すべきではない。
多くの者がそう思いながらも、既に合意に達しようとしていた。
*******
コンコン、と弁護士のユージーンが目の前のテーブルを軽く叩き、私の注意を促した。それは幸運を祈る仕草のようにも見えた。幸運、それこそ私たちが一番必要としているものだ。既に立っていた彼は、私にも立ち上がるように指示したのだ。どうやら、「全員起立」の一声を聞き逃してしまったらしい。
私は頭の中で巡る様々な思いをかき消すように深くため息をつくと、勢いをつけて前足を床から離し、後ろ足だけで立ち上がった。いつのまにか、裁判官も陪審員も法廷に戻ってきていた。最終弁論ののち、一時間も経たないうちに私たちは呼び戻された。
評決は全員一致が原則のはずだ。それにもかかわらずこんなに早く結果が出た。それが良いことなのか、悪いことなのか、まだ分からない。だが、不安で気が変になりそうだった。
私たちはハミルトン郡一般訴訟裁判所の法廷に集まっていた。正面入り口には壮麗な石柱がずらりと並んでいる、ルネッサンス・リバイバル様式の建物だ。白く高い天井には、碁盤の目のように金色の装飾が施されており、
私はこの裁判の原告、つまり訴えを起こした側だ。しかし、法廷に備えられた木の椅子は小さすぎて、座ることができなかった。人間用の椅子しかないのだから、当然である。私はニシローランド・ゴリラのメスとしては平均的な体型で、百キロほどの体重だが、身長は百四十センチしかない。しかし腕は長く、両手を広げれば二メートルにもなる。人間とは体の造りが違うのだ。
私の体は黒く短い毛に覆われているが、ブルーのパンツスーツを着てきた。今日のために特別にあつらえてもらったものだ。そして、両手にはいつものように特製のグローブをつけている。
私は人間のように原告席に座ることができないので、特別に被告席との間の床に座っていた。そこは部屋のちょうど真ん中であり、裁判長の真正面にあたる。
私は立ち上がりながら陪審員たちの表情を
被告人席に立っているドハーティ園長は、いつもと違ってそわそわしており、
「陪審員の皆さん、評決に達しましたか?」と裁判官の男性が低い声で
裁判長の着ている黒いローブのゆったりしたシルエットは、まるで私たちゴリラの仲間のように見える。尊大に思えるほどに力強い彼の言葉も、好感が持てるものだった。迷いのない、自信に
私は強いものが好きだ。味方であるはずのユージーンにそういった力強さを感じられなかったのが残念でならない。
私は弱いものを信じない。私だけでなく、弱いものに従う動物はいない。一目見た時からユージーンのことを信頼できていなかった。説得力に欠けた最終弁論を聞いた後では更に力不足を感じた。彼の話し方には彼の性格がにじみ出ていた。優しいが、どうにも押しが足りない。それに、彼はまだ若すぎる。学校を卒業したばかりのように、幼い顔つきをしている。裁判にも慣れていないようだった。自信がなさそうな
「はい、裁判長」と陪審員代表の男が軽く
私は強い
ふと、全てから逃げてしまいたくなった。
不安に圧倒され、その場に立っているのが精いっぱいだった。
「評決はどうなりましたか?」裁判官が先ほどと同じ音楽的な声で聞き返す。
私が勝つに決まっている。不安を押しのけるように、そう強く心に念じた。
私が負けるはずがない。夫は銃殺されたのだ。殺した側に非がないとは言わせない。そんな不条理が許されるだろうか? それなのに、周りの誰もが私に黙っていろと、大人しく運命を受け入れろと言った。
私は弱い女じゃない。黙っていられなかった。許せなかった。戦わずにいられなかった。
私が負けるはずがない。
私は食い入るように陪審員代表の男を見つめた。
「ローズ・ナックルウォーカー対クリフトン動物園に関して、私たちは原告の請求を棄却します」
男性は淡々とした口調でそう言った。評決が言い渡されると、傍聴席が騒めいた。裁判長はその評決に満足したように
ドハーティ園長がほっと胸を
男性の述べた評決は信じられなかった。私は負けたのだ。夫を亡くしただけでなく、裁判で負けた。私は暗い穴の底に落ちてしまったように感じられた。
ユージーンが隣にいる私に、
「残念な結果だ。力になれなくて、本当にすまなかった。大丈夫かい?」
ユージーンの弱々しい声が聞こえ、私はなんとか頷いた。だが、大丈夫じゃなかった。
全く、大丈夫じゃなかった。
全身から力が抜けていく。私は前足を下ろし、
私が途方に暮れていると、ドハーティ園長が静かに近づいてきた。
「今回の件は本当に残念だった。君には何度謝っても後悔が残るよ」
ドハーティ園長は私の顔を覗き込むようにして禿げた頭を傾けた。黒縁
「分かってくれるとは思うが、こちらも悪気はなかったんだ。許してくれとは言わないが、これからも動物園でうまくやっていけないかな?」低く誠実そうな声が私の心に触れた。彼の冷静な言葉が余計に私の気持ちをかき乱す。
今回の一件でこじれてしまった関係を元に戻したい、今までのように彼の丸く太った腹に抱きつきたい。そう思う一方で、自分がそんな風に考えていることを否定したい気持ちもある。私はまだ夫の死を受け入れられていないのだ。
ドハーティ園長の困惑顔を見るのは私としても心苦しい。だが、今は自分の気持ちをどう整理して良いか、全く分からなかった。たった一言で告げられた評決に、私の全てが否定された気がした。陪審員の間で、一体どんな審理が行われたのだろうか。私には知る由もなかったが、それを考えるだけで胸が痛んだ。
今は誰とも話したくない。自分の怒りを心の中に抑えておくだけで精いっぱいだ。私はドハーティ園長から顔を背けた。出口に向かって
ドハーティ園長は私の態度に腹を立てたのか、「六年だ! 私はオマリを六年間も見守ってきた。私の家族でもあったんだ。悲しんでいるのが君だけだと思ったら間違いだぞ!」と声を荒らげた。
私はその声も聞こえない振りをして、ホールを急ぎ足で駆けていく。厚みのある黒いグローブが白く
その瞬間、私は薄暗いジャングルの中を駆け抜けているような気分になった。私は
実際には私は綺麗に清掃された、数々の調度品で飾られたホールを、走り抜けているだけだった。周りに居合わせた人たちは驚いた表情で私を見つめている。全てが止まったように静かなホールの中を、私とチェルシーだけが走っていた。
「ローズ、待って!」なんとか私に追いついたチェルシーは顔を真っ赤にしている。「外には記者が大勢押しかけていると思うの。今後のためにも、そんなに取り乱した姿を見せない方が良いと思う。少し落ち着いてから外に出ようよ」チェルシーは声も絶え絶えだ。
私はゆっくりとその場に止まり、チェルシーに向き直った。私は彼女に自分の気持ちを伝えるために、手話を使った。
「ごめんなさい。負けるなんて思ってなかったから。どうしていいか分からない」
私はアメリカ式の手話を使う。両手に装着したグローブがその動きを認識して音声を発する。グローブに埋め込まれたスピーカーは他の人が話すようにスムーズな発話をする。私の手話の
「そうね。本当、こんなことになるなんて思わなかった」チェルシーはしゃがみこんで私を抱きしめた。
「あなたは頑張った。でもどうしようもないことってあるんだよね」
私は英語を聞き取ることができるが、チェルシーはいつでも私が分かりやすいように、喋りながら手話を使う。
「でも、メディアの人たちはあなたのことなんて考えてくれないよ。容赦なく
私は右手の拳を自分の頭の横に持ってくると、人差し指をピンと伸ばした。その動作を認識したグローブが「分かった」と発話した。
バタバタと足音が聞こえ、後ろを振り向くとユージーンがやっと私たちに追いついたようだった。ユージーンは私のすぐ近くまで来ると、疲れ切ったように両手を
「遅くなった。ごめんね。ローズは大丈夫かい?」
私は大丈夫じゃなかった。裁判に負けて大丈夫なはずがない。それなのに、何度も同じことを聞かれて私は腹が立った。大丈夫じゃないと伝えたところで、結果が変わるわけではないのに。
「今は話したくない。後で連絡する」
私がそう伝えると、ユージーンは心なしか少しホッとしたような表情を見せた。
「分かった。今後のこともちゃんと話さないとね。それと、メディアの連中がいっぱい外にいるだろうから、毅然とした態度でね。何も話さなくていいから」
チェルシーとその話をしたばかりだというのに、ユージーンは得意げに言った。私はユージーンに
「じゃあ、僕は帰るよ。何かあれば、連絡してくれ」
ユージーンの声が聞こえたが、私は振り向かずにチェルシーと目を合わせた。たとえ手話を使わなくても、チェルシーには私が何を考えているか伝わっているような気がした。もうユージーンに頼ることなんてない。彼を信用したのが間違いだった。
ユージーンの足音が遠ざかっていくのが聞こえた。
チェルシーは一息つくと「もう行こうか?」と言った。私はそれに軽く頷いて応えた。
「じゃあ、焦らずゆっくりと歩いて、一緒に外に出よう。マスコミが押し寄せてきても、私が守るからね」
チェルシーは軽く微笑んだ。グレーのジャケットのポケットから携帯端末を取り出すと、電話をかけて端末を耳に当てた。
「サム? 私よ。うん、もう終わった。車の準備をしてくれる?」彼女は短いメッセージを伝えると、私を見た。
「今、サムが来てくれる。車が見えたら、一直線に向かって行って、すぐに乗ろうね。マスコミには何も答えなくていい。絶対に私のそばを離れないでね。分かった?」
「分かった」私はさっきと同じジェスチャーを繰り返した。
「よし、じゃあ行きましょう」チェルシーは私の肩を優しく撫でた。
私たちはゆっくりと階段を降り、広々としたエントランスに向かった。入り口の端、柱の
チェルシーは私をチラリと見て微笑んだ。私は外のマスコミを
「大丈夫。なんとか二人で乗り切ろう。ほら、車が来た。準備は良い?」
私は軽く頷き、グゥームと低く
真冬のシンシナティは恐ろしく寒い。昨晩降った雪が、まだ建物や地面を白く輝かせている。私が育ったカメルーンでは、冬でも二十℃を切ることがほとんどない。
アメリカに来て初めて見た雪は美しく感じられたが、その冷たさは故郷から遠く離れてしまったことを思い出させた。
一陣の風が吹き、私は身を切るような寒さに体を震わせた。早く車まで移動しないと。
「よし、行くよ。何を聞かれても答えなくて良いからね」チェルシーは私に手を添えたまま、私に歩き出すように
リポーターの一人が私たちに気づき、マイクを向けて近づいてきた。私たちはすぐに群がる報道陣に取り囲まれた。
「敗訴とのことですが、今のお気持ちはいかがですか?」
「敗因はなんだったと思いますか?」
「今後、動物園との和解の道は残されていると思いますか?」
四方からマイクが私に突き付けられ、一斉に質問が浴びせられた。私は恐ろしかったが、同時に不思議な
敗因? そんなのは陪審員に聞けばいい。彼らがこの裁判の結果を決めたんだ。
そう、全ては陪審員が決めたことなのだ。十二人全員、人間の陪審員たちが。私の立場を理解してくれる者なんて一人もいなかっただろう。
「ノーコメントです」チェルシーは
「評決は妥当だったと思いますか?」
「クリフトン動物園に伝えたいことはありますか?」
私は言われた通り、黙ってマスコミの間を通り抜けていた。だが、マスコミの熱意を間近で感じたことで、興奮を覚えた。
マスコミの連中が踏み溶かした雪が、びちゃびちゃと私の服とグローブを汚す。
裁判は
「おい、ゴリラ! こっち向けよ!」
背後から信じがたいほどに
四足歩行する私の目線は低く、周りを固めている報道陣から見下ろされている。
「ローズ! こっちよ、ローズ!」チェルシーの声が聞こえるが、人ごみに
「上訴する予定はありますか?」スタイルの良い女性キャスターが私の前に立ちはだかった。私は彼女の横を押し進もうとした。だが彼女は人の良さそうな魅力的な笑顔を
上訴すべきなのか? もともとそのつもりはなかった。負けたらどうしようなどとは考えなかったのだ。
「今のお気持ちは?」女性キャスターは私が考え込んだのに気が付くと、質問を重ねた。私はチェルシーの助けを必要としていたが、彼女はマスコミの外に押し出されてしまった。質問に答えなければ通してもらえそうもない。
私は一言で答えようとした。指を広げた両手を胸の前にかざし、勢いよく上外側に広げた。
「私は憤りを感じている」
そうだ、私は憤りを感じている。だがそれだけではない。右手を首元に持っていき、何かを握りつぶすような動作をした。「私は恥ずかしい」
「私は夫を奪われた。正義を求めたが、拒否された。
私が語り出すとシャッター音が一層高鳴り、報道陣が活気づいた。グローブの発する味気ない口調が不快に感じられた。思わず、
「今後はどうするおつもりですか?」
「何も考えていない。私は
私の言葉にその場がどよめいた。喋らない方がいいと思ったが、止められなかった。
「正義が人間に支配されているとは、どういう意味ですか?」別のキャスターが質問を続けた。
「裁判官も陪審員も全て人間。誰も私たちゴリラのことを理解しない」
私がそこまで話した時、チェルシーが群衆に割って入り、私を車まで誘導した。
彼女が後部座席のスライドドアを開けてくれ、私は車に乗り込む。サムが前方から不安そうにこちらを覗いている。裁判の結果を聞きたがっているのだろう。サムは私の後に乗り込んできたチェルシーの表情を見て敗訴を悟ったようで、そのまま何も言うことなく車を前に進めた。
「話をしないでって言ったのに……」私のシートベルトを代わりに締めながら、チェルシーが小言を漏らした。
「正義は人間に支配されている、だなんて。きっと誤解されちゃうよ。変な報道をされたら、あなたのイメージが悪くなっちゃうかもよ」彼女はそう言いながら助手席に移動した。
車はシカモア・ストリートを通り過ぎると、オーバーン・アヴェニューに合流した。
「本当のことを言っただけ。誰も私のことを理解してくれない。人間は動物のことなんて考えてない」チェルシーの小言に苛立ちを覚え、私は反論した。
「そんなこと言わないで。今回は難しいケースだったんだよ。前例がない裁判だったんだし」
道路を挟む並木は既に葉が落ちきっていた。こんなに
ジャングルでは葉が落ちきるなんてことはない。いつだって数えきれないほどの枝葉が空を覆いつくしている。
雪の坂道で
私は故郷の群れを思い出した。いつも一緒に遊んでいた兄弟たちのことを。彼らは私のことを覚えているだろうか。
もうすぐ動物園に着く。だが、まだ動物園には帰りたくなかった。
どこまでも遠く、誰も私のことを知らないところまで逃げてしまいたい。
だが、どこまで行ったとしても、私を知らない人などいない。アメリカに来て一年半しか経っていないのに、有名になりすぎてしまった。
私はジャングルに戻りたかった。私が生まれ育った、動物の楽園に。
もちろん、帰ることなど許されないだろう。
私は私のものではないのだから。
私はアメリカのもの。アメリカがカメルーンから借りたものに過ぎないのだ。
私がここにいるのは取引の結果であり、私の自由意志でそれを覆せるとは思えない。
この裁判の結果も、とどのつまりはそういうことなのだろう。
私たちゴリラが動物である以上、人間のように扱われることはないのだ。
車はマーティン・ルーサー・キング通りを横切り、ヴァイン・ストリートへ流れていく。
民権運動のリーダーの名前を冠した道路はアメリカ中にあるが、シンシナティのマーティン・ルーサー・キング通りは町を東西に結ぶ重要な幹線道路だ。私は彼の名を聞くたびに、その功績に思いをはせる。
彼には素晴らしい夢があった。彼なら、私の状況をどう考えてくれただろうか。
私は窓の外を見ながら、ユージーンとの打ち合わせを思い出した。今思えば、彼は最初からオマリの事件を真剣に考えていなかったような気がする。なんで裁判を起こすのか、とユージーンに問われて、私は
「夫が殺されたら、警察を呼ぶ。犯人が裁かれないなら裁判を起こす。普通のこと。私は間違ったことをしてない」私の手話にあわせて発する機械音声は一定の
私は間違ったことをしていない。そう思っていた。
だが、陪審員たちはそう思わなかったようだ。
助手席のチェルシーが後ろを振り返り「もう動物園だよ。降りる準備をして」と告げた。
「動物園には戻りたくない。あそこにはもういられない」
オマリが殺されてから裁判が始まるまで、まるで何もなかったかのように動物園で暮らさざるを得なかった。私は怒りも不満も
だが、ドハーティ園長と裁判で争い、こちらが負けてしまっては、もうクリフトン動物園に戻ることなどできない。
「動物園に戻らないって、じゃあどうするつもりなんだ?」サムが驚いたように言った。彼は喋りながらも、まだ動物園の駐車場を目指して運転していた。
「チェルシーと一緒に暮らす」
「ローズ、私もできれば一緒に暮らしてあげたいけど。狭い部屋だし、難しいな」チェルシーは申し訳なさそうに言った。
「他の動物園に引き取ってもらう手はある。もともと、繁殖がうまくいかない場合はその予定だったしな」バンを駐車場に
「私たちで次の動物園を探してあげるから、安心して。できるだけ早く移動できるようにする。でも、今のところはこの動物園にいてもらうことになるから、残念だけど我慢してもらうしかないわ」
二人の言葉は心強かったが、それでもまだ我慢を
チェルシーはバンの後部座席まで来て、私の
「ローズ、大丈夫?」
私は人差し指を曲げて机をたたくように動かし、そのあとで両手の拳を胸の前で交差させた。それを見たチェルシーは瞳に涙を浮かべながら、腕を大きく広げ私を抱きしめてくれた。その次の瞬間に少し遅れて「抱きしめて欲しい」とスピーカーから機械音声が流れた。
「あなたは頑張った。私はあなたのことを誇りに思う」チェルシーの言葉を聞きながら、私は虚脱感を覚えた。悔しさとやるせなさに私は押しつぶされそうだった。私には時間が必要だった。
「一人にして」と私が伝えると、サムとチェルシーは気持ちを
「じゃあ、私たちは車の外にいるわ。気持ちが落ち着いたら教えて」
私はバンの中に取り残された。
どうして私はこんなことをしているのだろう? 普通のゴリラのようにジャングルで生きるわけでもなく、動物園で大人しく暮らすわけでもなく。
私はゴリラなのに、人間のように考え、人間のように行動する。今まではそれが嬉しかった。私は特別な存在で、幸せだった。だが、私が普通のゴリラではないからこそ、こんな苦しみを味わうことになった。他のゴリラや野生を生きる動物が決して知ることのない、屈辱と
つい一年半ほど前まではジャングルで幸せに暮らしていたのに。全てが突然目まぐるしく変わってしまった。
どうしてこんなことになってしまったのだろう?
振り返ってみると、全てはあの日に始まったのだ。
アイザックという一頭のゴリラと出会った日、私の人生は動き出していたのだ。
▶▶▶この続きは3月15日発売の単行本でお楽しみいただけます。
【MRC会員の感想はこちら】
【須藤古都離(すどう・ことり)プロフィール】
1987年、神奈川県生まれ。青山学院大学卒業。2022年「ゴリラ裁判の日」で第64回メフィスト賞受賞。