『クメールの瞳』斉藤詠一
文字数 20,158文字
第64回江戸川乱歩賞を受賞した『到達不能極』が、「賞はじまって以来、最大スケールの冒険譚!」とたちまち話題沸騰!
あれから3年――。
斉藤詠一さんの待望の最新刊『クメールの瞳』が絶賛大大大好評発売中です!
――あぁ、すっかり忘れていた、こういうロマン。説得力のある「嘘」を書くのが小説家の醍醐味だ。
と今野敏さんからもコメントが届いている本作!
刊行を記念して、その冒頭を特別に無料公開いたします!
序章
丸い視界の中、波打ち際の岩に休む鳥が見える。
大きさは、ハトくらい。全体に灰色で、頭は黒。アジサシの仲間のようだ。アジサシは世界中に約四十種が分布し、日本では主にアジサシとコアジサシの二種が見られるカモメ科の渡り鳥である。だが双眼鏡の向こうの、鮮やかな赤色のくちばしと足は、普通のアジサシよりも短い。畳んだ羽から、長い尾が飛び出ているのが目についた。
──キョクアジサシか。
興奮のあまり視界が揺れる。平山北斗は自らを落ち着けるように深呼吸すると、双眼鏡を握りなおした。
キョクアジサシは、地球上で最も長い距離──北極・南極間を渡る鳥である。渡りのルートから外れた日本には、台風に流されて迷った個体がまれに飛来する程度で、観察記録はごく少ない。会社員と兼業で(内心ではこちらが本業なのだが)カメラマンをしている北斗といえど、見るのは初めてだった。
──通り過ぎたばかりの今年最初の台風が、こんな置き土産を残してくれたとは。
ここは、神奈川県のとある海岸である。複数の撮影地候補からこの場所を選んだのは正解だったようだ。
傍らに置いていたカメラの三脚を摑み、急いで位置を修正する。その時ふいに、羽織っているカメラマンベストの、いくつもついたポケットの一つが振動し始めた。電話だ。
おいおいこのタイミングでかよ、と思いつつ、マナーモードで震えているスマートフォンを取り出す。画面には、「樫野先生」と相手先が表示されていた。
──出ないわけにはいかないか。
「もしもし、平山です」
少しだけ、不機嫌な声になってしまったかもしれない。
『ああ、平山くん。申し訳ない、忙しいところだったかな。樫野です』
白い顎髭をたくわえた優しげな顔が、頭に浮かぶ。電話をかけてきたのは、学生時代の恩師にして、今でも写真の仕事を紹介してくれている樫野星司教授だった。
「お久しぶりです。あの……いま撮影に来てまして。先生、すごいですよ。キョクアジサシがいます」
相手は、鳥類学研究室の教授である。きっとこの興奮を理解してくれると思ったのだが(そして電話もかけなおしてくれることを期待したのだが)、樫野教授の返事は意外なものだった。
『そうか……すごいな。でもすまない、大事な話があるんだ』
キョクアジサシよりもですか、と危うく口に出しそうになるのを我慢した。そこまでの用件とはなんだろう。樫野先生の声は、普段より硬いような気もする。どうやら本当に大事な電話らしい。北斗は、片手で操作しかけていたカメラから手を離した。
「なんでしょう」と訊くと、わずかな沈黙を挟み、電話の向こうで樫野教授は言った。
『……ちょっとわけがあって、君にいったん預けたいものがあるんだが、頼まれてくれるかい』
「どうしたんですか、急に」
キョクアジサシが動いているのがわかったが、それどころではなさそうだ。無意識に、スマホを持つ左手に力が入る。
『もしかすると、それで迷惑をかけてしまうこともあるかもしれないが……』
「迷惑だなんて思いませんが……。その、預けたいものって、何なんですか」
『電話ではあまりはっきり言わないほうがよさそうなんだ。かといって、会って話す時間はないかもしれなくてね。そういうものがあるとだけ、伝えておくよ』
──何を言っているんだ、先生は?
「すみません、お話が見えないんですが……僕に預けたいというものは何で、どこにあるんでしょうか」
もう一度同じことを訊いた北斗に、樫野教授は急に懐かしむような口調になって答えた。
『覚えているかなあ。昔、片づけ下手の私に、君がアドバイスをくれた時のこと……。本当にすまないが、課題みたいなものだと思ってくれ。それじゃあ、頼むよ──』
「あっ、先生、ちょ……」
それきり、電話は切れてしまった。
いったい、今のは何の話だったんだ──。
戸惑う北斗の視界の端で、キョクアジサシが青い海原へと羽ばたいていった。
第一章 遺物
一八六六年 インドシナ半島南部 フランス領コーチシナ
まとわりつくような湿った空気の中を、どこからか魚醬の匂いが漂ってくる。絶え間なく響く、街のざわめき。時折、大きな怒鳴り声も聞こえてくるが、フランス海軍少尉ルイ・ドラポルトにはその意味がよくわからなかった。コーチシナに着任して一年近く経つものの、現地の言葉はほとんど理解できないままだ。
サイゴン港に設けられたフランス海軍工廠内、士官食堂の、海を望むテラスである。十二月というのに、陽射しは夏とたいして変わらない。パラソルの陰のテーブルで、ドラポルト少尉は古い友人、フリエ・デンクール陸軍中尉と向かい合っていた。
「フリエ。まさか、故国から遠く離れたこんな場所で再会できるとはね。驚いたよ」
「ちょうど君が探検から戻ってきた時に俺の船が入港したのも、神の思し召しだろう」
話しながら、デンクールは顔の周りを飛び交う蠅を手で追い払っている。
「平気かい」ドラポルトは友人に言った。
「ああ。メキシコと変わらないさ。慣れてしまえばどうということはない。そうだ……。再会の記念に渡すつもりで、持ってきたんだ」
デンクールは軍服のポケットから小さな布袋を取り出すと、テーブルの上に置き、ドラポルトに開けるよう促した。
華やかな刺繡が施された袋には、骸骨を象った小さな人形が入っていた。骸骨といっても、グロテスクなイメージはない。鮮やかな極彩色の服を着せられ、しゃれこうべに模様が描かれた人形は、どこかユーモラスで可愛らしくもあった。
「メキシコには『死者の日』という風習があってね。その日は家を飾りつけ、ご馳走を食べながら、この世を去った者の思い出を皆で語り合うんだ。彼らは、死を暗いものとは捉えていないらしい。街中がお祭りのようで、これはその時に買ったものさ。カラベラといって、お守りだそうだ」
「なるほど、面白い」
軍人であるとともに探検家でもあるドラポルトにとって、確かに興味深い話だった。人形も、異文化の美術品としての価値を感じさせる。
「気に入ったよ。ありがとう」
ドラポルトは礼を言いながら、ふとあることを思いついた。自分も、返礼にちょうどよい品を持っているではないか。
ただ、それを本当に渡してよいものか。迷いつつ、ドラポルトは話を続けた。
「メキシコでは大きな働きをしたそうじゃないか。噂に聞いたよ、デンクール中尉殿」
二人が海軍、陸軍それぞれの士官学生だった一八六一年、フランス第二帝国皇帝ナポレオン三世はメキシコに出兵し、フランスの傀儡である第二次メキシコ帝国を建国していた。士官学校を卒業したばかりのデンクールはそこへ派遣され、反仏のメキシコ共和国軍との戦闘に参加したのだ。
メキシコ国民の支持を得た共和国軍の前に、フランス軍は次第に劣勢となったが、その状況下でもデンクールの指揮する小隊は常に戦果を挙げ続けたという。
「よしてくれ。中尉といっても、前任の小隊長が戦死したから野戦昇進しただけさ。昔のとおりフリエでいい。君のほうは、海軍軍人というよりはすっかり探検家に見えるぞ。まあ、ロシュの街一番のやんちゃ坊主ルイには、お似合いな気もするが。この前はカンボジアに行ったんだって?」
「ああ。調査隊の本隊はまだ向こうにいるんだが、僕たち分遣隊は先に戻ってきたんだ。そのおかげで君に会えたわけだ」
ドラポルトは、フランス植民地帝国学術調査隊の隊員として、この地に派遣されていた。
遡ること四年前の一八六二年、列強各国に遅れまいとアジアへ進出したフランス帝国は、阮朝との抗争の末にインドシナ半島南部を確保、仏領コーチシナと名付け植民地経営に乗り出していた。そしてこの一八六六年、ドラポルトたち調査隊はコーチシナ総督府の置かれたサイゴンからメコン川を遡上、カンボジアを目指したのだった。
調査隊は、純粋に学術目的のものではなかった。フランスが保護条約を結んだカンボジアとコーチシナの国境を明確にすること、さらにはメコン川を北上した先、中国との通商ルートを探ることなどが戦略目標として課せられていたのだ。また、植民地の宗主国フランスの存在感を誇示するという背景もあった。それゆえに調査隊の中に学者は少なく、隊員のほとんどが軍人によって構成されていた。
「それにしても、お互い世界中を飛び回っているな。君は、今度は東の果ての国か」ドラポルトは、感慨を込めて言った。
「東の果てだなんて言い方は、まるで地球平面説だな。海軍の人間とは思えないぞ」
そう笑って答えた直後、デンクールは顔をしかめた。どこからか漂ってきた、甘い腐臭のせいだろう。
「やっぱり、まだ慣れていないようだな」今度はドラポルトが笑う。
「戦争だったら別だがね。火薬の匂いがする場所なら、どこだって慣れてみせるさ」
デンクールが傷痕の残る額の下、目をぎらりと光らせる。その片手は、いつの間にかテラスに入り込んだ野良犬の頭を撫でていた。
「そうは言っても、今は世界中どこも落ち着いているんじゃないか」
「ああ。皇帝陛下は、メキシコからの撤兵を決めた。プロイセンとオーストリアの戦争にも、我関せずを決め込んでいる。実はアルジェリア行きも打診されたんだが、冗談じゃない。あそこは死ぬほど退屈だという噂だ。だから、この任務を志願したのさ」
その瞳を見たドラポルトは、自分たちが少年と呼ばれていた時代はもはや遠くに去り、二度と戻らぬことを悟った。
──戦争か。戦争が、あの優しかったフリエを変えてしまったのだ。
「どうした?」
気づかぬうちに、硬い表情になっていたようだ。訝しげにデンクールが訊ねてきたので、ドラポルトはごまかした。
「いや、なんでもない。すまん」
「メキシコにいた時に、わかったんだ。俺は、ある種の戦ぐるいなのかもしれない。戦争のあるところでしか、生きられない。今のフランスに、俺の居場所はないのさ」
感情が昂ったのか、デンクールの声が大きくなった。犬が慌てたように離れていく。
「でも、君の行く先では、戦争はしていないんじゃないか」
「匂うのさ」デンクールは、どこか陰のある笑顔をみせた。「きっと、戦になる。俺の勘は、当たるんだ」
「そうか……。気をつけてくれよ」
ドラポルトは、友人が向かう国についてよくは知らない。デンクールたち軍事顧問団十数名は、バクフと呼ばれるその国の政府の依頼を受け、近代的な軍隊を訓練するために派遣されるという。
メンバーはいずれも、遠い極東の地までフランスの栄光を知らしめんとする理想に満ちた、高潔な思想の持ち主と聞く。軍の一部にみられる、腐敗などとは縁がないだろう。
ドラポルトの心は決まった。やはりあれは、この古い友人に渡すのが一番だ。
隣の椅子に置いた鞄から、ドラポルトは紙の包みを取り出した。テーブルの上をデンクールのほうへ滑らせながら言う。
「戦に行く君に、僕からの餞別だ」
デンクールが包みを解くと、手のひらに収まるくらいの、青銅製らしいリング状のものが現れた。全周にわたって精緻な文様が刻まれているが、何より特徴的なのは、その中心に透明な水晶が嵌め込まれていることだった。水晶は、レンズのように真ん中が膨らんでいる。
「なんだい、これは……」
デンクールは、様々に角度を変えてそれを眺めた。「こうやって見ると、目玉みたいだな」
「カンボジアで見つけてきたのさ。青銅の部分に一ヵ所、穴が開いているだろう。そこに紐を通し、首から下げてペンダントにするものだと考えられる。かつて存在した、クメール王朝の遺物だ」
「大事なものなんじゃないか。いいのか」
「かまわないよ。お守りだというので身につけていたが、君にはメキシコのお守りをもらったし、交換だ。これは、そもそも戦士のお守りらしいからね。君のほうがふさわしい。似たようなものは他にも収集したし、一つくらい問題ないさ」
その話は、真実ではなかった。実際にそれが何かはわかっていない。しかし持っていても学術的に調べることは期待できないどころか、むしろ危険なのだった。
ドラポルトの頭に、それを見つけた時の記憶がよみがえる。
今回の探検の総指揮を執ったドゥダール・ドゥ・ラグレ海軍大佐は、探検の途中、隊を二つに分けていた。コーチシナ駐留部隊から異動してきたばかりのガルシア中尉が、メコン川の支流を遡ったジャングルにあるという未知の遺跡の調査を強く進言したためだ。
ドラポルトは、ガルシア中尉が直接指揮する十名ほどの分遣隊に編入され、その遺跡へ向かうことになった。本隊と別れて小さな船で支流を遡り、さらに一週間。緑の地獄のようなジャングルをさまよった末に姿を見せた、壮麗な廃墟の様子は今でも目に浮かぶ。気が遠くなりそうな数の砂岩や煉瓦を積み重ね、美しい直線と柔らかな曲線を複雑に組み合わせて造られたその建物こそ、数百年の昔に滅び去った、異教徒の文明の遺跡であった。
左右対称の建物は一部が崩壊し、蔦に覆われかけていた。かつての寺院だろうか、横に長い回廊の向こうには塔があり、その四面には周囲を見渡すように菩薩の微笑みが彫り込まれている。湿気に白く霞んだ空気の中、黒いシルエットとなったジャングルを背景に浮かび上がる様は、さながら幻影の城だった。
崩れ落ちた部分から遺跡の中に入ったドラポルトたちは、瓦礫の山を苦労して乗り越え、物陰にひそむ蛇に怯えつつ、その寺院跡を調べ回った。ところどころ開いた穴から射し込む光にぼんやりと照らされた建物の中は、石材の冷気で、ジャングルの中より涼しく感じられた。
祠堂らしき建物だけは、何か貴重なものが隠されているかのように重い石の扉で塞がれていたが、苦労して数人がかりで押しのけ、中に入ることができた。ランプを片手に部屋へ踏み込んだドラポルトたちが見つけたのは、山と積まれた遺物の数々だった。シヴァ神を象った精緻な彫像に、美しい模様の施された金属器……。
ヒンドゥー教や仏教の混淆した影響が見て取れる、それら貴重な遺物を、ガルシア中尉の命令で隊員たちは手あたり次第袋に詰め込んだ。誰にも罪悪感はなかった。ヨーロッパ列強は、各国の考古学的遺物を競い合うように持ち帰っては、ルーヴル美術館や大英博物館といった施設に収蔵していた。放っておけば遺跡の崩壊とともに無に帰してしまうのだから、むしろ善いことをしているのだという意識が強かった。それらを持ち去り、調べることこそが、自分たちにとっての正義、使命なのだった。
その部屋の奥には、もう一つ小部屋があった。そっちには何もなかったぞという仲間の声は聞き流し、ドラポルトは足を踏み入れた。
石の壁から放たれる冷気が、一段と増したような気がした。床面には、確かに何も置かれていない。だが見回せば、壁の一部には人や動物を象ったレリーフが彫られていた。赤みを帯びた砂岩に、躍動する人々が緻密に描かれている。何かしらのストーリーが込められているようにも見えたが、刻まれた文字も、語り継がれた伝承もないのであれば、いにしえの物語はもはや永遠に失われたも同然であった。
ただ、舞い踊る数人の踊り子たちが一様に、首からペンダントを下げているのはわかった。リングのような形のそれと同じものを、横に長いレリーフの隣の場面では、男が手に取っている。大勢の兵の奥に座る、王の格好をした人物だ。その人物は、別の場面ではペンダントを目の前にかざして覗くような仕草をしていた。
そして、その王らしき人物の、レリーフの中の視線を追った先にもペンダントの形があった。レリーフの一部が膨らみ、暗い部屋の中で輝きを放っている。
違和感を覚えたドラポルトは、レリーフの膨らんだ部分に手を伸ばした。隙間に指を入れると、それは容易く外れ、手のひらにおさまった。本物のペンダントが埋め込まれていたのだ。
薄暗い中でわかりづらかったが、ペンダントは青銅でできているらしく、リングの真ん中には丸い水晶が嵌められていた。
なぜこれだけが、レリーフの模様に隠すように取りつけられていたのだろう。
すぐに答えが出るはずもなかったが、調べる価値はある。
そう考えたドラポルトは、ペンダントを自分のポケットに入れ、皆のところに戻った。他の遺物と一緒に、袋へ詰め込んだりはしなかった。私欲にかられたつもりはまったくなかったのだが、結果としてそれが、ペンダントを救うことになった。
分遣隊が帰還したのち、ドラポルトは、持ち帰った遺物のすべてがガルシア中尉により売却されたのを知った。記録も、改竄されていた。遺跡を発見できず、調査隊は手ぶらで帰還したとされていたのだ。
今にして思えば、ガルシア中尉が探検に出発する直前に着任したのも、謀略の一部だったのだ。コーチシナに駐留するフランス軍の中には、植民地の財源でもある阿片を通じて現地の裏社会と手を結ぶ、腐敗した一派が存在していた。
隊員たちは、あっけなく買収された。遺物の売却益の一部を回すだけで、そのくらいの金は用意できたのだろう。ドラポルトにも話はあったものの、金は受け取らなかった。それだけは、してはならないと思ったのだった。その代わり他言しないことを約束させられたが、破ったらどうなるかは、考えなくてもわかる。進んで告発する勇気はなかった。命は惜しかったし、半生を賭ける覚悟でやってきたこの土地での探検をやめることはできない。
問題は、例のペンダントだった。金を受け取らなかったため疑念を持たれたのだろう、不在時に部屋を調べられた痕跡を見つけたこともあった。ペンダントを隠し持っていた事実が露見すれば、何をされるかわからない。このまま持っていては、危険だ。
もちろん、今さらガルシア中尉に渡すつもりもない。そんな時にデンクールと再会できたのは、ドラポルトにとって神の導きのように思えた。
これは、戦場へ赴く古い友人に、餞別として渡すのが一番よいのではないか──。
気づけば、デンクールはドラポルトをじっと見つめていた。まるで、本当の事情を見透かすかのように。
やがて、デンクールはふっと目の力を緩めて穏やかに笑った。
「ありがたく受け取るよ。……ルイ、またいつか会おう。その時には、君は軍人ではなく本当の探検家になっているかもしれんな」
デンクールはそう言って、空を見た。いつしか太陽は、流れてきた灰色の雲に隠れている。熱帯の街に、またぞろスコールが降り出すようだ。
二人は席から立ち上がった。大柄なデンクールを、ドラポルトが見上げる形になる。敬礼を送りあい、それでは、とデンクールは去っていった。
その背中を見つめるドラポルトは、あることをふいに思い出した。馬鹿馬鹿しいと、頭から振り払う。そんなものは迷信だ。
それは、探検に出る前、荷運びに雇っていた現地の者の言葉だった。自らの背よりも高い荷物を背負ったその皺だらけの老人は、真顔で言っていたのだ。
『クメールの遺物、持ち出してはならぬ──』
◇◇◇
じめついた空気が、夜の斎場を包み込んでいた。エアコンが効いているはずなのに、妙に蒸し暑い。
平山北斗は、額に浮かんだ汗をハンカチでぬぐった。黒いネクタイを緩めたいが、そうもいかない。実家から急いで送ってもらった兄の喪服は細身の体には大きすぎ、自宅を出た後ずっと着心地の悪さを拭えずにいる。
「その喪服、でかくね? ていうか、北斗はもうちょっと筋肉つけたほうがいいな」
隣で、友人の栗原均の声がした。着ている喪服は、かなりきつそうだ。
「そういうお前は、もうちょっと贅肉落としたほうがいい」
「そんな必要ないと思うけど」
露骨に腹を引っ込めた栗原は、ふいに真面目な顔をして言った。「……それにしても、あの樫野先生がなあ」
栗原の視線の先で、白い顎髭をたくわえた遺影が穏やかな微笑みを浮かべていた。
「ああ。まだ信じられない」
北斗が、十年来の友人であり、仕事でも時にコンビを組む栗原とともに参列しているのは、かつて二人が在籍していた南武大学理学部鳥類学研究室の恩師、樫野星司教授の通夜である。教授が野外調査中に事故で亡くなったという知らせを受け、北斗と栗原は通夜に駆けつけたのだった。
焼香の列に並びながら、栗原が残念そうに呟く。
「フィールドワークには慣れてるはずだし、あんなに慎重派だったのに、まさか崖から落ちるなんてな」
北斗は、学生時代に樫野教授と出かけた野外調査を思い出した。教授は、危険な場所には近づかないことを徹底していた。こっちのほうがよく見えますと崖の際に望遠鏡の三脚を据えつけた時など、かなり真剣な顔で注意されたものだ。
そんな樫野先生にも、魔が差すことがあったのだろうか。北斗は言った。
「でも、一人で調査中に誤って転落したって、警察は断定してるんだろ」
「研究室の学生から聞いたけど、まあ、そういうことなんだろうな」栗原は、自らを納得させるように答えた。
崖の上には三脚にセットされたカメラや、書きかけの観察ノートがそのまま残されており、争った形跡などはなかったという。また遺書の類は現場にも自宅にも見つからなかったそうだ。
台風の余波で海は荒れ気味だったが、遺体は波に運び去られなかったため、検視は可能だった。そして、その結果や状況証拠からみて、警察は事故死と判断したのだ。
だいたい、あの樫野先生が誰かに殺されたり、自ら命を絶ったりするなど考えづらい。やはり事故と結論づけるのが妥当とは思える。
やがて焼香の順番が回ってきて、北斗は遺族の席に向かって礼をした。
そう、事故だとは思う。思うのだけれど──気になることが、ないわけではないのだ。
焼香を終えた北斗は、ロビーの片隅で、栗原がトイレから戻ってくるのを待っていた。参列者の多くは既に振る舞いの席へ移り、軽食をつまんだりビールを飲んだりしている。
人々の思い出話が、ロビーまで漏れ聞こえてきた。それを耳にした北斗の脳裏を、様々な記憶がよぎっていく。
炎天下の調査の時、飲み物を差し入れてくれた先生。レポートの明らかな手抜きを見抜いて、穏やかに諭してくれた先生。北斗の新しい挑戦を応援してくれた先生──。
そのとき会場の扉が開いて、三人の男女がロビーに出てきた。憔悴した様子の年配の女性とは、何度か話をしたことがある。樫野先生の夫人、君江さんだ。隣には、先生と同じくらいの年齢に見える大柄な男性が付き添っていた。親戚だろうか。
もう一人の若い女性については、よく知っている。焼香の時も、その女性とは視線を交わしていた。
話しかけるべきか迷っている間に、彼女も北斗の存在に気づいたらしい。他の二人に何か言ってから、歩み寄ってきた。細いフレームの眼鏡の奥、大きな瞳がまっすぐ北斗へ向けられている。
「久しぶり」
表情のないまま、彼女は軽く頭を下げた。長い黒髪が揺れ、頰にかかる。樫野教授の娘──夕子だった。
何年ぶりだろう。ずいぶん大人っぽくなった印象を受ける。
「ああ、久しぶり」
言葉を返す際に笑顔を作りかけ、慌ててやめた。父親を亡くしたばかりの人とお通夜の場で会うのに、それはないだろう。
「妙なところでまた会うことになったけど」夕子が言った。
「そう……だね。この度は、お悔やみ申し上げます」
あらためて弔意を表した北斗に「お気遣い、ありがとうございます」と硬い答えが返ってくる。
八年前、北斗と栗原が樫野研究室の学生だった頃。夕子はしばしば、父親の弁当を研究室へ届けに来ていた。北斗たちより年下の彼女は別の大学の学生だったが、南武大学はその通学経路の途中にあったのだ。
頻繁にやってくる夕子と、北斗たちが軽口を叩き合う関係になるまでに、さほど時間はかからなかった。三人は仲のよい友人として若き日をともに過ごしたが、それぞれが社会に出て数年ほど経つと、仕事でやりとりのある栗原はともかく、夕子と連絡を取り合うことは自然と減っていた。学生時代の仲間同士にはありがちな話だ。
見つめてくる夕子の視線に戸惑いを覚え、北斗は合わせていた目をそらした。喪服から伸びる白い腕が、やけに眩しい。
「どう? 元気?」口調を和らげ、夕子が訊いてきた。
「ああ、ぼちぼちね」
「よかった」
昔にはなかった沈黙が降りてくる。
北斗が次の言葉を探していると、用を足し終えた栗原が近づいてきて、のんびりと言った。
「おう、夕子。大変だったな」
北斗は、正直なところほっとした。栗原という男は、北斗に言わせればデリカシーの概念が少々欠落している面はあるものの、それを補ってあまりある天性の憎めなさを備えていた。どれほど気づまりな状況でも、彼が発言するだけで場の空気が緩んでしまうのは一種の才能といってよいだろう。
夕子は小さな笑みを浮かべつつ答えた。
「相変わらずだね、栗原くん。フリーライターになったんだって?」
「そ。で、こいつがカメラマン」栗原は北斗を指さした。「樫野先生に紹介してもらった仕事なんかは、一緒にやってるんだ」
「そうなんだ?」夕子が、あらためて視線を北斗に向ける。
「俺は会社勤めしながらの、兼業だけどね」
「そっか……。でも、昔言ってた夢がかなったんだね。よかったね」
夕子は、少しだけ口元を綻ばせて言った。
ありがとう、と小さく声に出す。実際には、祝ってもらえるような状況とはいえないのだけれど。
そんな話ばかり続けてはいられないと、北斗は話題を変えた。
「お母さんに、ひとことご挨拶できればと思うんだけど……」
「ありがとう。でも、今はいい。それどころじゃないみたいだから」
そう断る夕子の態度が、ひどく気丈に思えた。彼女だって、それどころではないはずなのに。
その時、気になっていたことを栗原が訊いてくれた。
「お母さんの横にいる男の人、誰?」
「ああ……、お父さんの高校時代の親友で、塩屋さんっていう方。二十年くらい会ってなかったみたいだけど」
そうか、あの人は親友を亡くしたのか。北斗は隣にいる栗原をちらりと見て、その気分を想像した。塩屋という、武骨な雰囲気の男に同情を覚える。
やがて視線を察したのか、塩屋は北斗のほうへ目を向けてきた。予想外に鋭い、睨みつけるような眼差しだ。
慌てて目をそらす。好意を無にされたようで、北斗が気持ちのやり場に困っていると、脇から急に声がした。
「夕子サン」
声の主は黒いスーツをまとった、すらりと背の高い外国人の女性だった。欧米系の顔立ちだが、どこかしらオリエンタルな雰囲気もある。年齢は、自分たちよりいくつか若いくらいだろうか。セミショートの髪の色は、ダークブロンド。切れ長の一重瞼の下、ほのかに緑色を帯びた瞳が猫を思わせる。夕子が、「ああ、エルザ……」と小さく手を上げたところを見ると、知り合いのようだ。
「オクヤミ申しあげマス」
女性は、日本語で夕子に弔意を述べた。
「今日は、わざわざありがとう」
「樫野センセイには本当にお世話になりマシタ」
それから二言三言、エルザという外国人と英語混じりで親し気に会話を交わした後、夕子は北斗たちに彼女を紹介した。
「こちら、エルザさん。アメリカの大学の研究者で、日本に長期滞在してるの」
「エルザ・シュローダーといいマス。どうぞヨロシク」
女性が、控えめな笑みを浮かべる。語尾が若干気になるものの、なかなか綺麗な発音だ。綺麗なのは、言葉だけではない。北斗はつかの間、その容姿に見とれてしまった。
そういえば少し前の樫野先生からのメールに、『最近、外国の若手研究者が来ています』と書かれていた。わざわざそんなことを伝えてくるのも珍しいなとは思ったが、先生も何か教えてきたかったのかもしれない。
栗原が、やや緊張気味に自分の名を名乗った。「栗原均といいます」
北斗も頭を下げる。
「平山北斗です。僕たちは学生の頃、樫野先生の研究室にいたんです」
「ソウデスカ。ワタシは海鳥の研究をしてマシテ、樫野センセイにアドバイスをもらっていたのデス」
研究室に出入りする手続きを英語のできる夕子が手伝った縁で、親しくなったという。自己紹介の後、「お二人はドンナお仕事をしているのデスカ」とエルザは訊いてきた。
「僕は会社員をしながら、カメラマンの仕事もしています。鳥や野生動物の写真が主ですけど、注文があればなんでもやります」
北斗が写真を撮り始めたのは、学生時代に樫野教授から野鳥写真の手ほどきを受けたのがきっかけである。興味を覚えた北斗は急速にのめり込み、様々な分野の写真を撮り始めた。就職してからもカメラを手放すことはなく、数年してアマチュアのコンテストの佳作に何度か選ばれるようになったのは、それなりに才能もあったのだろう。本格的に兼業カメラマンとしての仕事を始めたのは社会人になって五年目、今から三年前のことだ。もちろん、仕事を選り好みできる立場ではないので、会社勤めをしつつあらゆるジャンルの撮影を請け負っている。
同じ頃に栗原も、勤めていた科学雑誌の出版社から独立し、フリーライターになっていた。
北斗と栗原がコンビを初めて組んだのは、樫野教授に紹介された、日本野生生物保護協会というNGOの会報誌の仕事だ。特集での、北斗の写真と栗原の記事が評判になり、それからはしばしば二人で協会の仕事を引き受けている。
回想は、栗原のいささか上ずった声に破られた。
「──最近、樫野先生とやりとりしたことですか? ええと、そうだなあ、いま平山くんと一緒にしている仕事は、先生に紹介されたものなんですけどね」
栗原の自己紹介は、長々と続いている。まずいと思ったが、たぶんもう遅い。同じ状況は、学生の頃から幾度となく経験していた。
話しながらエルザを見つめる栗原の眼が、とろりと溶けたようになっている。おそらく栗原は、何度目になるかもう数え切れないが、どう考えてもうまく行くはずのない恋へと踏み出してしまったのだ。数ヵ月後、やけ酒につき合う羽目になるところまで目に見えるようだ。
夕子も、同じことを思っていたらしい。二人で苦笑いを交わした。
それから夕子は、少し迷うそぶりを見せた後、小さな声で北斗に言った。
「お父さん、病気だったんだ……」
「えっ」
そんな話は、まったく聞いたことがなかった。
「もともと、長くはなかったみたい。わたし、そこまで悪いなんて知らなかったの」
夕子が、長い睫毛の下の目を伏せる。
「なあ、先生とは……」
「お父さんから仕事を紹介されてたんなら、聞いてたかもしれないね。ちょっと、うまく行かなくなっちゃってさ」
樫野教授からは、以前になんとなく聞いていた。夕子、最近はほとんど実家に顔を出してこないし電話もないんだ、と教授は言っていたのだ。学生時代、教授のために弁当を持ってきていた彼女からは想像もできなかったが、八年という歳月が流れる間に人は変わってしまうのかもしれない。
「最近は事務的なやりとりしかしてなかったの。エルザの手続きを頼まれたのが、最後だった。その後も時々連絡くれてたんだけど、無視しちゃって……。病気の話をしようとしてたのかな。こんなことになるなら、ちゃんと聞いておけばよかった」
夕子は寂しげに笑った。
「そうか……。でも、病気だったってことはまさか……」
「ううん。それを苦にして自分で、ってことはないと思う。研究だって、いろいろやりかけのままだったみたいだし。ルーズなとこもあったけど、その辺はわりときちんとした人だったから」
「そうだな……」
夕子の言う通り、自殺などあり得ないように思う。そもそもあの先生が、研究を残して身を投げたりはしないはずだ。
「警察も事故って言ってるし、頭ではわかってるんだ。引っかかる部分もなくはないけどね」
一見、夕子は落ち着いている。だがその声色も、その態度も、納得しきれていない時のものだと北斗にはわかった。夕子は、まだ父親の死を吞み込めていない。現実を受け止めきれていないのだ。ぎくしゃくしたまま唐突に永遠の別れを迎えてしまったのなら、それも当然だろう。
北斗とて、納得はできていない。
そもそも、昔からフィールドワークでの危険には細心の注意を払っていた樫野先生が、崖の縁に近づいて落ちたりするだろうか。事故と断定されても、気持ち悪さは残っている。
そして、亡くなる二日ほど前の電話だ。先生が、預けたいと言っていた何か。それに、先生の死との関係はなかったのだろうか?
北斗は、夕子に電話の件を教えるべきかどうか迷っていた。それを話して夕子の知っていることと照らし合わせれば、謎めいたメッセージの意味がわかるかもしれないし、場合によっては樫野教授の死への違和感を拭い去れるかもしれない。彼女が知らない、最近の父親の様子を伝えてあげられることにもなるだろう。
だが先生の口ぶりは、秘密にしておきたいようでもあった。世の中には墓場まで持っていったほうがよいこともあるのは、北斗自身、三十歳にもなればわかっている。特に、夕子とそんなに不仲だったのなら、知られたくない相手はそれこそ彼女なのではないか……。
ためらった末、北斗はそれとなく夕子に訊いてみた。
「先生は、何か遺していたりはしなかったの?」
「遺書とかはなかった。警察にも確認されたし、実際に家も研究室も調べられたけど、結局、何もありませんでした、やはり事故でしょう、って」
「警察は、研究室も調べたんだ」
「あの散らかった研究室、大変だったと思うけどね」
そう言って夕子が苦笑したわけは、北斗にもわかる。樫野先生は、とにかく片づけが下手な人だった。本やノートが床にまで山積みになった研究室の様子が頭に浮かぶ。
「なあ。先生がいなくなっちゃって、研究室はどうなるの」
何気なく訊いてから、北斗は言いなおした。「ごめん。今はまだ、そんなこと考えてる場合じゃないよな」
「ううん、大丈夫。でもたしかに、これからいろいろやらないとね」
夕子は吹っ切るように顔を上げると、北斗たちに「じゃあ、また」と言い残し、母親のところへ戻っていった。
いつの間にか、エルザと栗原の会話も一段落していたらしい。エルザも、「サヨナラ」と金茶色の髪をなびかせて去っていく。
夢みるような目をした栗原の脇腹を肘でつつき、北斗は言った。
「そろそろ起きろよ」
北斗と栗原は、振る舞いが用意された別室へ移動した。
テーブルの上の寿司やサンドイッチを小皿に取り分けている間、樫野教授の親族の会話が、聞くつもりはなくとも耳に入ってくる。
「星司さんがこんなことになって、君江さんと夕子ちゃん、二人でやっていけるのかねえ。夕子ちゃん、ひとり娘でしょう」
「夕子ちゃんが、早く婿を取っちゃえばいいんじゃない?」
「そういえば星司さんのお父さんも、婿養子だったのよね」
──好き勝手言うもんだ。
北斗は軽く憤慨しつつも思った。でもまあ、こういった席で親戚同士が話す内容など、そんなものだろう。
「そうそう、夕子ちゃん、最近いい人がいるって聞いたわよ」と別の声が割り込んできたところで、少し離れたテーブルから手招きする栗原の姿が目に入ってきた。
そこまで移動すると、栗原の前には既に何枚もの皿が並んでいた。ビールも数杯空けているらしい。その上、まだ何か取りに行こうとしていたようだ。
「まだ飲み食いするのかよ」北斗は呆れた声で言った。
「え? ダメ?」頰を赤くした栗原が困り顔をする。
「ダメってことはないけどさあ……。一応、こういう場だからな」
「いやいや、供養なんだからさ、食べたほうがいいぜ。それよりお前、なんか思い詰めた顔してんな」
「そうか?」
先ほどから引きずっているもやもやとした気分が、顔にまで出ていたらしい。結局夕子には話せなかった、樫野教授からの電話の件が引っかかっていたのだ。
その時ちょうど、夕子が部屋に入ってくるのが見えた。エルザも一緒だ。知り合いもおらず、一人ぼっちでいたエルザを案内してきたのかもしれない。
エルザのことが気になるのは、栗原だけではないようだ。見覚えのある若手研究者が、嬉々としてエルザに話しかけている。
夕子が一人になったのを見た北斗は、意を決してテーブルから離れ、彼女のところへ向かった。栗原も、どうしたんだよと言いながらついてくる。
「夕子、ごめん。ちょっといいかな」
「なに?」
「話していいかどうか、迷ってたんだけど……」
北斗は一度言葉を切った。たとえ先生が、夕子には黙っておきたかったのだとしても、こんな事態になるとまでは思っていなかったはずだ。夕子だって、これほど反省しているのだ。何も伝えずにいるのは、やはりいけないことのような気がする。
「亡くなる二日くらい前、先生から電話がかかってきたんだ」
「北斗くんに? なんて?」
夕子が訊き返してくる。栗原は、なんだ初耳だな、と興味深げな声を出した。
北斗は、樫野教授との最後のやりとりを話して聞かせた。
教授は、電話の向こうで言ったのだ。
『……ちょっとわけがあって、君にいったん預けたいものがあるんだが、頼まれてくれるかい』
それから、質問に一つも答えてもらえず切られた電話。引っかかっていたことをようやく口にできて、少しだけ肩の荷が軽くなった気がした。
「今思えば、いつもと感じが違ってたみたいでさ……」
「そう……。お父さん、何を言いたかったのかな」夕子は首を傾げた。「とにかく、教えてくれてありがとう」
「すげえ大事な話じゃないか。なんですぐに言わなかったんだよ」栗原が口をとがらせて話に割り込んだ。
「具体的な話は何もなかったし、なんだか秘密にしといてほしいようだったから……。とはいえ、言わずにいて悪かった」
「先生が秘密にしたがってたとしても、警察には話したほうがよくないか?」
栗原の考えは、意外にも夕子が否定した。
「そのくらいじゃ、警察は動いてくれないよ」
きちんと捜査した上で事故死と結論づけられているのだから、今さらその程度の、大して具体的ではない内容の電話があったというだけでは、改めて調べてくれたりはしないだろうという。
「じゃあ、この話はこれで終わりかよ」
「いや……。夕子に相談があるんだ」
北斗は、ずっと考えていたことを口にした。「先生が俺に預けたいと言っていたものを、探させてくれないか。今のところ、どんなものかもわからないけど」
その何かを見つけ出し、預かることが、先生の遺志に沿うことになるはずだ。
「そうね……」
少し考えた後で、夕子は言った。「うん、探してみて。むしろ、お願いします。お父さんが残していたものって何なのか、わたしも気になるし」
そうだ。それに、いささか突飛な考えかもしれないが、その『預けたいもの』をめぐって、先生が何かの事件に巻き込まれていたという可能性もあり得るのではないか。
北斗は、さっそく夕子に訊ねた。
「先生の家に、俺宛ての荷物とかはないよね」
夕子は首を横に振った。それはそうだろう。秘密にしておきたいものを、そんなわかりやすい形で置いておくはずはない。
いや待て。ならば──。
「研究室は?」
「そっちはわからないな。警察は調べてたけど、遺書がないかとか、そういう目でしか見てないだろうし……」
「さっきも聞いたけど、研究室はこれからどうなるかわからないんだよね」
「うん」
「じゃあ、今度、俺たちで整理しに行くよ。いずれやらなきゃいけないんだろ? ついでに、先生が俺に預けようとしていたものを探させてもらうってことでどうかな」
「それはありがたいけど……」夕子はいくぶん迷いがちに言った。「実は、落ち着いたら個人の研究資料はご家族で整理してくださいって言われてて。手伝いをお願いしようにも、助手の先生は非常勤で他のお仕事が忙しいし、現役の学生さんたちには試験とか就活とかもあるから、困ってたんだ。本当に手伝ってもらっていいの? 栗原くんも」
「別にいいよ。俺たちだったら、いろいろこき使えるだろうしな」
栗原の少々気のない風の答え方は、わざとだろう。
「いいの? なんかごめんね」
「気にすんなよ。樫野先生のためだからな」
北斗はそう言いつつ、先生のため、という部分を変に強調していることに気づいた。
夕子に別れを告げ、北斗と栗原が斎場を出ると、来がけに降っていた雨はもう上がっていた。生暖かい空気の中を、駅へ向かう。
珍しく黙り込んでいた栗原が、駅前商店街の灯りが見えてきたあたりで口を開いた。
「お前、夕子とは本当はどうなの」
なんだよ、と北斗が笑いながら横を見ると、意外にも栗原は真面目な表情をしていた。酔っている気配はない。
「どうって……。栗原が期待するような話は何もないよ。昔も、今も」
「本当に?」
「ああ。本当に何もない」
「そうか……。お前らはお似合いだって、昔から思ってたんだけどな」
「ないない」
正直なところ、そのように発展することを想像しなかったわけではない。だが、やはり自分と夕子は友人同士の関係が一番しっくりくると北斗は思っていた。
学生時代から今まで、北斗は三人の女性と交際したことがあった。その三人とも、短い間に彼女たちのほうから北斗のもとを去っている。もしかしたら、自分には何か大きく欠けている部分があるのかもしれない。
欠けているものが何かは、未だにわからない。ただなんとなく、夕子にその部分を見られるのは嫌だな、と思った。
それよりも、樫野先生が俺に預けようとしていたものとは、なんだったんだろう。それは、先生の死とは関係ないのだろうか。
とにかく、探してみることだ──。
「どうした、小難しい顔して」
隣から、栗原が覗き込んできた。
「ん? いや、なんでもない」
「ま、気持ちはわからんでもないけどな……」
勝手な誤解をしているらしい栗原が、そう言いながら水たまりを踏んだ。街の灯を映す水面を、静かに波紋が広がっていった。
第二章 端緒
一八六六年 南シナ海
昨日まで左舷にあった大陸の青い影は、ぼんやりと霞む水平線の彼方に消えていた。
右舷側へ目を向ければ、東の空は巨大な壁のような濃灰色の雲に占められている。しかも少しずつ、その壁は近づいてきていた。
低気圧が近づいているのだ。大きくうねる波頭には、白いしぶきが混じり始めている。
その光景を、フリエ・デンクール中尉は揺れる甲板から長いあいだ眺めていた。そろそろ部屋へ戻ろうと、船内へ通じる扉を開けた途端、乗組員と鉢合わせする。
急いでいるらしい乗組員は、「失礼しました」と短く言い残し甲板へ駆け出していった。慌てた様子なのは、その乗組員だけではなかった。船内のあちこちから、怒鳴り声が聞こえてくる。
フランス陸軍・日本派遣軍事顧問団を乗せた汽船『カンボジア』号がサイゴンを出港し、三日が過ぎていた。昨日までは平穏な航海を楽しませてくれていた南シナ海だったが、今朝になって急に気分を変えたらしい。
こうなると、ただの乗客が船内をうろついていても、邪魔になるだけだ。デンクールは、与えられた船室へおとなしく引き揚げることにした。
顧問団の同僚たちの姿は、甲板にも、食堂にも見当たらない。皆、船酔いに苦しんでそれぞれの船室にこもっているようだ。体質ゆえか、船酔いというものの経験がないデンクールは暇を持て余してしまい、むしろ皆が羨ましいくらいだった。
船室に戻ると、まずランプをつけた。淡い光の落とす影が、微かに聞こえてくる波音に合わせ左右に動く。壁に吊るされた小さな鏡は、ランプの光を映しつつ、ゆらゆらと振り子のように揺れていた。
デンクールは寝台にその大きな身体を横たえたが、睡魔がやってくる気配はまるでなかった。仕方ない、荷物の整理でもするかとすぐに起き上がる。
とはいえ、荷物は多くない。武器や装備の類は船倉に収めているため、船室には私物しか持ち込んでいなかったし、それらもすべて箱型をした革製の背囊ひとつに収まっていた。
中身を寝台の上に広げると、小さな紙包みが目に留まった。サイゴンで再会した幼馴染、ルイ・ドラポルトから餞別にと貰ったものだ。この船の名の由来であるカンボジアにかつて存在した、クメール王朝の遺物という話を思い出す。
包みをほどき、ペンダントを取り出した。ランプの光を受け、青銅のリングの中心で、瞳を連想させる丸い水晶が濡れたようにきらめいた。目の前に掲げてみると、向こう側が透けて見える。
──戦士のお守りか。
そうドラポルトは言っていたが、どこまで本当かはわからない。彼が何かを隠していることを、デンクールは薄々察していた。なぜかは知りようもないが、とにかく、これを自分が持っていくことが彼のためになるらしい。きっとそうせざるを得ない理由があるのだろう。デンクールは、古い友人を信じていた。
ドラポルトや仲間たちと過ごした少年の日々を懐かしく思い出しながら、手のひらの中のペンダントを見つめる。
ルイの話が、噓であったとしてどうだというのだ。これは戦場に向かう俺にとって、やはりありがたいお守りだ。デンクールはそう思いつつ、寝台に座ったまま、ペンダントの水晶を何気なくランプに向けた。透過してきたランプの光が、拡大して見え──。
突然、強烈な電撃に身体を貫かれたような気がした。雷に打たれたという考えが浮かび、すぐに、まさか船の中でそんなことはあるまいと否定する。額の古傷がまた開いてしまったのかとも思ったが、痛みがあるわけでもない。そうしているうちに、奇妙な映像が目の前で形を取り始めた。
不思議な感覚だった。視界には、船室の様子が映っている。一方、それとまったく同時に、頭の中へ何かのイメージが流れ込んでくるのだ。二つの映像を並行して、違和感なく認識できていた。妄想か、白昼夢か。しかし夢と呼ぶには、そのイメージはあまりにもはっきりとしていた。
頭の中に浮かんでいるのは、懐かしき故郷、ロシュの緑豊かな街並みだった。街の向こうで陽光をきらきらと照り返し流れるのは、アンドル川だ。
美しい街並みは、手を伸ばせば触れられるかのようだ。夢の場面が切り替わるように、視点は次々と移ろう。人々の行き交う石畳の道路を、馬車よりも速く滑っていくと、よく覚えている一角にたどり着いた。あれはドラポルト家の屋敷だ。その隣、オーギュスト家の邸宅を過ぎたところには、老いた両親が暮らす家があるはずだ。向かいには小さな木立。幼い頃、ルイと一緒に遊んでいた頃は鬱蒼とした森に思えたものだが、今見れば本当に小さい。そこを抜けた先には、あの頃胸を焦がしていた彼女の──。
突然、船が揺れた。咄嗟に寝台の手すりを摑み、デンクールはペンダントを取り落とした。同時に、イメージも搔き消える。
つい先ほどまでペンダントを握っていたその手は、細かく震えていた。
──いったい、何を見ていたんだ、俺は。
デンクールは、必死に冷静さを取り戻そうとした。
よし、落ち着け。大きく息をしろ。俺がいま摑まっているのは、寝台だ。ランプの灯りが照らしているのは、狭い船室と、薄汚れた壁。それが現実だ。
ではさっき見たものは、なんだ? 白昼夢というやつか?
デンクールはそこでふと、メキシコへ派遣されていた頃に聞いた話を思い出した。
なんらかの超自然的な力を持つマヤ文明の遺物が存在し、それを手にした者には勝利と栄光が約束されるが、一歩使い道を誤れば破滅と死をもたらすという。
それがどのようなものか、どのようにして役立てるのか、まったく具体性を欠く話で、単なる伝説、いかがわしい神秘主義だと一笑に付したものだ。
だが、いま俺が体験したのは何だったのだ?
マヤほど古くはないが、クメール人も謎を多く残した民族だとルイは言っていた。理屈はわからないが、このペンダントの水晶はクメールの秘術か何かによって、自分の記憶を呼びさますものなのか、あるいは遠くの情景を見られるものなのか? いや、まさかそんなことが──。
船室の扉越しに、乗組員が慌ただしく駆ける音が響いた。船の揺れる角度も、先ほどより増してきているようだ。
船体が、巨大なうねりに乗り上げたらしい。船首側がぐっと持ち上げられた次の刹那には、深く沈み込んでいく。寝台の手すりを強く摑みなおしたデンクールの耳に、砕け散る波の音が聞こえてきた。
続きは単行本でお楽しみください!
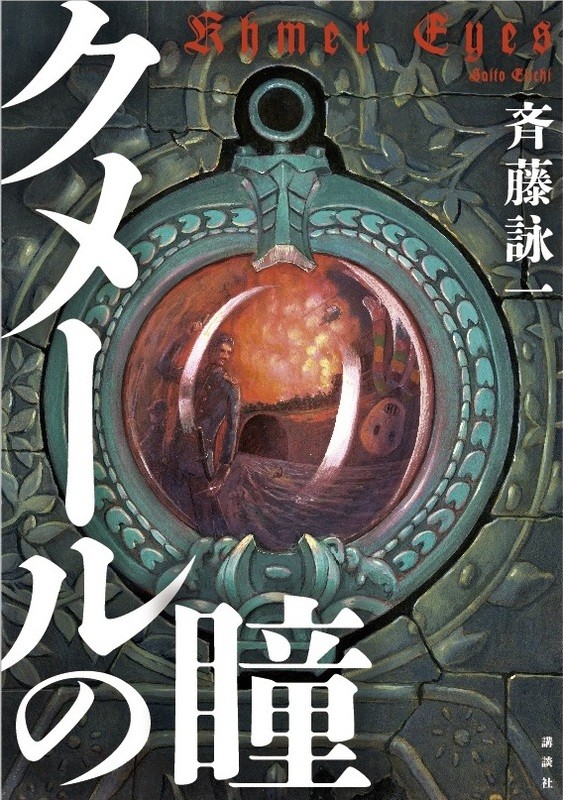
『クメールの瞳』斉藤詠一
あれから3年――。
斉藤詠一さんの待望の最新刊『クメールの瞳』が絶賛大大大好評発売中です!
――あぁ、すっかり忘れていた、こういうロマン。説得力のある「嘘」を書くのが小説家の醍醐味だ。
と今野敏さんからもコメントが届いている本作!
刊行を記念して、その冒頭を特別に無料公開いたします!
序章
丸い視界の中、波打ち際の岩に休む鳥が見える。
大きさは、ハトくらい。全体に灰色で、頭は黒。アジサシの仲間のようだ。アジサシは世界中に約四十種が分布し、日本では主にアジサシとコアジサシの二種が見られるカモメ科の渡り鳥である。だが双眼鏡の向こうの、鮮やかな赤色のくちばしと足は、普通のアジサシよりも短い。畳んだ羽から、長い尾が飛び出ているのが目についた。
──キョクアジサシか。
興奮のあまり視界が揺れる。平山北斗は自らを落ち着けるように深呼吸すると、双眼鏡を握りなおした。
キョクアジサシは、地球上で最も長い距離──北極・南極間を渡る鳥である。渡りのルートから外れた日本には、台風に流されて迷った個体がまれに飛来する程度で、観察記録はごく少ない。会社員と兼業で(内心ではこちらが本業なのだが)カメラマンをしている北斗といえど、見るのは初めてだった。
──通り過ぎたばかりの今年最初の台風が、こんな置き土産を残してくれたとは。
ここは、神奈川県のとある海岸である。複数の撮影地候補からこの場所を選んだのは正解だったようだ。
傍らに置いていたカメラの三脚を摑み、急いで位置を修正する。その時ふいに、羽織っているカメラマンベストの、いくつもついたポケットの一つが振動し始めた。電話だ。
おいおいこのタイミングでかよ、と思いつつ、マナーモードで震えているスマートフォンを取り出す。画面には、「樫野先生」と相手先が表示されていた。
──出ないわけにはいかないか。
「もしもし、平山です」
少しだけ、不機嫌な声になってしまったかもしれない。
『ああ、平山くん。申し訳ない、忙しいところだったかな。樫野です』
白い顎髭をたくわえた優しげな顔が、頭に浮かぶ。電話をかけてきたのは、学生時代の恩師にして、今でも写真の仕事を紹介してくれている樫野星司教授だった。
「お久しぶりです。あの……いま撮影に来てまして。先生、すごいですよ。キョクアジサシがいます」
相手は、鳥類学研究室の教授である。きっとこの興奮を理解してくれると思ったのだが(そして電話もかけなおしてくれることを期待したのだが)、樫野教授の返事は意外なものだった。
『そうか……すごいな。でもすまない、大事な話があるんだ』
キョクアジサシよりもですか、と危うく口に出しそうになるのを我慢した。そこまでの用件とはなんだろう。樫野先生の声は、普段より硬いような気もする。どうやら本当に大事な電話らしい。北斗は、片手で操作しかけていたカメラから手を離した。
「なんでしょう」と訊くと、わずかな沈黙を挟み、電話の向こうで樫野教授は言った。
『……ちょっとわけがあって、君にいったん預けたいものがあるんだが、頼まれてくれるかい』
「どうしたんですか、急に」
キョクアジサシが動いているのがわかったが、それどころではなさそうだ。無意識に、スマホを持つ左手に力が入る。
『もしかすると、それで迷惑をかけてしまうこともあるかもしれないが……』
「迷惑だなんて思いませんが……。その、預けたいものって、何なんですか」
『電話ではあまりはっきり言わないほうがよさそうなんだ。かといって、会って話す時間はないかもしれなくてね。そういうものがあるとだけ、伝えておくよ』
──何を言っているんだ、先生は?
「すみません、お話が見えないんですが……僕に預けたいというものは何で、どこにあるんでしょうか」
もう一度同じことを訊いた北斗に、樫野教授は急に懐かしむような口調になって答えた。
『覚えているかなあ。昔、片づけ下手の私に、君がアドバイスをくれた時のこと……。本当にすまないが、課題みたいなものだと思ってくれ。それじゃあ、頼むよ──』
「あっ、先生、ちょ……」
それきり、電話は切れてしまった。
いったい、今のは何の話だったんだ──。
戸惑う北斗の視界の端で、キョクアジサシが青い海原へと羽ばたいていった。
第一章 遺物
一八六六年 インドシナ半島南部 フランス領コーチシナ
まとわりつくような湿った空気の中を、どこからか魚醬の匂いが漂ってくる。絶え間なく響く、街のざわめき。時折、大きな怒鳴り声も聞こえてくるが、フランス海軍少尉ルイ・ドラポルトにはその意味がよくわからなかった。コーチシナに着任して一年近く経つものの、現地の言葉はほとんど理解できないままだ。
サイゴン港に設けられたフランス海軍工廠内、士官食堂の、海を望むテラスである。十二月というのに、陽射しは夏とたいして変わらない。パラソルの陰のテーブルで、ドラポルト少尉は古い友人、フリエ・デンクール陸軍中尉と向かい合っていた。
「フリエ。まさか、故国から遠く離れたこんな場所で再会できるとはね。驚いたよ」
「ちょうど君が探検から戻ってきた時に俺の船が入港したのも、神の思し召しだろう」
話しながら、デンクールは顔の周りを飛び交う蠅を手で追い払っている。
「平気かい」ドラポルトは友人に言った。
「ああ。メキシコと変わらないさ。慣れてしまえばどうということはない。そうだ……。再会の記念に渡すつもりで、持ってきたんだ」
デンクールは軍服のポケットから小さな布袋を取り出すと、テーブルの上に置き、ドラポルトに開けるよう促した。
華やかな刺繡が施された袋には、骸骨を象った小さな人形が入っていた。骸骨といっても、グロテスクなイメージはない。鮮やかな極彩色の服を着せられ、しゃれこうべに模様が描かれた人形は、どこかユーモラスで可愛らしくもあった。
「メキシコには『死者の日』という風習があってね。その日は家を飾りつけ、ご馳走を食べながら、この世を去った者の思い出を皆で語り合うんだ。彼らは、死を暗いものとは捉えていないらしい。街中がお祭りのようで、これはその時に買ったものさ。カラベラといって、お守りだそうだ」
「なるほど、面白い」
軍人であるとともに探検家でもあるドラポルトにとって、確かに興味深い話だった。人形も、異文化の美術品としての価値を感じさせる。
「気に入ったよ。ありがとう」
ドラポルトは礼を言いながら、ふとあることを思いついた。自分も、返礼にちょうどよい品を持っているではないか。
ただ、それを本当に渡してよいものか。迷いつつ、ドラポルトは話を続けた。
「メキシコでは大きな働きをしたそうじゃないか。噂に聞いたよ、デンクール中尉殿」
二人が海軍、陸軍それぞれの士官学生だった一八六一年、フランス第二帝国皇帝ナポレオン三世はメキシコに出兵し、フランスの傀儡である第二次メキシコ帝国を建国していた。士官学校を卒業したばかりのデンクールはそこへ派遣され、反仏のメキシコ共和国軍との戦闘に参加したのだ。
メキシコ国民の支持を得た共和国軍の前に、フランス軍は次第に劣勢となったが、その状況下でもデンクールの指揮する小隊は常に戦果を挙げ続けたという。
「よしてくれ。中尉といっても、前任の小隊長が戦死したから野戦昇進しただけさ。昔のとおりフリエでいい。君のほうは、海軍軍人というよりはすっかり探検家に見えるぞ。まあ、ロシュの街一番のやんちゃ坊主ルイには、お似合いな気もするが。この前はカンボジアに行ったんだって?」
「ああ。調査隊の本隊はまだ向こうにいるんだが、僕たち分遣隊は先に戻ってきたんだ。そのおかげで君に会えたわけだ」
ドラポルトは、フランス植民地帝国学術調査隊の隊員として、この地に派遣されていた。
遡ること四年前の一八六二年、列強各国に遅れまいとアジアへ進出したフランス帝国は、阮朝との抗争の末にインドシナ半島南部を確保、仏領コーチシナと名付け植民地経営に乗り出していた。そしてこの一八六六年、ドラポルトたち調査隊はコーチシナ総督府の置かれたサイゴンからメコン川を遡上、カンボジアを目指したのだった。
調査隊は、純粋に学術目的のものではなかった。フランスが保護条約を結んだカンボジアとコーチシナの国境を明確にすること、さらにはメコン川を北上した先、中国との通商ルートを探ることなどが戦略目標として課せられていたのだ。また、植民地の宗主国フランスの存在感を誇示するという背景もあった。それゆえに調査隊の中に学者は少なく、隊員のほとんどが軍人によって構成されていた。
「それにしても、お互い世界中を飛び回っているな。君は、今度は東の果ての国か」ドラポルトは、感慨を込めて言った。
「東の果てだなんて言い方は、まるで地球平面説だな。海軍の人間とは思えないぞ」
そう笑って答えた直後、デンクールは顔をしかめた。どこからか漂ってきた、甘い腐臭のせいだろう。
「やっぱり、まだ慣れていないようだな」今度はドラポルトが笑う。
「戦争だったら別だがね。火薬の匂いがする場所なら、どこだって慣れてみせるさ」
デンクールが傷痕の残る額の下、目をぎらりと光らせる。その片手は、いつの間にかテラスに入り込んだ野良犬の頭を撫でていた。
「そうは言っても、今は世界中どこも落ち着いているんじゃないか」
「ああ。皇帝陛下は、メキシコからの撤兵を決めた。プロイセンとオーストリアの戦争にも、我関せずを決め込んでいる。実はアルジェリア行きも打診されたんだが、冗談じゃない。あそこは死ぬほど退屈だという噂だ。だから、この任務を志願したのさ」
その瞳を見たドラポルトは、自分たちが少年と呼ばれていた時代はもはや遠くに去り、二度と戻らぬことを悟った。
──戦争か。戦争が、あの優しかったフリエを変えてしまったのだ。
「どうした?」
気づかぬうちに、硬い表情になっていたようだ。訝しげにデンクールが訊ねてきたので、ドラポルトはごまかした。
「いや、なんでもない。すまん」
「メキシコにいた時に、わかったんだ。俺は、ある種の戦ぐるいなのかもしれない。戦争のあるところでしか、生きられない。今のフランスに、俺の居場所はないのさ」
感情が昂ったのか、デンクールの声が大きくなった。犬が慌てたように離れていく。
「でも、君の行く先では、戦争はしていないんじゃないか」
「匂うのさ」デンクールは、どこか陰のある笑顔をみせた。「きっと、戦になる。俺の勘は、当たるんだ」
「そうか……。気をつけてくれよ」
ドラポルトは、友人が向かう国についてよくは知らない。デンクールたち軍事顧問団十数名は、バクフと呼ばれるその国の政府の依頼を受け、近代的な軍隊を訓練するために派遣されるという。
メンバーはいずれも、遠い極東の地までフランスの栄光を知らしめんとする理想に満ちた、高潔な思想の持ち主と聞く。軍の一部にみられる、腐敗などとは縁がないだろう。
ドラポルトの心は決まった。やはりあれは、この古い友人に渡すのが一番だ。
隣の椅子に置いた鞄から、ドラポルトは紙の包みを取り出した。テーブルの上をデンクールのほうへ滑らせながら言う。
「戦に行く君に、僕からの餞別だ」
デンクールが包みを解くと、手のひらに収まるくらいの、青銅製らしいリング状のものが現れた。全周にわたって精緻な文様が刻まれているが、何より特徴的なのは、その中心に透明な水晶が嵌め込まれていることだった。水晶は、レンズのように真ん中が膨らんでいる。
「なんだい、これは……」
デンクールは、様々に角度を変えてそれを眺めた。「こうやって見ると、目玉みたいだな」
「カンボジアで見つけてきたのさ。青銅の部分に一ヵ所、穴が開いているだろう。そこに紐を通し、首から下げてペンダントにするものだと考えられる。かつて存在した、クメール王朝の遺物だ」
「大事なものなんじゃないか。いいのか」
「かまわないよ。お守りだというので身につけていたが、君にはメキシコのお守りをもらったし、交換だ。これは、そもそも戦士のお守りらしいからね。君のほうがふさわしい。似たようなものは他にも収集したし、一つくらい問題ないさ」
その話は、真実ではなかった。実際にそれが何かはわかっていない。しかし持っていても学術的に調べることは期待できないどころか、むしろ危険なのだった。
ドラポルトの頭に、それを見つけた時の記憶がよみがえる。
今回の探検の総指揮を執ったドゥダール・ドゥ・ラグレ海軍大佐は、探検の途中、隊を二つに分けていた。コーチシナ駐留部隊から異動してきたばかりのガルシア中尉が、メコン川の支流を遡ったジャングルにあるという未知の遺跡の調査を強く進言したためだ。
ドラポルトは、ガルシア中尉が直接指揮する十名ほどの分遣隊に編入され、その遺跡へ向かうことになった。本隊と別れて小さな船で支流を遡り、さらに一週間。緑の地獄のようなジャングルをさまよった末に姿を見せた、壮麗な廃墟の様子は今でも目に浮かぶ。気が遠くなりそうな数の砂岩や煉瓦を積み重ね、美しい直線と柔らかな曲線を複雑に組み合わせて造られたその建物こそ、数百年の昔に滅び去った、異教徒の文明の遺跡であった。
左右対称の建物は一部が崩壊し、蔦に覆われかけていた。かつての寺院だろうか、横に長い回廊の向こうには塔があり、その四面には周囲を見渡すように菩薩の微笑みが彫り込まれている。湿気に白く霞んだ空気の中、黒いシルエットとなったジャングルを背景に浮かび上がる様は、さながら幻影の城だった。
崩れ落ちた部分から遺跡の中に入ったドラポルトたちは、瓦礫の山を苦労して乗り越え、物陰にひそむ蛇に怯えつつ、その寺院跡を調べ回った。ところどころ開いた穴から射し込む光にぼんやりと照らされた建物の中は、石材の冷気で、ジャングルの中より涼しく感じられた。
祠堂らしき建物だけは、何か貴重なものが隠されているかのように重い石の扉で塞がれていたが、苦労して数人がかりで押しのけ、中に入ることができた。ランプを片手に部屋へ踏み込んだドラポルトたちが見つけたのは、山と積まれた遺物の数々だった。シヴァ神を象った精緻な彫像に、美しい模様の施された金属器……。
ヒンドゥー教や仏教の混淆した影響が見て取れる、それら貴重な遺物を、ガルシア中尉の命令で隊員たちは手あたり次第袋に詰め込んだ。誰にも罪悪感はなかった。ヨーロッパ列強は、各国の考古学的遺物を競い合うように持ち帰っては、ルーヴル美術館や大英博物館といった施設に収蔵していた。放っておけば遺跡の崩壊とともに無に帰してしまうのだから、むしろ善いことをしているのだという意識が強かった。それらを持ち去り、調べることこそが、自分たちにとっての正義、使命なのだった。
その部屋の奥には、もう一つ小部屋があった。そっちには何もなかったぞという仲間の声は聞き流し、ドラポルトは足を踏み入れた。
石の壁から放たれる冷気が、一段と増したような気がした。床面には、確かに何も置かれていない。だが見回せば、壁の一部には人や動物を象ったレリーフが彫られていた。赤みを帯びた砂岩に、躍動する人々が緻密に描かれている。何かしらのストーリーが込められているようにも見えたが、刻まれた文字も、語り継がれた伝承もないのであれば、いにしえの物語はもはや永遠に失われたも同然であった。
ただ、舞い踊る数人の踊り子たちが一様に、首からペンダントを下げているのはわかった。リングのような形のそれと同じものを、横に長いレリーフの隣の場面では、男が手に取っている。大勢の兵の奥に座る、王の格好をした人物だ。その人物は、別の場面ではペンダントを目の前にかざして覗くような仕草をしていた。
そして、その王らしき人物の、レリーフの中の視線を追った先にもペンダントの形があった。レリーフの一部が膨らみ、暗い部屋の中で輝きを放っている。
違和感を覚えたドラポルトは、レリーフの膨らんだ部分に手を伸ばした。隙間に指を入れると、それは容易く外れ、手のひらにおさまった。本物のペンダントが埋め込まれていたのだ。
薄暗い中でわかりづらかったが、ペンダントは青銅でできているらしく、リングの真ん中には丸い水晶が嵌められていた。
なぜこれだけが、レリーフの模様に隠すように取りつけられていたのだろう。
すぐに答えが出るはずもなかったが、調べる価値はある。
そう考えたドラポルトは、ペンダントを自分のポケットに入れ、皆のところに戻った。他の遺物と一緒に、袋へ詰め込んだりはしなかった。私欲にかられたつもりはまったくなかったのだが、結果としてそれが、ペンダントを救うことになった。
分遣隊が帰還したのち、ドラポルトは、持ち帰った遺物のすべてがガルシア中尉により売却されたのを知った。記録も、改竄されていた。遺跡を発見できず、調査隊は手ぶらで帰還したとされていたのだ。
今にして思えば、ガルシア中尉が探検に出発する直前に着任したのも、謀略の一部だったのだ。コーチシナに駐留するフランス軍の中には、植民地の財源でもある阿片を通じて現地の裏社会と手を結ぶ、腐敗した一派が存在していた。
隊員たちは、あっけなく買収された。遺物の売却益の一部を回すだけで、そのくらいの金は用意できたのだろう。ドラポルトにも話はあったものの、金は受け取らなかった。それだけは、してはならないと思ったのだった。その代わり他言しないことを約束させられたが、破ったらどうなるかは、考えなくてもわかる。進んで告発する勇気はなかった。命は惜しかったし、半生を賭ける覚悟でやってきたこの土地での探検をやめることはできない。
問題は、例のペンダントだった。金を受け取らなかったため疑念を持たれたのだろう、不在時に部屋を調べられた痕跡を見つけたこともあった。ペンダントを隠し持っていた事実が露見すれば、何をされるかわからない。このまま持っていては、危険だ。
もちろん、今さらガルシア中尉に渡すつもりもない。そんな時にデンクールと再会できたのは、ドラポルトにとって神の導きのように思えた。
これは、戦場へ赴く古い友人に、餞別として渡すのが一番よいのではないか──。
気づけば、デンクールはドラポルトをじっと見つめていた。まるで、本当の事情を見透かすかのように。
やがて、デンクールはふっと目の力を緩めて穏やかに笑った。
「ありがたく受け取るよ。……ルイ、またいつか会おう。その時には、君は軍人ではなく本当の探検家になっているかもしれんな」
デンクールはそう言って、空を見た。いつしか太陽は、流れてきた灰色の雲に隠れている。熱帯の街に、またぞろスコールが降り出すようだ。
二人は席から立ち上がった。大柄なデンクールを、ドラポルトが見上げる形になる。敬礼を送りあい、それでは、とデンクールは去っていった。
その背中を見つめるドラポルトは、あることをふいに思い出した。馬鹿馬鹿しいと、頭から振り払う。そんなものは迷信だ。
それは、探検に出る前、荷運びに雇っていた現地の者の言葉だった。自らの背よりも高い荷物を背負ったその皺だらけの老人は、真顔で言っていたのだ。
『クメールの遺物、持ち出してはならぬ──』
◇◇◇
じめついた空気が、夜の斎場を包み込んでいた。エアコンが効いているはずなのに、妙に蒸し暑い。
平山北斗は、額に浮かんだ汗をハンカチでぬぐった。黒いネクタイを緩めたいが、そうもいかない。実家から急いで送ってもらった兄の喪服は細身の体には大きすぎ、自宅を出た後ずっと着心地の悪さを拭えずにいる。
「その喪服、でかくね? ていうか、北斗はもうちょっと筋肉つけたほうがいいな」
隣で、友人の栗原均の声がした。着ている喪服は、かなりきつそうだ。
「そういうお前は、もうちょっと贅肉落としたほうがいい」
「そんな必要ないと思うけど」
露骨に腹を引っ込めた栗原は、ふいに真面目な顔をして言った。「……それにしても、あの樫野先生がなあ」
栗原の視線の先で、白い顎髭をたくわえた遺影が穏やかな微笑みを浮かべていた。
「ああ。まだ信じられない」
北斗が、十年来の友人であり、仕事でも時にコンビを組む栗原とともに参列しているのは、かつて二人が在籍していた南武大学理学部鳥類学研究室の恩師、樫野星司教授の通夜である。教授が野外調査中に事故で亡くなったという知らせを受け、北斗と栗原は通夜に駆けつけたのだった。
焼香の列に並びながら、栗原が残念そうに呟く。
「フィールドワークには慣れてるはずだし、あんなに慎重派だったのに、まさか崖から落ちるなんてな」
北斗は、学生時代に樫野教授と出かけた野外調査を思い出した。教授は、危険な場所には近づかないことを徹底していた。こっちのほうがよく見えますと崖の際に望遠鏡の三脚を据えつけた時など、かなり真剣な顔で注意されたものだ。
そんな樫野先生にも、魔が差すことがあったのだろうか。北斗は言った。
「でも、一人で調査中に誤って転落したって、警察は断定してるんだろ」
「研究室の学生から聞いたけど、まあ、そういうことなんだろうな」栗原は、自らを納得させるように答えた。
崖の上には三脚にセットされたカメラや、書きかけの観察ノートがそのまま残されており、争った形跡などはなかったという。また遺書の類は現場にも自宅にも見つからなかったそうだ。
台風の余波で海は荒れ気味だったが、遺体は波に運び去られなかったため、検視は可能だった。そして、その結果や状況証拠からみて、警察は事故死と判断したのだ。
だいたい、あの樫野先生が誰かに殺されたり、自ら命を絶ったりするなど考えづらい。やはり事故と結論づけるのが妥当とは思える。
やがて焼香の順番が回ってきて、北斗は遺族の席に向かって礼をした。
そう、事故だとは思う。思うのだけれど──気になることが、ないわけではないのだ。
焼香を終えた北斗は、ロビーの片隅で、栗原がトイレから戻ってくるのを待っていた。参列者の多くは既に振る舞いの席へ移り、軽食をつまんだりビールを飲んだりしている。
人々の思い出話が、ロビーまで漏れ聞こえてきた。それを耳にした北斗の脳裏を、様々な記憶がよぎっていく。
炎天下の調査の時、飲み物を差し入れてくれた先生。レポートの明らかな手抜きを見抜いて、穏やかに諭してくれた先生。北斗の新しい挑戦を応援してくれた先生──。
そのとき会場の扉が開いて、三人の男女がロビーに出てきた。憔悴した様子の年配の女性とは、何度か話をしたことがある。樫野先生の夫人、君江さんだ。隣には、先生と同じくらいの年齢に見える大柄な男性が付き添っていた。親戚だろうか。
もう一人の若い女性については、よく知っている。焼香の時も、その女性とは視線を交わしていた。
話しかけるべきか迷っている間に、彼女も北斗の存在に気づいたらしい。他の二人に何か言ってから、歩み寄ってきた。細いフレームの眼鏡の奥、大きな瞳がまっすぐ北斗へ向けられている。
「久しぶり」
表情のないまま、彼女は軽く頭を下げた。長い黒髪が揺れ、頰にかかる。樫野教授の娘──夕子だった。
何年ぶりだろう。ずいぶん大人っぽくなった印象を受ける。
「ああ、久しぶり」
言葉を返す際に笑顔を作りかけ、慌ててやめた。父親を亡くしたばかりの人とお通夜の場で会うのに、それはないだろう。
「妙なところでまた会うことになったけど」夕子が言った。
「そう……だね。この度は、お悔やみ申し上げます」
あらためて弔意を表した北斗に「お気遣い、ありがとうございます」と硬い答えが返ってくる。
八年前、北斗と栗原が樫野研究室の学生だった頃。夕子はしばしば、父親の弁当を研究室へ届けに来ていた。北斗たちより年下の彼女は別の大学の学生だったが、南武大学はその通学経路の途中にあったのだ。
頻繁にやってくる夕子と、北斗たちが軽口を叩き合う関係になるまでに、さほど時間はかからなかった。三人は仲のよい友人として若き日をともに過ごしたが、それぞれが社会に出て数年ほど経つと、仕事でやりとりのある栗原はともかく、夕子と連絡を取り合うことは自然と減っていた。学生時代の仲間同士にはありがちな話だ。
見つめてくる夕子の視線に戸惑いを覚え、北斗は合わせていた目をそらした。喪服から伸びる白い腕が、やけに眩しい。
「どう? 元気?」口調を和らげ、夕子が訊いてきた。
「ああ、ぼちぼちね」
「よかった」
昔にはなかった沈黙が降りてくる。
北斗が次の言葉を探していると、用を足し終えた栗原が近づいてきて、のんびりと言った。
「おう、夕子。大変だったな」
北斗は、正直なところほっとした。栗原という男は、北斗に言わせればデリカシーの概念が少々欠落している面はあるものの、それを補ってあまりある天性の憎めなさを備えていた。どれほど気づまりな状況でも、彼が発言するだけで場の空気が緩んでしまうのは一種の才能といってよいだろう。
夕子は小さな笑みを浮かべつつ答えた。
「相変わらずだね、栗原くん。フリーライターになったんだって?」
「そ。で、こいつがカメラマン」栗原は北斗を指さした。「樫野先生に紹介してもらった仕事なんかは、一緒にやってるんだ」
「そうなんだ?」夕子が、あらためて視線を北斗に向ける。
「俺は会社勤めしながらの、兼業だけどね」
「そっか……。でも、昔言ってた夢がかなったんだね。よかったね」
夕子は、少しだけ口元を綻ばせて言った。
ありがとう、と小さく声に出す。実際には、祝ってもらえるような状況とはいえないのだけれど。
そんな話ばかり続けてはいられないと、北斗は話題を変えた。
「お母さんに、ひとことご挨拶できればと思うんだけど……」
「ありがとう。でも、今はいい。それどころじゃないみたいだから」
そう断る夕子の態度が、ひどく気丈に思えた。彼女だって、それどころではないはずなのに。
その時、気になっていたことを栗原が訊いてくれた。
「お母さんの横にいる男の人、誰?」
「ああ……、お父さんの高校時代の親友で、塩屋さんっていう方。二十年くらい会ってなかったみたいだけど」
そうか、あの人は親友を亡くしたのか。北斗は隣にいる栗原をちらりと見て、その気分を想像した。塩屋という、武骨な雰囲気の男に同情を覚える。
やがて視線を察したのか、塩屋は北斗のほうへ目を向けてきた。予想外に鋭い、睨みつけるような眼差しだ。
慌てて目をそらす。好意を無にされたようで、北斗が気持ちのやり場に困っていると、脇から急に声がした。
「夕子サン」
声の主は黒いスーツをまとった、すらりと背の高い外国人の女性だった。欧米系の顔立ちだが、どこかしらオリエンタルな雰囲気もある。年齢は、自分たちよりいくつか若いくらいだろうか。セミショートの髪の色は、ダークブロンド。切れ長の一重瞼の下、ほのかに緑色を帯びた瞳が猫を思わせる。夕子が、「ああ、エルザ……」と小さく手を上げたところを見ると、知り合いのようだ。
「オクヤミ申しあげマス」
女性は、日本語で夕子に弔意を述べた。
「今日は、わざわざありがとう」
「樫野センセイには本当にお世話になりマシタ」
それから二言三言、エルザという外国人と英語混じりで親し気に会話を交わした後、夕子は北斗たちに彼女を紹介した。
「こちら、エルザさん。アメリカの大学の研究者で、日本に長期滞在してるの」
「エルザ・シュローダーといいマス。どうぞヨロシク」
女性が、控えめな笑みを浮かべる。語尾が若干気になるものの、なかなか綺麗な発音だ。綺麗なのは、言葉だけではない。北斗はつかの間、その容姿に見とれてしまった。
そういえば少し前の樫野先生からのメールに、『最近、外国の若手研究者が来ています』と書かれていた。わざわざそんなことを伝えてくるのも珍しいなとは思ったが、先生も何か教えてきたかったのかもしれない。
栗原が、やや緊張気味に自分の名を名乗った。「栗原均といいます」
北斗も頭を下げる。
「平山北斗です。僕たちは学生の頃、樫野先生の研究室にいたんです」
「ソウデスカ。ワタシは海鳥の研究をしてマシテ、樫野センセイにアドバイスをもらっていたのデス」
研究室に出入りする手続きを英語のできる夕子が手伝った縁で、親しくなったという。自己紹介の後、「お二人はドンナお仕事をしているのデスカ」とエルザは訊いてきた。
「僕は会社員をしながら、カメラマンの仕事もしています。鳥や野生動物の写真が主ですけど、注文があればなんでもやります」
北斗が写真を撮り始めたのは、学生時代に樫野教授から野鳥写真の手ほどきを受けたのがきっかけである。興味を覚えた北斗は急速にのめり込み、様々な分野の写真を撮り始めた。就職してからもカメラを手放すことはなく、数年してアマチュアのコンテストの佳作に何度か選ばれるようになったのは、それなりに才能もあったのだろう。本格的に兼業カメラマンとしての仕事を始めたのは社会人になって五年目、今から三年前のことだ。もちろん、仕事を選り好みできる立場ではないので、会社勤めをしつつあらゆるジャンルの撮影を請け負っている。
同じ頃に栗原も、勤めていた科学雑誌の出版社から独立し、フリーライターになっていた。
北斗と栗原がコンビを初めて組んだのは、樫野教授に紹介された、日本野生生物保護協会というNGOの会報誌の仕事だ。特集での、北斗の写真と栗原の記事が評判になり、それからはしばしば二人で協会の仕事を引き受けている。
回想は、栗原のいささか上ずった声に破られた。
「──最近、樫野先生とやりとりしたことですか? ええと、そうだなあ、いま平山くんと一緒にしている仕事は、先生に紹介されたものなんですけどね」
栗原の自己紹介は、長々と続いている。まずいと思ったが、たぶんもう遅い。同じ状況は、学生の頃から幾度となく経験していた。
話しながらエルザを見つめる栗原の眼が、とろりと溶けたようになっている。おそらく栗原は、何度目になるかもう数え切れないが、どう考えてもうまく行くはずのない恋へと踏み出してしまったのだ。数ヵ月後、やけ酒につき合う羽目になるところまで目に見えるようだ。
夕子も、同じことを思っていたらしい。二人で苦笑いを交わした。
それから夕子は、少し迷うそぶりを見せた後、小さな声で北斗に言った。
「お父さん、病気だったんだ……」
「えっ」
そんな話は、まったく聞いたことがなかった。
「もともと、長くはなかったみたい。わたし、そこまで悪いなんて知らなかったの」
夕子が、長い睫毛の下の目を伏せる。
「なあ、先生とは……」
「お父さんから仕事を紹介されてたんなら、聞いてたかもしれないね。ちょっと、うまく行かなくなっちゃってさ」
樫野教授からは、以前になんとなく聞いていた。夕子、最近はほとんど実家に顔を出してこないし電話もないんだ、と教授は言っていたのだ。学生時代、教授のために弁当を持ってきていた彼女からは想像もできなかったが、八年という歳月が流れる間に人は変わってしまうのかもしれない。
「最近は事務的なやりとりしかしてなかったの。エルザの手続きを頼まれたのが、最後だった。その後も時々連絡くれてたんだけど、無視しちゃって……。病気の話をしようとしてたのかな。こんなことになるなら、ちゃんと聞いておけばよかった」
夕子は寂しげに笑った。
「そうか……。でも、病気だったってことはまさか……」
「ううん。それを苦にして自分で、ってことはないと思う。研究だって、いろいろやりかけのままだったみたいだし。ルーズなとこもあったけど、その辺はわりときちんとした人だったから」
「そうだな……」
夕子の言う通り、自殺などあり得ないように思う。そもそもあの先生が、研究を残して身を投げたりはしないはずだ。
「警察も事故って言ってるし、頭ではわかってるんだ。引っかかる部分もなくはないけどね」
一見、夕子は落ち着いている。だがその声色も、その態度も、納得しきれていない時のものだと北斗にはわかった。夕子は、まだ父親の死を吞み込めていない。現実を受け止めきれていないのだ。ぎくしゃくしたまま唐突に永遠の別れを迎えてしまったのなら、それも当然だろう。
北斗とて、納得はできていない。
そもそも、昔からフィールドワークでの危険には細心の注意を払っていた樫野先生が、崖の縁に近づいて落ちたりするだろうか。事故と断定されても、気持ち悪さは残っている。
そして、亡くなる二日ほど前の電話だ。先生が、預けたいと言っていた何か。それに、先生の死との関係はなかったのだろうか?
北斗は、夕子に電話の件を教えるべきかどうか迷っていた。それを話して夕子の知っていることと照らし合わせれば、謎めいたメッセージの意味がわかるかもしれないし、場合によっては樫野教授の死への違和感を拭い去れるかもしれない。彼女が知らない、最近の父親の様子を伝えてあげられることにもなるだろう。
だが先生の口ぶりは、秘密にしておきたいようでもあった。世の中には墓場まで持っていったほうがよいこともあるのは、北斗自身、三十歳にもなればわかっている。特に、夕子とそんなに不仲だったのなら、知られたくない相手はそれこそ彼女なのではないか……。
ためらった末、北斗はそれとなく夕子に訊いてみた。
「先生は、何か遺していたりはしなかったの?」
「遺書とかはなかった。警察にも確認されたし、実際に家も研究室も調べられたけど、結局、何もありませんでした、やはり事故でしょう、って」
「警察は、研究室も調べたんだ」
「あの散らかった研究室、大変だったと思うけどね」
そう言って夕子が苦笑したわけは、北斗にもわかる。樫野先生は、とにかく片づけが下手な人だった。本やノートが床にまで山積みになった研究室の様子が頭に浮かぶ。
「なあ。先生がいなくなっちゃって、研究室はどうなるの」
何気なく訊いてから、北斗は言いなおした。「ごめん。今はまだ、そんなこと考えてる場合じゃないよな」
「ううん、大丈夫。でもたしかに、これからいろいろやらないとね」
夕子は吹っ切るように顔を上げると、北斗たちに「じゃあ、また」と言い残し、母親のところへ戻っていった。
いつの間にか、エルザと栗原の会話も一段落していたらしい。エルザも、「サヨナラ」と金茶色の髪をなびかせて去っていく。
夢みるような目をした栗原の脇腹を肘でつつき、北斗は言った。
「そろそろ起きろよ」
北斗と栗原は、振る舞いが用意された別室へ移動した。
テーブルの上の寿司やサンドイッチを小皿に取り分けている間、樫野教授の親族の会話が、聞くつもりはなくとも耳に入ってくる。
「星司さんがこんなことになって、君江さんと夕子ちゃん、二人でやっていけるのかねえ。夕子ちゃん、ひとり娘でしょう」
「夕子ちゃんが、早く婿を取っちゃえばいいんじゃない?」
「そういえば星司さんのお父さんも、婿養子だったのよね」
──好き勝手言うもんだ。
北斗は軽く憤慨しつつも思った。でもまあ、こういった席で親戚同士が話す内容など、そんなものだろう。
「そうそう、夕子ちゃん、最近いい人がいるって聞いたわよ」と別の声が割り込んできたところで、少し離れたテーブルから手招きする栗原の姿が目に入ってきた。
そこまで移動すると、栗原の前には既に何枚もの皿が並んでいた。ビールも数杯空けているらしい。その上、まだ何か取りに行こうとしていたようだ。
「まだ飲み食いするのかよ」北斗は呆れた声で言った。
「え? ダメ?」頰を赤くした栗原が困り顔をする。
「ダメってことはないけどさあ……。一応、こういう場だからな」
「いやいや、供養なんだからさ、食べたほうがいいぜ。それよりお前、なんか思い詰めた顔してんな」
「そうか?」
先ほどから引きずっているもやもやとした気分が、顔にまで出ていたらしい。結局夕子には話せなかった、樫野教授からの電話の件が引っかかっていたのだ。
その時ちょうど、夕子が部屋に入ってくるのが見えた。エルザも一緒だ。知り合いもおらず、一人ぼっちでいたエルザを案内してきたのかもしれない。
エルザのことが気になるのは、栗原だけではないようだ。見覚えのある若手研究者が、嬉々としてエルザに話しかけている。
夕子が一人になったのを見た北斗は、意を決してテーブルから離れ、彼女のところへ向かった。栗原も、どうしたんだよと言いながらついてくる。
「夕子、ごめん。ちょっといいかな」
「なに?」
「話していいかどうか、迷ってたんだけど……」
北斗は一度言葉を切った。たとえ先生が、夕子には黙っておきたかったのだとしても、こんな事態になるとまでは思っていなかったはずだ。夕子だって、これほど反省しているのだ。何も伝えずにいるのは、やはりいけないことのような気がする。
「亡くなる二日くらい前、先生から電話がかかってきたんだ」
「北斗くんに? なんて?」
夕子が訊き返してくる。栗原は、なんだ初耳だな、と興味深げな声を出した。
北斗は、樫野教授との最後のやりとりを話して聞かせた。
教授は、電話の向こうで言ったのだ。
『……ちょっとわけがあって、君にいったん預けたいものがあるんだが、頼まれてくれるかい』
それから、質問に一つも答えてもらえず切られた電話。引っかかっていたことをようやく口にできて、少しだけ肩の荷が軽くなった気がした。
「今思えば、いつもと感じが違ってたみたいでさ……」
「そう……。お父さん、何を言いたかったのかな」夕子は首を傾げた。「とにかく、教えてくれてありがとう」
「すげえ大事な話じゃないか。なんですぐに言わなかったんだよ」栗原が口をとがらせて話に割り込んだ。
「具体的な話は何もなかったし、なんだか秘密にしといてほしいようだったから……。とはいえ、言わずにいて悪かった」
「先生が秘密にしたがってたとしても、警察には話したほうがよくないか?」
栗原の考えは、意外にも夕子が否定した。
「そのくらいじゃ、警察は動いてくれないよ」
きちんと捜査した上で事故死と結論づけられているのだから、今さらその程度の、大して具体的ではない内容の電話があったというだけでは、改めて調べてくれたりはしないだろうという。
「じゃあ、この話はこれで終わりかよ」
「いや……。夕子に相談があるんだ」
北斗は、ずっと考えていたことを口にした。「先生が俺に預けたいと言っていたものを、探させてくれないか。今のところ、どんなものかもわからないけど」
その何かを見つけ出し、預かることが、先生の遺志に沿うことになるはずだ。
「そうね……」
少し考えた後で、夕子は言った。「うん、探してみて。むしろ、お願いします。お父さんが残していたものって何なのか、わたしも気になるし」
そうだ。それに、いささか突飛な考えかもしれないが、その『預けたいもの』をめぐって、先生が何かの事件に巻き込まれていたという可能性もあり得るのではないか。
北斗は、さっそく夕子に訊ねた。
「先生の家に、俺宛ての荷物とかはないよね」
夕子は首を横に振った。それはそうだろう。秘密にしておきたいものを、そんなわかりやすい形で置いておくはずはない。
いや待て。ならば──。
「研究室は?」
「そっちはわからないな。警察は調べてたけど、遺書がないかとか、そういう目でしか見てないだろうし……」
「さっきも聞いたけど、研究室はこれからどうなるかわからないんだよね」
「うん」
「じゃあ、今度、俺たちで整理しに行くよ。いずれやらなきゃいけないんだろ? ついでに、先生が俺に預けようとしていたものを探させてもらうってことでどうかな」
「それはありがたいけど……」夕子はいくぶん迷いがちに言った。「実は、落ち着いたら個人の研究資料はご家族で整理してくださいって言われてて。手伝いをお願いしようにも、助手の先生は非常勤で他のお仕事が忙しいし、現役の学生さんたちには試験とか就活とかもあるから、困ってたんだ。本当に手伝ってもらっていいの? 栗原くんも」
「別にいいよ。俺たちだったら、いろいろこき使えるだろうしな」
栗原の少々気のない風の答え方は、わざとだろう。
「いいの? なんかごめんね」
「気にすんなよ。樫野先生のためだからな」
北斗はそう言いつつ、先生のため、という部分を変に強調していることに気づいた。
夕子に別れを告げ、北斗と栗原が斎場を出ると、来がけに降っていた雨はもう上がっていた。生暖かい空気の中を、駅へ向かう。
珍しく黙り込んでいた栗原が、駅前商店街の灯りが見えてきたあたりで口を開いた。
「お前、夕子とは本当はどうなの」
なんだよ、と北斗が笑いながら横を見ると、意外にも栗原は真面目な表情をしていた。酔っている気配はない。
「どうって……。栗原が期待するような話は何もないよ。昔も、今も」
「本当に?」
「ああ。本当に何もない」
「そうか……。お前らはお似合いだって、昔から思ってたんだけどな」
「ないない」
正直なところ、そのように発展することを想像しなかったわけではない。だが、やはり自分と夕子は友人同士の関係が一番しっくりくると北斗は思っていた。
学生時代から今まで、北斗は三人の女性と交際したことがあった。その三人とも、短い間に彼女たちのほうから北斗のもとを去っている。もしかしたら、自分には何か大きく欠けている部分があるのかもしれない。
欠けているものが何かは、未だにわからない。ただなんとなく、夕子にその部分を見られるのは嫌だな、と思った。
それよりも、樫野先生が俺に預けようとしていたものとは、なんだったんだろう。それは、先生の死とは関係ないのだろうか。
とにかく、探してみることだ──。
「どうした、小難しい顔して」
隣から、栗原が覗き込んできた。
「ん? いや、なんでもない」
「ま、気持ちはわからんでもないけどな……」
勝手な誤解をしているらしい栗原が、そう言いながら水たまりを踏んだ。街の灯を映す水面を、静かに波紋が広がっていった。
第二章 端緒
一八六六年 南シナ海
昨日まで左舷にあった大陸の青い影は、ぼんやりと霞む水平線の彼方に消えていた。
右舷側へ目を向ければ、東の空は巨大な壁のような濃灰色の雲に占められている。しかも少しずつ、その壁は近づいてきていた。
低気圧が近づいているのだ。大きくうねる波頭には、白いしぶきが混じり始めている。
その光景を、フリエ・デンクール中尉は揺れる甲板から長いあいだ眺めていた。そろそろ部屋へ戻ろうと、船内へ通じる扉を開けた途端、乗組員と鉢合わせする。
急いでいるらしい乗組員は、「失礼しました」と短く言い残し甲板へ駆け出していった。慌てた様子なのは、その乗組員だけではなかった。船内のあちこちから、怒鳴り声が聞こえてくる。
フランス陸軍・日本派遣軍事顧問団を乗せた汽船『カンボジア』号がサイゴンを出港し、三日が過ぎていた。昨日までは平穏な航海を楽しませてくれていた南シナ海だったが、今朝になって急に気分を変えたらしい。
こうなると、ただの乗客が船内をうろついていても、邪魔になるだけだ。デンクールは、与えられた船室へおとなしく引き揚げることにした。
顧問団の同僚たちの姿は、甲板にも、食堂にも見当たらない。皆、船酔いに苦しんでそれぞれの船室にこもっているようだ。体質ゆえか、船酔いというものの経験がないデンクールは暇を持て余してしまい、むしろ皆が羨ましいくらいだった。
船室に戻ると、まずランプをつけた。淡い光の落とす影が、微かに聞こえてくる波音に合わせ左右に動く。壁に吊るされた小さな鏡は、ランプの光を映しつつ、ゆらゆらと振り子のように揺れていた。
デンクールは寝台にその大きな身体を横たえたが、睡魔がやってくる気配はまるでなかった。仕方ない、荷物の整理でもするかとすぐに起き上がる。
とはいえ、荷物は多くない。武器や装備の類は船倉に収めているため、船室には私物しか持ち込んでいなかったし、それらもすべて箱型をした革製の背囊ひとつに収まっていた。
中身を寝台の上に広げると、小さな紙包みが目に留まった。サイゴンで再会した幼馴染、ルイ・ドラポルトから餞別にと貰ったものだ。この船の名の由来であるカンボジアにかつて存在した、クメール王朝の遺物という話を思い出す。
包みをほどき、ペンダントを取り出した。ランプの光を受け、青銅のリングの中心で、瞳を連想させる丸い水晶が濡れたようにきらめいた。目の前に掲げてみると、向こう側が透けて見える。
──戦士のお守りか。
そうドラポルトは言っていたが、どこまで本当かはわからない。彼が何かを隠していることを、デンクールは薄々察していた。なぜかは知りようもないが、とにかく、これを自分が持っていくことが彼のためになるらしい。きっとそうせざるを得ない理由があるのだろう。デンクールは、古い友人を信じていた。
ドラポルトや仲間たちと過ごした少年の日々を懐かしく思い出しながら、手のひらの中のペンダントを見つめる。
ルイの話が、噓であったとしてどうだというのだ。これは戦場に向かう俺にとって、やはりありがたいお守りだ。デンクールはそう思いつつ、寝台に座ったまま、ペンダントの水晶を何気なくランプに向けた。透過してきたランプの光が、拡大して見え──。
突然、強烈な電撃に身体を貫かれたような気がした。雷に打たれたという考えが浮かび、すぐに、まさか船の中でそんなことはあるまいと否定する。額の古傷がまた開いてしまったのかとも思ったが、痛みがあるわけでもない。そうしているうちに、奇妙な映像が目の前で形を取り始めた。
不思議な感覚だった。視界には、船室の様子が映っている。一方、それとまったく同時に、頭の中へ何かのイメージが流れ込んでくるのだ。二つの映像を並行して、違和感なく認識できていた。妄想か、白昼夢か。しかし夢と呼ぶには、そのイメージはあまりにもはっきりとしていた。
頭の中に浮かんでいるのは、懐かしき故郷、ロシュの緑豊かな街並みだった。街の向こうで陽光をきらきらと照り返し流れるのは、アンドル川だ。
美しい街並みは、手を伸ばせば触れられるかのようだ。夢の場面が切り替わるように、視点は次々と移ろう。人々の行き交う石畳の道路を、馬車よりも速く滑っていくと、よく覚えている一角にたどり着いた。あれはドラポルト家の屋敷だ。その隣、オーギュスト家の邸宅を過ぎたところには、老いた両親が暮らす家があるはずだ。向かいには小さな木立。幼い頃、ルイと一緒に遊んでいた頃は鬱蒼とした森に思えたものだが、今見れば本当に小さい。そこを抜けた先には、あの頃胸を焦がしていた彼女の──。
突然、船が揺れた。咄嗟に寝台の手すりを摑み、デンクールはペンダントを取り落とした。同時に、イメージも搔き消える。
つい先ほどまでペンダントを握っていたその手は、細かく震えていた。
──いったい、何を見ていたんだ、俺は。
デンクールは、必死に冷静さを取り戻そうとした。
よし、落ち着け。大きく息をしろ。俺がいま摑まっているのは、寝台だ。ランプの灯りが照らしているのは、狭い船室と、薄汚れた壁。それが現実だ。
ではさっき見たものは、なんだ? 白昼夢というやつか?
デンクールはそこでふと、メキシコへ派遣されていた頃に聞いた話を思い出した。
なんらかの超自然的な力を持つマヤ文明の遺物が存在し、それを手にした者には勝利と栄光が約束されるが、一歩使い道を誤れば破滅と死をもたらすという。
それがどのようなものか、どのようにして役立てるのか、まったく具体性を欠く話で、単なる伝説、いかがわしい神秘主義だと一笑に付したものだ。
だが、いま俺が体験したのは何だったのだ?
マヤほど古くはないが、クメール人も謎を多く残した民族だとルイは言っていた。理屈はわからないが、このペンダントの水晶はクメールの秘術か何かによって、自分の記憶を呼びさますものなのか、あるいは遠くの情景を見られるものなのか? いや、まさかそんなことが──。
船室の扉越しに、乗組員が慌ただしく駆ける音が響いた。船の揺れる角度も、先ほどより増してきているようだ。
船体が、巨大なうねりに乗り上げたらしい。船首側がぐっと持ち上げられた次の刹那には、深く沈み込んでいく。寝台の手すりを強く摑みなおしたデンクールの耳に、砕け散る波の音が聞こえてきた。
続きは単行本でお楽しみください!
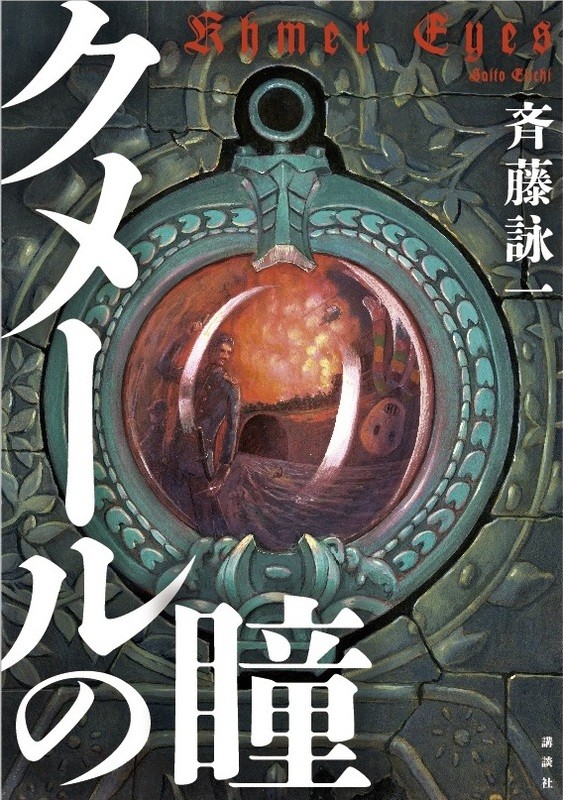
『クメールの瞳』斉藤詠一



