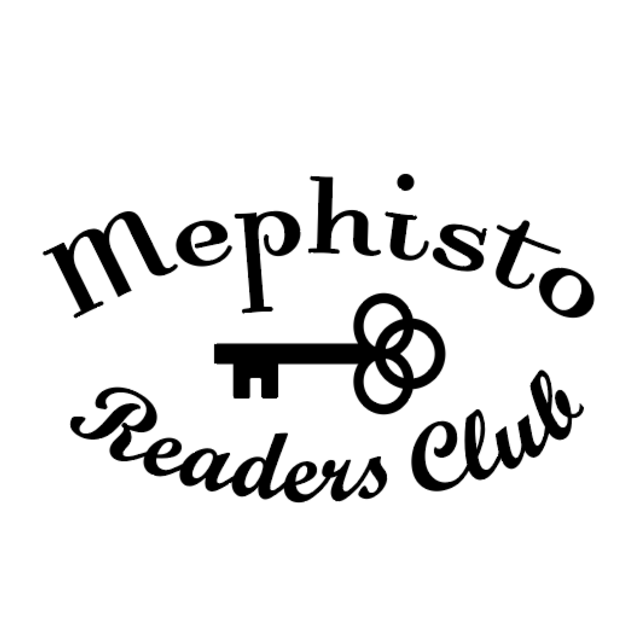【読書エッセイ】第一話 おしゃべりなレジ係
文字数 2,857文字
「おしゃべりは世界を救う」 吉川トリコ
義母には友だちが百人いる。義父が営むとんかつ屋を手伝いながら息子を四人育てただけでも大忙しの毎日だっただろうに、どこにそんな余裕があったのか、ご近所さんや息子たちの同級生の母親と仲良くなり、さらに彼らの家族や親族や友人へと友だちの輪をひろげ(だから息子たちより同級生の家族構成だったり家庭の事情にくわしい)、かなり広い範囲のネットワークを形成している。
一度つかんだ相手の手を決して離すことなく、まめに連絡をとりあい、何十年もつきあいを続けていくだけでもとんでもない才能だと思うが、友人たちの家族の名前やプロフィールまでインプットしている記憶力もすさまじい。なにより、その圧倒的なコミュニケーション能力というかおしゃべり力は驚異である。以前いっしょに行った鮨屋では、熟練のDJのごとくあの手この手で話題をくりだす義母に対し、頑固一徹なかんじの大将ですら態度を軟化させ、カウンターは最高のグルーヴに包まれていた。
真下みことさんの新刊『かごいっぱいに詰め込んで』の第一話「おしゃべりなレジ係」を読んでいちばんに思い出したのは義母のことだった。寿退社をして主婦になった主人公の美奈子は、子育てが一段落ついたのでそろそろ仕事を再開しようと思い立つものの、主婦の再就職がいかに困難であるか、現実の厳しさを思い知ることになる。夫や息子にすら、母さんにできる仕事などあるのかと笑われてしまう。しかし美奈子はめげず、近所のスーパーで「おしゃべりレジ係」という職を得る。
おしゃべりな自分にはうってつけの仕事ではないかという美奈子の直感は見事に的中! 現代社会を映し出すような顧客たち――だれかと話したくてしかたない独居老人や世を拗ねたような男性などを相手に、心の隙間にすっと入りこむようなコミュニケーションを展開し、どんなにつんけんした態度をとられても、「相手は怒っているのではなく、困っているのだと考えるようにして」決しておしゃべりを止めない。人間をあきらめない。そのタフネス、その善性、そのすばらしい仕事ぶり&止まらないおしゃべりのグルーヴは痛快で、涙が出そうにさえなる。
主婦の家事労働は多くの場合いまだ無償で行われているし、エッセンシャルワーカーの低賃金も問題視されている。ことほどさようにケア労働は軽視されがちだ。私たちの社会は、美奈子や義母のような人たちによってなんとかギリギリのところで持ちこたえているのに、国も市場経済も彼らに敬意を払おうとしない。能力を思うぞんぶん活かすことができずにいる主婦が、この国にはいったいどれだけいることだろう。「生産性」にばかり焦点をあて、既存のシステムにはめこんで女性を「活用」しようとするからそうなるのであって、彼らの能力に合わせて新しいシステムを構築するぐらいのことをしてみせろよとつい思ってしまう。
今年に入って佐原ひかりさんが上梓した『鳥と港』(小学館)も、加速する一方の新自由主義にブレーキをかけるような「新しい仕事」を提案する小説で、真下さんの今作もまさに「新しい仕事」を書いたものである。同時代的に若い作家からこのような作品が次々と発表されたことには頼もしさしか感じないし、おそらくこの流れは止まらないんじゃないかと期待もしている。
とはいえ「おしゃべりレジ係」を実際に導入してくれそうな余裕のあるスーパーは現状の日本ではあんまりなさそうなのだが(作中には「ゆくゆくは行政と連携」とあったので、それならあるいは、と感じさせるあたりがうまい)、商店街がかつてその役割をになっていた「地域の見守り役」の責任を果たすとしたら、やっぱりスーパーしかないんじゃないかと思う――っていうか、あんたらが商店街を駆逐したんだから、その責任を取って多少のコストを払ってでも地域のお年寄りや子どもたちの面倒ぐらい見てくれよ! というかんじではある。
ここで私自身の話をすると、中年の階段を順調にのぼり、そろそろ老後のことを考えはじめるお年頃。夫婦二人の生活は静かでのんびりしてはいるが、子どもがいない上にフリーランスをしていると、どうしても地域とのつながりが薄くなりがちで、将来の孤独を思っていまから戦々恐々としている。あいにく私には美奈子や義母のようなコミュニケーション能力もなく、地元に友だちもほとんどいない。
それでも、もし近所のスーパーに「おしゃべりレジ係」があったとしても、たぶん利用しないだろうなと途中までは思っていた。スーパーのレジが苦手で、むしろセルフレジのほうが気が楽なぐらいだからだ(しかし、セルフレジで少しでも操作につまずくとすぐに係の人が飛んでくる。あれはあれで恐ろしくてしかたがない)。
自分でもなにをそんなに恐れているのかわからないでいたのだが、「おしゃべりレジ係にはマニュアルがない」という部分を読んで、はっと気づかされた。そうか、「マニュアル対応」がこわいんだ、と。もちろんマニュアルがあることによってスムーズに運ぶ場面もあるだろうし、安心して働ける人もいるだろう。それでもやっぱり私は、あの言葉が怖い。人と人とのコミュニケーションとは対極のところにある、人間が人間を効率的に管理するために最適化されたグルーヴ絶無の言語に思えるから。
海外のスーパーに行くと、レジ係の人たちはみな椅子に座り、ゆるゆるだらだら客や従業員とおしゃべりしながら働いている。ハローでもボンジューでもなんでもいいけれど、レジ係から声をかけられると、その国の言葉なんかほとんどわからないのに、人間と話しているかんじがしてほっとする。
あの光景が日本で見られるなら、「おしゃべりレジ係」の行列に並んでみたいかもしれない。
吉川トリコ(よしかわ・とりこ)
1977年生まれ。2004年、「ねむりひめ」で「女による女のためのR-18文学賞」第3回大賞および読者賞を受賞し、同作収録の『しゃぼん』でデビュー。著書に『グッモーエビアン!』『戦場のガールズライフ』『少女病』『ミドリのミ』『ずっと名古屋』『光の庭』『女優の娘』『夢で逢えたら』『流れる星をつかまえに』『あわのまにまに』『コンビニエンス・ラブ』「マリー・アントワネットの日記」シリーズなどがある。2022年、『余命一年、男をかう』で第28回島清恋愛文学賞を受賞。エッセイでは、『おんなのじかん』所収「流産あるあるすごく言いたい」で第1回PEPジャーナリズム大賞2021オピニオン部門を受賞。