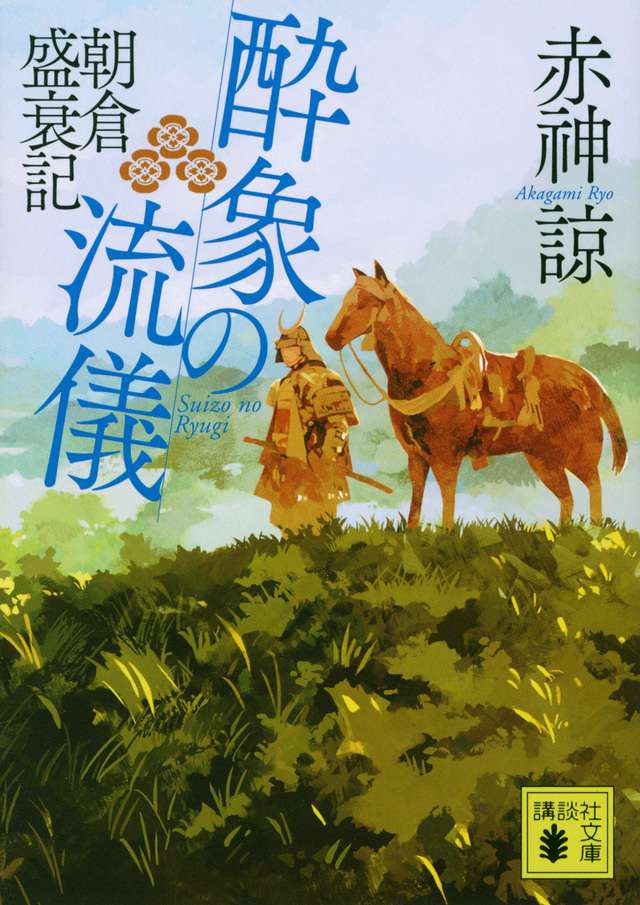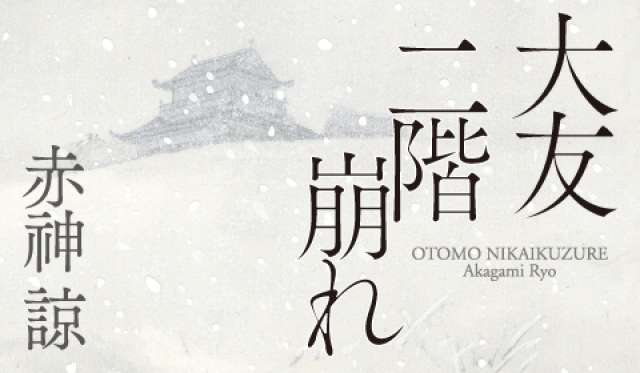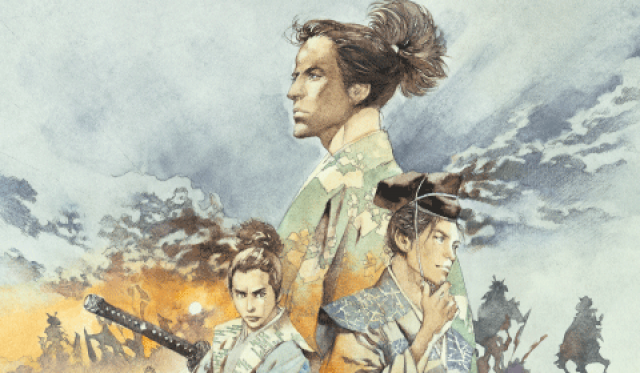◆No.4 幻の上洛 ~戦国朝倉家の7大 if (イフ)その1
文字数 1,726文字

2019年11月に、物語の舞台である福井市にお招きいただき、『戦国朝倉家の7大if(イフ)』と題して、お話をいたしました。
朝倉家は「滅亡か、存続か」の岐路に何度も立たされ、敗亡への道をひた歩んでいきます。
執筆しながら、<もしもこの時〇〇していたら……>と幾度も考えさせられました。
歴史には禁断の<if(イフ)> ですが、私は作家なので、
ここではあえて哀惜の念を抱きつつ、考えてみたいのです。
7つにしたのは「七不思議」とか、「七つ道具」とかを意識しただけで、深い意味はありません。
では、まず一つめ。
永禄11年(1568年)7月、朝倉義景は足利義昭の要請に応じず、義昭は信長のもとへ去りました。その結果、信長は義昭を奉じて上洛、畿内で勢力を急拡大していきます。
Q:もしも義景が、足利義昭を奉じて上洛していたら……。
A:大河ドラマ『麒麟がくる』で、義景は副主人公格になっていたかも知れません(笑)。
それは冗談として、当時の信長は美濃を制し、日の出の勢いでした。朝倉が信長にうまく対応できたかは、他勢力との連携次第だったでしょう。
覇権主義の信長との対決は結局、避けられなかったと思います。
それでも、将軍と朝廷を味方につけていれば、史実で敵方にされてしまったことを考えると、史実よりは有利に対抗できたはず。
最終的に服従したとしても、滅亡しなかった可能性があります。
義景には天下を取る気などなかったでしょう。
ですから、例えば朝倉家が浅井長政と協力し、敵対していた本願寺とも早期に協調できたなら、義景は信長と違って、幕府復権のために力を尽くしたのではないかと思います。その結果、もしかしたら幕府は一応存続するか、少なくとも滅亡が遅れたかも知れません。
さらにいえば、明智光秀も織田家には仕えず、義景とともに幕府で活躍して、もちろん本能寺の変も起こらず……
この辺でやめておきましょう。
義景の嫡男、阿君丸に、ある事件が起こったため、義景は上洛を断念します。
失望した足利義昭は、織田信長の元へ去ってゆくことになります。
どのような気持ちで吉家は、義昭を見送ったのでしょうか……。
■主な登場人物
山崎吉家 内衆の重臣。宗滴五将の筆頭「仁」の将
前波吉継 義景の側近。内衆の名門、前波家の庶子
堀江景忠 加越国境を守る国衆。宗滴五将の「義」
魚住景固 内衆の重臣。宗滴五将の「智」
朝倉景鏡 義景の従兄で大野郡司。宗滴五将の「礼」
朝倉義景 第五代・越前朝倉家当主
印牧能信 景鏡の懐刀。宗滴五将の「信」
お宰 義景の三人目の室
小少将 義景の四人目の室。美濃斎藤家にゆかり
蕗 小少将の侍女
いと 吉家の室
山崎吉延 吉家の弟
朝倉伊冊(景紀) 同名衆有力者で敦賀郡司。景鏡の政敵。
朝倉宗滴 朝倉家最高の将。