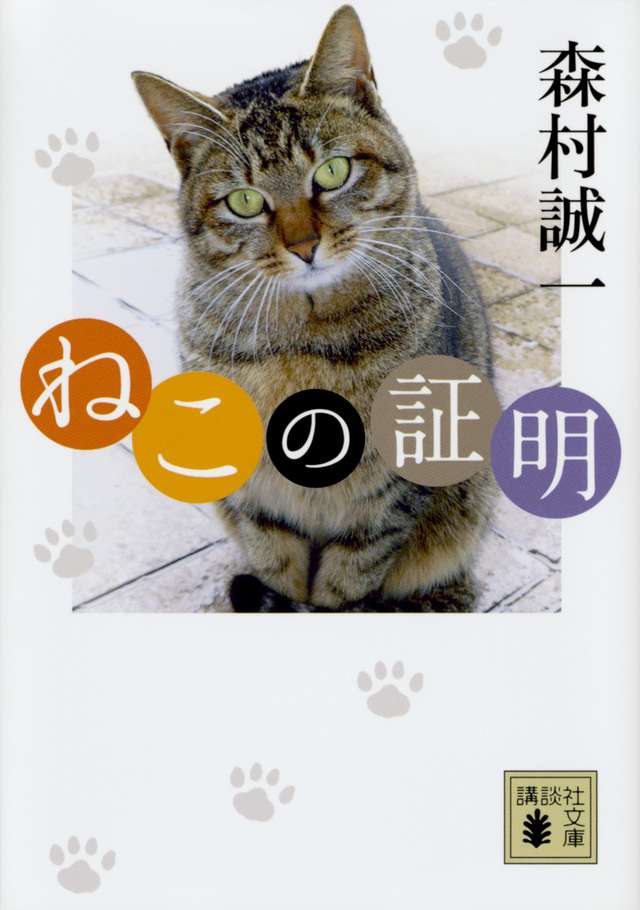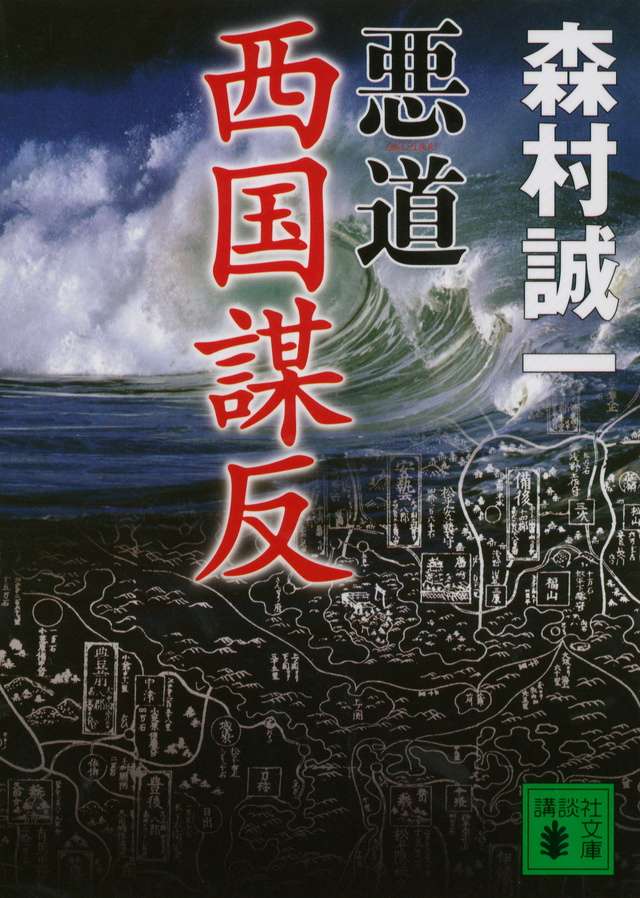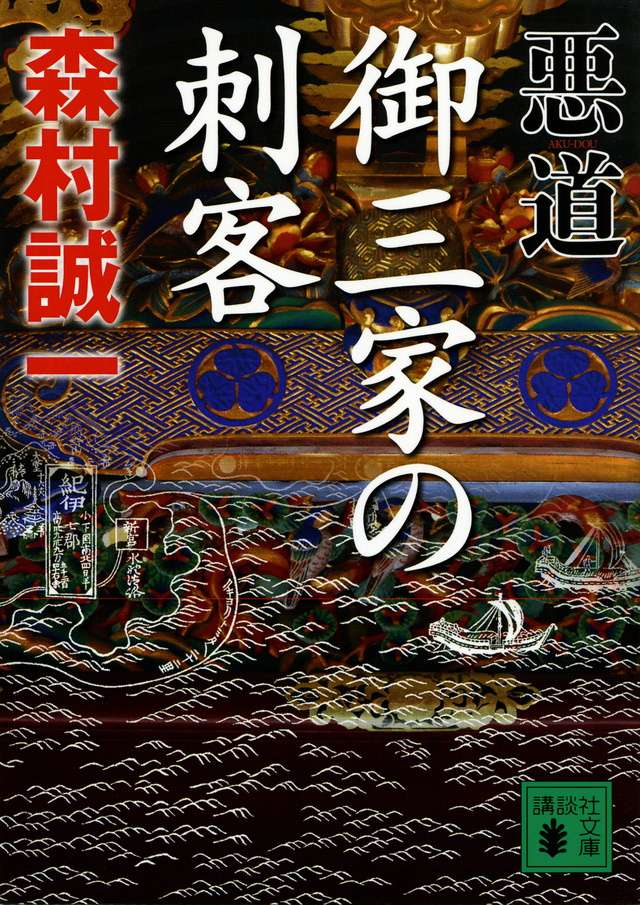追悼・森村誠一さん
文字数 3,361文字

森村誠一先生が亡くなられました。江戸川乱歩賞『高層の死角』で世に出られ、推理小説界で大山脈を築かれました。時代小説『悪道』で吉川英治文学賞を受賞されました。講談社文庫100冊目は『ねこの証明』。お人柄がにじむご自身の写真、俳句、エッセイ満載の一冊です。心からの感謝とともに、謹んでお悔やみ申し上げます。

人間の生活に最も深く関わっている動物は猫と犬であろう。そして猫派と犬派は真っ二つに分かれる。宮本武蔵のような二刀流もいるが、少数派である。
我が家は歴代猫派である。なぜ猫派になったのか、その辺のところは語り伝えられていないが、初代は野良が迷い込んで来て居ついてしまったらしい。初代からコゾと名づけられ、五、六代つづいた。コゾの次は現在のメイになっている。
メイも野良猫であったのが、我が家に迷い込んで来て、出て行かなくなった。白毛の中に三つの黒毛のハートマークがついている猫である。ペットショップで買ったり、他の人からもらったりしたのとちがって、本人(猫)の意志によって我が家に入り込んで来たことに、運命的な縁を感じた。
なぜ猫なのか。猫は犬ほど人間の役に立たない。たとえば強盗が入ったり、飼い主が窮地に陥ったりすると、犬は命を賭して主人を守ろうとする。だが、猫は真っ先に逃げ出してしまうであろう。飼育目的別にしても、犬は愛玩犬をはじめ、番犬、軍用犬、警察犬、牧羊犬、猟犬、闘犬、盲導犬、救助犬、輓曳(ものを引く)犬と多彩である。
それほど人間に役立つ犬に比べて、猫は家の中でのらくら眠っていたり、日向ぼっこをしていたり、ほとんどなにもしないのにもかかわらず、犬は愛玩犬を除いて、屋外の犬小屋に隔離されているのに対して、猫は家の中に迎え入れられ、人間同様に待遇されている。この差別はなぜであろうか。
しかも、差別は猫の間にもある。飼い猫は人間の手厚い保護を受けて二十年近くも生きるのに対して、野良の平均寿命は二、三年である。同じ猫でありながら、飼い猫と野良猫の差別は著しい。
その点、犬は保健所がどんどん狩り尽くして、野良犬はほとんど見かけない。飼い主による待遇のちがいはあっても、猫のような差別はない。だが、その差別のおかげで野良猫でも、二、三年は生きられる。
飼い主にしてみれば、理由などない。とにかく自分の猫が可愛くてたまらないのである。飼い主にとっては愛猫の仕種一つ一つがどうしようもないほど可愛らしい。炬燵の上や日溜まりに丸くなって寝ている姿や、箱座りという、前足を胸の下に折り曲げてうずくまっている姿などを見かけると、触りたくなる誘惑にほとんど耐えられない。猫が常に視野の中に入る家庭は安定感があって平和的である。
その点、使役犬が家の中に上がり込んでいると、どうも違和感がある。犬にしてみれば、自分たちの方がはるかに人間の役に立っているのに、大いに不満であろう。
「猫なで声で甘えているくせに、背中を向けると舌を出している」
と言って、猫に冷たかった。

炬燵から朦々と煙を発しており、母は竈の上に水のあんばいをしてといであった米入りの釜を取って来て、米ごと炬燵にかけた。発見が早かったので、小火のうちに消し止められた。最後の訪問客の煙草の火が炬燵蒲団に残っていて、くすぶり始めたらしい。危ないところをコゾによって救われたのである。
それ以後、母親のコゾに対する態度は一変した。大の猫嫌いであった母が、コゾを目に入れても痛くないような、文字通りの猫っ可愛がりをするようになった。
また、いつのころからか、恐ろしく不細工な黒猫が我が家に立ち寄るようになった。目は目やにだらけ、全身に擦りむけの湿疹が広がり、口は充分に閉じられず舌の先が少し覗いて、いつも涎を垂らしている。まさに化け猫を絵に描いたような面相をしていた。
なにかの弾みに、家人や私が餌をあたえたのに味をしめて、戸外の仕切り戸に影のように張りついている。だが、決して懐くことはなく、手を伸ばしても身体に触れさせない。餌だけ取ってさっと逃げる可愛げのない猫であった。
それでも次第に距離を縮めてきて、仕切り戸が開いていると、そろりそろりと家の中に入り込むようになり、家人の足音を聞くとさっと逃げ出した。だが、一定の距離を保って安心したように昼寝をするようになった。
そんな猫でも、我が家をテリトリーに居つくようになると可愛くなる。数日、旅行をしたりして不在の間は、気になる。餌をまとめて置いてきてあるが、他の野良猫も立ち寄るので、足りなくなるであろう。久しぶりに帰宅して、仕切り戸に影のように張りついている黒いシルエットを見かけると、ほっとする。
そんなクロが、不在にしてもいないのに姿を見せなくなった。見るからに不健康であったので、その辺で野垂れ死にをしたのか、あるいは猫狩りに捕まったのかと案じていると、十日ぶりぐらいに、秋の夕方、塀の上に姿を見せた。安心した家人が「クロ」と呼びかけて餌をあたえようとすると、一声長く鳴いて、フェンスから外側に飛び下りた。まるで夕陽に身を投げたように見えた。
その翌日、近所の人が、「おたくのクロが近くの空き地で死んでいる」と伝えてくれた。私の家で餌をやっていたので、うちの飼い猫だとおもったらしい。クロは自分の寿命を悟って、別れを告げに来たのだとおもった。野良でも「一飯」の恩を知っていたのであろう。死んだクロを丁重に葬りながら、あらゆる動物の中で猫が人間に最も近い位置にいるのは、犬のように目立った貢献はしないが、運命的な愛らしさを持っているからではないかとおもった。人間と犬は紐で結ばれているが、人間と猫は運命の糸によって結ばれているような気がする。

森村誠一(もりむら・せいいち)
1933年埼玉県熊谷市生まれ。青山学院大学卒。9年余のホテルマン生活を経て、1969年に『高層の死角』で江戸川乱歩賞を、1973年に『腐蝕の構造』で日本推理作家協会賞を受賞。1976年、『人間の証明』でブームを巻き起こし全国を席捲、『悪魔の飽食』で731部隊を告発して国際的な反響を得た。『忠臣蔵』など時代小説も手がけ、精力的な執筆活動を行っている。2004年、第7回日本ミステリー文学大賞を受賞。デジカメ片手に俳句を起こす表現方法「写真俳句」も提唱している。2011年、講談社創業100周年記念書き下ろし作品『悪道』で、吉川英治文学賞を受賞する。2023年7月逝去。
吉川英治文学賞に輝く時代小説の最高峰!