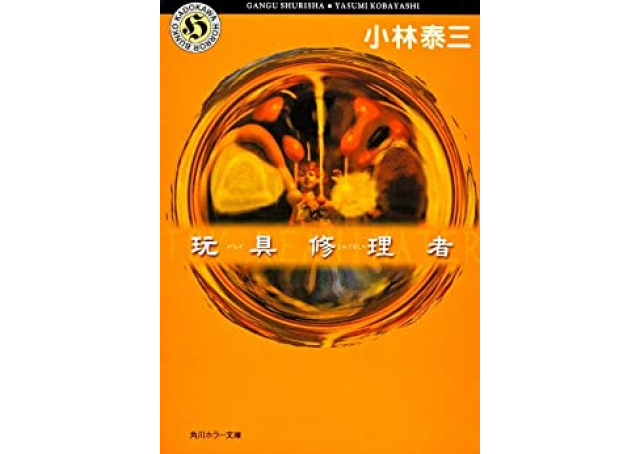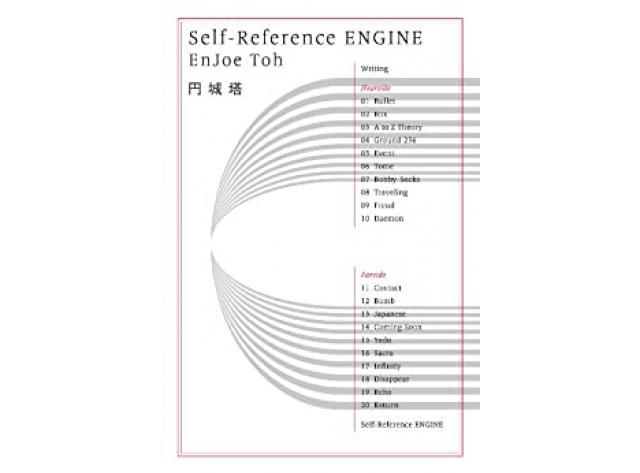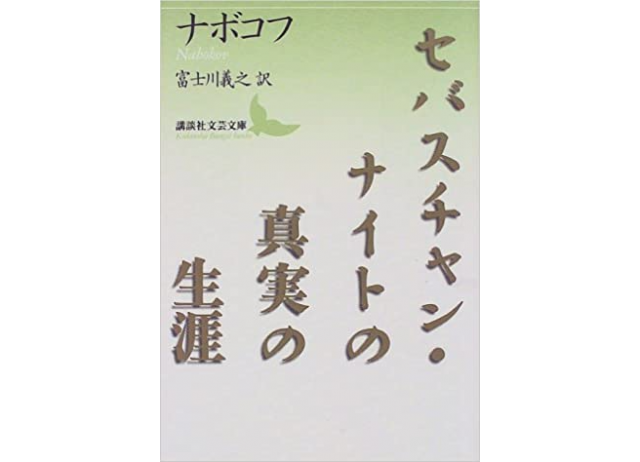早大生本読みのオススメ「記憶にまつわる小説」10選
文字数 4,234文字
今、どんな作品を読んだらいいの?
そんな疑問にお答えするべく、大学生本読みたちが立ち上がった!
京都大学、慶應義塾大学、東京大学、早稲田大学の名門文芸サークルが、週替りで「今読むべき小説10選」を厳選してオススメします。
古今東西の定番から知られざる名作まで、きっと今読みたい本に出会えます。
本を薦めるとは一体どういうことでしょうか。大抵は誰にも読まれることなく忘れられてしまうというのに……。
人の記憶に傷――たとえどんなに小さなひっかき傷だとしても――を刻みつけようと試みること、それが本を薦めることだと、少なくとも私は考えています。今すぐ読まれなくても、興味を持たれなくても構わないのです。数か月後、数年後、数十年後にどこかの誰かがふっと思い出して本を手に取ってくれたら充分……ということで、いつか誰かの傷を疼かせるような「記憶にまつわる小説」を10冊選んでみました。
(執筆:青いアイリス/ワセダミステリ・クラブ)
ワセダミステリ・クラブ(わせだみすてり・くらぶ)/早稲田大学
江戸川乱歩を初代顧問に持つ歴史あるミステリ研究会。最近はオンラインでの活動も盛んで、多角的な活動を続けている。入会は大学・学年を問わず随時受付中。興味のある方は公式Twitter(@wasemisu)までどうぞ。
伝記は、何であれ取りあえずは誰かの人生の記憶と言えます。
ではその人生の記憶を、小説のなかに落とし込んだ場合どうなるでしょうか?
この作品は、「『まんが』というタイトルの傑作を残して11歳で死亡した天才作家エドウィン・マルハウスの生涯を、ジェフリー・カートライトなる少年が記録した伝記」という形式の小説です。
なんだかややこしい。しかし、ジェフリーの記述のなかでのみ内容が示唆される『まんが』を中心に据えたこの「入れ子構造」こそ、作品全体をつらぬく重要な仕掛けなのです。
そして、仕掛けを意識しながら小説を読み進めてゆけば、冒頭の問いに対しても何か答えのようなものが見えてくるはずです。
「何物も忘れない、というのがわたしの性質であり、喜びであり、呪いでもある」と述べる人物、セヴェリアンの一人称で語られた、「完全な記憶」に基づく小説です。
惑星ウールスを放浪する≪拷問者≫セヴェリアンの物語はそれだけでも非常に魅力的ですが、この小説が「存在しない言語で書かれた書物の英語への翻訳」であることが明かされ、さらに本文中に現れる「馬」は我々の知っている「馬」とは異なる生物である(!)とまで仄めかされたとき、読者はもう言葉の迷宮のなかに引き込まれています。
果たしてこの小説の記述は正確なのか? セヴェリアンは本当に語り手として信頼できるのか? と読者が抱く疑問は、言葉で書かれた小説を「正確に」読むことなどそもそも不可能ではないだろうか、という原理的な問題へと姿を変え、「新しい太陽の書」シリーズが「小説を読むことをめぐる小説」であることを明らかにします。
言葉の魔術師ジーン・ウルフが〝翻訳〟した、至高の迷宮に迷い込んでみてください。
③『エンジン・サマー』ジョン・クロウリー
ひとつ挙げるならこれ、と言ってもよいくらいに書き出しが好きな小説です。
語り手の「ぼく」は「天使」に向かってみずからの物語を語り続けます。
はるかな未来、文明が衰退したアメリカを舞台に繰り広げられるノスタルジックで幻想的な冒険の物語は、やわらかな輝きを放ちながら読者の心を捉えるでしょう。
しかし最後まで読み終えたとき、この作品は最も純粋な「記憶にまつわる小説」と言えるかもしれないことが分かります。
「エンジン・サマー」とは、これ以上ないほどに適切で、かつ残酷なタイトルなのです。
芥川賞受賞作。
ここまで紹介した3冊には「一人称で語られる小説」という共通点がありましたが、この作品はやや毛色が異なり、少々複雑な「語り」から構成されています。
通夜の席に集まった親族たち一人一人の視点を自由に移動してゆく語りは一見すると典型的な三人称に見えますが、注意して読むとそう単純な話でもないことが分かります。
「死んでいない」者たちによる、「死んで居ない」者を記憶するための儀式である通夜は、「小説の舞台」となったときどのような効果を発揮するでしょうか。
古い修道院に住む老婆たちの姿が、三人称的な視点から語られることで小説は開始されます。
しかしここに≪ムディート≫と呼ばれる召使の一人称がたびたび紛れこみ、さらに≪ムディート≫はぶしつけにも、他の登場人物の台詞の中にまで入り込み何やら所感を並べ立て始めるのです。
この不安定きわまりない「語り」のために作中の時間が前後し、舞台があちこちへと移動し、登場人物が混然一体となり続ける様はまさしく「みだら」な混沌と言ってよいでしょう。
実に手強いこの小説を〝読む〟ための最初の足掛かりが、≪ムディート≫が饒舌に語り続ける彼みずからの記憶なのです。
ミステリー小説には、しばしば記憶を読み解くことをテーマにした作品があります。
本書に収録された中篇「ノヴァーリスの引用」もまた、アガサ・クリスティー『五匹の子豚』、有栖川有栖「桜川のオフィーリア」といった「記憶を読み解くミステリー」の名作のなかに数え入れられるはずです。
大学で共に学んだ男たちは、かつての仲間の1人「石塚」の不可解な死について、それぞれの解釈を語り続けます。
結果として導かれる「真相」は、むしろ謎解きやミステリー小説そのものの構造を脱臼させかねないものであり、のちに芥川賞を受賞する奥泉光の創作態度がよく表れていると言えるでしょう。
「人間の記憶」を、テーマというよりむしろ作品を成立させるためのガジェットとして徹底的に利用しつくした中篇「酔歩する男」が必読です。
パブで出会った見知らぬ男が語る、最愛の女性を取り戻すための奇妙にねじれた物語は、少しずつ作中の現実を侵食してゆきます。
最後まで読み終えたとき作品全体の構図が鮮やかに変化する様は、秀逸な短篇である表題作にも共通するものです。
「人間の記憶とは何か」という問題に真正面から挑んだ短篇「ぼくになることを」が収録されたSF短篇集です。
一定の年齢に達すると、記憶のバックアップが保存された「宝石」に〈スイッチ〉してみずからの脳を放棄することが当たり前になった世界。
〈スイッチ〉した後の自分は本当に〝同じ〟自分と言えるのだろうか、と「ぼく」は悩み続けます。
もちろん「人間の記憶とは何か」「自分とは何か」の問題に作中で答えが与えられることはありません。(与えることができたらノーベル賞もの、というか不可能?)
しかし、こうした自己言及的なテーマが選択されることによって、同時に「小説」そのものの在り方すら問われることがある……それがSFというジャンルのひとつの魅力ではないでしょうか。
自己言及的なテーマを突き詰めてゆくと、「小説とは何か」というある種使い古された問題に至ることになります。
円城塔は、むしろ向こうから積極的に「何が小説か」と問うてくるような作品をデビューから一貫して書き続けている作家であり、その挑発的とも言える作風によって「小説」そのものの在り方を〝いじり回して〟きました。
床下から飛び出す大量のフロイト、江戸弁で喋る巨大知性体といった奇妙な挿話がゆるやかに繋がってゆくこの連作短篇集は、「全ての可能な文字列。全ての本はその中に含まれている」という一文から始まります。
アーカイブ、つまり記憶としての書物の在り方について「自己参照するエンジン」とは、円城塔と名付けられた〈小説機械〉のことを指すのかもしれません。
最後に、「伝記」をめぐる小説をもう1冊紹介します。
この作品もまた、早世した作家セバスチャン・ナイトの「真実の」人生について、異母兄弟である語り手――名前は「V」としか明かされません――が記した伝記という形式の小説……であるかのように思えますが、そもそも、セバスチャン・ナイトと語り手の間にはほとんど親交が無かったというのだからおかしい。
ゆえに、「V」は生前のセバスチャンを知る人物を訪ねまわることで、継ぎはぎ的に「セバスチャン・ナイトの真実の生涯」を描き出すことになります。
結果として作品は「伝記」小説ともミステリー小説ともつかない曖昧な領域のなかを漂い、「真実」は宙吊りにされ続けるでしょう。
「記憶」「伝記」「人称」「言葉」……10冊を紹介するなかで何度も登場したキーワードすべてが、この作品には現れています。