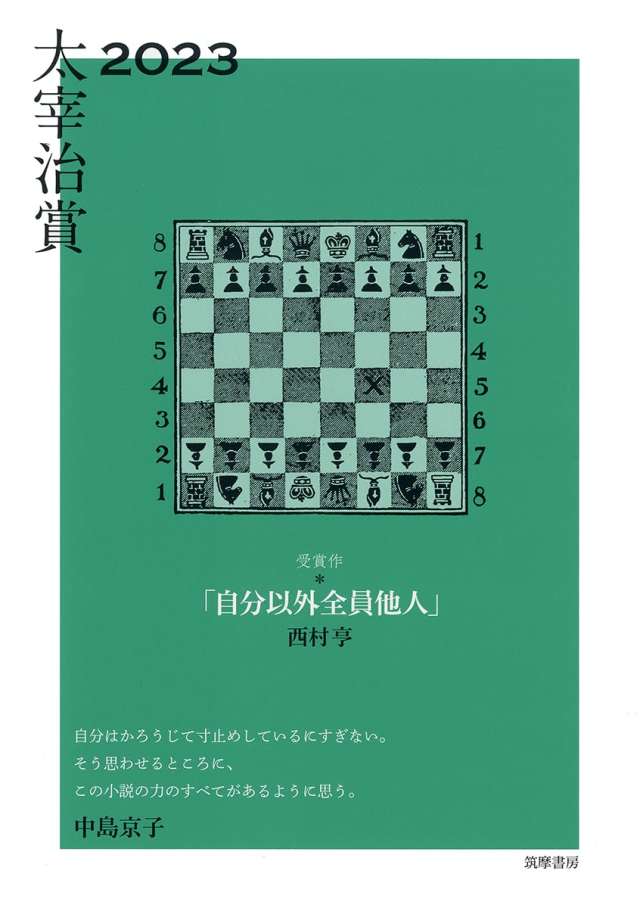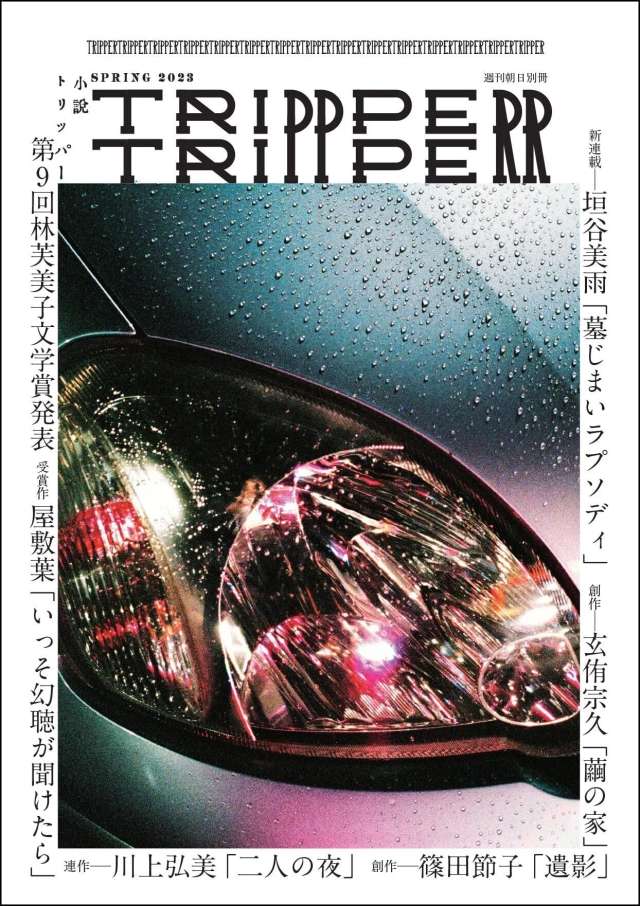生きづらい現代社会をどう生きるか? 自分勝手さに潜む現実のままならなさ
文字数 4,091文字
現代社会を生きているうえで、「生きづらさ」を抱いたことのあるひとも多いのではないでしょうか。
生きづらさを抱える原因には、他人とのコミュニケーションや社会がいまなお抱える歪みなど、多くの問題が背景として関わっています。そして、「ケア」という言葉が浸透した現代においても、生きづらさを吐露できないまま、苦しんでいるひとは少なくないはずです。
今回は個性的な語り手を通じて生きづらい社会を浮かび上がらせる、独特な新人賞受賞作を二作、紹介していきます。

生きづらい現代社会をどう生きるか? 自分勝手さに潜む現実のままならなさ
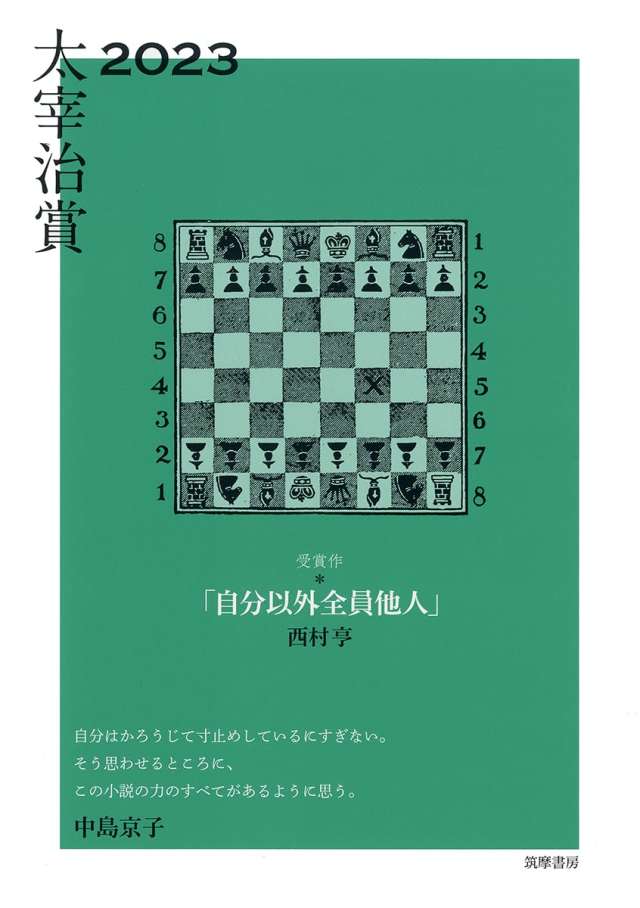
西村亨『自分以外全員他人』
第39回太宰治賞の受賞作。
物語の語り手は45歳を迎えようとしている柳田譲。彼はコロナ禍のなか阿佐ヶ谷のマッサージ店で働いて、他人の自分勝手な言動に苛立ちを募らせています。そして譲は苛立ちが爆発して他人に迷惑をかけてしまわないよう、自らに死亡保険をかけてゆるやかに自殺をしようと決めていました。
そもそも、「他人に迷惑をかけない」ように細心の注意をはらいながら生きている譲は、はたしてどのようにそれを実践するのでしょうか?
その答えはまずひとつ、趣味を見つけて気を紛らわせること。譲は新しくクロスバイクを購入し、ひたすら遠くに行く妄想をして息苦しい現実社会から逃れようとします。
そしてもうひとつが、規範に対して従属的になり本能的衝動を抑制すること。明文化されているルールや暗黙のうちに共有されているマナーに従っていれば、調和を乱すことも他人に迷惑をかけてしまうこともありません。それゆえ譲は規範に従うことで理想の自分をつくりあげ、生きづらい社会をなんとか生き抜こうとするのです。
そのため表面的な言動だけを見れば、譲は作中人物が評していた通り〈まともな人〉といえるのかもしれません。
しかしその胸中では、社会や他人に対する鬱憤がいまにもはちきれんばかりに溜まっています。自分が規範に従って他人に迷惑をかけない「理想的な人間」で在ろうとしているからこそ、規範に従おうとしない他人が事あるごとに目に留まってしまうのです。
コロナウイルスによって感染予防が課されている現代社会とも重ね合わせながら、自分勝手な人間を生々しく描いたいかにも共感できそうなエピソードがいくつも並べられています。
ただ、本作はままならない社会を我慢して生きている人間が、ルールを破る人間を糾弾するだけの話では決してありません。
はたして人間は、誰にも迷惑をかけない「理想的な人間」でいられるのか——その限界を突き詰めていくところに本作の面白さがあります。
たとえば譲は自転車で歩道を走りながら、歩道の真ん中を歩くひとや猛スピードで逆走してくる自転車に対し、ルールやマナーを守らない厚かましい態度に苛立ちを覚えていました。しかし、その感情が表で爆発することはありません。なぜなら、「本来自転車は車道の左側を走らなくてはならないと交通法で定められている」から。ルールやマナーを理由に苛立ちを抑えながらも、譲自身がルールやマナーを守れていないのです。
しかし譲は、自分が歩道を走行していたのは「車道の自転車レーンに路上駐車の車がひしめいていたから、歩道を走行するのもやむなし」と自己弁護し、悪いのはルールやマナーを守れていない他人だとして悪態をつきます。挙げ句の果てには「生きている限り自分は損するようにできているのだ」と境遇を嘆くのです。
作中ではこうした倒錯的状況——規範に従うよう他人に要請しながら、規範を守るために別の規範を破っている光景——が多々見られます。苛立ちを抑えるために〈理想の自分〉で在ろうとしているからこそ、抑えきれていない醜い他人に対して他責思考を働かせてしまい、逆に〈理想的な自分〉で在ろうとしている自分自身の言動に対して盲目になってしまう。自らが忌み嫌っている他人と同じことをしながらも自己を正当化してしまっているため、他人に迷惑をかけないよう気を配っているはずが「自分のことしか考えていない」矛盾に陥ってしまうのです。
それを一人称で、読み手に気づかせないよういかにも共感させるように描くことで、ほかの作品とは異なる独自の読み味を獲得していました。
物語の冒頭、譲は「図書館やサウナなどの公共の施設でもそうだが、いつも座っている場所を勝手に自分専用の場所とし、そこを使われたら嫌がらせをしてくる頭のおかしな人間というのはどこにでもいる」と語ります。
それでは、はたして彼自身は〈頭のおかしな人間〉ではないと確信をもっていえるのか——物語の結末には、この社会で「理想的な人間」で在り続けることの限界が描かれています。ぜひ読んで、譲の思考に浸ってみてください。
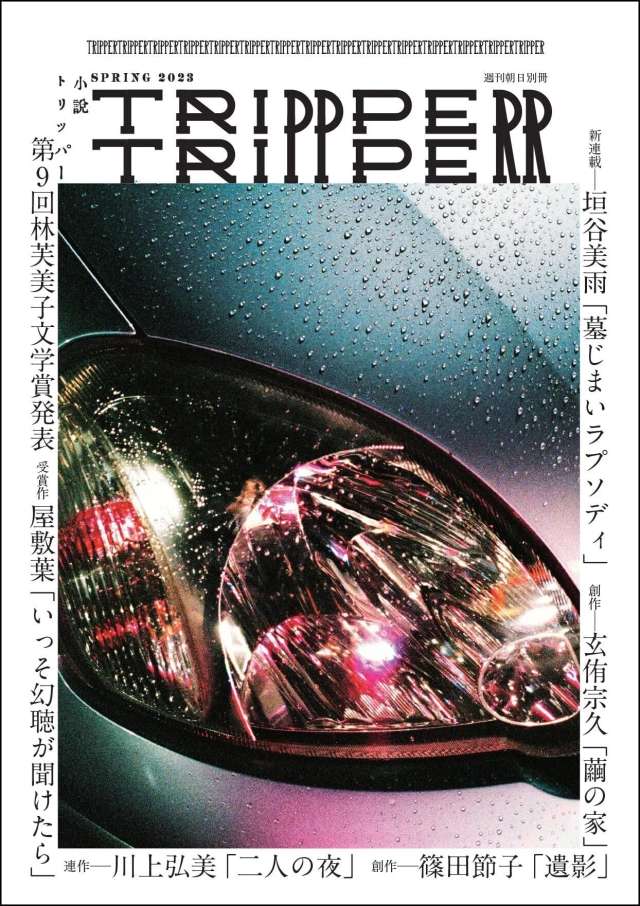
屋敷葉『いっそ幻聴が聞けたら』
第9回林芙美子文学賞の受賞作。
いっそ幻聴が聞けたら——そう望んでいるのは、30歳を迎えた主婦の板野陽子。陽子はこんにゃくを製造する工場に週3回、半日で終わるパートとして従事しながら夫の稼ぎに依拠して生活していました。あまり裕福とはいえない彼女の日常が淡々と描かれていきます。
男女格差の解消や経済成長などにより、女性の社会進出が進み始めている現代。働きに出ることなく家事に勤しむ専業主婦は家父長制批判と結びつき、「時代に遅れている」としてその在り方を糾弾されがちです。実際は女性がより社会に参加できるようにしながら、専業主婦に憧れてその生き方を選んだひとを否定ばかりしないのも肝要でしょう。
語り手を務める陽子もパートにこそ出ているものの稼ぎは少なく、生活の大部分を夫に依存しています。そんな陽子は自分の生活を顧みながら、「個性の尊重と報道するのだから、時代の波にのらない人だって許容されるべきだ」と語ります。これに関しては尤もな意見で、ここだけ抜粋すれば、陽子の立場を活かして多様性のありかたを訴える作品のように思えるかもしれません。
しかし、あくまでも正論なのは文章だけを抜き取った場合。時と場合によっては、「個性の尊重と報道するのだから、時代の波にのらない人だって許容されるべきだ」という言葉を自堕落な生活に対する自己弁護のように、都合よく利用してしまうことも可能なのです。
陽子は悪びれることなく、自らを最優先した言葉を次々に放っていきます。
「産めばさらに働かなくてよくなるだろうから、私も子供のことを考えなくもないが、痛いのは労働と同じくらい嫌なのだ」
「養っていただけるのならば、私は夫の前でどこまでもしおらしくいられる。」
「夫の顔は三日会わなかったら忘れそうだ。別にこの人でなくて良かった。でも、結婚してみてこの人でないとダメと思った。稼ぎは少ないが、妻にいて欲しい男。絶滅危惧種。利害の一致。」
そして挙げ句の果てにはふだん迷惑に思っている隣人の田端さんに対しても、養ってもらえるのであれば夫と離婚するから娘にして欲しいと名乗り出ます。さらには断られると「人のことを金目当ての薄情な女みたいに言ったが、利用していたのは田端さんの方じゃないか」と責任を擦りつけるのです。
他人の心情をことごとく軽んじて自分勝手な理屈で動き、いざ不都合があれば他責思考で自己正当化をはかる——先ほど紹介した「自分以外全員他人」の譲にも似た思考回路で、最後まで反省もなく開き直っている語りには独特の魅力があふれていました。どこまでも他人を理解できないさまが、寄り添うことなく突き放すかたちで描かれています。
一方、陽子の置かれている境遇は必ずしも、彼女の性格難だけで一括りにはできません。工場の仕事は男女で割り振られ、新しく入社してきた河村さんは少しでもお金を稼ぐためにぎすぎすした工場で生き残ろうとしています。対する隣人の田端さんは働くことなく親類ともども裕福かつ自適な生活を送っており、背景に潜んでいる透明化されたジェンダーギャップや貧富格差が突きつけられるのです。彼女が自分勝手に養われたいとこいねがっているのは生来の自堕落さを反映していると同時に、いまだに女性の雇用問題が解決しておらず、貧富の差が拡大し続けている事実を象徴してもいます。
彼女の「私、未来とかどうでもいいんです。今が辛くて、今を助けて欲しいんです。苦しくて、仕事に行くのが辛くて、何でお金がないと人は生きてちゃいけないんですかね?」という言葉は、決して無視できない現代人の多くが抱える生きづらさでしょう。
だからこそ、ラストシーンは自分勝手な彼女にどこか共感をおぼえてしまう、哀愁漂うものになっていました。
生きづらさを抱えて「幻聴がきけたら」と願う彼女の生きざまを、読んで確かめてみてください。
今回は以上の二作品を紹介していきました。
どちらの作品の語り手も、裕福とはいえない環境を生き抜いていくためにある種の「自分勝手」な振る舞いをしていました。それを「自己中心的」だと一顧だにせず切り捨てるのは簡単ですが、一方で、そうした背景には社会構造や人間関係を原因とした、理解されづらい生きづらさが潜んでいます。
独特な語り手の面白さを堪能しながら、現代社会の抱える歪みがはっきりと見えてくるようになっている両作です。
第13回「この新人賞受賞作がすごい!」で取り上げたのは――