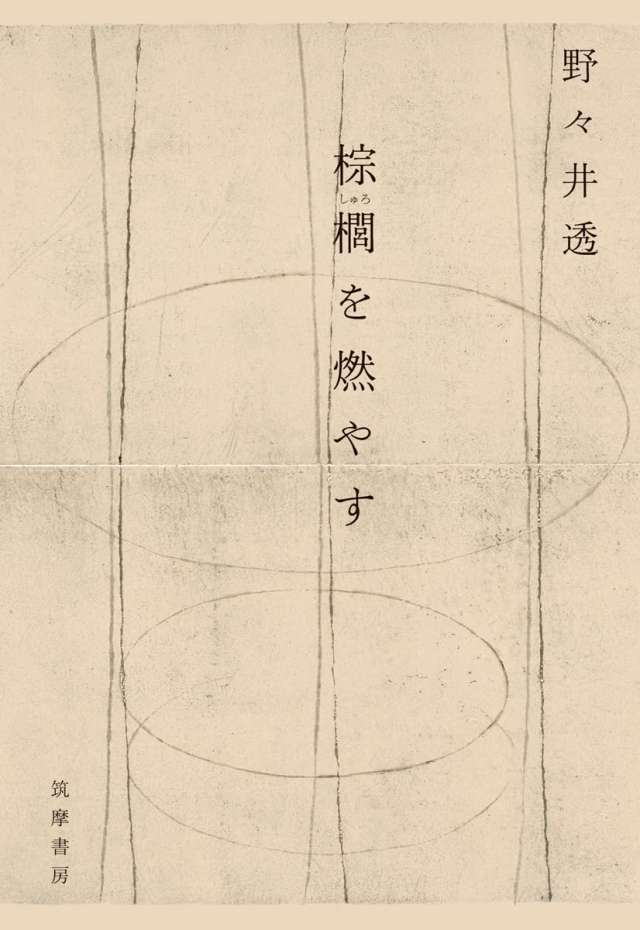父のすがたを捉える娘、その眼差しから広がる世界
文字数 3,448文字
みなさんにとって、父親とはどのような存在でしょうか?
もしかしたら、良い印象を抱いていない方もいるかもしれません。頑固さに振り回されたり、家庭を顧みなかったり、嫌な思い出を抱いているひともいるでしょう。フィクションにおいても、家父長制における負の象徴として「父」が描かれることはしばしばあります。それほどまでに、家庭内における「父」の影響力は大きいものです。
しかし、「父」の像は決して悪いものだけではありません。子どもを育てる役割を担い、愛をもって接していく父親も現実にはたくさんいます。
今回は父親を悪の象徴に据えるのではなく、娘の視点から父親を素直に捉えて、その周辺に広がる世界を描いていく新人賞受賞作を二作品、紹介していきます。

父のすがたを捉える娘、その眼差しから広がる世界
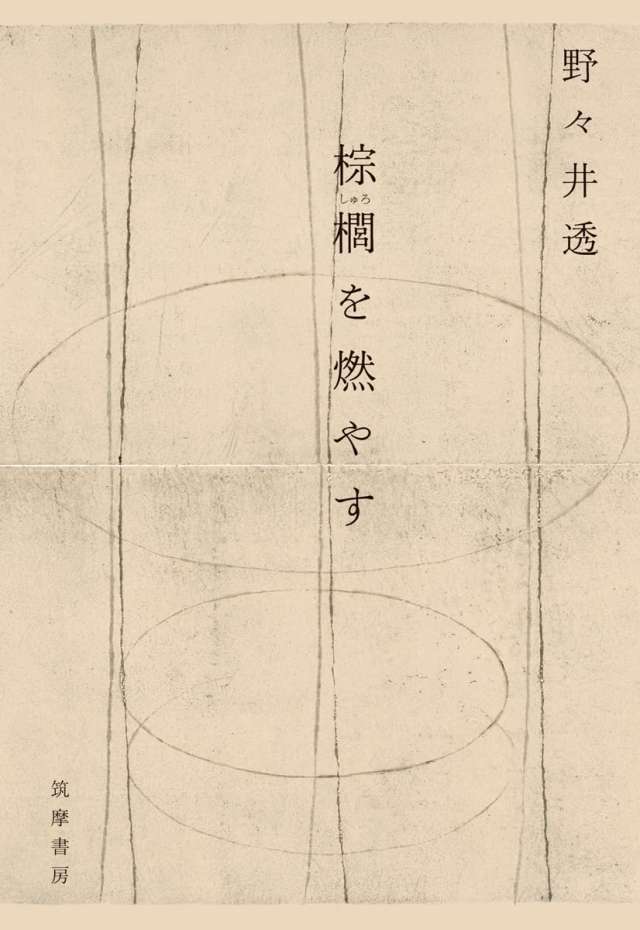
野々井透『棕櫚を燃やす』
第38回太宰治賞の受賞作。
語り手を務める女性、春野は、交際相手と同棲生活をはじめたものの数か月で頓挫し、いまは妹の澄香、そして父親の三人で暮らしています。火にかけ割れないよう必要なひびをいれ、「土鍋みたい」になんとか均衡を保っていた家族関係は父が病気を患い、余命一年と宣告されたことで崩壊のきざしを見せます。父親の余命宣告を受け、澄香は「これからの一年を、わたしたちはあまさず暮らそう」と春野に宣言するのでした。
三十前後の姉妹と病気の父親で、近所との交流も希薄なまま生活を続けているのは、世間一般から押し付けられる「しあわせな」家族像からはぐれています。しかし、誰かが誰かの幸せ/不幸せを決められるはずはありません。そのため、春野たちは他人から規定される模範的な家族の幸せ/不幸せを跳ね除けて、それらに干渉されない日常の生活を営もうとします。
春野の身に起きた交際相手との破局をはじめとする、社会と接触した結果の辛さを最低限の描写にとどめ、ひたすら生活の断片で作品を組み上げていくのが象徴的でしょう。冒頭の「張り付けて永遠のようにしたい瞬間」を交互に口にするやりとりや、澄香の話す仕事,同僚に関するエピソードの羅列など、些細な日常をあえて並列していくことで分厚い殻をつくり、身近な生活の輪郭をつくりあげています。
しかし、世間から押し付けられる幸せ/不幸せをかわそうと内なる家族の共同体にこもっても、次なる問題が発生します。似ている人間同士で集ったとして、他人が他人であるがゆえの、覆しようのない相互不理解がそびえているのです。
春野は「相互不理解のそびえる瞬間」、理解しているつもりになっていた相手がふと見せる新しい一面に対する怯えを、「むるむる」という擬音で説明しています。むるむるが与える未知の刺激は、「痛い」「悲しい」のような単一的な感情だけではない、理解しようと、現実の肉体に変化を与えようと願う心理が働きます。そして社会から遠ざかり日常の殻をつくっている春野にとって、能動的にアクションを起こすのは肉体と身体を剥がそうとする煩わしさを伴うのです。
そして病気を患い「さもありなん」(そんなこともあるだろうさ)と社会の苦しさを受け流すスタンスが崩れ、弱さを見せるようになった父に対して、春野はこの「むるむる」を抱くようになっていきます。社会から逃げた先として安心感を与えてくれていた父を前に、「面倒だから、悲しいだけにさせてよ」と、逃げ場をなくしたまま距離感を掴み損ねてしまうのです。大きな社会との軋轢を描くだけでなく、逃避した先の小さな社会でも直面する相互不理解という現実を突きつけることで、世界観を作り上げている殻が剥がれて逃げ場のない「個」が顔を覗かせるようになっていました。
それでは、突き詰めれば「個」でしかない、悲しみを共有できない私たちは他人とわかりあえないのでしょうか?
春野ら家族はディスコミュニケーションのすえに、胸の奥で震える触れられないもの、「たましい」を見出します。たとえ気持ちを共有できずとも、継がれてきたもの、残すことができるものはあるのだと悟り、「たましい」の部分では通じ合っているのだと、春野は改めて父を捉えるのです。「たましい」は、身体と肉体を剥がした先にある芯の部分に違いありません。
病んでいく父と向き合う、一年間にわたる娘の静かな日常が描かれている作品でした。

平沢逸『点滅するものの革命』
第65回群像新人文学賞の受賞作。
多摩川緑地沿いの団地で父親と二人暮らしをしている「わたし」ことちえは、まだ小学生にも満たない少女。父親は河川敷に埋まっているかもしれない懸賞金付きの拳銃を見つけるべく、毎日河川敷へと繰り出して意味のない行為を繰り返しています。ちえは父親に連れられながら、河川敷で遭遇するひとびと、雀荘を経営する鈴子さんや大学生のレンアイをはじめとする、父親の知り合いたちを五感をもって観察していきます。
まだ小学生にも満たない「わたし」を一人称視点に据えるとき、ほとんどの作品では年齢相応の無垢な語りが採用されます。しかしこの作品で語り手を務めるちえは、非常に理性的です。地の文で「これはもうまったく恥ずかしい話なのだが、わたしは最近になってようやく自分がいつか父ちゃんや鈴子さんのような大人の姿になるという事実に気づきはじめたところだった。」と語り、煙草の銘柄や麻雀の役だろうと何度も正確に語っていくのです。到底、子どもらしい語りのスタンスではありません。
それでは、はたしてこの「語り」は物語にどのような意味をもたらすのでしょうか? それは台詞や風景を同化させた、五感で喚起される等身大のイメージです。
目の前で繰り広げられる大人たちの会話に対し、ちえは自分の言葉を発しなければ、思考を挟むこともありません。つまりちえは観測者の立場に立ち、大人たちの会話はそのまま意味のない言葉の羅列として据え置かれます。そして多摩川の緻密な情景描写と重なることで、ちえの目の前に広がる世界を、離れたところにいる距離からスケッチをしているような描写が延々と続くのです。
それを象徴するように、ちえが描写のための置物のように扱われている描写もいくつか見受けられます。鈴子さんが父に「(ちえは)どうせ聞いちゃいないから」と話しているのに対して〈鈴子さんの言うとおりわたしはふたりの会話などまるで聞いていなかった〉と反応したり(まるで聞いていないなら反応はできない)、「父ちゃんが眠っている私をおぶり」と語ったり(眠っているなら知覚はできない)。
普通の物語であれば矛盾した描写になりえる文章は、本作だとこうした描写を挟むことで前述した「スケッチしているような」距離感を物語にうみだします。多くの一人称作品のように少女が知覚する世界を〈無垢な世界〉として写実的に写しとるのではなく、作者の手によって少女をスケッチするように描くことで、〈リアルな世界〉に写し取られる少女の瑞々しい五感をより繊細に表現しているのです。
下手をすれば違和感だらけになってしまいそうなこの手法が成功しているのは、新人離れした描写力の上手さが備わっているからに他なりません。父親やその周囲の人々との日常が、瑞々しく表現されている物語です。
今回は以上の二作品を紹介していきました。
どちらも娘の眼差しから周囲を捉えつつ、独特の表現方法でオリジナルな世界を立ち上げているのが印象的です。
たとえそれが父親を中心とした小さな世界だとしても、当人にとってはかけがえのない唯一無二の居場所に違いないでしょう。ひとによって見えている世界は異なるのです。
第9回「この新人賞受賞作がすごい!」で取り上げたのは――
交際相手と同棲を解消した春野は、妹の澄香、そして父親の三人で暮らしていた。
「さもありなん」というスタンスで日々を送る家族だったが、ある日父が病気を患い、余命一年と告げられる。
多摩川緑地沿いの団地で暮らしている小学生にも満たないちえは、父親の目を盗んで多摩川に遊びにいく。ちえは夏の多摩川の風景と、周りの大人たちの会話を五感で捉えていく。