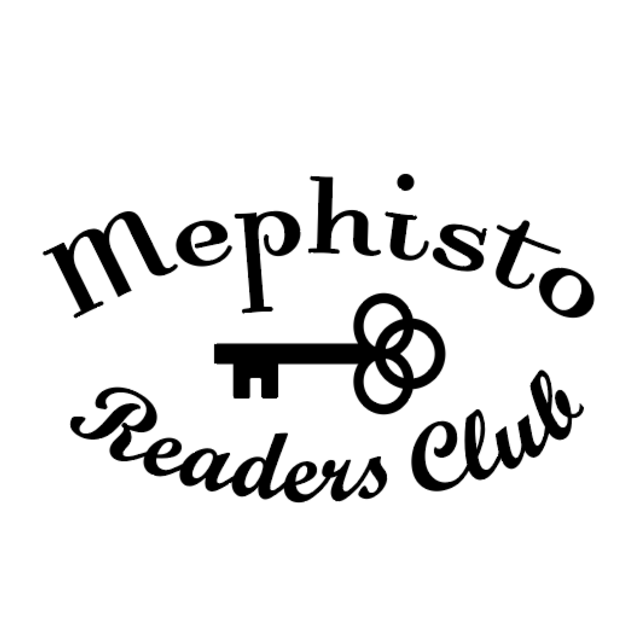青春の痛さを「声」に託す 三宅香帆
文字数 2,171文字
青春の痛さを「声」に託す
青春はなぜ痛いのだろう。
いやそんなことはない、一般的に青春とはキラキラしてて切なくて美しい思春期のきらめきのことを指すはずだ、と普通は思うのかもしれない。しかし、考えてみてほしい。キラキラした青春なんて、いったいどれほどの人が体験したことがあるのだろう。振り返って自分自身のことを考えてみると、青春と呼べる時期を思い出すだけで、胸の奥底が痛痒くなってくるような、むずむずとした暗い感情を抱くことになる。他人との距離がうまく取れなくて、他人とずっと一緒にいたいわけでもないけれどひとりにもなりたくなくて、エネルギーだけを持て余しているような、そんな日々のことを私は思い出す。これ以上生きたくないけど死にたいわけでもないみたいな、傲慢で切実な時期。それが私にとっての青春である。どう考えてもそこに私はキラキラした要素を見出すことができない。ただ、痛かった。
前置きが長くなったが、本作を読んでいる時に私の頭を突き刺したのは、自分にとっての暗くて痛い青春の記憶だった。本作の描く青春は、私の思い出す青春と、たいして違いがない。そのことに驚いた。なぜこの作者はこんなにも青春の痛さを鮮烈に描くことができるのだろう?
物語は、とある男子高の二年E組の人気者である「山田」が亡くなった、というショッキングな知らせから始まる。山田は交通事故で突然、亡くなってしまった。彼の死から3日後、静かになってしまったクラスメイトに教師が話しているその時、驚くべきことが起きる。山田の声が、スピーカーから響いたのだ。しかも山田は教室の人々と話ができる。亡くなった山田は、スピーカー越しに生き返った。声だけで。
二年E組の山田の友人たちは、やがて成長していく。いつかは教室を卒業する。しかし山田は声のままで、教室のスピーカーに存在し続ける。果たして彼はどうなるのだろう? 青春小説としか言いようのない本書は、男子校を舞台に、声だけになってしまった山田と友人たちとの関係性を描いてゆく。
本作の魅力のひとつは、男子校の会話を写し取ったのかと思うほどリアルでテンポの良い「会話」にある。男子学生たちの会話は、大人が読むと苦笑してしまうほど、くだらなくてとても繊細だ。自分たちの今しかない楽しさを確認するかのように、彼らは会話を重ねる。山田は「声」だけの存在になってしまっているから、彼の声で発する言葉がすべてなのだ。それはある意味、大量のテキストでコミュニケーションするようになってしまったSNS時代の青春小説においてとても珍しいことなのかもしれない。テキストではなく、発される会話によって、コミュニケーションが進んでいく。それが小説で綴られる快楽が、たしかにある。おそらく読者のなかには「そうそう、男子高校生だった時の会話ってこんな感じだった」と思う方もいるのではないだろうか。
また声だけの存在になった山田は、週末の夜にラジオを始めるようになる。この描写がまた秀逸なのだ。ラジオとは一方的なコミュニケーションだ。ひとりで喋って、一方通行で思いを伝えようとする。私はこの描写を見て、「でも、山田だけじゃなくて、青春と呼ばれる時期を過ごす10代の時って、だいたいこんな感じのコミュニケーションだよなあ」と思ってしまったのだ。
一方通行に、ひたすら自分の思ったことをしゃべってしまう。時には他人に気づかれない場所で、他人に言えないことを、ひたすら言いたくなってしまう。しかしそれが他人に気づかれないのは、ちょっとだけ寂しい。気づいてくれたら、嬉しくなる。人がいないところで喋ってるから、気づかれないのは当たり前のことなのに、でも、どこかで気づいてほしいと思ってしまう。――山田のラジオは、10代を通過した人々みんなにとって、どこか思い当たる節のある描写となり得るのではないだろうか?
なぜ本作は、こんなにも青春の痛みを描くことに成功しているのか。それはきっと、青春と呼ばれる時期に痛さを感じたことのある人は……一度死んだ山田のように、声だけの存在であったことがあるからだ。
こんなふうに言い切ってしまうと、なんだか誤解を生むだろうか。しかし私はやっぱりどうしても本作の核はそこにある、と思ってしまう。10代の時、誰かに認められたくて、好かれたくて、愛されたくて、だけどそれが叶わなくて、仲間と同じような場所にいられない。ひとりだけ死んだような気がしてしまう。でも自分の声は、だれかに届いてほしくて、ひたすら喋ってしまう。身体と感情はどこかに置いてきたような気がしてしまう。
――山田の痛みは、思春期を経験した人すべての痛みである。
こう書くと、言い過ぎだと苦笑されるかもしれない。が、それでも私は山田というキャラクターに普遍的な共感を呼び起こす力があると思っている。
青春は痛くて、10代の頃のコミュニケーションなんてたいしてうまくいかない。自分だけどこか置いていかれたような気持ちになるものだし、自分だけ教室にしがみついている心地のする人もいるかもしれない。しかし、だからこそ、山田のいた日々は鮮やかに描かれる。
青春の痛みが、声だけになった山田に託される。それはきっと、読者にとってもどこか覚えのある、懐かしい痛みそのものであると私は思うのだ。