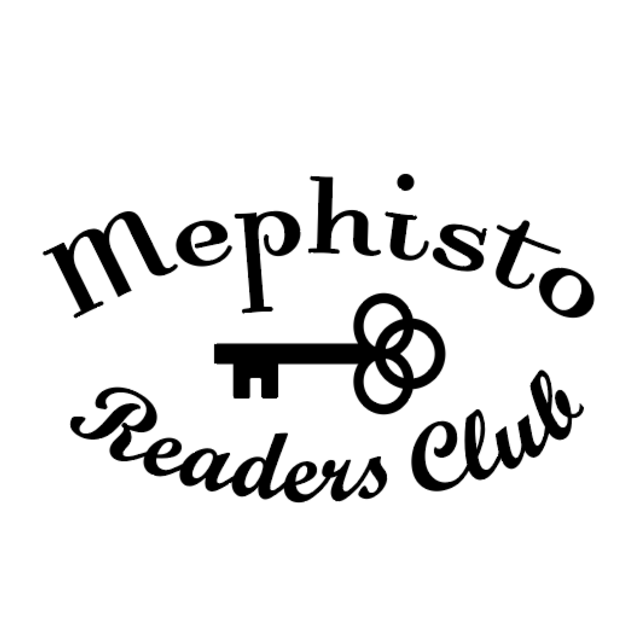『死んだ石井の大群』試し読み
文字数 43,918文字

理由なんてなかった。
物心ついたときから、ずっと、ただ、なんとなく、死にたかった。
朝起きると死にたかった。
死にたいまま学校へ行き、死にたいまま授業を受け、死にたいまま家に帰った。
死にたいままご飯を食べ、死にたいままだらだら過ごし、死にたいまま眠った。
死のうとした。何度も。
死ねなかった。いつも。
首を
薬をたくさん飲んだ。
結局目覚めた。
屋上のへりに立った。
足が
線路に飛び込んだ。
寸前で電車が止まった。
死は念願だった。
念願のはずだった。
わたしを救ってくれるのは、わたしを連れ去ってくれるのは、死だけのはずだった。
なのに。
わたしは生きている。
〈生き残った皆さま、おめでとうございます。第二ゲームは隣の部屋にて実施されます。ご移動をお願いいたします〉
扉がひらく。
唯以外の生存者が、ぽつぽつと重い足取りで、次の部屋へ歩みを進める。
唯も続く。
扉の前で振り返る。
血で
唯は目をつむり、手を合わせる。
〈速やかにご移動をお願いいたします〉
唯は死にたいが、まだ死ねない。
こんないかれた遊びを
第一章 デッド・ドッジ・ボール
【唯】
白い部屋にいた。
人がたくさんいる。
唯は寝ぼけまなこで、辺りを見回す。
知らない部屋だった。体育館を半分にしたみたいな広さの、真っ白い部屋。
知らない人ばかりだった。おばあちゃんやおじいちゃん、小学校低学年くらいの男の子、女の子もいた。幅広い年齢の男女が、寝たり、座ったり、立ったり、歩いたり、話したりしていた。百人はいる気がする。唯は座ったまま、しばらくそれを
首に異物感があった。行き交う人たちの、首を見る。
そもそもこの状況は、何?
唯は記憶を探る。何をしていたか、まったく思い出せない。学校へ行っていた気もする。家に帰った気もする。ベッドで寝た気もする。何があって、今、こうなっているのか、見当がつかない。
全員が、体操着を着ている。大人も子どもも。唯も。うちの中学のと、似ているけど、微妙に違う。のか? 自信がなくなってくる。記憶がふわふわしている。白い、
死にたいな、と唯は思う。
なんだかよく分からないし、死にたい。
左手首に目を落とす。線状の
右手で、そっと
目を開けると、唯を見つめる女の子がいる。慌てて腕を隠す。
「大丈夫?」おそらく同年代の、
「いや、」目を合わせ、
「ごめんね、急に話しかけちゃって」女の子はぺたんと座り、唯と向き合う。花がひらくみたいに笑って「同い年くらいの子、探してて」
「あぁ」唯は低い声で応じる。わたしもこの子みたいに、高い女の子っぽい声を、とっさに出せるようになりたい。「なるほど」番号に目を
「いくつ?」その子に
「
「うん」
「十四」
「え、一緒」
「ほんと?」
「うん。あたしも十四」
「中二?」
「そう」
「じゃあ同学年だ」
「だね」その子は
「年下の子も、いそう」
「あーたしかに」その子はきょろきょろと見回し「小学生っぽい子もいるね」
「ここ、どこか分かる?」唯は訊いてみる。
「ぜんぜん分かんない」困った表情を見せながらも、その子は常に笑っている。「なんか、起きたらここいた」
「わたしも」
「意味わかんないよね」
「意味わかんない」
「名前は?」
「えーと、」
「ごめんあたしから名乗る」その子は座ったまま背筋を伸ばし「イシイアカリです」
「イシイ? わたしも」唯は驚く。声が弾み「石井唯」
「えっすご!」アカリちゃんの声も、さらに高くなり「めちゃ偶然」
「公園とかにある石に、井戸の井?」
「そう!」アカリちゃんが、公園て、と笑い、「てか
「……ないかも」唯も笑い「ちなみにわたし、唯一の唯」
「へぇ可愛い」
「いやいや」首を振る。「アカリちゃんは?」
「街灯の灯に、草冠に便利の利の、あれ」
「……
「そ!」灯莉ちゃんが両手をぱちんと鳴らす。
「え、可愛い」
「そう?」
「いいなぁ」
「え~唯もでしょ」
「灯莉ちゃんにぴったりの名前って感じする」
「いやいやそんな」灯莉ちゃんが照れる。「てか灯莉でいいよ」
「あ、じゃあ、」声にする手前で緊張し、重い舌を動かし「灯莉」
「唯」灯莉が唯を見つめ、呼び返す。「よろしくね、唯」だから、目が、大きいって。
「……よろしく」
「って言っても、なに始まるのかよく分かんないけど」灯莉が小首をかしげ、体操着の刺繡部分を指で摘まみ「なんかいつの間に着替えさせられてるし」
「5番」唯は灯莉の数字を指差し「強そう」
「なにそれ」灯莉が笑い「唯のが強そうじゃん。数字大きいし」
「いや、一桁のが、なんか強そう」
「どういうこと?」けらけら笑ってから、ふと真顔になり「あ、携帯」不安そうに「どこ行った」
「あ」たしかに。ポケットを探る。無い。灯莉も体操着のあちこちをぽんぽんと触るが、何も出てこない。「ないね」
イシイ、という単語を、耳が拾う。振り返る。何組かの大人が、立ちながら、座りながら、話している。たしかに今、イシイと聞こえた。後ろから。たぶん男の人の声で。誰だろう。二メートルくらい先で話す、おじさん二人組に目を向ける。この人たち? 唯と灯莉を意識している雰囲気はない。
「どうしたの?」灯莉が不思議そうに尋ねる。
「いや、今なんか、イシイって聞こえた気がして」
「そうなの?」さっき唯が見ていたほうを、灯莉も見る。「あたしたちの会話、聞こえてたのかな」
「分かんないけど」
灯莉の目線が、すうっと下がる。唯も追う。赤い線の外側に、小学生くらいの男の子が、
反応がない。
「ねぇねぇ、お話しようよ~」灯莉が声を掛け続けるが「名前は? あたし灯莉。君は?」まるで石に話しかけているみたいに「ねぇねぇ」いっさい反応がない。
生きてる? と唯は男の子を観察する。
「ダメだ」灯莉が線の内側に戻ってくる。「
「だね」唯は
〈大変お待たせしました〉
声が響いた。
低く、太く、硬い、機械みたいな声。
〈これより、第一ゲームのルールを説明いたします〉
息を
部屋中のさざめきが、一瞬消える。
〈第一ゲームは、ドッジボールです〉
誰の声? 聴覚を研ぎ澄ます。上下左右。どこから聞こえる? 分からない。部屋全体から、声が鳴り響いている気がする。
……ドッジボール?
〈皆さまには、六十分間、ボールを
灯莉の顔が固まっている。
場に騒がしさが戻りつつある。
〈コートは床に引かれた赤いラインの内側です。ラインに靴先が掛かるのはセーフですが、少しでも踏み越えた瞬間にアウトとなります。ボールは四方の壁に埋め込まれた機械より発射されます〉
ごごごご、と、機械音が鳴る。唯は壁を見上げる。たぶん二メートルくらいの高さに、首振り型のバレーボールマシンのようなものが出現する。各壁に一台で、計四台。
〈ノーバウンドのボールが
唯は説明を聞きながら、ドッジボールで遊んでいた頃を思い出そうとする。当時はどんなルールだったっけ。得意だったっけ。苦手だったっけ。記憶に
〈首輪より上にボールが当たった場合は、顔面セーフとなります。また、キャッチしたボールの使い道は自由です。壁際の溝に捨てていただいても、手にしたままでも構いません〉
唯は壁沿いに目を
ドアノブも引き手もない、壁と同じ色の扉に気付く。正面の壁に、ひとつだけ。別の部屋へと
〈残り時間は壁に表示されます〉
正面の壁に、黒い画面が投影される。思い思いの方角を向いていた人たちが、周りに
60:00.00
黒い画面の上端に、緑色のデジタル数字が浮かび上がる。六十分。
〈三つのゲームを実施し、最終的に勝ち残った一名のみが生還となります。参加者はこちらの方々です〉
001 石井 愛 002 石井 藍実 003 石井 葵
004 石井 茜 005 石井 灯莉 006 石井 亜希子
007 石井 暁斗 008 石井 秋成 009 石井 晃仁
010 石井 昭道 011 石井 彰由 012 石井 章
013 石井 朝子 014 石井 あさひ 015 石井 明日香
016 石井 梓 017 石井 篤子 018 石井 厚士
019 石井 絢 020 石井 綾香 021 石井 礼輝
022 石井 彩音 023 石井 歩 024 石井 新
025 石井 幾恵 026 石井 郁夫 027 石井 育裕
028 石井 勇 029 石井 泉 030 石井 到
031 石井 一郎 032 石井 壱平 033 石井 瑛作
034 石井 叡二 035 石井 栄介 036 石井 悦男
037 石井 恵美 038 石井 江里佳 039 石井 応輔
040 石井 織人 041 石井 開 042 石井 凱
043 石井 海渡 044 石井 楓 045 石井 香李
046 石井 薫 047 石井 岳 048 石井 和明
049 石井 一尊 050 石井 主彦 051 石井 数馬
052 石井 和由 053 石井 勝彦 054 石井 克弥
055 石井 佳苗 056 石井 彼方 057 石井 要
058 石井 鑑三 059 石井 貫太 060 石井 絹江
061 石井 公彦 062 石井 鏡子 063 石井 恭治
064 石井 匡四郎 065 石井 京平 066 石井 潔
067 石井 清人 068 石井 究 069 石井 邦博
070 石井 胡桃 071 石井 慧 072 石井 憩子
073 石井 圭司 074 石井 佳祐 075 石井 慶三
076 石井 憲 077 石井 玄 078 石井 研一
079 石井 元気 080 石井 健司 081 石井 謙介
082 石井 顕造 083 石井 剣太郎 084 石井 紘一
085 石井 耕一郎 086 石井 興起 087 石井 浩司
088 石井 幸助 089 石井 巧太 090 石井 昴大
091 石井 晃矢 092 石井 琴絵 093 石井 権蔵
094 石井 咲 095 石井 さくら 096 石井 貞夫
097 石井 佐知子 098 石井 皐月 099 石井 聡
100 石井 覚 101 石井 沙也加 102 石井 小百合
103 石井 汐里 104 石井 茂雄 105 石井 滋人
106 石井 静香 107 石井 志帆 108 石井 柊
109 石井 修三 110 石井 首里 111 石井 瞬
112 石井 順 113 石井 潤一郎 114 石井 俊斗
115 石井 隼之介 116 石井 峻平 117 石井 淳也
118 石井 将 119 石井 翔希 120 石井 省吾
121 石井 祥太 122 石井 晋 123 石井 迅
124 石井 慎一 125 石井 紳介 126 石井 信太郎
127 石井 伸也 128 石井 傑 129 石井 進
130 石井 澄人 131 石井 誠太 132 石井 勢也
133 石井 惣五 134 石井 壮太 135 石井 宗太郎
136 石井 創平 137 石井 颯真 138 石井 泰河
139 石井 乃司 140 石井 汰一 141 石井 大地
142 石井 太陽 143 石井 孝男 144 石井 隆樹
145 石井 鷹志 146 石井 崇人 147 石井 貴洋
148 石井 卓磨 149 石井 拓海 150 石井 琢也
151 石井 健男 152 石井 毅 153 石井 武則
154 石井 赳治 155 石井 丈政 156 石井 猛
157 石井 佑 158 石井 忠重 159 石井 竜巳
160 石井 達哉 161 石井 珠江 162 石井 環
163 石井 保 164 石井 暖人 165 石井 ちあき
166 石井 知紗 167 石井 チヅ 168 石井 千奈都
169 石井 茅春 170 石井 智尋 171 石井 司
172 石井 務 173 石井 恒治 174 石井 翼
175 石井 剛 176 石井 鉄兵 177 石井 哲也
178 石井 照男 179 石井 東史 180 石井 塔也
181 石井 徹 182 石井 俊夫 183 石井 利秀
184 石井 年浩 185 石井 巴昭 186 石井 友一
187 石井 朋輝 188 石井 伴光 189 石井 巨
190 石井 尚貴 191 石井 猶稔 192 石井 直哉
193 石井 夏実 194 石井 菜那 195 石井 七絵
196 石井 菜美恵 197 石井 望 198 石井 和香
199 石井 暢男 200 石井 延泰 201 石井 展吉
202 石井 昇 203 石井 紀一 204 石井 典子
205 石井 教之 206 石井 元 207 石井 華
208 石井 駿夫 209 石井 遥 210 石井 晴喜
211 石井 ひかり 212 石井 寿史 213 石井 久徳
214 石井 ひさ代 215 石井 偉和 216 石井 暎隆
217 石井 秀嗣 218 石井 英永 219 石井 日出紀
220 石井 等 221 石井 仁美 222 石井 雛子
223 石井 日向 224 石井 響 225 石井 比呂
226 石井 広明 227 石井 洋樹 228 石井 裕子
229 石井 弘人 230 石井 博範 231 石井 大夢
232 石井 尋行 233 石井 深 234 石井 房枝
235 石井 芙美 236 石井 冬海 237 石井 穂高
238 石井 帆乃 239 石井 茉衣 240 石井 舞花
241 石井 真緒 242 石井 摩季 243 石井 誠
244 石井 昌樹 245 石井 征司 246 石井 将次
247 石井 賢直 248 石井 政憲 249 石井 正文
250 石井 晶也 251 石井 円香 252 石井 眞菜
253 石井 まひろ 254 石井 守 255 石井 万柚
256 石井 眉美 257 石井 鞠花 258 石井 麻莉奈
259 石井 幹雄 260 石井 美咲 261 石井 水里
262 石井 瑞鈴 263 石井 みずほ 264 石井 巌勝
265 石井 充寛 266 石井 路代 267 石井 光孝
268 石井 允彦 269 石井 満 270 石井 宮土理
271 石井 未波 272 石井 稔 273 石井 雅
274 石井 実侑 275 石井 美優紀 276 石井 麦
277 石井 芽依 278 石井 巡 279 石井 萌
280 石井 基 281 石井 桃子 282 石井 弥栄子
283 石井 安邦 284 石井 靖 285 石井 泰弘
286 石井 唯 287 石井 有一 288 石井 優一朗
289 石井 侑喜 290 石井 佑悟 291 石井 宥士
292 石井 融太 293 石井 遊飛 294 石井 結香
295 石井 ゆかり 296 石井 雪絵 297 石井 諭季子
298 石井 幸典 299 石井 譲 300 石井 由多可
301 石井 弓歌 302 石井 夢乃 303 石井 友梨
304 石井 杳子 305 石井 義男 306 石井 世志貴
307 石井 淑子 308 石井 能周 309 石井 良直
310 石井 嘉法 311 石井 芳久 312 石井 好峰
313 石井 敏之 314 石井 莉英 315 石井 梨央
316 石井 理樹 317 石井 力也 318 石井 陸
319 石井 律子 320 石井 李名 321 石井 龍太郎
322 石井 亮 323 石井 良太 324 石井 涼平
325 石井 臨斗 326 石井 留美 327 石井 瑠璃
328 石井 礼子 329 石井 怜奈 330 石井 麗央
331 石井 蓮之介 332 石井 若菜 333 石井 航
残り時間の下に、番号と名前が一斉に表示された。
唯は緑色の文字を食い入るように見つめる。
石井、石井、石井、石井、石井──。
全員、石井。
石井が三百三十三人。
刺繡の通り、「286」が唯。「005」には、たしかに灯莉の名前が表示されている。おそらく五十音順。さっきの少年は「018」だから
〈ではこれより三十秒後にゲーム開始となります。現在、赤い枠の外側にいる方は、内側へご移動ください〉
唯は足元を見る。一応内側だけど、
「おい!」目の前で怒号が響く。「勝手に始めるな! どういうつもりなんだ!」六十歳くらいの男の人が、
そうだ! 説明しろ! と怒号が重なる。
応答はない。
「あ、やば」隣で灯莉が呟く。「あの子、まだ外いる」
視線の先を追う。18番の厚士くんが、放送が流れる前と変わらない格好で、じっと縮こまっている。
もう大半の人が、線の内側へ移動している。厚士くんだけが外にいる。
「ねぇ始まるよ! こっち来て!」線の内側から、灯莉が呼ぶ。
動かない。膝でこめかみを挟むようにして、自分の靴だけを見つめている。
「耳」唯は
「え」
「時間ない」駆け出す。線を越える。厚士くんの肩を揺する。「ねぇ立って。こっち」目が合う。
ビイイイイイイイイイイイイとブザーが鳴る。
〈ゲーム開始です〉
空気を切る音。
ボールが肌にぶつかる乾いた音が、少し遠くから聞こえる。
ボールは床を跳ね、まだ立ち上がれない唯の近くまで転がる。
水色のボールが、赤い線を越え、壁際の溝に消える。
〈65番石井
「えっ」若い男の人がうろたえる。「え、」
小さい爆発音。
顔が宙を舞う。
顔だけが。
血しぶきが飛び、周囲を赤く濡らす。
首から下が、ゆっくりと倒れ、鈍い音を立てる。
生ぐさいにおいが漂う。
悲鳴が上がる。
空気を切る音が、今度は別の壁から聞こえる。
【伏見】
「なんか面白いことねぇかなぁ」
「ないっすよ」蜂須賀がスマホで文字を打ちながら、すげなく返す。「てか今ってバイト代出てる認識でいいんすよね?」
「出てねぇよ」伏見もすげなく返す。「お前いま仕事してねぇだろ」
「いや、」スマホに当てた親指をぬるぬる動かしたまま「こうやって事務所来てる時点で、この時間は拘束されてるわけだから、バイト代出すべきじゃないすか?」
「なんでだよ。もともとお前休みだったのに、『暇なんで来ていいすか?』とか言いだしたから、いさせてやってるだけだろ。別に拘束してねぇよ」
「や、もともと今日シフト入ってたのを、『いま案件少ないから休みで』って急にバラシにしてきたのは伏見さんじゃないすか。こっちはこっちでカツカツなんで、バイト代欲しいんすよ」
「だから『来ていいけど仕事ねぇよ』って、ちゃんと言っただろうが」
「えー。ひどい」表情は変えず、スマホをいじったまま棒読みで「ケチくないすか?」
「ケチじゃねぇよ。こっちだってカツカツなんだよ」
「というか、」何かを打ち終えた蜂須賀が上半身を起こし、伏見を向く。「『がぁーって来てばぁーん』てなんすか。作家にあるまじき
「そっちはもう廃業したっつってんだろ」資料を上書き保存し、蜂須賀と目を合わせる。報告期限は来週だから、別に急ぎの仕事じゃない。「今はただの探偵だよ」冷めたコーヒーを
「かっこいいすね」伏見の口調を
「
「してないっすよ」
伏見が探偵事務所を開業したのは六年前、三十六歳のときだ。蜂須賀と知り合ったのは十二年前、三十歳のとき。そのころ伏見は小説家を目指し、バイトをしながら新人賞への投稿を繰り返す生活をしていた。蜂須賀は高校一年生で、小説を書きはじめたばかりだった。二人は小説投稿サイトで、お互いの小説の感想を送り合っていた。なんとなく波長が合い、家も近いと判明したことから、オフラインでも頻繁に会うようになった。その二年後、三十二歳の年に、伏見が文芸誌の新人賞を
伏見は立ち上がり、凝った肩と腰をほぐす。「なんか書いてた?」
「はい?」蜂須賀が訊き返す。
「それ」蜂須賀のスマホを指差し「さっきからずっと、なんか文字打ってたじゃん」
「あー」蜂須賀が画面に目を落とし「ネタっす」
「どんな?」
「なんかよく、ドラマとかで、『お前は俺の本当の息子じゃないんだ』って告白するシーンあるじゃないすか」
「あぁ」
「その告白を、もんじゃ、ホットプレートで焼きながらする、って設定のコントっす」
「……それ面白いか?」
「面白くないすか? なんでそんなバタバタしながら、っていう。あ
出会った当時は十六歳だった蜂須賀も、今や二十八歳だ。もうアラサーだってのに、十二年前から変わらぬ態度で接してくる。高校生だった蜂須賀は大学生になり、社会人になり、無職になり、養成所に通い、大手事務所に所属する芸人となり、事務所を辞め、今はフリーのピン芸人をしている。小説はもう書いていないらしい。芸人としての活動は地下ライブへの出演がほとんどで、それだけでは到底食っていけないため、しつこくお願いされ、伏見の事務所で雇うことになった。が、よくよく話を聞くと、生活費は
「……なんでもんじゃ?」
「や、朝食バイキングとか、
「あー」
「ちゃんと考えてます?」
「まぁ」生返事をする。「なんか派手な仕事来ねぇかな」
「だからないっすよ」蜂須賀が再び、ソファに全身を預ける。「派手ってどんなんすか」
「なんか、殺人事件とか」伏見はストレッチを終え、作業チェアに戻る。
「警察の仕事っすよ」蜂須賀が冷たく返す。「あとフツーに不謹慎すよ。人死んではしゃぐの」
「いやさ、身辺調査ばっか六年もやってると、さすがに飽きるんだよな」
「いいんすよ」蜂須賀も大きな欠伸をし「平和が一番す」
「浮気とか不倫とか、正直どうだっていいんだよな」
「それ探偵事務所やってる人が絶対言っちゃダメすよ」
カランコロンカラン、とドアベルが鳴る。
蜂須賀が慌てて立ち上がる。伏見も姿勢を正す。
ドアの隙間から、見覚えのある顔が覗く。「お、いる」やたら毛量の多い
「
「頼みたいことがあるんだが、」さっきまで蜂須賀が寝転んでいたソファに目を遣り「座っていいか?」
「あぁ」と伏見が返すより先に、鶴田はソファに腰を沈めている。
伏見も反対側のソファに座り、テーブルを挟んで向かい合う。「知ってたのか? ここ」
「
「……あぁ」四年ほど前、小澤から妹の結婚相手の身辺調査を頼まれたことがあった。
「え、え、あれすか?」蜂須賀が落ち着きなく、伏見と鶴田を見て「お二人は、あれすか? お知り合いすか?」
「高校の同級生だ」鶴田が答える。
ちなみに小澤も同級生で、と伏見は補足しようか迷うが、別にいいかとやめる。
「あ、そうなんすね、伏見さんの。なるほどなるほど」蜂須賀は
「いい」鶴田が骨ばった手を蜂須賀へ向け、提供を断ってから「人を捜してほしい」早速本題に入りはじめる。
「人? どんな?」助走が一切ないところが、高校時代からまるで変わってないな、と伏見は思う。十年ぶりなんだから、相談の前に近況を言い合うくらいしてもいいだろう。鶴田の仕切った文化祭の出し物決めが、当時の担任
「この男なんだが」鶴田がスマホの画面を向ける。おそらく同年代の、地味な顔をした男が、そこに写っている。写真というよりは、映像の切り抜きに見える。照明と背景の雰囲気からして、舞台か?
「まだ演劇やってんの?」
「やってる」鶴田が
気まずそうに突っ立つ蜂須賀が、視界の端で気になる。「一緒聞くか?」ソファの座面をぽんと叩く。
「あ、いいんすか」蜂須賀の顔がぱっと明るくなる。
「いいよ」伏見が答えると、蜂須賀は隣に
「手持ちの情報量に
鶴田は画像を表示させたまま、テーブルの上にスマホを置く。
声は低く
見つけたい人物の名は、石井
その
二日前、2024年3月25日、月曜日の出来事だった。
開演数分前になっても石井有一と連絡が取れず、鶴田は
鶴田は烈火のごとく怒った。石井有一に俳優失格の
解散後、酒も抜け冷静となった鶴田の怒りは、心配へと形を変えた。
これまで石井有一を何度も舞台へ上げてきたが、こんなことは一度もなかった。
怠惰や不注意が原因で、千秋楽だけ舞台をすっぽかすなんてことが、果たしてありえるだろうか。
一夜明け、鶴田は何度も石井有一へ電話を掛けたが、繫がらなかった。
何か、事件や事故に巻き込まれたのではないか。
石井有一は途方もない才能を秘めた俳優だった。
演技の
さらに一夜明けても、音信不通は続いた。鶴田はいてもたってもいられず、警察を訪れた。
石井有一を捜して欲しいと訴えるも、事件性が明らかではない成人の失踪は、捜索願を受理するのみで、積極的な捜索を行うことは出来ないとの回答だった。
舞台をすっぽかすなんてありえない、事件に巻き込まれているに違いない、と主張しても、警官の態度は冷たかった。「ちっちゃい劇場でやる演劇でしょ? 気が変わってばっくれただけじゃないの?」と、多忙をこれ見よがしにアピールしながら、面倒そうに繰り返すばかりだった。
「だからお前を頼った」鶴田は視線を上げ、言った。「石井有一は、俺の舞台に必要な俳優だ。どんな手段を使ってでも、見つけ出してくれないか」
鶴田の
「……なるほど。分かった」欲しい情報はまだまだあるが、ひとまず伏見は鶴田の目を見返し、同じように真剣な表情を作った。「そういうことなら、ぜひ協力したい」
「本当か」鶴田の声が大きくなる。「捜し出せそうか?」
「失踪から二日しか
「恩に着る」鶴田が頭を下げる。
「だがその前に、」伏見は一呼吸置き「まぁ古い付き合いだし、ボランティアでやってやりたいのは山々だが、こっちにも生活がある。多少まけてやってもいいが、大体」
「報酬は支払う」鶴田が伏見の言葉を
「そうか。よかった。調査期間にも依るんだが、」
茶封筒が差し出される。
「手付金だ」戸惑う伏見の手に、封筒を握らせ「見つかれば、この倍を追加で払う」
伏見は受け取り、中を覗く。
「うわっ」頭を寄せ、封筒を覗いてきた蜂須賀が、驚きの声を上げる。「まじすか」
伏見は封筒に指を入れ、軽く数える。ひとまず提示しようとしていた額の、軽く三倍は入っている。「鶴田、こんなには、」
「必ず見つけてほしい」伏見を抑えつけるように語調を強め、さらに深く、鶴田は頭を下げる。「大事な俳優なんだ」
鶴田の後頭部を見下ろす。ごわごわと茂った癖毛は相変わらずだが、頭頂部だけが、少し薄くなっているような気もする。というより、鶴田の後頭部を、こんなにまじまじと見たことがあっただろうか。鶴田に頭を下げられたことが、高校時代を含め、かつてあっただろうか。
「頭上げてくれ」伏見は言う。
ゆっくりと上体を起こす、鶴田と目が合う。
「
「やってくれるのか」
「あぁ」伏見は隣を見て「すまん蜂須賀、やっぱりお茶、
「え、」蜂須賀がきょとんとし「いいすけど」
「とにかく情報が欲しい。焦ってはいるだろうが、一度落ち着いて、冷静になって、覚えていることを全て話してくれ」伏見は鶴田を見据える。「石井有一の全てを、俺に教えてくれ」
【唯】
〈282番石井
爆発音が、続けて鳴る。
誰かが
顔が二つ舞い、血が飛び散る。
悲鳴と怒号が渦巻き、白い床が赤く塗られていく。
〈167番石井チヅさん、アウトです〉
ぶつかったボールが跳ね上がり、
唯は
「ふざけるな! 首輪を
唯の左腕に、くさくてぬるい、血が掛かる。
〈151番石井健男さん、アウトです〉
今ボール当たった?
当たってなくない?
〈大変申し訳ございません。お伝えしそびれていましたが、ゲーム中に首輪を外そうとすると、爆発します。皆さま、お気をつけください〉
注意が流れる間にもボールが飛び、人の首が舞う。
淡々とした、アウトです、がまた響く。
唯の右後ろで、爆発音がする。
首の取れた死体が、赤いラインの向こうで倒れている。
〈302番石井
地獄絵図だった。
パニックを起こした人たちが、それでも首輪を外そうとして、線を越え逃げようとして、爆発した。
ボールが当たると、首が飛んだ。
訳が分からなかった。
目の前で起こっていることを、現実と思えなかった。
壁を見上げる。
58:53.22
まだ一分しか経っていない。三百三十三人がずらりと表示されていた名簿が、ところどころ欠けている。
死ぬと、名前が消えるんだ、と唯は思う。
命が消え、名前も消える。ざっと見る限り、もう三十人近くが消えている。
ボールが発射されるタイミング以外でも、アウトの宣告が相次ぎ、名前が消えていく。首輪を外そうとする人、逃げようとする人が、後を絶たない。
「唯! 唯! 唯っ!」隣で誰かが、わたしの名前を叫ぶ。「唯、どうしよう、みんな死んじゃう、どうしよう、」震えた声を絞り出すのは「どうしよう、」そうだ、灯莉。
「どうしよう」頭が回らず、同じ
灯莉の後ろに、厚士くんがいる。倒れ込んだ姿勢のまま、そこにいる。
右側の壁から、ボールが出てくる。
あっ、と、その軌道を目で追い、唯は声を上げる。
あ。
厚士くんの肩に、ボールが当たる。べちっと低い音を立て、ほとんど跳ねず、ボールは床を転がる。
厚士くんが、肩に目を向ける。表情は変わらない。
〈18番、石井厚士さん、アウトです〉
ぼん、と鳴って、厚士くんの首が舞う。
灯莉が頭から血を浴びる。唯の足首にも、血が飛び散る。
赤く濡れた箇所が、温度とぬめりを感じる。厚士くんの、温度と、ぬめり。濡れた皮膚が感覚の全部になるみたいに、視覚や聴覚が遠のいていく。
ぼやける視界で、灯莉と目が合う。口をだらしなく
死んでしまった。
厚士くんが、死んでしまった。
名簿を見る。
「017 石井 篤子」と「019 石井 絢」の間に、ぽっかりと黒いスペースが空いている。
死にたいな、と唯は思う。今すぐに、死んでしまいたい。
ボールがわたしに、飛んでこないだろうか。いや。そんな必要ない。赤い線を、踏み越えればいい。それか、首輪を外せばいい。そうすれば、わたしは終われる。
腕が、ゆっくりと上がっていく。首へ。自分の意志とは関係ないみたいに。左腕のくさくてぬるい血を、体操着のお
正面の壁から、ボールが飛び出す。軌道を追う。あそこのお兄さんに、当たる──。
ばしっ、と力強い音が響く。ボールは大きな両手に挟まれ、動きを止めている。
「おい! みんな! 聞いてくれ!」ボールを赤線の向こうに投げ捨て、くるりと周囲を見回し、
「みんなでは無理じゃない?」すらっとしたお姉さんが、お兄さんに反論する。「『三つのゲームを実施し、最終的に勝ち残った一名のみが生還』って言ってたでしょ。仮にドッジボールで生き残っても、ひとり以外全員死ぬんじゃない?」
「そうとも限らない」お兄さんが投影された画面を指差し「主催者がどこの誰か知らないが、ゲームが進んでいけば、きっと対話する機会はある。みんなが生還できる道もあるかもしれない。まずは生き残ろう。出来るだけ多く、このゲームを勝ち抜こう」
〈87番石井
向こうの
誰かに当たったボールが跳ね、連鎖したんだろう。
「みんな落ち着け!」さっきのお兄さんが、また周囲に呼び掛ける。「大丈夫だ!」プロレスラーみたいな、がっしりした体格。「出来るだけ、視野を広く持とう。発射口は四つある。全てを視界に収めるのは難し」「がたがたうるせぇなさっきから」怖い顔をした男の人が、お兄さんに詰め寄る。「お前はなんなんだ? 勝手に仕切りやがって」胸倉を摑んで揺すり上げ「お前はあいつらの仲間か? 俺らを監禁して、こんないかれた遊びやらせてんのはお前か?」
〈311番、石井
また誰か死んだ。
「違う!」襟ぐりに伸びた手を、太い腕でぐっと摑む。「俺も被害者だ。生き残ろうと、必死なだけだ」
「はっ」怖い男の人が、殴りつけるように手を放し「どうだか」お兄さんの元を離れる。
〈210番、石井
やりとりを見ていた一人にボールが当たり、首が飛ぶ。
「……っ!」お兄さんが悔しそうな
空気が変わった。恐怖が
唯の腕は首輪まで届くことなく、気づけば垂れ下がっていた。
「生きなきゃ」灯莉が口にする。血を浴びた
「うん」唯は頷き返す。「こんなのに殺されるなんて、嫌だし」
数歩、後ろへ下がる。ここなら、前、左、右の三つの発射口が視界に入る。背後のひとつは、たまに振り返って確認すればいい。
ボールが放たれる。「うわっ」小学校高学年くらいの男の子が、ジャンプで避ける。「危ね」
淡々と、ボールが放たれていく。アウトになってしまう人も多いけど、避けたりキャッチしたりする人も増えてくる。
唯は間隔を数える。五秒。残り時間を見る。あと四十九分。
制限時間は六十分だから、秒に直すと、三千六百秒。五で割ると七百二十球。全滅もあり得る。ひとり二、三球避ければ生き残れる計算だけど、一球で連鎖アウトになったり、ボールとは関係なく死んだ人も多いから、実際はもっと厳しい。
発射口を気にしつつ、名簿をざっと確認する。既に三分の一くらいが消えている。十分経ったから、だいたい百二十球ちょいを消化。最初の一分で三十人ほどが一気に消えたことを考えると、アウトになるペースが落ち着いてきている。
ボールの行方を観察する。冷静でさえあれば、アウトを防ぐことはそこまで難しくないように思える。ボールのスピードだって、それほど速いわけじゃない。
ボールの出る機械の上に、レンズのようなものが見える。カメラだろうか。見上げ、目を凝らすと、天井の
誰かが見ている。
これを見て、楽しんでいる誰かがいる。
〈75番石井
張り詰めた空間に、アナウンスと爆発音が響く。
白い床に、たくさんの死体が転がっている。
血の匂いに慣れてしまったのか、もうあまり、くさいと感じられない。
〈残り四十五分となりました。ここまで生き残った皆さま、大変お疲れさまでございました。引き続き、ご健闘をお祈りします〉
うるさいな。
〈現在は『ドッジボール』と呼ばれるこの球技ですが、日本に伝来した当初は『デッドボール』と呼ばれていたそうです。その後、コートが円形から方形へ変わったり、キャッチすればアウトとはならないルールが追加されたりした上で、『ドッジボール』と呼称を変え、日本中に広まっていったそうです。すなわち、当たれば即死のこのゲームは、まさに『デッドボール』であり『ドッジボール』と言え──211番石井ひかりさん、アウトです〉
本当にうるさい。殺してやりたい。勝ち残って、これを考えたやつの顔に蹴りを──
来る。
正面の壁から、唯にボールが飛ぶ。
水色のボールが、縦に回転して迫ってくる。
音が消え、視界が低速になる。
ソーダ味の
摑みやすいようにか、合皮っぽい素材の表面が
このままだと、唯の右肩に当たる。
一歩左へ。
ボールが唯と灯莉の間を通り過ぎる。
「怖っ」灯莉が呟く。「え! 怖! 怖すぎる!」声が高くなっていき「やばくない? 今死ぬとこだったよね?」
「うん」唯は発射口に目を向けたまま「危なかった」
「やばすぎ。足震える」
灯莉の動揺とは裏腹に、唯は安心していた。
見えていれば、避けられる。
唯はこっそりと、左手首の傷痕を撫でる。ざらざらする。生きている。大丈夫。
「うおうっ」さっき避けるのに成功していた男の子が、とっさにしゃがみ、頭上をボールが通過する。「よっしゃっ。セーフ」自分を鼓舞するように、両手に
五秒ずつの空き時間で、胸元の番号と名前を、照らし合わせる余裕が生まれる。
この、やたらすばしっこい男の子は、137番、石井
さっきみんなに呼び掛けていたお兄さんは、42番、石井
お兄さんに反論していた、すらっとしたお姉さんは、329番、石井
お兄さんの胸倉を摑んでいた怖い人は、264番、石井
「018 石井 厚士」と書いてあったはずの空白を、もう一度見つめる。
名前はもう消えてしまったけど、大丈夫。わたしが覚えてる。
予想外のタイミングで、ボールが誰かにぶつかる。
えっ。
少し先で、二十歳くらいのお兄さんが呆然としている。
ボールは発射されていなかった、はず。
発射口から通常間隔のボールが飛び出し、誰かがそれを避ける。
アナウンスは聞こえない。さっきたしかに、お兄さんに当たったのに。
「ドッキリでした~」
「は?」当てられた側のお兄さんがキレる。詰め寄り「お前ふざけんなよまじで」
「すんません!」男の子が肩をすぼめ「でもなんか、空気悪かったんで、和ませようと思って!」
「てめぇ殺すぞ」お兄さんが男の子に摑みかかり「ふざけんのも大概にしろや」
「静かにしないか」断ち切るような、大人の声がする。五十歳くらいのおじさんが、
お兄さんと男の子が黙る。
「発射口を、四台同時に見るのは難しい。だから、音を聞くしかないんだ」おじさんの、低く豊かな声が響く。「協力してくれ」
お兄さんは怒る気力を
男の子は電池を抜かれたみたいに固まっていたが、次第に表情が緩み、また口元に笑みを浮かべる。
お兄さんは64番石井
孝男さんの呼び掛けが響いたのか、静寂が辺りを満たす。
唯と灯莉も無言で、耳を澄ます。
たしかに、ボールが発射されるコンマ数秒前に、ガガッ、と微かな機械音が鳴っている。
これを聞き取れれば、背後からボールが飛んでくる前に、振り返って対処することが可能かもしれない。
〈180番、石井
ボールをキャッチしそびれた、誰かの首が飛ぶ。
油断は出来ない。
たとえば灯莉と背中合わせになって、発射口を二つずつ、常に視界に収めたら、と考える。ボールが飛んできたら、その方向をすぐ、相手に伝える。いや怖い。焦ってうまく伝えられず、灯莉にボールが当たってしまったら、取り返しがつかない。それに、わたしは灯莉を信じられるけど、灯莉がわたしを信じてくれる保証はない。耳を頼りに、自分に飛んできたボールだけを、確実に対処したほうがいい。
時計を見上げる。あと約三十五分。まだ半分も経っていない事実に、唯は心が折れそうになる。
灯莉が伏せ、ボールを躱す。立ち上がり、唯と目を合わせ、「危なかった」と細い声で言う。序盤に比べ、明らかに疲れ切っている。
「すごい」唯も小声で返す。「よく躱せたね」あと三十分以上、お互い気力が
みんな言葉少なに、ボールが発射される瞬間に意識を集中させている。
処理に失敗し、爆発する人が出ると、唯の内臓はきゅっと縮まる。
あんなに死にたかったのに、こんなにも今、死ぬのが怖い。
〈残り三十分となりました〉平淡なアナウンスが聞こえる。〈ついに半分が経過しましたね。引き続き、ご健闘をお祈りします〉
あと半分。灯莉を見る。表情は硬い。
もう半分、ではなく、まだ半分。
名簿を見ると、半数以上の石井さんが、すでに消えている。死体も増え、足の踏み場が減ってきた。
小学校低学年くらいの女の子に、ボールが飛ぶ。避けようとしたその子が、死体に足を引っかけ、転ぶ。あ、まずい。女の子の背中で、ボールが跳ね上がる。目で追う。床へ着く前に、視界の外から凱さんが滑り込む。あっ。ギリギリのタイミングで、ボールが凱さんの手に収まる。
「間に合った」凱さんがふぅと息を
女の子が泣きそうになりながら、凱さんの手を取って立ち上がる。安心したのか、声を上げて泣きはじめる。体操着や腕に、血がべっとりと付いている。女の子が手で涙を拭おうとするのを、凱さんが優しく制する。「血が目に入るとよくないから」
えぐっ、えぐっ、と泣き続けるその子の頭を、凱さんが撫でる。「俺のそばにいたほうがいい」
かっこよすぎないか、と唯は思う。なんだあの人。顔もかっこいいし。マッチョだし。あんなヒーローみたいな人いるんだ。
泣きじゃくる女の子の数字が見える。001。石井
遠くの隅を、怜奈さんが陣取っているのが見える。いかにも才色兼備そうな、切れ長の目を光らせ、ボールを警戒している。
そうか、あそこまで下がれば、発射口を四台とも視界に入れられるのか、と唯は思う。
でも、ちょっとでも線を越えたら即死なわけだし、あそこに立つ勇気はないな、と考えていると、別の隅へ男性が駆けていくのが目に映る。角で立ち止まり、振り返ろうとした男性の、首が飛ぶ。
〈33番、石井
「血で、線が見づらくなってる」灯莉がぼそっと口にする。「怖いな」
「でも、下手に動こうとしなければ」
「うん、あんま動かないほうがいいね」灯莉は消え入りそうな声で返してから「あんま動かないほうがいいね!」声を張り上げ、同じ台詞を繰り返す。
「なんで二回言ったの?」唯は少し笑う。
「気合い、入れようと思って!」灯莉の声に、つやが戻りはじめる。「がんばろう! あと二十五分!」
「うん」唯は笑みを返す。「がんばろう」
集中して、ボールの行方を追い続ける。
唯のもとへ二度、灯莉のもとへ三度、ボールが飛んでくる。全て躱す。
あと十五分。
凱さんに突っかかっていた巌勝さんが、隅のポジションを奪うため、人を
最悪、と唯は思う。あれには近寄りたくないな、絶対。
生きている人が、かなり減ってきた。残り七十人くらいかな。
このゲーム、集中力と反射神経も大事だけど、運も大きい。ここまで生き残れたのは、運が良かったからだ。
ともあれ、あと十分と少し。ボールを躱し続ければ、生き残れる。
〈残り十分となりました〉アナウンスが流れる。
09:58.01
思わぬタイミングで、ボールが風を切る。
「は」
〈64番石井匡四郎さん、アウトです〉
匡四郎さんの首が飛ぶ。
それを見ている間に、またボールが風を切る。
〈319番、石井
なんで。秒数を見る。五秒経ってない。二秒経つごとに、ボールが飛んでくる。
〈お伝えしそびれていましたが、残り十分を切りましたので、ラストスパートです。皆さまのご健闘を、心よりお祈り申し上げます〉
ふざけんな。
ボールが飛ぶ。
飛ぶ。
飛ぶ。視覚と聴覚をフル稼働させる。息つく間もない。唯の後頭部に、ボールが当たる。死んだ、と思う。違う。顔面セーフ。ボールが飛んでくる。飛んでくる。あっちからもこっちからも。アウトコールが鳴り
唯の手がボールを弾く。
ボールが高く舞い上がる。
死んだ。
高く高く舞い上がったボールが、
おじさんがボールを抱く。
「あ」
おじさんが声を漏らす。
おじさんと目が合う。
地味なおじさん。
アウトコールは聞こえない。
ボールが飛ぶ。誰かに当たる。
〈113番、石井
わたしの名前は聞こえない。
「ありがとうございます」唯は言う。「ありがとうございます」繰り返す。
「いえ、まぁ、」ボールを抱いたまま「その、」おじさんが目を逸らす。「そんな、」287番。石井有一さん。覚えた。
02:56.88
あと三分。ボールが飛ぶ。ボールが飛ぶ。ボールが飛ぶ。人が死ぬ。ボールが飛ぶ。人が死ぬ。ボールが飛ぶ。躱す。ボールが飛ぶ。人が死ぬ。あと一分。
隣を見る。灯莉がいる。名簿を見る。もうだいぶ減ってる。
ボールが飛ぶ。人が死ぬ。ボールが飛ぶ。人が死ぬ。
00:02.01
あと二秒。最後の一球が、灯莉に飛ぶ。灯莉の腕が、ボールを弾く。横に跳ね上がる。灯莉が、唯が、手を伸ばす。届かない。追いかける。届かない。ボールが床に落ちる。
〈5番、石井灯莉さん、アウトです〉
灯莉の首が飛ぶ。
00:00.00
〈ゲームが終了しました〉
ブザーが鳴り響く。
灯莉から
顔がぬめる。
襟から入った血が、
血が重力を帯び、首を、胸を、腹を伝う。
目を見ひらいた灯莉の顔が、唯の足元に転がる。
〈生き残った皆さま、おめでとうございます。──〉
生きている。
第二章 禁字しりとり
【伏見】
すまん予定が、と事務所を去る鶴田を見送り、伏見はソファに腰を下ろす。
「情報少ないっすねぇ」蜂須賀が嘆き、黒いマーカーのキャップを嵌める。ホワイトボードを離れ、伏見の向かいに座り「せめて最寄り駅くらいは特定したかったんすけど」
蜂須賀が書記を担当したホワイトボードを、伏見は眺める。
最後のコンタクト→3/24(日)ソワレ終演後 21時過ぎ ダメ出しをして解散
前日の様子に不審な点なし 特にきびしいこと言ってない
家にいる可能性? 現住所不明 京王線沿い(たぶん)
バイト→ウーバー配達員
「石井有一」は本名(運転免許ちらっと見た)住所は覚えてない
出演料は手渡し 銀行口座は不明
共演者、過去作の関係者にも当たった→手がかり×
出身地、家族構成→不明
さてどうしたものか、と考える。
ブラインドの隙間から覗く外は、すっかり暗くなっている。
「これフツーにばっくれた可能性高くないすか?」マーカーを指で回しながら、蜂須賀が顔をしかめる。「あの鶴田って人が嫌になって逃げただけじゃないすか」
蜂須賀の端正な字を、伏見は繰り返し、目でなぞる。
「つかあの人大丈夫な人なんすか? なんか怪しくないすかフツーに」
「まぁ」伏見は反射で返してから、じっくり言葉を選び「取っつきづらいやつではある」
「ずっとあんな感じなんすか? 昔から」
「あんな感じだな」伏見は高校の教室を思い出す。「寡黙で、何考えてるかよくわからんが、妙に積極性があって、悪いやつじゃない」
「ん~」蜂須賀が
「そんなキツいダメ出ししたやつが、わざわざ警察行って、探偵事務所来て、高い金払って、人捜そうとするか? 見つけたところで、じゃないか?」
「自覚ないパターンあるじゃないすか。ハラスメントするやつって大抵認知
「でもなぁ」伏見は組んだ両手を後頭部に当て、首の後ろを伸ばし「いくらしんどくても、公演期間中にいきなり音信不通とか、ありえんのかな」
「全然ありえますよ」
「そうか?」
「全然。キツくなったら全然。というか失踪前日の出来事だけじゃなくて、前々から蓄積してた不満がちょっとしたキッカケで爆発して、もう全部嫌になってブッチした、的な」
「でも石井有一、四十五だぞ? 新入社員じゃねぇんだぞ?」
「わかんないすけど、ありえるんじゃないすか。別に世代とか関係なく」
「どうだろう」
「てかあの人の芝居おもろいんすか? 伏見さん
「十年以上前に観たことあるけど、」記憶を掘り返す。たしか下北沢の劇場で、タイトルは思い出せないが、鶴田の雰囲気に似合わず、テンションが高い芝居だった。「可もなく不可もなく、って感じだったな」
「あーなんかそんな気しますよ。てかスベってません? 既に。なんか服装もあれだし、劇団名とか、『愛以外もください』ってタイトルとか、だいぶキツくないすか? てか三十七回公演? え、三十七? 三十七!? なんでそんな続けられるんすか? 実家太いんすか?」
「知らんけど、ファンがけっこういるんじゃないか?」
「いないっすよ」
「決めつけんなよ」
伏見は再び、ホワイトボードを見つめる。「とりあえず、」背もたれから身体を
「しかないすよね現状」蜂須賀もスマホを手に取る。
伏見は鶴田から受け取ったメモを、蜂須賀との間に置く。そこには鶴田が把握している限りの、石井有一が出演した舞台のタイトルが羅列されている。
伏見は蜂須賀と手分けして、インターネットに漂う情報を漁った。いくつかのSNSを探ったが、石井有一自身のアカウントと
検索を重ねる。石井有一と共演経験のある俳優のアカウントが複数見つかったため、手当たり次第にDMを送った。
「鶴田の芝居で共演経験あるやつは全員当たってみたって言ってたし、望み薄な気もするけどな」
「や、分かんないすよ。鶴田から石井有一を
「まぁな」
人捜しの場合、情報は新しければ新しいほど有用なため、出来れば直近の公演『愛以外もください』の関係者と早めに接触したかった。『愛以外もください』は三人芝居で、劇団員の宮本
「……田中ファイナルウェポン?」蜂須賀が呟く。
幸い、二名ともSNSアカウントを有していたため、至急連絡を取りたい旨のメッセージを送ることが出来た。
「田中ファイナルウェポン?」蜂須賀が繰り返す。「え、田中ファイナルウェポン? どういう芸名?」
「うるせぇな。いいだろ別に」伏見はスマホを見たまま返す。「芸名なんだから自由だろ」
蜂須賀はそのアカウントを凝視し「これ三十後半とかじゃないすか? 三十後半でファイナルウェポン? てか思ったより見た目地味じゃないすか? なんか区役所職員みたいじゃないすか? この感じで田中ファイナルウェポンなんすか?」
「そっとしといてやれよ」
「え、どうします? もし将来、伏見さんの娘さんが、伏見ファイナルウェポンとかいう芸名で役者やりはじめたら」
「どうもしねぇよ」
「ちゃんと応援できます? 伏見ファイナルウェポンを」
「するに決まってんだろ」当たり前だ。全ステージ観に行く。「てかお前の芸名のほうがあれだろ」
「どこがすか。『蜂須賀』の何がいけないんすか」
「こう、フルネームでもなく、
「あ、すげぇ悪口。ひでぇ」口を
「あー、そうね、どうしよう」
「しりとりでもします?」
「しねぇよ。暇じゃねぇんだよ」伏見はUSBメモリを手に取り「鶴田から渡された映像、観とくか」
「いいっすね」
伏見はデスクへ向かい、ノートPCを応接用のテーブルへ移動させる。蜂須賀とソファに並ぶ。USBメモリを挿し、中に入っているファイルを確認する。十五秒ほどの動画と、一時間半ほどの動画の二つ。
十五秒ほどの動画は、昨年8月に行われた第三十六回公演『羊の代わりにあなたを数える』の打ち上げで「題名クソダセぇ」「クソダセぇとか言うなよ」劇団員の一人が撮影したものだった。
「石井さ~ん、お疲れさまでした~、飲んでますか~?」という画面外からの女性の問い掛けに、地味な小男が「はい、まぁ」とぎこちない笑みで応じている。「石井さんの演技、今回も最高でした~」と華やぐ声に、「いえいえ、その、そんな」と恐縮し、ほのかに顔を赤らめている。
「なんかあれっすね」蜂須賀がぼそりと「市役所職員、って感じすね」
「お前引き出し少ねぇな」伏見は言う。「役所に頼りすぎだろ」
「区と市でニュアンス違うんで」
「一緒だろ」
「え、てかそんなん言うなら、伏見さん
「廃業してる」伏見は突っぱね、再び動画を再生する。石井有一は黒い無地のTシャツを着ている。「まぁあれだな、容貌がはっきり分かったのはいいが、特に手掛かりっぽいもんは映ってねぇな」バンドやアイドルのTシャツでも着ていれば、そこから
「そっすね~」蜂須賀がマウスに手を伸ばし、また動画を再生する。「あれっすね、……生徒から
「イマイチだな」
「もう次の動画いきましょう」伏見を押し退けるように、マウスを奪い「はい、こっち、再生!」
長いほうの動画は、第三十六回公演『羊の代わりにあなたを数える』の配信映像だった。「どうやったらこんなダサいタイトル思いつくんすか」「しつけぇな」鶴田曰く、『愛以外もください』も映像を撮影済であるが、編集が終わっていないため、舞台上の石井有一の雰囲気はこちらで確認して欲しい、とのこと。「ちなみに今って時給発生してる認識でいいんすか?」「してる」「よっしゃよっしゃ~、よっしゃっしゃ~」「観てる間は黙っててくれ」
『羊の代わりにあなたを数える』は、夢の中で出会った少女に恋をした男が、不眠症に
「どう思った?」再生し終えてから、伏見は蜂須賀に尋ねる。
「アリス的な異世界と現実世界を行き来する構成に既視感が拭えず、台詞も凡庸でくどくどしく、そもそも物語の主題が単に作者の願望を」
「じゃなくて、石井有一の演技。どう思った?」
「悪くないんじゃないすか?」蜂須賀が
「だよな」
「はい」
「憑依系というか」
「そっすね。まさに」
伏見はスマホを操作し、DMを確認する。まだ返事はない。「そっちは?」
「まだっすね」蜂須賀がスマホをいじり「なんも反応ないっす」
「そうか」伏見は腕時計を見る。九時を過ぎている。だいぶ遅くなってしまった。「今日は解散で」
「ういっす」蜂須賀が眠そうに頷く。「いやぁ働いた働いた」
「そんな働いてねぇだろ」
「またまた~」
もし返事が来たら石井有一に関する情報を出来るだけ引き出しておくこと、明日も出勤してもらうことを約束し、二人は事務所を後にした。
【唯】
体操着のまだ白い部分で、目の周りの血を拭う。
むせ返るような濃い匂いが、自分の全身から立ち昇る。
もう
丸くて大きな目を、高くてきらきらした声を、唯は脳裏に浮かべる。
浮かべたそれを、縫い付けて、
また、白い部屋。
白い階段。
神殿みたいに広い階段が、部屋の奥に向かって伸びている。
均質に白く、
目を凝らし、数える。十五段。
上がった先に、ドアノブも引き手もない白い扉。
その上に投影された、黒い画面。
10.00
001 石井 愛 042 石井 凱 102 石井 小百合
137 石井 颯真 143 石井 孝男 187 石井 朋輝
209 石井 遥 257 石井 鞠花 264 石井 巌勝
286 石井 唯 287 石井 有一 329 石井 怜奈
たった十二人。
三百三十三人もいた石井さんが、もう十二人しかいない。
「減ったわねぇ」隣にいたおばさんが、顎に手を当てながら呟く。「なんで私が生き残れたのか、」唯を見る。「不思議でしょうがないわよ」
優しそうな、誰かと話したくてうずうずしてそうな、友だちのお母さんみたいな、おばさん。102番。石井
「ねぇ? そう思わない?」何も返せずにいる唯に「大変だったわよね? あなたも」ぐいぐい話しかけてくる。
「はい」唯は声を出す。「……あ、でも、わたしが生き残れたのは、」あのおじさんを探す。
いた。つむじが薄い、猫背の後ろ姿に「あの、」声を掛ける。「すみません、」肩を叩く。
「はい?」有一さんが振り返る。「えーと、」不安そうに、唯を見る。
「あの、さっきは本当に、ありがとうございました」唯は頭を下げる。
「あー、その、えーっと、」
「ボール、」顔を上げ「捕ってくれてなかったら、わたし死んでました」
「あぁ」ぴんと来たみたい。「はい、あー、いえ、」唯の目を見てすぐ、視線を斜め上に飛ばし「あれはその、たまたまですし、まぁその、えぇ、」しどろもどろに続ける。
「なに? あなたこの人に助けてもらったの?」小百合さんが興味津々そうに「すごいじゃない。よかったわねぇ」
「はい」唯は頷く。「有一さんのおかげです」
「いやその、ほんと、たまたまですよ」目を合わせないまま、耳の後ろを搔かき「ほんとたまたま、ボールが飛んできて、たまたま捕れただけ、というか。そもそもボクのところ、それまで一回もボールが飛んでこなくて、その、ラッキー続きで。自分でも、なんで生き残れたのやら、という」
「へぇ~ラッキーっすね」近くで話を聞いていた男の子が、会話に混ざってくる。「自分けっこうボール飛んできましたよ」この人はたしか、いたずらでボールをぶつけていたずらでボールをぶつけて
「そうよねぇ。危なかったわよねぇ」小百合さんの声にエンジンが掛かり「私なんて、もう二十回くらいはボール飛んできて、そのたび必死になって避けてたわよ。二十回は言い過ぎかしら。十回くらいかしら。八回くらいかもしれないわ。少なくとも、五回は飛んできてたわね。怖かったわぁ。私ふだん運動なんてしないから、もう大変で大変で。よく身体が動いたものね。人間、あれよね、火事場の馬鹿力っていうの? 死ぬかもってなると、とんでもない力を発揮するのねぇ。あなた中学生?」
「あ、はい、」急に矛先を向けられ、唯はどぎまぎする。「そうです。中二です」
「あらそう。若いわねぇ。こんなのに巻き込まれて大変ねぇ」朋輝さんに「あなたは?」
「高一っす」
「あそう」有一さんに「あなたは? おいくつ?」
「ボクは」一瞬、数えるような間を置き「四十五です」
「あら!」小百合さんが目を輝かせ「歳近いじゃない!」
「おばさんは何歳なんですか?」尋ねる朋輝さんを「女の人に年齢訊くもんじゃないわよ~」食い気味に
思ったより若いな、と唯は感じる。
「でもほーんとよく生き残ったわよねぇ、私たち」小百合さんが感慨深そうに言う。唯たちは入って右側に固まっているが、左の奥のほうにいる女の人をちらっと見て、声を潜め「あの人どうやって生き残ったか、あなた見てた?」
「え、見てないです」自分が生き残るのに必死で、そんな余裕なかった。あの人は257番だから、
「違うのよ、それが」もっと近寄るようにジェスチャーをして、さらに声を潜め「死体の山に隠れてたのよ」
「えっ」
「私びっくりしたんだから。終了のブザーが鳴って、画面見たら十二人まで減っちゃってて、でも立ってる人数えたら十一人しかいなくて、あれおかしいわね、なんて思ってたら、あの人が死体の山からのそのそ
急に話変える癖あるなこの人、と思いながら、唯は顔を離す。
「ボクは、その、俳優をしています」有一さんが答える。
「あら! すごいじゃない! テレビとか出てるの?」
「いえ、まったく」縮こまるように首を振り「舞台だけです。それも、その、小さな舞台だけで」
「でもすごいわよ~。俳優さんだなんて」
「いえ、ほんとうにそんな、」有一さんが顔を隠すように手を振り「バイトしないと、その、食っていけないですから」
「なんか意外っすね。有一さんが俳優って」朋輝さんが有一さんの顔をじっと見て「俳優というより、県庁の職員さん、って感じっすよね」誘うように笑う。
「えぇ、それはその、よく言われます」有一さんがへこへこして「公務員っぽい、と、よく」
「うるせぇなお前らさっきから」巌勝さんが
空気が凍る。
唯たちが竦み上がり、言葉を発せずにいると、巌勝さんは大きな舌打ちを部屋中に響かせ、
嫌なやつだが、言うことは正しい。
これからまた、人が死ぬ。
それは、唯かもしれないし、小百合さんかもしれないし、朋輝さんかもしれないし、有一さんかもしれない。
〈皆さま、大変お待たせしました〉
声が降る。
〈これより、第二ゲームの準備を行います〉
温度のない、感情のない、機械めいた声。
〈まずは皆さま、階段の手前に、横一列に並んでいただけますか〉
緊張が走る。
出方を探るような、たくさんの視線が
「ゲームの内容を教えてくれ」凱さんが画面を見上げ、はっきりとした口調で尋ねる。
〈まだお伝えすることは出来ません〉
「並んだ順番は、ゲームに関係するのか?」
〈順番にゲームを行っていただきます〉
「右と左、どっちが先だ?」
〈まだお伝えすることは出来ません〉
凱さんがさらに何か訊こうと息を吸うが、言葉は発されず、沈黙が下りる。
「これ、真ん中のほうがいいんですかね」有一さんが
「どうなんすかね」と呟いた朋輝さんが、急に駆けだし、左の端まで行って止まる。
「え」
「なんとなく、真ん中選ぶの
残った三人で、顔を見合わせる。
「あなたどうするのよ」小百合さんが、有一さんを肘でつつく。「真ん中行くの?」
有一さんが下を向き、考え込む。顔を上げ「ボクは、そうですね、まぁその、真ん中に」ぼそぼそと「まぁ罠でも別に」部屋の中ほどまで歩みを進める。
「あなたは?」小百合さんが訊いてくる。「どうするの?」
どうしよう。真ん中と端っこ、どっちが有利なんだろう。
階段がある。階段を使ってやるゲーム。グリコとか? でもグリコだったら順番関係ないな。というかこんな大勢でグリコ出来なさそう。なんだろう。なんのゲームだ。
うじうじ悩んでいると、周りが動き終え、順番が固まってしまう。
〈止まってください〉アナウンスが響く。〈こちらの順番で、ゲームを開始します〉
左から、朋輝さん、愛ちゃん、凱さん、
結局、端になってしまった。
〈石井唯さん〉急に名前を呼ばれ、びくっとする。〈
……へ? 何? 急に、えっ? 鯛焼き?
〈お答えください。鯛焼きは、頭から食べますか? お尻から食べますか?〉
ずらりと並ぶ十一人が、
まじでどういうこと? 鯛焼き? え、どっちから食べてるっけ? てかなんでわたし? え、どうしよう、ぜんぜん思い出せない。最後に鯛焼き食べたのいつだ? やばい、本当に思い出せない、けど「お尻です」唯は答える。
〈お尻ですか?〉
「はい」頭って答えると最初になりそうで、怖い。から、本当はどうだか知らないけど、お尻ってことにする。というかお尻って変じゃない? ふつう
〈第二ゲームは、しりとりです〉
え。
〈『お尻』を取った唯さんが最後、反対側の朋輝さんが先頭です。朋輝さん、愛さん、凱さん、と続き、唯さんの次は、また朋輝さんへ戻ります〉
しりとり?
〈ルールを説明します。皆さまは『しりとり』で遊び、口にした文字数に応じて階段を上がっていただきます。階段は十五段あり、のぼりきった先着六名がクリアとなります〉ざわめきに構わず、平板な説明が続く。〈基本的なルールは、通常のしりとりと同様です。前の方が口にした言葉の、語尾の一音を頭文字とした別の言葉を、次の方が発する、という行為を繰り返していただきます。ただし、禁字を口にした瞬間に、首輪が爆発します。清音、濁音、半濁音を合わせた六十八音のうち、五音が禁字です〉
禁字? なに? 意味不明。唯の頭がこんがらがる間も、説明は続く。
一通り聞いた後、凱さん、怜奈さん、孝男さんが、質問を重ねる。
だんだんと、ルールが分かってくる。
《爆発条件》
①「ん」で終わる単語を口にする。
②すでに使用された単語と同一の単語を口にする。
※同音異義語(雨・飴など)は「同一の単語」として取り扱う。
③禁字を口にする。
④『
⑤単語を発しないまま、制限時間十秒を経過する。
※残り時間はその都度、投影された画面でカウントダウンされる。
⑥首輪を外そうとする。
なお、爆発した回答者が最後に発した単語は無効となる。したがって次の回答者は、爆発した回答者の前の回答の語尾に続ける形で単語を選択する。
《ゲーム終了条件》
①六名が階段を上がりきる。
②生存者が六名以下になる。
※六名が階段を上がりきった時点で、残された全員の首輪が爆発する。
《細則》
【清音】あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわん(四十五音)
※「い」と「ゐ」、「え」と「ゑ」、「お」と「を」は重複扱い
【濁音】がぎぐげござじずぜぞだでどばびぶべぼ(十八音)
※「じ」と「ぢ」、「ず」と「づ」は重複扱い
【半濁音】ぱぴぷぺぽ(五音)
計六十八音のうち、五音が「禁字」
※
ルールを必死に
不利すぎない?
十五文字を消化すればクリア。先着六名。唯は最後尾の十二番目。
無理じゃない?
唯は「お尻」と答えたことを後悔する。
どう考えても、順番が早いほうが有利だ。ミスった。終わった。ここで死ぬんだ。
元から死にたかったわけだし、それでよくない? と囁く声が、意識の奥で響く。
そうだけど。
でも。
嫌だ。
こんな、わけ分からないまま、わけ分からないやつに
灯莉のためにも、厚士くんのためにも、生きなきゃいけない。のに。
質問が途絶え、時が止まったような沈黙が訪れる。
〈それではゲーム開始です。最初の回答者は石井朋輝さんです〉
「え待って、まだ、え」朋輝さんが焦り「どうすんのこれ、」
〈最初の文字は、しりとりの『り』です。『り』は禁字ではございませんので、その点はご安心ください〉
「え、いや、えっ、」
09.99
カウントが始まる。
「やば始まってんじゃん、どうしよう、え、」
数字が減っていく。
朋輝さんは声を出すのをやめ、時計を見つめながら、
02.01
あと二秒。
00.98
一秒。
「倫理」
口にしながら、朋輝さんが段を三つ上がる。
09.99
次のカウントがもう始まっている。「あっぶねぇ~」と朋輝さんがへたり込む三段下で、愛ちゃんが固まっている。
倫理。りんり。『ん』が使われた。『ん』の安全が確認された。いま禁字じゃないことが確実に分かっているのは、『り』『ん』の二文字。語尾に付けたら即死の『ん』を
「愛ちゃん! 答えて!」凱さんが叫び、愛ちゃんの肩を揺する。「『り』で始まる言葉! しりとり! 分かるよな?」
愛ちゃんが振り向く。泣きそうな顔で、ふるふると首を動かす。
「なんでもいい! 『り』で始まる言葉! 言わなきゃ愛ちゃん死んじゃうよ」
03.05
あと三秒。
「早く!」凱さんが地団駄を踏み「お願いだから! なんか言ってくれ!」
「りす」
葉が擦れるような、微かな声。
09.99
次のカウントが始まる。
その場を動かない愛ちゃんに〈石井愛さん。二文字消化しましたので、二段、階段を上がってください〉無機質な声が降る。
愛ちゃんがたどたどしく、段を上がる。
04.87
その間にも、時計は進んでいる。
愛ちゃんが「りす」と言ったことで、新たに『す』が解放された。『り』『ん』『す』の三文字は、もう安全。
02.55
愛ちゃんを見届けた凱さんが、引き締まった表情で、時計を睨む。
「すり」
あと一秒を残し、口にする。
ほのかに悔しさを滲ませながら、凱さんが二段上がる。
09.99
凱さんがリスクを避けた。安全が保証されている三文字の中で、二文字を消化した。
凱さんの次は、209番の遥さん。
血の付いた体操着姿なのに、どこか洗練された、おしゃれな雰囲気なのは、メイクと
たぶん二十歳前後の、少し芸術家っぽい、美大生みたいな雰囲気。
03.42
時間が過ぎていく。遥さんは表情のない、彫刻みたいな顔で、時計を見上げている。
00.31
「リスク」
顔が飛ぶ。
遥さんの首から上だけが宙を舞い、数段先に着地し、ころころと下まで転がる。
身体が静かに倒れ、階段に横たわる。真っ白な段が、赤く染まっていく。
転がった顔が、唯を向いて止まる。
まるで、本物の彫刻になったみたいな、きれいな顔。
08.79
遥さんが、禁字を踏んだ。
時計が進んでいる。
リスク。りすく。『り』と『す』は安全。『く』が禁字。
「リンス」
巌勝さんの、重い声が響く。靴底が床を擦り、三つ段を上がる。
09.99
こっちでよかったのに、と唯は思う。
「リンス」なら、リスクを一切負わずに、三段上がれたのに。
スタイルのいい、マネキンみたいな死体を、唯は見つめる。
もっと文字数を、と考えたのかもしれない。それで、残り一秒を切って、焦って、何度も頭を巡っていたはずの「リスク」を、とっさに口にした。
02.16
「寸劇」
二秒を残し、有一さんが呟く。段を四つ上がり、誰よりも高い位置に立つ。
09.99
爆発音は鳴らず、次のカウントが開始される。
有一さんが、ふぅと息を吐く。心底ほっとした顔で、次の怜奈さんを見下ろす。
新たに二文字開いた。すんげき。『げ』と『き』が解放された。これで『り』『ん』『す』『げ』『き』の五文字を、爆発の心配なく使うことが出来る。
有一さん、大胆だな。一気に二文字開ける度胸は、わたしにはない。
ぼやっとした顔を、改めて眺める。気が弱そうに見えて案外、勝負師なのかもしれない。それか、リスクをあまり考えず、自分の職業に関連する単語を、とりあえず口にしただけかも。
01.22
「喜劇」
怜奈さんが口に出す。三段上がる。思考が一段落したような、澄ました顔で。
09.99
ノーリスクで三段。悪くない。怜奈さんの切れ長の目が、自信を
このゲームは、いかにリスクを取らず、多くの文字数を消化できるかが
次の回答者は鞠花さん。死体の山に隠れていた、という
01.09
「喜劇的」
爆発する。
鞠花さんの首が取れ、赤黒い血を噴き出し、だらしなく沈む。
〈『喜劇的』は、『広辞苑 第七版』に収録されておりません〉
乾いた音声が響く。
07.61
時計が進んでいる。颯真くんが、血を垂れ流す鞠花さんの死体を、呆然と見下ろしている。第一ゲームではどこか楽しげに、俊敏にボールを躱していた颯真くんの顔が、恐怖に歪んでいる。
鞠花さんは、怜奈さんの『喜劇』に乗っかる形で、『て』だけリスクを負って、一気に五文字を消化しようとした。だけど、広辞苑に載っていなかった。「○○的」とかは、広辞苑に載ってない? たまたま『喜劇的』だけが載ってない? 分からない。いずれにせよ、「○○的」はもう、怖くて口に出来ない。
もう二人死んだ。
一周もしないうちに、二人。
02.33
「答えろ! 颯真!」凱さんが叫ぶ。「なんでもいいから!」
00.17
「木登り」
死体に目を落としたまま、颯真くんが呟く。
09.99
〈石井颯真さん。四文字消化しましたので、四段、階段を上がってください〉また同じように、無機質な声が降る。
颯真くんが段を上がる。
きのぼり。『の』と『ぼ』が開いた。これで、安全が確定したのは『り』『ん』『す』『げ』『き』『の』『ぼ』の七文字。判明した禁字は、五文字のうち、『く』だけ。全部で六十八文字だから、まだ六十文字に、爆発の可能性が残されている。
「利率」
残り一秒となってから、孝男さんが
09.99
『つ』が開いた。顔が
次は小百合さん。雑談していたときとは打って変わった真剣な
「
二秒残して声を発し、階段を上がる。
09.99
唯の番が来る。
08.75
もう一秒が経った。減っていく数字を見つめながら、思考を高速で回す。
『や』も開いた。『り』『ん』『す』『げ』『き』『の』『ぼ』『つ』『や』の九文字がノーリスク。『く』だけはダメ。言ったら死ぬ。最後尾は不利。だから出来るだけ多くの文字を。危険な文字は使えない。死ねない。左手首の傷痕に触れる。死にたい。死にたくない。今は。
02.40
あと二秒。出来れば四文字以上。『き』で始まる。き。なんだ。き。他あとなに使えたっけ。き。やばい。言わなきゃ。死ぬ。
「きつつき」
09.99
カウントダウンが始まる。
唯は踏みしめるように、段を四つ上がる。
同じ段に、有一さん、颯真くん、小百合さんが並んでいる。上には誰もいない。
ノーリスクで四文字。上出来。
【伏見】
鶴田から依頼を受けた翌日。午前十一時過ぎ。
新宿駅からほど近い、比較的安価なコーヒーチェーンの二階で、伏見と蜂須賀は田中ファイナルウェポンを待っている。
「楽しみっすね、田中ファイナルウェポンに会えるの」先がスプーン状に拡がったストローで、蜂須賀がコーヒーフロートのアイスを
「田中ファイナルウェポン〖圏点:さん〗な」伏見は熱いブラックコーヒーを啜り、釘を刺す。「というか呼ぶときは別に、フルネームじゃなくていいと思うぞ。田中さん、とかで」
「ウェポンさん」
「田中さんにしてくれ」
昨日の解散後、DMの返信がちらほら来たが、ほとんどが空振りに終わった。そもそも石井有一はあまり社交的な性格ではなく、蜂須賀がやりとりを担当した半数も、特に新しい情報はもたらさなかったと言う。
面会のアポが取れたのは二件。
まず、直近の公演『愛以外もください』で石井有一と共演した田中ファイナルウェポン。お昼前の十一時くらいから少し時間が取れるとのことなので、職場に近いという新宿駅のカフェで待ち合わせることにした。
次に、鶴田とは直接関係のない、劇団・犬用ケーキの公演『はじめての
蜂須賀がまたアイスを口へ運んでから、慌ただしくコーヒーを吸い上げる。
「なにバタバタしてんの」
蜂須賀が
「飲み込んでからでいいだろ」
「出来るだけ同時に近づけたいんすよ」そう言ってまた、アイスとコーヒーを
「というか人から話聞こうってときにコーヒーフロート頼むなよ」
「いいじゃないすか別に」
階段を上がった位置で周囲を
田中ファイナルウェポンだ。
伏見は立ち上がり、田中ファイナルウェポンを手招きする。
伏見に気付くと、田中ファイナルウェポンは軽く目礼し、こちらへ向かってくる。
どうも伏見です、田中です、どうも、と言葉を
「いえいえ、私こそすみません、遅刻してしまって」田中ファイナルウェポンがテーブルへ置いたトレイには、コーヒーフロートが
蜂須賀の何か言いたそうな視線を無視し「お忙しい中、ありがとうございます」伏見は頭を下げつつ座る。
「いえそんな、忙しくないので、全然」田中ファイナルウェポンは両手を小刻みに揺らし、目を合わせては逸らし「歯医者に行ってただけなので」
「あれ、お仕事では」
「あぁ午後からです、今日は」田中ファイナルウェポンは人見知りを感じさせる早口で「私新宿区役所でバイトしてて、シフトが一時からなので午後一時からなので今日は。朝歯医者に行って、奥歯の神経を取ったんですけど、取ったのは先週で今日は埋めてきたんですけど、むしろ時間がぽっかり空いてしまっていたので、逆に、はい、ありがとうございます」
「いえいえ。こちらこそです」伏見は
「はい、よろしくお願いします」
田中ファイナルウェポンの印象は、SNSに投稿された文章や写真と相違ない。三十代後半と思しき、地味で
「区役所でバイトされてるんすね」蜂須賀が口をひらき「あ、助手の蜂須賀です」遅れて名乗る。
「はい、どうも、はい」田中ファイナルウェポンは蜂須賀に一瞬目を向け、ぺこりと首を倒し「舞台だけだと食べていけないので、もう十年くらいかな? 新宿区役所でバイトしてまして。受付とかデータ入力とか。
「なるほど。区役所すか」蜂須賀が相槌を打ち「なるほどっすねぇ」何か言いたそうな視線を、伏見へ向ける。
「溶けないうちにどうぞ、召し上がってください」伏見は無視し、田中ファイナルウェポンのコーヒーフロートに手のひらを向ける。「というかすみません、先払いのカフェにしてしまって。お飲み物代、お支払いします」伏見は財布を開ける。
「あ、いえ、そんな、」田中ファイナルウェポンがアイスを口に運ぶやいなや、大急ぎでコーヒーを吸い上げ「全然、お
蜂須賀が何か言いたそうに伏見を見るが取り合わず「それいくらだった」小声で訊く。
「四百五十円っす」蜂須賀がにやにやしながら、アイスの溶けはじめたコーヒーを吸い上げる。なんで俺が少数派になるんだよ。
遠慮する田中ファイナルウェポンに無理矢理小銭を握らせ、レシートを受け取る。財布にしまい、コーヒーを一口飲んでから「それで、石井有一さんのことなのですが、」本題に入る。
「ええ」田中ファイナルウェポンが頷き「私に出来ることであれば、はい、なんでも、」心持ち、姿勢を正すようにして「いくらでも、お話しします」
「ありがとうございます」伏見は蜂須賀を横目で見る。メモ帳をひらき、ペンをノックしている。「石井有一さんと最後に会ったのはいつですか?」
「DMでもお伝えしましたが、3月24日の、夜の回の終演後です。下北沢の劇場を出て、聖太朗くんも一緒に、駅まで歩いて。有一さんは京王線、私と聖太朗くんは小田急線、と別れて、」宮本聖太朗とは蜂須賀がコンタクトを取っていた。しばらく予定が詰まっているらしく面会は断られてしまったが、同じように駅で別れたとのことだった。「そこからは、はい、LINEも送ってみましたが、今も、既読すら付かずで」
田中ファイナルウェポンが差し出した、スマホの画面を見る。
3月25日、千秋楽当日の17時37分に送った「大丈夫ですか?」も、一夜明けた3月26日13時02分に送った「心配です。大丈夫ですか?」も、既読は付いていない。
「なるほど」伏見はスマホを返し「何か、失踪の予兆のようなものは感じませんでしたか?」
「……いえ、」田中ファイナルウェポンがストローで、グラスの中身をかき混ぜる。溶けゆくアイスと、黒く染まった氷を見つめ、「特には。ご連絡いただいてから、改めて思い返してみたのですが、特に、心当たりがなく」伏見と一瞬目を合わせ、また
「そうですか」伏見は言う。「鶴田の演技指導は、厳しいものではなかったですか?」
「それも、特には」田中ファイナルウェポンがコーヒーを吸い上げる。「失踪の前日も、いつも通りの鶴田さんでした」
「普段から厳しいんじゃないんすか?」蜂須賀が
「いえ、そういう感じでもなく」田中ファイナルウェポンが首を横に振る。「鶴田さんはぶっきらぼうな方で、最初は少し、厳しい印象を受けたりもするのですが、
蜂須賀がペン先をメモ帳に置いたまま、トレイの隅を見つめ、考え込むような顔つきになったので「鶴田はそういうやつだよ」伏見からも言い添える。「昔から」
「んー」蜂須賀が低く
「はい」田中ファイナルウェポンが頷き、伏見を見て「伏見さんと鶴田さんは、高校の同級生なんでしたっけ?」気弱げな笑みを浮かべる。
「そうですね」蜂須賀のやつ、田中さんじゃなくてウェポンさんって呼びやがった。「十年会ってませんでしたが」
「昔から、こう、
「ええ、そうです」伏見は苦笑し「
自然な笑いが漏れ「じゃあもう、ずっとなんですね。ずっとあの感じ」田中ファイナルウェポンの態度が、また少しほぐれる。
穏やかな雰囲気のうちに、出来るだけ情報を引き出したい。
「田中さんは、鶴田の芝居に出るのは今回が初めてなんですか?」
「ええ。そうです」
「石井有一さんと共演するのも?」
「初めてです。今回の共演者は、皆さん初めましての方でした」
「なるほど。石井有一さんには、どんな印象を抱きました?」
「大人しい方、というか、不思議な方というか。役に入っているときと、そうではないときで、雰囲気がガラッと変わるので驚きました」
「稽古の合間などで、石井有一さんと会話を交わす機会はありましたか?」
「三人芝居だったので、それなりに。ただ有一さんはなんというか、人を寄せつけない感じというか、自分の中に
「厭世的? たとえばどんなことを言っていました?」
「うーん。なんでしょう」田中ファイナルウェポンがむず
「なるほど」
「ちょっと、情緒不安定というか。急にニヤついたり、泣きそうな顔になったり、やたら機嫌がいいかと思えば、死にたいとか言いはじめたり」
「死にたい、ですか。何か具体的に、死にたい原因があったのでしょうか?」
「どうなんでしょう」田中ファイナルウェポンが長考する。「具体的には、あまり言ってなかったかもしれません。もう四十も
蜂須賀が無表情で、ペンを走らせる。
伏見は考える。もし石井有一が、25日に自宅で自殺していた場合。今日は28日。春らしい陽気が続いている。隣人が腐臭に気付きはじめるころかもしれない。
早く石井有一の家へ。椎木ワタルとの待ち合わせを早められないか──と思考は巡るが、もし25日に死を選んでいれば、いずれにせよ手遅れだ。
今は落ち着いて、田中ファイナルウェポンから話を聞くべきだろう。
「鶴田の演出に対する
「それはないです。一切」田中ファイナルウェポンが手を振って否定する。「むしろ、鶴田さんには感謝している、とよく言ってました。目的もなく生きていた自分に、死ぬまでの
「死ぬまでの暇潰し、ですか」たまに聞くフレーズだ。「ちなみに、石井有一さんの家族構成や出身地について、知っていることはありますか?」
田中ファイナルウェポンが、記憶を絞り出すように眉を寄せ「……長崎出身、と言っていたような。……自信ないですけど」
「長崎のどちら、までは」
「それは分からないです」申し訳なさそうに「家族構成もすみません。独身で彼女出来たことない、とは言ってましたが、ご両親や兄弟の話は、有一さんから聞いたことないですね」
「そうですか」長崎の実家に戻っている可能性もあるだろうか。だが、見つけに行くには情報が少なすぎる。別の切り口を探す。「失踪前日の公演で、何か普段と変わった点はなかったですか?」
「特に変わった点はない、と、」戸惑いがちに眼鏡の位置を直し「お伝えしたはずですが」
「失踪の件を、一度忘れてください」伏見は出来るだけ柔らかい笑みを作り「本当になんでもいいんです。ネガティブな変化に限らず、ポジティブな変化でも。どれだけ
田中ファイナルウェポンがストローの飲み口を見つめる。「
「はい」続きを
「リラちゃん、という名前の、すごく可愛い子で。中学二年生の。まだ中学生なのにメイクとかもしてて、TikTokとかそういうの自分ですごい発信してるような、ませた子で。十代の女の子を、全力で満喫してる感じの。リラってこういう字書くんですけど」
「いえいえ。まったく下手じゃないです。それに、情報は多ければ多いほど良いですし」
「ありがとうございます」田中ファイナルウェポンは首を竦め「私、姉がいて。姉は前からたまに私の芝居観に来てくれてたんですけど、初めて、莉楽ちゃんも連れて来てくれて。あ、すみません、姉が美人なんですよ。父がハンサムなんですけど、姉は父に似て。あと姉の
「なるほど」伏見は顎を撫で「その後、鶴田のダメ出しがあり、一緒に帰った形ですか?」
「はい。聖太朗くんも一緒に」
「帰り道も、引き続きご機嫌で?」
「そうですね、うん、」また記憶に潜るように視線を外し「あ」なにか思いついたような声を漏らし「まぁ、これはでも、」
「なんですか?」伏見は逃さず尋ねる。「どんな些細なことでもいいので、思い出したことがあったら、聞かせてください」
「なんか説明が難しいんですけど、」と口にし、五秒ほどが経過する。伏見を向き、困った表情のまま「駅まであと三分くらいのところで、有一さん急に立ち止まって」
目で続きを促す。
「急に焦ったような感じで、『シュウジさん? え?』って」
「シュウジさん?」
誰だ?
「私も全然知らない名前なんですけど、急にそう言って。聖太朗くんが『どうしました? 知ってる人いました?』って訊いたら、また一瞬はっとしたみたいに『いや、』って首振って、また歩きはじめて。それから、有一さんがいつになく低い声で『疲れた』って」
「『疲れた』? 有一さんがそれを言うのは珍しいですか?」
「いえ、珍しくないです。なのでふつうに、私も『疲れましたねぇ。でも明日で千秋楽ですよ』とか返して、有一さんが『ですね。明日で終わりなので、もうひと頑張りですね』みたいに言って、駅で別れて」
「なるほど」公演期間も終盤だ。『疲れた』と漏らすこと自体は自然だろう。それより「『シュウジさん』には、まったく覚えはなく?」
「ないですね」田中ファイナルウェポンが頷き「その場はすぐ流れてしまったので、特に追及することもなく。知り合いとすれ違ったんですかね」白く
「ふむ」シュウジさん、か。後で検索してみるか。「他に覚えていることは?」
田中ファイナルウェポンはたっぷりと考えてから、「もうないですねぇ」と声を引き伸ばす。言いながら思い出せれば、と最後まで
隣の蜂須賀を見る。こんなところですかね、と言いたげな顔で、グラスの底に
田中ファイナルウェポンがコーヒーフロートを飲み切るまでの間、石井有一の性格をさらに深掘りしようとしてみるが、あまり打ち解けた会話は交わしていないらしく、有用な情報は得られなかった。
そろそろカフェを出ようかというタイミングで「ウェポンさん、」蜂須賀がきりっとした顔を作り「最後にひとつ、訊きたいことがあるのですが」
「はい」田中ファイナルウェポンが、自分の鞄に触れた手を戻し「なんでしょう」緊張気味に、蜂須賀に向き直る。
「なぜ、田中ファイナルウェポンという芸名にしたんですか?」
おい。
蜂須賀、おい、余計なこと聞きやがって、失礼じゃねぇか、という気持ちを、好奇心が上回る。たしかに話せば話すほど、真面目で親切な印象が際立ち、ファイナルウェポン感の薄さが気にはなっていた。
伏見は口を挟まず、回答を待つ。
「私、」田中ファイナルウェポンが、口をひらく。神妙な面持ちで「本名が、田中
伏見と蜂須賀は無言で頷き、先を促す。
「高校のとき、仲いい友だちからずっと、ナルポンと呼ばれていて」
伏見と蜂須賀も神妙な面持ちとなり、「はい。それで」小声で先を促す。
「その友だちが、ある日、家に遊びに来て。私のことナルポンって呼ぶのを聞いた父親が、ファイナルウェポンだ! ファイナルウェポンの略だ! って騒ぎはじめて。それで、気づいたら、田中ファイナルウェポンを名乗っていました」
笑っていい話なのか分からず、伏見は神妙な面持ちを保ったまま「なるほど」席を立つ。「今日はお時間いただき、ありがとうございました」
「いえいえ。あまりお役に立てず、すみません」田中ファイナルウェポンが頭を下げる。「コーヒーフロート、ご
何か言いたそうな蜂須賀を無視したまま、店を出る。
歌舞伎町へ消えていく、田中ファイナルウェポンの背中を見送る。