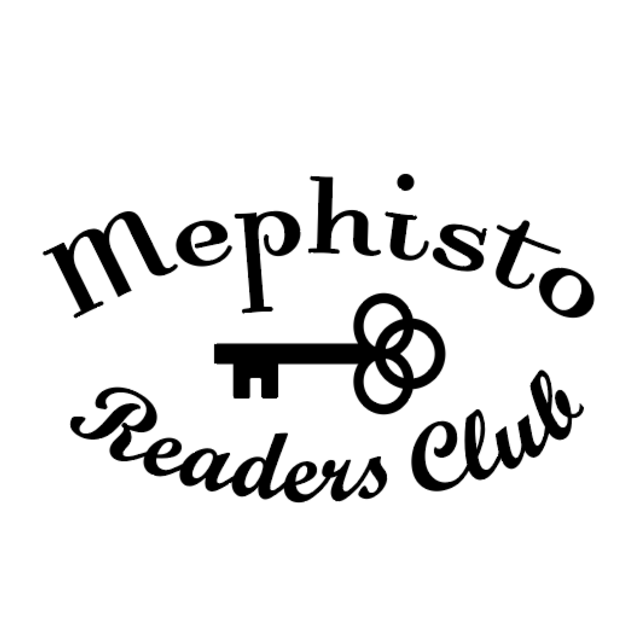純文から転向した著者のエンタメ力に脱帽 瀧井朝世
文字数 1,805文字
純文から転向した著者のエンタメ力に脱帽
交通事故で死んだクラスの人気者・山田が、教室のスピーカーに憑依する話なんだって――そう説明すると必ず「なにそれ! 面白そう」という反応が返ってくる。今のところ100%である。そういう自分も、最初は人からあらすじを聞いて同じ反応をしたクチだ。シンプルな内容紹介だけで読者の期待を最高値に高めてしまうデビュー作、それが金子玲介の『死んだ山田と教室』だ。大丈夫、その期待は決して裏切られない。
本作はメフィスト賞受賞作である。広義のエンタメ作品を募集している賞だが、ミステリ作品を多く世に送り出しているイメージが強い。そのため、本作もミステリだと思って手にとる人は多いだろう。実際、話が始まって早々にまるで館ミステリの見取り図のような、生徒の名前と部活が書き込まれた座席表の図版が掲載される。ここになにかヒントがあると思ったあなた、この座席表で教室の左右両方が窓になっていることに秘密があると思ったあなた、第三話で新聞部の倉持と泉が山田の死の真相を探ろうとするのを読んで「お、やはり単なる交通事故じゃなかったのか!」と思ったあなた。完全にメフィスト賞という看板のトラップにかかってますね。はい、私もそうでした。ちなみに後日知ったのだが、教室の両側が窓になっているのは、著者自身が通っていた高校の教室が実際にそういう作りだったのだそうだ。
ページをめくるうちにいつしか、ミステリ要素の有無などどうでもよくなっていく。教室内のおバカな会話に笑い、山田の喋りの上手さに感心し、それを描き出す著者の言葉選びのセンスと描写力に感服し、ただただ高校生たちの群像劇を読むだけで楽しくなってしまう。生徒たちの個性や事情もさまざまで、かつ、山田の死や彼がスピーカーに憑依したという不思議な現象の受け入れ方にも個々人でグラデーションがあり、思春期世代の群像劇として読ませる。そしてそのグラデーションは、時が経つにつれて幅を広げていく。
山田の存在は二年E組の秘密事項だ。クラスメイトたちが進級し、卒業したら、教室に留まる山田の話し相手はいなくなってしまう。「人は二度死ぬ」とはよく言われる言葉で、一度目は肉体的に死んだ時、二度目は人々から忘れ去られた時だという。山田の場合はちゃんと成仏するかもしれないので、三度の死があるといえそうだ。肉体的な死はすでに訪れているが、忘れ去られる時と成仏する時と、どちらが先に訪れるのか。成仏するとしたら、それはどんなきっかけで訪れるのか。
この作品は誰かの死後、遺された人々の変化と同時に、死んだ本人の変化までが分かるのが読みどころだ。生活がどんどん変わっていくクラスメイトたちと、何も変わらずそこにいる山田の対比が鮮烈に浮かび上がる。前半で描かれる二年E組の日常があまりにもおバカで愛らしいからこそ、時間の経過による変化がなんとも切ない。そうした若い世代の姿を生々しく描いた作品なのだな――と思ったら終盤で驚きの真相が立ち現れる。やはりメフィスト賞、あなどれません。ただしその驚きは、読者をあっと言わせるために強引に用意されたものではなく、思春期の切実な本音を、リアリティを持って突きつけてくるものとなっている。人間の複雑さと繊細さ、残酷さとある種のしたたかさが現実味をともなって浮かび上がってきて、終盤の展開はもう、腑に落ちるとしかいいようがない。圧巻である。
著者の金子玲介氏は高校時代に小説を書き始め、純文学系の文藝賞やすばる文学賞の最終選考に残ったこともあったという。ちなみに、すばる文学賞の最終選考で彼の作品を強く推したのが選考委員の金原ひとみ氏だったそうで、彼女はこの『死んだ山田と教室』にも推薦コメントを寄せている。著者に聞いてみたところ、その時の応募作は一人の少女が死ぬまでを彼女の視点で綴り、その合間に、彼女が死んだ後に交わされる友人や教師らの会話を断片的に挟む形のものだったそうだ。つまり、死という大きな喪失と、その後の人々の変化についての興味は以前からあったというわけだ。エンタメに方向転換してもなおその重く普遍的なテーマを保持しつつ、こんなにも、愉快で愛らしくて哀しくてサプライズに満ちた小説に仕立て上げた手腕に脱帽。すでに年内に第二作『死んだ石井の大群』と第三作『死んだ木村を上演』の刊行が決まっているという。金子劇場の開幕である。