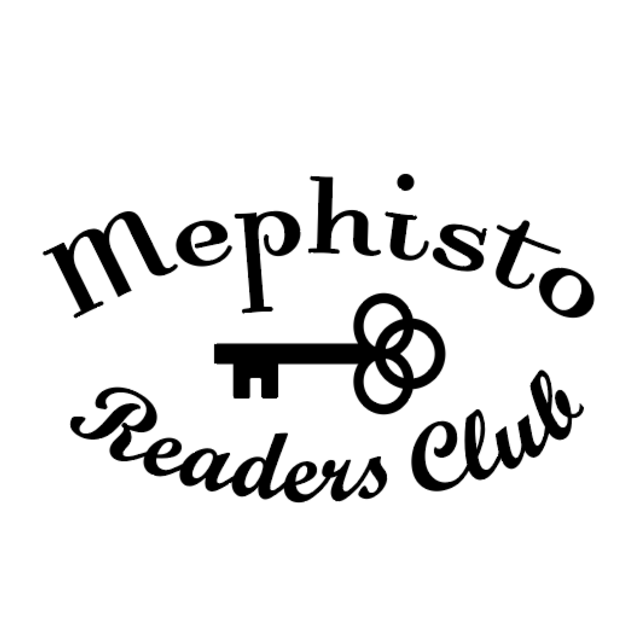喪の作業の大切さか、モラトリアムを共有した者の別れの悲劇か 千街晶之
文字数 2,053文字
喪の作業の大切さか、モラトリアムを共有した者の別れの悲劇か
私はこれまでに幽霊の類を一度も見た経験がないが、見たことがあるという知人も少なからずいるので、そうした存在を肯定する気も否定する気もない。死後の世界が存在するか否かについても、そんなものは死んでみなければわからないという立場である。
しかし、幽霊になった時の気分はどうか、あるいは死後の世界に行ったらどんな気分なのかを想像してみることはある。肉体が滅んだ以上、幽霊は食事はできないし(そもそも五感があるのかどうか)、恐らく睡眠もしないだろう。想像するだに退屈そうである。ごく少ない霊感持ちの人間と遭遇するまでは自分の訴えを聞いてもらうこともできないのだとすれば、あまりの孤独に発狂してしまうのではないかと思う。
第六十五回メフィスト賞を受賞した金子玲介のデビュー作『死んだ山田と教室』に登場する山田が、幽霊と定義されるのかどうかはわからない。取り敢えず、死んだ人間の意識だけが残った存在と呼ぶべきだろうか。
物語の主な舞台は、ある高校の二年E組の教室。男子校なので生徒は全員男子である。その一人である山田が、夏休みが終わる直前に交通事故死して三日が経った。お通夜が続いているような教室の雰囲気を心配した担任の花浦は、臨時のホームルームを開始する。教室の真ん中にぽっかり空いた山田の席がある状態では、それを意識してみんな凹むだろう――という花浦の提案で席替えをしようとした時、
〈いや、いくら男子校の席替えだからって盛り下がりすぎだろ〉
という声が聞こえたのだ――他ならぬ山田の声が。
花浦や生徒たちは驚愕して教室を見回すが、相変わらず山田の声は聞こえている。山田本人も、自分の身に何が起きているのか全くわからず混乱しているらしい。
やがて状況を整理した結果、山田の声が教室の全員に聞こえていること、山田の周囲は完全に真っ暗で、身体の感覚もなく完全に声を出すだけの存在として教室のスピーカーに宿っているらしいことなどが判明する。どう考えても戦慄すべき異常事態であり、ここからホラー的展開になだれ込んでもおかしくはないのだが、そこで山田が提案したのはなんと「席替えの仕切り直し」。そして、山田の声が聞こえる現象は、二年E組の生徒たちおよび担任の花浦だけが共有する秘密とすることになった。
これが本書の導入部である第一話だが、その後、山田は二年E組の仲間たちと他愛もないお喋りをしたり、死んでから初めての誕生日を祝ってもらったりする。山田の事故死から「真相」を探り出そうという動きも出てくるが、そこはおバカな(一応、偏差値高めの進学校なのだが)男子生徒同士の会話であり、ミステリめいたシリアスな解決篇があるわけでもない。舞台が男子校なので、彼らの悩みは童貞を卒業できるかどうかといった能天気なものである。
といった調子で、死者の声が聞こえる点を除けば日常的な学園生活が淡々と続くかに見えるのだが……ちょっと考えればわかる通り、月日が流れれば二年E組の面々は三年生になるのである。教室は山田にとって見も知らぬ生徒たちが過ごす場となる。級友たちが学校にいるあいだは、機会を見つけて二年E組を訪れて山田と会話することは可能だとしても、卒業すればそうもいかない。彼らの卒業と同時に山田が成仏する――といった展開が待っていれば御の字だが、そんなに都合良く事が運ぶとは限らない。そう、冒頭で私が想像したような、孤独で退屈な死後の世界が山田を待っているのである。
月日の流れとともに成長してゆく級友たちと、高校二年生の夏休みまでの時間に閉じ込められた山田。彼らのあいだのズレは、どんどん大きくなってゆく。在学中から既に級友の中にも、「山田の死を、全員がちゃんと悼むためにも、山田はああいう形じゃなく、きちんと死ぬべきだったと思う」と主張する者が出てくる。
私は五十代半ばに近づいており、人生の後半戦に入った事実をどうしても意識せざるを得ないこともあって、本書をまず、喪の作業を経ることの重要性を描いた小説として読んだ。死者にきちんと別れを告げることの大切さ。それを体験し損ねたことで、山田と級友たちの関係はどんどん歪で不自然なものになってゆくのだ。
しかし、別の読み方をすれば、本書はモラトリアムの時代を共有した者同士が、そこから卒業した立場と、そこに取り残された立場とに引き裂かれてしまう悲劇を寓意的に描いたものでもあるだろう。モラトリアムの時代には誰もがいつか別れを告げなければならないのだとしても、早々に巣立った者と、そこに囚われた者とのあいだに生まれる時間の流れの差はどうすることもできない。死をまだ身近とは思えない若い世代にとっては、そちらのほうが実感のある読み方だろう。世代や読者それぞれの死生観などによって、本書から感じ取るものが何かは大きく違ってくるのではないだろうか。そのぶん、若い世代のみならず、幅広い読者層に訴えかける要素がある小説と言えそうだ。