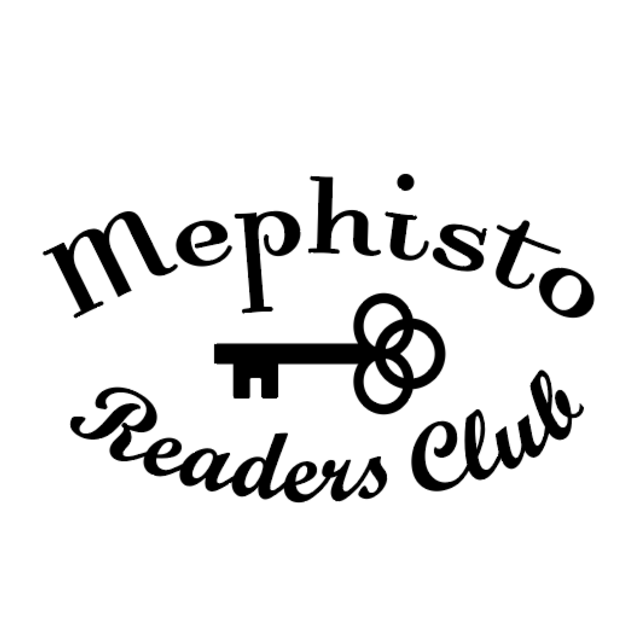虎は死して皮をとどめ、山田は死して教室に声を残す 吉野 仁
文字数 1,910文字
虎は死して皮をとどめ、山田は死して教室に声を残す
ぶっとんだ発想、豊かな語り口、ユーモアあふれる展開により、ありえない出来事を現実に変え、驚きの連続から胸を打つ結末へと読み手を運んでいく。『死んだ山田と教室』は、こうした魅力にあふれた小説だ。
物語は、クラスの人気者だった山田が死んだことからはじまる。まもなく夏休みが終わろうとしているとき、交通事故にあったのだ。そして二学期がはじまると二年E組の教室は静まりかえっていた。三十五人になった教室の生徒たちにとり、山田はかけがえのないひとりだった。
ところが、突然、教室のスピーカーから声がした。死んだはずの山田の声だ。なんと山田がしゃべっているではないか。どうやら彼はみんなが話す声を聞くことができるらしい。目は見えないが、音は聞こえ、はっきりと語りかけることができる。
なぜこんなことになったのか、とたずねると、
〈あぁー、わかんないすけど、俺このクラス大好きで、二Eのみんなとずっと馬鹿やってたいなっていつも思ってるから、それでこうなったのかもしんないっす〉
と山田はこたえた。
二年E組の一員として声だけの存在ながら山田は復活した。およそ信じられない現象だけに外部には秘密にしておこうとの約束が二年E組内でできあがった。それから毎日、死んだ山田は教室でしゃべりつづける。
読みはじめて驚くのは、教室における男子高生徒たちの言動がみごとに活写されていることだ。
単にいまの若者らしい言葉づかいや現代日本の風俗をそのまま活字に落とし込んでいるだけにとどまらない。もはやこどもでもないが大人とは言い切れない年ごろである高校生とは、たいがい下ネタ好きのどうしようもなく馬鹿な連中である。それでいて思春期特有の自意識をもてあまし、問題を隠し抱えている。取扱注意の札をさげた大人こどもたち。しかも閉じた教室のなかだけに、彼らは共鳴と増幅を重ねて、たちまち大騒ぎとなる。意味のない言葉遊びに興じたり、話が脱線しつづけたりするのだ。こうした様子をうまくとらえておもに会話のやりとりだけで描いている。作者のもつ言語感覚のすごさ。活字から声が聞こえる。自分もまた同じ教室に居合わせているような感覚になってしまった。
なにより山田がいかにクラスのみんなから愛されていたか、冒頭からよく分かるように書かれている。とくにE組で授業を持っている先生のものまねを山田は全員分できるし、しかもそのクオリティがめちゃくちゃ高かったというエピソードだ。人気者だったのもとうぜんだ。毎日が山田のおかげで愉しくてしかたないという教室の雰囲気がこの部分だけでしっかりと伝わってくるではないか。
そしてつぎに興味を引くのは、展開の面白さだ。このクラスが大好きだったと語る山田だけに、全員のことをじつによく知っているのだ。そして、クラスの人気者だった山田自身にも隠された謎や秘密のあることが次第にほのめかされたり、暴かれたりしていく。読みはじめ当初、奇想に満ちたドタバタ学園小説だと思っていた読者は、そこではっと驚かされるだろう。文化祭をはじめ学園小説の定番のような行事や深夜だれもいない教室での出来事などを通じて、いくつもの事実が語られ、同時に、山田がどんな男でどんな過去があったのか、次第に掘り下げられていくのだ。また、それまでの馬鹿馬鹿しい描写との対比で、シリアスな場面がより神妙に、より切なく感じられるのもみごとだ。
しかし、途中までの展開はなんとなく読めるものの、その先になにが待っているのか、中盤からまったく分からなくなっていく。どんな結末が待ち受けているのかは、読んでからのお楽しみとなるので、これ以上詳しくは書けないが、あらためていえば、やはり「クラスの人気者だった山田が教室で声だけの存在となってよみがえる」という設定がとても秀逸だと思うばかりである。
死んだ人間が死にきれず魂となってこの世をさまようという幽霊譚なら、これまで膨大な数の話が語られてきたことだろう。もしくは死者をAIでよみがえらすという現代的な発想で書かれたものも、すでに山ほどあるのかもしれない。その人がそれまで残した写真や動画や録音された声などのデータをもとにまだ生きているかのごとく再現してみせるアイデアは、とっくに商業化されている。だが、この『死んだ山田と教室』はちがう。男子高校生の日常のくだらなさとそのかけがえのなさをあらためて認識させてくれる小説でありつつ、それだけで終わらないのがすごいところだ。
「死んでしまったがまだ意識と声だけ生きている」山田が、いったいどんな運命をたどるのか、それを見届けていただきたい。