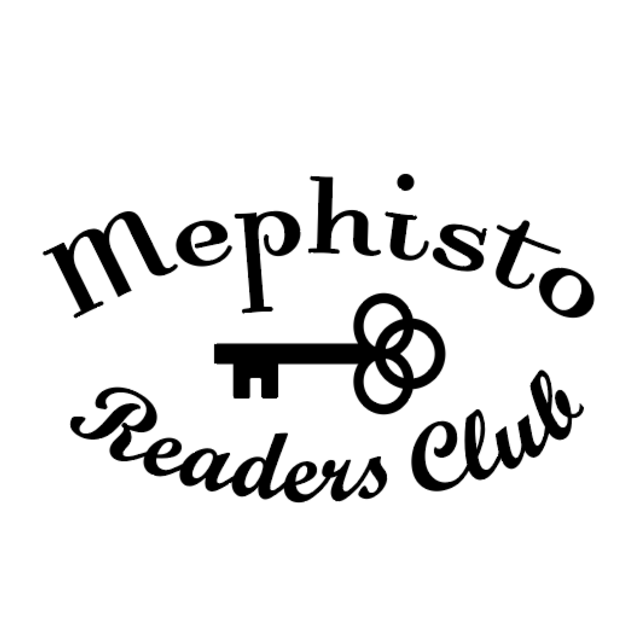「わたしはなぜ人間じゃないの?」・・・ 大森 望(翻訳家・書評家)
文字数 1,232文字
「わたしはなぜ人間じゃないの?」――根源的な問いに迫るSF法廷劇
二〇一六年五月、米シンシナティ動物園で一頭のゴリラが射殺された。柵をすり抜けて内側の堀に落ちた三歳の男の子の足首をつかんで引きずり回したためだ。殺されたのはニシローランドゴリラの雄のハランベ。その死を悼む声が全世界に広がり、ネット上では男の子から目を離した母親が猛烈にバッシングされると同時に、動物園の責任も追及された。なぜ麻酔銃を使わなかったのか? 絶滅危惧種であるゴリラを射殺した判断は正しかったのか?
現実に起きたこの事件を意外な角度から小説化したのが、須藤古都離のメフィスト賞受賞作『ゴリラ裁判の日』。作中では、射殺されたゴリラの〝妻″であるローズが動物園を相手取って賠償請求の裁判を起こす。彼女は、生後間もない頃から手話を学び、その知力は人間の高校生並みだとされる。圧倒的に不利な状況を覆し、ローズは勝利をつかめるか? 原告側代理人は、傲岸不遜を絵に描いたような、負け知らずの辣腕若手弁護士ダニエル。
……と、ここだけとりだせばユニークなリーガルサスペンスだが、物語の本質は、「人間並みの知性(言語能力)と感情を持って人間と対話できる存在をどう扱うべきか?」というSF的・哲学的な問いにある。実際、前半は、人間の社会とゴリラの社会のはざまで生きるローズの日常がリアルに描かれる。
手話ができるゴリラといえば、二〇一八年に四十六歳で死んだ雌のローランドゴリラ、ココが有名だ。本書の中で言及される映画『コンゴ』(マイクル・クライトン『失われた黄金都市』が原作)にも、手話ができるゴリラ、エイミーが登場するが、たぶんココがモデルだろう。ココは子猫をペットのようにかわいがり、死の概念を理解していたとも言われるが、ほんとうのところはよくわからない。
人間の定義をめぐって法廷で争う小説の先例には、ヴェルコール『人獣裁判』(一九五〇年)がある。人類進化のミッシングリンクを求めてニューギニア奥地に向かった調査隊が、未知の霊長類パラントロプス(通称トロピ族)を発見。彼らを安価な労働力として使おうとする者もいる一方、主人公はトロピ族の雌と交わって子どもを産ませ、その子を自分の手で殺すことで〝殺人犯″として法廷に立つ……。
もっとも、小説的に『ゴリラ裁判の日』に近いのは、アイザック・アシモフの短編「バイセンテニアル・マン」(映画『アンドリューNDR114』の原作)かもしれない。こちらは、製造から百五十年を超えたロボットが、自分が人間だと認めてもらうために裁判を起こす。
それらの前例と比べて、本書のゴリラ裁判ははるかにハードルが高い。いったいどんなロジックでゴリラ殺しが〝殺人″だと陪審員に認めさせて勝訴できるのか? ツッコミどころは無数にあるが、ユーモラスな語り口と意外性満点の展開で(まさか、ローズが******になるとは!)、読んでいる間は疑問を抱かせない。意欲あふれる堂々のデビュー作だ。