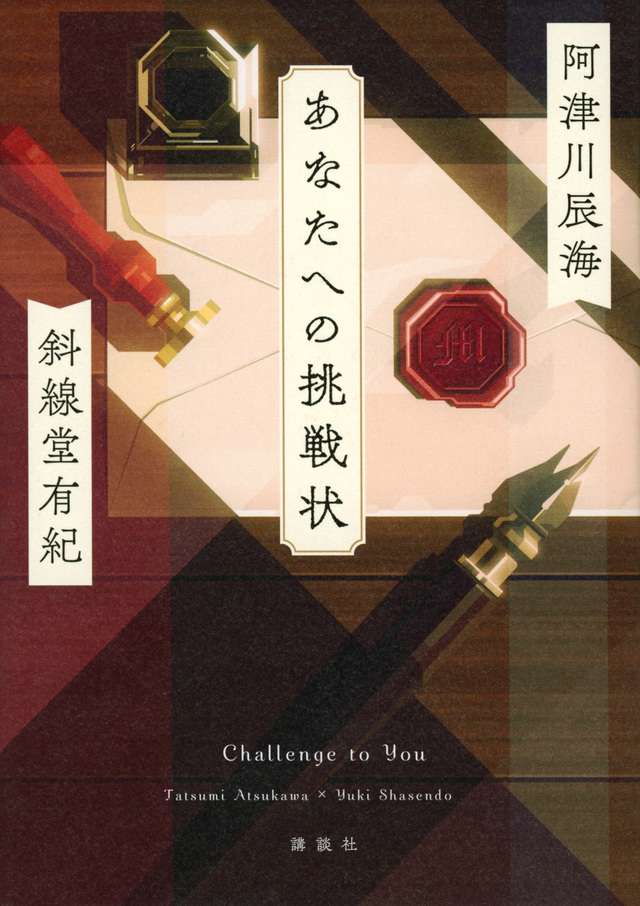三月*日
文字数 5,474文字

1日1冊、3年で1,000冊の本を読み、月産25万字を執筆し続ける小説家・斜線堂有紀。
謎めいた日常はどのようなものなのか――
その一端が今ここに明かされる。
毎月第一・第三月曜日、夕方17時に更新!
夕暮れどきを彩る漆黒の光・”オールナイト”読書日記が、本日も始まる。
前回の日記はこちら
三月*日
『回樹』のサイン本を作りに早川書房へ行く。
道すがら、ペ・ミョンフン『タワー』を読んだ。これは674階建ての巨大タワー国家・ビーンスタークを舞台とした摩天楼エンタテインメント小説である。奇抜な構造の特殊国家ということで、勝手にディストピア小説だと思っていたのだが、実はこのビーンスタークは問題が多いもののなかなか住みよく、周辺住民からは移住を望まれるほどの場所なのだ。
674階もあり人50万人もの人間が暮らすビーンスタークがほどよく良い場所として成立しているのは、ここに住む人々が不完全でかつ優しいからである。「どんな場所でも住む人によって様変わりする」というのがこの作品の裏テーマであるかのように、この奇怪で優しい社会がなんとなく続いていく様が描かれている。
特に「タクラマカン配達事故」に出てくる青いポストの仕組みは、ビーンスタークの住人でなければ成立しないものでユニークだ。けれど、この優しさは恐らく、外の住人達よりもビーンスタークの住人達の方が「余裕」だからなのだろうとも思う。彼らはある程度恵まれた地位におり、それが故に忍び寄る不穏やちょっとした事件を流しながら生きることが出来るのだ。そのシビアな温度感も含め、奇妙な味の短篇集である。個人的に好きなところは、作中に出てきた小説や資料が巻末に載っているところだ。これにより、世界のどこかにあるかもしれないビーンスタークを感じることが出来るのだ。
さて、サイン本作成だ。優しい営業部の方々は「いっぱいサインさせちゃってすいません」などと言ってこちらを労ってくれるけれど、私からしたら「こんなにサインさせて頂いて良いんですか」という気持ちだ。もうすっかり有名になった話だけれど、サイン本というものは返本が出来ない。つまり書店さんが買い切ってくださらないといけないのだ。即ち、サイン本というのは仕入れるのに少々のリスクがあり代物なのである。
仕入れるのに少々のリスクがあるものを、営業部の人は売り込まなければならない……。そう思ってしまって、サイン本を作る時はいつも申し訳無さとありがたさでいっぱいだ。何の時に一番気合いが入るかは人それぞれだろうけれど、私はサイン本作成の時に一番「仕事をしなければ……」と思う。そうして作った沢山のサイン本、どうか色んな人に手に取ってもらえたらいいんだけれど……と願ってやまない。
三月○日
MRC(※編集部注:メフィストリーダーズクラブの略。オトクな特典たくさん!)のミステリーカレンダーに自分の誕生日が載っていた。四月一日のところにどんと載せられた「斜線堂有紀誕生」の言葉に、嬉しくも恥ずかしい。というわけで、誕生日である。ついこの間まで大学生だったような気分なのに、気づけば普通に大人だ。(ここで初出情報だが、実は斜線堂有紀は大学を一留ではなく二留しているので、本当についこの間まで大学生だった。周りの友人も後輩も全員先に卒業しているので、二留したことがバレなかったのである。これ読んだ友人達、びっくりしたかな?)
自分に何か誕生日プレゼントでも買おうかなあと辺りをうろついていると、懐かしいものを見つけた。なかえよしを・上野紀子の絵本『ねずみくんのチョッキ』である。小さい頃に大好きだった絵本が街中の雑貨店で売られているだと!? と驚いたら、なんと今限定で『ねずみくんのチョッキ』のグッズが売られているというのだ。絵本のグッズってあるんだ? と思ったが、よく考えたらミッフィーなどもその枠なんだな……。『ねないこだれだ』のグッズもあることだし……。
それにしても『ねずみくんのチョッキ』は渋い。
『ねずみくんのチョッキ』はなかなかショッキングな物語である。
ある日、ねずみくんはお母さんに赤いチョッキを編んでもらう。そのチョッキを大層気に入ったねずみくんは色んな動物たちに見せに行くのだが、あまりに素敵なチョッキである故に、みんなに「貸して」と言われ、ねずみくんのチョッキはどんどん又貸しされていってしまう。ねずみくんと明らかにサイズの違うライオンや馬、果てはゾウにまでチョッキが貸された結果、ねずみくんの大好きなチョッキは伸びて着られなくなってしまうのだ……。
どういう話なんだ。
ゾウが自分のチョッキを着ているのを見つけた時のねずみくんのセリフは「うわーぼくのチョッキだ!」である。この時のネズミくんの目は血走り、身体は飛び上がっている。そりゃあそうなる。
それを見た私は、強い衝撃を受けた。伸びてしまったチョッキを引きずってとぼとぼと帰るねずみくんを食い入るように見つめ、世の恐ろしさに震えた。一応、この物語にはあっという救いのサプライズがあるにはあるのだが、そんなものは入ってこなかった。ねずみくんのチョッキが着られなくなったことだけが重要なのだ!!!!!
この絵本を読んだ時、私はねずみくんが愛おしくて悲しくてたまらなかった。私は昔から、誰かの大事にしているものが壊される描写に弱いのだが、その原点は『ねずみくんのチョッキ』なのではないかと思う。小さい頃の私は「多分、この本は『本当に大切なものは人に見せてはいけないんだ』ということを伝えたいのだろう」と救いの無い解釈をしていたのだが。
その『ねずみくんのチョッキ』が今こうしてグッズになり、同じように大人になった人達の財布を緩めているのだなあ、としみじみ思った私は、件の絵本とねずみくんのポーチを購入した。自分への誕生日プレゼントで半ばトラウマでもあるものと向き合うのだなあ、と思いつつも、何年経ってもシュールでおかしいこの絵本で久しぶりに笑った。
三月☆日
『新潮2023.4』の特集(言論は自由か? 戦前を生きる私たちの想像力)に寄せられた村田沙耶香「おろか」を読む。四十を少し越えた年の語り手である梢は、ある日虫生瑠璃子という中学の頃の同級生から「久しぶりにたえを展示する」という連絡を受ける。瑠璃子は実の妹・たえの考え方から人生までを全てコントロールすることによって、彼女を作品と仕立て上げている人間だった。梢は一時期、たえの『制作』に加担していた過去がある。年を経てなおも続けられた『制作』の果てにあるものを、梢は今になって目の当たりにさせられることになるのだった。
さて、制作というからには当然制作意図があるもので、虫生たえの制作コンセプトは以下の通りだ。
「この人間には人間のおろかさ全てが宿っています。どうぞご自由に対話し、おろかさを味わい、お楽しみください。」
見ている人間を平静ではいられなくするこのキャプションから、じわじわとたえの『制作』に対する薄気味悪さが炙り出される。ただでさえ『人間』を『制作』するというテーマには、こちらをざわつかせるものがあるというのに、畳み掛けるように彼女の制作意図が明かされる時、読者はこの短篇が何の特集に寄せられたものかを改めて考えさせられることとなる。それにしても、相変わらず村田先生はこちらの倫理や考えを揺さぶってくる物語を描くのが上手い、と心の中から悔しい気持ちになった。最後の一文まで、この短篇は一貫し続けている。
この短篇の面白さを受けて、読んでいなかった『絶縁』を読む。これはタイトル通り「絶縁」をテーマに、アジアの気鋭の作家9名が短編を書き下ろしたアンソロジーである。ここには村田沙耶香「無」が寄稿されている。これは、若者達の間で突然〝無〟がブームとなり、至る所で〝無街〟が建設されることに相成った、という物語だ。無を目指す若者達は、自分の中から出来るだけのものを排出しようとする。感情も今までの記憶も、なるべく無かったことにして過ごすのだ。親世代からは、当然ながらこの〝無〟ブームが理解されない。
この短篇もまた、意図を持って人間を作り上げる小説で、「おろか」と重なる部分が面白い。だが、若者達が〝無〟になろうとするのは、確固たる信念の結果というよりは「ブームだから」という受動的なものだ。与えられたブーム自体は奇妙で恐ろしいのに、それを形作るものは普遍的で誰でも理解が出来る安直さだ。一方「おろか」では、その根にあるものへの理解がまるで出来ない。この差違が違った読み味を生み出しているのだと思う。
『絶縁』では大好きなチョン・セランがそのまま「絶縁」というタイトルの作品を寄稿していて、そちらもとても面白かった。これは別々の六人に手を出した男への処罰を巡ってそれぞれの考え方が浮き彫りになるという短篇で、絶縁というものが何故起こるのかを如実に表している。
話を新潮に戻すと、この号は舞城王太郎「恐怖は背骨になる。」も面白かった。母親の再婚相手が何故かだるまを怖がる……という話から始まった物語は、やがて語り手の心を揺さぶる小さな恐怖へと繋がっていく。一体これは何の物語なのだろう? と思わせておいて、なるほどこう締めるのかと思わされた一作だった。これは同作者の「秘密は花になる。」や「喜びは鳥になる。」に連なるゆるやかなシリーズなのではないかと思っているのだけど(タイトルが似通っていて同じ掲載誌なので)この三編に共通するのは、こうして日常に差し挟まれる恐怖に向き合っている点なのだろうか?
ともあれ『新潮2023.4』は面白いものばかり載っているのでおすすめですよ。
三月△日
とある仕事で参考にしようと思い、ヴィクトル・ユゴーの『ノートル=ダム・ド・パリ』を読んだ。かの有名なディズニー映画『ノートルダムの鐘』の原作である。小さい頃の私はあまり明るい話ではない『ノートルダムの鐘』が少し怖かったのだが(民衆が縛り付けたカジモドにトマトをぶつけるシーンが、子供が見るには純度100%の悪意で流石に慄いた覚えがある)それ以上に、焼き討ちや火炙りなど炎の恐怖が強調されている描写に強く心を惹かれて何度も観ていた。(幼い頃の私が人間って焼けるんだ……と衝撃を受けたのが『ノートルダムの鐘』を見た時と、桜井信夫・梶鮎太『おまえが魔女だ』を読んだ時である)
さておくとして、原作の『ノートル=ダム・ド・パリ』は当然ながらディズニー版とはまるで違う内容であった。ノートルダム大聖堂の前に捨てられていた醜い赤ん坊・カジモドは大聖堂の副司教であるフロロに拾われて、鐘撞きの仕事を担わされる。孤独を深めていくカジモドだったが、パリに現れた美しいジプシーの踊り子・エスメラルダと出会ったことで人生が大きく動いていく。
『ノートル=ダム・ド・パリ』とディズニー版で一番大きい差違だと思ったのは、カジモドが鐘撞きの仕事によって失聴し、他者と上手くコミュニケーションを取るのが難しくなっている点だと思う。カジモドはこれにより育ての親であるフロロとしか意思疎通が出来ず、周りから断絶している。カジモドの考えていることが誰もわからないから、周りはより一層彼を邪悪な怪物だとして扱う。心優しいエスメラルダはカジモドを庇ってはくれるものの、彼の容貌の醜さを結局は厭う。
ディズニー版でのカジモドは失聴しておらず、問題無く他人とコミュニケーションを取ることが出来る。その結果、エスメラルダとも言葉を交わし、その内面の美しさによって真の友人となれたのだった。
『ノートル=ダム・ド・パリ』でカジモドがコミュニケーションを取れないのはある種象徴的に描かれていて、この物語に出てくる登場人物の多くがコミュニケーション不全により不幸へと陥っていく。エスメラルダに思いを寄せながら、彼女と全く通じ合うことが出来ず、最悪の選択をしてしまうフロロ神父を筆頭に、妻子持ちの不貞な男に騙されてしまうエスメラルダ、婚約者がエスメラルダに惹かれていることを知り嫉妬の炎に焼かれるフルールなど、相手としっかりとコミュニケーションが取れていれば避けられた悲劇に見舞われている人間が少なくない。
だが、コミュニケーションというのは一人が頑張ったところでどうにかなるものではなく、片方が相手にまるで向き合う気の無い場合は全く成立のしないものなのだ。最終的に、この物語は極めて悲劇的な形で幕を閉じ、誰も幸せにはならない。それが故に、カジモドが迎えた結末が胸を打つのだが、言葉によって相手を理解し隔たりを無くしていくディズニー版を見ると、この大きな違いに苦しさを覚える。それにしても1831年の小説が今日も面白く読めるというのは凄い。
”これ読んだ友人達、びっくりしたかな?”
!?????!??
次回の更新は、4月17日(月)17時を予定しています。
Written by 斜線堂有紀
小説家。2016年、第23回電撃小説大賞にて“メディアワークス文庫賞”を受賞。受賞作『キネマ探偵カレイドミステリー』でデビュー。著作に『詐欺師は天使の顔をして』(講談社)、『恋に至る病』(メディアワークス文庫)、『ゴールデンタイムの消費期限』(祥伝社)などがある。2021年、『楽園とは探偵の不在なり』(早川書房)が本格ミステリ大賞にノミネートされ、注目を集める気鋭の書き手。