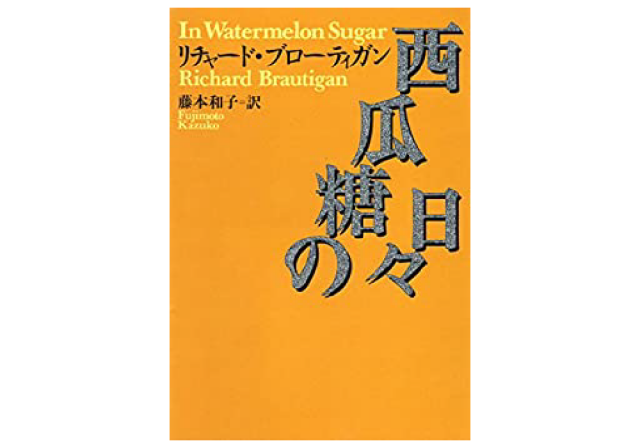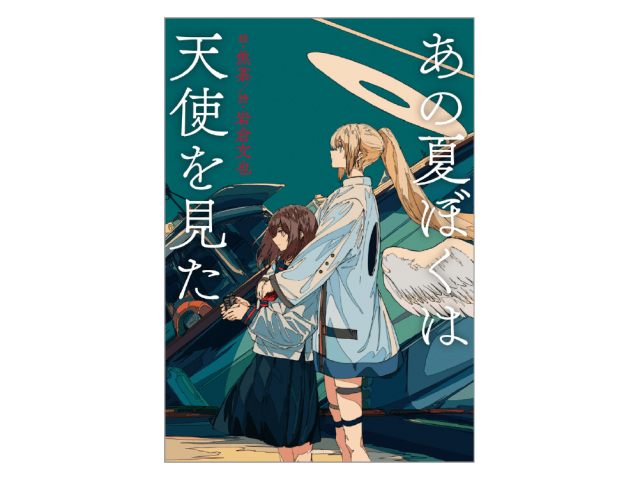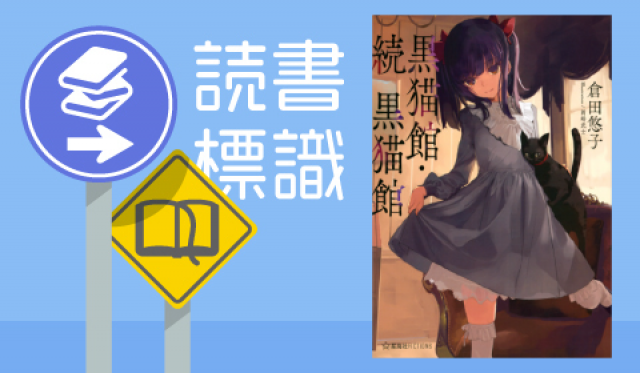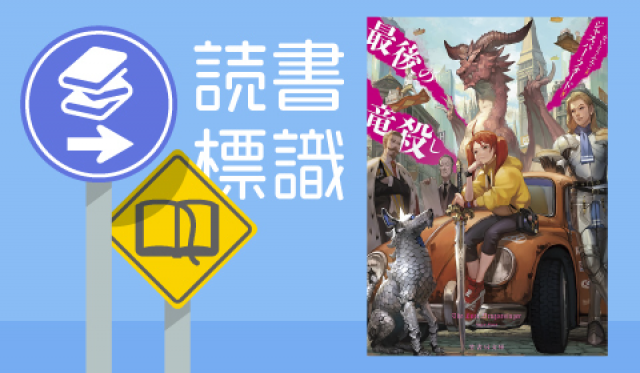『西瓜糖の日々』R・ブローティガン/もうだいじょうぶでした(岩倉文也)
文字数 1,953文字
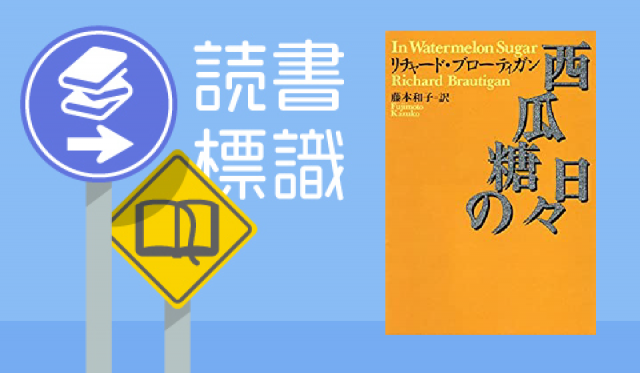
本を読むことは旅することに似ています。
この「読書標識」は旅するアナタを迷わせないためにある書評です。
今回は詩人の岩倉文也さんが、リチャード・ブローティガン『西瓜糖の日々』について語ってくれました。
ぼくはただ単純でありたいと思う。透き通った硝子かなんかのように、陽や月の光を通過させるだけの物質になりたいと思う。
それが無理ならせめて、なにも感じずに生きてゆきたい。
日に日に強まってゆくこうした思いに応えてくれるものはこの世界には少ない。単純であるということはそれ自体で異常なのだ。
わずかに詩や短歌、俳句と言った言語芸術の数少ない結晶のみが、ぼくの心の渇きを癒してくれる。ぼくは、詩というものの本質は世界の単純さの発見にあると思う。
だからぼくはいつからか小説を読まなくなった。ぼくはきっと、小説が内包する世界の複雑さに耐えられなくなったのだ。
透明でありたい。単純でありたい。思想も、意味も、歴史も、主題も、ぼくは欲しくない。ぼくはそれらを敬遠し、避けて通った。
そうしているうちに、ふと、一冊の本がぼくの前に現れた。いいや、最初からそれはぼくの部屋にあったのだ。
『西瓜糖の日々』。この美しいタイトルの本は本棚の片隅にねむっていた。本との出会いはいつも再帰的だ。ぼくはこの本をいつ手に入れたのか憶えていなかった。
そう、ぼくは遠くにいる。とても遠くに。
この本に描かれた西瓜糖の世界に対して、読者はつねに異邦人でいるほかはない。登場人物たちの行動原理も、この世界の在りようも、ほとんど理解することはできないだろう。かれらは「アイデス」という場所に住み、その外側には「忘れられた世界」が広がっている。あらゆるものは西瓜糖でつくられ、曜日によって太陽はその色を変える。かつては人語を喋る虎たちが「アイデス」を脅かしたが、今では一頭残らず殺されてしまった。
こうした記述になんらかの寓意や象徴を読み取ろうとするのは不毛だろう。西瓜糖の世界においては、全てはただ〝そうある〟のである。
ぼくはこの本を一度読み、続けてもう一度読んだ。ぼくがまず感じたのは、なにか茫漠とした影の通過である。つぎに感じたのは、ぼくの内心が全くからっぽになってしまっているという、心地よい実感だった。
なぜだろうか? と考える。その秘密はどこにあるのだろう。
思うに、本書に描かれた世界の手触りにその秘密はあるのではないか。
西瓜糖の世界は、あるいはそこに暮らす住民は、みなおよそ子供じみている。妖精的、と言ってもいいのかもしれない。残酷で、純粋で、無関心。
しかし同時に、かれらはひどく年寄じみてもいる。なにが起きても動じない。仕方がなかったんだと、すぐに納得してしまう。
その最たる例は、幼少期に主人公が両親を虎たちに喰い殺されたときの反応だ。
主人公は両親を殺した虎たちにこう言う。
「算数を手伝ってほしい」
主人公は算数が苦手なのだ。そうして算数を教えてもらい、虎たちがすっかり両親を喰い尽くして帰っていこうとすると、
「算数教えてくれてありがとう」
と言って、虎たちと別れるのである。
これがぼくの言う〝手触り〟だ。かれらの生きている世界の、驚くべき単純さ。それは、透明に輝く水晶のようにぼくを魅惑する。ここでは、残酷さまでもが清涼なのだ。
ページをめくる度に、ぼくのなかに空虚が広がってゆく。空虚とは、なんと甘美なものだろう。ぼくは読みながら、なにも考えない。どんな残酷も、純粋も、かなしみも、等しく西瓜糖の世界では重さを持たずに、ただ遠くへと流れ去ってゆく。
『西瓜糖の日々』を読むことで、ぼくたちはある世界を回復する。ぼくたちがいずれ経験するであろう、そしていつか経験したことのある単純な世界。
そこでぼくたちは人間のような、しかし人間とは決定的に異なる奇妙な生物として、やさしくしずかに暮らすのだ。
夜明けだと勘違いしたのだろうか、西瓜糖の掛け蒲団をかぶって、ポーリーンが寝言をいった。散歩に出かけた小羊の話をしていた。
「小羊は花の中に坐ったのです」とかの女はいった。「小羊は、もうだいじょうぶでした」それが物語の結末だった。
詩人。1998年福島生まれ。2017年、毎日歌壇賞の最優秀作品に選出。2018年「ユリイカの新人」受賞。また、同年『詩と思想』読者投稿欄最優秀作品にも選出される。代表作に『傾いた夜空の下で』(青土社)、『あの夏ぼくは天使を見た』(KADOKAWA)等。
Twitter:@fumiya_iwakura