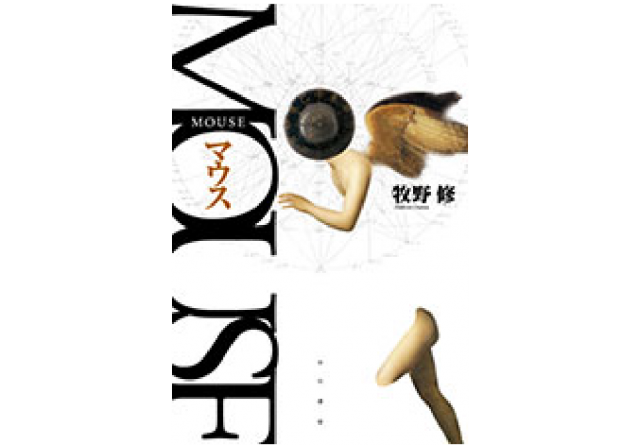『MOUSE』牧野修/役立たずだけど気持ちいい(岩倉文也)
文字数 2,373文字

次に読む本を教えてくれる書評連載『読書標識』。
月曜更新担当は作家の岩倉文也さんです。
今回は牧野修『MOUSE』(ハヤカワ文庫)をご紹介していただきました!
詩人。1998年福島生まれ。2017年、毎日歌壇賞の最優秀作品に選出。2018年「ユリイカの新人」受賞。また、同年『詩と思想』読者投稿欄最優秀作品にも選出される。代表作に『傾いた夜空の下で』(青土社)、『あの夏ぼくは天使を見た』(KADOKAWA)等。
Twitter:@fumiya_iwakura
そういえば最近、というより東京に来てから、ぼくはあまり詩集を読まなくなった。たぶん上京してから十冊と読んではいないのではなかろうか。詩が嫌いになったわけではない。むしろ詩を感じるセンサーはかつてより鋭敏になったくらいだ。
ではなぜなのだろう? と考えるに、ぼくは恐らく詩集の持つ退屈さに嫌気が差してしまったのだ。詩集の持つ退屈さとは、開けば必ず詩が載っているという部分にある。何を当然な、と思われるかもしれない。しかしぼくにとって詩を楽しむとは詩を発見することと同義であり、詩集というジャンルからは、あらかじめその楽しみが損なわれている。
急いで付け加えるが、ぼくもかつては、詩集を読むことそれ自体にこの上ない喜びを感じていた。それはこの世界から「詩集」を見つけ出したという喜びである。詩がたくさん載っている本がある、という発見それ自体が驚異だったのだ。
だがやがて詩も生活の一部となり、詩集は退屈な剥製となる。それでぼくは別ジャンルへの越境をはじめた。アニメ、漫画、イラストレーション、美少女ゲーム、小説……。そういったものの中でふときらめく「詩」を見つけ出し翫賞する。それがぼくのささやかな楽しみとなった。
詩的、とは何かを考える。ぼくは詩的なものが好きだ。むしろそれ以外に興味はない。
牧野修によるSF小説『MOUSE』は詩的である。詩的とはきっと、美しい無意味を見つけた際に人が覚える、どこか懐かしいがしかし鋭い感慨のことだ。
本作の舞台となる廃墟島「ネバーランド」は、十八歳以上の大人立ち入り禁止の楽園だ。社会から隔絶されたその地で、自らを〈マウス〉と呼ぶ子供たちは特殊な装置を用い常時体内にドラッグを注入しながら生活を送っている。鎮静剤、幻覚剤、興奮剤、その他さまざまなドラッグのカクテルを摂取し続けている彼らは、主観と客観、夢と現実が入り混じる妄想世界に生きていた。彼らは誰ひとりとして同じ現実を見てはいない。だからお互いの世界を共有するただそれだけのためにも、意識を同調させる儀式が必要となる。
「それじゃ始めるよ……月」
「月の光り」
「爪」
「爪で掻く金属の皮膚」
「剣、剣の上」
「剣の上に乗る裸足の脚の先」
(中略)
「裸足の人形の土でできた十二匹の鼠」
「青く塗られた人形の前にひざまづき歌う十二人の水兵」
「水兵の青く塗られた唇に挟まれた薄荷煙草の……」
「煙草の先の炎に眼をつけ世界を見る柔らかな少年……」
「少年の海は疲れた魚の群に頭をつけて……」
このようにお互いに言葉を掛けあうことで、意識を同調させてゆく。しかしこれを見ていると、何だかぼくはツイッターを思い出す。お互いが同じものを見ている、と信じるためには、同じ言葉が、同じ語彙体系が、必要なのだ。ぼくらは慎重に言葉のチューニングを合わせる。ぎこちなくなってはいけない。あくまで詩のように軽やかでなくては……。
意味と無意味。現実と幻想。それらを辛うじて繋ぎ合わせているものが、言葉だ。本作では、それらの境界が言葉によって攪拌されてゆく。〈マウス〉たちの間では、発された言葉が、幻想が、たちまち現実となって襲いかかる。ドラッグによって歪められた認識を持つ彼らにとって、認識に影響を及ぼす言葉こそが武器なのだ。彼らはそんな言葉の力を駆使し、夜ごと抗争を繰り広げている。
ここで読者は思うだろう。つまり彼らは、妄想の中でのみ異能バトルを行っているのか、と。それは半分正解であり、半分間違いだ。確かに〈マウス〉たちは実際に超能力を持っている訳ではない。全てはドラッグによる幻覚あってのことだ。いくら相手を燃やそうと、巨人になろうと、それらはみな幻覚の中のみでの出来事である、と一応は言える。しかし本作を読んでいると、そうした区別に果たして意味があるのか疑わしく思えてくる。
そもそも登場人物のほとんどがジャンキーの子供たちであり、ここまでが現実、ここからは幻想といった分かりやすい区別は最初から存在しない。全てが混然一体、絢爛たるイメージに取り巻かれながら、読者は先へ先へと押し流されてゆく。
そして気づくのだ、妄想に外側などないということを。
「役立たずだけど気持ちいい」とは、本作のあらゆる側面を端的に表した言葉だ。〈マウス〉たちは社会にとってなんの役にも立たない。ドラッグがそうであるように。詩がそうであるように。けれど彼らは、どこか社会の、そして人間の本質に繋がっている。
妄想が現実を形作る。妄想は妄想でありながら、徐々に現実を侵食し、現実と区別がつかないものとなる。それは、恐ろしいことだ。しかし同時に、たとえようもなく魅力的だ。子供たちによる頽廃の楽園を描くことによって、本作はそのことを、何よりも雄弁に語っている。