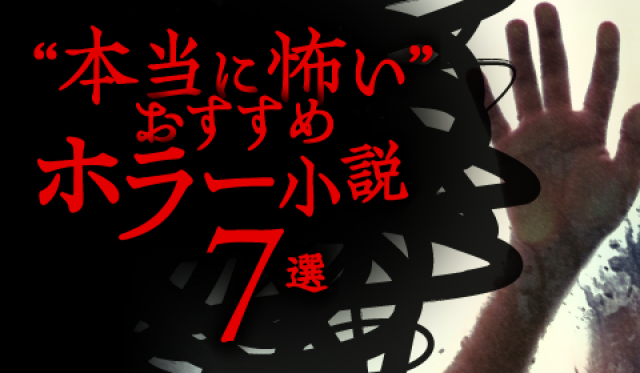『紙の動物園』『もののあはれ』ケン・リュウ/メメント・モリのその先へ(岩倉文也)
文字数 2,415文字

本を読むことは旅することに似ています。
この「読書標識」は旅するアナタを迷わせないためにある書評です。
今回は詩人の岩倉文也さんが、ケン・リュウの『紙の動物園』『もののあはれ』の2作について語ってくれました。
最近ぼくはよく右の手のひらを体の中心に押し当てて、心臓の鼓動を確かめる。時にはなんの手ごたえもなく、時には明確な鼓動が手のひらに伝わってくる。
ぼくは自分が生きていることが不思議でならない。それと同時に、自分がいつ死んでもおかしくないという考えがつねにぼくを支配している。
そう言えばぼくが最初に詩に興味を持ったのは、それが死を超越しているように感じられたからだ。詩でならば、まったく未知で、不気味で、恐ろしい死というものを、人間にも受け入れ可能な甘美な、むしろ望ましいものとして描くことができる。死をひたすら嫌悪していたかつてのぼくは、そうした点に詩の根源的な魅力を感じていた。
いまぼくのテーブルの上には二冊の本が置かれている。SF作家ケン・リュウの短編集『紙の動物園』と『もののあはれ』。この二冊の文庫本は、もともと一冊だった単行本が文庫化に際して二冊に分かれたものらしい。
どの短編を読んでいても、まず小説としての構成の完璧さ、その非の打ちどころのない完成度に圧倒される。ぼくはSFというものをほとんど嗜まない人間であるが、テーマ設定から主題の展開の仕方まで、どれを取っても一級であることが即座に了解できる小説というのも珍しい。画家の描いた精巧なデッサンのような、有無を言わせぬ明晰さ。
だがぼくの常として、均衡よりはむしろ偏りに目を向けてしまう。全体より部分に、畢竟たった一文のなかにその書物の持つ魅力の全部を感じてしまう。
ぼくが今回この二冊の本に見たのは「死」だった。「死」とどう向き合うか。あるいは感じるか。それが多様なSF的テーマと絡み合いつつ、繰りかえし語られているように思えてならなかった。
「紙の動物園」で描かれているのは、愛されるということへの、人間の致命的な鈍感さだ。深い愛情。ほんものの愛情というものがもしあれば、それはきっと、目には見えないし、感じることも難しいものだろう。愛が純一であればあるほど、それは押し付けがましさを失い、透明になってゆく。この作品では、母親から息子への愛の報われなさ、そのひりつくような痛みの感覚が、緊密で隙のない構成のもと描き出されている。
中国出身で英語を満足に扱えない母親は、しかし折り紙の動物に命を与える不思議な力を持っていた。母親の息が吹き込まれた折り紙の動物は、まるで生きているかのように動き出し、主人公の良き遊び相手となる。
そうした美しい子供時代の情景と、成長した主人公の母親への冷たい態度が好対照をなしつつ、この作品はしずかに悲痛な結末へと近づいてゆく。
SFと言うよりはファンタジーに属するであろう本作は、いつも手遅れである愛の本質を余すところなくぼくらに伝えてくれる。
次にもう一つの表題作である「もののあはれ」について語らねばならない。実のところ、ぼくが普段は手を出さないSF小説を読もうと思ったのは、この「もののあはれ」を知人に勧めてもらったことがきっかけだった。
「もののあはれ」は原題も「Mono no Aware」であり、日本人が主人公の作品だ。
巨大小惑星〈鉄槌〉が地球に迫るなか、主人公とその父はある晴れた夕暮れ、一緒に散歩に出かける。俳句や漢詩を交えて父子が語り合うこの場面は、沁み透るような感動に満ちていて印象的だ。
〝もののあはれ〟とはつまり死への感受性だ。万物が死してゆくということに開かれた心のありよう。本作が語っているのは、死が単なる終わりではなく、次の生へと開かれてゆくという感覚である。その感覚が日本的なるものの核として描かれている。
日本の精神の本質がそこにあるのかぼくには分からない。だが少なくとも『紙の動物園』そして『もののあはれ』両二冊の短編集を通して、「死」というものが生者を衝き動かし、未来へ導くものとして描かれていることは確かである。
『もののあはれ』所収の「円弧(アーク)」における次の台詞は、端的にそのことを象徴している。
「あなたに死んでほしくない。死が生に意味を与えるというのは神話だわ」
キャシーが一度も会ったことのない父親とそっくりのことを口にできたのは謎だった。
「もしそれが神話なら、それはわたしが信じている神話なの」

『紙の動物園』ケン・リュウ/古沢嘉通編・訳(ハヤカワ文庫)&『もののあはれ』ケン・リュウ/古沢嘉通編・訳(ハヤカワ文庫)
詩人。1998年福島生まれ。2017年、毎日歌壇賞の最優秀作品に選出。2018年「ユリイカの新人」受賞。また、同年『詩と思想』読者投稿欄最優秀作品にも選出される。代表作に『傾いた夜空の下で』(青土社)、『あの夏ぼくは天使を見た』(KADOKAWA)等。
Twitter:@fumiya_iwakura