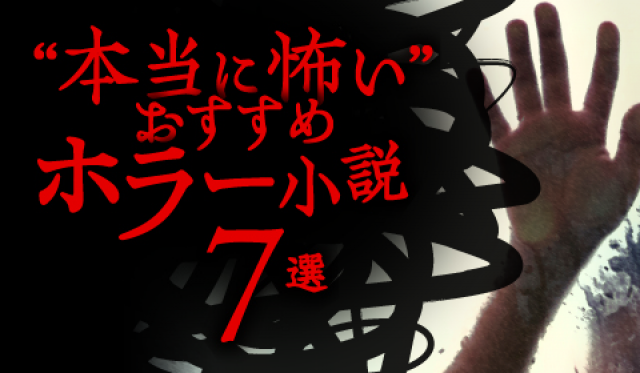『霧が晴れた時』小松左京/恐怖小説の見本市(岩倉)
文字数 2,686文字

次に読む本を教えてくれる書評連載『読書標識』。
月曜更新担当は作家の岩倉文也さんです。
今回は小松左京『霧が晴れた時』(角川ホラー文庫)をご紹介していただきました!
詩人。1998年福島生まれ。2017年、毎日歌壇賞の最優秀作品に選出。2018年「ユリイカの新人」受賞。また、同年『詩と思想』読者投稿欄最優秀作品にも選出される。代表作に『傾いた夜空の下で』(青土社)、『あの夏ぼくは天使を見た』(KADOKAWA)等。
Twitter:@fumiya_iwakura
それにしても、ぼくはホラーを売りにした作品を楽しめたことがない。と言うか、興味を持てたことすらほとんどない。かなり幼かった頃は、テレビでやる心霊番組などを純粋に怖れ、楽しんでいた記憶があるのだが、それはずっと遠い過去の記憶だ。
ではいつごろからホラーを楽しめなくなったのかと考えるに、あの震災のことが脳裏にちらつく。つまりは、何の意味も、呪いも、因縁もなく、誰が悪いわけでもないのに突然襲ってくる冷徹な自然災害こそが、ぼくにとっては何よりも恐ろしい。それに比べれば、巷にあふれるホラー作品などちっとも怖くはなく、刺激的でもなんでもない、と無意識に考えていたらしいのである。
昔みたテレビ番組のことを思い出す。いつのことだったか定かではないが、それは阪神淡路大震災を特集した番組だった。そこでは一人の若者の夢や希望にあふれた毎日が再現ドラマによって描かれる。だがある朝、ふいに地震がきてその若者は死んでしまう。たぶん「震災で亡くなった沢山の人達にも、それぞれの夢や希望、生活があった」というメッセージを伝え、死者を追悼するといった趣旨の番組だったのだろうとは思うが、ぼくにはその、あまりに不条理な死の模様が恐ろしく、ほとんどトラウマのようになってしまった。
だから、と言うのも変かもしれないが、ホラー作品によく見られる日常が徐々に壊れてゆき、最後には──という物語構造自体に、どこか違和感を覚えてしまう。ぼくにとって恐怖とは、脈絡なく全てを奪われることであり、そこには物語もなにも存在しえない。恐怖は物語のようには段階を踏まずに、一足飛びにやってくる。
まあ、くどくどと述べてみたところで、要するに食わず嫌いである。なので今回、本欄の担当編集さんに送ってもらったままずっとほったらかしにしてあった小松左京の自選恐怖小説集『霧が晴れた時』を読んでみることにした。
恐怖小説とは言っても、本書には様々なジャンルの作品が収められている。勿論みなある種の「恐怖」を題材にしているわけだが、たとえば冒頭の一編「すぐそこ」には、五〇年代の田舎には残存していた自然そのものの不気味さ、草深い道を歩くときの心細さが、山からいつまでたっても脱け出すことのできない主人公を通して象徴的に描かれている。
かと思えば「くだんのはは」では、著者の実体験を反映していると思しき戦時中の兵庫を舞台に物語は展開される。大空襲によって家を焼かれてしまった主人公は、かつての家政婦・お咲が現在勤めている屋敷に仮寓することになるのだが、そこでは夜な夜なだれかの泣く声が聞こえ、さらには屋敷の主人である「おばさん」は、なぜか戦争の経過を予言するような言葉を度々口にする。そして予言通り終戦を迎えた主人公は、最後に「あるもの」を見てしまう。
本作は妖怪「件(くだん)」がモチーフとなっているが、そうした都市伝説についてまるで実体験のような筆致で語ってゆき、私的な体験とフィクショナルな怪談とを接続させる手法などは、古典的でありつつ著者の抜群の筆力もあいまって非常に魅力的である。
本書にはまた、SF的な趣向を持った作品も収められている。以前「世にも奇妙な物語」の原作となったこともある「影が重なる時」がその代表格である。本作はある日を境に、特定の地域に住む人間にだけ、自分にしか見えない幽霊が出現する、というお話で、その幽霊は自分とまったく同じ姿で、ひとところに塑像のように固まっている。各人が、自分にしか見えない、自分自身の幽霊を見るのである。ではその幽霊の正体とは何か?
藤子・F・不二雄のSF短編漫画を髣髴とさせる読み味をもつ本作は、最初怪談だと思われたものがふいにSFに反転する際の驚きと戦慄を存分に味わわせてくれる快作だ。
では本書の中でいちばん好きな作品は何かと問われれば、ぼくは表題作である「霧が晴れた時」を挙げるだろう。
本作はごく短い作品であり、筋書きも単純だ。主人公は妻とふたりの子供を連れて山にピクニックに出かける。山を登っていると深い霧が立ちこめてきて、それが晴れると妻と娘は忽然と姿を消している。主人公は息子を連れて慌てて町へとおりるが、町にはだれもいない。電車も線路の途中で無人のまま停まっている。主人公はこの世界の全ての人間が消えてしまったのではないかと不安に駆られながら、息子を乗せ闇雲に車を走らせる……。という所で本作は終わっている。霧はなんの理屈も説明もないままに、ただ不条理として主人公から大切なものを、いや世界そのものを奪い去ってしまう。
ぼくにはこの小説の意味のなさ、ある日すべてをなくしてしまうのではないかという純粋な恐怖のみが結晶したような単純で簡潔な筋の運びが、この上なく美しいものに思える。それに、本作はぼくの根源的な恐怖とも近いところにある作品だ。
しかし、恐怖小説の見本市とも呼べそうな本書を通読して思ったのは、ホラーとは必ずしも「恐怖」といった刺激を受け取るために読むものではないし、別に「怖い」と感じなくとも作品は楽しめるということだ。ホラー小説、殊に短編においてはほぼ明確な「型」が存在する。それは、日常から段階を踏んで異常へと移行し、異常性が極点に達したところで断ち切られるように物語が終わる、というものである。その殆どがバッドエンドな訳だが、それに至るまでの構成のあざやかさ、また如何にリアリティを担保したまま怪異を描くのかなど、見るべき点は数多い。
とこうして書いてみると本当にホラーが楽しめているのかやはり疑問ではあるが、しかしホラーであるとかないとかを脇に置くとしても本書は読み物として無類に面白く、かつ繊細で具象的な小松左京の文章は目を通しているだけで心地よい。
全てを忘れ、読書の快楽そのものとなって読み耽りたい一冊である。
★こちらの記事もおすすめ