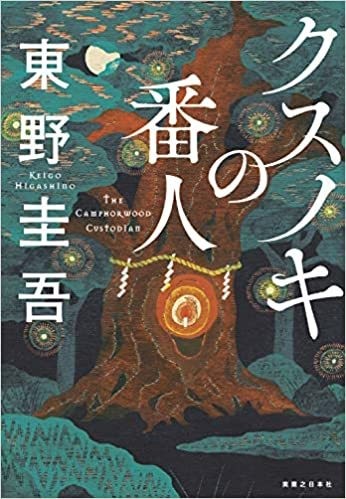〈7月9日〉 東野圭吾
文字数 2,413文字
みんなの顔を
朝、目が覚めるとカーテンの隙間から薄日が差していた。ベッドから身体を起こし、テーブルに置いた腕時計を見ると午前七時を過ぎていたので、体温計を腋に挟んだ。間もなく、ピピッと電子音が鳴る。今の体温計は本当に計測時間が短い。
『37.5』という数字を見て、がっかりする。
朝食後、担当の医師が入ってきた。ブルーの防護服に身を包み、マスクとゴーグルを付け、ビニールの帽子を被っている。この医師の素顔を見る日は来るのだろうか。
「残念ながら、昨日の検査結果も陽性でした」
申し訳なさそうにいった医師の言葉に、私は肩を落とした。「そうでしたか……」
医師は、私が紙に書き込んだ体温の数値をちらりと見てから、「では、今日もいいですか」と細長い棒を手にいった。その棒の名称は知らない。紙縒り、と心の中で呼んでいる。
「はい、お願いします」私は上を向いた。
医師は紙縒りを鼻の穴に突っ込んできた。喉の奥にまで達しているんじゃないかと思うほど深々と刺され、おまけにぐりぐりとかき混ぜられる感覚だ。痛くて辛くて涙が出そうになる。何度やっても慣れない。
ではまた明日、といって医師は出ていった。部屋を出る前に、防護服やらマスクやらをすべて段ボール箱に捨てていった。たったこれだけのために毎回使い捨てだ。
私は祈る。明日こそ良い結果が出ますように。『陰性』になっていますように。
妻が感染症の検査で陽性判定を受けたのは二十日ほど前だ。職場で感染したらしい。
彼女が入院した翌日、私も検査を受けるよう保健所から連絡があった。毎日顔を合わせているから濃厚接触者というわけだ。
まずいなと思いつつ受けてみたら、案の定、陽性だった。その翌日から、この病室にいる。完全隔離で家族にも友人にも会えなくなった。
感染症の自覚症状はない。咳は出ないし、息苦しさもない。
ただし体温は高い。しかし私の場合、そんなには気にならない。妻の感染がわからなければ、たぶん検査を受けることはなかっただろう。
通常、無症状ならば十日で退院できる。症状が出た人でも、快復後に二度続けて検査結果が陰性になるか、発症から十日が経過し、尚且つ快復後から七十二時間が経っていれば退院してよいとされている。
私の場合、すでに入院から十日以上が経っており、自分では快復していると思っている。だが微熱がネックになっていた。平熱に戻らないかぎり、快復とはいえないのだ。この熱が感染症によるものでないと証明するには、検査で陰性という結果を得る必要がある。
ところがどうしたわけか、なかなかそうならなかった。連日検査を受けるのだが、ことごとく結果は陽性だ。熱も下がらず、したがって退院できない。
早々に退院している妻にメールを出すのは日課だ。文面はずっと同じ。『今回の結果も陽性でした』、だ。
すぐに妻から電話がかかってきた。「残念だったわね。体調はどう?」
「ぼちぼちだ。相変わらず熱は少しあるけどな。今日も検査した」
そう、と妻は短く返事した。励ましの言葉など、虚しいだけだとわかっているのだろう。
だが翌朝、医師が大股で入ってくるのを見て、いい予感がした。マスクで見えないが、笑っているような気がしたのだ。
「陰性でした」待望の言葉だ。抑えた口調ではあったが、声に力強さがあった。
ありがとうございます、と私は頭を下げていた。大きなご褒美を貰った気分だった。
では早速、と医師が紙縒りを構えた。はい、と私は忠実な犬のように顎を上げた。
次の日、無事に二度目の陰性判定を得た。夕方、病院まで迎えに来てくれた妻は、私を見て涙を浮かべた。私も胸が熱くなった。人目がなければ抱き合っていたかもしれない。
タクシーで自宅に帰った。長年住み慣れた古い日本家屋だ。ようやく帰ってこられた。ところが玄関で靴を脱ぎ、一歩足を踏み出したところで、ふっと意識が遠のいた。
お爺ちゃん、お爺ちゃん──聞き覚えのある声で目が覚めた。
気づくと布団の上だった。「あっ、気がついたみたい」妻の声がいった。
ぼんやりとしていた視界が、少しずつはっきりしてきた。妻と娘夫妻、そして孫娘の顔が並んでいた。
「おう、みんなか」弱々しい声を出すのが精一杯だった。
「お爺ちゃん、退院おめでとう」小学校二年になった孫娘がいった。
「うん、ありがとう。みんなの顔を見られてよかった」
これでいつでも死ねる、と思った。
末期がんと宣告されて半年、自宅療養中の身だった。八十歳を過ぎているし、特に思い残すことはなかったが、死ぬ時には家族たちと一緒にいたかった。
私は布団から出した手を妻のほうに伸ばした。彼女は泣き顔になり、「病気をうつしてごめんなさい」といって手を握ってきた。
私はかぶりを振り、笑った。献身的に看病してくれた彼女に落ち度などない。
「手を握ったらいけないって先生がいってたよ」孫娘が口を尖らせた。
「いいんだよ」私は笑いかけた。愛する家族の手も握れずに、何が新しい生活様式だ。
強烈な眠気が襲ってきた。消えゆく意識の中で、これで葬式でも最後の別れをしてもらえるな、と思った。
東野圭吾(ひがしの・けいご)
1958年、大阪府生まれ。大阪府立大学卒業。1985年『放課後』で江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。1999年『秘密』で日本推理作家協会賞、2006年『容疑者Xの献身』で直木賞、本格ミステリ大賞、2012年『ナミヤ雑貨店の奇蹟』で中央公論文芸賞、2013年『夢幻花』で柴田錬三郎賞、2014年『祈りの幕が下りる時』で吉川英治文学賞を受賞。2019年、海外を含む出版界への貢献により、野間出版文化賞を受賞。最新刊は『クスノキの番人』。
【近著】
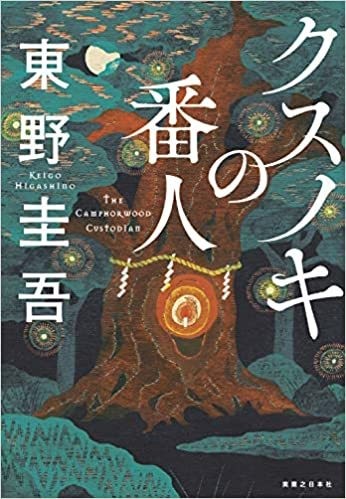
朝、目が覚めるとカーテンの隙間から薄日が差していた。ベッドから身体を起こし、テーブルに置いた腕時計を見ると午前七時を過ぎていたので、体温計を腋に挟んだ。間もなく、ピピッと電子音が鳴る。今の体温計は本当に計測時間が短い。
『37.5』という数字を見て、がっかりする。
朝食後、担当の医師が入ってきた。ブルーの防護服に身を包み、マスクとゴーグルを付け、ビニールの帽子を被っている。この医師の素顔を見る日は来るのだろうか。
「残念ながら、昨日の検査結果も陽性でした」
申し訳なさそうにいった医師の言葉に、私は肩を落とした。「そうでしたか……」
医師は、私が紙に書き込んだ体温の数値をちらりと見てから、「では、今日もいいですか」と細長い棒を手にいった。その棒の名称は知らない。紙縒り、と心の中で呼んでいる。
「はい、お願いします」私は上を向いた。
医師は紙縒りを鼻の穴に突っ込んできた。喉の奥にまで達しているんじゃないかと思うほど深々と刺され、おまけにぐりぐりとかき混ぜられる感覚だ。痛くて辛くて涙が出そうになる。何度やっても慣れない。
ではまた明日、といって医師は出ていった。部屋を出る前に、防護服やらマスクやらをすべて段ボール箱に捨てていった。たったこれだけのために毎回使い捨てだ。
私は祈る。明日こそ良い結果が出ますように。『陰性』になっていますように。
妻が感染症の検査で陽性判定を受けたのは二十日ほど前だ。職場で感染したらしい。
彼女が入院した翌日、私も検査を受けるよう保健所から連絡があった。毎日顔を合わせているから濃厚接触者というわけだ。
まずいなと思いつつ受けてみたら、案の定、陽性だった。その翌日から、この病室にいる。完全隔離で家族にも友人にも会えなくなった。
感染症の自覚症状はない。咳は出ないし、息苦しさもない。
ただし体温は高い。しかし私の場合、そんなには気にならない。妻の感染がわからなければ、たぶん検査を受けることはなかっただろう。
通常、無症状ならば十日で退院できる。症状が出た人でも、快復後に二度続けて検査結果が陰性になるか、発症から十日が経過し、尚且つ快復後から七十二時間が経っていれば退院してよいとされている。
私の場合、すでに入院から十日以上が経っており、自分では快復していると思っている。だが微熱がネックになっていた。平熱に戻らないかぎり、快復とはいえないのだ。この熱が感染症によるものでないと証明するには、検査で陰性という結果を得る必要がある。
ところがどうしたわけか、なかなかそうならなかった。連日検査を受けるのだが、ことごとく結果は陽性だ。熱も下がらず、したがって退院できない。
早々に退院している妻にメールを出すのは日課だ。文面はずっと同じ。『今回の結果も陽性でした』、だ。
すぐに妻から電話がかかってきた。「残念だったわね。体調はどう?」
「ぼちぼちだ。相変わらず熱は少しあるけどな。今日も検査した」
そう、と妻は短く返事した。励ましの言葉など、虚しいだけだとわかっているのだろう。
だが翌朝、医師が大股で入ってくるのを見て、いい予感がした。マスクで見えないが、笑っているような気がしたのだ。
「陰性でした」待望の言葉だ。抑えた口調ではあったが、声に力強さがあった。
ありがとうございます、と私は頭を下げていた。大きなご褒美を貰った気分だった。
では早速、と医師が紙縒りを構えた。はい、と私は忠実な犬のように顎を上げた。
次の日、無事に二度目の陰性判定を得た。夕方、病院まで迎えに来てくれた妻は、私を見て涙を浮かべた。私も胸が熱くなった。人目がなければ抱き合っていたかもしれない。
タクシーで自宅に帰った。長年住み慣れた古い日本家屋だ。ようやく帰ってこられた。ところが玄関で靴を脱ぎ、一歩足を踏み出したところで、ふっと意識が遠のいた。
お爺ちゃん、お爺ちゃん──聞き覚えのある声で目が覚めた。
気づくと布団の上だった。「あっ、気がついたみたい」妻の声がいった。
ぼんやりとしていた視界が、少しずつはっきりしてきた。妻と娘夫妻、そして孫娘の顔が並んでいた。
「おう、みんなか」弱々しい声を出すのが精一杯だった。
「お爺ちゃん、退院おめでとう」小学校二年になった孫娘がいった。
「うん、ありがとう。みんなの顔を見られてよかった」
これでいつでも死ねる、と思った。
末期がんと宣告されて半年、自宅療養中の身だった。八十歳を過ぎているし、特に思い残すことはなかったが、死ぬ時には家族たちと一緒にいたかった。
私は布団から出した手を妻のほうに伸ばした。彼女は泣き顔になり、「病気をうつしてごめんなさい」といって手を握ってきた。
私はかぶりを振り、笑った。献身的に看病してくれた彼女に落ち度などない。
「手を握ったらいけないって先生がいってたよ」孫娘が口を尖らせた。
「いいんだよ」私は笑いかけた。愛する家族の手も握れずに、何が新しい生活様式だ。
強烈な眠気が襲ってきた。消えゆく意識の中で、これで葬式でも最後の別れをしてもらえるな、と思った。
東野圭吾(ひがしの・けいご)
1958年、大阪府生まれ。大阪府立大学卒業。1985年『放課後』で江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。1999年『秘密』で日本推理作家協会賞、2006年『容疑者Xの献身』で直木賞、本格ミステリ大賞、2012年『ナミヤ雑貨店の奇蹟』で中央公論文芸賞、2013年『夢幻花』で柴田錬三郎賞、2014年『祈りの幕が下りる時』で吉川英治文学賞を受賞。2019年、海外を含む出版界への貢献により、野間出版文化賞を受賞。最新刊は『クスノキの番人』。
【近著】