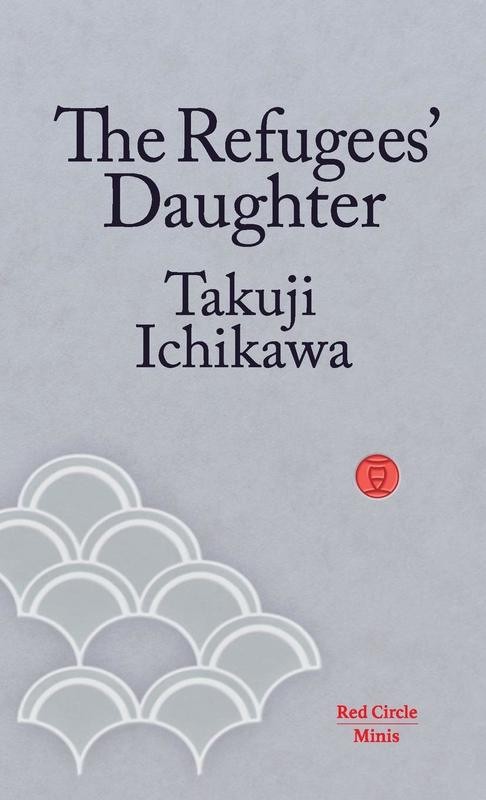〈6月12日〉 市川拓司
文字数 1,284文字
国境なき少年少女団
今日、初めてわたしは仲間の「声」を聞いた。ユーリって名のロシアの少年だった。「声」は言葉よりもむしろ旋律や香りに近い。だからこそ言語の壁を越えて深く理解し合える。彼がすべてを教えてくれた。2020年は人類にとって大転換の年なんだそうだ。始まりは南半球の山火事だった。さらにはCOVID-19、サバクトビバッタの群れ、巨大ハリケーンと、ありとあらゆる災厄が堰を切ったように人類を襲い始めた。人々は自然の脅威に恐れおののき混乱した。為政者たちは国境を封鎖し、保身のために他国を辛辣 な言葉で攻撃した。人々は分断され孤立した。
そんな中生まれたのが「わたしたち」だった。ユーリは自分たちは「国境なき少年少女団」なんだって言ってる。わたしたちに国境はない。願えば地球の裏側とだって瞬時に繋がり合える。皮肉なものだ。この能力を呼び覚ましたのは間違いなくこの「大分断」なのだから。人間はそのようには出来ていない。わたしたちは人の温もりを求め、誰かに愛を与えたいと願っている。それが禁じられたとき、わたしたちの中でなにかが芽生えた。繋がり合う力。言ってみれば自前のSNSみたいなものだ。でも、この感覚はモニター越しのコミュニケーションなんかよりはるかにリアルで温かい。驚くほど深く共感し合えるし、不思議なほど相手に優しくなれる。とげとげしさなんて微塵もない。ユーリの話じゃ「仲間」はどんどん増えているらしい。毎日のように誰かが「覚醒」している。十代の子供たちに限定されているのは、脳の神経ネットワークの可塑性となにか関係があるらしい。
仲間の少女たちの中には「癒やす」力に目覚めた者もいる。じつはわたしもそのひとりだ。これもまた過酷な状況が生み出した幸福な副産物だ。病や傷で苦しんでいる隣人をそっと抱き締め、「生きて!」と強く願う。不思議だけど、そうするだけで彼らの苦しみは癒えていく。ワンダーウーマンのように男たちを叩きのめす戦闘能力は無いけれど、わたしたちはいたわりの心で世界を救えるかもしれない。
わたしたちは大人のひとたちとは違う種なのかもしれない。ゼネレーションωありα。日毎に世界の優しさの総和が増えていく。もう、明日を恐れたりはしない。新しい世界は母親の愛のように大らかであって欲しいと思う。気前が良くて寛容で、ちょっとやそっとのことじゃ動じない。きっと、そんなふうになるって気がしてる。
市川拓司(いちかわ・たくじ)
1962年東京都生まれ。2003年発表の『いま、会いにゆきます』が映画化、テレビドラマ化され大ベストセラーとなる。著書には他に『吸涙鬼 Lovers of Tears』(講談社文庫)『恋愛寫眞 もうひとつの物語』『そのときは彼によろしく』『こんなにも優しい、世界の終わりかた』などがある。近著は『The Refugees’ Daughter』(Red Circle Minis、英語版のみ刊行)。
【近著】
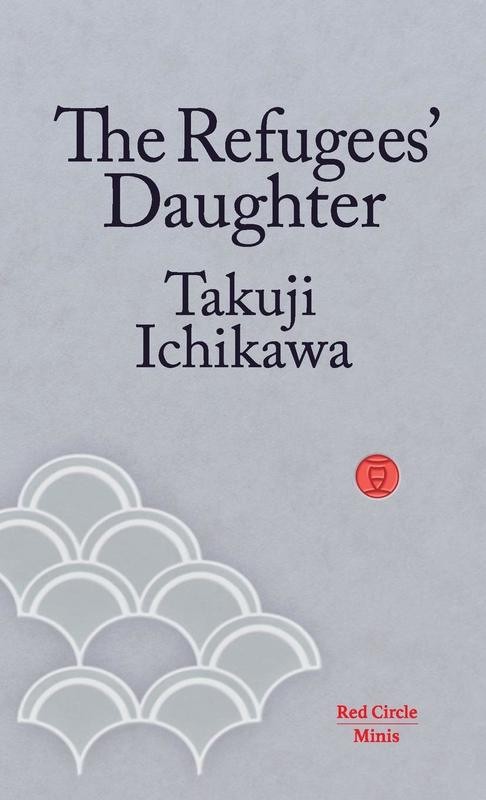
今日、初めてわたしは仲間の「声」を聞いた。ユーリって名のロシアの少年だった。「声」は言葉よりもむしろ旋律や香りに近い。だからこそ言語の壁を越えて深く理解し合える。彼がすべてを教えてくれた。2020年は人類にとって大転換の年なんだそうだ。始まりは南半球の山火事だった。さらにはCOVID-19、サバクトビバッタの群れ、巨大ハリケーンと、ありとあらゆる災厄が堰を切ったように人類を襲い始めた。人々は自然の脅威に恐れおののき混乱した。為政者たちは国境を封鎖し、保身のために他国を
そんな中生まれたのが「わたしたち」だった。ユーリは自分たちは「国境なき少年少女団」なんだって言ってる。わたしたちに国境はない。願えば地球の裏側とだって瞬時に繋がり合える。皮肉なものだ。この能力を呼び覚ましたのは間違いなくこの「大分断」なのだから。人間はそのようには出来ていない。わたしたちは人の温もりを求め、誰かに愛を与えたいと願っている。それが禁じられたとき、わたしたちの中でなにかが芽生えた。繋がり合う力。言ってみれば自前のSNSみたいなものだ。でも、この感覚はモニター越しのコミュニケーションなんかよりはるかにリアルで温かい。驚くほど深く共感し合えるし、不思議なほど相手に優しくなれる。とげとげしさなんて微塵もない。ユーリの話じゃ「仲間」はどんどん増えているらしい。毎日のように誰かが「覚醒」している。十代の子供たちに限定されているのは、脳の神経ネットワークの可塑性となにか関係があるらしい。
仲間の少女たちの中には「癒やす」力に目覚めた者もいる。じつはわたしもそのひとりだ。これもまた過酷な状況が生み出した幸福な副産物だ。病や傷で苦しんでいる隣人をそっと抱き締め、「生きて!」と強く願う。不思議だけど、そうするだけで彼らの苦しみは癒えていく。ワンダーウーマンのように男たちを叩きのめす戦闘能力は無いけれど、わたしたちはいたわりの心で世界を救えるかもしれない。
わたしたちは大人のひとたちとは違う種なのかもしれない。ゼネレーションωありα。日毎に世界の優しさの総和が増えていく。もう、明日を恐れたりはしない。新しい世界は母親の愛のように大らかであって欲しいと思う。気前が良くて寛容で、ちょっとやそっとのことじゃ動じない。きっと、そんなふうになるって気がしてる。
市川拓司(いちかわ・たくじ)
1962年東京都生まれ。2003年発表の『いま、会いにゆきます』が映画化、テレビドラマ化され大ベストセラーとなる。著書には他に『吸涙鬼 Lovers of Tears』(講談社文庫)『恋愛寫眞 もうひとつの物語』『そのときは彼によろしく』『こんなにも優しい、世界の終わりかた』などがある。近著は『The Refugees’ Daughter』(Red Circle Minis、英語版のみ刊行)。
【近著】