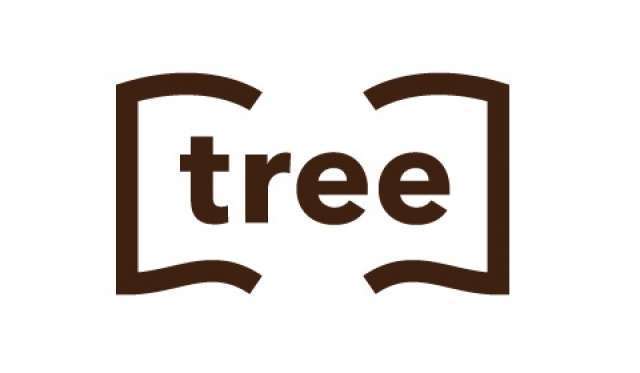明治の東海道を舞台としたデスゲーム。彼らがたどり着くのは未来か、滅びか。
文字数 3,748文字
話題の作品が気になるけど、忙しくて全部は読めない!
そんなあなたに、話題作の中身を3分でご紹介。
ぜひ忙しい毎日にひとときの癒やしを与えてくれる、お気に入りの作品を見つけてください。
『イクサガミ 天』今村翔吾
この記事の文字数:1,680字
読むのにかかる時間:約3分21秒
■POINT
・幕末を潜り抜けた強者たちが集う「遊び」がはじまる
・剣客と少女が共にする旅路
・王道の物語、キャラクター、だからこそ心が躍る
■幕末を潜り抜けた強者たちが集う「遊び」がはじまる
「奪い合うのです! その手段は問いません!」
そうして、殺し合いは始まった。
直木賞作家・今村翔吾の最新作『イクサガミ 天』。全三巻に渡るシリーズ作の第1巻にあたる。カバーイラストを手掛けているのは『東京喰種』、『超人X』の石田スイだ。
時代は、明治11年。日本が大きく変化を遂げている最中だったころの話だ。
あるとき、「豊国新聞」なるものに胡乱な内容が掲載された。
「武技ニ優レタル者。本年5月5日、午前零時。京都天龍寺境内ニ参集セヨ。金十万円ヲ得ル機会ヲ与フ」
当時の巡査の年俸は48円。2000年以上分に当たる。
そんな大金が本当に支払われるのか、と疑いつつも、天龍寺に集まったのは腕に覚えがある292人。
292人の前に立った「槐」が告げたのは「こどく」という名の「遊び」を行うこと。
そしてその遊びには7つの掟があること。
292人は、そのときから点数を集めながら東海道を辿って東京を目指す「遊び」に強制的に参加させられることになる。
それぞれに配られたのは1枚の木札。1枚につき、1点。点数を稼ぐためには、ほかの参加者から奪うしかない。
明治の東海道を舞台とした、デスゲームがスタートする。
■剣客と少女が共にする旅路
主人公となるのは、剣客・嵯峨愁二郎。天龍寺で見かけた12歳の少女・双葉を守りながら、東京を目指す。
2人の共通点は、家族が流行り病のコレラで苦しんでいるということ。日本ではころりと人が死んでしまうことから、「コロリ」と呼ばれていた。家族を助けるためには薬が、金が必要だ。そのために決死の参加を決めたのだ。
「こどく」スタート時に咄嗟に双葉を助けた愁二郎。でなければ、双葉はスタートの時点で命を落としていただろう。最初は警戒をする愁二郎に警戒をする双葉だったが、自身の話をしていくうちに心を開いていく。生きるか死ぬかの修羅場で人を信じるというのは、度胸と純粋さが必要だ。無垢なだけではない、これまで生きてきた双葉の人生の過酷さも垣間見える。
また、愁二郎も、東京にたどり着くためにはひとりのほうが圧倒的に有利だ。それでも、双葉を助け、その後の旅路も共にすることに。剣の腕だけではなく、優しさも持ち合わせている。ただ、それが今後の旅路で弱さになる可能性もある。
■王道の物語、キャラクター、だからこそ心が躍る
「武技ニ優レタル者」という募集要項もまた残酷である。自薦でOK。本当に強い者も集まるが、中途半端な腕しかない者もいる。
序盤で中途半端な腕の者は淘汰され、あっという間に強い者だけになっていく。
強さにも理由がある。
元忍者、剣客、アイヌの村の若き長、人を殺すことに快楽を覚えるタイプの“人斬り”もいる。いろんなジャンルのキャラクターがいることで、刀だけではない、異種格闘技戦のようなアクションが展開される。それぞれが得意とする得物も違うので、咄嗟にどのような戦い方をするのか思案する様子もおもしろい。相手にしたくない得物というのもあるだろうが、勝たなければ先に進めない。それぞれがどのように攻略していくのかも見どころだ
更に最古の剣術ともいわれる京八流の後継者候補たちも。
京八流の継承は、継承者候補たちが殺し合い、残ったひとりが継承者となる。つまり、「こどく」とルールは変わらないのだ。ふたつの殺し合いが重なることでどのように物語が展開していくのか。おまけに、愁二郎もこの京八流の継承者候補のひとりだというからおもしろい。問題は、ずっと前に行われているはずの継承がまだ行われていないということ。行われなかったのは愁二郎が原因しているらしいが、その真相も今後明らかになっていくのだろう。
「天」を読み終えたところでは、どうやら「こどく」は新政府が関わっているようにも見える。だとしたら目的はなんなのか。新政府を脅かすような強者を一斉に排除するためか、それともほかの理由があるのか。早く、続きが読みたい。
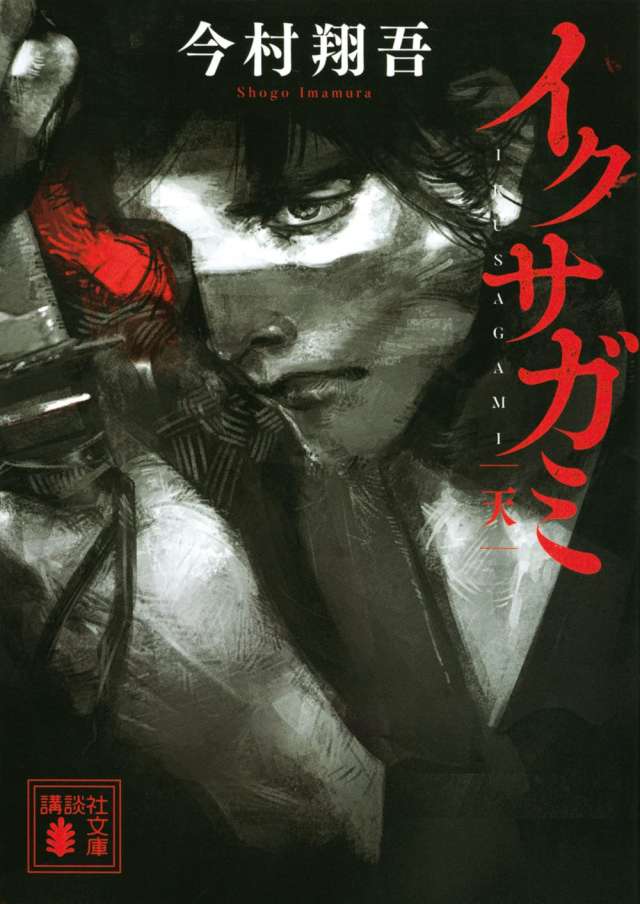
「忙しい人のための3分で読める話題作書評」バックナンバー
・「推しって一体何?」へのアンサー(『推し、燃ゆ』宇佐見りん)
・孤独の中で生きた者たちが見つけた希望の光(『52ヘルツのクジラたち』町田そのこ)
・お金大好き女性弁護士が、遺言状の謎に挑む爽快ミステリー(『元彼の遺言状』新川帆立)
・2つの選択肢で惑わせる 世にも悪趣味な実験(『スイッチ 悪意の実験』潮谷験)
・「ふつう」も「日常」も尊いのだと叫びたい(『エレジーは流れない』三浦しをん)
・ゴッホはなぜ死んだのか 知識欲くすぐるミステリー(『リボルバー』原田マハ)
・絶望の未来に希望を抱かざるを得ない物語の説得力(『カード師』中村文則)
・黒田官兵衛と信長に叛旗を翻した謀反人の意図とは?(『黒牢城』米澤穂信)
・恋愛が苦手な人こそ読んでほしい。動物から学ぶ痛快ラブコメ!(『パンダより恋が苦手な私たち』瀬那 和章)
・高校の部活を通して報道のあり方を斬る(『ドキュメント』湊かなえ)
・現代社会を映す、一人の少女と小さな島の物語(『彼岸花が咲く島』李 琴峰)
・画鬼・河鍋暁斎を父にもったひとりの女性の生き様(『星落ちて、なお』澤田瞳子)
・ミステリ好きは読むべき? いま最もミステリ愛が詰め込まれた一作(『硝子の塔の殺人』知念実希人)
・人は人を育てられるのか? 子どもと向き合う大人の苦悩(『まだ人を殺していません』小林由香)
・猫はかわいい。それだけでは終われない、猫と人間の人生(『みとりねこ』有川ひろ)
・指1本で人が殺せる。SNSの誹謗中傷に殺されかけた者の復活。(『死にたがりの君に贈る物語』綾崎隼)
・“悪手”は誰もが指す。指したあとにあなたならどうするのか。(『神の悪手』芦沢央)
・何も信用できなくなる。最悪の読後感をどうとらえるか。(『花束は毒』織守きょうや)
・今だからこそ改めて看護師の仕事について知るべきなのではないか。(『ヴァイタル・サイン』南杏子)
・「らしさ」を押し付けられた私たちに選ぶ権利はないのか(『川のほとりで羽化するぼくら』彩瀬まる)
・さまざまな「寂しさ」が詰まった、優しさと希望が感じられる短編集(『かぞえきれない星の、その次の星』重松清)
・ゾッとする、気分が落ち込む――でも読むのを止められない短編集(『カミサマはそういない』深緑野分)
・社会の問題について改めて問いかける 無戸籍をテーマとしたミステリー作品(『トリカゴ』辻堂ゆめ)
・2つの顔を持つ作品たち 私たちは他人のことを何も知らない(『ばにらさま』山本文緒)
・今を変えなければ未来は変わらない。現代日本の問題をストレートに描く(『夜が明ける』西加奈子)
・自分も誰かに闇を押し付けるかもしれない。本物のホラーは日常に潜んでいる(『闇祓』辻村深月)
・ひとりの女が会社を次々と倒産させることは可能なのか?痛快リーガルミステリー(『倒産続きの彼女』新川帆立)
・絡み合う2つの物語 この世に本物の正義はあるのか(『ペッパーズ・ゴースト』伊坂幸太郎)
・新たな切り口で戦国を描く。攻め、守りの要は職人たちだった――(『塞王の楯』今村翔吾)
・鍵を握るのは少女たち――戦争が彼女たちに与えた憎しみと孤独と絆(『同志少女よ、敵を撃て』逢坂冬馬)
・運命ではない。けれど、ある芸人との出会いがひとりの女性を変えた。(『パラソルでパラシュート』一穂ミチ)
・吸血鬼が受け入れられている世界に生きる少女たちの苦悩を描く(『愚かな薔薇』恩田陸)
・3人の老人たちの自殺が浮き彫りにする「日常」(『ひとりでカラカサさしてゆく』江國香織)
・ミステリーの新たな世界観を広げる! 弁理士が主人公の物語(『特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来』南原詠)
・大切な人が自殺した――遺された者が見つけた生きる理由(『世界の美しさを思い知れ』額賀澪)
・生きづらさを嘆くだけでは何も始まらない。未来を切り開くため「ブラックボックス」を開く(『ブラックボックス』砂川文次)
・筋肉文学? いや、ひとりの女性の“目覚め”の物語だ(『我が友、スミス』石田夏穂)
・腐女子の世界を変えたのは、ひとりの美しい死にたいキャバ嬢だった(『ミーツ・ザ・ワールド』金原ひとみ)